« 2011年09月 | TOPページへ | 2011年11月 »
2011年10月26日
料理本のソムリエ [ vol.31]
【 vol.31】
「西洋料理通」を読む
実は私、先月末ついに取締役に別室へ呼びだされてしまいました。書類を片手に深刻な面持ちです。リストラ? リストラなのか? 変なブログが原因か?
ところが開口一番「産業医の先生から、内視鏡検査を受けたほうがいいという連絡があった」。えええええっ! またなの? また飲めと? …と思ったら、検査済みという連絡が先方に通っていなかったようでして。だいいち検査結果の正式な通知はもうもらっているんですけどね、軽い胃炎だったせいだか知りませんが「1年間経過観察のうえ再検査」なんですよ。また来年にはアレが控えているかと思うとストレスで胃に穴が開きそうなんですけど…。
ということで胃カメラの話は思い出すだけでも胃に悪そうなので、これでもうおしまい。トンカツの話の続きです。
そもそもトンカツの前身である「カツレツ」のルーツをたどるのが大変でありまして、小菅和子氏が日本で最初のカツレツレシピとして紹介している文献からして大問題。『西洋料理通』の「ホールクコツトレツ」がソレなんですが、原文を見てびっくり。

まずこの本についてですが、猫々道人こと仮名垣魯文先生の訳であります。教科書にだって出てくる明治の戯作者で、猫グッズマニアという意外な一面もある御仁。出版は明治5(1872)年で、全部で百十等(「等」は、今でいう「節」や「項」ですね)の料理メモが紹介されています。訳とはいっても、横浜に居留していた某イギリス人が使用人にむけて書いた指示とその訳が原書でして、それを校訂したものとか。原書はカタカナ書きだったところをひらがなに改めたが、外来語はカタカナを残したと凡例にあります。かながき先生なだけにカナの扱いにはうるさいですな。
もっともこうした注意書きが必要なのは、今のような日本語かな表記のルールが確立する前だからでありまして、この本はまだ江戸の出版物の雰囲気を色濃く残しています。木版刷りで、ひらがなは現行のものではなく変体がな(蕎麦屋の看板に書かれているやつです。上の魯文の石碑もそうですね)も混じっていて、促音や拗音の表示はないし(早い話が今なら小さい“っ”や“ゅ”で書くところが小さくなってない)、句読点で区切られてない。現代人には難物です。おまけにカタカナの音写は発音に忠実なような不慣れなようなビミョーな感じでして、本来ついているべきところに半濁点や濁点がなかったりで、ちょっと見なんのことかよくわかりません。たとえばパセリはハリセリイだったりハルセリーだったりペルセリーだったりパンセリーだったり…。いっそ英語のままにしてほしかった。西洋料理の知識があればどうにかこうにか解読できるレベルでして、こんなの当時の人の何の役に立ったのか、とも思いますが、外国の料理の紹介というだけで売れたんですねえ。うらやましいねえ。
そこで句読点を補って活字化したものが『明治文化全集』風俗編に収められているのですが、昭和の初めの仕事なので漢字は旧字のままですし、ルビの振り方の不統一や誤植など結構ケアレスミスが見つかります。誰だい、校訂したのはと思ったら、若き日の高橋邦太郎氏でした…。料理通として有名なフランス語の翻訳家で、小社からも『パリのカフェテラスから』を出版されています。英語なので手を抜いたのか? もっとも編集者の校正ミスの可能性も…(くわばらくわばら)。ここではそこも修正しつつ紹介しましょう。ブログではルビがふれないので、随時カッコで補います。
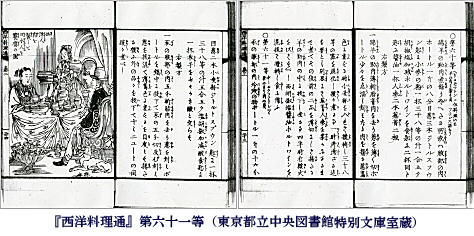
pork cutletのことらしき「ホールクコツトレツ」は、第六十一等にのっておりまして、文章は材料の列挙と「右製方(しかた)」の二つで構成されています。材料は「豚の腋(あばら)部の肉冷残(にあまり)の物/ボートル一斤の十六分目/葱二本/小麦粉ジトルトスプウン匙に一杯/三十八等の汁五合五勺/塩胡椒加減/酸(す)食匙に一杯/芥子を少々かき酸と交らす」。作り方は「豚の腋部の肉五分斬、脂肉(あぶらみ)を去り、葱を刻み、ボートルを鍋中に投下(いれ)て、豚の五分切及び刻み葱を投混(いれまぜ)て、薄鳶色に変ずるを目度とす。揚たる後に外の品々を投下(いれ)て、十ミニュートの間、緩々(ゆるゆる)煮べし」
ね、お経みたいで頭が痛くなるでしょ。ボートルはバターのことで、1斤を600gとするなら16分の1は37.5g、ジトルトスプウン匙はほかのところではシトルトスプウンとして出てくるのですが、なんのことやら。柑橘用のシトラススプーン(sitrus spoon)のことでしょうか、あるいはバースプーンを当時はスティアドスプーン(stirred-spoon)とでも呼んだのでしょうか…。ネギはポロネギではなく、恐らくタマネギの代用品ですね。別のレシピではクローヴを刺したり、オニオンスープのところでもネギを使ったりしていますので。冷残の肉というのはいったん煮て冷ましたもののようです(保存のためでしょうか…)。まあ早い話、豚肉をタマネギとともに多めのバターでソテーして、引き揚げた後、焼き汁を煮溶かしてソースに仕上げる料理のように読めます。
なお約1リットルも加える「三十八等の汁」ですが、原文にあたりますと「クレビーフヲル。ロースト。ミート」でした。変換ミスじゃないですよ。なんでこんなところに句点が入っちゃったのか…。これは恐らくgravy for roast meatでしょう。「やきたる肉に用いる露物」と説明されていますし(グレービーをつゆ物って…)。材料は以下の通りです。「第二等の白汁種(しろにだし)を二合/ハルセリー二撮(つま)み細(こまか)に刻み/ボートル胡桃の実の大きさ/肉豆蒄(にくづく)の末(こな)/丹胡椒いづれも加減」。そんでもって製法は「パンセリー並にボートルを第二等の黒汁の中に投入(いれ)、緩火にて煮る事半時、雲母(きら)を去り善く陶(こ)す。丹胡椒、肉豆蒄を加減の上散投(ちらしこむ)べし」。
丹胡椒には「あかこしょう」とルビがふってあったので、てっきりレッドパッパーかな、と思ったのですが、当時の辞書をみたらカイエンヌペッパーの日本語訳のようです。雲母というのは表面に張った脂やあくの膜のことですかねえ。このレシピの中に今度は「第二等の汁」が出てきますが、いったい白いんだか黒いんだか…。その材料と作り方の詳細はえらくスペースを割くのでもうやめておきましょう。これまたわかりづらいレシピなのですが、牛スネほか鳥獣類の肉でとったブイヨンらしきもの。もっともバターと香辛料がたっぷり入っています。煮出す水の量は少なくて煮込み時間が意外と短めでした。燃料代が高かったからですかねえ。
率直に言って、これって名前がコットレツというだけでまったく違う料理ですよねえ。衣すらついていないし。事実、小菅先生は「いまでいうポークソテー」と説明しています。だったら初めから無視しなさいな。ソテーといっておきながら、原文の変体がなをことごとく読み間違えて「…薄鳶色に変たるを目度とし揚げ、さる後に…」と紹介しておりまして、揚げ物料理っぽい印象を与えております。おかげでトンカツの来歴を扱う本はことごとくふり回されっぱなし。『とんかつの誕生』に至ってはどうしちゃったんだか終始「ホールコットレッツ」と紹介しているし…。fowl cutletでは鳥カツになっちゃいますよ?
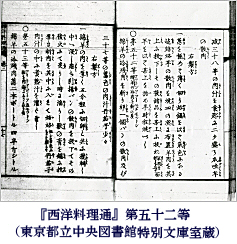 この他人の空似の第六十一等よりもですね、私は第五十二等の「コツトンツ、コールドモツトン」が気になってしかたない。お経だからって、面倒臭がらずにレシピを読まなきゃだめですよ? 隣の第五十三等のほうはカレーのレシピとかで、大変有名なのに…。
この他人の空似の第六十一等よりもですね、私は第五十二等の「コツトンツ、コールドモツトン」が気になってしかたない。お経だからって、面倒臭がらずにレシピを読まなきゃだめですよ? 隣の第五十三等のほうはカレーのレシピとかで、大変有名なのに…。
材料は「綿羊の冷残肉を斬り/卵一個/パンの散肉(ちらし)及び三十七等の鳶色の肉汁(にだし)/丹茄子(あかなす)少々」。作り方は「綿羊の肉を厚く五分程に切、卵と共に攪転(かきまわ)し、中へ浸し忽(たちま)ち引揚、パンの散肉を投下て、その後、火にて炙りし時に滴りし獣の膏(あぶら)を鍋に投(いれ)、厚き斬肉を其中に入れて焙烙(いり)、但し鳶色になるを期とす。丹茄子肉汁の中に煮熟汁(にえじる)を灌(そそ)ぐべし」。
ね? こちらはちゃんと卵もパン粉もつけてまして、動物の油脂で加熱しています。焙烙は煎り焼きのニュアンスではありますが、ミラノ風カツレツを作るときの加熱法はこんな感じ。こちらこそが日本に初めてお目見えしたカツレツレシピではないでしょうか。コツトンツはコツトレツの誤植じゃないですか? それが証拠に、この料理のモツトン(mutton)の「ン」の字は逆に「レ」によく似ていて取り違えやすそう…。なお材料の中の三十七等の煮汁はブラウン・グレービーのことでして、このレシピではいまいち使い方がわかりませんが、トマトを煮て加えるようです。
日本の「カツレツ」は英語圏から来た言葉のカットレットに由来するようですが、もとはフランス語のコートレット、つまり骨つきロース肉から来ています。西洋料理通に出てくる「コツトレツ」は元々の骨つきロース肉のほうの意味なんですね。その証拠にほら、「ホールクコツトレツ」も「コツトンツ、コールドモツトン」も料理名の脇に小さく「豚のきり肉の義」「綿羊の冷肉を斬の義」と説明されておりますでしょう? 本来はただ部位を表すだけの言葉なのに、典型的な調理法がパン粉揚げだったものですから、英語ではそれとイコールにとらえられるようになったというわけです。

 さらに意味が広がって、骨つきロースでなくとも小判状にしてパン粉をつけて揚げた肉料理は英語では何でもカットレット、イタリア語ではコトレッタと呼ばれるようになりました。吉川敏明シェフの『新版イタリア料理教本』には、豚肉以外にもポレンタやモルタデッラに衣をつけて揚げるコトレッタが出てきます(二冊組だったのが、新版では一冊にまとまって引きやすくなりましたよー、とPR)。とくに骨つきロース肉であることを示す場合は、コストレッタとするのだとか(元はラテン語で、フランスでも古語はcosteletteなのです)。
さらに意味が広がって、骨つきロースでなくとも小判状にしてパン粉をつけて揚げた肉料理は英語では何でもカットレット、イタリア語ではコトレッタと呼ばれるようになりました。吉川敏明シェフの『新版イタリア料理教本』には、豚肉以外にもポレンタやモルタデッラに衣をつけて揚げるコトレッタが出てきます(二冊組だったのが、新版では一冊にまとまって引きやすくなりましたよー、とPR)。とくに骨つきロース肉であることを示す場合は、コストレッタとするのだとか(元はラテン語で、フランスでも古語はcosteletteなのです)。
またミラノ風カツレツの項の説明によると、ミラノのコトレッタとウィーンのウィンナーシュニッツェルはどちらがオリジナルなのか本家争いをしているそうです。なるほど『月刊専門料理』1999年7月号「イタリア情報」にその一端が載っておりました。18世紀初めからイタリア建国までの間、ミラノがオーストリア帝国の統治下にある間にウィーンからミラノへ伝わったというのがオーストリア側の主張。それに対してイタリア側は、ウィンナーシュニッツェルに使うのは仔牛のモモ肉で、パン粉をつけてから卵に浸し、ラードで揚げるなど、ミラノ風カツレツとの違いを強調。また1134年のメニューに出てくる「lombolos cum panitio」はパン粉をまぶした肩ロースという意味であること、オーストリアのラデツキー元帥が副官アテムス伯爵にあてた手紙でコストレッタについて説明しているということから、当時ウィーンにはカツレツがなかったというのがその主張です。いやはや、アジアの端っこでカツレツの起源を調べるのは想像以上に大変です。
ここで注目してほしいのは、イタリアでもオーストリアでも仔牛肉から作る料理であることです。フランス語ではレットは小さいという意味で、同じ骨つきロースでも牛だの豚だのの部位を示す場合はただのコートです。カツレツは、それよりはちょっと小さいサイズの肉が取れる家畜、つまり、仔牛や仔羊から作るのが本来の姿でしょう(もっともイタリア語では牛のロースはコスタータでも、豚のロースはコストレッタの組に入るようですが)。
ところが『西洋料理通』にはもうひとつ、第三十等に「サルモン。コツトレツ」が出てまいりまして、こちらは鮭をバターを塗った紙で包んで焙り焼いております。英語では鮭の切り身もまたcutletと呼ばれるようでして、早い話それっぽい形の切り身なら何でもありなんですねえ。おおざっぱといえば、おおざっぱ。ならば何の肉を使ってもパン粉揚げならカットレットとする心情もわかります。日本では仔牛肉にはなじみがありませんから、より手軽な白身肉ということで、鶏や豚から作るようになったのでしょう。最初はチキンのカツレツだのポークのカツレツだのといちいち断っていたのが、はしょって豚(とん)+カツになっちゃった。一方関西のビフカツは、仔牛の代わりに成牛に走ったというわけですね。
豚と牛、どっちも仔牛の代用なことには変わらないのですが、ビフカツのほうが本式という文章も見かけます。やれやれ…。白身の仔牛肉(ヴィール)と赤身の牛肉(ビーフ)ではまったく別の素材でありまして、シンコをコハダ、いやコノシロと一緒にするくらいに無神経。そういえば23日、政府がBSE問題で2001年以降禁止していたフランスからの牛肉輸入の再開を検討し始めたというニュースが入りました。業界が嘱望しているのはフランス産仔牛肉なんだから、アメリカ並みに生後20カ月以下に限ってとっとと再開すればよかったのに、今頃何を言ってんだかなあ、という感じでありますな。
投稿者 webmaster : 10:53
2011年10月13日
料理本のソムリエ [ vol.30]
【 vol.30】
内視鏡検査の〆はトンカツで
先頃私、ついに定期健康診断でひっかかって、胃カメラで再検査されるはめになりました。噂には聞いていましたが、なかなかつらいもんですねえ。太さは覚悟していましたが、管が思っていたよりも柔らかくない。「のどをもっと開いて飲みましょうかー」なんて気軽に言ってきますが、一本うどんをつるつるってえならともかく、こちらで自主的に飲んでるわけじゃないんだから。「こりゃ飲むじゃなくって、突っ込むいうんじゃあボケえ」と心の中で叫んでも、口は開いているのに言葉がでない。向こうも突っ込めなきゃこちらも突っ込めない。ボケ不在の漫才です。
そもそもなぜ当人の目の前にモニターを据えて、どこまでカメラが入ったか胃の中を刻々と見せるのですか。拷問? 拷問なのか? フォワグラや北京ダックとなるために飼育されているアヒルになった気分です(もっともアヒルは痛覚が鈍くて、強制的に餌を食べさせられても苦しくはないそうですが)。「太らせなくったって食卓に上げるくせに、どうして動物虐待とか言うんだろう? 幸せ一杯健康的に育てられ、安心しきったアヒルの信頼を最後の最後で裏切るのとではどちらが罪深いのかしら?」とか「トマトが甘くなるようにぎりぎりまで水を与えないでいると、バケツと柄杓を携えた植物保護団体の運動家に妨害されるのだろうか?」とか哲学的命題を思索して気をまぎらわせましたよ……というのは嘘です。そんな余裕はありません。人間追い詰められると、目の前のことしか頭にありませんからね。とはいえ目の前にあるのはミョーにリアルなR‐15指定映像。苦しさとやるせなさから涙で視界がぼけてきました…。あ、そうか、目をつぶればいいんだ。

こうしてさんざ苦労した挙句の果てが「軽い胃炎みたいですねー」だってさ。定期健康診断の前日は夜8時までに食事を済ませなくてはいけないとかで、あわてて近くのラーメン屋に飛び込んで担担麺を食べたんですが、そのせいでは…? 以前、丸呑みさえすれば調べたいところまで勝手に泳いでいって写してくれる、カプセル状ヒレつき胃カメラが開発されたという報道がありました。なんと一億総人間ポンプ計画! ぜひとも実現してほしいものです。
さて、検査の後は「がんばった自分へのご褒美」(笑)と思って、いそいそとトンカツを食べに行きました。上野近辺はトンカツ屋さんの名店が多くて有名ですが、まあまあ結構なお値段ですし、さすがにこの年齢になると昼にトンカツはちょっと重たくて…。その点、今日は特別だぞ。なにせ今回も夜8時以降何も食べるなっていわれてたからね。
 向かうは「本家ぽん多」。いかにも重そうな木製の立派なドアに臆して入れずにきた名店です。なるほどここのトンカツときたら、あんなに肉は厚いのに衣は色白で、さっくり軽くて油ぎれがよい。揚げ終わったらすぐに油を大きなボウルに移していたのをみて、どんなものを使っているのか会社に戻って『日本の洋食』を調べてみたら、自家製のラードだそうです。むむむ、動物性油だからといって重たいとは限らないのですね。勉強になりました。
向かうは「本家ぽん多」。いかにも重そうな木製の立派なドアに臆して入れずにきた名店です。なるほどここのトンカツときたら、あんなに肉は厚いのに衣は色白で、さっくり軽くて油ぎれがよい。揚げ終わったらすぐに油を大きなボウルに移していたのをみて、どんなものを使っているのか会社に戻って『日本の洋食』を調べてみたら、自家製のラードだそうです。むむむ、動物性油だからといって重たいとは限らないのですね。勉強になりました。
余勢を駆って日を改めて今度は「蓬莱屋」へ。こちらは純和風の建物とヒレ肉が売り物で、衣はごく薄くて濃い狐色と、何から何まで対照的。厚い肉の芯まで火が通るように、揚げてからすぐに切り分けずに、しばらく休ませていたのになるほどと思いましたね。
ところで上野はいつからトンカツの町になったのでしょう。昭和の初めにはすでにトンカツといえば上野のようでしたが、いつ、ここまで普及したのでしょう。
 トンカツの歴史については、そのものずばり『とんかつの誕生』という本がありますが、残念ながらトンカツについては巻末間近の第5章で取り上げられるのみです。著者の岡田哲先生はトンカツにはさほど思い入れはなくて、サブタイトルの『明治洋食事始め』が執筆テーマだったのに、編集者が売れそうなタイトルにしちゃったのでしょう。その証拠に本書ではトンカツの誕生に関する論考は富田仁氏の『舶来事物起源事典』にゲタを預けております。明治28年に銀座の「煉瓦亭」が豚肉のカツレツを始め、大正10年には早稲田高等学院の学生がかつ丼を発明、そして御徒町の「ポンチ軒」島田信二郎が改良し、厚い豚肉を使って箸で食べやすく切り分けたトンカツを昭和4年に発明したというのがざっとのあらましです。さらに大正7年には浅草の「河金」がカツカレーを始めたというところが『舶来事物…』にはない新知見ですね。
トンカツの歴史については、そのものずばり『とんかつの誕生』という本がありますが、残念ながらトンカツについては巻末間近の第5章で取り上げられるのみです。著者の岡田哲先生はトンカツにはさほど思い入れはなくて、サブタイトルの『明治洋食事始め』が執筆テーマだったのに、編集者が売れそうなタイトルにしちゃったのでしょう。その証拠に本書ではトンカツの誕生に関する論考は富田仁氏の『舶来事物起源事典』にゲタを預けております。明治28年に銀座の「煉瓦亭」が豚肉のカツレツを始め、大正10年には早稲田高等学院の学生がかつ丼を発明、そして御徒町の「ポンチ軒」島田信二郎が改良し、厚い豚肉を使って箸で食べやすく切り分けたトンカツを昭和4年に発明したというのがざっとのあらましです。さらに大正7年には浅草の「河金」がカツカレーを始めたというところが『舶来事物…』にはない新知見ですね。
これによると豚のカツレツがトンカツと呼ばれるようになるまで30年以上かかった計算になります。おまけにカツカレーとかつ丼はトンカツのお兄さんのようですが、どちらも切り分けずにでーんと丸のまんまカレーや丼飯に添えていたんですかねえ。かつ丼はスプーンで食べていたのかな?
『舶来事物起原事典』は小菅洋子氏の『にっぽん洋食物語』を参考にしており、トンカツの起源の項目はこの本が典拠であることがわかります。そんでもって『にっぽん洋食物語』はというと1970年刊の『事物起源辞典』(まぎらわしいですね)を参考にしており、ここにはかつ丼とポンチ軒の話はでてくるのですが、煉瓦亭は登場しておりません。たどっていくと、新しい著者が次々と新知見を付け加えることによって、話が深まるどころかこんがらがっていく過程が見えてきます。うーん、Wikiみたいだ。
また岡田先生は、明治大正の料理文献で紹介されているカツレツのレシピを一覧表にまとめて、初出は明治28年の『女鑑』と紹介しています(これは明治24年から42年まで出版された婦人雑誌なのですが、引用中にも参考文献リストにも何月号なのか書かれていません。雑誌記事だってわかってんのかなあ)。うーん、これっぽっちの量で変化を追うのはちょっと危険ですね。なぜなら洋食の場合は翻訳も多いので、現実にその時代の日本のお店や家庭で行なわれている調理法を反映しているとは限らない。また単行本は過去に発表した記事をまとめて出版したりしますし、当時の人たちは(今の人も?)、ちゃっかりよその本のレシピを写したりもいたします。そのため昔の作り方の本と新しい今風の作り方の本が同時期に出版される可能性もありますので、かなりのサンプルを見つけて世の中の流れの変化をつかまねばなりません。
表を見ていると新聞、雑誌から採った情報の絶対量が足りません。本に載っているレシピや料理店なんてのは九牛の一毛、大海の一滴ですからねえ…。ところが岡田先生の本に限りませんが、明治大正の料理の由来を扱った本でみずから雑誌や新聞まであたって丹念に調べた例に出会った試しがありません。例外は、前坊洋氏の労作『明治西洋料理起源』くらいでしょうか……(ちなみにこの本によると明治23年5月4日の新聞『時事新報』に「ポークカトレツト」が登場するそうです)。『にっぽん洋食物語』でこの分野の先鞭をつけた小菅氏は、『近代日本食文化年表』では新聞記事などからの引用も挙げていますが、これは森銑三『明治東京逸聞史』からの孫引きなどでして、ご自身で調べた形跡がどうもうかがえません。
まあ古い雑誌や新聞は所蔵先が少なくて調べるのは大変ですが、料理本にしたって公的な図書館の所蔵状況はけっして良いとはいえないんですよ。たかが料理の作り方の載った本なんか大学図書館では相手にしませんし、公立図書館でも実用書を大事に後世までとっておこうという心理が働きづらいのでしょう。おかげで稀観書の数たるやおびただしいこと…。料理本を調べるなら調べるで、相当な覚悟と手間が必要なんですぞ。
そんなわけでして、洋食の始まりに関する本はおおむね手放しで信じることはできません。自分の足で調べずに安易に過去の著作を孫引き、おっと違った「参考」にするものだから、いつまで経っても同じところで足踏みしていて謎が解明される気配がありません。
一例を挙げましょう。岡田氏の本は「明治洋食事始め」をうたっておきながら明治後半から大正にかけて流行した屋台の洋食の実態についてはほとんど考察しておりません。御維新の頃には珍しくて高級だった洋食も、あっという間に庶民のところまで降りてきまして、露天の屋台商が現れ、普及に一役買いました。当時の素人向け開業案内書に、うどん屋やおでん屋などと一緒に洋食の屋台も候補に挙げられておりまして、フライやシチューのような煮込みものを出していたことがわかります。衛生的にそのほうが安心だったからでしょうね。にぎわう浅草や上野は、そうした屋台の多い土地でした。
カツレツの歴史もこの屋台という業態抜きには語れません。岡田氏自身も例のカツカレーは、大正7年に「東京浅草で、屋台洋食を始めた河野金太郎が始めた」とさらっと紹介しておりますが、それがなんだかわかってない。あともう少し掘り下げてほしかったなあ。たぶん人気料理だから両方ともメニューにおいたものの、什器の数も洗い物の回数も省力したい屋台営業ですから、えいやっと一皿に合体させちゃったんじゃないですかねえ。
 実はあの「蓬莱屋」も屋台からスタートしています。昭和6年10月1日号の『実業之日本』によると、それは大正6年4月4日のことで、創業者の山岡正輝さんは当時42歳。愛媛県の造り酒屋だった山岡さんは家産が傾き、はるばる東京に出て小資本で始められる屋台の洋食屋に賭けたとあります。カツの揚げ方はまったくわからず、隣の天ぷらの屋台の主人に教わったとか。安くてうまいのをめざしたのはもちろんですが、繁盛したのはお客さんが山岡さんの気性にひきつけられたから。ぼろを着た労働者でも平等に扱い、その一方でごねて迷惑をかける酔客は許さない。この年齢だからこそできる客あしらいですね。10年で店を持つという夢には少し遅れましたが、昭和3年9月28日に同じ上野広小路の地で立派な店舗を持つことができたとのこと。記事をなんでもかんでも鵜呑みにするのは危険ですが、店舗開業から3年後に主人に直接取材した内容ですから、戦後の食べ歩きマニアの噂話なぞよりははるかに信頼性が高いでしょう。ご丁寧に日付まで入っていますしね。
実はあの「蓬莱屋」も屋台からスタートしています。昭和6年10月1日号の『実業之日本』によると、それは大正6年4月4日のことで、創業者の山岡正輝さんは当時42歳。愛媛県の造り酒屋だった山岡さんは家産が傾き、はるばる東京に出て小資本で始められる屋台の洋食屋に賭けたとあります。カツの揚げ方はまったくわからず、隣の天ぷらの屋台の主人に教わったとか。安くてうまいのをめざしたのはもちろんですが、繁盛したのはお客さんが山岡さんの気性にひきつけられたから。ぼろを着た労働者でも平等に扱い、その一方でごねて迷惑をかける酔客は許さない。この年齢だからこそできる客あしらいですね。10年で店を持つという夢には少し遅れましたが、昭和3年9月28日に同じ上野広小路の地で立派な店舗を持つことができたとのこと。記事をなんでもかんでも鵜呑みにするのは危険ですが、店舗開業から3年後に主人に直接取材した内容ですから、戦後の食べ歩きマニアの噂話なぞよりははるかに信頼性が高いでしょう。ご丁寧に日付まで入っていますしね。
蓬莱屋のHPを見ますと二度揚げとヒレを使ったカツはここが始まりとありますが、残念なことにこの記事ではそこまで触れておりませんでした。ただ、経営誌なので料理の作り方に関心がなかったかもしれませんし、昭和6年以降の可能性も否定できません。ほかの戦前の文献を見ていると確かに蓬莱屋は昔からヒレカツを売り物にしていたようです。
正直な話、トンカツがらみの発明者はいろいろ候補が挙がっていまして、理路整然と説明するのは困難です。まず日本に伝わったカツレツがあり、それが普及し、進化を遂げた。その過程に関わっていろいろ工夫を加えた人たちがみな発明者として名乗りを上げているために、話が混乱していると思われます。誰が最初かどうかなんてのは、当人の思い込みもあるでしょうし、よそにも同じことを考えついた人がいてもおかしくないでしょうしね。
庶民的な料理ほど記録に残りづらく、起源を調べるのは実に難しい。それなのにテレビだの食べ歩き雑誌だのは、発明秘話を取り上げたがります。唐辛子の伝来じゃありませんが、「だいたい○○年くらい」でもいいと思うのですが、それでは企画にならないようです。
そもそもトンカツの起源と発達史を語るには、オリジナルの「カツレツ」についても視野に入れて考察せにゃなりませんが、もはやスペースがありませんね。ちょっと胃カメラの話で熱くなりすぎました。続きは次回に。
投稿者 webmaster : 11:41
2011年10月06日
『簡素なお菓子』 Part 5
 『簡素なお菓子』
『簡素なお菓子』
著者:河田勝彦
発行年月:2011年5月14日
判型:B5変 頁数:96頁
2種類のカスタードクリーム
フラン はフランスの家庭菓子です。
タルト生地の中にカスタードクリームを入れて焼く、シンプルなお菓子。
河田さんはこれまでの取材では、カスタードクリームを炊くときには
「粉にしっかり火が通る意識で炊け」といってこられました。
ふつふつといってきたらもうひと息炊くのが基本でした。
ところがフランでは、ふつふついってきたらすぐに火をとめたのです。
???
なんでだろう?
追加取材のときに聞いてみました。
「うー、あれはとろんとさせたいんです。
ふつうのパティシエール(カスタードクリーム)みたいに火を入れると、
冷めたときにくっとしまってきて食感が悪くなります。
あー、また粉は小麦粉だと火を入れ切らないと粉っぽさが残ってしまうので、
コンスターチにしたわけです」
なるほど。。。
「とろんとさせたい」ということから加熱時間も素材もチェンジ!
しかもなるべく早く食べてほしいとのこと。「とろん」が命なので。
シンプルなものでも、イメージがきちんとあるのです。
それに沿って基本のクリームをマイナーチェンジしたわけです。
パティシエのみなさん、そういう発想があるでしょうか。
何年か前にあるお店でフランをいただきました。午前中です。
ホールで冷蔵庫から出したものをその場でカットして供されたそのフランは、
ギュッと締まって固かったのです。正直、あまりおいしいとはいえませんでした。
とかく配合主義、「これはこうつくる」と決まっているのがお菓子の世界です。
でも、おいしく食べさせたいと思う意識が味を変えます。
つくり方を少しだけ変えます。
簡素なお菓子だからこそ、そのことがよくわかります。
「ムラング・コック」と「ムラング・シャンティイ」というメニューがあります。
同じメレンゲでも方向性の違う配合、つくり方のものを河田さんはあえて選んでいます。
違うものを2つ並べて見せる理由があります。
それはどうぞ本でご覧ください。
 (左)ムラング・コック
(左)ムラング・コック
エスプレッソと合いそうな苦甘いメレンゲ
(右)ムラング・シャンティ
香ばしいサクサクの生地においしい生クリーム
同書には、基本的なおいしさに関するそうしたヒントが隠れているのです。
あなたはいくつ読みとれるでしょうか?
探してみてください。
レシピだけから読みとれたら、素晴らしいかもしれません。
 それでも変えてはいけないこともあるようです。
それでも変えてはいけないこともあるようです。
今回は「フラン・ナチュール」を紹介しています。
バニラもなにも入れないから
「ナチュール(味を加えない)」です。
でも、卵の味が素朴すぎて、
つい「バニラとか入れちゃだめなんですか?」
と聞いてしまいました。
「ナチュールですから、それはそういうものです」
と河田さんはきっぱり。
変えなくてはいけないとこと、変えてはいけないところがあります。
バカな質問をしてあらためて気づきました。
投稿者 webmaster : 13:32