2016年01月27日
料理本のソムリエ [vol.68]
【 vol.68】
大根もちがもち米から作られないわけ
ほぼ10カ月ぶりのブログ更新です。まだ続くむね、予告しておいて本当によかったです。このまま社会からひっそりフェードアウトするところでした。なんだか不定期掲載の漫画みたいになってきましたが、100話まで書きたい気持ちとネタの在庫はあるんですよお。あとは時間と根気だけ。オラにみんなの元気を分けてくれ! いくつ書けるかどうかわかりませんが、どうか今年も見捨てずよろしくお願いいたします。
さて私の正月ですが、今年は昆布と鰹節をえいやっとおごりまして、本気の一番だしを引いて雑煮を作ってみました。ただし、もちは当ブログ同様に昨年からの繰り越しでして、11月に賞味期限がきれたもの。昨年はついハッスルして自分でもちを搗いちゃったので(vol.66参照)、買い置きが余ってしまいまして。ちなみに一昨年は黒豆を炊きまして、その前の年は栗の渋皮煮でした。
毎年ひとつだけ日本文化継承の、一点豪華主義です。
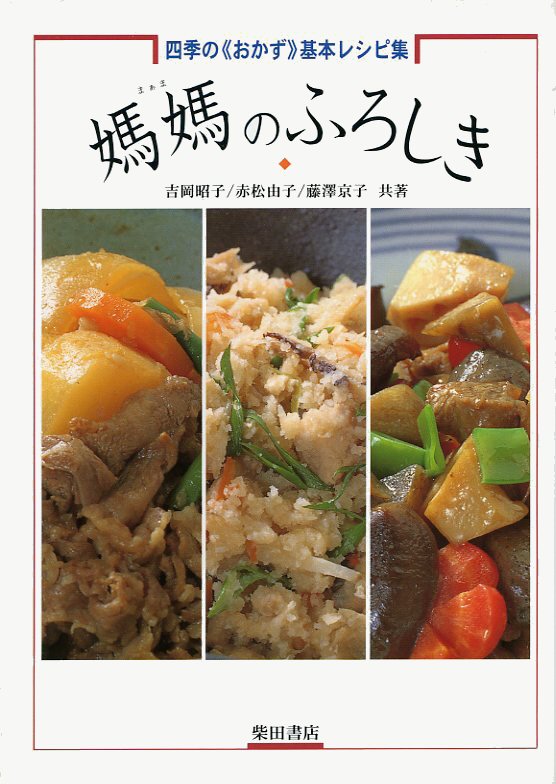
一昨年の黒豆の蜜煮やその前の渋皮煮は小社刊『媽媽のふろしき』のレシピを参考にしてみました。この本は、著者である料理研究家の女性たちが“娘時代に親しんだような活字中心のレシピ本を現代に”というコンセプトで作られた文字本でして、「プロセスやできあがりの写真がなくても、なんとかなるさ」という前向きもしくはおおらかな向きには結構便利。365日のおかずを提案するものですから、掲載レシピ数が多くてとくに和風の料理が充実しています。
ですが、タイトルでちょっと失敗しておりまして。媽媽(まあま)は中国語の「お母さん」のことなんですが、まず日本人には読めませんし、わかりません。おまけになんだかエッセイ風で、このタイトルではレシピ集だと言われてもぴんときません…。
そもそも「媽媽のふろしき」とは、中国で立春のときに食べる春餅(チュンビン)をアレンジして命名した著者たちのオリジナル料理だそうです。そりゃ何だかわかるわけないわなあ。
日本だと立春の前日に食べる料理は太巻きってことになっちゃいましたけど(vol.65参照)、中国料理だって“年中行事との密接な関わり”はちゃあんとありまして、世界無形文化遺産である和食の専売特許ではありません。
春餅は“春の餅”と書きますが、日本人の想像するもちではなくて、小麦粉を溶いてクレープ状に広げて焼いた「ビン」のことです。細く切った肉やもやしの炒め物、あぶり焼いた肉などの具を包んで食べます。北京ダックもこれで包んで食べられることから、最近は日本の餅(もち)と中国の餅(ビン)が別物であることは、広く知られるようになってきましたね。
それじゃあ、中国にはいわゆるもち米から作るびよーんと延びるもちはないのかしらといいますと(もちもちややこしいので、以後はもち米は「糯米」と書きましょう。そんでもって日本の餅は「モチ」といたします)、辺境の雲南地方のほうで見られることは前回お話した通り。これはちょっと特殊な少数民族の食品ですが、もっと一般的なものとしては「年コウ」っていうのがあります。こちらは春節に食べるものという点でも、日本のモチとよく似ております。春節は、立春とちょっと混同しちゃいそうですが、旧暦の正月のこと。太陰太陽暦ってややこしいですねえ。
 さて、ここまで書いておおいに弱ったのですが、このブログ上では書体の都合上、コウという漢字を示すことができません。へんは米へん、つくりは羊の下にレッカ(点4つね)を組み合わせたやつ。「窯」という字から穴かんむりを取った形なんですが、わかるかなあ? ああまどろっこしい。左の写真を見てください。ちんすこうの「こう」はこの字を書きます。写真の製品では達筆で、レッカがシタゴコロみたいで米へんに「恙」みたいに見えますが。ちなみに恙の音読みは「ヨウ」、訓読みは「つつがない」。前々回のしょっぱなのあいさつは伏線だったわけですぞ(嘘)。
さて、ここまで書いておおいに弱ったのですが、このブログ上では書体の都合上、コウという漢字を示すことができません。へんは米へん、つくりは羊の下にレッカ(点4つね)を組み合わせたやつ。「窯」という字から穴かんむりを取った形なんですが、わかるかなあ? ああまどろっこしい。左の写真を見てください。ちんすこうの「こう」はこの字を書きます。写真の製品では達筆で、レッカがシタゴコロみたいで米へんに「恙」みたいに見えますが。ちなみに恙の音読みは「ヨウ」、訓読みは「つつがない」。前々回のしょっぱなのあいさつは伏線だったわけですぞ(嘘)。
ちんすこうとモチとではずいぶん印象が違いますが、コウ(仕方ないので以下はカタカナで示します)は粉から作る固めた食品のことを指す漢字だからでして、中国語での発音は「カオ」になります。
 そもそもコウは米で作られることが多くなったので米へんを当てられましたが、元をただせば食へんでした…って、これまた表示できません(泣)。仕方ないので今度はこちらの画像を。またまた沖縄物産店で見つけました。「豆腐よう」の「よう」にこの字が使われてました。
そもそもコウは米で作られることが多くなったので米へんを当てられましたが、元をただせば食へんでした…って、これまた表示できません(泣)。仕方ないので今度はこちらの画像を。またまた沖縄物産店で見つけました。「豆腐よう」の「よう」にこの字が使われてました。
「コウじゃなくてヨウじゃないのさ」、と思われるかもしれませんが、コウと同じく粉菓子の意味で食へんに恙って書く例もあるそうです。こちらの場合はまさしく音読みはヨウです。
それよりも、なんでトウフヨウにこのコウの字を当てるのかが、よくわかりませんでした。粉菓子みたいな形だから?と思ったのですが、豆腐ってもともと四角いものねえ。ちなみに中国では麹で発酵させた豆腐は「腐乳」と申します(vol.16参照)。食へんに恙って書くつもりが達筆すぎてこんがらがっちゃったんですかねえ。
なおコンビニやスーパーで売っているマーラーカオの「カオ」は米へんのコウの字を書きます。「マーラー」のほうは「麻辣」じゃなくて(甘いもんねえ)、「馬拉」でして、マレーシアという意味です。マレーシアにはこういう蒸しパンみたいなお菓子があるのかしら。お隣のインドネシアには和菓子のかるかんみたいにもちもちした、ボル・ククス(ボルは菓子で、ククスは蒸すという意味)というのがありますが…。

 また台湾屋台料理の大根もちも、「蘿蔔カオ」と書きます。小社刊『食在台湾』によりますと、本場の大根もちは「在来米」と呼ばれるインディカ米から作るようです。まずひと晩水に浸けて水挽きしたどろどろの生地を作りまして、炒めた大根のせん切りや干し海老などの具を混ぜます。これを型に流して蒸し固め、提供するときに鉄板で焼くのです。
また台湾屋台料理の大根もちも、「蘿蔔カオ」と書きます。小社刊『食在台湾』によりますと、本場の大根もちは「在来米」と呼ばれるインディカ米から作るようです。まずひと晩水に浸けて水挽きしたどろどろの生地を作りまして、炒めた大根のせん切りや干し海老などの具を混ぜます。これを型に流して蒸し固め、提供するときに鉄板で焼くのです。

蘿蔔カオは形がモチみたいな米料理だから日本では「大根もち」と呼ばれて、広く親しまれていますが、台湾には「猪血カオ」という強烈なものもあります。「猪」とありますが豚のこと(中国語では豚は「家猪」ですので)でして、ひと晩水に浸けた糯米に豚の血を混ぜて、型に流して蒸したものです。
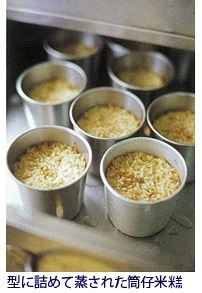 ほかには「筒仔米カオ」という、筒型に糯米を詰めて蒸し上げたおこわ料理もありまして、カオといえば四角いものだと思っていた私はびっくり。
ほかには「筒仔米カオ」という、筒型に糯米を詰めて蒸し上げたおこわ料理もありまして、カオといえば四角いものだと思っていた私はびっくり。
コウ(カオ)という字が示す概念はすごく広くて、ちんすこうやマーラーカオのように小麦粉から作られるコウもあれば、インディカ米で作られるコウもありますし、粉を使わなくても今ではコウの仲間なんですね。大陸ではアイスクリームだって「雪コウ」って言ったりするものね。
さてさて、話を戻して「年コウ」なんですが(なんかこう書くと囲碁の万年コウみたいだなあ。漢字カタカナ交じりでどうも座りが悪くて申し訳ありません)。「年年高」=「年々上っていく」というおめでたい文句と発音が同じなので、縁起物とされています。ただ、日本人にはあんまりなじみがないので春餅より知名度はぐぐっと低いです。だいぶ昔の本ではありますが、サントリー学芸賞を受賞なすった『中国料理の迷宮』には、年コウを回族の食べものって書いてありまして、タイトルに恥じない迷宮っぷりに仰天したものです。
まあ、かくいう私も年コウってどうやって作るかまでは知りませんでしたが、3年前に、この年コウを扱った中国書の和訳が出版されました。原題は『慈城年コウ的文化記憶』(ただし中国の出版物だから字は簡体字です)なんですが、翻訳版ではマイナーな漢字を本のタイトルに使うとどっかの会社のレシピ本の二の舞になりかねませんので、『中国慈城の餅文化』とされておりました。
著者は年コウが春節に食べるものであり、原料に糯米が使われることから、日本のモチとの共通点に着目しています。なるほど慈城の年コウは真っ白で、四角く固めてあってちょっとモチと似てますね。この本、図版が豊富で、日本ではあまり知られていない中国の民俗文化に触れることができるのが貴重です。
ただこれを読むとモチと年コウには共通点もあるけれど、相違点もかなりあることが浮かび上がってきます。慈城の年コウも横杵で搗くのですが、糯米を水に浸してから搗き、粉にしてから型に入れて蒸し固めるんです。どうも日本人の感覚からいうと、米粒を蒸してからぺったんぺったん搗かないとモチと言えない感じがします。糯米を臼で水挽きして粉にしたものは日本では白玉粉。白玉団子はつるんとした触感でおいしいのですが、モチとはちょっと違う気も…。
日本の場合、慈城の年コウのような米粉から作る食べ物は古くは「しとぎ」といいました。今やほとんどなじみがありませんが、法政大学出版局の『もち』によると、東北地方の北部では日常食で、いろりで表面を焼いてから熱い灰に突っ込んで蒸し焼きにして食べていたそうです。
かたや南に目を転じますと、沖縄の「ムーチー」もまた糯米の粉から作られます。どんな味なんだろうと思ってちんすこうと豆腐ようを購入した上野の沖縄物産店で探したのですが、扱っておりませんでした。うーん残念。
ムーチーは発音通り「餅」と書きますが、搗くのに横杵は使わず、旧暦の12月8日に食べられるとか。この日は中国でいう臘八節。中国では「臘八粥」という穀物入りの甘いお粥を食べますね。また沖縄ではご先祖様を祭る4月の清明祭(シーミー)でもヨモギ(フーチバー)を入れたフーチムチが欠かせないそうです。
 沖縄に近い台湾でも、清明節にヨモギのペーストと糯米を練ったモチをお供えすると『食在台湾』にありまして、よく似た習俗です。ただネットを検索してみますと、この日に「潤餅」(ルンビン)を食べる地域もあるようです。潤餅は、具をクレープ状の生地で巻く「春餅」によく似た料理。さあ、またわからなくなってきたぞ。大陸から来た外省人の人たちが持ち込んだものなのか、昔からあるものなのか…。
沖縄に近い台湾でも、清明節にヨモギのペーストと糯米を練ったモチをお供えすると『食在台湾』にありまして、よく似た習俗です。ただネットを検索してみますと、この日に「潤餅」(ルンビン)を食べる地域もあるようです。潤餅は、具をクレープ状の生地で巻く「春餅」によく似た料理。さあ、またわからなくなってきたぞ。大陸から来た外省人の人たちが持ち込んだものなのか、昔からあるものなのか…。
 なお、日本の草モチの作り方には蒸した糯米にヨモギを入れて搗き混ぜる方法と、上新粉で作る方法とがあります。おおそういえば、上新粉はうるち米を水でふやかして柔らかくしてから粉にしたもので、糯米じゃありませんぞ。柏モチもそうですが、普段意識していないだけで、意外とうるち米から作るモチっていうのも日本にありますねえ。
なお、日本の草モチの作り方には蒸した糯米にヨモギを入れて搗き混ぜる方法と、上新粉で作る方法とがあります。おおそういえば、上新粉はうるち米を水でふやかして柔らかくしてから粉にしたもので、糯米じゃありませんぞ。柏モチもそうですが、普段意識していないだけで、意外とうるち米から作るモチっていうのも日本にありますねえ。
投稿者 webmaster : 17:20
2015年03月26日
料理本のソムリエ [vol.67]
【 vol.67】
横杵(横槌じゃないよ)は、
どこでいつから使われるようになったのか
話が横にそれすぎました。横槌じゃなくて横杵のほうに戻しましょう。
前回は江戸時代の話になっちゃいましたが、そもそも杵も臼も、古代から日本にある歴史の古い道具です。なにせ国宝の銅鐸の文様に登場するくらいだもの。これは杵臼のほかにも亀や狩りのシーンなどが描かれてまして、旧所蔵者の名前をとって「大橋銅鐸」なんて呼ばれているユニークな銅鐸ですが、この世でひとつきりなのではなく、同じような文様のものが神戸からも出土しています。ほれ、教科書なんかで見たでしょ? 覚えてない?
わざわざブログ用に写真を借りるのもねえ……と思っていたら、上野の国立博物館のミュージアムショップでこの銅鐸にちなんだ商品を発見! 海洋堂製のフィギアがガチャガチャの丸いケース入りで売られていました。ただしそこはガチャガチャですから、銅鐸以外にも埴輪や土偶など計6種ありまして、中身は開けてみないとわからない。コンプリートはなかなか大変そう。考古学マニアの琴線をくすぐる商品であります。穴の開いた透明な箱に詰められてまして、つかみ取りで自由に選ぶスタイルで売られていたのですが、もういっそ、丸ケースごと砂の中に埋めて発掘する趣向にすればいいのに。

さらにそのものずばり、国宝の銅鐸に描かれた各種線画のハンコが売られていましたよ。特別展の「みちのくの仏像」でも仏様のハンコがいくつも売られていたけど、昔はこんなお土産なかったよなあ。近ごろの自作スタンプブームにあやかっているのかしら。
 教科書なんかとはとっくの昔におさらばして記憶があやふやな方たち、こちらをご覧ください。思い出しました? 銅鐸の文様に描かれているのはこの通り、竪杵です。もっともこれはもちを搗いているわけではなくて、脱穀・精米のシーンと思われます。
教科書なんかとはとっくの昔におさらばして記憶があやふやな方たち、こちらをご覧ください。思い出しました? 銅鐸の文様に描かれているのはこの通り、竪杵です。もっともこれはもちを搗いているわけではなくて、脱穀・精米のシーンと思われます。
いっぽう横杵はと言いますと、これは意外に歴史が新しく、江戸時代に普及したと言われています。それというのも、銅鐸から始まって中世の絵巻物など、絵画資料に登場するのは、どれもこれも竪杵ばかり。
民俗学者の宮本常一は『絵巻物に見る日本庶民生活誌』で、「直幹申文絵詞」や「福富草紙」といった、二人組の女性が竪杵を片手に持って臼を搗いている資料を紹介しております。そして「・・・杵も竪杵が幕末のころまでは多かったようだが、そのころ(注・菅江真澄が「百臼の図」を記した文化五年=1808年)から横杵も行なわれてくる。「百臼の図」によると、秋田土崎・江戸のものなどがあげられており、重さは六貫五、六百目から十四、五貫に及んだ。このような重さでは片手で搗くことはできない。両手で柄を持って搗く。そしてこの作業は主として男が行なうようになる」と述べています。
これは柳田国男が名作『木綿以前の事』において、「女性が日本の手杵で穀粉をはたいている間は、いかに糯米が糊分の多い穀物であろうとも、是を搗きつぶして今のような餅にすることはできない。それが可能になったのは横杵の発明または輸入で、男子がこれを取扱うようになった結果である。横杵の使用は多分支那から入ってきた技術であろう。男の力でないと取扱えぬかわりに、餅も米の精白もこのために手早くなった」
と述べているのを受けたのかもしれません。えええ、竪杵では完全な餅は搗けないの? それじゃあすりこぎレベルではなおのこと…。もっとも柳田国男は「すりこぎ」の「こぎ」は小杵(こぎね)からきていると述べておりました。すりこぎはああ見えて杵のお仲間なんですねえ。
ところで、彼は横杵は中国起源と推測しておりますが、もちを搗く文化って、中国にあるのでしょうか? 中国でも月の模様をウサギの姿に見立てておりますが、竪杵で搗いているのはもちではなくて仙薬なんだそうですが……。
もち米が粘るのは、そのでんぷんの中にアミロースをほとんど含まないからで、突然変異として生まれたもの。こうしたもち性穀物はアワやキビ、トウモロコシなどにも見られます。これら“もちもち穀物”を好んでわざわざ栽培するのは、東南アジアから中国南部、さらに日本へと広がる照葉樹林文化圏の特徴です。
もっとももち米の食べ方も、おこわだの粽だのいろいろありますよね。民族学者の佐々木高明先生によりますと、ぺったんぺったん搗いたもちを食べる地域は照葉樹林文化圏のなかでもさらに限られているとか。「せいぜい中国の雲南から揚子江流域一帯、一部は朝鮮半島にも分布していますが、それだけですね」と『民具が語る日本文化』の対談でコメントされておりました。ただし同じページに載っております国立民族学博物館蔵の杵の写真、どう見ても横杵なんですが、「竪杵」ってキャプションがついてましたよ……。編集者もやっぱりこんがらがるよねえ。
民博所蔵の杵は中国の少数民族である苗(ミャオ)族が使っていたもので、一緒に写っている臼は、バスタブみたいな横長の形。日本ではこのタイプの臼は応神天皇が酒を仕込むのに使ったとされていまして、「横臼(よくす・よこうす)」といいます。ちなみにもち搗きに使うほうは「立臼(たちうす)」ね。
『西南中国の少数民族』によりますと(ただしこの本は、雲南じゃなくて隣の貴州省で暮らす苗族の研究書なんですが)、旧暦の九月九日、苗族のお祭りの日である十月から十一月にかけての卯の日、春節と、一年のうち3回もちを搗くんだそうです。臼が横長なのは、両側から交互に搗くからだとか。
これまた写真を借りるのもねえ……と思っていろいろ探したらNHKの学習用動画がありました。これまたすばらしい。百聞は一見に、静止画像は動画にしかずですよ。
http://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402644_00000&p=box
なんか見慣れた作業風景のような、そうでないような……。苗族と日本人、共通の文化的基盤を持つというのが照葉樹林文化論なんですが、もち搗きだけは微妙にスタイルがずれていますね。おまけに横杵だけずいぶん遅れて日本に伝播したってのもなんだか変。いったいいつ、どこからどうして伝来したのかしら?
そもそも佐々木先生は『照葉樹林文化の道』では1979年に聞いた話として、「…湖南山地に住むヤオ族、ミャオ族、トン族などの間ではモチ種のイネの栽培が盛んで、モチ米は甑で蒸してオコワをつくるほか、それを臼と杵を用いて“ペッタラコ”と搗いて円いモチをつくるということであった。しかも、その杵はいまはタテギネを用いているが、三〇年ほど前までは日本のモチツキギネとそっくりのヨコギネを使っていたというのである」と報告しておりまして、これじゃあますますわけがわからない。横杵から竪杵へと逆行しています。
のちに『日本文化の多重構造』では「つまり、横杵を用いて「搗きモチ」をつくる慣行は、照葉樹林帯に広く分布するモチ文化圏の中でも、きわめて限定された地域にみられるものなのである。日本式の「搗きモチ」に象徴される文化のルーツは、この限定された地域に求めることができそうだが、くわしくは将来の研究を待たねばならない」と結論を留保しています。どうも横杵は照葉樹林文化論にとって鬼門みたい。
ようし、それなら考古学の世界ではどうなっているのでしょう。銅鐸の絵はさておいて、杵そのものは出土しているのかな?
以前はと言いますと、横杵は戦国時代の都市遺跡、草戸千軒の井戸からの出土品くらいしか知られておらず、江戸時代に普及したという説を補強していました。しかし最近の報告書を見ると、竪杵の数に比べるとごくわずかではあるものの、弥生時代や古墳時代の横杵の出土例もあるようです。
『木の考古学 出土木製品用材データベース』は、縄文時代から江戸時代まで、日本各地で出土する木製品にどんな樹種が使われているかを整理した労作でして、出土品が器種別に細かく整理されており、CD-ROMつきで検索ができます。ためしに「横杵」を検索してみたら、ちょっと江戸時代のものも混じっておりましたが、41点がヒットしました。一方竪杵はと言うと665点で10倍以上。ちなみに例の横槌は826点でして、さらに圧倒しておりますが、それでも横杵もまったく出土していないわけではないんですね。
たとえば今世紀になって発掘され、4年前には1000点あまりの出土品が重要文化財に指定された石川県の八日市地方遺跡からは、トネリコ製とツバキ製の2点の弥生時代の横杵が出土しています。さらに竪杵も3点出土しているのですが、こっちのほうが横杵よりも造りがていねいで格上な感じです。
この遺跡の出土品は小松市のHPに動画で紹介されています。といっても、HPに写真も貼られているのですけれどね。
竪杵は7分10秒あたりに登場。残念ながら横杵はありません。考古学の雑誌で写真を見つけたのですが、柄の折れた横杵でして、みんなが杵と聞いてイメージするごく普通の形のもの。これじゃあありきたりで面白くないと判断されて、動画では割愛されたんですかねえ。こっちのほうが珍しいのに……。
さてさて、横杵が江戸時代以前から日本でも使われていることがわかりまして、がぜん照葉樹林チームが元気づいてきましたよ。メジャーな道具ではなかったので絵画資料に描かれなかったんじゃないかしら? ただし、形がおんなじだからといって、昔からもち搗きに使っていたとは限りませんよねえ。案外でっかい銅鐸を叩いて鳴らすのに使ってたりしてね。そこが考古学のつらいところ。
先に紹介した『民具が語る日本文化』は、いろんな学者さんの論考や座談会のアンソロジー本でして、この中の「ヨコヅチをめぐって 考古資料と民具」で渡辺誠氏は、考古学者は横槌をなんでもかんでも「砧」としてしまうことを批判していました。渡辺氏によると横槌は形によって7種類に分かれるそうで、なるほどバットみたいなタイプもあるようです。そして、それぞれ用途が異なり、ワラを細工するために叩いて柔かくする作業のほか、豆を叩いてさやから落としたり綿を叩いて柔らかくしたり。紙の原料のコウゾや漉き直す古紙をとんとん叩いて柔らかくする(vol65参照)のにも使うんだそうで。確かに江戸時代の川柳には、浅草の漉き返しの作業を詠んだ「寝ぬ里へひびく山谷の紙砧」なんてのがありました。布を叩く以外にもいろいろなことに使うから、横槌がやたらにたくさん出土するんだねえ。

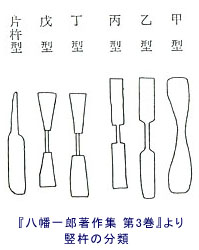 それじゃあ竪杵のほうはと言いますと、こちらは考古学と民族学を両睨みにした学者、八幡一郎の調査があります。昭和24(1949年)、すたれつつあった竪杵について、どんなものが使われているかアンケート取材を行なっておりまして、八幡先生は竪杵の形を6種類に分類しております。
それじゃあ竪杵のほうはと言いますと、こちらは考古学と民族学を両睨みにした学者、八幡一郎の調査があります。昭和24(1949年)、すたれつつあった竪杵について、どんなものが使われているかアンケート取材を行なっておりまして、八幡先生は竪杵の形を6種類に分類しております。
1200通あまりのアンケートのうち、どれくらい返ってきたのかわかりませんが、126例が報告されておりまして、それによると、当時すでに近畿地方や関東地方では、竪杵はほとんど使われていませんでした。そんでもってその用途ですが、味噌搗という回答が圧倒的に多く、さらにかまぼこだのコンニャク作りだの、昆布を粉にするだの意外な回答があるわ、あるわ。
こうしてみると重いばかりで小回りの利かない横杵のほうは、道具としての用途が広くないような気がします。もち搗き以外には、大量の脱穀・精白くらいしか使い道が思いつきません。それが出土資料や絵画資料の少なさにつながるのかもしれません。
なお横杵を使って精白するには、臼でもち搗きの要領で搗いてもよいのですが、唐臼というさらに進化した道具を用います。踏み臼ともいいまして、シーソーの端に横杵がくくりつけられているようなものを想像してください。これを踏むと杵が持ち上がり、はなすと自重で下りて臼の中に振り下ろされます。らくちんらくちん。
それじゃあもちを搗くのだって、唐臼を使えばいいじゃない。正月食べるめでたい食べ物だから、搗き手と返し手の二人が呼吸を合わせて心をこめて搗かなきゃいけない伝統だったのでしょうか……、と思ったら、実際に唐臼でもちをついている事例がありました。
小社の『食生活の構造』には、昭和50(1975)年の年末年始に潮田鉄雄氏が聞き歩いた広島の民俗調査が収録されているのですが、そこにこんな証言が。
「…小人数の家族ではキノ(横杵)で餅を搗くこともあるが、これは歴史が新しく、君田村では大正時代から出現した。杵より踏臼のほうが餅の伸びがよく、ヤネッこく(大変で)ない」「臼で搗く餅は、二た臼か三臼と少ない時や、近年家族数が少なくなった若い家庭で用いている」
臼みっつ分で少ないなんて……。それに昭和50年代は若い家庭も、ちゃんと家でもちを搗いていたんですねえ。日本人の米の消費量が減るわけだよねえ。
 となると先の湖南山地のミャオ族も家族が少なくなって、横杵から竪杵へ戻ったのかしら。少数民族には一人っ子政策は適応されないはずだけど……。それとも文化大革命のせいかしら。
となると先の湖南山地のミャオ族も家族が少なくなって、横杵から竪杵へ戻ったのかしら。少数民族には一人っ子政策は適応されないはずだけど……。それとも文化大革命のせいかしら。
投稿者 webmaster : 17:41
2015年02月16日
料理本のソムリエ [vol.66]
【 vol.66】
江戸時代のおうちレシピにみる、
もちの保存法と砧大根
皆さん、世界無形文化遺産継承の大任はつつがなく終えられましたでしょうか。私は今年の正月は頑張ってもちを搗いてみましたよ。
毎年暮れには農家の叔母からのしもちが送られてきていたのですが、年が年でだんだんつらくなっているらしく、今年はもち米だけが届きまして。こんなにもち米ばかりあっても赤飯も粽もしばらく作ってないしなあ、もちなんて杵と臼がなければ搗けないし…、と思っていたのですが、なんとすりこぎとすり鉢で代用できるという情報をネットで見つけました。
でも、いざすり鉢を前にして、躊躇することしばし。なんだか手元がすべって突き割ってしまいそう。だいいち、こんなに溝だらけで張り付かないの? ボウルを臼代わりにするという手もあるらしいのですが、すぐに冷めそうですし、軽くて安定が悪そう…。
そこではたと気づきました。もちはもち屋…じゃなかった、もちには炊飯器では? 炊飯器の内釜なら、形といい、張り付きづらい材質といい、重さといい、最適じゃあありませんか。ずっと前に壊れた炊飯器の内釜だけをとっといてあるしね。早速トライ!
前日から水に浸しておいたもち米を蒸し器で蒸しまして、内釜に移して、いざスタート。えぐり込むように突くべし!! 突くべし!! 突くべし! 突くべし、突く、べし…、突…く……べ……し………。 ふー、すりこぎが細いので、なかなかもち米がつぶれませんねえ。息が上がって、途中でへとへとであります。ビール瓶でやればよかったかな?
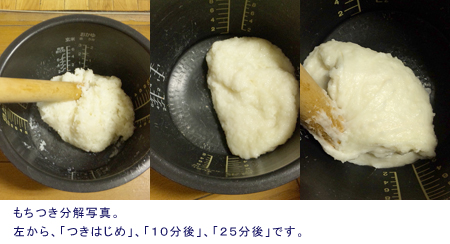
ボウルほど薄くはないにせよ、しょせん内釜も金属ですから、搗き上がるころにはもうすっかり冷めておりまして、熱くてちぎるのが大変どころか固くなってきていてひと苦労。ちょっと粒々感もあります。それでもどうにかこうにか形になりました。めでたし、めでたし。
このもちを搗く道具ですが、すりこぎみたいに縦長な専用の道具がちゃんとありまして、「竪杵(たてぎね)」といいます。木の棒の中ほどがくびれていて握りやすくなってるんですが、ご存知かなあ。ほれ、月に住むウサギがもち搗きに使っているやつですよ。月の模様はウサギが前かがみになってごそごそ何かしている感じで、贔屓目に見ても杵を持っている姿とするには無理がありそうですが、「ツキでもちツキ」っていう親父ギャクを狙ったのかしら。
いっぽう普通もち搗きに使われるのは横杵(よこぎね)です。これってトンカチや一寸法師が使う打出の小槌の大将みたいな形ですが、槌はどっち側からも叩けるリバーシブルな構造なのに対して、横杵は頭がでかくて一方向にしか搗けません。重いのをどーんと降りおろす横杵のパワーには、竪杵はかないません。
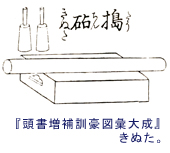 ところで竪杵を半分に切ったような、マスカラみたいな形をしている道具がありまして、こっちは「横槌(よこづち)」といいます。ややこしいね。横槌は洗練された形の棍棒とでも申しますか、まあ早い話が叩くのに使います。代表的なのは砧(きぬた)ですね。
ところで竪杵を半分に切ったような、マスカラみたいな形をしている道具がありまして、こっちは「横槌(よこづち)」といいます。ややこしいね。横槌は洗練された形の棍棒とでも申しますか、まあ早い話が叩くのに使います。代表的なのは砧(きぬた)ですね。
「砧」という言葉は「衣板(きぬいた)」からきていまして、本来は洗濯して糊をつけた布を叩いてしわをとり柔らかくする、今のアイロンがけみたいな作業のことをいいます。麻や木綿の場合はたたんで板(打盤といいます)の上でコンコンやる作業だったのですが、絹のような柔らかい布は横にわたした棒にくるくる巻きつけて、外側を布で包んで回転させながら叩きます。おかげでなのか知りませんが、板よりも叩くほうの横槌のほうがクローズアップされまして、砧の作業に使う横槌も砧と呼ばれるようになっちゃいました。骨董に「砧青磁」なんてのがありますが、この種の青磁に多く見られる花活けの形が横槌に似ていることからきているのでしょう(叩く音のように、世に響き渡る名品だから砧という、なんて説もありますが、こじつけっぽいよねえ)。ちなみに中国語では砧は板のほうを指しまして、「鉄砧」は鍛冶屋さんが使う金床、「砧板」はまな板のことだったりします。
 日本料理の世界では、かつらむきにしたダイコンやカブをくるくる巻く「砧巻き」という言葉がありますね。スモークサーモンや柿を芯にした紅白の砧巻きはおせちに詰められたりもするので、お正月に食べたばかりの方もいらっしゃるのでは? 当て字で「サーモン絹多」「柿絹田」なんて書く店も多いこともあって、もはや何のことなのかわからなくなってきていますが…。これって横槌の形から来ているのかな? それともくるくる巻いた絹のほうから来ているのかな?
日本料理の世界では、かつらむきにしたダイコンやカブをくるくる巻く「砧巻き」という言葉がありますね。スモークサーモンや柿を芯にした紅白の砧巻きはおせちに詰められたりもするので、お正月に食べたばかりの方もいらっしゃるのでは? 当て字で「サーモン絹多」「柿絹田」なんて書く店も多いこともあって、もはや何のことなのかわからなくなってきていますが…。これって横槌の形から来ているのかな? それともくるくる巻いた絹のほうから来ているのかな?
川上行藏先生の『食生活語彙五種便覧』を調べてみますと、「きぬた牛蒡」という項目に「きぬたは切り方の名。この料理言葉は『料理歌仙の組糸』に始まる」とありました。確かにゴボウは薄く切ってくるくる巻けないもの、素材の切り方かもしれませんねえ。横槌の形にむいたのかしら?
「始まる」とあるからには、ほかにも素材をきぬたに切った例が江戸時代の料理書にあるのかと探してみたのですが、今のところ見つかっておりません。それじゃあかつらむきのダイコンやカブで巻いた料理のほうはどうだろうと探したところ、「きぬまき」となってました。『精進献立集』ではダイコンやカブの薄く切ったものを酢に浸けて(こうするとしんなりして巻きやすくなります)、細く巻いて向付に添えてます。これだとただの巻きものなんですが、「きぬまきかぶら」では芯にワサビを入れてました。
ちょっと砧巻きから遠いですねえ。『精進献立集』にはこのほか、取肴に「ぎおんぼうだいこんまき」というのがでてきまして、これがかなり現代の砧巻きっぽい。祇園坊というのは柿の品種のことで、これをへいで二つに切ります。ダイコンはかつらむきじゃなくて厚く紙のごとくむき、やっぱり酢に浸けて、柿を巻き、しばらく押してから小口切りにします。柿なますの応用形ですよね。
一方小学館の『日本国語大辞典』の第2版には、「きぬただいこん」が登場します。
<(その形が砧に布を巻いたのに似ているところから、戯作者初代立川焉馬の命名したもの)五 ― 六センチメートルの厚さに切った大根を、かつらむきにし、生姜のせんぎりを巻いて味噌づけにしたもの。生姜のかわりに輪唐辛子を用いたものを紅葉巻(もみじまき)という>
なんだかとっても具体的。そのくせ、毎度のことながら出典が書いてありません。勘弁してよー。
探したら、これは平亭銀鶏の『家内の花』(1833年刊)が元でした。幸いにも東京家政学院大学(家政大とは別だから注意してね)の昨年の紀要に大江文庫所蔵本の翻刻がありまして、ネット上でも見ることができます。
http://www.kasei-gakuin.ac.jp/library/kiyou/zenbun/54-15.pdf
ちなみに大江文庫は慶応の石泰文庫(vol19参照)と並んで、江戸の料理本を多く所蔵することで知られておりまして、同大学の同窓会グループによって手書き翻刻化された150種350余冊が、同大の図書館に並んでいるそうです。
さてこの論文の解題によりますと、銀鶏は天保の大飢饉のときに立て続けに倹約生活本を出しており、『家内の花』もそのひとつ。サブタイトルは「たくはえでんじゆ(貯え伝授)」でして、江戸の著名人の家に伝わる(ときどき他の本からの引用や無名の人のレシピも混じってますが)各種常備菜を掲載した本でした。いわば江戸時代のおうちレシピ。ほかには山東京伝や式亭三馬、唐衣橘州なんかの秘伝料理も登場いたします。
さて、例の砧大根のレシピ、ところどころ句読点を足してご紹介しましょう。
<大根のふときを皮のまゝ木口より薄くきり、日にいだして干上(ほしあげ)、からからとなりたるとき、一枚づゝのばして其中へ生姜を千にうちたるをいれて、木口よりいかにもかたく、くるくると巻きてふた物へだんだんにならべてつめ、醤油味淋をとうぶん、酢を其半分合しざつと煮えたてゝ、大根の見えぬ程にかけて貯ふべし。生姜のうちへとうがらしを半分いれたるを紅葉巻といへるよし。口取にいたつて奇也>
皮つきのまま薄く切り、干してからからにしたダイコンで作るのでしたら確かに日持ちしそう。漬け床も醤油1、ミリン1、酢0.5の割合ですから、ぜんぜん味噌漬けじゃありません。日本国語大辞典のものはかなりアレンジされていますねえ。どこから引用したんだろう?
ちなみに銀鶏先生、他人のレシピばかりを集めているわけではなく、この本の筆頭には自身の工夫として、「切餅の貯へ様」というのを載せております。
<酒のあき樽を調へ、鏡の板へ五寸四方の穴をきりあけ、穴の四方を二寸ほどはなして、厚紙にて六寸ほどの丈に袋のなりにこしらへ其内より手を入れて餠をいだし、其跡をしつかりと蓋をして、四方より袋にてふたのうへをたゝみこみ、其上へ手ごろの石をのせおくなり。又樽の外をば、ふたも底もあつがみにて水張に三遍ほどはるべし>
この文からだとちょっと厚紙の袋の仕様がわからないのですが、そこはちゃんとイラストがついております。樽の上に空けた穴にティッシュボックスみたいな箱がセットされておりまして、そこから手を突っ込むようになってました。この貯蔵法なら正月搗いたもちも4月までカビないとか。
銀鶏先生の考えではもちにカビが生えたり酸っぱくなるのは風にあたるからであって、酒樽を密閉したくらいでは空気が入るのは完全に防げず、梅雨は越せないそうです。けれども錫の壺とフラスコに浅草海苔を貯えてみたところ、香気も味も変わらなかったとも述べておりまして、実に科学的かつ実証的な姿勢です。たいしたものです。
さて、そのほか江戸の料理本の献立中に「砧巻き」を見つけたのですが、どれもお菓子でした。これも日本国語大辞典によりますと「小麦粉に砂糖を入れて水でこね、薄く焼いて巻いた菓子」のことだそうです。これだとなんだか葛焼きみたいですね。幕臣にして維新後は出版人になった中根香亭の『酔迷余録』によりますと、「砧巻きは皮葛製にてもあらんか、いと薄く弱かにて、羽二重の如く、是をもて餡を巻きたれば、其の名其の物によく称(かな)へり」とありまして、餡を入れるのもOKのようです。
実際京都の長久堂では「きぬた」という菓子を売ってらっしゃいますが、こちらは羊羹の求肥巻きで、芯の羊羹は赤くて今の料理の砧巻きとよく似ております。嘉永六(1853)年に考案し、パリ万博にも出品したそうで…。
ああああ、すみません。もちどころか、いよいよ求肥巻きになっちゃったよ。杵と槌の話をするはずだったのに…。まだまだ続きます。
投稿者 webmaster : 13:41
2014年12月25日
料理本のソムリエ [vol.65]
【 vol.65】
世界無形文化遺産の共演
和食と和紙の夢のコラボ
1年ぶりのブログ更新です。
前回、世界無形文化遺産登録の裏話をバクロしてしまったのがばれて、農水省に拉致されて「貧乏農場」で働かされておりまして……というのはウソですが、ブログをさぼってせっせと農作業をしてたのはホントです。
屋上農場の経営(vol58参照)が病膏肓に入りまして、今年はピーマンを植えたりスイカに手を出したりバケツ稲に挑戦したり。このブログを執筆するには、裏づけ調査のために土日はせっせと図書館に通わなければならないのですが、水やり虫取り堆肥づくりにせっせと精を出してました。それが寒くなってきて、芋も掘ったし豆も植えたし、することがなくなったので再開です。
そうこうしているうちに、もう次の世界無形文化遺産が決まっちゃいました。今度は「和紙」なんですね。実は2009年には石州和紙が指定を受けており、それに本美濃紙と細川紙を追加して指定し直しただけなんですが、5年前と違ってずいぶん話題になりました。
というわけで今回のテーマは「和紙が和食に貢献したこと」について。心を入れ替えて政府におもねりたいと思います。近頃はメディアが国益を損ねるとしかられるみたいだし。
まっさきに浮かぶのは「紙塩」ですかねえ。素材にぬらした和紙をかぶせて、その上から塩をふり間接的に塩味を回す技法です。淡くデリケートな味つけですね。
それから「奉書焼」。松江名物としても有名な、素材を和紙で包んで焼く焼物です。適度な蒸し焼状態になり、焼き汁が逃げません。まあどっちも洋紙でも作れないことはないと思いますが、なんとなく和紙じゃないとサマになりません。
ちょっと変わったところでは「紙鍋」なんてのもありますね。金属の籠の内側に和紙を敷いて鍋代わりにして煮るという、現在見られるスタイルの紙鍋は、大阪の「蘆月」が始めたそうです。昭和5年刊行の『京阪食べある記』(vol42参照)で松崎天民が、「幻妙不思議鍋」という章を立てて、創業当時から話題となった紙鍋についてレポートしています。
「この紙鍋と云ふ奴、紙製の鍋と思ひきや、銅製の鍋の形した鋼の上、薄い美濃紙一枚を敷いて、それにだしを入れたり、鯛や海老やいかを入れてジワジワと煮て食べるのである」
銅製の鍋の形の「鋼」というのが今の金網にあたるかどうかわかりませんが、魚すきの一種と見なされていたようですし、ほぼ同様の形とみていいでしょう。
「抑(そもそ)もその美濃紙一枚の上には、何か知らぬ油を布いてあつて、その油に曰く因縁種仕掛がおますのやろ。少し遠い炭火ではあるが、汁のアクや魚の脂肪は煮え立つと共に紙の裏面に廻つて、魚も汁も極めて美味く食べられるのが蘆月紙鍋の自慢だとある…(略)…紙一枚が鍋の危なかしさも、時にとつての座興であるが、その煮た物が美味いとあつては、無條件に頭が下がつてしまう」
天民先生べたぼめであります。当時道頓堀には金鍋を使う肉屋があって、銀鍋であればざらにあり(そういや魯山人の「銀茶寮」は銀鍋が売り物でした)、朝鮮風の石鍋もあったそうですが、「美濃紙一枚の紙鍋は、何と云つても珍中の珍」なんだそうで。こうなると、この紙の秘密が知りたいところですが、「何でもあらへんもんだすがな。そやけどな、しやべつてしもたら、人に真似されますよつてに、秘密の法で威張つて居まんね」と天民に向かって笑う「蘆月」の女将さん。うーん、いけずですなあ。
 ただ、これよりもっとシンプルな紙鍋は、はるか200年前から存在しておりまして、享保17(1732)年序の『万金産業袋(ばんきんすぎわいぶくろ)』に出てまいります。紙を折って箱形にして、それを鍋代わりにして豆腐を煮ちゃう。茶袋のような細長い形にして酒の燗をつける「ちろり」代わりにするという使い方もあるとか。どうもこれは手元にあるものを使って鍋を作る、手品的効果を狙った料理(vol14参照)のようです。使い終わったら燃やしてしまえばいいわけで、片付けが楽そうだしね。
ただ、これよりもっとシンプルな紙鍋は、はるか200年前から存在しておりまして、享保17(1732)年序の『万金産業袋(ばんきんすぎわいぶくろ)』に出てまいります。紙を折って箱形にして、それを鍋代わりにして豆腐を煮ちゃう。茶袋のような細長い形にして酒の燗をつける「ちろり」代わりにするという使い方もあるとか。どうもこれは手元にあるものを使って鍋を作る、手品的効果を狙った料理(vol14参照)のようです。使い終わったら燃やしてしまえばいいわけで、片付けが楽そうだしね。
紙製の鍋を火にかけたらすぐ燃えてしまいそうですが、紙の発火点は華氏451度(233℃)っていいますから、鍋の中は汁が沸騰しても100℃どまりなので、煮つまるまではそれ以上温度が上がらず火がつく心配はないというわけです。どちらかというと紙がふやけて汁がもれちゃいそうではらはらしますが、その点蘆月では、秘密の油を引いておりました。
いっぽう『万金産業袋』では、コンニャク糊を引いて耐水性を高めた紙で作るとあります。コンニャク糊は逆に料理のほうが和紙に貢献した事例でして、コンニャク引きの紙はなんと布代わりに使われていました。軽くて水をはじくので、僧侶の服や陣羽織などになったそうです。さらに先の戦争では、世界初の大陸間弾道兵器である風船爆弾にも使われました。不発弾を回収したアメリカ軍は、さぞや首をひねったことでありましょう。
うーん、なんだかどの事例もぱっとしないですねえ。
そこで真打のご登場。焼海苔こそが製紙技術を食品に転用したものであり、日本が誇る文化です。なにせSUSHIには欠かせませんぞ。
 ただし海苔作りに使われているのは漉返紙(地漉き紙)、つまり再生紙の技術です。使い古した紙を水に浸けてふやかしてよく砕き、簾を敷いた枠の中に流し入れ、これを干して再び紙として使うわけです。世界無形文化遺産の和紙作りでは、水中で枠をゆらして繊維を均一に広げる「流し漉き」に職人技が光りますが、こちらはもっと簡単な「溜め漉き」です。元の紙の字や模様なんかが砕ききれなくて残っちゃったりするのはご愛嬌。
ただし海苔作りに使われているのは漉返紙(地漉き紙)、つまり再生紙の技術です。使い古した紙を水に浸けてふやかしてよく砕き、簾を敷いた枠の中に流し入れ、これを干して再び紙として使うわけです。世界無形文化遺産の和紙作りでは、水中で枠をゆらして繊維を均一に広げる「流し漉き」に職人技が光りますが、こちらはもっと簡単な「溜め漉き」です。元の紙の字や模様なんかが砕ききれなくて残っちゃったりするのはご愛嬌。
海苔の歴史は少々ややこしくて、宮下章先生の『海苔』によりますと、初期の浅草海苔は今みるような漉き海苔ではなくて、自然に生えた海苔を摘んで、広げのばして干しただけの簡単なものだったようです。葛西あたりで採った海苔を浅草観音の参詣客目当てに販売したのが始まりで、浅草には海苔専売の商人も現れました。
浅草で海苔が「作られる」という記述が見られるようになったのは、万金産業袋と同じ享保の頃。ちょうどこの頃には品川で「海苔ひび」を使った海苔の養殖が始まります。浅草には紙すき町という地名があるほど再生紙作りが盛んに行なわれていまして、その技術と出会い、今みるような漉き海苔が誕生したわけです。「浅草の名物観音、海苔と紙」っていう句があるくらい、海苔と紙は浅草を代表する商品となりました。
宮下先生の本には、「巻鮓の現れた時期は明らかではないが、安永のころ(1772―81)になると、すでにいろいろな巻鮓が作られている。笹巻、ゆば巻、玉子巻、海苔巻がそれである」とあります。安永年間の『新撰献立部類集』には海苔巻きの作り方があり、浅草海苔、河豚の皮または紙をすだれに敷いて、飯をのせ、魚を並べてすだれで巻きます(宮下先生はフグの皮や紙でできたすだれと解していますが、恐らく間違いです)。ここまでは今の巻き簾の使い方と変わりませんが、最後に四角い枠に入れて重石をかけるそうです。押しずしの変形だったんでしょうか。
宮下先生によると、そもそも巻きずしは湯葉や昆布などで巻くほうが古く、関西や九州では明治になってもこちらのタイプのほうがポピュラーだったそうです。江戸時代の漉き海苔はまだまだ高級品で、海苔でくるんだおにぎりや缶入りの海苔が全国の家庭に普及するのは第一次世界大戦後からだとか。この頃、全国に養殖産地が広がり、遠く朝鮮半島でも海苔が作られるようになり、海苔の生産量が激増するのです。
となると節分の恵方巻は、海苔巻の販売促進のために始まったもの、という説明も合点がいきますね。「恵方巻」の起源と普及の研究は、熊本大学の岩崎竹彦先生が先駆者で、広島の食品メーカー「あじかん」50周年記念誌の『日本の伝統食巻寿司のはなし』に1章を立ててまとめておられます(残念ですが非売品。私は広島の「喜多丘」さんにいただきました)。戦前の大阪の鮓商組合による「恵方に向かって巻寿司の丸かぶりすると大変幸運に恵まれるという習しが昔から行事の一つになつてゐて年々盛んになつています」などと書かれたビラの存在が確認されておりまして、戦後になってからは大阪海苔問屋協同組合も協力し、飛行機でビラをまいたこともあったそうです。
 しかし昭和45年小社刊の『すしの本』(vol2参照)で篠田統先生が恵方巻について興味深い証言を残してくれています。「四十四年の節分の日、日本風俗史学会食物史分科会の月次例会の席上、大阪市立博物館の平山敏治郎館長から「ここへ来る途中、阿倍野橋のすし屋の表に本日巻きずし有りという広告を見たが、何のことかしら」という質問あり。美登利鮓の久保登一氏の返事に、節分に巻きずしを食べる風は大正初めにはすでにあった。おもに花街で行なわれ、ちょうど新こうこうが漬かる時期なので、その香の物を芯に巻いたノリ巻を、切らずに全(まる)のまま、恵方のほうへ向いて食べる由。老浪華人の塩路吉兆老も今日まで知らなんだ、と言われる。もちろん、私も初耳だ。普通の町家ではあまりやらないようだ。全国ではどうだろうか」
しかし昭和45年小社刊の『すしの本』(vol2参照)で篠田統先生が恵方巻について興味深い証言を残してくれています。「四十四年の節分の日、日本風俗史学会食物史分科会の月次例会の席上、大阪市立博物館の平山敏治郎館長から「ここへ来る途中、阿倍野橋のすし屋の表に本日巻きずし有りという広告を見たが、何のことかしら」という質問あり。美登利鮓の久保登一氏の返事に、節分に巻きずしを食べる風は大正初めにはすでにあった。おもに花街で行なわれ、ちょうど新こうこうが漬かる時期なので、その香の物を芯に巻いたノリ巻を、切らずに全(まる)のまま、恵方のほうへ向いて食べる由。老浪華人の塩路吉兆老も今日まで知らなんだ、と言われる。もちろん、私も初耳だ。普通の町家ではあまりやらないようだ。全国ではどうだろうか」
この本は昭和41年に出版されておりまして、45年版は版型を大きくして加筆したもの(今さらですが吉兆は誤植でして、正しくは塩路吉丁でしょう)。わざわざ新たに一項立てたのは、篠田先生てばよほど印象に残ったのでしょう。ちなみに大阪市立博物館の後継施設である大阪歴史博物館には、昭和15年の節分の日付がある「美登利」が配った「幸運巻寿司」のビラが所蔵されています。
このことから当時の大阪人でも知らないほうが多数派で、今のように普及するのはスーパーやコンビニが宣伝するようになってからというのがうかがえますね。鮓商組合のいう「昔から」というのは何を根拠にしているのかはわかりませんが、江戸時代ではなさそうです。だいたい無言で1本丸まる食べるなんて贅沢でお行儀の悪い食べ方、宴会芸以外の何ものでもないもんね。節分の座興もいいけど、こぼしたり残したりしてはいけませんぞ。なにせ海苔巻の海苔は日本の誇る「モッタイナイ」文化が生んだ、リサイクル技術の応用なんだから。
そういえば海苔ってちり紙と形も大きさも似ているよね……って言っても、みなさんロールペーパーやボックスティッシュしか知らないか。「毎度おなじみのちり紙交換」って言ってもぴんとこない若い人も多いかもね。これまた無形文化遺産に指定してもらわないと……。
投稿者 webmaster : 10:48
2013年12月26日
料理本のソムリエ [vol.64]
【 vol.64】
特定秘密の漏洩に当たらないうちに
世界無形文化遺産登録について
しゃべっちゃおう
「和食」の世界無形文化遺産登録が12月5日にユネスコによって決定しましたね。去年からはらはらしながら見ていたのですが、やれやれという感じです。ここまできたらこれまでの流れについて、知ってることをばらしても怒られないよね? つかまらないよね?
一部でも報道がありましたが、最初日本は「会席料理(正確には“会席料理を中心とした伝統をもつ特色ある独特の日本料理”。特色と独特がかぶってますね)」で登録しようと考えていて、途中であわてて「和食」に変更しました。というのも日本より一歩先んじて登録をめざしていた「韓国宮廷料理」が、昨年の予備審査の段階で差し戻しを食らったからです。予備審査を行なう委員会補助機関の担当国は持ち回りで、このときはイタリア、クロアチア、べネズエラ、ケニア、ヨルダン、そして韓国も入ってました。ですから通過は鉄板だと思われていたのですが、「文化を享受している層が少ない」とみなされて、追加情報の提出を求められてしまうというまさかの展開。無形文化遺産は万が一登録を却下されても、世界遺産の場合と違って4年待てば再チャレンジすることができますが、臆して取り下げてしまったようです。韓国宮廷料理は「チャングム料理」という遺伝子操作で生まれた新種がすごい勢いで増えて生態系を脅かしているので、「緊急に保護する必要がある無形文化遺産」にも相当すると思うのですが…(まさか、この機に乗じて新種も一緒に認定してもらう気だったんじゃないでしょうね?)。
韓国のつまづきで、浮き足だったのが日本側。お高そうな会席料理では同じ轍を踏みかねないと方向修正することになりました。それでか昨年農水省のお役人さんが、ヒヤリングなのか湯島天神へ登録合格祈願するついでなのか、わざわざ小社にもみえました。ご苦労様です。ところでなんで仕切っているのが文化庁じゃなくて、農水省なんだろ?
それで「日本料理」の資料として、京都府の提案書というのを見たのですが、もうがっかりしたりあきれたり。「さしすせその基本調味料」「料理の字義は“はかりさだめる”」「割主烹従」「五味五色五法の技法」「料理の三真」…でてくるわでてくるわ。これらのお題目の真偽はおいといて、どうやって外国の人に説明するつもりだったのでしょう?
「ソモソモさしすせそとは何のコトデスカ? ナゼshouyuがseなのデスカ?」「リョウリがナゼ、料リ理メルと同じなのデスカ?」 本題に入る前に、まず日本語表記と五十音図の歴史から説明しなけりゃなりません。こんなのプレゼンで用意してどうするつもり?
先の提案書は、何が日本料理の特徴なのかさっぱりつかんでおりませんし、その中の何を伝えたいのか、まだ海外に知られていない魅力は何か、整理されておりませんでした。ただなんとなく偉そうな料理関係のフレーズ(日本料理の世界では割合よく見る香具師口上)を書き連ねて立派そうに見せただけ。こりゃ先が思いやられるよ…。
会社にみえたお役人さん(上司の方もご臨席になるはずがドタキャンあそばされ…じゃない、ご多忙によりおめもじかないませんでした)には、そもそも何のために無形文化遺産に登録するのかって訊ねてみました。なんかいいことあるのかしら。
料理がらみでほかに登録されているのは2010年の「フランスの美食」「メキシコの伝統料理」「イタリア、スペイン、ギリシア、モロッコの地中海ダイエット(ダイエットといっても減量じゃなくてオリーブ油を使う食習慣って意味です)」だそうです。じゃあ無形文化遺産になった後で、フランスやメキシコはそれをどのように国内や対外的に生かしてきたのか。日本は登録されたらこれからどうするつもりなのか…。ところが、将来登録の条件が厳しくなりそうなので、韓国に先を越される前に…というあせりが先に立っていて、今後についてはこれから検討するという。走りながら考えている感じ。
とにもかくにも日本料理の魅力をPR(ひいては日本の食材。農水省だからね)したいらしいので、「外国人が知っている日本料理は寿司だったり天ぷらだったり焼き鳥だったりすき焼だったりするので、会席料理で登録するにしてももっと門戸を広くして、天ぷら会席だとか鳥会席だとか言いくるめて、これらも強引に含めちゃいなさい。あと、登録したあとのPRでは各種料理人の協力も必要になるでしょうから、そっぽを向かれないように、今のうちに挨拶回りでもしておきなさい。調理師団体は衛生や就労の関係から厚労省の肝入りなので」と言っておきました。例の「食育」って奴の場合、厚労省と農水省と文科省でこいつはうちの縄張りだと取りあいっこしていて迷走していますからね。
そうしたらいきなり寿司どころか「会席料理」の看板を取り下げて「和食」に替えたので、ずいぶん思い切ったことをするなあ、と思ったんです。ゲイシャガールやティーセレモニーの知名度に頼って登録する作戦だとばかり思っていたのに…。農水省HPに挙げられております和食の特徴をみますと「多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重」「栄養バランスに優れた健康的な食生活」「自然の美しさや季節の移ろいの表現」「正月などの年中行事との密接な関わり」とありまして、ずいぶん観念的だし、程度の差こそあれ他国の料理文化でも言えないこともない。こんなふわっとした説明で大丈夫なのか?
そんなこんなで心配していたのですが、まあ無事に通りまして一安心。お隣の韓国も「キムジャン文化(キムチ作りとおすそ分けの習慣)」が登録されまして、顔が立ちましたし。キムチそのものが無形文化遺産になったわけではないので、商業的な宣伝に使うなと、ユネスコに釘を刺されていましたけど。
ところで、この世界無形文化遺産ってなんなのでしょう。報道では料理関係としてもうひとつ2011年登録の「トルコのケシュケキの伝統」っていうのを含めて、「食の文化遺産はこれまでに4つある」というふうに説明されていますよね。ガストロノミー、先住民族の食文化、地中海世界共通の食生活ときて4つめだから、これってかつてヨーロッパを震撼させたオスマントルコを象徴するような究極の料理かと思いきや、“麦粥”って説明されています。いきなりスケールダウンだよ。ちょっと調べてみるといたしましょう。
なぜか小社は『トルコ料理 東西交差路の食風景』っていう立派な本を出しておりまして、オール現地取材で食材や料理を紹介する凝りようは、他書の追随を許しません、ていうか、どの出版社もついてこようとしていません。なにせコーディネイトした現地スタッフがシリア国境に近い田舎出身で、錦を飾りたいがために自分の故郷に日本のカメラマンを呼んじゃった。そのためいきなり遊牧民の生活の紹介から始まりまして、子ヤギ一頭のさばき方が載っています。イスラムの教えにのっとった屠畜の映像は一見の価値あるものですが、図書館で小学生男子が女子に見せてきゃーきゃー大騒ぎするのに使われているかも。まあ、欧米人からみると小社の魚のおろし方の本も、おんなじように見えるのかもしれませんが。

ところがそんなレア映像も載っているこの本にも、ケシュケキは収録されていませんでした。ケシュケキはアナトリアや黒海といったトルコでも田舎のほうで行なわれるものなのに、残念です。
幸いユネスコの世界無形文化遺産のHPにはケシュケキ作りの動画がアップされていました。おじさんおばさんたちが歌いながら、麦を杵と臼でついて引き割り麦に加工しておりまして、餅つきみたい。肉と一緒に鍋に入れて棒で叩き混ぜてくずしながらどろどろになるまで煮て、トマトソースをかけてみんなで食しておりました。ただし同じ器から直箸ならぬ直スプーン。よーく叩いてガムみたいにびよーんとのびればのびるほどいいそうで、最近はケシュケキ作り用のミキサーもあるそうです。これまた餅みたい。
 ケシュケキは婚礼料理だと説明されている報道もありましたが、お葬式のときだって作られます。つまり共同体で人が集まる機会に作られる料理ってわけ。日本でいえば餅つきとか芋煮会みたいなもんですかね。レストランのメニューにないのは当然ですし、トルコ人でも都会暮らしの人にとっては縁がありません。ですから、一昨年ケシュケキが世界無形文化遺産に登録されても、話題にならなかったそうです。それよりも、ナザル・ボンジュー(トルコへ旅行した人ならご存じの、そこらじゅうにある魔除けの目玉です)が落選したことのほうが彼らにとって大問題だったそうで。今年は「トルココーヒーの文化と伝統」が無形文化遺産入りしたので、トルコの人も面目が立ったかな?
ケシュケキは婚礼料理だと説明されている報道もありましたが、お葬式のときだって作られます。つまり共同体で人が集まる機会に作られる料理ってわけ。日本でいえば餅つきとか芋煮会みたいなもんですかね。レストランのメニューにないのは当然ですし、トルコ人でも都会暮らしの人にとっては縁がありません。ですから、一昨年ケシュケキが世界無形文化遺産に登録されても、話題にならなかったそうです。それよりも、ナザル・ボンジュー(トルコへ旅行した人ならご存じの、そこらじゅうにある魔除けの目玉です)が落選したことのほうが彼らにとって大問題だったそうで。今年は「トルココーヒーの文化と伝統」が無形文化遺産入りしたので、トルコの人も面目が立ったかな?
それにしてもキムチもケシュケキも料理というよりは、それを作る習慣のほうに焦点があたってますよね。実は無形文化遺産には別に「料理」というカテゴリーがあるわけではないのです。じゃあ食の文化遺産が4つっていうのも、数え方次第でどうにでもなるじゃない。どうして2010年登録の北クロアチアのジンジャーブレッド作りっていうのは含まれないのか、食べられる素材で作ってあっても飾りだからダメなのか、と思っていたのですが、これで合点がいきました。
 それなら日本でも能登地方の「アエノコト」という、田んぼの神様に料理をお供えする儀式が2009年に登録ずみ。せっかくだからこれも仲間に入れてあげてよ。アエノコト(アイノコトとも書きます)は、民俗学の世界では民間の新嘗祭として有名な祭り。田んぼから神様を家までお連れして、お風呂に入れて、食事でもてなします。田んぼの神様は目が不自由な老夫婦なので(“設定”とかいうんじゃありませんよ)、主人が手取り足取りお世話いたしまして、料理については一つ一つ説明いたします。二股のダイコンとハチメ(メバルの仲間)がつきもので、ほかにブリや野菜の煮物などをお供えし、あとでみんなでおいしくいただきます。食事だけの行事ではありませんが、料理なしでは成り立ちません。
それなら日本でも能登地方の「アエノコト」という、田んぼの神様に料理をお供えする儀式が2009年に登録ずみ。せっかくだからこれも仲間に入れてあげてよ。アエノコト(アイノコトとも書きます)は、民俗学の世界では民間の新嘗祭として有名な祭り。田んぼから神様を家までお連れして、お風呂に入れて、食事でもてなします。田んぼの神様は目が不自由な老夫婦なので(“設定”とかいうんじゃありませんよ)、主人が手取り足取りお世話いたしまして、料理については一つ一つ説明いたします。二股のダイコンとハチメ(メバルの仲間)がつきもので、ほかにブリや野菜の煮物などをお供えし、あとでみんなでおいしくいただきます。食事だけの行事ではありませんが、料理なしでは成り立ちません。
アエノコトは1976年には日本の重要民俗文化財に指定されています。実は無形の文化遺産を保護するという制度は世界に先駆けて日本で始まりました。ユネスコの無形文化遺産はそうした取り組みを参考に2003年に条約が結ばれ、2008年から登録がスタートした新しい制度なのです。ユネスコ日本政府代表部でこの条約の成立時から関わってきた七海ゆみ子氏の『無形文化遺産とは何か』には、誕生の経緯や“無形文化”という概念を各国の言葉でどのように共有するのかといった苦労(この条約の正文は6カ国語で書かれているので)などとともに、この制度の全容がまとめられております。この本を読めば、世間がなあんとなく思っている、「日本の重要無形文化財の世界版」「世界遺産の無形文化版」とはけっしてイコールではないことがわかります。
そもそも無形文化遺産は世界遺産とは同じユネスコでも担当部署は別ですし、設計思想が異なります。最初は「傑作」という形で登録が始まったものの、すぐに「優れているから認定する」というスタンスをとらなくなりました。遺跡や建物、景観を対象とする世界遺産では先進国ばかり認定されることへの反省や、民俗文化の保護が遅れがちな第三世界を支援する目的ではじまったのであって、優劣をつけるためではありません。それで非常に登録が難しい世界文化遺産と違って、ちゃんと書類を揃えて申請すれば原則登録可能とし、文化を維持するコミュニテイの存在や、人類の文化の多様性という視点を重視する姿勢を打ち出しています。
フランス料理が登録されたのは、料理技術が優れているからではなくて、フランス人のレストランでの会食の習慣が評価されてのこと。地中海世界全体の食習慣と能登半島の家族のお祭りが同列の扱いなのも、文化に優劣はないというスタンスからです。
ところが中国・韓国がわが国の優れた文化を世界に知らしめるチャンスとばかりにやたらと登録しようとしてきたので、事務作業が膨大なことになりユネスコはてんてこまい。いっぽう日本も、300近くもある国の重要民俗文化財を指定の古いものから順に送り込むという機械的なお役所仕事をするものだから、後ろがつかえてます。これでは本来もっと申請してほしいアフリカやアジア諸国からの登録がさっぱり進まない。業を煮やして1国あたりの申請数を制限すべきという意見も飛び出しました。農水省があせったのはそのせいなんですね。こうした苦悩と問題点は『ユネスコ「無形文化遺産」生きている遺産を歩く』でレポートされております。
ネットをみていると韓国と中国の世論は無形文化遺産の趣旨をまったく理解していないみたいですね。「和食よりもわが中国料理のほうが優れているのにおかしい」とか(くりかえしますが、優秀かどうかはいっさい関係ないのです)、「日帝に先を越される前に済州島の海女文化の登録を急げ」とか(よく似たものは共同登録すればいいのです。地中海ダイエットなんか今年さらに3カ国が相乗りして7カ国共同になりました)、ナショナリズムを煽る煽る。もっとも日本人だってあんまり変わりません。和食ハラショー日本サイコーっていう論調がおおっていますが、もっと落ち着いて自らの食生活を見直したほうがいいですよ。
それに「和食、日本人の伝統的な食文化」が世界無形文化遺産になったって報道されていますけど、正確には「和食、日本人の伝統的な食文化 ― 正月を例として」じゃないですか。ユネスコの和食を説明する動画をみると、餅はつくわお重が並ぶわ子供が親御さんの指導で魚をおろすわで、ちょっと赤面しちゃいます。わが家じゃお供えは飾らないし、おせちだって作ってないぞ。毎年買ってきたのし餅を切って紅白なますを瓶一杯作るくらいだよ…。こりゃあ大変だ。皆さんも無形文化遺産の継承作業、がんばってください。
投稿者 webmaster : 16:29
2013年12月06日
料理本のソムリエ [vol.63]
【 vol.63】
畑のトマトをもぎとった少年はおもむろに…
 さてさて、ケチャップの話はいい加減これくらいにして、再び生のトマトのお話を。明日にも枯れんばかりだった我が家のミニトマト(vol58参照)は見事回復あそばされまして、ついに結実なさったこの喜びを、早くご報告したくてうずうずしていたのですが、朝ドラにつられて寄り道が過ぎました。もたもたしている間に熟して落っこっちゃうよーと思いきや、開花が遅れたせいと日が低くなってビルの陰になったせいとで、いつまで待っても赤くなってくれません(泣)。
さてさて、ケチャップの話はいい加減これくらいにして、再び生のトマトのお話を。明日にも枯れんばかりだった我が家のミニトマト(vol58参照)は見事回復あそばされまして、ついに結実なさったこの喜びを、早くご報告したくてうずうずしていたのですが、朝ドラにつられて寄り道が過ぎました。もたもたしている間に熟して落っこっちゃうよーと思いきや、開花が遅れたせいと日が低くなってビルの陰になったせいとで、いつまで待っても赤くなってくれません(泣)。
日本へのトマトの伝来については、横浜の外国人居留地で初めて栽培されたとか、政府が試験栽培したっていう話はいろんなとこに載ってますが、じゃあその後、どんな品種が栽培されるようになって、どんなふうに消費者に受け入れられるようになったのか。たとえばミニトマトって昔はなかったのか…ってのが今回のテーマ。
結論からいうと、導入当時のトマト品種はいろいろあってバラエティ豊かだったのが、次第に日本人好みのものに絞り込まれて、同じようなものばかり作られるようになった模様です。今の日本のトマトは桃太郎とファーストという二大品種が君臨していまして、どちらも“桃色系”といって皮が透明で薄いタイプなんですが、これは世界的にみると特殊な現象。戦前は皮が赤くて厚い“赤色系”のトマトも作られていましたし(近年は、調理用として再び日本でも栽培されるようになってきましたね)、「金柑トマト」という愛称で、黄色いミニトマトすらありました。
 戦前の品種名を見ているとベストオブオールとかアーリアナとか英語名ばかり目につきまして、アメリカやイギリスの種苗会社から種を導入していたことがわかります。中でも桃色系のポンデローザという大型品種が人気でした。今でもトマトのイラストが、ひだひだのあるつぶれた扁平な姿に描かれるのは、この品種の与えたイメージが大きかったのだと思います(桃太郎はつるんとして丸いし、ファーストはお尻がとんがってるもんね)。これを親にして愛知トマトや世界一なんていう国産品種も作り出されました。
戦前の品種名を見ているとベストオブオールとかアーリアナとか英語名ばかり目につきまして、アメリカやイギリスの種苗会社から種を導入していたことがわかります。中でも桃色系のポンデローザという大型品種が人気でした。今でもトマトのイラストが、ひだひだのあるつぶれた扁平な姿に描かれるのは、この品種の与えたイメージが大きかったのだと思います(桃太郎はつるんとして丸いし、ファーストはお尻がとんがってるもんね)。これを親にして愛知トマトや世界一なんていう国産品種も作り出されました。
ちなみにこのトマト、ポンデが発音しにくかったのか昔から「ポンテローザ」とまちがわれることが多く、試しにポンデとポンテでネットで検索してみたら、ヒット数はかなり拮抗していました。ポンデローザのほうが一馬身優勢ってとこでしょうか…。ただし、どうやらポンデローザという名前の競走馬もいるらしくて、これがヒット数に加算されているみたい。おまけにこの馬も「ポンテローザ」としているサイトが結構ありまして、もう何が何やらわかりません…。ちなみにponderosaはラテン語で「重い」という意味なので、バラやレモンや松などにもこの名の品種があるようですね。
なお宮沢賢治の『黄いろのトマト』にも、このトマトが登場しています。この童話は原稿のみの未発表作で、ミニトマトは表記がチェリーになったりチェリイになったりぶれているのですが、ポンデローザは「テ」になったりはしていませんでした。さすがあ。
<だからね、二人はほんとうにおもしろくくらしていたのだから、それだけならばよかったんだ。ところが二人は、はたけにトマトを十本植えていた。そのうち五本がポンデローザでね、五本がレッドチェリイだよ。ポンデローザにはまっ赤な大きな実がつくし、レッドチェリーにはさくらんぼほどの赤い実がまるでたくさんできる。ぼくはトマトは食べないけれど、ポンデローザを見ることならもうほんとうにすきなんだ。>
この童話は、博物館のハチドリの剥製(そりゃあトマトは食べないでしょう)が作者に語りかけてきたというストーリー仕立てでして、面白く暮らしていた二人というのは、ペムペルとネリという幼い兄妹。不思議な異国の香りがする話ですので、トマトもそんな外国の野菜という感覚で登場しているのでしょうか…。それでも大正末の宮沢青年にとって、トマトは童話の小道具になるような親近感のある存在だったと思います。
もちろんその域までたどりつくには、トマトの枝みたいにくねくねうようよ曲折があったのはいうまでもありません。さかのぼって明治の子供たちにとってトマトがどんな野菜だったかは、木村毅の昭和14(1939)年刊行の随筆集『南京豆の袋』に収録された「トマトが初めて村へ来た頃」に描かれております。
いきなり木村毅って書いてもちょっとわからないですね。だいいち下の名が読めません。同郷の政治家の犬養毅にあやかってこの名がつけられたそうなんですが、キムラ・ツヨシでもタケシでもなくて、キムラ・キって読むそうです。へんなの。彼は文学者でも作家でも学者でもない、自称「投書家あがりの文士」。投書家というのは雑誌への投稿で腕を磨いてきた叩き上げという意味でして、小説や伝記、翻訳書を著すかと思えば、文学史や明治文化史を研究するいっぽうで、編集者としても活躍しておりまして、『明治文化全集』は彼の編集です(vol31の『西洋料理通』が収録されている本。もっとも彼が担当したのは戦後の増補版ですが)。その業績は多岐にわたり、書誌学者の谷沢永一が乗り出して、膨大な著作リストをまとめています。
ちなみに彼が編集した本の中には昭和26(1951)年刊行の『東京案内記』というのがありまして、戦前の東京案内書が備えていた格調の高さと戦後のタウンガイドのような情報量の多さの両方を合わせもった、過渡期的な作品です。戦禍から息を吹き返した昭和20年代半ばの料理店の動向を調べるのに役立ちます(たとえば会社の近く池の端のうなぎ屋「伊豆栄」はこの時期旅館をしていたとか)。ですがこの本、実は図書館泣かせ。天下に名だたる谷沢先生も東京のガイドなんかにゃとんとご関心がなかったせいかお気づきありませんが、なぜか初版が9月10日と10月25日の2種類あるんです。同業者のカンというか憶測ですが、どうも出版上のトラブルがあって急遽刷り直した気配が…。ひゃー。くわばらくわばら。
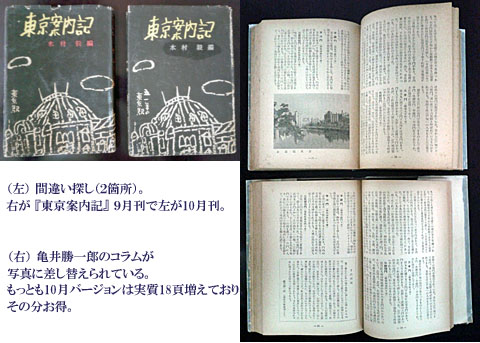
おおっと、脱線はこれくらいにして、話をトマトに戻しましょう。ところは岡山県の東の勝間田村、ときは日露戦争が始まった明治37(1904)年。村一番の新し物好きの素封家に生まれた木村少年が、10歳のときにもらった一袋のトマトの種をまいてみた顛末、長いのでところどころはしょりながら引用してみます。
<やがて黄色い、小さい花が、葉陰にさきだした。「やつぱりなすだなあ。花の形はこちらのもの(日本の)と同じだ。」と奉公人がのぞいてゐる事があつた。(…略…)私は或る朝、もういゝと思つて一つ千切つて、本能的に鼻口に持つてつてにほひをかいでみた。そして思はずそれを地面へたゝきつけた。それから私は、ふろ場へ駆け込んで、石鹸で手を洗つては、二度も三度も指先をかぎ直してみた。かいでは又、皮膚のすりむける程、石鹸でこすつた。
私は生まれてから、あんなにひどい、厭らしい、悪臭をかいだ事はないやうに思つた。>
童話や朝ドラと違って現実の子供ったら横暴な……。いきなり地べたにスプラッタですよ。嫌らしい悪臭って、トマトかわいそう。
<その夏休みに、兄が都会から帰つて来て、庭さきの西洋茄子を見ていつた。『はゝあ、うちでもこれを作つたのかい。拙(まづ)いもんだらう。おれも神戸にゐる時、八百屋の店さきでこれを見つけて、てつきり柿だと思つた。いくらだと聞いたら一銭に三つだといふから、馬鹿に安いなと思つて、買うて帰つて、かぶつて見て吐き出したよ。』(…略…)そして西洋人はこれをどんなんして食べるのかゞ、随分、問題になつた。焼くにしても、煮るにしても、日本のなすのように堅くなくてプヤプヤしてゐるのだから、手が付られない>
兄弟して、もうさんざんな言いよう。ちなみにこのあと、お母さんがもったいない精神を発揮してぷやぷやする前の青いトマトを漬け物にしたものの、誰も箸をつけなかった、なんてオチも出てきます。
<それから六年たつた明治四十三年に上京したが、あの頃は洋食をたべに行つても、カツレツやビフテキにつくのが、キャベツの刻んだのだつた。
それからどの位な年月が立つてかであつたかよく覚えてないが、或る洋食屋で始めて紙のやうに薄つぺらに切つたトマトが、刻んだキャベツと一緒に皿の上へ載つて来た。
「はゝあ、西洋なすが載つて来たとは珍らしいなあ。これはかうして食ふもんかえ」
「馬鹿! 何が西洋なすなもんか。トマトだい。」
と、同行の友人(中村白葉君)が教へてくれた。私は始めてそれがトマトといふ名のものである事を知つた。それからいつしか私はその味になれて、馬鹿にトマトを貪食するやうになつた。
イギリスにゐる時、北の田舎のヨークシャアの古城で開かれた独立労働党の夏期学校の食卓で、私はトマトの皮をむいて食塩をふりかけて食べてゐたら、傍の女学生が不審さうに聞いた。
『へえ、日本人はトマトの皮を捨てますか。私達はそれをカチリと歯でかみ切つて食べるのに快感を覚えるのですが。』
これで私ははじめてトマトの皮ごと食べるものである事を知つた。私の遅鈍なる、トマトを完全に克服するまでに正に二十五年かゝつた。>
明治23(1890)年生まれの翻訳家の中村白葉は、10歳まで神戸で育ったために洋食好きを自認しておりまして、木村兄と違ってトマトに理解があったのでしょう。どうやらトマトはキャベツのせん切り同様、まずは外食の付合せとして認知されたようです。そういえば卯野め衣子さんは木村の一回り年下なんですねえ。すごい世代間ギャップ。明治44年の開明軒たらクロケットの下にトマトの角切りやらパイナップルやら、時代の先端を走りすぎ……って、おっとそれは言わない約束でした。
ただ明治も37年ともなると、岡山の少年がトマトの種を手に入れることができたところから察するに(どこから手に入れたかは書いてありませんでした)、この頃にはトマトが広く栽培されていたこともうかがえます。お兄さんは神戸の八百屋で馬鹿に安く売ってたって言ってますしね。
明治42(1909)年、はじめて国の統計にトマトが採用されるようになります。その時の生産面積は39町歩(つまり約39ヘクタール)で、生産量は513トンでした。同じ年のタマネギが945町歩で13700トン、キャベツが2000町歩で33000トンなのとは比べものになりませんが、それでもこの程度の量は作られていたんですね。大正12(1923)年には346町歩で5480トンと、10倍の規模になっていますが、まだまだ洋食の付合せはキャベツが優勢だったってことでしょう。なお『カゴメ一〇〇年史』の資料編によると、大正12年にカゴメ1社が調達したトマトだけで262トンにのぼるそうです。
生産量は増えたものの加工用の占める割合も高くて、家庭での普及はもうちょっとかかったことでしょう。森田たまのいうように、夏にしか出回らなかったようですし。木村毅のように抵抗感なく食べられるようになった者もいれば、「まったく嫁には困ったもんや、フォンだのトマトだの勘弁してほしいわ」っていう家庭もあったのかもしれません。
 当時どんな食べ方が紹介されていたんだろうと、戦前のトマト栽培書を見ていて驚いたのが、トマトの中身をくりぬいて、そこに卵や野菜なんぞで作った生地を詰める料理がでてくること。これって今でもときたま日本料理店で見かけまして、スタッフド・トマトを真似して戦後に生まれたのかしら、とばかり思っていたのですが、歴史が古くてびっくりです。また水加減した米にトマトの裏ごしを加えて炊く「トマト飯」なんてのもありました。リゾットもどきみたいですが、当時の人たちは炊込みご飯の一種としてとらえていたのでしょうか。
当時どんな食べ方が紹介されていたんだろうと、戦前のトマト栽培書を見ていて驚いたのが、トマトの中身をくりぬいて、そこに卵や野菜なんぞで作った生地を詰める料理がでてくること。これって今でもときたま日本料理店で見かけまして、スタッフド・トマトを真似して戦後に生まれたのかしら、とばかり思っていたのですが、歴史が古くてびっくりです。また水加減した米にトマトの裏ごしを加えて炊く「トマト飯」なんてのもありました。リゾットもどきみたいですが、当時の人たちは炊込みご飯の一種としてとらえていたのでしょうか。
こうした今で通用しそうなハイカラ日本料理がある一方で、昭和になっても相変わらず、トマトの臭いが気になる人はゆでろとか(湯むきが目的じゃなくてトマトの風味を抜くのです)、塩ではなくて、砂糖だのジャムだの酢だのをかけろなんていう乱暴な食べ方が紹介されておりました。そもそもポンデローザが人気だったのもトマト臭が薄かったからでして、でかいぶん大味だったようなのですが、それが食べやすくて受け入れられた模様です。
前に日本ではフルーツみたいな味のトマトが喜ばれると書きましたが、隔世の感があります。トマト自体の味もそうですが、われわれの味覚もずいぶん変わったってことでしょう。“温室育ちのトマト”(実際には施設栽培だからといって促成とは限らないのですが)を嫌う人は、「畑でその場でもぎって食べたトマトは、トマトらしい香りがしておいしかった」なんていう昔話をよくされますが、そんな経験と感覚をもつ世代っていうのも、意外と期間限定なのかもしれませんね。
投稿者 webmaster : 13:45
2013年11月25日
料理本のソムリエ [vol.62]
【 vol.62】
オムライスと制服のメイドさんは
西洋をまとった日本なのだ
朝ドラでは、チキンライスをオムレツで包んでケチャップをかけたオムライスは、明治44年にめ以子のお父さんが発明したことになってましたね。今回これに異議申し立てを行なうと皆さん期待されていたかもしれませんが、いい大人ですからね、ドラマと現実が違うことくらい、知っていますよお。実在の人物、料理とは一切関係ありません。
実際には銀座の「煉瓦亭」で明治30年代に誕生したとする説と、大阪の「北極星」の前身である「パンヤの食堂」で北橋茂男氏が大正14(1925)年に発明したとする説があるそうですが、何をもってオムライスの完成と言っていいのかがよくわからないので、どっちにも軍配は上げられない、というのが正直なところです。
まず煉瓦亭が生んだ明治時代のオムライスですが、これはご飯と卵を一緒に炒めるような料理だったそうで、今のオムライスとはちょっと違います。ご飯はオムレツの具の扱い。『週刊現代』1997年4月5日号の「グルメ・スペシャル オムライスからカツ丼まで「元祖」の名店」に載っていた煉瓦亭3代目主人の談話によると、元はまかない食だったこの料理が明治33(1900)年にメニューに取り入れられたときは、上にケチャップこそかけていたものの、ご飯は白かったそうです。その後、明治35年にピラフ入りの改良型になったとのことですが、このピラフがトマト味だかどうかは書いてありませんでした。
一方北橋氏の発明譚は、柔らかいオムレツとご飯をセットで必ず注文する胃の悪い常連さんのために、わざわざ二皿別々に注文しなくても一度に食べられるような料理を発明したっていう話なんですが、先の週刊現代には出てきませんでした。『サライ』1999年6月3日号「ハヤシライスとオムライスの謎」にはあったのですが、大正11年に発明して、14年からメニューにのせたとある。かと思えば、『dancyu』1992年10月号(ABC朝日放送時代の宮根誠司がオムライスの作り方を教わっておりました)では、誕生したのは大正13年頃とあります。どうもよくわかりません。北橋氏の著書『幸福は食べ物によって左右される』を見ていても、卵は血液がアルカリ性になるから身体によくないという話はあっても、オムライスにはまったくふれておりませんし。まあネット上では大正11年説も13年説も見当たらないので、14年っていうことにしておきましょう。
 やっぱり赤ーいトマト味のチキンライスやハムライスをオムレツでくるんでこそのオムライス。チキンライスを使ったオムライスの初出文献については、例の小菅桂子氏が『にっぽん洋食物語』で、『家庭料理法大全』だと紹介しています(ちなみに煉瓦亭のオムライスの話もでてきます)。これに対してつい先日出版された『ニッポン定番メニュー事始め』という本の中で、澁川祐子氏は以下のように述べております。
やっぱり赤ーいトマト味のチキンライスやハムライスをオムレツでくるんでこそのオムライス。チキンライスを使ったオムライスの初出文献については、例の小菅桂子氏が『にっぽん洋食物語』で、『家庭料理法大全』だと紹介しています(ちなみに煉瓦亭のオムライスの話もでてきます)。これに対してつい先日出版された『ニッポン定番メニュー事始め』という本の中で、澁川祐子氏は以下のように述べております。
<現在のようなオムライスが料理書に初登場するのは、一般に1928(昭和3年)発行の『家庭料理大全』だと言われている。では、どうせなら大正から昭和初期にかけての料理本を実際に当たってみよう。
手当たり次第、西洋料理を紹介する家庭料理本の目次をめくる。そこで発見できたのが、1926(大正15)年発行の『手軽においしく誰にも出来る支那料理と西洋料理』。通説より2年ほど早い。「オムライス(卵と肉の飯)」とその名も正しく紹介されていた。材料は、鶏卵、牛肉、グリーンピース、タマネギ、トマトソース、塩、胡椒、牛脂であるヘット、ごはん。牛肉なのでチキンライスではないが、トマトソースを使っているところがポイントだ。作り方は、あらかじめ卵以外の材料を炒め、焼飯を作る。別のフライパンで、卵を薄く大きく焼く。
<焼けたならば拵らへ置きたる炒飯(いりめし)を一人前位宛(ずつ)入れ、卵の周囲を箸にて折込み、フライパンに皿を當(あて)がひ、ポンと返しますと、丁度卵で包んだ様に皿に盛れます>
まさに現在、料理本に載っている作り方と同じだ。最後には<スプーンをつけて供します>とあり、食べ方の指導が必要なくらい目新しい食べものだったことがよく表れている。>
澁川氏のこの本、小菅桂子氏や岡田哲氏の洋食起源本と比べればかなりまとも。料理を専門としているライターさんではないにもかかわらず、頑張って調べているなあ、という印象です。ただ残念なことにどれもこれもが、テーセツだのツーセツだのを出発点に調べ始めて、それがどうやらまちがってるらしいってことがわかったところでめでたしめでたし、おしまい。惜しいねえ。そっから先が面白いのにもったいない、という印象です。そもそも、まちがってないほうが珍しいんだってば(笑)。
このオムライスの一件も、なぜか『家庭料理大全』というタイトルで覚えちゃったせいか、昭和3年刊の『家庭料理法大全』自体はご覧にならなかったようです。こちらの本の著者も『手軽においしく誰にも出来る支那料理と西洋料理』とおんなじ小林定美なんですよ。
<フライパンをよく拭って、ヘットを一面に敷き、強火にかけて、そこへ攪き混ぜた卵を入れ、薄くフライパン一面に焼きます、一寸火から外して、炒り飯を丁度包める丈け卵の上に載せ、四方から卵と攪き寄せるやうに致しまして、(この場合決して、飯を包み切らなくともよろしい、只卵はほんの周囲の格好を作る為に攪き寄せるのですから)再び火にかけて一寸焼き、皿をフライパンにかぶせて、反対にフライパンを起します、すつかり卵で包まつたご飯が上手く皿に受かります>
 『家庭料理法大全』ではグリーンピースを使うのをやめて、より詳しく、誰でも作れるように配慮していますね。小林定美は自分のレシピを再構成して似たような本をいろんな出版社から出しております。うーん、商売上手の出版社泣かせ。たとえば同じ昭和3年に『一年中朝昼晩のお惣菜と支那、西洋料理の拵へ方』という本も出しているのですが、こっちのオムライスは『手軽においしく誰にも出来る…』とおんなじレシピです。
『家庭料理法大全』ではグリーンピースを使うのをやめて、より詳しく、誰でも作れるように配慮していますね。小林定美は自分のレシピを再構成して似たような本をいろんな出版社から出しております。うーん、商売上手の出版社泣かせ。たとえば同じ昭和3年に『一年中朝昼晩のお惣菜と支那、西洋料理の拵へ方』という本も出しているのですが、こっちのオムライスは『手軽においしく誰にも出来る…』とおんなじレシピです。
それにしても1925年に大阪で北橋氏が発明した翌年には、もう東京で活字化されているとは。そんなに短期間でパクられるほど北橋式オムライスは世に広まっていたのでしょうか。当時の人は小林がオムライスの発明者と思わなかったのか、ちょっと心配になっちゃいました。小林は大日本家庭料理協会を主宰しておりまして、著作は多いし、巻末には質問券をくっつけておりまして、発信力があるしなあ。
ちなみに小林定美は和洋中なんでもござれで、鶏のマレンゴ風のような素敵なフランス料理ではなく、現在あるような折衷家庭料理の普及を推し進めた一人。新聞、雑誌と活躍しますが、昭和5年に忽然と姿を消し……おっと、この話はラーメンの回のときにでも。
ただし小林式レシピにはトマトソースはでてきても、ケチャップを使うとはありませんでした。北橋氏がオムライスの発明者というのは、画竜点睛、ケチャップを使ったチキンライスと組み合せたことを指すのかもしれませんね。
さて、同じ大正14年。『改造』4月号には童謡作家のサトウハチローがこんな文章を書いています。
<こゝは西洋料理店です。豚もあります。ほんとうの牛肉もあります。夏にはおいしい生ビールも呑ませてくれます。さて、ひよつとこの話しで食べに行きたくなる読者諸君の為に伝四郎の店をくわしくいふなら、浅草広小路の露天飲食の田原町の方から数へて十何軒目の母子(おやこ)軒と染めてある暖簾がそれです。(…略…)伝四郎の暖簾の中に帰つて来ると貞チンは酒をやめて飯を食つてゐます。伝四郎得意のオムライス――卵焼の中に飯の這入ったもの、その名を笑ふ勿れ>
生ビールも出すちょっと変わった屋台の店主の名は、サトウハチロー曰く「御前試合の遺恨から闇討を食わして逐電した敵役」みたいな橋口伝四郎。どうせなら「父子軒」のほうが侍っぽいのに、なぜ母子? 伝四郎のお母さんが手伝ってたんですかねえ。橋口氏が作っていたオムライスは卵焼きにご飯が混ざっているタイプなのかくるんであるタイプなのか、ご飯は白いのかチキンライスなのか、この文章からはわかりませんが、銀座だけでなく浅草の屋台でも「オムライス」という料理が売られていたのは確かなようです。
 ちなみに伝四郎の子でも母でもないサトウハチローですが、この記事を執筆する3年前の19歳のときに、母子軒で何度もツケで食事をしたあげく、アルバイトをしておりました。生ビールのポンプを押したり、皿を洗ったり、キャベツの上に紅生姜をパラパラまいたりしているうちに、カツと“玉三肉二”くらいは揚げられるようになったと『ぼくは浅草の不良少年 実録サトウハチロー伝』にあります。“玉三肉二”って何だろうと思って原典を探したところ、タマネギと肉を交互に(タマネギが3なのは外側にくるからです)刺したものと説明されていました。肉フライってやつですね。
ちなみに伝四郎の子でも母でもないサトウハチローですが、この記事を執筆する3年前の19歳のときに、母子軒で何度もツケで食事をしたあげく、アルバイトをしておりました。生ビールのポンプを押したり、皿を洗ったり、キャベツの上に紅生姜をパラパラまいたりしているうちに、カツと“玉三肉二”くらいは揚げられるようになったと『ぼくは浅草の不良少年 実録サトウハチロー伝』にあります。“玉三肉二”って何だろうと思って原典を探したところ、タマネギと肉を交互に(タマネギが3なのは外側にくるからです)刺したものと説明されていました。肉フライってやつですね。
このアルバイトの件は、昭和11年に朝日新聞東京版の連載をまとめた『僕の東京地図』にも出てきます。この本は、全体の3分の2ほどですが復刻もされておりまして、原本ではあっちこっちへ飛び回っていた文章を、浅草なら浅草、上野なら上野と地域別にまとめて編集し直しているので、当時をしのんで脳内お散歩するのにちょっと便利な造り。復刻の企画段階ではグルメ探訪を意図していたそうで、そっちの話題も豊富です。それも菓子や屋台など庶民的な店がたくさん出てまいります。
さっきの『ニッポン定番メニュー事始め』では、戦後の闇市でソース焼きそばが誕生したとかいうテーセツに異議を唱えまして、昭和10年代にお好み焼屋の店内で生まれたという仮説を立てておりますが、証拠にまでは迫りきれていませんでした。残念、いい線ついてるのに。この本を読めばちゃんと出てきます。
<ヤキソバ同じく五銭なるものがうまい。ソバを鉄板で、いため焼きにして、キャベツのみじん切りと、ジャガ薯(いも)のサイノメが混じっているのだ。ソースの香りにむせびながら食うとよろしい>
このヤキソバの店も屋台でして、向島のお風呂屋さんの前に陣取って、風呂上りのお客さん相手にご商売しておりました。お好み焼も出しますが、ポテトフライにロールキャベツ、カツレツも作っていたとのこと。一方浅草公園の章には、ヤキソバではありませんが、モチ天、キャベツボール、パンカツなんていう、サトウハチローもちょっと判断に苦しむものを売っていたお好み焼の屋台「御笑楽」が登場します。お好み焼は戦後生まれなんていうツーセツを信じている人たちの想像を絶していますねえ。
中国料理の炒麺をウスターソースで作っちゃったのがソース焼きそばなら、洋食の定番のオムレツとなんちゃって洋食だったチキンライスをえいやっと一皿でドッキングさせたのがオムライス。なんだかカツカレーみたいですね。そういえばカツカレーも浅草の屋台店が起源と言われております(vol30 参照)。『僕の東京地図』には、銀座の松坂屋の横の屋台「青葉亭」では、カツ丼の兄貴分みたいな「オムカツライス」を出していたとありました。現在見るようなオムライスは屋台文化の中から生まれた可能性は高いと思います。
例の北橋氏も大正11年に23歳で起業した時は、大阪の西区幸町で奥さんにパン屋をやらせて、自分は一銭洋食(これまたお好み焼のルーツですね)の屋台を引いていました。屋台がはかばかしくいかなかったので、のちにテーブル3つ椅子7つを買って、間口二間のパン屋の半分を仕切って安洋食屋を始めたのです。それでパンヤの食堂っていうわけ。一皿の料金が均一の料金体系だったので、二皿に分けて出すよりも一つにまとめたほうが常連さんへのサービスになったんですね。
 それならカレーとオムレツは仲良くくっついたりしなかったのかしらと思ったら、これまた1925年刊、秋穂敬子著『美味しく廉く手軽に出来る日本支那西洋家庭料理』に、オムレツト・インデアンというのがありました。カレーソースにご飯を混ぜて、広げたオムレツの上に盛って、柏餅のようにくるむとあります。柏餅っていうのが言いえて妙。そういえばコンビニでは、チキンライスをオムレツでくるんだ丸い「オムすび」が売ってますよね。オムライスの和風志向もここまで来たかと驚くやら、感心するやら。
それならカレーとオムレツは仲良くくっついたりしなかったのかしらと思ったら、これまた1925年刊、秋穂敬子著『美味しく廉く手軽に出来る日本支那西洋家庭料理』に、オムレツト・インデアンというのがありました。カレーソースにご飯を混ぜて、広げたオムレツの上に盛って、柏餅のようにくるむとあります。柏餅っていうのが言いえて妙。そういえばコンビニでは、チキンライスをオムレツでくるんだ丸い「オムすび」が売ってますよね。オムライスの和風志向もここまで来たかと驚くやら、感心するやら。
ところで日本オリジナルといえば、カゴメの社史を見ていて驚いたのは、昭和33(1958)年発売のアルミチューブ入りトマトケチャップ。細長い絵具みたいな形です。ここからケチャップがにゅるりと出てくることを想像するとちょっと楽しい。今見られるようなソフトビニール製のボトルは昭和41(1966)年登場とありまして、意外に新しいですね。このタイプの容器はマヨネーズのほうが先行していましたが、ケチャップでは酸素が透過すると変色するので開発に苦労したようです。海外ではマヨネーズはビン入りですし、ハインツのケチャップはひっくり返して立てて置ける固いプラスチックボトル入り。ホットドック店用はともかくとして、家庭用の搾り出せるボトルっていうのは日本独特の模様です。
秋葉原のメイド服(これまたイギリスのメイド文化にあこがれてアレンジしたものですね)姿の娘さんが、オムライスにケチャップでちゅるちゅる字を書くっていうのは、まさに日本文化の極みなのですね。メイドカフェのオムライスは外国からの観光客の皆さんに喜ばれるっていうのもなんとなくわかりますね。
投稿者 webmaster : 18:00
2013年11月08日
料理本のソムリエ [vol.61]
【 vol.61】
「素」が先か、トマト味が先か
朝ドラの「ごちそうさん」、ご覧になりました? 「あまちゃん」だってなかなかリアルタイムで見られなかった私なものでとびとびでしか見ていないのですが、完全に一本取られた心地です。地雷を避けるどころか、地雷原の中を戦車でスラローム。こりゃあどうも確信犯みたいですね。前に大河ドラマがリアルさを追求しすぎてストーリーの足をひっぱっているっていう批判がありましたが、それに学んでの演出なのかも。明治や大正の西洋料理や食事情をリアルに再現しても、大喜びするのはごく一部のマニアだけで、お茶の間受けしそうにないものねえ。でも食がテーマって堂々謳っておきながら、こんなにも時代考証がいい加減でいいのかしら……?
西洋料理店の開明軒の描かれ方や塩むすびに使った塩の種類といった重箱談義はこの際棚上げするとしても、明治生まれの子供らにフランス料理(それも牛肉の赤ワイン煮やフォワグラのフラン)をふるまう超展開には度肝を抜かれました。そんでもって先週はいよいよフォンが登場。そりゃまギッド・キュリネールだってフォンは載ってますけどね。卯野大五シェフは、平成のホテルから明治時代にタイムスリップしてきたっていうエピソードの伏線かしら?
まあ、話もまだ途中なのに小舅っぽいことは言いますまい。ためしてガッテンのような情報番組ならいざしらず、目を転じればチャングムなんていうアストロ球団クラスの事例(vol2参照)もありますし。自由奔放荒唐無稽なら、そうとわかるように徹しきってエンターテイメントとして楽しませてくださいね。当ブログ、洋食と大阪料理の話はしばらく封印しまして、「ごちそうさん」を生温かく見守っていきたいと思います。
ただ、ここんとこずっとトマト縛りで書き続けているので、このシリーズが終るまではご勘弁を。前回ケチャップの由来についてちょろっと触れましたが、それでは日本人はいつからケチャップに親しむようになったのかっていうのが気になって、もうずいぶん前にいろいろ調べちゃったもので。
ケチャップの日本への導入はウスターソースに遅れるものの、明治後半には国産化されています。『カゴメ一〇〇年史 本編』によりますと、カゴメでは明治41(1908)年には試作を始めたそうで、大正末の生産量はトマトソースの3分の1ほどだったのが、昭和5(1930)年に逆転し、14(1939)年には6倍近くにもなったそうです。業務用中心だったトマトソースに対し、保存のきくケチャップは家庭にも広がっていったため売れ行きものぼり調子だったとか。そういえば戦前は、桃屋さんもケチャップを販売してました。
そんなケチャップ、戦前の庶民にとってどんな存在だったかがわかる森田たまの一文をご紹介。『絹の随筆』(1961)の中の「トマトカチップ」です。慶応大の学生だった森田七郎と結婚したての大正半ばのお話(おお、どっかの家とちょっと似てる)。同じ「絹の随筆」という副題がついている『森田たま随筆全集第3巻』には収められておりませんのでご注意を。
<栗と松茸をふんだんに入れた、チキンアラマレンゴーをつくつてみようと思つたのは、新学期のはじまる九月であつた。久しぶりで顔をあはせる友人たちに、すこし贅沢なごちそうをしたいと思つたのであつたが、あいにくなことに、なまのトマトを切つて入れる、とあるそのトマトが、もう八百屋にはなかつた。
どうしようかしら、これはやつぱりトマトで煮ないと味が出ないんでせうねと思案してゐる私に、常連の一人が智慧をさづけてくれた。
「三越の食品部へ行くと、トマトカチップといふ壜詰を売つているけど、あれどうかしら。トマトの汁だからいいんぢやないかと思ふけど。…」
鶏と玉ねぎと栗と松茸を、トマトカチップ入りのスープで煮て、おろしぎはにちよつとセリ酒を落したこの料理は、ハイカラな慶応ボーイに大好評であつた。さうして、トマトカチップは、煮込物に入れるだけでなく、そのままなめてもおいしいし、スコッチエッグなどにかけると、一そう風味をますといふことも同時に発見した。トマトカチップはわが家にとつて、お醤油についで重宝な調味料となつた。
トマトカチップがトマトケチャップであると知つたのはいつのころか分らない…(略)…人生の半ばを病床に暮し、三十年来台所に起つたこともない。チキンアラマレンゴーはいまだにわが家の秋の料理の一つとなつてゐて、必ず九月の食卓にのぼる。みんながおいしいといふと夫は、しかし昔ママのつくつた方がもつとおいしかつたといふ。
カチップ時代のそれには、青春といふ調味料がもう一つ入つてゐたせゐであらう。>
「え? 昔おいしかったのはマツタケが入ってたからじゃあないの?」と思わずつっこんでしまいそうになったのですが、1959年に発表された文章なので、森田家では戦後もマッシュルームではなくてマツタケ入りだったのかもしれません。マツタケは昭和も30年代までは、大正時代と同じくらいの量が採れていましたから。
うーん、こうなると実際に試してみないわけにはいきません。ドラマの時代考証をくさすのならば、みずから範を示さねば。ええい、ここはひとつ大枚をはたいてマツタケを買ってやろうじゃありませんか!
ところがもう11月なので、輸入のマツタケしか出回っていませんでした。いやあ、これはしたり。丹波のマツタケをふんだんに使う気まんまんだったのに残念残念。それにしてもアメリカだのトルコだのから来たマツタケを使った場合、ブログに「松茸」って書いて大丈夫なのでしょうか? 栽培のシメジは今後はちゃんとブナシメジやヒラタケって書かないと怒られるのかなあ。
 随筆には作り方が書いてあるわけではなく、量も“ふんだんに”としかわからないので、柴田書店刊『フランスふだんのおそうざい』を参考にしてみました。といっても使う材料が全然違うので(ていうか、マツタケはともかく鶏と栗の組合せって赤ワイン煮込みならわかるけど、マレンゴ風じゃないよねえ?)、雰囲気だけ。「青春」という調味料はスーパーで調達できなかったので、森田家戦後バージョンです。どうです、本当にマツタケ入りでしょ? すみません、勇気がなくて生トマトでも作っちゃいました。マツタケがもったいなくて。
随筆には作り方が書いてあるわけではなく、量も“ふんだんに”としかわからないので、柴田書店刊『フランスふだんのおそうざい』を参考にしてみました。といっても使う材料が全然違うので(ていうか、マツタケはともかく鶏と栗の組合せって赤ワイン煮込みならわかるけど、マレンゴ風じゃないよねえ?)、雰囲気だけ。「青春」という調味料はスーパーで調達できなかったので、森田家戦後バージョンです。どうです、本当にマツタケ入りでしょ? すみません、勇気がなくて生トマトでも作っちゃいました。マツタケがもったいなくて。

ところが実際に食べてみるとケチャップタイプも結構いけました。この料理、栗とタマネギでかなーり甘いので、甘酸っぱい味と合うんですね。マツタケはふんだんでも、ケチャップはほんのちょっと使うのがこつ。ちなみにフォンやスープは使いませんでした。マツタケだって別に使わずとも、シメジでもエリンギでもよさそう(泣)。
それにしてもこの時代に鶏のマレンゴ風なんてずいぶんハイカラですが、おしゃれな海の向こうの料理を作ってみたい食べてみたいという願望は、昔も今も変わらないようです。その甲斐あって、西洋かぶれのナウい慶応ボーイにばかうけ。大阪のどっかの家庭とは大違い。
当時のケチャップはわざわざ三越の食品部に行って買う、ちょっと贅沢な調味料だったようですが、醤油のようにかけてもなめてもおいしいというのがミソで、それが家庭に広まった秘密なのでしょう。昭和になるとかなり一般的な存在になったのは、前回のナポリタンの一件からも想像できますね。
ちなみにカゴメは戦時中、海軍向けにカレーのルーみたいなキューブ状に固めた固形ケチャップも製造しています。流血を連想させるから液状なのを嫌った……んじゃなくて、持ち運びの便を考えてのことですね。さすが洋食党の海軍、そこまでしてケチャップを使いたかった……というわけではなくて、ビタミンが不足がちになる船上での栄養面を考えてのことでしょう。実際スライスしてご飯にのっけて賞味されていたようですし。
これではただのケチャップのせご飯ですが、炒めればケチャップライスになりますね。これこそナポリタン同様、日本人の発明した西洋料理です! 鶏を使ったのがチキンライス、ハムを使えばハムライス。君はどっち派? なんてきいても若い人には、「はあああ? トマトリゾットの具ですかあ?」とか言われちゃうかも…。
『にっぽん洋食物語』で知られる小菅桂子氏は、2005年7月に昭和女子大近代文化研究所から出した『チキンライスの日本史』というブックレットで、大正末に鎌倉ハムからトマト風味の具とソースが入った「ハムライスの素」が発売されて以来、ハムライスブームが起こり、その姉妹品として「チキンライスの素」も発売されて、昭和になってチキンライスがハムライスの地位にとって変わったという仮説を立てています。さては先生、ハムライス派だね。
また明治18(1885)年のクララホイットニーの『手軽西洋料理』、同36(1903)年10月の『家庭之友』、同42年の『四季毎日 三食料理法 冬の部』に登場するチキンライスはみなトマトを使わないピラフ風で、大正3(1914)年の『家庭料理講義録』のチキンライスは味つけにキャラメル(もちろんお菓子でなくカラメルですね)を、大正7(1918)年の『海軍五等主厨厨業教科書』ではドミグラスソースを使っており、ハムライスブーム以前のチキンライスは混沌としていてまだトマト味の時代ではなかったとしています。さらに勢い余って「大正期でもまだ、料理本を見て西洋料理を作ろう、などという人はほとんどいなかった。料理本は西洋の文化の香りを読んで楽しむものだったのである」とも。おいおい、そんなこと言って大丈夫? 森田さん家は例外中の例外なの?
ここんとこちょくちょく取り上げている『トマトが野菜になった日』には、昭和以前のトマト味のチキンライスがちゃんと紹介されています。トマトの本だからね。明治39(1906)年2月号の『月刊食道楽』にはトマト味のシチューを白いご飯にかけるタイプ。大正7(1918)年の『婦女典範実用家庭顧問』には、鶏肉の具を炒めた鍋にトマトの裏ごしとご飯を入れてパラパラになるまで火を通して作るタイプ。小菅先生は、『チキンライスの日本史』に続いて翌月には同じブックレットシリーズの2号として『トマトの日本史』も出しておりまして、この中ではちゃっかり『トマトが野菜になった日』を引用していますが、前の号を出したあとで慌てて手に入れたのか、読んではいたけど気づかなかったのか。
ちょっと調べてみたら、赤堀吉松らの『家庭応用洋食五百種』と家田啓造の『西洋料理法 活用』は、どちらも明治40年(1907)の本なのですが、これらに出てくるチキンライスは、鶏肉の具とトマトの裏ごしとご飯で作るタイプでした。赤くてトマト味のチキンライスって明治の末からあるじゃないのさ。そもそも手軽に作れる「素」や「種」が売れるようになるには、ライスカレーの前例が示すように、その料理がある程度認知されてなきゃ始まんないと思うんですけどねえ(vol34)。チンジャオロウスって聞いて何のことだか見当もつかない人が、青椒肉絲の素を買ってみようって気にはなかなかならないよねえ。
「チキンライス」を名乗るには鶏とご飯さえ使ってあればよいわけですから、黎明期にはかなりいろいろなタイプがあったのは事実です。ただ次第にトマト味がスタンダードとなってきて、さらに素だのケチャップだのを使った簡単バージョンが普及するようになった……というのが自然な解釈ではないでしょうか。当時の人もちゃんと、チキンライスはカレーライスとも違う日本生まれの洋風ご飯料理(そもそもご飯を使った西洋料理ってのを探すのに苦労していたのだから)である、と認識していました。日本人好みの味にするべく、試行錯誤あっての完成形なのでしょう。
それから小菅先生がチキンライスの資料として引用している『家庭料理講義録』なんですけどね、これは通信教育のテキストで、大正3年どころか明治末から、それも毎月出されていました。そりゃあ実際に作るのは一苦労だろうけど、誰もがみんなひたすら見て楽しむだけのために延々購入したわけでもありますまい。また赤堀吉松は赤堀割烹教場(今の赤堀料理学園の前身)3代目校長だし、家田啓造は岐阜県師範学校女子部と岐阜県立高等女学校(今の岐阜大と岐阜高校の前身)の先生です。レシピを眺めるだけで作らなかったとか言うと、卒業生に怒られちゃいますよ。

さて、そろそろお気づきでしょうが、ここまでが壮大な前ふり。
もちろんこの後はオムライスの話ですよ(続く)。
投稿者 webmaster : 18:27
2013年09月26日
料理本のソムリエ [vol.60]
【 vol.60】
「ナポリたん」ってお子ちゃまキャラだと思ってたのに、
いったいどんな過去が…
朝ドラのあまちゃん、いよいよクライマックスですねえ。料理人の皆さんはご覧になっているのかしらん。本放送中は仕込みだの仕入れだのをしていそうだし、再放送はランチの真っ最中だからねえ…。高校野球のシーズンは厨房でラジオを聞いてる料理人さんを見たことがあるけれど、さすがにテレビはねえ。
私にいたっては午前8時なんて深い時間帯の放送にはあんまりご縁がなくて、夜中の一挙ダイジェスト放送でようやく全体像をつかむことができました。なるほど、よくできたドラマだわー。伏線がよく練られていて、きっちり回収されるのには感動です。さらに驚いたのは、てっきり震災は最後の最後のほうでちょこっと触れて、涙なみだのハンカチとオブラートに包んでおしまい、となるとばかり思っていたのがあにはからんや。まさかの正面突破です。批判もあるかもしれませんが、そのプロ意識に拍手を送りたい。
そんなにわかファンはいまさら会社の近くが東京編の舞台になっていることに気づきまして、さっそくアメ横女学園東京EDOシアターの幻影を求めて聖地巡礼してみましたよ。ていうか、昼めし食べに行くあたりなので。シアターのモデルのアメ横センタービルには食材の仕入れでご厄介になっているし。それで初めてこの商店街が、あまちゃんで街おこしをしていることにも気づきました。まあ周りじゅう看板だらけでほとんど目立たないので、本気度は不明です。

「無頼鮨」はどこかモデルがあるんだろうか? 小上がりとはいえ庭もあって、それなりのお値段そうな店だけど、アメ横周辺にはわれわれでも手が届く庶民的な寿司屋さんが多くて、そっちのほうしか知らないや。画面に写っていた電信柱の住所からいうと御徒町駅のすぐ近くなんだけど、あれはセットだしなあ……なんて狭い裏路地できょろきょろしていたら、背後から声をかけられました。ここでドラマだと種市先輩だったりするのかもしれませんが、フード・ラボのO澤所長。思いっきり不審人物。かなり恥ずかしい。
 さて、この流れで寿司の本の話へもっていきますと、たいへん自然で柴田書店のブログらしいのですが、私が釣られるのはいつも斜め上方の隅っこのところでして。ドラマで気になったのは、春子ママが万引き未遂のユイを「リアス」に引っ張り込んで、ナポリタンを出して言う「ほら、あばずれの食いもんだよ」てセリフ。じぇじぇじぇ、ナポリタンってあばずれ御用達なの? 浅倉南ちゃんが作ってくれるものって、この間のdancyuに載ってたじゃない! アメ横近くのロッテリアはナポリぱんだバーガーが限定商品なのに、こんなにかわいいのにそんな……。「昔のドラマや映画の不良がみんなナポリタン食べる」って、言ってたけど学校さぼって喫茶店に昼間っぱらからたむろしている不良ってことなのかしら……。でも、ナポリタン好きの不良って、たいしたことなさそう(笑)。
さて、この流れで寿司の本の話へもっていきますと、たいへん自然で柴田書店のブログらしいのですが、私が釣られるのはいつも斜め上方の隅っこのところでして。ドラマで気になったのは、春子ママが万引き未遂のユイを「リアス」に引っ張り込んで、ナポリタンを出して言う「ほら、あばずれの食いもんだよ」てセリフ。じぇじぇじぇ、ナポリタンってあばずれ御用達なの? 浅倉南ちゃんが作ってくれるものって、この間のdancyuに載ってたじゃない! アメ横近くのロッテリアはナポリぱんだバーガーが限定商品なのに、こんなにかわいいのにそんな……。「昔のドラマや映画の不良がみんなナポリタン食べる」って、言ってたけど学校さぼって喫茶店に昼間っぱらからたむろしている不良ってことなのかしら……。でも、ナポリタン好きの不良って、たいしたことなさそう(笑)。
 ちなみに吉川敏明シェフの『ホントは知らないイタリア料理の常識、非常識』によりますと、スパゲティ・アッラ・プッタネスカなら娼婦風だし、アッラ・ケッカならおかま風なんですが、アッラ・ナポレターノは不良風てのはありません。ナポリっ子に怒られちゃうよね。
ちなみに吉川敏明シェフの『ホントは知らないイタリア料理の常識、非常識』によりますと、スパゲティ・アッラ・プッタネスカなら娼婦風だし、アッラ・ケッカならおかま風なんですが、アッラ・ナポレターノは不良風てのはありません。ナポリっ子に怒られちゃうよね。
念のためにパスタばかりのレシピを1300以上集めた『新パスタ宝典』をひもときますと、ナポレタニーナ(napoletanina)っていうのがありました。これは肉や生ハムをトマトや卵と一緒に混ぜて生地を作り、ゆでたマカロニと一緒に器に入れて湯煎にかけるもの。スパゲティとは関係ないねえ……。
さらに探すとスパゲティでなくてパスタだけど、「ナポリ風ラグーのパスタ、ヴェラーチェ」ってのが載ってまして、こっちのほうがナポリタンぽい。みじん切りのタマネギ、ニンジン、セロリを豚の脂で溶けるくらいまで炒めて、仔牛の腰肉を入れて、トマトのピュレとオリーブ油を加えて作るソース。水またはブロード(ブイヨン)を加えながらできるだけ時間をかけて煮まして、肉は取り出して別の料理に使います。ちなみにヴェラーチェ(verace)とは「本物の」という意味で、もっとも古い伝統的な作り方だからだそうです。真のナポリパスタ協会の承認つきなのかしら。
ほかに「パスタのナポリ風、簡単なミートソース和え」っていうのもありました。こちらは煮込んだラグーじゃないので、調理法は「センプリチェ(semplice)」。野菜を炒めたら粗びきの牛肉を加えて軽く色づけてまして、マジョラム、ナツメグ、塩コショウを加えて、ワインを注ぎ、裏ごししたトマトの果肉(湯むきして薄切りにしてもよい)を加え、弱火にしてゆるま湯またはブロードで煮る……ってぜんぜん簡単じゃないし。
こうした真摯な姿勢のソースに比べたらケチャップで麺に味をつけちゃうスパゲティナポリタンっていうのは、インスタントの極みだよねえ。恐らくトマト味のラグーで和えるナポリ風のパスタを作ろうとしたものの、保存がきいて手に入りやすいケチャップに頼った結果、生まれたのでしょう。じゃあそれはいったい、いつのこと?
ナポリタン愛がこうじて、各地の特徴的なスパゲティナポリタンを訪ねたり、アメリカのハインツ社やケチャップの消費量の多いスウェーデンにまで足を伸ばしたルポ『ナポリタン!』は、『とことんおでん紀行』や『カレーライスと日本人』といった先人のスタイルにならった労作なのですが、歴史考証の中途半端さは否めません。ケチャップで作るナポリタンは横浜のニューグランドホテルの入江茂忠シェフがGHQの将校のために作ったのが始まりっていう説をとっていますが、これは100%ありえないでしょう。だってケチャップ味のスパゲティナポリタンって戦前からありましたもん。
『婦人之友』の昭和12年12月号ではうどん料理の記事で、うどんを代用して作る「スパケテナポリタン」を紹介しています。麺がうどんだなんて安い学食みたいだけど、日中戦争が始まってなんでもかんでも代用で節約が推奨された時期だからね。フライパンで豚か仔牛の肉100gと脂50g、ニンニク3片を炒めて取り出し(これも肉は別の料理に使います)、さいのめに切ったトマト小2個を入れて炒め、トマトケチャップを加え(トマトがないときには少し多めに)、月桂樹の葉2,3枚を入れて、シェリー酒5、6滴を落とします。湯(煮出し汁があればなおよし)でのばして、塩コショウで味をつけてできあがり。これをゆでたうどんにかけて、粉チーズをふります。
所詮うどんなのに材料にシェリー酒なんて使ってお洒落さんなのは、料理研究家の趣味なのか、標準レシピなのかよくわかりません。解説には「これはイタリーでよくする料理で、これさへあれば他のものはいらないといふ人のある程そんなに美味しいものです」とありまして、れっきとしたイタリア料理とうたっております。スパ「ケ」テなのにね。
これってうどんで作る特殊な事例じゃないの?と疑う向きには次の資料を。童謡作家、有賀連の作品集『風と林檎』(1932)にある「マカロニ」という子供向けの詩です。
マカロニナノダヨ、コノ皿ハ フォークニマイテル、アノヒトモ
― プルン、ルン、ルン、マカロニダ
マカロニナノダヨ、ミテゴラン トマトケチャップガカケテアル
― プルン、ルン、ルン、マカロニダ
マカロニナノダヨ、コノ皿ハ タベルヨ、ボクハ、スキナンダ
― プルン、ルン、ルン、マカロニダ
マカロニナノダヨ、アノナベハ マカロニナノダヨ、ヤハラカイ
― プルン、ルン、ルン、マカロニダ
ずっとマカロニマカロニ言い続けてますが、フォークに巻いているのでロングパスタでしょう。戦前の資料を見ていると、マカロニを正しく「管饂飩」っていう身も蓋もない説明をしているものもありますが、今の「パスタ」のように総称として使っていたりもします。一コマ漫画でマカロニって言ってるのに、明らかにロングパスタが描かれているのもありました。ちなみに戦前の加工食品に関するお堅い資料だと、スパゲティという単語より英語からきた「ヴァミセリ」のほうがよく使われていたりします。
さてこれは、童謡として書かれた詩に出てくるっていうのがミソでして、子供がマカロニという食べものがどんなものか知っているのが大前提となっていることを示しています。いまヴァミセリの歌ってのを作っても、大人にだってぽかんとされちゃうでしょ? 昭和7年の段階でパスタにトマトケチャップをかけるのがさほど珍しくなかったという傍証です。ナポリタンはデパートの食堂の洋食の付け合せとして生まれたという説もありますが、ニューグランド誕生説よりはずっと傾聴に値します。
そろそろみなさん戦後の発明っていうのは変だということに気づかれたようで、入江氏よりも前にニューグランド初代料理長のサリー・ワイルが発明した説ってのもありますが、彼はスイス人でれっきとしたフランス料理のシェフなのに、わざわざスパゲティだのケチャップを使う必然性ってのが感じられないんですよねえ。むしろワイルや入江シェフが、日本人の好きなナポリタンを、ホテルで提供できる域まで高めたっていうのなら合点がいきますが…。
ナポリタンってケチャップで甘酢っぱいので、不良というより子供の好物。柔らかくて食べやすいしね。カレーと並んで子供に人気ですが、それじゃあそもそもミートソースでもグラタンでもいいけど、スパゲティやマカロニがいつどのような形で日本人の舌に受け入れられるようになったかというと、これがどうもよくわからない。やたらうんちくを垂れるカレーと違って、この件に関してはみんな頬かむり。実際、いつの間にか素知らぬ顔で洋食屋のメニューにまぎれ込んだ感じでして、これを調べるのはかなり大変そう。
例の魯山人は、1935年10月の『星岡』で、大正時代にマカロニを売りにした洋食屋があったと証言しています。「その頃「伊太利」とか云ふ洋食屋があつて、イタリー風の「うどん」を自慢にしてゐる料理人があつた。「ゑり治」の横邊りだつたか、三共の横邊りだつたかにあつた。二百種類位マカロニを拵へると云ふのでね。僕は毎日違つたのを作らせて毎日食つたもんだ」(星岡60号)。先生場所がちょっとうろ覚えですが、半襟屋のゑり治があったのは銀座竹川町、喫茶部もあった三共薬品は銀座尾張町でして、今の銀座5丁目から7丁目のあたりでしょう。彼いわく17年か18年前の上京した頃の話ということなので、大正前半のできごと。魯山人に無理やり毎日違うパスタ料理を作らされて、ついスパゲティをケチャップで和えちゃったりしなかったんでしょうかねえ。
ケチャップってアメリカ人が好んで使うので、先の本で吉川シェフはナポリタンはアメリカ生まれで英語から来ているんじゃないかと想像していますが、アメリカでもスパゲティにケチャップを使う習慣はなくて、日本に来たアメリカ人がたまげているのをネット上で見かけます。やはり日本生まれじゃないかと思うのですが、いかがでしょう。
 もっとも私もケチャップ自体はアメリカで生まれたものかと思っておりましたら、『トマトが野菜になった日』によりますと、そもそもこの言葉、魚醤からきているんですって。それが東インド会社経由でイギリスにわたって、19世紀のアメリカでトマトや砂糖が加えられるようになったとのこと。インドネシアでも「ケチャップ・マニス」(あまいケチャップ)や「ケチャップ・サンバル」(トウガラシソースのケチャップ)っていうのがありまして、アメ横センタービルでも買えますが、まさかこちらが正当後継者だったとは。
もっとも私もケチャップ自体はアメリカで生まれたものかと思っておりましたら、『トマトが野菜になった日』によりますと、そもそもこの言葉、魚醤からきているんですって。それが東インド会社経由でイギリスにわたって、19世紀のアメリカでトマトや砂糖が加えられるようになったとのこと。インドネシアでも「ケチャップ・マニス」(あまいケチャップ)や「ケチャップ・サンバル」(トウガラシソースのケチャップ)っていうのがありまして、アメ横センタービルでも買えますが、まさかこちらが正当後継者だったとは。
ああ、それにしてもあまちゃん、最終回を平常心で迎えることができるでしょうか。だってだって、これが終わっちゃったら次の作品は、「食」がテーマなんですってよ、奥様! こわごわちょろっとNHKの公式HPを見たところ、「志村! うしろ、うしろ!!」の気分。ああああ、この時代設定、人物紹介! 地雷があちこちにてんこ盛りですよ(泣)。どうか神様、NHK様、珍説や思い込みを、もっともらしくストーリーにちりばめませんように…。
投稿者 webmaster : 13:30
2013年09月02日
料理本のソムリエ [vol.59]
【 vol.59】
京野菜を育んだのは土か人か
トマトがらみでもうひとネタ。アメリカでは生食用トマトでも、果汁が少なくて固いものが喜ばれるんだそうです。「加熱調理用ならまだしも、なぜまたそんなトマトを?」と思ったら、ハンバーガーに挟むのに果汁たっぷりだとパンズに染みて困るからだそうでして。固いとスライスしやすいしね。日本のトマト農家は甘くてみずみずしい、果物のような味を追い求めていますが、ずいぶん方向性が違います。
お国が変わると料理が変わり、当然求められる野菜の性格も違ってきます。だから各地でいろいろと特徴的な品種の野菜が作られてきたわけでして、郷土の料理と地元の野菜は密接に結びついております。その際たるものが京野菜でして、かぶら蒸しを作るにはやっぱり聖護院蕪、田楽茄子を作るのには賀茂茄子がぴったりですよね。
京野菜は今や全国に通じるブランドですが情報不足気味だった時代が長く、90年代以前は林義雄先生の『京の野菜記』(1975)、『京の野菜―味と育ち』(1988)、高嶋四郎先生の『京野菜』(1982)しかありませんでした。というか、現地をよく知る専門家の京野菜の本は今でもこれくらいかなあ。高嶋先生は改訂増補するつもりでいましたが果たせず、お弟子さんたちが遺稿をまとめて『京の伝統野菜と旬野菜』(2003)として出版しております。
京都府立大農学部の高嶋先生の本は各種京野菜の履歴書というか、いつの時代にどこからもたらされたのかといった学術的な内容。お弟子さんだった林先生の本は京都府の農業試験場所長や指導所長だったキャリアを生かして、生産者の様子も盛り込んだちょっとエッセイ風になっています。ただどちらもモノクロ写真中心なのと、まったく現場を知らない人向けには書かれていないという難点が…。
 以前堀川牛蒡の栽培について調べていたときのこと。高嶋先生の本をひもとくと、歴史的な由来しかない。一方林先生の『京の野菜記』のほうには「…植える苗は前年の九月にまいた苗のうちから、長さ一尺五寸(四五センチ)以上で…六月の中、下旬に植える。植え方は普通の植物の植え方とは違って、東南に向けて一五度の角度に寝かせて浅く植える」ってあったんですが、これって横にして植えなおすってこと? ゴボウを?? たしかに堀川牛蒡ってよく見ると、頭と尻尾のところでクランクみたいにカクカク折れ曲がっていまして、寝っころがっていないとあの形に育たない。半信半疑で、わざわざ農家に電話して確認してしまいました。今ならネットで検索すりゃ写真入りでぞろぞろヒットしますが…。便利になりましたねえ。
以前堀川牛蒡の栽培について調べていたときのこと。高嶋先生の本をひもとくと、歴史的な由来しかない。一方林先生の『京の野菜記』のほうには「…植える苗は前年の九月にまいた苗のうちから、長さ一尺五寸(四五センチ)以上で…六月の中、下旬に植える。植え方は普通の植物の植え方とは違って、東南に向けて一五度の角度に寝かせて浅く植える」ってあったんですが、これって横にして植えなおすってこと? ゴボウを?? たしかに堀川牛蒡ってよく見ると、頭と尻尾のところでクランクみたいにカクカク折れ曲がっていまして、寝っころがっていないとあの形に育たない。半信半疑で、わざわざ農家に電話して確認してしまいました。今ならネットで検索すりゃ写真入りでぞろぞろヒットしますが…。便利になりましたねえ。
このときにふと思ったのですが、京都の野菜ってどうして土の中へ深く伸びるタイプのものが少ないんでしょう。ナスやトウガラシのような空中に実るものはともかくとして、聖護院蕪はもちろん聖護院大根もまん丸で、半分土から顔を出しています。九条葱は白い根深ネギじゃなくて葉ネギだし(まあ白ネギは土寄せするんですけどね)。
アクがないので有名な山城のタケノコだって、厚い盛り土をしてふかふかにした特別な竹やぶで育てるからあんなに柔らかくて白いのです。海老芋は品種自体は唐芋なので普通なら寸胴型になるはずなんですが、土寄せを何度もして、先細りのあの独特な形に育てます。農家はなんだか土と戦っている感じ。それなのに、そこいらのマスコミはおおむね「京野菜がおいしいのは土がいいから」「水がいいから」って解説しています。ホントか?
賀茂川や桂川が氾濫するたびに、山から栄養をたっぷり含んだ水が供給されるため京都の土は肥沃になったっていう説明も見たことがありますが、それってナイル川じゃないの? そもそも、いったい何年前の栄養に頼って野菜を作り続けているの??
京都帝大農学部の大槻正男先生は、宮城県生まれで東京帝大出身。大正時代に京大に赴任して初めて接した京野菜のおいしさに驚きます。ところがある日、隣の家の竹やぶのタケノコが自宅の庭に生えてきまして、さっそくゆでてみたところ、普通にアクがあって固かった。そのため、おいしさの秘密は独自の栽培方法にあり、と気づいたそうです。ネコババしておいて、ねえ。隣の家に形見の皮は届けのたかしら。
大槻先生は、当時の京都では水田を翌年には畑にする転作が行なわれており、栄養分やミネラルの富んだ農業用水が引き込まれた後の土地で作るため、野菜がうまいのだろうと推測されました。これなら氾濫説よりも納得がいきます。
林先生の『京の野菜―味と育ち』でも、この転作の習慣は紹介されておりまして、“田畑輪換”というそうです。また、畑にしても一つの畦に同じ作物を作るではなく、複数種を植える“複作”が行なわれていたともあります。これも転作同様に狭い土地を有効活用する知恵なんですが、組合せによっては日陰を作ったり病気を防いだりと互いを助け合い、収量を伸ばすことができます。最近よく耳にするコンパニオンプランツってやつですね。
 ついでにいうと京都の水質がいいからおいしい野菜が育つっていう説明もおかしな話で、野菜と豆腐を一緒にしちゃいけませんよ。野菜の栽培は基本的に雨水やため池なんかに頼るもんですが、上賀茂や伏見は湧き水が豊富で農業用に使われています。水がいいからじゃなくて水に恵まれているからなんですね。そもそも灘の宮水じゃあるまいし、野菜が喜ぶようなミネラルたっぷりの硬水は飲んでもおいしくないです。
ついでにいうと京都の水質がいいからおいしい野菜が育つっていう説明もおかしな話で、野菜と豆腐を一緒にしちゃいけませんよ。野菜の栽培は基本的に雨水やため池なんかに頼るもんですが、上賀茂や伏見は湧き水が豊富で農業用に使われています。水がいいからじゃなくて水に恵まれているからなんですね。そもそも灘の宮水じゃあるまいし、野菜が喜ぶようなミネラルたっぷりの硬水は飲んでもおいしくないです。
京都は盆地で大阪平野や濃尾平野のように沖積土でもなければ、関東平野のように火山灰土でもない。北山の花崗岩が風化した真砂(まさ)土です。肥持ちがいい(肥料が流失しにくい)一方で、小石まじりで酸性土壌。粘土状に細かくくだけてしまうと水はけが悪くなり、長所ばかりとはいえません。前回触れた『菜園づくりコツの科学』の著者の西村和雄先生はやはり京大の先生で京都在住なんですが、雨の翌日はぬかるみになるような水はけの悪い畑を、牧草の力を借りて改良した、なんて苦労話が載っています。
京都は関東ローム層なんかと違って耕土が深くない土地だったから、それに合った品種や栽培方法で野菜が作られてきたのではないでしょうか。事実、聖護院大根は元をたどると尾張の宮重大根(青首大根のご先祖様。フツーの形です)でして、その中から太くて短いものを選抜していった結果、あの大きなカブのような姿になったそうです。そんな風土と農家の努力が京野菜を京野菜たらしめてきたわけですが、有名になるにしたがって、素人相手の説明として、手っ取り早くてなんとなくわかったような気にさせる「土」だの「水」だのが担ぎ出されてきた気がします。
あるいは農家の人が謙遜して、「いやあ、土がいいからおいしいんですよ」なんて言ったのを鵜呑みにしたのかもしれません。料理人さんが「いやあ、素材がいいからおいしいんですよ」って謙遜するのと一緒ですね。こっちも額面通りに受け取られているようですが、いくら素材がよくったって、腕が悪けりゃぶち壊しですからね。
料理の世界だと、スタッフが同じ材料と分量と手順でまったく同じように作っても料理長が作ったほどおいしくない、っていうことはよくあります。一見同じようでいても火力が違ったり、作業のタイミングが違ったりしていまして、そこがレシピのポイントだったりするわけです。でも、これって言葉にするのが難しかったり、料理長自身もいつの間にか身につけていて自覚していないってことがあります。料理の世界では「仕事は見て盗め」なんていう。前近代的だという批判はもっともなんですが、教えたくても教える言葉もスキルも持ち合わせていないので、勝手に観察して探ってくれ、という意味だったりもするんです。まあ、そこを無理やりにでも引き出すのが、我々の仕事だったりするわけですが。
ところが農業だと料理と違って仕込みから完成までひとシーズンかかりますので、雑誌記者やテレビクルーがちょっと眺めたくらいじゃ作業の特徴がわからない。農家も親から教えてもらった方法なので、よそではどういうふうに作業しているか知らなかったりしますし、そもそも赤の他人が修業のために一緒に働くっていう機会はないので、料理人以上に作業内容を言葉で逐一説明するのに慣れてない。となると地元の試験場の林先生や高嶋先生のような立場の人でもない限り、名人芸を指摘することはできないでしょう。
京都の野菜の評判が高いのは、よい野菜を作れる腕利きの農家がたくさんあったから。そしてそうした野菜が作れてこれたのは、京都の街の人や料理人がよい野菜を求め、高いお金を払ってでも買ったから。こうした消費者の声に熱意ある農家が応えて、さらに料理向きの野菜へ改良されていったのにほかなりません。
京都の農家は市街地が近いので、化学肥料のない時代でも街から出る屎尿やゴミを肥料とし、畑を肥やすこともできました。それでも、『京の野菜―味と育ち』によりますと、屎尿やゴミを取りにいくことができる距離の農家は限られているうえ、戦前から宅地化が進み、どんどん減る一方だったそうです。なにせ当時はすべて人力で運んでいましたからね。ちなみにこの本では京都の農家で使われてきた各種農機具の説明に30ページ以上を割いておりまして、そのひとつひとつから、農家の工夫と苦労がしのばれます。
もし、放っといてもおいしい野菜がワサワサ作れるくらいに京都の土と水が理想的なら、伝統野菜にとどまらず、レンコンやら大豆やらお米やらどんどん栽培すればいいんですよねえ。市内には数えきれないほどのお寺さんがありますから、境内に畑を作って、収穫物をお土産や精進料理にして観光客にふるまいつつ仏の心を説けば、6次産業化をはるかに超えた高次元産業化も夢ではありませんよ。
それとも儀式用ならいざしらず、宗教団体の土地で野菜を育てるのは、公益事業ではないから違反なのかしら。むむ、ここは国の出番ですぞ。TPPに負けない強い農業作りってやつのために、異次元緩和しなきゃね。
投稿者 webmaster : 13:44
2013年08月14日
料理本のソムリエ [vol.58]
【 vol.58】
夜トマトダイエットは
甘ーいフルーツトマトでもいいの?
暑いですねえー。梅雨の話でも書こうかと思っていたら、東京は七夕前に明けちゃったよ。織姫、彦星大喜び。一方東北や北陸は8月になってようやく梅雨明けを迎えたようで、その差はなんと1カ月。今年の夏はいったいどうなってんでしょうかねえ。
さすがアベノミクス、野菜の値段がだいぶ上がってらあ、と思ったら猛暑やら少雨やら豪雨やらで、日本のあちこちで野菜の育ちがかんばしくないそうです。その点、わが家は自衛にぬかりありません。柴田書店の盟友、七つ森書館(vol.20参照)の『おいしく育てる菜園づくりコツの科学』と『有機農業コツの科学』を社内で見つけまして(何でも落ちてるね、この会社)、それを教科書に野菜作りに精を出しております。
震災の年からグリーンカーテン作りを始めたわが家でありますが、1年2年と経つうちにあの暑い夏の記憶は風化し、葉っぱよりもぶら下がるもののほうに魅力を感じるように。今年はキュウリを植えてみました。もはやただの家庭菜園であります。涼しくなるために始めたのに、この炎天下でせっせと水やりにいそしんだりして、最初の目的はどこへやら。
一応無農薬で育てておりますが、拾った教科書が有機栽培の本なのと、隣に洗濯物を干しているためでして。たかだかプランター栽培だし、街中なので害虫といってもアブラムシやヨトウムシくらいしかつかないし、園芸用薬剤ってのもばかにならないし(本音)。
そんな愛情は注ぐが金はかけていない可愛い可愛いわが家のキュウリですが、ある日根元から元気な子ヅルが伸びてきました。よしよし葉っぱと花が増えるのは大歓迎と思っていたら・・・なんだこりゃ? キュウリの花の10倍くらいの大きさの花が咲きました。むむ、このひときわでかい花、どこかで見覚えが・・・。
 そう、あれは蒸し暑い、一昨年の夏のことでありました・・・。煎って食べるつもりでとっといたカボチャの種から芽がでてきたので、なにげなく植えてみたのです。そんな遊び半分の軽い気持ちで始めたのがいけなかったのでしょうか・・・。雄花ばかりで、たまに雌花がついても受粉せず、あげくのはてに葉っぱが真っ白に粉吹くうどん粉病に。咲いてはポタリ、またひとつ咲いてはポタリ・・・。うらめしそうにいくつも地面に散っていったあのカボチャの花ではありませんか! 親の因果が子に報い、生まれいでたる南瓜胡瓜…きゃー!!
そう、あれは蒸し暑い、一昨年の夏のことでありました・・・。煎って食べるつもりでとっといたカボチャの種から芽がでてきたので、なにげなく植えてみたのです。そんな遊び半分の軽い気持ちで始めたのがいけなかったのでしょうか・・・。雄花ばかりで、たまに雌花がついても受粉せず、あげくのはてに葉っぱが真っ白に粉吹くうどん粉病に。咲いてはポタリ、またひとつ咲いてはポタリ・・・。うらめしそうにいくつも地面に散っていったあのカボチャの花ではありませんか! 親の因果が子に報い、生まれいでたる南瓜胡瓜…きゃー!!
なあんて、じつはこのキュウリの苗、台木はカボチャでありまして、そっちのほうから子ヅルが生えてきちゃったんですねえ。放っておいたらキュウリとカボチャの両方の形質を継いでズッキーニが実ったり・・・するわけもありません。キュウリの台木に使われている食用に向かないぺポカボチャが実るだけのようです。ここは心を鬼にしてチョッキン。
それにしても実際に野菜を作ると、農家の大変さがよくわかります。家庭菜園なんて量も質もたかが知れてますし、花が落ちたって生計が立たなくなるわけじゃありません。その点、プロはいつでも結果を出さなきゃいけないのに、天候にふり回されたり相場にふり回されたり・・・。スーパーの野菜がどれも立派なのに割安で、お買い得に見えてきました。
キュウリひとつとってもちゃんと育てるには、病気に強い台木に継ぎ木したり、風で揺れないように添え木をしたり、ネットに誘引したり、剪定したりと手間がかかること。トマトだのナスだの果菜のたぐいの作業は、なんだか花や庭木の園芸に近い感じです。
これは江戸時代から園芸文化が発達した日本のお家芸なんですかねえ。トマトはキュウリのように長く伸びるものの、巻きつくツルを持ち合わせておらず、枝を整理してうまく固定しなければなりません。その画期的な方法として、千葉県農業試験場の青木宏史先生が昭和56年に発表したのが「連続摘心栽培」。摘心とは生長点をちょん切ってこれ以上伸びないように止めることでして、普通は主枝から分かれて出てきた脇芽は摘み取って1本仕立てにし、主枝がある程度伸びてきたら先端を摘心します。ところが連続摘心栽培では、主枝から脇芽が出てきたら主枝のほうを切り、脇芽から脇脇芽が生えてきたら脇芽のほうを切り、脇脇芽から脇脇脇芽が生えてきたら脇脇芽のほうを・・・と繰り返す。常に生えたての生きのいい若枝を伸ばしていく仕立て方なのです。トマトではほかには「つる下ろし整枝法」とか「斜め誘引整枝法」とかありまして、どれもこれも器械体操の技名か何かみたいですごそう。
もう15年くらい前、イタリアのサンマルツァーノ種のトマトについて調べていたときのこと。栽培農家が減ってしまった理由の一つにこの品種は栽培が難しかったから、とあったのですが、日本の農業試験場に聞くとそんなことはないという。どうも意見が合わない、おかしいおかしいと思ったら、加工トマト品種は通常「芯止まり」と呼ばれるある程度以上丈が伸びないタイプでして、支柱も立てずに放っときぱなしなのに対し、サンマルツァーノは例外だったのです。いっぽう日本の生食用トマト品種はみな「非芯止まり」でして、先に述べたような各種整枝法が発達しております。そのため日本の感覚でいうと、サンマルツァーノの栽培がたいして大変に思えないというわけなんですね。
イタリア人の名誉のために一言申しますと、彼らが怠け者で作業が面倒だからサンマルツァーノが衰退したのではありません。手間いらずで安く作れるように改良された新しい加工用品種との競争に押されてしまったということです。いくら品質がよいといっても、トマト缶は量が勝負の世界ですから、太刀打ちできなかったというわけ。
実際、イタリアでも非芯止まりの品種のトマトもまだまだ栽培されていまして、シチリアのパキーノのようにブランド化に成功したものもあります。『イタリア・トマトのすべて』によると、カンパーニャのチェリートマトも鈴なりに実をつけるタイプで、まだ青いうちに枝つきで収穫して、束ねて吊り下げて翌春まで保存するのが伝統だそうです。これを「ピエンノロ(振り子)」というとか。おお、こっちもなんか技名みたいで格好いいぞ。この本はちょっと大判ですが、図版が豊富。缶詰加工の歴史やEUの規定に翻弄されるイタリアの栽培事情についても詳しく、現地のトマト栽培の実際について知りたい方にお勧めです。

そんなイタリアを代表する野菜のトマトも、もともと観賞用として南米からもたらされ、最初の頃は毒があると信じられていたというのは有名な話。そうしたトマトがヨーロッパに受け入れられるまでの経緯については、『トマトが野菜になった日』をどうぞ。原産地のペルーやメキシコ訪問記もありまして、野生トマトがどんな植物なのかがわかります。
ところでトマトといえば永田農法が有名ですね。原産地に近い環境で育てるというのが謳い文句で、水と肥料を与えすぎないようにすると、トマトもホウレン草も本来備えている味になるそうです。もっとも、そもそも原産地のアンデスやイラン高原ってそんなに甘いトマトやホウレン草が出回っているのかしら、という素朴な疑問がわいて参りますが・・・。
 トマトに関しては、甘く育てるためのノウハウはかなり解明しているようで、先の青木先生の『消費者志向を重視したトマトの栽培技術』によりますと、水分ストレスをかけるとよいとあります。それには土壌水分を乾燥気味にする方法(水切り栽培ってやつですね)と、肥料を多く与えて根圏を濃度障害気味に管理する方法があるそうです。具体的には根の周りを囲うようにシートを埋めて、ある程度以上根が広がらないようにするとか・・・。群馬産のブリックスナインはまさにこれですな。糖度が10度近い甘いフルーツトマトってのも、最近は珍しくなくなっちゃいましたね。
トマトに関しては、甘く育てるためのノウハウはかなり解明しているようで、先の青木先生の『消費者志向を重視したトマトの栽培技術』によりますと、水分ストレスをかけるとよいとあります。それには土壌水分を乾燥気味にする方法(水切り栽培ってやつですね)と、肥料を多く与えて根圏を濃度障害気味に管理する方法があるそうです。具体的には根の周りを囲うようにシートを埋めて、ある程度以上根が広がらないようにするとか・・・。群馬産のブリックスナインはまさにこれですな。糖度が10度近い甘いフルーツトマトってのも、最近は珍しくなくなっちゃいましたね。
なお永田農法では有機肥料は否定しておりまして、液体の化学肥料を使うのが前提です。ぎりぎりの量を与えるわけですから、不確定要素の多い有機肥料は使いづらいのでしょう。永田農法創始者の永田照喜治氏は、1960年代に九大農学部の福島栄二先生と砂栽培を共同研究していたそうでして、その当時から一環して液肥主義なのです。今でいう養液栽培ですね。
じゃあ、もういっそ液肥を加えた水の中で育てちゃえ、というのがハイポニカ農法です。球根の水栽培のようにして育てますと土の中の病原菌やら害虫の害が防げるうえに、土が成長を邪魔しないぶんぐんぐん根が伸びる。釣られて枝もぐんぐん伸びて一本のトマトが大木になるそうで、昭和60年のつくば万博で展示されていました・・・が、若い人は知らないかな。グリーンカーテンにはもってこいではありますが、根が常に新しい水に触れるようにポンプで循環させねばならず、節電にならないのが悩ましい。あと、水切り栽培と対極の方法なので、永田農法と違って甘く育てるのは難しい模様です。
「〇〇農法」は百家争鳴汗牛充棟玉石混交。リンゴひとつで映画が作られる昨今ですが、どうも私は〇〇健康法や〇〇ダイエットの本を読んでいるのと同じ既視感にとらわれてしまいます。そのうち農パン栽培法とか、右農・左農診断とか現れたりしそう・・・。
あ、ちなみにわが家のプランターではミニトマトも栽培しているのですが、花が落ちたと思ったら、葉色がすぐれず、すっかりおやつれになられまして・・・(泣)。梅雨明け直後のいきなりの猛暑がこたえて体調を崩されたか。はたまたちょん切られたキュウリの台木のカボチャに呪われたか。ネットで調べたら引っこ抜いて焼却処分しろですって。有機栽培関係の本を見ても、もともと健康に育つのが前提なので、病気に対する情報はあんまりありません。
農家の場合は、病気が広まったら一大事だし、治療に手間をかけると採算がとれなくなる。だから初めから病気にならないよう、消毒したり病気を媒介する虫を殺したりしてきたわけです。そんな農薬に頼りっきりの過保護な育て方ではいけないってのはわかるのですが、病気になってもお薬ひとつ与えないってのもなんだかせつないです。
うちのトマトは1本しか植えてないので広まりようがないし、引っこ抜いたら今年の楽しみがなくなっちゃう。そこでいちょう病を抑える効果があるとかいうコーヒーかすをダメもとでまいてみました。お金がかからないし(これ大事)。そうしたら不思議なもんで今まで枯れてばかりいたのが健全な脇芽が生えてきまして、再び花もつけました。おお、コーヒーかす農法。私はこれでみるみる元気になった!という本を書いたら売れるかしら。
なあんて喜んでいたら中腰で作業をしすぎて、こっちが腰をいわしました。痛てててて。インドメタシンの湿布のありがたさよ。人間様にはいろいろ治療薬があって幸せですね。
投稿者 webmaster : 16:11
2013年06月14日
料理本のソムリエ [vol.57]
【 vol.57】
マンガの料理を作ってみたよ
前回ちょっと料理マンガについて書いてはみたものの、やはり絶対的な読書量が足りないことをつくづく感じました。マンガは入れ替わりが激しいうえにアイテムが無数にあるので、新刊棚を眺めていても見落としてしまう作品がいくらでもありそう。しかし、こればっかりは図書館に探しにいくわけもいかず、マンガ喫茶に入るのにはお金がかかる。時間もかかる。そこで柴田書店社員のみなさんに「おすすめの料理マンガは何?」とたずねてみましたよ。社内一斉メールで。普通の会社なら確実に上司にお目玉を食らうところです(笑)。
そしたら営業部のC水谷さんに営業部作成の料理マンガリストを渡されて、びっくり。どんな会社だ。書店の料理書フェアをお手伝いするために、いろいろ情報収集しているんですね。
制作部の井 ̄さんからは料理マンガに関するHPをいくつか教えてもらったのですが、あまりの作品の多さに立ちくらみ。ちなみに井 ̄さんは、よしながふみ押しでした。『きのう何食べた?』はもちろんですが、ほかの作品でもレシピをまじえて料理が効果的に使われているようです。この作品はレンタルコミック店から借りたものの、前に借りた人がヘビースモーカーだったらしく、タバコのにおいがしみついているのに閉口して翌日返したばかりでした。ほかのマンガならまだしも、料理が出てくるシーンでにおいを想像できないってのは困るので。ていうか、やはりお金を払って買わなきゃだめですね。
秀逸だったのは〇田君のレポートです。
<久住昌之の原作の食マンガでいうと、
「かっこいいスキヤキ」 絵・泉晴紀(泉昌之名義) 1983年
「孤独のグルメ」 絵・谷口ジロー 1997年
「花のズボラ飯」 絵・水沢悦子 2011年
と、14年周期で漫画家を変えて、同じようなネタを使いまわしつつヒットを飛ばすというサイクルがあるのに僕は気づきました。次は多分2025年です>
そうかっ、始まりは「夜行」だったか! 『かっこいいスキヤキ』はY田君も推薦していましたが、こちとら谷口ジローの絵のイメージが強くて存在をすっかり忘れていましたよ。14年後の作品はぜひわが社で…。
そういえば、会社の書棚で『花のズボラ飯うんまーいレシピ』を見つけました。マンガを見てりゃ作り方はわかりそうなのに、こんなレシピ本もでているんですねえ。ちょっと屋上屋を架す感じもしなくもないですが、プロセスやできあがりを写真で見たいという需要もあるんでしょう。そもそもこの作品、単行本は2巻まで出ているのに、1巻めはただの『花のズボラ飯』でどこにもナンバリングされていません。版元の秋田書店は当初は2巻も出す予定はなかったのかなあ。だとしたら、主婦の友や宝島社からレシピ本まで出るなんて大出世ですよね。
こうしてみるとマンガの中に出てくる料理を再現するっていうレシピ本もまた、結構出版されているようです。アマゾンの上半期ランキングで、料理本のジャンルに『ONE PIECE PIRATE RECIPES 海の一流料理人 サンジの満腹ごはん』(長いタイトルだ…)ていうのが入っていたので、「え、ワンピースって料理マンガだったの?」(私は連載第1回しか読んだことがないんです)とさっそく本屋に駆け込んだら、作品中に出てくる料理(それもコマのはしっこだったり)をピックアップして再現するというものでした。
これはマンガやアニメの舞台になった土地や建物を観光する“聖地巡礼”っていうのと同じ心理ですね。料理を再現し、味わうことで、しばし作品世界にひたろうというわけです。ただしそれには特殊なスキルがいるので、聖地巡礼のように誰でもできるわけではありません。そこで「ママー、このマンガに出てくる料理作ってー」という声に応える本に市場性があるわけですね。でもこういうのって、お母さんの本気度が問われます。「はいはい、もう、わかったわよー、ほら、これでいいでしょう?」的な再現だと、「ちがわいちがわい、サンジの作る料理はこんなんじゃないやい」とだだをこねられてしまいます。マンガ人気にあやかって気軽に手を出すと、逆に水を差すことになりかねないかも。
そして料理を再現する場合は、前回このブログで書いた話と真逆ですが、あんまり絵がうまくない人の作品を選んだほうがいいのかもしれません。なまじ絵がうまい人の作品だと、せっかく頭の中でいろいろふくらんでいた想像上の料理が、写真をつきつけられることでしぼんでしまうような気もします。そう、マンガがドラマ化されたときにおきる、あのザンネンな感じに似ています。それを防ぐには、原作ファンも納得するような、本気の再現料理であってほしいものです。
このタイプの本には『まんが・アニメ・絵本に出てきた「あの料理」と「あのお菓子」を作れる夢のキッチン』(これまた長いタイトルだ…)や『マンガ食堂』があります。前者のマンガだけではなく絵本も・・・という戦略は、なかなか商売のツボを心得ていますね。もっとも絵本の料理ってオムライスだったり目玉焼きだったりで、再現しがいがありませんが・・・。後者は元はブログだったものを単行本化したもので、素人が純粋な探究心からできるだけ作品に忠実に再現したものなので、あなどれません。
 本気度からいうと、『まんがキッチン』は出色でしょう。作り手は料理研究家ですから、レシピも本気なら写真の撮り方も本気なのは当然。それでいて全篇作品愛がだだもれです(笑)。もっとも再現というより、紹介しているのは作品からイメージして作った菓子なので、読者によって評価が分かれるかもしれませんが、そのへんのニュアンスはちょっとわかりません。なにせ少女マンガ主体なため、どれも有名な作品ではありますが、この本で取り上げられているマンガのうち私が実際に読んだことのあるのは3作しかなかったもので…。と思っていたら、会社の浅Eさんから紙袋に入った『のだめカンタービレ』お試しセットというのを渡されました。
本気度からいうと、『まんがキッチン』は出色でしょう。作り手は料理研究家ですから、レシピも本気なら写真の撮り方も本気なのは当然。それでいて全篇作品愛がだだもれです(笑)。もっとも再現というより、紹介しているのは作品からイメージして作った菓子なので、読者によって評価が分かれるかもしれませんが、そのへんのニュアンスはちょっとわかりません。なにせ少女マンガ主体なため、どれも有名な作品ではありますが、この本で取り上げられているマンガのうち私が実際に読んだことのあるのは3作しかなかったもので…。と思っていたら、会社の浅Eさんから紙袋に入った『のだめカンタービレ』お試しセットというのを渡されました。
ほかには『空想お料理読本』てのもありました。著者の柳田理科雄氏の作風から想像するに、いろんな料理マンガのレシピを検証して、この料理は科学的にまちがっているとか、このコマの通りに作ると20人前の分量になるとか、突っ込みを入れまくる本なのかなあと思ったら、ただのレシピ再現本でした。ケンタロウ氏とのぬるーい対談が続きまして、「人気作品だからなんとなく再現してみたけど、どう?」っていう空気に覆われています。そもそも柳田氏の一連の著作は、どれもこれも作品に対するリスペクトが感じられなくて、単なる居酒屋トークにしか思えないのですが、これで子供の理科離れが防げると本気で思っているのかしら?
それにしてもこの本といい『まんが・アニメ・絵本に出てきた「あの料理」と「あのお菓子」を作れる夢のキッチン』といい、どうして『はじめ人間ギャートルズ』の骨付き肉は人気なんですかねえ。あれを見てあこがれたっていう話はよく聞きますが、私には単なる符号にしか見えなくて、おいしそう、食べてみたいとは思わなかったなあ。ちなみに私がマンガで見て心底食べてみたいと思ったのは、学研の『発明・発見のひみつ』(子供を理科好きにするならこっちでしょう)に出てくるニコラ・アペールが発明した豆とベーコン(だったかな?)の瓶詰めが最初でした。変だって? なんだか西洋料理っぽくてあこがれたんだよう。
さて。せっかくなのでこれらの再現レシピ本の中からいっちょう作ってみようか、と思ったのですが、どうも読んだことのない作品のものはおいしそうでもあんまり作る気になれません。そうなんですよ、再現本というのはあくまでも作品世界に浸るのが目的なんですから。じゃあ逆に、「こんな料理が出てくるなら、この作品を読んでみようか」という気持ちになるかというと、それはよほどの料理好きじゃなければありえないでしょう。基本的にこのジャンルはマンガの人気にのっかった、ファンブックなんですね。
 いろいろ考えた挙句、今回は、五十嵐大介作『リトル・フォレスト』から。制作部の井 ̄さんもお勧めの作品です。ただし、『マンガ食堂』に載っていたレシピは「ある日の朝ごはん」でしたので、ブログの記事のほうからばっけみそ(ふきのとう味噌)を再現することにしました。だって料理を作るのは、いつも夜中に一杯飲るためだし。ちょうどデザイナーのT島さんからフキノトウだのワラビだのフキウドだの、新潟の山菜をもらったところだし。
いろいろ考えた挙句、今回は、五十嵐大介作『リトル・フォレスト』から。制作部の井 ̄さんもお勧めの作品です。ただし、『マンガ食堂』に載っていたレシピは「ある日の朝ごはん」でしたので、ブログの記事のほうからばっけみそ(ふきのとう味噌)を再現することにしました。だって料理を作るのは、いつも夜中に一杯飲るためだし。ちょうどデザイナーのT島さんからフキノトウだのワラビだのフキウドだの、新潟の山菜をもらったところだし。
ブログのほうは手順だけで、分量のような無粋なものはぜんぜん書いてありません。普通の読者なら愚痴のひとつも言うところでしょうけれども、こちとら慣れているのでびくともしません。「味つけ(日本料理の料理人さんは“あたり”といいます)は目分量ではなくて、舌分量(料理人さんはこれを“口あたり”といいます。口に入れた時の触感とは違いますからね)でってね。へへ、プロっぽいね…」とか調子にのっていたら、酔っ払ってたもんでミリンと酢を間違えました。がーん。しかしここで少しもあわてず、そのまま調理続行です。だってフキノトウって酢味噌和えにしたりもするじゃない。
できあがったのがこの写真。食べてみたら意外といけました。そのままでも、キュウリにつけてもよさそうです。え、負け惜しみ? そんなことないって。調味料を取り違えたりした日には、マンガですと食べたとたんに口から煙が出てばったり倒れたりするもんですが、現実なんてこんなもんですよ。
投稿者 webmaster : 15:03
2013年05月21日
料理本のソムリエ [vol.56]
【 vol.56】
グルメコミックコンベンションに行ってみたよ
ゴールデンウィークが明けましたねえ。皆さんどこかへお出かけになりました? 桜を見に東北へ? 休みをとって10連休にして海外へ? 結構結構。人が外に繰り出さなければ経済は活性化されませんものね。おおいに羽根をのばしてください。
私はといえばね、本を片付けていましたよ。ふう。現在、会社の資料本(段ボール43箱もあった・・・)を大整理中なもんで。そしたら、あちこちに百舌(モズ)のように隠していた私物が出てきまして(日本酒の製造工程を描いた額とか箸袋コレクションとか)、それをしまうには今度は家の本を片付けなきゃならない。本の片付けの連鎖核反応でいつまで経っても終らない。
でもね、一日だけちゃんとお出かけしました。場所は浅草、東京観光のメッカです。目的は図書館のカードの更新や新しくできた古本屋モールを覗くこと(笑)。それからもうひとつ、料理系同人誌専門の即売会です。なんでもこのたび初開催とか。こちとら、おいしい料理と本の匂いのするところにはどこにでも現れますよ。
「柴田書店と料理マンガ、それも同人誌って、無関係じゃない?」と思うかたもいらっしゃることでしょうが、まったくご縁がないわけでもない。むかーし、雑誌『料理百科』は、同人誌即売会を取り上げたことがありまして。執筆者は『月刊ホテル旅館』元編集長の松坂健氏。旅行宿泊業界から見ると、全国から膨大な参加者が集結してかなりのお金を落としていくコミケはものすごいイベントでして、驚きの目をもって終始好意的に紹介したのです。そもそもコスプレだって、ホテルを借り切って開くアメリカのSFファン大会に起源があるわけですから、宿泊業と縁があります。今でこそ、クールジャパンとか称してコミケだのコスプレだのを持ち上げる空気がありますが、2001年当時は物好きなオタクの集まりというのが圧倒的な見方でしたから、先見の明がありました。記事のところどころが間違っていたらしくて(コミックマーケット準備会を準備委員会と記すとか)、つっこみも受けていましたが、コミック業界の外側にいる雑誌が好意的に取り上げるのは異例のことだったので、ネット市民の間で歓迎されておりました。ちなみにこの文章、『食ベンチャーのキーワード』に収録されておりますが、ぜんぜん直っておりません(笑)。

というわけで、柴田書店は同人誌即売会にやさしいのです。だから、どうかおじさんが足を踏み入れても場違いな変な奴という目で見ないでね。なんせ私、ビッグサイトで開かれているコミックマーケットは行ったことがありません。チケットを買わなきゃいけなかったりするのかしら。撮影した写真をブログにアップしてもいいのかしら。会場の空気もお作法もぜんぜんわからない。あ、ちなみに川崎と晴海なら行ったことがあります(笑)。

 秋葉原の本屋に貼ってあったポスターには開始時間がまったく書いてないし、会場の東京都立産業貿易センターのHPにはイベントそのものの記述がないしで、半信半疑で午後遅くに行ってみたら(並ぶのは嫌だしねえ)、閉会寸前でした…。料理専門の即売会ですからネギを振り回す人や食べ物の着ぐるみを着た人がいるのかと思ったら、だだっ広い会議室のようなところに机が並んでいるだけ。主催者や出展者が想像していた以上に人気で、売り切れ続出だそうで、会場はまばらな状態。そんなところにのこのこおっさんが来たので、さらに目立つことに。もう半泣きです。残っていた本を立ち読みさせてもらったのですが、作り手たちを目の前に、黙って突っ返してぷいっと立ち去る勇気がありません。結果として全ブースの商品を1冊ずつ買うはめに。うわーん。
秋葉原の本屋に貼ってあったポスターには開始時間がまったく書いてないし、会場の東京都立産業貿易センターのHPにはイベントそのものの記述がないしで、半信半疑で午後遅くに行ってみたら(並ぶのは嫌だしねえ)、閉会寸前でした…。料理専門の即売会ですからネギを振り回す人や食べ物の着ぐるみを着た人がいるのかと思ったら、だだっ広い会議室のようなところに机が並んでいるだけ。主催者や出展者が想像していた以上に人気で、売り切れ続出だそうで、会場はまばらな状態。そんなところにのこのこおっさんが来たので、さらに目立つことに。もう半泣きです。残っていた本を立ち読みさせてもらったのですが、作り手たちを目の前に、黙って突っ返してぷいっと立ち去る勇気がありません。結果として全ブースの商品を1冊ずつ買うはめに。うわーん。
落ち着いて戦利品を見渡してみますと、食べ歩きだの商品比較だのが多くて、学生の研究サークルっぽいノリですね。実は期待していたのは、料理レシピの同人誌だったのですが、それらもあったことはあったけれども売り切れてしまったようです。
料理系同人誌という本にじわり活気があることは、すでに前から情報を掴んでおりました。どっちがうまいか料理で勝負したり、新聞記者がウンチクを垂れたりするいわゆる料理マンガではなく、パスタや丼ものなどの自作レシピを紹介するというものです。いよいよこのジャンルにも採算を度外視して物づくりに励むマニアたちが進出してきたのか……。市場性だの読者層だの売上げだのに縛られるわれわれとしては、素人のピュアな情熱というのはなかなかの脅威です。ライバルの芽は早めに摘み取ってやるっ、こんなレシピ本で作る料理が食えるかっ女将を呼べ女将を!とか嫌がらせをしてやるっというのはウソで(それができれば全ブースの売上げに貢献したりしません)、みなさんどんな本を作っているのか見てみたいという好奇心からでした。
そういう若い才能を青田刈りした商業出版物もすでにありまして、同人誌として発表したものをまとめた『リア充ごはん』は発売直後に購入済みです。われわれとは違った感覚で作られていまして、「へえ、料理プロセス写真の背景に写り込んだものはわざわざ画像ソフトで消しちゃうんだー」とか、興味深かったです。
それにしても、いわゆる料理対決マンガやウンチクマンガの同人誌があんまり見当たらないのはどうしてでしょう。これらは商業出版では欠かせないアイテムであっても、素人が作りたい!と思うものではないのかもしれません。
ちょうど会社の本を片付けていて『花のズボラめし』と『てんまんアラカルト』を拾ったものですから(なんで書籍部の棚にあったんだろう?)、プロの料理マンガもちょっと見てみようという気持ちになりました。新古書店を覗いてみたのですが、世の中いつの間にかずいぶんいろいろな料理マンガが出版されていたんですねえ。
パラパラ立ち読みしてみたのですが、ここなら黙って本棚に戻しても心が痛みません。なかなか買いたいと思うものが見つからない。それはこちらの職業病で、マンガで語られている料理テクニックやウンチクの元ネタが透けてみえて興ざめ、という事情もあるのですが、原因はそればかりではありません。
まず第一にマンガ家は料理好きとは限りません。そのためか、かなりの率で料理マンガは原作者つきです。原作者が傾ける情熱を作画家が共有できるとは限りませんし、原作者つきでなくても編集者の企画先行で、作者は乗り気じゃなさそうだなあ、という作品も見かけます。原作マンガがいつもだめなわけではないし、ちばてつやはボクシングに詳しかったわけではありませんが、描き手に熱意はあったほうがいいでしょう。
作画家が料理好きでなければならない理由はなぜか。料理マンガは「この料理おいしい!」というシーンが出てこなければストーリーが成り立ちません。ところがおいしそうな料理を絵で表現するのは、かなりハードルが高いのです。基本的にモノクロですし、グラデーションのあるものやごちゃごちゃしたものを表現しづらいのがマンガの絵ですから。
おそらく資料写真を撮ってそれを絵におこしたのだろうというものを多く見かけますが、だいぶリアルに見えてもおいしそうとは限らない。グラビアアイドルの写真集からおこした登場人物が、はたして生き生きした魅力的な絵に見えるかというのと同じ理屈です。それでも可愛い女の子の絵が描きたいとひたすら腕を磨くマンガ家は多いことでしょうが、料理をおいしそうに描くことに血道を上げる人はそうはいないでしょう。
食指が伸びない絵であえて押し切る強気な料理マンガもありますが、『美味しんぼ』のように、料理専門のアシスタントがいて、料理だけは登場人物の雰囲気と全然違うリアルな画風の絵で登場するというのもよく見かけます。美味しんぼはストーリー展開よりも知識優先(そもそも吹き出しの中にあんなにびっしり文字が並んでいますし)ですから、これはこれでいいでしょう。教育テレビでは、お人形とお姉さんが同じ画面に登場して、イラストボードで説明したかと思えば実験風景に切り替わったりしても、あんまり気にならないと一緒です。
ところがドラマに重きをおいた作品でこの手のことをやると、アニメの中に実写キャラクターが登場するみたいで、違和感を生じてしまいます。おまけに料理の絵をいくつも描くのは大変だからと、同じ絵をコピーして使い回したりする例もみかけます。作品上もっとも魅力的でなければならないはずのものが手抜きで平気というのだから、不思議です。
料理のおいしさを描くのには、登場人物にセリフでおいしさを説明させたり、食べっぷりで表現する手もあります。vol44、45で出てきた例の「まったり」なんかがそれですね。ところがこれもネタがつきると、オーバーアクションだの背景の心理描写だのに逃げるようになります。審査員の後ろになぜか宇宙空間が現れたりする奴ですね。料理対決マンガで一度これに手を染めると、より強い敵が現れるたびに(ライバルインフレーションってやつです)エスカレートしなければならなくなり、どんどん滑稽になっていきます。『食戟のソーマ』の今後が心配でなりません。
とまあ、いろんな事情がありまして、料理対決マンガは実はなかなかに難しい。フランス料理や中国料理は「この調理法だとおいしくなる」という理屈が説明しやすいため、対決マンガに取り上げやすいのですが、読者が見たことも食べたこともない外国の料理は、せっかくおいしそうに描けていても共感を得にくいことでしょうしね。
その点で、最近多いのは日常系のものですね。料理そのものもさることながら、それを作る準備や食べる状況、人間関係に光を当てる。出てくる料理はみんなが知っているものなので説明はそんなにいらないし、登場人物に無理やりうまいうまいと言わせなくてもよい。荒唐無稽ではないので、読んでてこっちも食傷しません。
こちらの分野も知らない作品が一杯ある……。新刊は新古書店ではなかなか見つからないので、とりあえず『ごはんしよ!』と『幸腹グラフティ』をジャケット買いしてみましたが、どちらも料理を粗末に扱っておらずひと安心。たとえ予定調和であったとしても、料理で幸せになる話ってのはいいもんです。後者は食事シーンになるとちょっと線画風でリアルな絵になります。料理はある程度書き込まないとおいしそうに見えませんから、これは正しい戦略ですね。『花のズボラめし』も料理の作り方はズボラであっても、料理自体はしっかりと描けており、執拗に細かく描き込まれた背景となじんでいます。洗練された線ではない女性誌らしからぬ画風は、好き嫌いが分かれるとは思いますが、とってつけた感がありません。日常感あふれる日常系料理マンガ。人気の秘密はこのあたりにもあるのかもしれません。
さて、どうする。不慣れな少女マンガ系も探してみるか? 料理マンガ道は登り始めたばかりで、はてしなく遠いです。
投稿者 webmaster : 13:20
2013年04月30日
料理本のソムリエ [vol.55 ]
【 vol.55】
戦後強くなったのは前菜と松花堂弁当志向
前回、前菜の話をするはずが、山内金三郎のほうにぐいぐい反れていってしまいました。最後の最後でようやく戻ってきたぞお、というところで終わりましたので、続きです。
魯山人の前菜は、器ひとつとっても特徴的です。彼が使ったような四角四面な陶器というのは、さらにさかのぼると尾形乾山に行き着きまして、器を色紙や短冊に見立て、乾山はそこに絵や書の筆をふるっています。しかし縁が欠けやすいので、作り手としても使い手としても経済面からいうとあまり歓迎したくない器形です。
また4つの皿を組み合わせるというのも、なかなかに異端児。日本料理では盛り付けは奇数に揃えるのが一般的でして(2は別ですよ)、それが証拠に前回紹介した『あまカラ』の吉兆の前菜もあえて偶数を避けています。
前菜 吉兆
餅の花 川海老照焼
みしほ胡瓜
こがねいか
うに餅花
橙 すゞ子
割 かす漬
さん
しょ
五種 兵庫やきぬき
さか 海老塩焼
な 松葉かれ
寒もろこ
やはらか煮
金柑甘煮
膳松花堂好
松花堂と印が捺してある縁高の右上のコーナーに盛り付けられているのは、川海老照焼、味塩胡瓜、黄金烏賊、雲丹餅花を柳らしき枝で串刺しにしたもの。正月の餅花に見立てた演出ですが(どうにも長くて真四角の空間にはちょっと納まりが悪いです)、料理は4種類なのに、わざわざ海老だけ2尾用意しまして、合計5つを刺しています。
左上にはすず子(いくら)の粕漬を盛った割山椒形の橙釜。そして右下には兵庫産の焼き抜き(かまぼこの一種)、海老塩辛、金柑甘煮の3種類、左下には寒もろこ柔らか煮、松葉かれいの2種類を盛っているのですが、献立上は3+2の5種肴と称しております。
ところが魯山人の前菜のほうは4(死)に通じる数を選んでおり、ちょっと違和感があります。これは何でも“対”にしたがる中国人の好みです。それもそのはずで、彼はデビュー当初、中国料理のよさを日本料理に取り込むというのがウリでした(これも前に書きましたね)。なにせ自分の発明した鯛料理に「白汁魚王」って名づけちゃう人ですから。和食と中華の折衷なんて、今でいうフュージョンの元祖ですな。
 魯山人が中国料理を学んでいた件は、小社の『日本料理の四季』15号(1992年)で、吉田耕三氏(直弟子の一人で、魯山人伝の最初の執筆者です)が指摘しておりますし、吉田氏と仲の悪かった平野雅章氏も『魯山人料理控』(1994年)で、魯山人の中国かぶれに触れております。
魯山人が中国料理を学んでいた件は、小社の『日本料理の四季』15号(1992年)で、吉田耕三氏(直弟子の一人で、魯山人伝の最初の執筆者です)が指摘しておりますし、吉田氏と仲の悪かった平野雅章氏も『魯山人料理控』(1994年)で、魯山人の中国かぶれに触れております。
<星岡茶寮の料理内容も、料理主任だった武山一太の回想談によれば、「やはり、中国風の料理でした。大体ね、中国料理から始まったんですよ。中国へ二度も三度も行っているでしょう、で、現地を見ているからね。それでフカのヒレだとか、キンコだとか、スッポンだとかね……」ということで、いわゆる“中国かぶれ”の一時期があった。のちには変貌して中国料理は嫌いだとは言うものの、当時は「中国なら牢屋でもいいと思ったことがある」というくらいの惚れ込みようだった>
この武山氏の発言はもともと『別冊太陽 北大路魯山人』(1983)に収録されているものなんですが、世に広まっていた魯山人のイメージと合わないせいか、その後の平野氏はこの件を声高に語ることはありませんでした。おかげさまで最近の不勉強なくせにお説教臭い魯山人マニアたちにいたっては、こんなこと夢にも思っていないでしょう。
百聞は一見にしかず、ここで実例を挙げておきましょう。この間、大日本水産会の機関誌『水産界』の中で見つけた大正12(1923)年4月25日の「美食倶楽部」での献立です。会長、常務理事、水産講習所所長を迎えた宴席なので、魚づくしではありますが。
食単 四月念五日晩
一、小菜六珍 海鱧(はも)嫩芋、絲豆、仮西施舌(赤貝)薄醃鱒(ます)温魚(いわし)
一、餅鯨汁椀(鯨のおばけ)
一、大真歯(かれひのせびれの肉)
一、比目扁魚酒洗(かれひ)
一、腐脳羹(白子) 一、海鷂半汁(あかえひ)
一、白汁魚王(鯛) 一、碧緑魚炒製(べらの天婦羅)
一、蒪菜椀 一、食後珍果及飲料
ね。やたらむつかしい漢字だらけで中国料理のメニューみたいでしょ? 献立ではなくて「食単」っていうのがそのまんま中国流だし。調理法までもがどこまで中国風だったかはわかりませんが、当時の魯山人の料理を食べた人の感想に、国際的だ、長崎料理みたいだと書かれていたのはむべなるかな、であります。
こうしてみるとマスとタイはともかくとして、4月のハモやベラは時季がちょっと早いですねえ。それどころか食後の果物はスイカにブドウにビワにミカン、漬物はウリ、キュウリ、ナス、細根ダイコン、菜などの温室早成ものが用いられていました。初期の魯山人は味の素も使ってますし、世間様が思っていらっしゃるのとはだいぶ芸風が違います。
おっと、それはともかく、この献立の最初に出てくるのが「前菜」ではなく「小菜」と書かれているのにご注目ください。これまた、まさしく中国料理の呼び方ですね。4種類ではなくて6種類ですが。魯山人のこの時季の献立では小菜が12種類というのもありまして、やはり偶数に徹しています。
その後、魯山人の料理は中国色が薄まるとともに、オードブルの訳語の「前菜」が用いられるようになります。
<先づ最初に前菜と申すのを、出しますが、これは関西でやつてをりますつきだしと云ひますもので、東京では以前にはなかつたものであります。私共は美食倶楽部と云つた時代から、関西のつきだし風のものを前菜、又は小菜と呼んでやつてをりますので、東京の料理で前菜を付けましたのは、私共をもつて嚆矢と云ふべきと存じます。
関西のつきだしはほんの一品でありますが、例へば普通ならばゑんどう豆とか上等になりますと、カラスミとか、一品出すのでありますが、私共の前菜を作る趣意は、別に前菜といふ料理をつくるのではなくして、料理をした色々の材料の端切、残りものをうまく利用して、風情あるものに、之を最初に供しますればあとの料理を供するのにゆとりが出来るといふやうな便宜もありますし、之は、もともとロシヤなどでやつて居ります一般欧州の料理でもさうですが、その風習を取り入れて、純日本風にやつて見ましたものです>
これは昭和8(1933)年10月29日の「第二回日本風料理講習会」での魯山人の講演の筆記でして、自分が前菜を普及推進してきた第一人者と自負しておりました。
ちょうど同じ頃の『日本料理研究会会報』(昭和8年10月号)の座談会では、日本料理で「前菜」が広まり始めたころの混乱が見てとれます。
小林清次郎 近頃前菜と云ふ言葉が流行るが何処から出たか。
渋谷利喜太郎 前菜は四なら四、五なら五残つて居る、それが前菜である、五なら五残つて居る、後にさかなが十色出るといふし、それで以つて最初三つ出て居ると後六品出ると言つた具合……。
小林梅吉 卓袱から出たらしい、卓袱の方で前菜と云ふことがある。
小林(清) 詰り前菜と云ふと日本の言葉ですね。
小林(梅) さうです。
渋谷 長崎が先ですね。
渋谷利喜太郎は戦前の東京の日本料理界の重鎮なのですが、ちょっと説明がわからない。前菜が4品(偶数ですね…)出ると残りの料理は4品ある合図という意味なのでしょうか? それとも倍になる決まりで、最初に3品出ると残り6品ってことなんでしょうか??
これまた重鎮の小林梅吉は渋谷翁の説明を軽くスルーして、卓袱(しっぽく)料理から来たものと言っています。渋谷翁もちゃっかり尻馬にのっておりますが、卓袱料理で出てくるのはやはり「小菜」であって、前菜ではありません。このクラスの料理人さんとなると「知らない」とは言えず、困ってしまったのかもしれませんね(笑)。研究会理事の小林清次郎氏は、恐らく洋食のオードブルとの関係が知りたかったのではないかと思うのですが、日本の言葉と聞いて安心したようです。
 小社刊『お通しと前菜』(1983年)で小坂禎男氏は「お通しは、突き出しともいわれ、料理の始まる前に、まず出される酒の肴である。元来、壺と皿の二品を出したもので、壺は和えものや塩辛など汁気を含んだもの、皿はきすの焼いたのやくわい煎餅など乾いたもので、だいたい決まったものが多かった。(略)前菜はどちらかというと新しい料理形式で、昔はなかったものだ。料理の始めに、色や形に趣向をこらした一口大の料理を三品か五品盛り合わせたもので…」と述べていまして、やはり奇数にこだわってますね。
小社刊『お通しと前菜』(1983年)で小坂禎男氏は「お通しは、突き出しともいわれ、料理の始まる前に、まず出される酒の肴である。元来、壺と皿の二品を出したもので、壺は和えものや塩辛など汁気を含んだもの、皿はきすの焼いたのやくわい煎餅など乾いたもので、だいたい決まったものが多かった。(略)前菜はどちらかというと新しい料理形式で、昔はなかったものだ。料理の始めに、色や形に趣向をこらした一口大の料理を三品か五品盛り合わせたもので…」と述べていまして、やはり奇数にこだわってますね。
ただし魯山人もいうように、関西にはもともと豊かな「突出し」の文化がありまして、さまざまな料理が考案されていました。大阪の日本料理の職人の団体である「京繁」は大正11(1922)年に『浪花料理集突出号』を出版しておりまして、昭和に入ったのちも改訂新版を出しておりました。
また料理人さんに聞いた話ですが、魚すきで有名なミナミの「丸萬」では、入れ込みの席(小上がりに並べられたちゃぶ台で、複数のグループ客が食事するスタイルのことです。そば屋や居酒屋さんによくありますよね)に、突出しを入れた手提げを持った店員が回って、好きなものを選んで取ってもらっていたそうです。まるで香港の飲茶みたい。
一方戦前の関東の料亭はといいますと、お通しとしては「座付吸い物」や「座付き菓子」なんてのが普通でした。席についたらまずは、ちょっと汁気のあるものや小さなお菓子でお腹を落ち着かせてもらうというものです。酒呑みの人は食事前に汁だの菓子だの食えるかいっと思うかもしれませんが、そもそも料亭は酔っ払うための場所ではないという考えが背景にあるのかもしれません。
こんなふうに突出し=前菜の提供スタイルにもいろいろあったわけですが、戦後は華やかな盛り込みで提供することが多くなりました。魯山人が言っておりますように、最初に作りおきの料理を組み立てるだけで済む前菜を提供しますと、続く料理を作る時間をかせげます。ですから突出しは数が多いほうがあとあと楽なんですね。
先ほど細かく見てきた昭和27(1952)年の吉兆の前菜なんですが、塩辛と金柑だなんて甘いものと辛いものが同居しています。前回紹介した昭和11(1936)年の大阪毎日新聞では日本料理は一品主義、いろんな味が盛り込まれるなんて眼移りしてしまってぶち壊しとまで言っていた湯木氏が、この頃にはオードブル盛り合わせ派に宗旨変えしています。
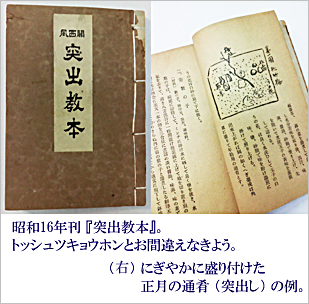 湯木氏がこの記事中でも述べていたように、にぎやかな突出しは戦前からありましたが、それを推し進め、料理を餅花に見立てるというような演出でセンスよく盛り付けて、世の称賛を集めたのは吉兆さんが嚆矢でしょう。もしかしたら、GHQがよいお得意だった事情が生んだのかもしれません。彼らは味はわからなくとも、日本風な趣向の料理を喜びましたので。
湯木氏がこの記事中でも述べていたように、にぎやかな突出しは戦前からありましたが、それを推し進め、料理を餅花に見立てるというような演出でセンスよく盛り付けて、世の称賛を集めたのは吉兆さんが嚆矢でしょう。もしかしたら、GHQがよいお得意だった事情が生んだのかもしれません。彼らは味はわからなくとも、日本風な趣向の料理を喜びましたので。
しかし、それ以上にこの可愛らしい料理に心を奪われたのはご婦人方だったと思います。戦前の料亭を利用するのは旦那衆で、接待や宴会の席と相場が決まっていましたが、戦後は昼に集まって食事をする婦人グループという新客層がぐんぐん台頭してきました。戦前、ご婦人同士の食事といえば、そばや甘味屋、百貨店の食堂あたりがお決まりだったのが、外食産業の大革命であります。
松花堂弁当だってこの流れが生んだものですよね。恐らくは大正から昭和にかけて流行した大寄せの茶事(たくさんの出席者を集める、形式にとらわれない茶事)で、昼にたくさんの料理を出す知恵として点心を弁当形式で提供する方法が考え出され、それが戦後の料理屋の昼営業の定番商品となったのではないでしょうか。
そもそも松花堂弁当の画期的な点は、4つの仕切りの中に器をはめこむことにあります。通常は4箇所ともではなくて、そのうちの2箇所くらい。器のはまってないところは汁気の出ない焼物や、「物相」という型で押し固めた御飯を入れたりします。
これはよーく考えると変なことなのです。松花堂弁当は枡の一部は直接料理を盛る食器として使われ、一部は食器をはめる容器であるという、不思議な使われ方をしています。
日本料理の盛り付けは、食器の上に食器をのせることを嫌います(最近は平気でやっている人も見かけますが、昔気質の料理人さんに怒られますよ)。だからわざわざ先の吉兆の前菜みたいに橙や柚子で釜を作るのでありまして、もし器を使うのでしたらせいぜい「つぼつぼ」といって、ごく小さい壺型の器に珍味を入れて縁高や平皿にのせるくらい(それも本来は、下に葉蘭や塩なぞを敷きます)。器の上に器をのせると安定が悪いし、高台の造りによっては傷をつけかねません。折敷だって塗りのものは布を張ったりして耐久性を高めていますよね。
ところが松花堂弁当は平気で器をはめ込みます。温かくて汁気のある煮物と冷たい刺身を一緒に提供するのに便利なうえ、あらかじめたくさん盛り付けておいて、一気に組み合わせて提供することができます。おせちと一緒ですね。まあvol.51で述べたように上げ底になるうえ、見栄えもよくなるんですが(笑)。
「弁当」といっても汁気があるうえに器がはまっているぶん重いので、幕の内のように持ち歩きができるわけではありません。ワンプレートランチとでもいうべきで、一品出しをせずとも会席料理をセンスよく提供できる。松花堂の器は八幡で生まれたものだとしても、松花堂弁当という提供スタイルを完成させ、普及させたのは湯木氏だとしたら、これだけで立派な功績だと思うんですけどね。事実をきちんと検証のうえ、顕彰してしかるべきでしょう。
投稿者 webmaster : 18:13
2013年04月10日
料理本のソムリエ [vol.54]
【 vol.54】
弁当の蓋を開けたら前菜が?
前回のブログを読んで、「大阪くんだりまでして公園で探偵ごっこかい? まったくいいご身分だねえ」なんて思われたそこのあなた! 誤解、誤解ですよー。めっそうもありません、ちゃんと仕事はしてますからねっ。我々の取材は料理店さんのアイドルタイムに集中するので、変な時間帯がぽこっとひまになることがあるんです。あの日は夕方にまたミナミの取材先まで戻って、寝台列車で帰ったんですからね。夜は大阪の味の勉強と称して、著者とお寿司とおでんで飲んでたのはここだけの話ですぞ。
ここんとこタイトなスケジュールで動いているのは、会社のフロアの大規模なレイアウト変更があるため本を棚から出したり箱に詰めたり台車で運んだり腰を痛めたりしていたのと、今月発売の『月刊専門料理』に出張コラムを1本書いてたせいもありまして。修業中の若い料理人さんに向けて、役立つ本を12冊薦めるという企画です。独立開業特集号だと聞いてたもんで、てっきり修業を終えたオーナーシェフ向けの本を案内するのと勘違いしてたこともあり、時間切れでなんだか不完全燃焼な仕上がりになっちゃった。どっかのブログで紹介済みの本やこれから取り上げようと思っていた本も混じっているうえ、終始マジメを気取っております。そのくせ相変わらずみっちりぎゅう詰めで、これから料理本に親しもうっていう人には文字だらけで不親切……。

くよくよ言い訳するのはこれくらいにして、本題へ。前回のWikipediaの松花堂弁当の項ですが、<その後、毎日新聞が<吉兆前菜>として取り上げたことで話題となり、松花堂弁当の名が広まった。>という部分の考証がまだでしたね(われながらしつこいね)。この一文はvol.52で引用した『吉兆味ばなし』の記述に基づくものと思われますが、出典が正確ではありません。『吉兆湯木貞一』によると、この記事は昭和11(1936)年2月20日の大阪毎日新聞に掲載されたものなんだそうです。さっそく見てみますと「洋食・和食を通じてこの頃“前菜時代”です」と銘打って、大阪ガスビル食堂の鈴木吉蔵料理長が洋食のオードブルについて、湯木氏が和食の前菜について説明しておりました。
<飲み屋などで銚子一本につき出しの小皿をたくさん出してお客さんを喜ばす、つまり前菜を賑わすといふことが流行つてゐます。これは酒のサカナが少しづゝ数多くが好ましいといふ酒飲みの心理に投じた戦法で…(略)…しかし本当の日本料理の立て前からいへばオードウブルはあくまで一品主義でありたいもので、これが日本料理の最高位である懐石料理が西洋趣味と本質的に違ふところです、酸、甘、鹹味を一時に出す方法は美味求真的な心から眼迷ひさせて純日本的な食卓では気持のブチ壊しとなります。
だからつき出しでもやはり力のある風味の籠つた料理を落ついて味ふといふのがあくまで日本料理の前菜の行き方でありたいと思ひます、もつとも一品だけであまり淋しいといふ場合趣味のある容器、たとへば松花堂が薬箱に使つたといふ春慶塗の蓋ものなどに、昨今だと小鯛の塩辛、若鮎の黄身ずし、嫁菜の浸し、蛤田楽などをとり合せてオードウブルのセツトがはりに出すなどといつた方法がいゝと思ひます>
昭和11年の時点で湯木氏は、春慶塗りの四つ切り箱を4種盛りの前菜に使うことを提案していたのには注意が必要ですね。昭和8年には弁当箱として使い始めたが、飽きて前菜にも使うことにしたのかしら? 前菜を盛る場合にも貴志邸に挨拶に行ったのかしら? そもそもこの記事から、何がどうなって松花堂弁当という名で広まっちゃったのかしら?
戦後もこのスタイルで提供する前菜は続いたようでして、『あまカラ』(現在出版されているグルメガイド雑誌じゃないですよ)の6号(1952年2月)では、山内金三郎がイラスト付きで松花堂弁当(前菜を盛る場合は縁高と呼んだほうがふさわしいですね)に盛られた吉兆の前菜を紹介しています。
山内金三郎は「神斧」「吾八」と号しておりまして、民具のおもちゃコレクターであり、ギャラリーや古書店経営、雑誌編集もしておりました文化人です。そういえば彼が編集長をしていた雑誌の文面に対し、魯山人が激怒した手紙が3年前に見つかってニュースになりましたね。朝日や毎日は大阪本社版のみですが、読売は全国紙でも扱っておりました。
<43年10月にも開催予定だったが、同社の広報誌の記事に引用された「(戦時中という)時節柄、どんなよいものでも高くてはいかん。(中略)少しでも安く売るやうにし給へ」との小林の言葉に魯山人が激怒。10月9日付で「安くて買(かえ)ると云ふハ金高之問題なりや実貨価値を論するものなりや」などとする手紙を書き、送りつけた。
また、同17日付の手紙では、「づに乗って馬鹿になり切つた」「猪口才にして笑止千万」「意思の疎通絶無」と記事を執筆した編集長を罵倒。「これが貴下のお気に入ってゐるとあつては摩訶不思議」などと小林を責め、展覧会中止とわび状の提出を申し入れている。以降の手紙はなく、同展が開催されたか否かも不明という。>(読売新聞2010年10月9日朝刊)
 記事の前半をはしょったのでちょっと補足しますと、この手紙は阪急グループ総裁の小林一三(逸翁)宛てでして、逸翁美術館の建替えで未整理の書簡の中から見つかったものです。問題の雑誌編集部は阪急百貨店内にありましたが、広報誌ではなく美術雑誌でして、『美術・工芸』の昭和18(1943)年10月号。阪急百貨店で開かれる魯山人の作品展の予告の最後に、<肝入りの一人である小林逸翁も『時節柄、どんなよいものでも高くてはいかん。世話人とよく相談して、少しでも安く売るやうにし給へ。それなら僕も大賛成だ』といつてゐられました。今度の展覧会はその趣旨に従つたものです>と一言載せたのがことの発端でした。アッツ島で日本軍が玉砕し、配給が滞りはじめ、国が統制する“国民食器”が使われていた頃ですから、贅沢品販売とにらまれてもおかしくありません。そこで余計な気を遣ったばっかりに、我輩のすんばらしい芸術をなんと心得ておるのかと烈火のごとくお怒りになったようです。
記事の前半をはしょったのでちょっと補足しますと、この手紙は阪急グループ総裁の小林一三(逸翁)宛てでして、逸翁美術館の建替えで未整理の書簡の中から見つかったものです。問題の雑誌編集部は阪急百貨店内にありましたが、広報誌ではなく美術雑誌でして、『美術・工芸』の昭和18(1943)年10月号。阪急百貨店で開かれる魯山人の作品展の予告の最後に、<肝入りの一人である小林逸翁も『時節柄、どんなよいものでも高くてはいかん。世話人とよく相談して、少しでも安く売るやうにし給へ。それなら僕も大賛成だ』といつてゐられました。今度の展覧会はその趣旨に従つたものです>と一言載せたのがことの発端でした。アッツ島で日本軍が玉砕し、配給が滞りはじめ、国が統制する“国民食器”が使われていた頃ですから、贅沢品販売とにらまれてもおかしくありません。そこで余計な気を遣ったばっかりに、我輩のすんばらしい芸術をなんと心得ておるのかと烈火のごとくお怒りになったようです。
先の読売新聞の書きようだと、時局におもねる百貨店の俗物編集長に魯山人大先生がお目玉を食らわせたように見えますが、当時の山内は阪急美術部の嘱託で、昭和14(1939)年に銀座のギャラリーで開かれた魯山人の画展には、竹内栖鳳に東郷青児、長谷川伸に森田たま、根津嘉一郎に小林一三といった文化人、財界人のお歴々と並んで推薦文を寄せていたくらいですから、それを頭に入れて読んでみるとちょっと受け止め方が違ってきます。
そもそも山内は東京美術学校の卒業生でして、梶田半古の弟子。小林古径ら京都画壇との交流もあり、明治の末には美術店「吾八」を経営し、大正時代にはおもちゃの版画集『寿々』を出版しています(20年ほど前にオリジナルの版木を使った復刻本が出ています。すごく贅沢な造りです)。こうしてみるとちょっと魯山人とかぶるところがありますね。
のちにその画力が買われて「主婦之友」社に入社したのですが、文化人に顔が広いのと企画力があるので編集者としてもめきめき頭角を現します。同社が公募した社章の審査員を務めたり、絵画も陶芸も染色もこなす市井の天才芸術家(魯山人のことではありませんよ)の藤井達吉と旅行したときの記事を雑誌に掲載したりと、これまた多才に活躍し、最後は事業部長を務めました。彼が主婦之友社に入ってしばらくして、同誌にデビューしたての魯山人が文章を寄せていますから、その当時から面識があったかもしれません。
なお彼は、全国の菓子を集めた画文集『甘辛画譜』の著者であり、食通としても知られておりました。じゃなきゃ『あまカラ』に連載なんて持てないものね。『新修茶道全集』(1951年)の懐石の巻の編集を担当しております。
<「懐石編」のとりまとめに、編集者の立場から少し蛇足を加へてみますと、懐石などといふものは、それ自体が実際的なものであり、実用的なものなので、いたづらに理論に流れたり、高踏ぶつた文献の解説に終始するやうなことは仕度くないと思ひました>
 とは同書月報中の彼の弁であります。確かに戦前の昭和16(1941)年に刊行された『茶道全集』懐石編(戦後復刻もされました)と比較すると、前回登場した木津宗泉以外の執筆陣を一新。魯山人もバッサリはずされて、代わりに辻嘉一氏や湯木貞一氏が加わっております。ちなみに辻嘉一氏は、例の問題になった『美術・工芸』の翌11月号にビルマ戦線からレポートを送っておりまして、当時から親しい間柄だったようです。
とは同書月報中の彼の弁であります。確かに戦前の昭和16(1941)年に刊行された『茶道全集』懐石編(戦後復刻もされました)と比較すると、前回登場した木津宗泉以外の執筆陣を一新。魯山人もバッサリはずされて、代わりに辻嘉一氏や湯木貞一氏が加わっております。ちなみに辻嘉一氏は、例の問題になった『美術・工芸』の翌11月号にビルマ戦線からレポートを送っておりまして、当時から親しい間柄だったようです。
このように、主婦之友から阪急グループに移ったのちも、山内の手腕は衰えませんでした。数々の展示会を手がけ、『武者の小路』昭和13(1938)年11月号で<山内さんは次から次へと絶間なしに催物をやつてゐられるが、どれもこれもヒツトするには敬服させられる。兎に角山内さんは阪急の儲け大将だ>と絶賛されるほど。魯山人の手紙の中の<これが貴下のお気に入ってゐるとあつては摩訶不思議>というセリフはこうした背景に基づくものです。もしかしたら魯山人は、やっかみや山内に認められたい気持ちもあってちょっかいを出したんじゃないかしら? なにしろ彼は、柳宗悦にも手紙でからんだ前科がありますからねえ。それに魯山人は山内本人にもくどくど文句を書きたてた手紙を出しておりまして、それが4年前の夏の古書展で売りに出されておりました。出品者は昭和15年と27年の手紙と推定していましたが、一部はこの一件に関するものかもしれません。
ちなみに魯山人は戦後に、先の『あまカラ』誌上でも一騒動やらかしております。12号と13号(1952年8・9月)で行なわれた「甘辛往来」というアンケート企画に対し、<私ハ一生涯かゝつても申上げられない程の話をもつてゐますから、記者の上京の際でも御立寄り下さいお話します>と偉そう…じゃなかった堂々と答えました魯山人先生。その後、編集部からなしのつぶてだったのにしびれをきらしたのか、この企画に対しまして編集部宛てに貴重なご意見を送られました。<(略)…直接物の味のことばかり言つて、其の背後に大きな役割を持つてゐる「美」の支配力には甘辛往来回答者は無関心である。この点甚だ物足りない回答で満ちたことを嘆いてゐる次第だ>と憂いていらっしゃいます。そして親切にも各コメントの感想を寄せて下さり、一挙掲載されました。
でもねえ、このアンケート企画は(1)わが家で好んで食べる料理、自慢料理、(2)好きな外食とその店、てな実にありふれたお題でして、そんなに力こぶを作って答えるほどのものかしら。たとえば小林一三の回答は<(1)ハンペンのテリ焼、ブリの一塩、塩鮭のヤイたの等、田舎ものゝ趣味也。(オオはずかしや)(2)京都大市のスツポン>。これをご覧になった魯山人は<(1)最も恵れない一人である。諸事貧乏性に出来た人、血色が悪い、シワが多い所以である。(2)不老長寿が狙ひでせう>とあんまり美しくない言葉でお嘆きになっています。
山内金三郎はといえば、(1)が菜園のナスの油炒めを生姜醤油で食べる、庭のタケノコで作った筍飯、妻の柿の葉すし、(2)は戦後復活した美々卯のそばと答えているのですが、これに対しては<(1)油で炒めるのは、歳より若い味覚。筍は敢て飯とは限らない。柿の葉すし、多分よささうである。(2)大阪でそばは大したことはあるまい。尤も東京でも旨いのはないが>ですって。
中には<かれこれ及第。あなたは少し分かるらしい>なんておほめの言葉を頂戴した人もおりますが、<三等食道楽><マヅイ物をあさる食通のやうに聞えます><(1)も(2)も味覚に天分の無い人を明かにしてゐます。そのくせラジオの食物対談に出られるが>なんて誹謗中傷も…。こんな調子で49人の回答について逐一批評しています。なんだかグルメ気取りのブロガーみたい。そのうえよーく見てみると、料理通として知られていた本山荻舟や山本嘉次郎、裏千家の井口海仙、友人の菊岡久利や大阪星岡茶寮のパトロンだった志方勢七らの回答には、いっさい触れていないのはどうしてかしら?
その後、この手紙の論調に気分を害した読者の投書を掲載したり、パリ滞在中の魯山人のふるまいを大岡昇平が暴露する「巴里の酢豆腐」(例のトゥール・ダルジャンで醤油と粉ワサビで鴨を食べた話です。タイトルからわかるように知ったかぶりを描写する内容なんですが、世間一般ではなぜか魯山人が食通ぶりを発揮した逸話に脳内変換されています)を掲載したりと、『あまカラ』編集部はなかなか人が悪いですね。
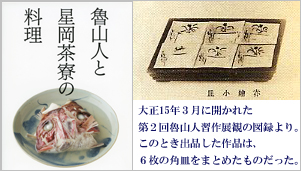 おっとあんまり揶揄すると魯山人先生と変わらなくなっちゃう。最後にちょっとほめておきましょう。4つに分かれた器で提供する前菜に話を戻しますとね、賢明な読者諸氏はお気づきかと思いますが、vol.5やvol.25でも書きました通り、これってとっくのとうに魯山人が提供していたスタイルでしたよね。このオリジナルの器に盛った前菜こそが星岡茶寮の名物料理でして、日本料理の前菜は自分の発明であると自慢しておりました。
おっとあんまり揶揄すると魯山人先生と変わらなくなっちゃう。最後にちょっとほめておきましょう。4つに分かれた器で提供する前菜に話を戻しますとね、賢明な読者諸氏はお気づきかと思いますが、vol.5やvol.25でも書きました通り、これってとっくのとうに魯山人が提供していたスタイルでしたよね。このオリジナルの器に盛った前菜こそが星岡茶寮の名物料理でして、日本料理の前菜は自分の発明であると自慢しておりました。
Wikiの錚々たる執筆陣はさておき、吉兆開業前から魯山人に傾倒していて、星岡茶寮で修業するのが夢だったという湯木貞一氏がそれを知らないわけがありません。ただし、魯山人の前菜の器は、四角の陶器を組み合わせてひとつの盆にまとめたものですから、松花堂縁高の前菜はそのまんま真似たわけではないのですが、多分に意識はしていたでしょう。
また吉兆では、薬味入れみたいな浅くて四角い皿が6つ(2行3列です)つながった状態で焼かれた「絵の具皿」もオリジナルの器として有名でして、こちらも前菜や刺身を盛るのに用いられています。これまた魯山人の前菜をリスペクトしたものではないのでしょうか。
投稿者 webmaster : 16:08
2013年03月05日
料理本のソムリエ [vol.53]
【 vol.53】
松花堂弁当のすみっこをつついてみました
前回、松花堂弁当の謎がホームズばりに明快に解決されるはずが、証言が錯綜しているうえに松花堂の所有者がいろいろ変わる間になんだかよくわからなくなってしまったということがわかりました。どちらかというと芥川ばりの藪の中です。煙草盆とお重は同じ十字の仕切りがあっても別物なのに混同されてどっちが松花堂弁当の元になったのかがわからないのと、オリジナルから写した後世の作があるために話がややこしくなったのと、証言者の記憶があいまいだったり息子さんの伝聞だったりでバイアスがかかっているせいだと思われます。誰かがどっかをまちがえているのは確かです。
あ、それからお気づきの方もおられるかもしれませんが、現在Wikipediaの松花堂弁当の項にはこの推理とはまったく違う由来が書かれています。これはおもに3人の執筆者によるものです。
まず2008年11月30日に、国宝級の本をたくさんお持ちのような「書陵部」なるうらやましいハンドルネームの人物が次のように書き込みました。
<昭和の始め(昭和8年(1933年)頃とされている)、代々式部卿を務めた貴志宮家の大阪(桜宮)邸内の茶室「松花堂」で茶事が催された折、日本屈指の名料亭である大阪の「吉兆」の創始者である湯木貞一が、貴志家の当主、貴志奈良二郎(二代貴志泉松庵)より、この器で茶懐石の弁当をつくるように命じられ、後にその事が話題となり、松花堂弁当の名が広まった>
ちょっと見はもっともらしい説明ですが、「式部卿を務めた貴志宮家」っていうのが何のことかわかりません。いったいどこの宮様で? また昭和の初めなら貴志奈良二郎は家業を継いで彌右衛門(二代貴志彌右衛門)を名乗っているのに、「泉松庵」という号にしか触れていないのはなぜなのでしょう…。
まあ、これだけなら西村芳次郎と貴志奈良二郎とを取り違えただけのようにも読めますが(どっちもジロウだし)、12月1日にはさらに次の一文が足されました。
<湯木は、当時他家から松花堂弁当の依頼を受けると、その都度貴志家への挨拶を怠らなかったという。>
心温まる話みたいに結ばれていますが、同じ日に書き込まなかったのがうさんくさい。あとから思いついたんじゃないの? それに湯木氏は律儀に何度も挨拶に通ったにもかかわらず、自著ではころっと忘れてしまったとしたら、かなりそそっかしいように思えます。
そんなこんなで放っておったのですが、先月久しぶりにWikiのこの項目を開いたら、さらにややこしいことになってました…(呆然)。昨年8月30日に式部卿云々という記述がおかしいことに気づいた人がいて、よせばいいのにここだけカットされてました(ほかのところは大丈夫なの?)。そして11月14日と15日に二人の人物によって<…この器で茶懐石の弁当をつくるようにと命じたのがはじまりである>のすぐ後に出典と新情報が書き加えられています。今度の人たちはハンドルネームを使っておらず、203.139.219.58と124.212.169.61というIPアドレスしかわかりません。もっとも誰かがパソコンを遠隔操作して書き込んだのかもしれませんが(笑)。
<(昭和8年「西田幾多郎日記」 太田喜二郎「絵茶會記」より)。その後、毎日新聞が<吉兆前菜>として取り上げたことで話題となり、松花堂弁当の名が広まった。>
これまた真実味たっぷりの書きぶりですが、西田幾多郎は日記を1日1行くらいしか書かないうえに三日坊主の気がありまして、毎年正月になると思い出したように再開しては挫折の繰り返し。昭和8年は5月で放り出しております。そもそも貴志氏はどの年にも登場しておりません。
「絵茶会記」っていう文献(初めの書き込みでは「茶会の画」だったのですが、16分後にタイトルを改めて投稿し直しています。なぜ「会」の字だけ旧字なんだろう?)は、この書き方だと西田幾多郎日記に引用されているみたいにもみえますが、もちろん見当たりません。ちなみに洋画家の太田喜二郎も日記を5冊残しておりますが、ベルギー留学時代の明治から大正の初めにかけてのものしかないようです。
この投稿が困るのは、何から何までデタラメというわけでもなさそうなところ。貴志奈良二郎は宮様ではなくて紀州の武士の家系なんですが、確かに大阪市・桜宮の彼の邸内には松花堂写しの茶室がありました。前回でも触れました数寄屋建築研究者の中村昌生氏の調査によると、心斎橋の樋口十郎兵衛宅に移った初代貴志彌右衛門が、土蔵に残されていた廃材が松花堂茶室と知り、明治25(1892)年に肥後橋南詰に再建し、同32(1899)年に桜宮へ移築したそうです。また太田喜二郎は西田幾多郎の娘に絵を教えており、奈良二郎の親友でもあります。正座のできない太田に二つ折りの座布団をあてがって茶室でもてなし、お茶のファンにしたのは、奈良二郎その人です。これらの登場人物が揃う茶会というのは、けっして不自然ではありません。
こりゃもうアームチェアディテクティブではラチがあかないぞ、ワトソン。事件は現場で起きているんだっ。大阪のもう一つの松花堂に行ってみよう。GOGO!
淀川ほとりにあった貴志家の邸宅は大阪市に寄付されて、今は大阪市桜宮会館となっております。JRの大阪城北詰駅の近く。この辺はお屋敷町だったようで、地図を見たら藤田邸跡庭園の隣あたりかも。5時の閉園間際に飛び込んできょろきょろしていると、壁の向こうに和風建築みたいなの発見! と思ったら、大阪市公館庭内のあずまやでした。こちらはかつては「大阪市長公館」だったのですが2007年に改名して「長」が取れたそうで、母屋の洋館のほうでは1日1組限定のウエディングも行なっているそうです。ちょっと民業圧迫な気もしますが、さすが大阪市、稼げるものなら何でも使おうってわけですね。公館から追い出されちゃったから市長は永田町あたりでうろうろしているのかあ。

とにかく広くて迷っていたら、川沿いの桜宮公園で何か黒いものをうっかり踏みそうに…。カラスの死体だ! これはこの件から手を引け、という警告かっ! ほうほうの体で公園から転げ出たら、ようやく桜宮会館らしき場所に…。な、ない! 建物があとかたもなく消えている! すでに彼らの手がここまで…。
実は隣の太閤園が拡張してブライダル施設を建設中でした。昨年の『月刊ホテル旅館 12月号』のニュースにちゃんと取り上げられておりまして、知ってて行きました(笑)。というか、これまで非公開だった松花堂も、工事中なら塀がとっぱらわれて外観が見られるかもと思って行ったんですが、危ないから解体してどこかで保管中のようです。そりゃそうだ。9月開業予定の新施設の庭の中に復元されるそうで、もうしばらくのご辛抱。

ところで、貴志奈良二郎の長男である康一は、戦前を代表する音楽家でありました。大正15(1926)年に甲南高等学校在学中の17歳で単身渡欧し、スイスの国立音楽院とベルリン国立高等音楽院で学び、20代の若さでベルリンフィルを指揮。さらに映画会社を興して、日本が独自開発したカラー技術や魚眼レンズを使った前衛的な作品を撮るなど、八面六臂で活躍した華々しい経歴の持ち主です。『貴志康一 永遠の青年音楽家』など彼の評伝や研究が刊行されておりますし、彼が作曲した作品も『ベルリンフィル ― 幻の自作自演集』『竹取物語』(湯川秀樹がノーベル賞を受賞したストックホルムの晩餐会で演奏されました)など、いくつもCDに焼かれております。松花堂弁当の話はこうした貴志康一ファンの間から出てきた逸話なのでしょうか…。
貴志家は新聞の長者番付にものる資産家で茶人でもありますから、吉兆さんがお出入りしていたのはありえる話ですが。
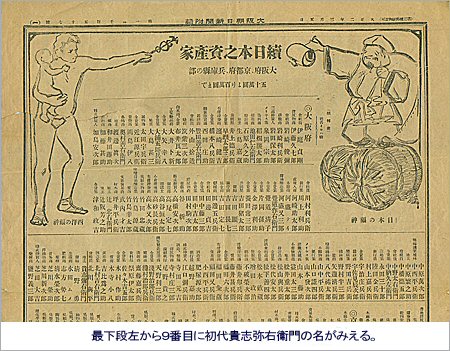
貴志康一は、日本にヨーロッパの名器の音を知ってもらおうとストラディヴァリウスを購入したり、日本とドイツを行き来して映画上映や演奏会を行なうなど、日欧の文化交流に努めましたが、それにかかった莫大な資金の一部として実家の支援もあおいでいます。奈良二郎は甲南女子高等学校の教頭として学校教育に尽くし、桜宮が工業化して空気が悪くなると子供たちのために芦屋に移ったほど家庭を大事にしていました。息子の型破りにスケールの大きい夢の困難さを案じつつ、その実現を応援し続けました。
康一は昭和6年9月27日号の『週刊朝日』で、<…シリング氏と画家(中略)のラファイエル・シュスター・ヴォルダン教授と僕の三人で一度日本の音楽(勿論日本の楽器により)を用い日本の脚本で純日本式のオペラを造り上げることを子供のように空想したことがあった。第一舞台は歌舞伎風に例えば青松がありその前にサッパリとした日本の座敷、深くシンミリとした寺院、…(中略)…音楽も勿論平均律などの東洋独特なものを使うなど…>と述べており、かねてよりヨーロッパの地で音楽と舞台を通じて日本を表現することを夢みていたことがわかります。
さらに10月25日号の『週刊朝日』では<日本を紹介する又真に理解させる最善の方法はトーキーだと思う><日本のフィルム界を代表する松竹、日活などよろしく今後は海外に発展し真の日本文化、風俗、自然を紹介していただきたいものだ>と述べていたのですが、もはや他人をあてにしていられないと思ったのか、のちに自らメガホンをとって日本を紹介する芸術映画を作り、例の昭和8年にはドイツで上映しております。タイトルは「鏡」で、桜宮の松花堂も登場します。平成13(2001)年に国立近代美術館フィルムセンターの職員がドイツに残されていたフィルムを発見して里帰りしておりまして、昨年10月にNHKの「探検バクモン」の「禁断の映画パラダイス」(前編)にて一瞬取り上げられています(有料ですが10月までNHKオンデマンドで見られます)。映画の導入部にあたる、ひさしぶりに日本に戻った青年(これはベルリンで演劇を学んだ康一が演じております)と父が食事をしているカットが流れておりました。丸い折敷(松花堂弁当ではありませんよ)の上にお造りがはっきり見てとれまして、ほかに金襴手のような皿に焼物らしきもの、ご飯のおひつ、お椀などが並んでいて、とても豪華。これまた吉兆さんの出仕事だとしたらちょっと面白いですね。いずれにせよ、本格的な日本料理が動画で海外に紹介された走りではないでしょうか。
なお太田喜二郎はひんぱんに親友の奈良二郎と手紙のやりとりをしており、中には近況を記した絵手紙もありました。淡交別冊の『近代の数寄者―続茶人伝』には、スイスのシュルス夫妻を招いた茶会を描いた「茶会帖」(絵茶会記ではありません)が掲載されています。この中に四角い折敷に筒向と汁、ご飯が載せられた絵がありまして、その折敷が深くてまるで縁高のよう。Wikiの御仁はこれをうろ覚えで松花堂弁当と勘違いしたのかも? もっともこの絵の茶会は昭和2(1926)年5月2日のことで、昭和8年ではないのですが。
日本とドイツの架け橋となるべく奔走した康一は昭和11(1936)年6月に盲腸炎の悪化で倒れました。ところがその看病での無理もたたってか、奈良二郎のほうが持病の丹毒に肺炎を併発して11月に先立ってしまいました。父の死の前月には妹の照子も出産直後に亡くなっており、愛する家族を二人も失くす不幸の中で闘病生活を続けた康一は、翌年後を追うようにして亡くなりました。28歳の若さでありました。
もし昭和8年に松花堂弁当箱の製作を奈良二郎が命じていたとしたら、湯木氏が挨拶に貴志邸に通ったのはたった4年弱のできごととなります。こうしてみると、なんだかWikiの投稿はモリアーティ教授のいたずらのような気がいたします。
それに私には、もうひとつ心配ごとがあります。実は戦前の大阪には、桜宮のほかに生玉町にも松花堂が存在したことが知られています。大阪で「浮瀬」と人気を分けた料亭「西照庵」(vol50に載せた番付では浮瀬の隣に並んでいます)の跡地あたり、実業家の田中吉太郎所有の庭園の中です。昭和13(1938)年9月号『武者の小路』の松花堂特集号によると、ここは元は浪速十人両替だった近江屋休兵衛の別荘だったそうで、夕陽閑渓と名づけられた広い敷地には、ほかにも閑月庵や残月檐、寰海亭などの建物がありました。大阪大空襲を受けて、こちらの松花堂は残っておりませんが、昭和11(1936)年刊行(戦後に覆刻もされています)の『数寄屋聚成4巻』に写真と図面が載っております。生玉町の松花堂には八幡の松花堂と同じく、茶室としては珍しく土間に3連のかまどが据えてありまして(桜宮のほうにはありません)、料理を作るにはもってこい。
また庭園史研究の大家の重森三玲によると、大阪・堀江の越井邸や京都・東山の浅野邸にも松花堂タイプの茶室があったそうです。松花堂昭乗の遺徳をしのんで、あちこちに松花堂を写した茶室が建てられたのかもしれませんね。
さあ、大変だ。もしかしたら湯木氏はどこかほかの松花堂と混乱して、まちがえてそっちに挨拶に行っちゃったかもしれませんよ。生玉町も堀江も店から近そうだし。Wikiの松花堂の項の執筆者の方々、ぜひ真相を明らかにしてください。
投稿者 webmaster : 10:07
2013年02月06日
料理本のソムリエ [vol.52]
【 vol.52】
松花堂の2つの箱をめぐる謎
やあ、ワトソン君! 前回のosechiのレポート、興味深く読ませてもらったよ。東洋の新年の風習の紹介は知的興奮をそそられたね。しかし僕としてはいささか不満が残らないでもないな。十字に仕切りの入った器といえばbentoについて触れないわけにはいかないだろう。ほら、あの松花堂弁当! これに知性と科学の光をあててみようじゃないか!
君は堅物だから東洋の芸術にはあまり関心がないかもしれないな。まずはじめに断っておくが、「松花堂弁当」は日本の江戸時代の僧侶にして当時を代表するカリグラファーの一人、松花堂昭乗にちなんだ器のことなんだがね、彼が住んだと言われる2畳あまりの草庵も「shokado」と呼ぶため、少々ややこしい。ここでは今も八幡市にある歴史的建築物のほうを「松花堂」、持ち主は「昭乗」、器は「松花堂弁当」と呼び分けることにしよう。正確さを期すことは、思考の整理に欠かせないからね。

実際、ときどきまちがった記述を見かけるが、松花堂弁当は昭乗が発案したものではない。彼が愛用していた十字に仕切られた箱を、弁当の器に転用したことからそう呼ばれているのに過ぎないんだ。じゃあ、もともとは何に使われていた箱なのかというと、これは残念ながら結論は出ていない。種入れだったり薬箱だったり絵の具箱だったり煙草盆だったりと諸説紛々だ。
ちなみに煙草盆というのは、東洋の喫煙具だ。キセル、火入れ、灰落としなどの道具セットを客前に運ぶためのトレイさ。まあ盆といっても物によって引き出しつきだったり、ぶら下げやすいようになっていたりするので、あまりそこにはこだわらないほうがいい。
この仕切りのある形の箱に弁当を盛ることを思いついたのは、日本を代表するレストラン、「吉兆」の湯木貞一氏と言われており、本人の証言もある。
証言A<その庵のなかに、薬箱にも、種箱にも、たばこ盆にも、弁当にもしたのでしょう、四角い箱で、深さは七、八センチ、なかを十文字に四つに仕切ったものがあったのです。(略)昭和のはじめに、松花堂のあるお寺が、これをおとき入れに使っていた、それを私が見てきて、これはいい、これに点心を入れて出そうとおもったのが、はじめです。それを当時の毎日新聞が<吉兆前菜>としてとり上げて、出してくれました。(略)松花堂にあったのは、ちゃんと四隅に金具が打ってあって、それはいいものでした。まんなかの仕切りは外せないようになっていました>『吉兆味ばなし』(1982)
証言B<昭和5年ごろ、京都と大阪の中間あたりに位置する八幡で、木津宗匠が釜をかけていらっしゃいました。私もそこへお招きいただきました。そこは、江戸時代初期の文人数寄者であった松花堂昭乗の庵で、金具つきの箱が五、六個重ねてあり、煙草入れや薬入れ、種入れなどの物入れとして使っていたのを見つけました。ああ、これはお弁当に使える、と思い、そのころはまだそうした道具を注文できる頃ではなかったのでアイディアだけで帰ったのですが、のちにそれを模して作らせ、使い始めたところ、大評判になりました。本歌には四隅に金具がついており、中に絵が描いてありました(本体256ページ参照)。が、それらをとり、蓋をかけるようにしたのは私のアイディアでした>『世界の名物「日本料理」』(1991)
これが彼が生前語った松花堂弁当誕生のいきさつだ。AとBの10年ほどの間に、忘れていた事実が浮かんできたのだろうか? それとも勘違いというノイズが紛れ込んだのか?
ところで証言Bに「本体256ページ参照」とあるだろう? この本『世界の名物「日本料理」』は豪華写真集『卒寿白吉兆』につけられたわずか50ページあまりの別冊にすぎない。ご指示通り、写真集のほうの256ページを開いてみるとしようか。
証言C<戦後のことでしたが、昭乗が住んでいた方丈で茶会があったときに、積んであった仕切りのある物入れ箱をふと見て、これは茶料理に使えると思い、一つお譲りいただいて帰りました。のちにやや深めにして蓋をつけて、黒漆の塗物として仕立て、大徳寺縁高の変わりに懐石のお弁当に用いたところ、あちこちでおほめいただいたものです。(略)四方に金具がついており、高さはいろいろでしたが、大きさは全部同じで重ねられるように作ってあり、内側に墨で盆石、梅の古木、雁などが描かれています。お譲りいただいたものは今も大切に保存してあります>『卒寿白吉兆』(1991)
なんたることだ! 戦後? 譲ってもらった? 別冊とはまったく話が違うじゃないか。編集者は不思議に思わなかったのかね?
湯木美術館元キュレーター、末廣幸代氏の『吉兆 湯木貞一 料理の道』(2010)には、Cの説が採用されている。もっとも戦後ではなく、なぜか昭和8年のこととなっているがね。
<昭和八年(1933)頃、湯木が現京都府八幡市にある松花堂昭乗(岩清水八幡宮の社僧・寛永の三筆/一五八二 ― 一六三九)の遺跡を訪れた時、部屋の片隅に重ねられていた茶色の四角い盆(松木地盆)に眼がとまり、料理の器に使えるのではないかと考え、その一つを分けてもらった。その時は煙草盆あるいは薬入れなどに使うものと聞いた>
ここに「松木地盆」とかっこ書きがあるのは、戦前の茶人、高橋箒庵の日記『萬象録』に「煙草盆 松花堂好松木地盆」が出てくるのを末廣氏が見つけて、それと同じ品と断じたからだ。だがね、茶道の世界では耳つきのまさしくトレイのような形の煙草盆もまた「松花堂好 煙草盆」と呼ばれているんだよ。それに例の256ページに写っている貞一翁が大切に保存していたという湯木美術館所蔵の煙草盆は、茶色の木地じゃなくて春慶塗りだ。松木地盆にこだわると、真実から目を背けてしまうことになるだろうね。
さて証言AとBとC、どれが湯木氏の真意だったんだろうか? 証言Aの「おとき」は寺で提供する簡単な昼食のことで、「松花堂のあるお寺」が舞台だ。いっぽうBは八幡の松花堂の庵で開かれた、木津宗匠のティーセレモニーでのこととなっていて、一見矛盾しているようにみえる。だがね、このAとBは恐らく同じ場所の同じ出来事を指している。
 大正時代に昭乗の事績を顕彰しようという機運が盛り上がり、忘れられていた彼の墓を守るために大正9(1920)年に泰勝寺という寺が建立された。そこに昭乗ゆかりの閑雲軒という茶室が再現され、ここを会場にして大正11(1922)年から毎年5月17日頃に、松花堂会という集まりが開かれている。この松花堂会の開催に尽力したのが、武者小路流の茶人である木津宗泉だ。恐らく湯木氏は閑雲軒と松花堂とをごっちゃにしたんだろうね。
大正時代に昭乗の事績を顕彰しようという機運が盛り上がり、忘れられていた彼の墓を守るために大正9(1920)年に泰勝寺という寺が建立された。そこに昭乗ゆかりの閑雲軒という茶室が再現され、ここを会場にして大正11(1922)年から毎年5月17日頃に、松花堂会という集まりが開かれている。この松花堂会の開催に尽力したのが、武者小路流の茶人である木津宗泉だ。恐らく湯木氏は閑雲軒と松花堂とをごっちゃにしたんだろうね。
まあ、世間一般で知られているのはだいたいこんなところかな。だがね。実のところ、僕は湯木氏が十字に仕切られた箱を見つけたのが、昭和5年だろうと戦後だろうとどちらでもいいんじゃないかと思ってる。
 というのはね、まったく違う由来がもう一説あるんだよ、ワトソン君! 『専門料理』1993年10月号では、ノンフィクション作家の笠井一子氏が、京都の漆器商「象彦」の西村英太郎会長から、大正初期に会長の父親が、松花堂にあった箱を写して製作したという逸話を聞きだしているのさ。
というのはね、まったく違う由来がもう一説あるんだよ、ワトソン君! 『専門料理』1993年10月号では、ノンフィクション作家の笠井一子氏が、京都の漆器商「象彦」の西村英太郎会長から、大正初期に会長の父親が、松花堂にあった箱を写して製作したという逸話を聞きだしているのさ。
<大阪に加賀正ゆう株屋はんがあるねん。その時うちの親父が呼ばれて行っとった。その加賀正太郎ゆう人が株で儲けて大きな家建てて、その時にちょっとお客さんするのに象彦さん何か(漆器を)考えてくれへんか、と。その自分、親父は松花堂へよう行ってて、西村はんにこれ(松花堂弁当)見せてもろて>
これは失敬。関西弁なうえに、ちょっと言葉が足りないので捕捉しながら説明しようか。なにしろ二人のMr.西村が登場してややこしい。
発注者の加賀正太郎はニッカウヰスキーの筆頭株主で、芸術とスポーツに理解のある青年実業家だ。留学中にはわがロンドンのキュー・ガーデンにも足を延ばしたことのあるそうだから、どこかですれ違っているかもしれないぜ。彼の新築の家とは大正6(1917)年に最初の建物が完成した大山崎山荘を指すと思われる。八幡からみて宇治、桂、木津の3本の川を挟んだ対岸は大山崎で、地理的にも近い。
そして「西村はん」こそが、松花堂と昭乗の遺品を守り続けた八幡の郷土史家、西村芳次郎だ。河川の洪水から松花堂を守るために明治24(1891)年に今の場所に移した、国学者の井上忠継の息子であり、当時の松花堂は彼の邸内にあったんだ。
松花堂弁当誕生のいきさつは、西村英太郎会長の『漆器の四季』(1981)でも紹介されていて、八幡市の円福寺の裏にあった西村家(象彦のほう)の松茸山の管理を、芳次郎氏にお願いしていたために二人は昵懇だったそうだ。当時の松花堂には<角形で四隅に止め金具のある溜塗で、内側を四つに仕切り、墨絵で四季草花、水仙、柳つばめ、菊、芦、小家禽の絵が書かれた器>があり、これに蓋をつけて来客用点心に用いていたが、<西村さんと相談して寸法を考案加減して、「松花堂縁高」として作ったのが始まり>だとしている。
 縁高とは折敷よりも縁が高く上がった塗りの容器を指す言葉で、お昼の点心や菓子を盛る。「大徳寺縁高」がよく知られているが、こちらには仕切りがない。確かに戦後でもちょっと昔の本を見ていると、松花堂弁当ではなく松花堂縁高と書かれているものを見かける。『うまいもん巡礼』(1956)や、『舌鼓ところどころ』(1958)のようにね。
縁高とは折敷よりも縁が高く上がった塗りの容器を指す言葉で、お昼の点心や菓子を盛る。「大徳寺縁高」がよく知られているが、こちらには仕切りがない。確かに戦後でもちょっと昔の本を見ていると、松花堂弁当ではなく松花堂縁高と書かれているものを見かける。『うまいもん巡礼』(1956)や、『舌鼓ところどころ』(1958)のようにね。
 寸法をどう“考案加減”したかについては、『専門料理』のインタビューによると、はずせば底にぴったりはまるような蓋をつけ、さらに隅金具が小さすぎたので大きな金具に変え、背も高くした、のだそうだ。もっともこのインタビューでは芳次郎氏が持っていた本歌には蓋がなく、八寸に使っていたと証言していて、これまた微妙に異なっている。人間の記憶というものは実にあやふやで移ろいやすいものだねえ。『漆器の四季』には<最近、この器と同じものが知人の宅にあり、それには瀧本盆と箱書して八寸用と付記されていた>とあるので、この本の執筆から10年経つ間に元から八寸用だったと思い込んでしまったのかもしれない。なにしろこの瀧本盆、くだんの知人から譲ってもらったようで、『専門料理』では象彦の所蔵として写真が載っているからね。
寸法をどう“考案加減”したかについては、『専門料理』のインタビューによると、はずせば底にぴったりはまるような蓋をつけ、さらに隅金具が小さすぎたので大きな金具に変え、背も高くした、のだそうだ。もっともこのインタビューでは芳次郎氏が持っていた本歌には蓋がなく、八寸に使っていたと証言していて、これまた微妙に異なっている。人間の記憶というものは実にあやふやで移ろいやすいものだねえ。『漆器の四季』には<最近、この器と同じものが知人の宅にあり、それには瀧本盆と箱書して八寸用と付記されていた>とあるので、この本の執筆から10年経つ間に元から八寸用だったと思い込んでしまったのかもしれない。なにしろこの瀧本盆、くだんの知人から譲ってもらったようで、『専門料理』では象彦の所蔵として写真が載っているからね。
さあて第二の証人の登場だ。ワトソン、君ならどう解釈するかね? 僕の推理はこうだ。象彦が大正時代に作った写しは昭和に入って、松花堂の西村邸や閑雲軒の泰勝寺でも使われるようになっていた。湯木氏が見つけたのはそれだったとすれば、矛盾はないだろう?
そもそも証言Aで湯木氏が見た器は深さ7、8cmで金具つきとあるが、現在、松花堂庭園・美術館に伝わっている「松花堂好 四つ切塗箱」は四隅に金具がなく、高さも3.8cmしかない。湯木氏が譲ってもらったという湯木美術館所蔵のものには大きい止め金具がついているが、高さは3.5cmしかない。
ところが西村芳次郎はもっと深くて金具つきの箱も所蔵していた。昭和14(1939)年アトリエ社刊の『松花堂』に載っている「松花堂好膳」がそれだ。この年の正月に亡くなった西村氏を追悼する『武者の小路』(昭和14年4月号。発行は木津宗泉の息子、乙象だ)で、井川定慶がはじめて西村邸を訪ねた折に“松花堂好みのお重”に蔬菜、魚をとりまぜた茶料理と吸い物椀でもてなされたと述懐している。またそれから5号後の木津宗泉追悼号では、泰勝寺の堀尾海応住職が<懐石料理の事に就いても中々の大通であつた。当山の縁高料理は宗匠に何時も賞められてゐたもので、湯葉の油揚が御好きで前菜には殊によいとの事で「黄金の樋」と銘をつけられた>と木津宗匠の思い出を語っている。このお重と縁高料理、同じ器の気配がしないかい?
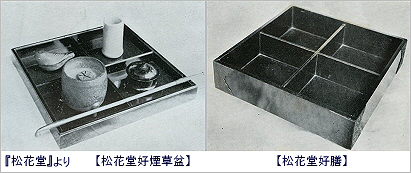
アトリエ本の「松花堂好膳」の写真には残念ながら大きさが書かれていない。だが、幸い『茶道雑誌』1974年8月号に、塚本松花堂美術館と名が変わった時代の訪問記である「松花堂昭乗の遺跡を訪ねて」が掲載されている。
<ついでに野添さんは私共に馴染深い松花堂弁当の箱(写真5)を出してみせて下さいました。前の箱よりやや小型で深く、やはり溜塗で中が四つに敷ってあり、外角には金鍍唐草模様の金具が打ってあります。蓋が付いており、昭乗が付近の農家で使っていたものを見て好んだということです>
見たまえ! 写真5のキャプションは「松花堂弁当箱(本歌)27.5cm角 深サ6.7cm」とあって、アトリエ本に載っているのとそっくりで、こちらには蓋も写っている。管理人の野添氏は、この器に昭乗自身がご飯や料理を盛ったと信じていたようだがね。
それじゃあ西村芳次郎が象彦の西村氏に見せた正真正銘の松花堂弁当の本歌は今どこにあるのか、だって? いい質問だ、ワトソン!
昭乗の死後100年ほどして八幡を訪れた青木凡鳥の延享3(1746)年5月27日の記録に<待合のたはこ盆、滝本好ミ、四角にして薄く、折敷程有而、中を十文字ニ仕切を入、上の縁何茂唐戸面ニ而、組天井のことし、一仕切の内ニ滝本の墨絵有、春慶塗少はげて、絵委敷見へ不申候也>とあり、十文字の春慶塗の箱がかつて松花堂にあったのはまちがいないようだ。しかし現在松花堂庭園・美術館に伝わっている「松花堂好 四つ切塗箱」は近代の作品であって、昭乗の時代のものではないとされている。そもそも湯木美術館にも象彦にも、さらにはたばこと塩の美術館にも同じような形の煙草盆(こちらの高さは3.4cm)が所蔵されているところをみると、どうもあちこちで写しが作られていたらしい。
松花堂は今でこそ八幡市立の松花堂庭園・美術館となっているが、戦後は西村家から迫田盛太郎、さらに塚本素山と所有者が二転三転している。その間に伝世品の詳細はわからなくなったのだろう。
一方手放した西村大成氏は、茶室研究で知られる中村昌生氏の松花堂に関する論考に感激して、彼を自宅に招いて次のように語ったという。昭和40年代の話だ。
<私に甲斐性がなく、とうとう手放さねばならなくなり先祖の名を汚して恥ずかしい思いをしています。世を忍んで隠れ住んでいるのですが、松花堂に対する思慕の情は変わりません。(略)松花堂の遺構だけでなく、それに添っていたすべてのものも譲り渡してきました。ただ一つこれだけは、と手放さなかったものがあります。この頃流行っている松花堂と呼ぶお重ですよ。あれの本当の原形、昭乗が身辺で使ってたもの、これだけは今も持っているんです。今日はそれに家内の手料理を盛って、召し上がって頂くことにしました。今の私の出来る唯一のおもてなしです>『数寄屋と五十年』(2007)
中村氏は後日、西村大成氏が黒谷の山内で托鉢をしていると人づてに聞いたが、その消息は知らないという。もともと滝本坊の僧侶だった昭乗の遺愛品だ。一介の老僧の手元に残ったのだとしたら、それはそれで愉快じゃないかね?
投稿者 webmaster : 16:15
2013年01月21日
料理本のソムリエ [vol.51]
【 vol.51】
おせちって仕切りが大事だよね
はっ! 気がついたらもう2013年だ! カレンダーが新しくなってるよ! 世界の終わりだからとパッと景気よく使っちゃった人や海外のパワースポットまで避難した人たちの怨嗟の声で満ち溢れるかと思ったら、セの字もありません。みんな忘れっぽすぎるよー。
日本人って執念深くないというか、過去のニュースをすぐに忘れちゃいますよね。正月といえば2年前、ネットで注文したら見るも無残にスカスカしたおせちが届いてせっかくのお祝い気分がぶちこわしになったという騒ぎがありましたね。みんな覚えてる?
あの事件は、当時もてはやされていた共同購入割引サイトからの販売だったり、社長がツイッターやブログで宣伝していたのをネタに2ch住民がかみついたり、グルメサイトに上がった苦情のレビューが管理者の手でどんどん消されていったりと、ネットがらみの話題が豊富だったために、あれほどの大騒ぎになったのですが、写真と中身が違うというクレームの本質はお見合い結婚の時代から目新しいことではありません。
報道によるとキャビアがランプフィッシュの模造品になったりシャラン産鴨が国産になったりカマンベールがプロセスチーズになったりといった明らかな質的劣化もあったようですが、おせちの盛り込み作業写真をネットにアップしてアピールしていたくらいですから(ところがスタッフが普段着だったので、非衛生的だとそれがまた問題になったのですが)、初めから詐欺を働くつもりだったとも思えない。一番の問題は、「どうせよそから購入する出来合いの食材を詰め直すだけだろう」という安直な姿勢と見通しの甘さと思われます。焼き鳥居酒屋カフェ(どんな業態なんだ…)が普段出している商品とおせちとでは、まったく要領が異なるのに参入するなんて素人考えで稚拙だったわけですが、そもそもこの店はなんでこんな失敗をしでかしたか、ということに対する考察は見かけませんでした。
当時の報道では、100個販売するつもりだったが好評につき受注枠を500個に増やしたため、仕入れが間に合わなかったせいと説明されていました。これってただの言い訳ですよねえ。普通なら間に合わないことがわかった時点であせってなんとかするよねえ。
確かに年も押し迫ってから業務用品を大量に追加注文するのはむずかしいでしょうけど、ちまたに完成した正月料理があふれかえっている時期ですから、足りない分は築地にでも行って蒲鉾だのくわいだのきんとんだのを買って埋め合わせれば、なんとか形になったはず。見本写真と料理が異なった点は断り書きのひとつも入れておいて、奮発して見た目に豪華に仕立てさえすればあそこまで大きな騒ぎにはなりませんよね。なんで「少しずつ盛りつける量を減らせばなんとかごまかせるさ」と思っちゃったのか。少しずつどころかあんなにスカスカになるまで足りなくなったわけですが、なぜそれが予見できなかったと思われますか?
この会社の最大の失敗は容器を変更したことなのです。販売数が5倍に増えたために用意できなかったのか、はたまた初めから発注ミスしたのかはわかりませんが、ネットに上げられていた見本写真によりますと、お重に9つの間仕切りを井桁に組んでそこにぴったりはまる角皿に料理を詰めています。ところが実際に使われていたのは十字の4つの間仕切りのものでした。それなのに角皿どころか、お弁当用の銀ホイルのカップすら満足に用意していません。
皿がなければ当然のことですが、仕切りの数が減っただけでも箱に入る量はぐーんと増えます。素人にはそこがピンとこない。箱のサイズは同じ7寸だからそんなに変わらないだろうと、あてずっぽうで量を見込んでいて、実際に詰めている途中でぜんぜん足りないことに気がついたが後の祭り…。恐らくこの辺りがことの真相でしょう。
予定していたおせち料理は33品。9区×3段に詰めるはずが4区×3段に変わったということは、33÷12≒3で、ほとんどの区分けの中に料理を3種類ずつ盛り込むことになります。盛り合わせは難易度が高く、バイトの素人には手に負えません。皿もはまっておりませんから、傾ければ料理が端に偏るのは目に見えています。単品を個別に盛っているときよりも、盛り合わせた料理は傷みやすくなります。おせちを甘く見すぎです。
 こんなにおせちについて熱弁をふるっているのは(って。このブログ、いつでも無駄に暑苦しいか…)、おせちは取材するほうも大変だったから思い入れもひとしおなのです。デパート販売のちらし用に見本を作っている店ならいいのですが、限られた数を予約のみで作っている店は、とうぜん31日にならないとできあがりが準備できない。つまり撮影が大晦日、掲載は翌年の新年号になるってわけです。私はたまたま家族旅行が北陸方面だったカメラマンに頼み込んで、雪の金沢で早朝5時におせちを取材いたしましたですよ。帰りには近江町市場で年末セールのカニを主婦と取り合ったりして、それはそれで楽しかったですけどね。二年参りのラッシュに巻き込まれて身動きとれなくなる年越し蕎麦の現地ルポと並んで、酷な取材のひとつでした。
こんなにおせちについて熱弁をふるっているのは(って。このブログ、いつでも無駄に暑苦しいか…)、おせちは取材するほうも大変だったから思い入れもひとしおなのです。デパート販売のちらし用に見本を作っている店ならいいのですが、限られた数を予約のみで作っている店は、とうぜん31日にならないとできあがりが準備できない。つまり撮影が大晦日、掲載は翌年の新年号になるってわけです。私はたまたま家族旅行が北陸方面だったカメラマンに頼み込んで、雪の金沢で早朝5時におせちを取材いたしましたですよ。帰りには近江町市場で年末セールのカニを主婦と取り合ったりして、それはそれで楽しかったですけどね。二年参りのラッシュに巻き込まれて身動きとれなくなる年越し蕎麦の現地ルポと並んで、酷な取材のひとつでした。
今でこそデパートだのスーパーだのでいろいろなメーカーのおせちが販売されておりますが、はるか昔は料理店が予約のみを受けるもので、それもごく限られたお得意さんに対する内々のサービスでした。なぜか? おせちを詰めるお重は店が用意するのではなく、お客さんからの持ち込みが一般的だったからです。
そもそもおせちは家庭の主婦が正月の間だけでも台所に立たずにすむよう、年末のうちにまとめて作る料理ですよね。とはいえ、それすらできないほど忙しい家となると、黒豆だの昆布巻きだのを外から買ってきて、おうちのお重に詰めて済ますわけです。ところが立派な資産家になるとそれでは面目が立たないので、料理店に頼むという裏技が昔もありました。しかしお重の大きさは各家庭で違いますから、請け負った側はあらかじめ値段のつけようがありません。実際に詰めてみて初めて請求書が書ける商品では、親しいごく限られたお得意さんしか相手にできません。業務用の使い捨ての杉板の折箱に詰めて、カラー写真を撮ってちらしを刷って予約をとって、保冷剤つきでクールの宅配便にのせて…なんて販売方法は最近のものですよね。
 本来の塗りのお重には、間仕切りなんかありませんでした。ですからせいぜい葉蘭で区切るくらいです。それが仕切りの入った市販の箱を使うことで、盛り込み作業が簡単になったため、手がける料理店は格段に増えました。
本来の塗りのお重には、間仕切りなんかありませんでした。ですからせいぜい葉蘭で区切るくらいです。それが仕切りの入った市販の箱を使うことで、盛り込み作業が簡単になったため、手がける料理店は格段に増えました。
何の仕切りもない箱にぎっしりと料理を詰めるには、まんぜんと行なっていてもうまくいきません。仮想の仕切りがあると見立てて、それをめやすに詰めていくという高度な技が必要でして、昨年末に出版された『東京會舘おせち料理と節句料理』にその一端が紹介されています。ちなみにこの本、タイトルに「おせち」とあるので書店さんが家庭料理のコーナーに分類している例を見かけますが、内容はどちらかといえばプロ向け。東京會舘の鈴木直登料理長は今や少なくなった東京料理の後継者でして、つけ板を使った蒲鉾のつくりかたなど、関西の料理人さんはご存知ない(東京の料理人さんだって若い人は知らない)珍しい技法が紹介されています。詰め方も、正確に切り出した蒲鉾をきっちり詰めるといった関東のおせちの特徴が見られます。
今のおせちは色とりどりの料理を少量ずつ盛る「散し盛り」が主流です。こちらはどちらかというと関西の料理店が得意としています。もっとも亡くなった京都の「菊水」の板前新三さん(戦前、法善寺横丁にあった名店「みどり」の元料理長でもあります)によりますと、京都でも昔は「流し」といいまして、同じ料理がずらりと一列に並ぶだけのずっとシンプルな盛りつけだったそうです。
おまけに中京区あたりの問屋さん相手に、正月早々出張仕事をしたとか。こうした大きな商家には、元日には親戚縁者はもちろん、かつて奉公していた雇い人やお得意先など大勢の人が訪れます。おせち料理を詰めたお重は床の間にででんと飾られておりまして、お年始にきたお客さんに取り分けてお出しする。そうして減ったらすぐに台所に引っ込めて、料理人が補充する(確かに流し盛りは取り分けやすい反面、減ってくるとモロ分かりで格好悪いですもんね)。そうしたらまた床の間に飾る…の繰り返し。
ちなみにそんなお年始客がわんさか訪れるのはわずらわしいからと、小説家やら政治家やらは家を留守にして、ホテルや旅館で正月をのんびりすごすというのが戦前から行なわれていました(さすがに海外へ、とまではいきませんが)。庶民は庶民で有名神社へ初詣するなんて習慣がありますが、これは鉄道や市電が発達してからだそうでして。正月の在り方というのは伝統行事のようでいて、ずいぶん変化したもようです。おせちを家族で楽しむいろいろ詰まった豪華な食事ととらえるのも、最近の傾向なのですね。
多品種化が進んだうえ、数を販売するようになったおかげで、日本料理店にとっておせちの仕事は段取りを「仕切る」のもとっても大切なことになりました。どでかい厨房があってたくさんの冷蔵庫があって、さらに空調管理された専用の広い盛りつけ場があるならいざしらず、普通の料理店では通常の施設を使っておせち料理を仕込んでいます。ガスの火口の数が限られますから、一度にたくさんの種類の料理は仕込めません。日持ちのきくものから順にパーツを作っていって、最後に一気に組み立てなければなりません。調理前の材料が冷蔵庫を占領していては仕舞えませんから、仕入れも計画的に進めなければならず、それこそ途中で販売数の大幅な変更なんてできっこありません。「専門料理」2007年12月号は、実際のスケジュール管理について取材していますが、料理店の主人がそろそろおせちにとりかからねば、と考え始めるのはなんとお盆明けから。確かに栗の蜜煮なんぞは秋のうちから仕込まねばなりませんしね。

私が昔聞いた料理人さんの話だと、鍋の大きさにもよりますが、通常規模の割烹では30個くらいが無理のない範囲だとか。100個というのは利益が出にくい微妙な個数で、それなら専用厨房を用意したりPBで工場で作ってもらったりしてもっと大きく商ったほうがいいといわれています。先の焼き鳥居酒屋が500個に増やしたというのは経営判断としては正しいのですが、それだけの量を用意し、組み立てる技量はとてもなかったということでしょう。
一番大変なのは盛り込みでして、空の器をずらありと並べるスペースと人数が必要です。30日には徹夜作業となるのに、おせちを販売した店の主人は、万が一食中毒が発生したりしないだろうかと、3が日の間も心配でおちおち寝ていられないともききます。傷まないようにするには既成品のようにしっかりと濃い味をつけてしまうのがひとつの手段ですが(もっと手っ取り早いのは保存料を使うことなのでしょうが)、梅型にむいたニンジンひとつとっても、梅酢を使ったり、だしは傷みやすいので酒で旨みをつけたり、加熱時間を普段より長めにしたりと、工夫を凝らすのが料理人の意地だったりします。
ちなみに私がはるーか昔に撮影したおせちは、予備として作ってあったものでした。注文の取り間違いやら先方の勘違いやらで、大晦日当日に数が合わないことがあるので、念のため余計に作っておくという店すらあるんです。それでも足りなくなって、帰郷するスタッフにもたせてやるはずのぶんを泣く泣く供出した、なんて話もあります。手作りしている店では売上げは、立ってもさほど儲からないという話もよくききます。
もっともネット通販を見ていたら、最近は冷凍技術が発達しているせいか松の内をすぎてもおせちが販売されているんですね…。破格なバーゲン値段で。なんだか閉店まぎわに売られているお弁当みたい。元旦でもコンビニどころかスーパーだって普通に営業しているし、世の中めりはりがなくなってきましたね…。これまた時代の流れでしょうけど。
投稿者 webmaster : 09:46
2012年12月27日
料理本のソムリエ [vol.50]
【 vol.50】
ミシュラン?なにそれ?美味しいの?
いやあ、もうクリスマスだなんて一年は早いですねえ。いつもの年は「仕事ですよ、仕事!」っていう堂々たる言い訳が利きましたが、今年は何の因果かクリスマスイブが連休の最終日。旅行先で聖夜をお迎えの方もいらっしゃったことでしょうね。「みんなハッピーってわけじゃないんだってばクリスマス!」
ところがですよ、どうもクリスマスどころじゃないそうじゃありませんか。何でも21日から23日にかけて大異変が起きて世界が終わるという耳より情報が飛び込んできました。マヤ文明の長期暦が2012年12月21日で終わっているのがその証拠だそうで。なあんだ、じゃあ原稿を書いても無駄じゃない。この連休はコタツでごろごろしてよっと。ぐう。
そんなこんなで今26日です。なぜだっ。
 クリスマスはレストランにとって一番の書き入れ時で、仕入れとメニュー内容、仕込みやオペレーションをどうするかは、皆さん頭を悩ませるところ。そこに焦点をあてた1990年12月号の月刊専門料理のクリスマス対策特集は、折りしもバブルがはじけつつあった微妙な時期だったこともありまして、参考になると喜ばれました。
クリスマスはレストランにとって一番の書き入れ時で、仕入れとメニュー内容、仕込みやオペレーションをどうするかは、皆さん頭を悩ませるところ。そこに焦点をあてた1990年12月号の月刊専門料理のクリスマス対策特集は、折りしもバブルがはじけつつあった微妙な時期だったこともありまして、参考になると喜ばれました。
そんな私はといえば、クリスマスにレストランに行ったことなんて…行ったことなんて(涙目)…おお、思い出した! ありましたよ、雑誌の先輩たちと一緒に(笑)。「ホントだ、同じ鹿でも仕入れを確保しやすいニュージーランド産だっ」「どのテーブルも同じ料理が同じタイミングでサービスされている!」なんて大興奮。いま考えたらすごく場違いなグループだったと思いますが、なあにカップルなんて周囲なんか目に入りませんてば。
もっともどのカップルも幸せとは限りません。クリスマスに奮発したフランス料理店でうまくふるまえず、それがトラウマになって大衆料理以外は認めないと心に誓ったり、逆にいつか見返してやるとモーレツに知識を溜め込む人たちがいるようです。後者のガリ勉タイプは料理以外の、あの店のオーナーはどこだとか業界の構造だとか「俺しか知らない裏話」が好きですね。芸能ゴシップ好きの中学生みたい。
不思議で仕方ないのはそうしたガリ勉タイプのグルメさんの間に、「自腹で食事をしないと評価ができない」という主張がみられることです。そりゃ身銭をきれば身につくことも多いでしょうが、書評や映画評論や音楽評論や演劇評論は、みんながみんな自分のお金を払って本を読んだり試写会に行ったりアルバムを買ったりチケットを取ったりしているのでしょうか…。「自分はこんなにお金をつぎこんだ」「こんなにたくさんの店で食事した」というのがご自慢の方たちは、AKB劇場に通えばいいのに。
こうして誕生した自称グルメさんたちは、「こんなに料理にうるさい俺ってすごくね?」という性格のようにお見受けします。「料理店が好き」「食べることが好き」「いま食べている料理が好き」なんじゃなくて「いま料理を食べている俺が好き」。普段は奥さんに頭が上がらなかったり、後輩にうっとうしがられたりしている人も、料理店に行けば下にもおかず顔を立ててくれますから、そんなナルシストでも気持ちよく過ごせますしね。
ただし、彼らは自分より手厚くもてなされている奴が世の中にいるなんて我慢ならない。たまたま隣に座っている人が店のご贔屓筋で、料理長が挨拶にきた挙句にサービスの1品でも出してもらっていたのに気づいた日には、不倶戴天の敵に会ったような目で睨みます。背中越しに。その場では「お、おいしかったよ」と震える声で会計をすませて、すごすごおうちに帰ったとたんに鬱憤のすべてを恨み日記にぶつけるわけです。今はブログとかグルメサイトとかあってすぐにアップできて便利ですね。
他人にご馳走されるといくらかかったかわからない、という主張はまだ納得いくのですが(ただ、値段がわかっても満足度は本人の懐具合や胃袋の大きさにも左右されるから、絶対的な指標にはならないとも思うんですけどねえ。「この本は2000円なのに500ページもあってすばらしい」っていう書評はあんまり見当たらないよねえ)、さらに覆面調査でないとダメとおっしゃる方もいらっしゃいます。顔見知りのお客に出す気合の入った料理では、その店の真の実力はわからない、というご主張のようです。
これは3割くらい真実ですが、7割くらい見当はずれです。正直な話、有名ひょーろく玉…じゃなかった評論家が来るからといって、そうそう特別な料理はできません。そんな臨機応変なシェフは、そのことだけでも実力がある証拠です。とくにチームプレイで仕事をしている高級フランス料理店ともなると、急にレベルを変えることはできません。せいぜいお高い食材の盛りをよくするとか、おまけの一品がつくとか、お値段を勉強するくらいですかねえ。あ、有名評論家はただで飲み食いするそうだから、値段は関係ないか。
料理店がヒョーロン家様に便宜を図って、都合のいい記事を書いてもらっている、なんて話はステマが話題になるはるか以前から言われていることですが、そうでもしなきゃ人気を維持できない店は早晩だめになると思うんですが…。掲載料をとって店を載せるガイドブックってのも昔からある手法ですが、情報過多の時代ではもはや通用しませんよねえ。
そもそも「ステマを告発!」なんて息まく人たちも、実は特別待遇を受けている(に違いない)ヒョーロン家諸氏がうらやましくって悔しいんじゃないかしら、ってうがちたくなります。ナルシストというのはひがみっぽくて傷つきやすいものでして、自分が特別扱いされない現実を直視したくないし、顔を知られると陰であることないこと好き勝手に書けなくなるし、直接反論されるのが怖く怖くて仕方ない。その点、匿名なら安心安心。
「俺ってお世辞を言わない本音評論家だからさ」、なんていうのもありますね。内弁慶のまちがいでは? お店のことを思ってのきついアドバイスなら直接その場で伝えてあげてください。ホントに偉いのはたとえどんなに贔屓されたとしても、面と向かって堂々と欠点を指摘できる人で、そういう評論家なら煙たがられても尊敬を集めると思いますよ。
これから料理ヒョーロン家を名乗ろうとする人は、年間に通う店の数や妄想たっぷりのギョーカイ裏話で煙に巻くのではなくて、その視点の鋭さと分析の正しさ、表現力を売りにしてのし上がってほしいですね。なにせほとんどの人たちは、読者に納得してもらうのは大変だからでしょうか、てっとり早く誰かを貶めるものばかり。叩くことで権威づけして優位に立とうとするわけですね。「塩っぱい」「冷めている」「だしがうすい」「感動しない」…。文句をつけるのは駄々っ子だってできますし、異論に対しては「そりゃ、チミの感覚が鈍いからだよ」と開き直ればよろしい。辛口毒舌なほど偉いなら、このブログなんてそりゃもう相当なもんです(笑)。
落語の「子ほめ」からわかりますように、実は大変なのはほめるほうでして、第三者にもそのよさを納得してもらうのは難しいことです。それでは彼らはけなしてばかりでは芸がないのでほめるときはどうするかというと、誰から見ても問題なさそうな老舗か、逆にまだ誰も知らない新店をほめます。これなら反論される心配はありませんし、「こんな老舗に常連の俺ってすごくね?」「こんな店をもう知ってるなんて俺すごくね?」という自尊心を満足できます。そうしておいて、みんなが通うようになったところで、「あそこの店は味が落ちた」とけなします。上げて下げて二度おいしい。
こうしてみると3段階の格付だけで勝負するミシュランガイドというのは、それなりに良心的かつ言質をとられにくい賢いシステムなのがよくわかります。ミシュランの調査手法については、元調査員だったパスカル・レミが『裏ミシュラン―ヴェールを剥がれた美食の権威』で明らかにしています。ミシュランガイドに似せた装丁にしたため無駄にでかい文字組のこの本、邦題から連想するような内部告発的暴露本というよりは、芸能記者の語る裏話的な内容です。覆面調査といっても食事後はシェフに話を聞いたりすることも多いようで、身分を明かすのはかまわないようです。むしろ身分を明かして水戸黄門のような快感を味わってまして、大丈夫かしらとこっちが心配になるほど。もっとも調査員というのはかなりの激務で(レストランだけでなくホテルの格付もするわけですからずっとドサ回り)、そんなちょっとした楽しみがないとやっていられないようで、同情いたします。
意外と地味なミシュランの調査がいかにブランドを勝ち取ったか、その歴史と編集方針の変化については、最近『三つ星と世界戦略』が出版されました。またミシュランを生んだフランスの食ジャーナリズムについては『フランス料理と批評の歴史』が力作です。
これらの本にも書かれておりますが、ミシュランというのはタイヤメーカーなので、その出発点はマイカー族のための旅行ガイドでした。ですから移動先で快適にすごすために、という視点で編集されておりまして、その店がどこにあるか知っていないと掲載ページにたどりつきづらく、料理人名から検索できず、ネットで公開される前は不便なものでした。バブル真っ盛りの頃には、フランスからシェフを招聘しようとしているホテルの広報だか代理店だかから、「○○というフランス人シェフの星の数を教えてくれ」なんていう問合せが何度か会社にかかってきましたっけ(それも有名人ならいいのですが、どっかの田舎の1ツ星シェフばかりで)。どうしてそんなことも知らずに日本に呼ぼうとしたんだろう?
 一方、作り手に焦点をあて、著者独自の視点から格付するガイドとして一世を風靡したのがアンリ・ゴーとクリスチャン・ミヨの共著「ゴー・ミヨ」です。保守的なミシュランに対して、ヌーベルキュイジーヌという料理界の動きを評価したいというジャーナリストらしい主張で始まったものの、二人は途中で袂を分かちます。アンリ・ゴーは一人でガイドを出版し、88年には小社から『フランスのレストランベスト50』として翻訳されましたが、21世紀を迎える前に亡くなりました。一方クリスチャン・ミヨのほうはゴー・ミヨの出版を続けますが、ヌーベルキュイジーヌブームの終焉とともに編集方針の主軸を失ってしまいます。書き手の顔の見えないミシュランの無敵さはここでも証明されています。
一方、作り手に焦点をあて、著者独自の視点から格付するガイドとして一世を風靡したのがアンリ・ゴーとクリスチャン・ミヨの共著「ゴー・ミヨ」です。保守的なミシュランに対して、ヌーベルキュイジーヌという料理界の動きを評価したいというジャーナリストらしい主張で始まったものの、二人は途中で袂を分かちます。アンリ・ゴーは一人でガイドを出版し、88年には小社から『フランスのレストランベスト50』として翻訳されましたが、21世紀を迎える前に亡くなりました。一方クリスチャン・ミヨのほうはゴー・ミヨの出版を続けますが、ヌーベルキュイジーヌブームの終焉とともに編集方針の主軸を失ってしまいます。書き手の顔の見えないミシュランの無敵さはここでも証明されています。
いま日本で見られる料理ガイドはおおむねゴー・ミヨのスタイルですが、ジャーナリズム魂の代わりにお客様気分と業界人気取りが詰まった「俺好みの店ベストテン」の域を出ておりません。『東京いい店うまい店』のように複数の覆面調査員に基づくものもありますが、各店の紹介文には調査員の主観と意見があふれておりまして、むしろ不安を掻き立てられます。どうして日本ではミシュランのような一歩引いた格付が見られないのでしょう。
そもそも日本には「見立番付」という立派な格付システムがありまして、これはミシュランなんぞよりもずっと古い。相撲番付に見立ててランク付けするもので、これは評価システムというよりも「給食で一番好きだったものランキング」と同じような、一種の遊びですね。vol45で紹介した「浪花みやげ」にもこうした番付が収録されております。
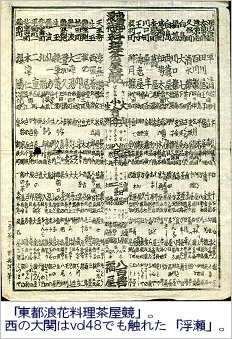 またもう少し批評色の強い「評判記」という伝統もあります。岩波新書の『江戸名物評判記案内』によりますと、上上吉という日本独自の表示方法で、役者から学者、小説、名物までありとあらゆるものにランク付けをいたしました。講評ものせているのが番付と違う点ですが、欠点を指摘する「悪口」担当者がいれば、支持を表明する「贔屓」がいて、全体を総括する「頭取」が仲裁するというふうに役割分担のある架空対談形式をとります。なあなあで丸く済ませるのが日本的だ、と思われるかもしれませんが、万人を不快にさせずに文章力で納得させる、高等技術だともいえます。
またもう少し批評色の強い「評判記」という伝統もあります。岩波新書の『江戸名物評判記案内』によりますと、上上吉という日本独自の表示方法で、役者から学者、小説、名物までありとあらゆるものにランク付けをいたしました。講評ものせているのが番付と違う点ですが、欠点を指摘する「悪口」担当者がいれば、支持を表明する「贔屓」がいて、全体を総括する「頭取」が仲裁するというふうに役割分担のある架空対談形式をとります。なあなあで丸く済ませるのが日本的だ、と思われるかもしれませんが、万人を不快にさせずに文章力で納得させる、高等技術だともいえます。
残念なことにこうした伝統が失われた挙句に、ネットの世界は自称グルメさんたちのレビューで一杯。そこにきて本家の黒船襲来です。日本版ミシュランを叩くことで溜飲を下げるとともに、相対的に自分の地位を高く保とうとする人もいますが、デートにせよ接待にせよ、世の中の圧倒的な人たちは「星がたくさんついている有名店に行きたい」わけでして、「なんとかいう料理ヒョーロン家がほめている知る人ぞ知る店」っていうのに対するニーズはそんなに高くありません。どうも勝負は見えている気がします。
じゃあ、そんなミシュランがすばらしいかといいますと…あははははのは。日本版のミシュランはよせばいいのに画質の悪い写真と店の中途半端な紹介文という蛇足がついてますからねえ。フランス料理のシェフたちが、若い頃あこがれだったミシュランの星に心がざわつくのはわかりますが、日本料理の料理人さんまでもが振り回されるのは見ていて残念。イタリア人はミシュランなんて意に介せず、『ガンベロロッソ』のほうを気にしますよ。
こんなに手厳しくてあとでいろいろ言われないかって? だあいじょぶですよー。実は私、大変なことに気づいてしまったのです。去年の今ごろ古本屋さんにもらった神宮館高島暦は12月の31日で終わっていたんですよ。それどころか会社に貼ってある印刷会社のカレンダーもその先がない。
「2と3を寝ぼけて見違えたんだっ! マヤの予言は12月31日のことだったんだよ!」
「な、なんだってー!!」
それでは皆さま、よい終末を。
投稿者 webmaster : 19:48
2012年12月14日
料理本のソムリエ [vol.49]
【 vol.49 】
一日に白米六合と六銭ぶんのおかずを食べ
今年もあと半月。思い起こせば柴田書店のある文京区では、2012年は森鴎外押しの年でした。なんでも織田作之助よりも半世紀先輩にあたる生誕150周年だそうで、年初めにはお祝いの旗が街灯だの商店の軒先だのに掲げられまして、会社のあるビルの1階エレベータ横にも飾られていたほどでした。区を挙げてお祝いムードを盛り上げようということなんでしょうが、配りすぎ。おまけにこれがまた吸盤が弱くて、落ちること落ちること。エレベータから足を踏み出すと鴎外先生にうらめしそうににらまれてぎょっとしました。

そうこうしているうちにいつの間にか片付けられたと思ったら、秋にはずいぶんかわいくなったVサインする鴎外さんが近所の酒屋さんにお目見えして、またまたぎょっとしました。ぜんぜん懲りてない…。と思いきや、どうやら11月1日に森鴎外記念館が完成するのに先駆けて作られたもので、この旗を見つけた人は景品2000点以上が当たる抽選会の参加資格が得られるという催しだったようです。旗には気づきましたけど、抽選会の告知がどこにあるのかまったく気づきませんでしたよ…。
悔しがっていたら今度は図書館でスタンプラリーを実施していました。区内の4館を回ると記念品をくれるそうです。図書館ならひんぱんに出入りしているからちょうどいいや。今度は取り逃がしませんぞ。ついでにくだんの森鴎外記念館にも寄るといたしましょう。
森鴎外の遺品なら高校生の頃に見たことがあります。当時は本郷図書館に付属する記念室でこぢんまりと展示されていたのですが、図書館機能は近所に移して丸まる記念館として建て替えたというわけ。もともとこの場所は鴎外の自宅である観潮楼の跡地でして、戦火で丸焼けになりましたが、門柱の基礎石や鴎外が座った庭石などが残っています。
それにしても今度の施設のまあ立派なこと。と思ったらがっちり入場料をとられましたよ(泣)。でっかいiPhoneよろしく、著名作家たちが鴎外に送った葉書の画像を指スクロール&クリックすると、ひっくり返って裏側が見られるなんていう展示もありまして、お金がかかっております。素敵なカフェが併設されており、区内の和洋菓子店が開発した鴎外ブランドの菓子も食べられます。鴎外の焼印を押したものあり、作品にちなんだものあり、ちょっとこじつけっぽいのはご愛嬌。

個人的に興味深かったのは、開館にあたって新しく寄贈された「日本兵食論大意」自筆原稿の展示です。文豪森鴎外は、陸軍に仕える軍医森林太郎という顔ももっておりました。この論文は「大意」とありますように、鴎外がドイツ語で執筆した論文の要点を日本語にまとめて、留学先のドイツからわざわざ送ったものです。当時最先端のドイツ医学を取り入れたこの研究があとあとまで尾を引いて、鴎外と周囲の人を振り回したんだよなあと思って眺めると感慨深いものがあります。
鈴木梅太郎が世界に先駆けてオリザニンことビタミンB1を発見したことは、子供向けの偉人伝などにとりあげられるほど有名な話。また日本海軍はカレーだの肉ジャガだの洋食の普及に一役買っていますが、そもそもの始まりは海軍軍医の高木兼寛が脚気防止のために洋食の献立を採用したからでした。彼は明治17年に戦艦「筑波」を使って従来の食事で脚気患者を大量に出した航路でパンや洋食を取り入れた改善食を与え、比較実験することで、米を減らして麦を多く採ることが脚気予防に有効なことを立証したのです。
それに対して陸軍が延々脚気に悩まされ続けたこと、その責任の一端が日本兵食論大意で軍首脳部をミスリードした森鴎外にあると語られるようになったのは平成に入ってからでしょうか。失敗の歴史というのは、なかなか言うのにはばかれるようで、広まるには時間がかかるようです。
ここで事情を知らない方にざっくり説明しますと、「舞姫」「阿部一族」「山椒大夫」などの作品で知られる森鴎外は文筆で生計を立てていたわけではなく、れっきとした医学博士でありました。あまりのかしこさに2歳年をごまかして(逆サバを読んだわけです)12歳で現在の東大医学部に入学し、19歳で卒業して陸軍省に入ります。すぐに念願のドイツに4年留学しまして、コッホなどの著名な研究者の元で学んでおります。当時のドイツは細菌研究が飛躍的に進みつつあったものですから、鴎外も脚気の原因を未知の細菌に求めてしまいます。
最先端の学問を学んだ早熟の天才鴎外にとっては、先輩たち(vol34の三宅秀とか)など何するものぞ。高木兼寛の洋食採用にも異を唱えます。高木は洋食採用で脚気が防げるのは窒素(タンパク質)の割合が高いからと考えており、鴎外はその誤りを突きます。
しかし理論の正しさはともかく、ただでさえ麦は白米よりビタミンB1が多いうえに、おかずもしっかり食べる海軍の食事のほうが優秀だったのは明白でした。日清戦争での陸軍の戦死者は1000人、戦傷死は300人程度に対し、病死者は2万人以上でこれにはマラリアや赤痢も含まれますが、そのうち4000人が脚気で亡くなっております。複数回かかる人がいるものですから、全体の発生率はなんと180%。日露戦争はさらに苛烈で、戦死者は4万6000人にものぼりましたが、脚気による死者もそれに負けじと2万7000人強。戦地での入院患者は約25万人でその半数が脚気でした。これではなんのために大陸くんだり連れてこられたのかさっぱりわかりません。一方海軍はといいますと日清戦争での脚気の死者は1人、日露戦争では3人です。いくら海軍兵士のほうが全体の人数が少ないとはいえこの差は…。
椅子からぶらぶらさせた足の膝小僧の下をぽんと叩くと、反射で本人の意思にかかわらずつま先がぴょんと前に出る。もしうんともすんとも言わなければ脚気の疑いあり……なんていうのが学校検診にありましたが今も行なわれているのでしょうか? 当時は脚気になったがどうしたと馬鹿にしておりましたが、重度の脚気で命を落とすというのは驚きでした。くわばらくわばら。炭水化物をエネルギーに変えるにはビタミンB1が不可欠でして、これが不足すると末梢神経に障害がおきて、疲れやすく、歩くのも困難になります。さらに心臓の動きも弱まり、「衝心」すなわち心不全になってしまうというわけです。
ビタミンB1は水溶性で多めにとっても尿として排出されてしまうので、常に一定量を摂取しなければなりません。しかし陸軍兵士に1日に支給される食事は明治6年に白米6合と副食物6銭6厘(4年後には政府の財政難を受けておかず代は6銭に減らされます)と定められました。6合という数字は江戸時代の武士の一人扶持(家族手当)で支給された米が5合だったので、兵隊はもっと必要だろうとソロバンをはじいたそうです(もっとも武士も米ばかり食べていたわけではなく、これを換金して生活費としていたわけですが)。
米が給料替わりだった江戸時代の食事はいきおい米偏重となり、武士階級から脚気が流行りはじめます。田舎にいるとかからないので「江戸わずらい」と呼ばれ、その療法としては豆や麦の粥を食べることが有効だということは経験から知られておりました。
実は陸軍も、平時においては麦飯を採用することで脚気患者を減らすのに成功していました。ところが肝心の日露戦争時においては、麦が傷みやすくて運びづらいことから白米偏重という愚を犯したのです。輸送力があり厨房も備えた軍艦暮らしの水兵と違って、人力で食糧を運んで屋外で調理する歩兵では、おかずが少なくてすむ握り飯(麦飯はぽろぽろくずれやすいのであくまでも白米です)中心の食事にしたほうが簡単だったという事情もありました。もっとも大陸のような極寒の地では握り飯は凍って食べられなくなってしまうのは、浅間山荘事件でのカップラーメンの活躍でご存知の方もいらっしゃることでしょう。脚気の蔓延に苦悩した戦地の軍医たちは麦の支給を求めますが、脚気は伝染病という頭のある陸軍上層部の動きはにぶく、すべてが後手後手となりました。
『高木兼寛伝』を著した松田誠氏は、脚気伝染病説に固執した東大出身の学者たち、とくに鴎外は実験室での研究を重視するあまり、実際の患者の病状から考える疫学的手法をおろそかにしたと批判的です。イギリス医学を学んで看護婦教育にも取り組んだ高木兼寛は、理論よりも救済のほうに重点をおきました。パン食を嫌ってこっそり捨てる者が後を絶たないことから海軍の献立に麦飯も取り入れるといった融通性をもっておりました。なお高木の生涯は、吉村昭の小説『白い航跡』でも追うことができます。
いっぽう脚気研究で知られる山下政三氏は、『鴎外森林太郎と脚気紛争』で鴎外の立場を擁護し、脚気がビタミンB1不足による病気と学術的に証明されたのは、鴎外が医務局長として立ち上げた臨時脚気病調査会の功績であることを明らかにしています。またいったん脚気撲滅に成功した海軍もたんぱく質にこだわるあまり、缶詰や精白率の進んだ麦の採用などでビタミンが不足がちになり、再び脚気患者を出すようになったとも指摘しています。もっとも松田氏は高木が創始した慈恵医大、山下氏は東大の先生ですからちょっと割り引いて読みたくなりますが。
山下氏は陸軍の米飯偏重はひとえに鴎外の上司の石黒忠悳に責任があるとしていますが、坂内正氏は『鴎外最大の悲劇』で、あくまでも主導は現場に近い鴎外にあったと推測しています。どちらにしても鴎外にまったく責任がなかったとはいえないでしょう。臨時脚気病調査会の研究もうがった見方をすれば、学術的に立証されるまでは説を曲げたくないという鴎外の頑固さが原動力だったともとれます。理論の正しさに拘泥するあまり、予防につながらなかったとしたら本末転倒な気もいたします。
 それにしてもなぜ日本軍ばかりが脚気に悩んだのでしょう。日露戦争では、ふらふらしながら突進してくる日本兵を見て、恐怖心を振り払うために酒に酔っているのだとロシア兵に勘違いされたそうです。ビタミンB1は豚肉にも多く含まれますので、欧米人や中国人にとっては縁遠い病気だったのです。おまけに西洋料理や中国料理に欠かせないニンニクがビタミンB1の吸収の助けになるのだとか。『栄養「こつ」の科学』によりますと、ビタミンB1はニンニクと一緒にとると、におい成分のアリシンと結びついて脂溶性のアリチアミンとなり、吸収しやすく、蓄えやすくなるそうです。さらにアリチアミンは交感神経に働きかけてノルアドレナミンの分泌量を増やし、エネルギー代謝を促すとあります。ネギやニラのにおい成分も同様の効果があるそうですから、薫酒山門に入るを許さずというのも理由があるわけですね。
それにしてもなぜ日本軍ばかりが脚気に悩んだのでしょう。日露戦争では、ふらふらしながら突進してくる日本兵を見て、恐怖心を振り払うために酒に酔っているのだとロシア兵に勘違いされたそうです。ビタミンB1は豚肉にも多く含まれますので、欧米人や中国人にとっては縁遠い病気だったのです。おまけに西洋料理や中国料理に欠かせないニンニクがビタミンB1の吸収の助けになるのだとか。『栄養「こつ」の科学』によりますと、ビタミンB1はニンニクと一緒にとると、におい成分のアリシンと結びついて脂溶性のアリチアミンとなり、吸収しやすく、蓄えやすくなるそうです。さらにアリチアミンは交感神経に働きかけてノルアドレナミンの分泌量を増やし、エネルギー代謝を促すとあります。ネギやニラのにおい成分も同様の効果があるそうですから、薫酒山門に入るを許さずというのも理由があるわけですね。
それでは迎え撃つロシア兵は元気はつらつだったかといいますと、こっちはこっちで壊血病に悩まされておりました。壊血病はビタミンC不足から起きる病気で、コラーゲンが作られなくなって毛細血管から出血し、こちらも死に至ります。野菜や果物が不足する長期航海の船員たちがことごとく壊血病になり、海の湿気のせいだとか、伝染病だとか恐れられていました。脚気と違って日本では問題にならなかったのは、普段から親しんでいる漬物や緑茶にビタミンCが含まれていたからでしょうか。
それにしても日露戦争の時代に壊血病とは。柑橘類を食べることで防げるとわかってとっくの昔に克服されていたのでは?と思ったら、西欧でも米食論争のようなことをしていたのでした。『壊血病とビタミンCの歴史』を読むと、オレンジやレモンが壊血病防止に有効らしいとわかったものの、体積を減らそうとして煮詰めたり(当然ビタミンは壊れます)、硫酸でも代用できるとか麦芽がいいとか百家争鳴で、なかなか撲滅できなかったことがわかります。極地探検隊は壊血病に悩まされるのに野菜と無縁なエスキモーは平気(彼らは肉の生食でビタミンを摂取していたのですが)なので、さらに混乱。イギリス軍は南欧から輸入するレモンが高いのを嫌って、西インド諸島産のライムにとびつきますが、これはレモンよりもビタミンの含有量が少なくて効果が薄いため、柑橘そのものの有効性まで疑われます。そのうえビタミンCを多く含むジャガイモが普及することで、余計に原因がわかりづらくなってしまいます。壊血病予防にレモンが有効というのは、イギリス海軍軍医のジェームズ・リンドの実験で18世紀後半にはわかっていたにも関わらず、根本的な解決は20世紀のビタミンC発見を待たなければなりませんでした。
生鮮の果物が効果的らしいとわかっても、痛みやすいだのかさばるだのと理由をつけて別のものに頼ろうとして失敗するところなんて、麦と米との関係に似てますね。学者が自説や理論にこだわるあまりに真実から目をそむける、なんていうのは洋の東西を問わないようです。
 そうそう、図書館めぐりの結果をお話してませんでしたっけ。天神、湯島、本郷、根津(天神図書室は湯島三丁目に、湯島図書館は本郷三丁目に、本郷図書館は千駄木三丁目にあってややこしいです)をぶじ制覇しまして、賞品を見事ゲットしました。鉛筆1本でした。でも、鴎外ブックカバーとしおりもくれたのでこちとら結構ご満悦であります。
そうそう、図書館めぐりの結果をお話してませんでしたっけ。天神、湯島、本郷、根津(天神図書室は湯島三丁目に、湯島図書館は本郷三丁目に、本郷図書館は千駄木三丁目にあってややこしいです)をぶじ制覇しまして、賞品を見事ゲットしました。鉛筆1本でした。でも、鴎外ブックカバーとしおりもくれたのでこちとら結構ご満悦であります。
投稿者 webmaster : 11:07
2012年11月28日
料理本のソムリエ [vol.48]
【 vol.48 】
法善寺横丁と落第横丁と
前回紹介した『専門料理』連載用の料理完成写真にえびの揚げ物みたいなのが写っているけど、今月号に見当たらないじゃないか!とお怒りになっている方はいませんか? 実はここには雑誌未収録の料理も写っております。というのも、品数も魚種も増やして単行本化すべくプロジェクトがひそかに動いておりまして。おかげで大阪に行く機会がめっきり増えました。しめしめ。
追加撮影の会場は法善寺横丁の「喜川」さん(喜の字はご存知の通り七みっつなんですが、許してね)の2階にて。この横丁もかなりお店が入れ替わりましたが、ぜんざい屋の「夫婦善哉」や「正弁丹吾亭」、そして店の軒先の織田作之助の歌碑は健在です。

(左)夫婦善哉
(右)法善寺の水掛不動
西鶴と文楽を愛し、戦後の闇市時代を走りぬけるように生きた“オダサク”こと織田作之助。『夫婦善哉』が有名すぎて人情物作家のようなイメージもありますが、ヒロポン中毒で逝った彼は太宰治同様、無頼派と目されております。来年は生誕100周年でして、中之島図書館ではそれを記念して先週まで特別展も開かれておりました。
大谷晃一がまとめた伝記『織田作之助 行き、愛し、書いた。』によると、彼は大正2年、生玉町前の生まれで、家業はすし店兼鮮魚店。父織田鶴吉は料理店「浮瀬」の元板前でありました。
浮瀬は日本の料亭の嚆矢であり、江戸時代の大阪で「西照庵」と並んで人気を二分した名店。寛永年間に清水寺の茶店としてスタートし、芭蕉や蕪村、馬琴や江漢、さらにシーボルトらオランダの商館員たちも利用しました。大きな貝殻を加工して酒器にした「浮瀬」や「鳴戸」、朱塗りの「七人猩々」などが名物で、わざわざそれを見るために全国から訪れる人が絶えません。その盛名を借りて、京都や江戸にも同じ名前の店が登場するほどです。
とはいうものの鶴吉が勤めた明治20年代の浮瀬はかつての勢いはありませんでした。店を切り盛りしていたのは福浦イハという女性だったとのことで、すでに店のオーナーは変わっていたのかもしれません。23年にイハは亡くなり、この頃店も閉じております。浮瀬200年の歴史については、坂田昭二氏の畢生の作『浮瀬奇杯ものがたり』でまとめられておりまして、また稿をあらためて。
 ちなみに織田作之助の絶筆「土曜夫人」は、戦後間もない京都が舞台でして、大谷の伝記では、そこに出てくる貸席「田村」は「美濃吉」がモデルとされております。ただし、享保年間に三条大橋のたもとで開業した料亭美濃吉は、戦中は本店の土地建物を売却して給食事業に携わっておりました。粟田口で料亭を復活させたのは昭和25年のことです。昭和22年に読売新聞に連載された土曜夫人に登場するマダム貴子は、その旧美濃吉の施設を購入した大阪のやり手女将がモデルですからお間違えなきように。
ちなみに織田作之助の絶筆「土曜夫人」は、戦後間もない京都が舞台でして、大谷の伝記では、そこに出てくる貸席「田村」は「美濃吉」がモデルとされております。ただし、享保年間に三条大橋のたもとで開業した料亭美濃吉は、戦中は本店の土地建物を売却して給食事業に携わっておりました。粟田口で料亭を復活させたのは昭和25年のことです。昭和22年に読売新聞に連載された土曜夫人に登場するマダム貴子は、その旧美濃吉の施設を購入した大阪のやり手女将がモデルですからお間違えなきように。
さて時計のねじをいささか回しまして、昭和20年3月13日の大阪空襲の1カ月後の話。織田は4月22日号「週刊朝日」の「起ち上る大阪」で、空襲にもめげない千日前の喫茶店主と書店主を取り上げて、こう記しました。
<「あんた所が焼けたので、雑誌が手にはいらんようになったよ」
すると三ちゃんは、滅相もないという口つきを見せて、「何いうたはりまんねん。一ぺん焼かれたくらいで本屋やめますかいな。今親戚のとこへ疎開してまっけど、また大阪市内で本屋しまっさかい、雑誌買いに来とくなはれ」>
実際三ちゃんは戎橋通の表札屋の軒店に移転して、新刊書の本屋を開業しました。織田は終戦直後の9月9日号の後日談「永遠の新人」で触れております。
<ささやかな店で、書籍の数も中学生の書棚くらいしかないが、それでもこの店は大阪の南で唯一軒の新刊書を商う店だと、三ちゃんは自慢している>
この三ちゃんこそが、われらが波屋書房の2代目主人、芝本参治さんです。この一件、ブログのネタとして温めていたら「大阪春秋」の最新号でとりあげられちゃった。後塵を拝してちょっとがっかりですが、さらに掘り下げていきましょう。
実はこの文章は、意に沿わぬものだったと織田は1年後の「神経」の中で語っています。
<…その南が一夜のうちに焼失してしまったことで、「亡びしものはなつかしきかな」という若山牧水流の感傷に陥っていた私は、「花屋」の主人や参ちゃんの千日前への執着がうれしかったので、丁度ある週刊雑誌からたのまれていた「起ち上る大阪」という題の文章の中でこの二人のことを書いた。しかし、大阪が焦土の中から果して復興出来るかどうか、「花屋」の主人と参ちゃんが「起ち上る大阪」の中で書ける唯一の材料かと思うと、何だか心細い気がして、「起ち上る大阪」などという大袈裟な題が空念仏みたいに思われてならなかった。…(略)…ところが、戦争が終って二日目、さきに「起ち上る大阪」を書いた同じ週刊雑誌から、終戦直後の大阪の明るい話を書いてくれと依頼された時、私は再び「花屋」の主人と参ちゃんのことを書いた。言論の自由はまだ許されておらなかったし、大阪復興の目鼻も終戦後二日か三日の当時ではまるきり見当がつかず、長い戦争の悪夢から解放されてほっとしたという気持よりほかに書きようがなかったので「花屋」のトタン張りの壕舎にはじめて明るい電燈がついて、千日前の一角を煌々と照らしているとか、参ちゃんはどんな困苦に遭遇しても文化の糧である書籍を売ることをやめなかったとか、毒にも薬にもならぬ月並みな話を書いてお茶をにごしたのである。
そして、そんな話しか書けぬ自分に愛想がつきてしまった。私は元来実話や美談を好かない。歴史上の事実を挙げて、現代に照応させようとする態度や、こういう例があるといって、特殊な例を持ち出して、全体を押しはかろうとする型の文章や演説を毛嫌いする。ところが、私は「花屋」の話や参ちゃんの話を強調して、無理矢理に大阪の前途の明るさをほのめかすというバラック建のような文章を書いてしまったのだ。はっきり言えば、ものの一方しか見ぬリアリティのない文章なのだ>
起ち上る大阪というタイトルも「文章を書く人間の陥り易い誇張だった」とし、自己嫌悪の念が湧いて来たとまで告白する織田作之助。自らの一言一句をとぎすまそうとする気迫が伝わってきます。歴史人物になぞらえたり威勢のいい文句であおったりで、軽々しく思いつきのご高説をふりまく今のマスコミや政治家は爪の垢でも煎じてご賞味あれ。
さてそんな落ち込み気味の織田の前に、三ちゃんならぬ参ちゃんは三たび現れます。
<声のする方をひょいと見ると、元「波屋」があった所のバラックの中から、参ちゃんがニコニコしながら呼んでいるのだ。元の古巣へ帰って、元の本屋をしているのだった。バラックの軒には「波屋書房芝本参治」という表札が掛っていた。
「やア、帰ったね」
さすがになつかしく、はいって行くと、参ちゃんは帽子を取って、
「おかげさんでやっと帰れました。二度も書いてくれはりましたさかい、頑張らないかん思て、戦争が終ってすぐ建築に掛って、やっと去年の暮れここイ帰って来ましてん。うちがこの辺で一番はよ帰って来たんでっせ」と、嬉しそうだった。お内儀さんもいて、「雑誌に参ちゃん、参ちゃんて書きはりましたさかい、日配イ行っても、参ちゃん参ちゃんでえらい人気だっせ」…(略)…お内儀さんは小説好きで、昔私の書いたものが雑誌にのると、いつもその話をしたので、ほかの客の手前赤面させられたものだったが、しかし、今そんな以前の癖を見るのもなつかしく、元の「波屋」へ来ているという気持に甘くしびれた。本や雑誌の数も標札屋の軒店の時よりははるかに増えていた。
「波屋」を出て千日前通へ折れて行こうとすると、前から来た男からいきなり腕を掴まれた。みると「花屋」の主人だった。
「花屋」の主人は腕を離すと妙に改まって頭を下げ、
「頑張らせて貰いましたおかげで、到頭元の喫茶をはじめるところまで漕ぎつけましてん。今普請してる最中でっけど、中頃には開店させて貰いま」
そして、開店の日はぜひ招待したいから、住所を知らせてくれと言うのである。住所を控えると、
「――ぜひ来とくれやっしゃ。あんさんは第一番に来て貰わんことには……」
雑誌のことには触れなかったが、雑誌で激励された礼をしたいという意味らしかった>
美談が嫌いとワルぶっているオダサクですが、心底うれしかったのだと思いますよ。『夫婦善哉』で活写されているように、彼の目は大阪の庶民の暮らしに注がれておりました。
ちなみに織田作之助全集には収録されておりませんが、昭和20年5月20日の東京新聞には「東京サン!」という短文を寄せております。3月の空襲で焼かれた東京の安否をラジオ局のコールに託して気遣い、いまラジオドラマ制作中の大阪の役者は悪条件下で頑張っているから東京も負けるなという趣旨のこの短文も、彼にとっては意に染まぬものだったのでしょうか…。私はこれもまた彼なりの優しさの表れだったと思うのですが。
実は彼は昭和12年から13年にかけて本郷で下宿しており、東京には知己もおりました。お気に入りだったのが、現在の本郷郵便局脇にある落第横丁の「ペリカンレストラン」です。学生街らしくおでん屋(もちろん震災後に関西から進出してきた関東煮屋ではありません)や喫茶店などが並ぶ横丁の中で異色だったこの店、太宰治や武田麟太郎など文学青年たちが出入りしておりましたが、昭和14年のある日突然古本屋さんに模様替えしまして、常連客を驚かせております。店主の品川力氏は内村鑑三研究で知られ、誤植に厳しく、その著書『本豪落第横丁』では冒頭から「書物に索引を付けない奴は死刑にせよ」なんていう出版社が震え上がるような警句を吐く読書人でありました。

(左)落第横丁入り口の看板
(右)現在の落第横丁
 織田作之助が昭和22年に取材で訪れていた東京で息を引き取ったとき、品川氏も骨を拾いました。そんな品川氏も平成18年に亡くなり、今はペリカン書房の看板が残るのみです。 織田が下宿していた秀英館はとうになく、東京の落第横丁は正直なところただのありふれた路地で、当時を偲ぶよすがはありません。
織田作之助が昭和22年に取材で訪れていた東京で息を引き取ったとき、品川氏も骨を拾いました。そんな品川氏も平成18年に亡くなり、今はペリカン書房の看板が残るのみです。 織田が下宿していた秀英館はとうになく、東京の落第横丁は正直なところただのありふれた路地で、当時を偲ぶよすがはありません。
いっぽう法善寺横丁はといいますと、今も水掛不動は苔むしておりますし、織田作之助の碑だけでなく、岸本水府の句碑や藤島恒夫の「月の法善寺横丁」の歌碑などがあちこちに並び、かつてをしのばせてくれます。もちろん空襲で焼けているので戦前のままではありませんし、平成14年9月、15年4月と近年立て続けに二度の火災に見舞われましたが、石畳の風情は失われておりません。
何度でも起ち上る大阪はたくましい。「せやろ、せやろ、けッけッけッ」と上機嫌なオダサクの独特の笑声が聞こえてきそうです。
投稿者 webmaster : 20:17
2012年11月14日
料理本のソムリエ [vol.47]
【 vol.47 】
波屋書房のカクテル本を訪ねて
実は前々回に「まったり」の話をアップしたあと、ちょっと反省したのですよ。まったりの使い方について考察するのは東京スカイツリーの足元なんかより、京都タワーや通天閣のほうがずっとふさわしいんじゃないかって。このブログでは以前にもおでんの大阪起源説や震災後の関東煮東漸説に冷水をぶっかけたりしているし(vol39)、大阪人からいらぬ反感を買ったんじゃないか。フライドチキンの創業者像と一緒に戸板にくくりつけられて道頓堀に放り込まれたりしないかしら…。
 わが身の安全のために弁明しますと、とんでもない誤解ですからね。私は以前から大阪での取材が多かったこともありまして、彼の地に対する愛はハンチクなものではありませんぞ。その証拠にほら、写真は現在『専門料理』で連載中の「魚介 浪速割烹」の撮影を見学したときのもの。上野修三さんとそのお弟子さんたちの調理風景ですね。こっちが完成した料理です。雑誌撮影にしちゃ会場が広くないかって? そりゃもちろん、これからみんなで試食するからですよ? だから私がこうして参加してるんじゃないですか。このときの料理は来週発売の12月号に掲載されますのでお楽しみに。
わが身の安全のために弁明しますと、とんでもない誤解ですからね。私は以前から大阪での取材が多かったこともありまして、彼の地に対する愛はハンチクなものではありませんぞ。その証拠にほら、写真は現在『専門料理』で連載中の「魚介 浪速割烹」の撮影を見学したときのもの。上野修三さんとそのお弟子さんたちの調理風景ですね。こっちが完成した料理です。雑誌撮影にしちゃ会場が広くないかって? そりゃもちろん、これからみんなで試食するからですよ? だから私がこうして参加してるんじゃないですか。このときの料理は来週発売の12月号に掲載されますのでお楽しみに。
撮影はなんばの一心寺の研修会館で午前中からお昼にかけて。終わった後はぶらぶら大阪見学です。黒門の市場といい道具街といい、大阪はどこに行くのも近くて歩いていけるのがいいですね。ここまできたら料理本のメッカ、千日前の波屋書房さんにも寄っていかなきゃね。
 なんばグランド花月のすぐ近くのお店の中に一歩足を踏み入れればご覧の通り。マンガや風俗雑誌は見当たらない代わりに、右の棚も左の棚も料理本がずらり。お店のほぼ半分を料理本が占めておりまして、その在庫の多さは半端ではありません。おまけに家庭向けレシピ本は奥の方にちょっと決まり悪そうに並んでいる一方で、前のほうでどーんと幅を利かせているのはプロ向けや食文化を扱う読み物です。料理関係の文庫や新書ばかりを集めた棚なんて、よそではなかなかお目にかかれませんよ。
なんばグランド花月のすぐ近くのお店の中に一歩足を踏み入れればご覧の通り。マンガや風俗雑誌は見当たらない代わりに、右の棚も左の棚も料理本がずらり。お店のほぼ半分を料理本が占めておりまして、その在庫の多さは半端ではありません。おまけに家庭向けレシピ本は奥の方にちょっと決まり悪そうに並んでいる一方で、前のほうでどーんと幅を利かせているのはプロ向けや食文化を扱う読み物です。料理関係の文庫や新書ばかりを集めた棚なんて、よそではなかなかお目にかかれませんよ。
ちなみに小社では一昨年の創業60周年記念に過去の書籍の中から10種類を復刻し、通常の流通ルートには乗せずに限定販売したところ、出版業界専門紙「新文化」のニュースに取り上げられるなど業界内では話題になったりしたのですが、この復刻本を扱っていただいたのは丸善、ジュンク堂と並んで波屋書房さんのみ。これだけでも、そのすごさがお分かりいただけるでしょ。
なお新文化の連載コラム「本のソムリエ・ロックスター団長がいく」(ちなみにこのブログのタイトルの元ネタです。ネーミングセンスが悪いとかいうと団長に言いつけますからね(笑))でも、波屋書房さんは取り上げられております。
<難波の繁華街を食べ歩いていると、にこやかに手を振る紳士を発見! その方は、芝本尚明さん。大正8年創業の老舗「波屋書房」の三代目店主です。さっそく店内に入ってみてビックリ! 敷地約30坪のスペースの大部分が「料理書」なんです! その理由を聞いてみると「20年前くらいに、店内の5分の1くらいの棚を使って料理書フェアをやってみたところ、予想以上の好評。とはいえ、料理書フェアのために売れ筋の風俗誌を減らしたため、収益面でのデメリットもありました。今後どうするか悩みましたが、お客様と会話しながら楽しく仕事できたことが嬉しかったので、そのまま料理書を置き続けることに決めました」とのこと>
実はこの料理書フェア、当社の温井営業部長(当時)がご案内して芝本さんとFOODEX(国際食品・飲料展)に出掛けたのがきっかけ。そこで販売していた柴田書店ブースにヒントを得て手がけられたものなんですって。えへん。
<それまでの波屋書房は、純文学との関わりが深く、『辻馬車』ゆかりの書店ということで有名でした。『辻馬車』とは、藤沢桓夫氏を中心とした大阪文学を代表する作家によって作られた同人誌です。この時代の名残りは、現在は波屋書房のブックカバーに引き継がれています。時の人気画家・宇崎純一氏作で、藤沢氏の自筆文字も印字されている貴重なものです。レトロな雰囲気がかわいくて、一目惚れしました! カバー単品で買いたいくらいです(笑)>
このように波屋書房さんは大阪文化の発信地として、文学研究の世界ではよく知られた存在です。ただね、ときどき「かつて文芸で知られた」なんていう取り上げ方をする輩がいるのがちょっと気に食わない。なんだか文芸のほうが偉くて料理本はずっと格下だとか思っておられませんか?
ざーんねんでした。波屋書房さんと料飲業界の縁は創業時からなのです。大正時代に盛名を馳せ、“西の夢二”とまでうたわれた宇崎純一氏の弟の祥二氏が波屋書房の創業者。挿絵画家“スミカズ”の活躍はかなりの間忘れられてきましたが、近年再評価が進んでおりまして、今発売中の雑誌「大阪春秋」148号にその最新成果が詳しく載っております。
戦前の波屋書房は出版業も行なっておりまして、のちに『飲食事典』を著す本山荻舟の『江戸前新巷談』など幅広く手がけておりましたが、その中に『家庭で出来るコックテールの作り方』があります。今の辻学園の前身の大阪割烹学校編。純一氏はここでスケッチの授業を担当されておりまして、学校の広報誌『婦人之世紀』のイラストも担当し、生徒さんたちの修学旅行に同行したりと深く関わっていたのです。
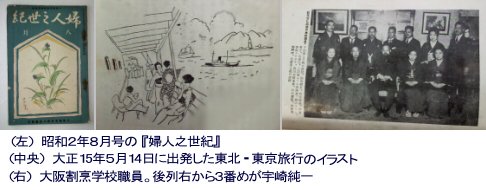
これは気になるぞ。どこかの図書館が所蔵していないか探してみたら、大阪府立大学にありました。もちろんこれは行かないわけには参りますまい。
 広ーい構内を抜けまして図書館にたどりつきますと、おおっ、入り口に水島卜也の写本が展示されている! 水島流は江戸時代の礼法の流派のひとつで、式庖丁に関する資料のようです。礼法は日本料理についても深く関わっておりまして、その影響は研究が待たれる分野であります。
広ーい構内を抜けまして図書館にたどりつきますと、おおっ、入り口に水島卜也の写本が展示されている! 水島流は江戸時代の礼法の流派のひとつで、式庖丁に関する資料のようです。礼法は日本料理についても深く関わっておりまして、その影響は研究が待たれる分野であります。
その奥には『料理の起源』で知られる民族学者の中尾佐助教授のコーナーも。うーん、料理との縁が深いですね。実は阪府大は数年前に大阪女子大学を併合しまして、その蔵書をそっくり引き継いでおります。大阪女子大学は大正時代に女子専門学校として開校されており、貴重な料理関係書も多く所蔵しているのです。
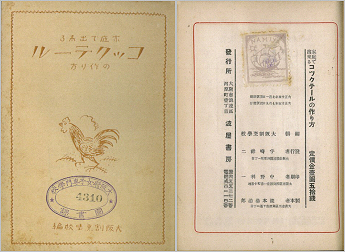 さて目的の『家庭で出来るコックテールの作り方』はといいますと、江戸時代の貴重書ではありませんから簡単に出納できましたが、図書館の蔵書なのでカバーがはずされておりました…。うーん、この習慣、本の作り手側から言いますとなんともさみしい話でして、どうにかならないもんですかねえ。なにせ装丁は宇崎純一によるものなんですから。もっとも扉のイラストもこの通りスミカズ調で、小さいながら粋な造りです。約200種類のカクテルのレシピが載っておりまして、サワーやポンチなども網羅しています。
さて目的の『家庭で出来るコックテールの作り方』はといいますと、江戸時代の貴重書ではありませんから簡単に出納できましたが、図書館の蔵書なのでカバーがはずされておりました…。うーん、この習慣、本の作り手側から言いますとなんともさみしい話でして、どうにかならないもんですかねえ。なにせ装丁は宇崎純一によるものなんですから。もっとも扉のイラストもこの通りスミカズ調で、小さいながら粋な造りです。約200種類のカクテルのレシピが載っておりまして、サワーやポンチなども網羅しています。
おやおや、カキやハマグリのコックテールなんてのも載っておりますよ。
<オイスター・コツクテール(OYSTER COCKTAIL)
牡蠣のむき身の冷やしたもの(小) ………………………六個
トマトキヤツプ …………………………………………中匙一杯
ウシターソース ……………………………………………三滴
西洋酢 (ビネガー)…………………………………………二滴
レモンの搾り汁 ……………………………………………少量
食塩…………………………………………………………少量
胡椒…………………………………………………………少量>
トマトキヤツプはトマトキチヤツプの誤植で、ケチャップのことですね。シャンパングラスに入れて “ゆるやかにセーク(スプーンでかきまはすこと)”して小さじを添えてすすめるそうです。これはカクテル違いのような気もするけど、しゃれかしら?
ただ、例の五色の酒(vol12)のレシピを期待していたのですが、残念なことに載っておりませんでした。宇崎純一氏はモダンな文化人で、大阪のカフェの先駆け「キャバレー・ヅ・バノン」の常連でもありました。ここでも五色の酒は名物だったのですが…。
なお弟の祥二氏が波屋書房を経営していたのは昭和4年までで、店は番頭だった芝本参治さん(尚明さんのお父さん)が引き継ぎました。というのも祥二氏は29歳の若さで亡くなったからです。
ことの発端は、波屋書房発行の雑誌『辻馬車』に、編集担当の武田麟太郎がカフェの女給の橋本スミ名義で、「無政府主義者は革命革命と威勢はいいが実際はカフェで騒ぐばかりだ」と揶揄する詩を載せたため。怒った彼らは祥二氏を自宅近くで待ち伏せ、橋本を出せと問い詰めます。「知らない」(そりゃ、変名ですから。同人仲間だって誰の文章かわからなかったくらいです)と答えたために激昂した無政府主義の青年たちに袋叩きにあい、その傷が元で2年後に亡くなってしまったのです。まったくもってひどい話です。
あ、最後に断っておきますが、いま大阪府立大学の図書館に行かれても水島卜也の写本は飾られていないと思います。だって、上野さんの連載は雑誌掲載の1年前に撮影を終えておりますし、図書館に行ったのも今年の春。すみませんこのブログ、ネタはずいぶん前から仕込んでいるんですがなにぶん遅筆なもんで。次はあんまり間が空かないようがんばります。
投稿者 webmaster : 13:33
2012年10月26日
料理本のソムリエ [vol.46]
【 vol.46 】
鉄人鉄人どこへゆく
およそ3カ月ぶりのごぶさたです。前回のブログを書き終えてみたら、図らずも夏休み宣言ぽい締めくくりになったので、なし崩しにそのままお休みをとらせていただいておりました。「それにしたって長すぎるだろ」とおっしゃられるかもしれませんが、8月から小社は毎年恒例の新刊ラッシュでHPの編集部だよりは更新につぐ更新、このブログの出番がありませんでしたし。あと、私も別段さぼっていたわけではなくて、このラッシュアワーになんとか乗り遅れまいと大汗をかいていたので休んだ記憶がありません(泣)。左うちわどころか、背中のほうでぶんぶん回っている扇風機の音が夏の思い出です。
とはいえ「そろそろ再開を……」とHP担当のE野さん。確かに自宅の扇風機も昨日は分解掃除されてたし、いい加減寒くなってきたのに夏休みもないもんだ。
「ネタがなくなっちゃったんでしょ」ですって? ぎくり。すみません、その通りです。ただし物理的に。ためていた資料の一部を夏休みの間にどこかにやってしまいました。これまでも2回失くしているコピーはようやく掘り出されたのですが、どうしてもまだ見つからないものがありまして(たしか机の下に入れといたはずなんだけどなあー)。あと、せっかく撮った写真が、忘れもしない8月30日にメールソフトごと開けなくなりました(泣)。ちょうど雑誌の校了寸前だったのに! 始業式寸前に宿題帳を失くした小学生の気分です。
とまあ言い訳だらけの再開第1回めは小ネタをひとつ。なんでもこの秋からアメリカで人気の料理番組「アイアンシェフ」が、日本でも放映されるらしいですよ。2004年から放送され、今年の年末にはシーズン11がスタートする人気番組。前に正月の特番で見たような記憶があるぞ……すみません、つまんないボケで。1993年から6年間放送された「料理の鉄人」ですね。料理ガイドの『東京いい店やれる店』の新版も18年ぶりに出ていましたし(ホイチョイプロダクションズってまだスピリッツで連載しているんですねえ)、昭和30年代「三丁目の夕日」ブームの次は、広告代理店とテレビが全盛期だった懐かしの前世紀末ブームでも狙っているのかしら。
「料理の鉄人って知ってる?」と月刊専門料理の若手スタッフに聞いてみたら「小学生の頃やってました」ですって。がーん。わたしゃその頃ばりばり働いてましたよ。「○○○○っていう料理人が載っている本があったらコピーを送ってほしいんですけどお」という見ず知らずの製作スタッフの電話に、「ばかたれ神保町に行って自分で買え!」って怒鳴ってましたよ。もしかしたら鉄人なんて言葉、聞いたこともありませんっていう平成生まれもたくさんいらっしゃるかもしれませんね。
この番組タイトルは「料理の鉄人」という称号を有するとの触れ込みの和仏中の3人(のちに伊が加わって4人になりました)のプロの料理人からきています。彼らがラメラメぴかぴかの派手な衣装を身にまとい、キッチンスタジアムという名のスタジオで挑戦者と料理バトルを繰り広げるという痛快料理バラエティです。その場で発表された1種類の食材をテーマに、1時間以内で料理を作り、腕を競い合う様子を実況します。できばえの判定はゲストを含めた3,4人の美食アカデミーメンバーが試食して行ないます。ちなみに挑戦者の料理人は誰でもいいわけではなく、事前に審査しているみたいでして、それで会社に変な電話がかかってきたようです。
私はといえば、「フランス料理界のヴィスコンティ(笑)」こと石鍋裕さんがフレンチの鉄人を担当していた頃はそこそこ見ていたのですが、すぐに飽きてやめてしまいました。というのも、見ていてイライラするのですよ。肝心の料理を作るプロセスがきちんと撮られておらず、カメラが適当にあちこち右往左往するだけ。さっき切っていた野菜がどこに行っちゃたのか、鍋の中がどんな状態になっているのか知りたくても、カメラマンが料理というものをさっぱりわかっていないので追いかけてくれません。映像で押さえきれないところは実況中継や解説でフォローしてくれればいいのですが、それもない。というかコメントが間抜けで聞くに堪えない。具体的にどのように作ったどんな料理なのか最後までよくわからないまま勝敗がついたところで面白くもなんともない。
全放送を総括した『料理の鉄人大全』を読んでみましたら、企画段階ではF1調のスポーツ実況をめざしていたが、担当した福井謙二アナウンサーがボクシング調ならできると提案して格闘技風になったそうです。福井アナウンサーは<本来なら、この料理実況を100%スポーツ風に喋るとするならば、服部栄養専門学校に行って、1― 2ヵ月弟子入りをして包丁さばきの一つでも習うというのが本来のスポーツ実況の理想なんですけども。…略…まあヘンなマニアックな番組になりすぎちゃうと面白くないですからね>と述べておりました。へええ、スポーツ番組の現場の感覚ってこんなものなんですかねえ。
あの放送を私なりにサッカー中継に置き換えてみるとこんなイメージです。
「いまボールを左足で蹴りました。横に飛んでいきましたね」「彼の足が速いのはフォームがきれいだからなんですねー」「お、シュートがはじかれましたよ。「福井さん!試合前に挑戦者は“鉄人には負ける気がしない、われわれのゴールは鉄壁だ”と力強く語ってくれました」「太田リポーターありがとうございます。あっと、いつの間にかフォワードが交代しているようです」
ただ見たまんま(笑)。こんな試合を流したら苦情の電話がばんばんかかってきますよ。ど素人目にはボールを蹴りっこしているだけに見えるサッカーも、フォーメーションをどうとか中盤のスペースをどうとかの解説があってより面白くなる。選手の動きも何台ものカメラを使って撮影し、ここぞというところでアングルを変える。いわんや複雑な料理においてをや、であります。
ちなみにこの本、料理番組の作り手の現場裏や、テレビの企画というのはどんな論理で作られるのか、各鉄人たちがどんな気持ちで番組に臨んだのかがわかって、意外と楽しめました。ただ、相変わらず料理の解説がぬるいっていうかひどい。<フランスでも最高級の味と値段を誇るブルターニュ産のオマールを、フレンチの鉄人・坂井氏は、カブを器にかつお出汁と白味噌のスープでいただく料理に仕立て上げました。日本古来の出汁と調味料が、オマールの魅力を引き立てている傑作です>ですって。これまた見たまんま。オマールのどこの魅力が引き出されているのか。オマールは焼いたのか煮たのか蒸したのか。なぜ出汁と味噌を使ったのか。どのあたりにフランス料理の技法を駆使したのか。まあ、正直なところ視聴者は、料理の内容なんかどうでもよくて、挑戦者が負けて悔しがったり、おいしそうだけどなんだかよくわからない料理に審査員が一喜一憂してくれれば満足なんでしょうけど。
それから「おくりびと」の小山薫堂氏もインタビューされていました。彼ってプロデューサーだか企画だかを務めたのだとばかり思っていたら、構成作家の一人だったんですね。当時の小山氏の作品に『小説料理の鉄人』っていうのもありました。第1巻「道場六三郎対周富徳・富輝の戦い」から第1章ラストの名シーンを抜粋してみましょう。
<じりじりと、太陽が、海の上に、這い上がってくる。
ぎらぎらと、真っ赤な――富輝にはそれが、道場の顔に見えた。
(道場――)
と、
(お前の首は)
富輝は、
(おれが)
と、胸のなかでつぶやいた。
ひとつの闘う魂が、もうひとつの闘魂を、かぎつける――二人の道がおなじなら、どうしたって勝負になる。
「いくぞ」
富輝は、リオをしたがえて、ふたたび走り出した。
勝負は、真昼だ。迎えの車がくるまで、まだ間があった。>
おおお、さすがアカデミー賞外国語映画賞受賞作品の脚本家。登場人物の気持ちと情景が実にわかりやすく伝わってまいります。筒井康隆に薫陶を受けたのでしょうか、ぎゅうぎゅう詰まった、どこかのブログと、大違いで、読みやすいし。見習わなきゃなりません。
どっちがうまいか料理で勝負っていう構図はテレビやマンガでよくありますが、料理人さん自身も実は大好き。厨房にこもってひたすら作り続けていては自分の料理のレベルがわからない、誰かに評価、判定してほしいという気持ちは多くの料理人さんが抱いています。ですから料理バトル自体は否定しませんが、それも主催者次第です。
 当日発表されたある食材をテーマに制限時間内で料理を競作し、それを試食して優劣をつける、というスタイルの競技会はプロの世界でも行なわれています。典型的な例が80年代後半から90年代前半にかけて、1年おきにフランス食品振興会が開催していた「フランス食材を使ったプロのための全国料理コンクール」でして、全国5都市の予選を潜り抜けた18名が腕を競い、小野正吉氏や緑川廣親氏などのトップシェフたちが審査をしておりました。もちろん味だけでなく、技術やプレゼンテーションも加味されます。数があるし、決勝だけで半日はかかるから審査する側も覚悟と体力が必要。何回か取材を担当しましたが、そのときの緊張感といったらありませんでしたね。
当日発表されたある食材をテーマに制限時間内で料理を競作し、それを試食して優劣をつける、というスタイルの競技会はプロの世界でも行なわれています。典型的な例が80年代後半から90年代前半にかけて、1年おきにフランス食品振興会が開催していた「フランス食材を使ったプロのための全国料理コンクール」でして、全国5都市の予選を潜り抜けた18名が腕を競い、小野正吉氏や緑川廣親氏などのトップシェフたちが審査をしておりました。もちろん味だけでなく、技術やプレゼンテーションも加味されます。数があるし、決勝だけで半日はかかるから審査する側も覚悟と体力が必要。何回か取材を担当しましたが、そのときの緊張感といったらありませんでしたね。
制限時間は銀盆に盛ったメインデッシュとデザートで計4時間。料理は8分おきに完成され(それでもすべての選手が提出し終わるのに2時間以上かかります)、地下の試食会場に運ばれます。われわれは、その移動ルート上の幅1メートルもないスペースに撮影セットを構えて手ぐすねひいて待っておりまして、ホイッと置かれたら、すぐにアングルを決めて(三脚に据えた大判カメラですよ。そうじゃないと端から端までピントがあいません)露出を変えて3回シャッターをきる。反対側で待機していたスタッフがひょいっと持ち上げてそのままエレベータへ。これを延々繰り返します。当時の料理撮影はデジタルではありませんからポラロイドで露光をチェックするのですが、そのひまもない。
最後の回の撮影担当は日本最速にして日本一の腕利き料理カメラマンだった故・林浩二さんで、1品15秒とかかっていませんでした。それでも「料理が冷めている。撮影のせいじゃないか?」とジョエル・ロブションがいぶかりだし、「てめえ、フランスの腑抜けカメラマンと一緒にするな! こっちに上がってきてその目で見てみろ!」と息巻く取材陣(というか私)。なにせ撮り直しはききませんし、盛り付けを崩したりしたらそれだけで選考に影響します。こちらも料理を運ぶスタッフたちもぴりぴりしどおしでしたが、終わったあとの達成感と優勝者の晴れがましさといったら…。ちなみに会場は服部栄養専門学校でして、コンクール運営のノウハウ(アシスタントとか)が料理の鉄人に生かされていたようです。
ところがテレビのほうの審査はというと毎週開いているもんですから、もうぐだぐだ。真剣さが伝わってきません。さんまがメッシにインタビューしているみたいです。そもそも設定も演出もおふざけなんだから本気にすんなよというのが製作者サイドの言い分なのかもしれませんが、だったら初めから全部台本にして、少しはわかりやすく解説しなさいな。中途半端に本格ガチバトルのふりをするからいけないんですよ。
ちなみに料理の鉄人とほぼ同じ頃、同じフジテレビで「解析料理」という料理のテクニックに焦点をあてた番組が放送されておりまして、これは会社の中でもかなり評判がよかったのを覚えています。変に通ぶったりはしない、抑制のきいた作りの教養番組だったように記憶しているのですが、若かりし時分の思い出は美化されているのかもしれません。こっちを再開してほしいんだけどなあ。アメリカで放送して凱旋しなきゃだめですかねえ。
投稿者 webmaster : 11:23
2012年07月31日
料理本のソムリエ [vol.45]
【 vol.45 】
「まったり」について
マターリと語ってみた 2軒め
(前回の続き)それではこの「まったり」という味の表現、国語辞典ではどう解説されているんでしょうか。
『広辞苑』では91年の第4版には見当たらず、98年刊の第5版からようやく登場しておりますが、例の『日本国語大辞典』にはちゃあんと74年の旧版から収録されております。まったりは<落ち着きがあり、奥のある感じ、柔らかい中に、こくのあるさまを表す言葉>と説明されており、用例として『江戸大坂芝居問答』(1830 ― 44年)「大坂の方 義太夫もまったりとおもしろさ」が挙げられています。
実は64年刊『近世上方語辞典』にまったりの項がありまして、<義太夫も…>の用例とともに、この解説の前半に相当する<落ち着きがあり奥のある感じにいう>と説明されております。日本国語大辞典はここから孫び…、おっと参考にされたのかもしれませんね。引用するにあたって、ちゃんと江戸大坂芝居問答はご覧になったかな?
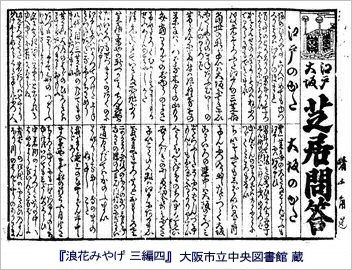
この文献、実はかなりのくせものでして「江戸大坂…」は本のタイトルではなくて瓦版です。『近世上方語辞典』が天保時代のものと推測したのは、この頃に活躍した草双紙屋の「塩屋喜兵衛」が瓦版を集めた『浪花みやげ』に収録されているのを知っていたからでしょう(この『浪花みやげ』がまた取り扱いの難しい資料なのですが、いずれそのうち)。上段が江戸の方(江戸の人)、下段が大坂の方のセリフからなる掛け合いでして、この一例だけでは、当時のまったりの使われ方はよくわからないですね。まったりとおもしろいってどんな感じなんでしょう? いい年なのについこの間まで金髪だったおつむには、ちょっとむずかしい奥のある面白さってこと? ただ大阪の誇る義太夫の魅力を、大阪の言葉で語ったという感じは伝わってきます。
日本国語大辞典はさらに「方言」として<(1)ゆったりとしたさま。緩慢なさま。(2)食物のからすぎたりしないおだやかな味のさま。>と説明しており、出典も挙げております。一応vol.39のぽん酢の誓いを守って引用元にもあたってみましたよ。52年の『彦根ことば』に<温やか(=した味がする)>、55年の『大阪方言事典』に<食物の辛くない落ち着いた味をいう。ゆるくおとなしい>とありました。やはり関西の話ことばのようですね。(1)の「ゆったりしたさま」のほうには戦前の文献が4つ挙がっておりますが、書名ではなく論文タイトルらしきものが多く、46年刊『京言葉』の<マッタリスル 温慢になる>しか確認できませんでした。でも、このニュアンスからすると今の若い人が使う「まったり」も、あながち見当はずれとはいえません。
なお2001年の『日本国語大辞典』第2版では、まったりの用例として、江戸大坂芝居問答のほかに秦恒平「青井戸」(77年刊『閨秀』所収)が加わりました。京都生まれの秦は抹茶を<唇に触れてまったりと流れる口中のかすかな重み>と表現しております。前回のお茶の家元ったら、もしかしたらマスヒロ氏をからかわれたのかしら? なんていけずな…。
それでは国語辞典ではなく方言辞典ではどうでしょう? 井之口有一・堀井令以知両氏の『京都語辞典』(75年刊)は、まったりの説明にかなりのスペースを割いております。
<とろんと穏やかな口あたりをいう。「お雑煮は白のオムシで祝いますが、マッタリと舌にとろけるような味はよろしオスナ。」「梅酒も二、三年置くと、マッタリしておいしオス。」重厚な感じの人に「あのお方はマッタリシトイヤス。」ともいう。マタイ(全)の語幹に、状態を表す接尾語「リ」をつけて促音化したもの。天保ごろから使用。>
オムシというのは白味噌の味噌汁のことですね。「またい」とは完全であるという意味の形容詞で、その副詞が「まったく」、動詞になれば「まっとうする」でありますが、まったりがこの仲間だとは…。堀井氏は関西言葉に関する本を多数出版されておりまして、『京都語辞典』のこの説明は『分類京都語辞典』(79年)や『京ことば辞典』(92年)、『上方ことば語源辞典』(99年)などでまるまる踏襲され、最近では2006年の『京都語を学ぶ人のために』などでも白味噌だの梅酒を挙げて同じように説明しており(あとがきにまで出てきます)、まったりを正しく説明した先駆者と自負されているようですね。もっとも『京ことば集』(72年)の真下五一氏だって、<この「あまったるい」と「まったり」とは全く違った味で、「まったり」の方は決して甘いという意味ではなく、とろんとおだやかな口あたりとでもいおうか、「やっぱりお雑煮だけは京都風に限りますなァ。どうしても白のおむしやなけな、お雑煮祝うた気ィしまへんもんな。あの、まったりと舌にとろけるような味……」となる。>と書いております。
それでは白味噌や梅酒以外のものに対して「まったりした味」というと京都の人に小馬鹿にされるかな? 実はお茶の家元ではなくて町の普通の人々に、「まったり」とはどんな場面で使っているか聞いてみた研究もあります。2002年の『日本家政学会誌』53巻5号には、小田原女子短大の早川文代先生と統計数理研究所の馬場康維先生が首都圏と京都地方で行なった「まったり」に関するアンケートとその分析が掲載されております。52品目の食物と53の食物を形容する言葉を挙げて、どの食物がまったりしていて、どの言葉がまったりに関係しているか調べるというものです(ネット上に公開されておりますので詳しくはそちらをご覧ください)。
それによると大学や短大生といった若年層の答えは首都圏も京都もあまり変わらず、まったりという言葉を同世代やマスコミを通して知ったという回答が多いのに対し、京都の30代、40代の中年層群、50代以上の高年層群と年齢層が上がるにつれ、上の世代から聞いて知ったという回答が増えてきます。ただし、どんな食物がまったりしているかという回答は年代が上がるほどばらけてきます。またどの年齢層もまったりは「まろやかで口にゆっくり広がる感じ」というイメージでとらえていますが、高年齢層はおだやかでよいイメージなのに対し、年齢層が低くなるにしたがって味、テクスチャーとも濃厚な感じが強くなるそうです。
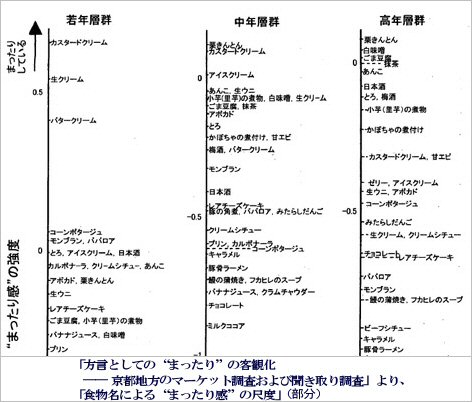
それにしても30代から中年扱いなのはともかくとして、50代以上を高年層でひとくくりにしては、今の高齢化社会を考察するには不充分そう。もっともっとお年を召した方の言い分はいかがでしょう。明治30年代生まれの4人のお年寄りからの聞き取り調査、『町家の京言葉分類語彙篇』によると、彼らにとっての「まったり」は「舌に刺激のない、こくのあるおいしさ」。一方で「まったりした人」というのは、「円満な人、穏やかな人」を指すいっぽうで、「少し鋭さに欠ける人」というマイナス評価にも使われるようです。そういえば『京都語辞典』によると、まったりの元となった「またい」も京都言葉では鈍いとか間抜け等の意味とありますものね。「あのお方はまったりしといやす」なんて柔らかい口調の人物評も裏を読まねばならないわけか…。京都のお年寄りもまた皮肉屋ですねえ。
先のアンケートでは、前回小説家たちがまったりと表現した食べものについてはどうとらえているのでしょう。残念ながら調査対象の52品目にきつねうどんだのニョクマムだのは入っておりませんでした。唯一すし飯が挙がっていたのですが、京都の若年層、中年層ともまったりしているという回答があまりに少なかったため、分析対象からはずされてしまう始末です。
上に掲げたまったり度評価の上位群をみると、京都の若年層もカスタードだのクリームだのが高い割合でまったりするとなってまして、美味しんぼ作者と意見が合うようです。しかし高年層になると栗きんとんや白味噌のほうがまったり度が高いです。例の梅酒もちゃんと上位グループに入っていますね。あと少し下がりますが日本酒も……。
実は戦前の文献には酒をまったりしているとする例も数多くありまして、かの谷崎潤一郎も、日本酒を「まったり」と表現しております。
<なんという酒かわからないけれども壜詰めの正宗を飲んだあとでは程よく木香(きが)の廻っているまったりした冷酒の味が俄かに口の中をすがすがしくさせてくれるのであった>。(1932年発表『蘆刈』)
最近でこそスッキリしていたり、キレがある酒が好まれているようですが、日本酒の芳醇な味わいはマッタリしていると表現するのにふさわしいですよね……と思ったら、この時代、洋酒すらもまったりしてました。写真は戦前の総合雑誌『改造』と大衆雑誌『キング』なんですが、サントリーのウヰスキーの広告に「まったり」という表現が出てまいります。あんなに度数の高いウイスキーがまったりしているってのには個人的にはちょっと違和感があるのですが…。
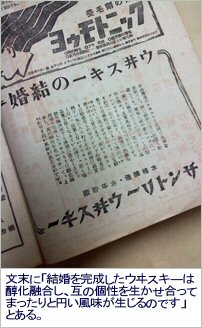
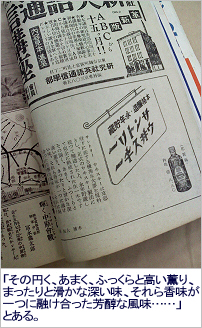
札幌生まれながら大阪の文化を愛した森田たまは、1936年の『もめん随筆』で次のように記しています。
<女同志のつきあいがちょうど場ちがいのするめをたべるように、噛めば噛むほど筋が残つてくるのに引かえて、男の友人は西洋のお酒のように、月日がたてばたつ程まったりとした味の出てくるものである>
小さい頃にはしじゅう料理屋へ連れて行ってもらい、十数年来ほとんど台所に立ったことがないと記した森田たま。こう書くとなんだか鼻持ちならない女性のようですが、子供のときに鯖の味噌煮を小説で知り、未知の味にあこがれたような食いしん坊でして、この随筆集も食べもの関係のところがなかなか味わい深いです。バブル臭が抜けなかったり生活臭がしなかったりする現代の女流エッセイストに飽き足らない方は、ぜひご一読を。
なお戦後になりますが、荻昌弘は72年の『男のだいどこ』で健康によさそうな素材をなんでもかんでも酒に漬けてみた顛末を記しておりまして、<瓶の中身は、まったりとコクのある意外な美酒へ変質していたことに気づいたのである>と表現しております。東京生まれの彼とても、「まったりとした酒」というフレーズは普通の感覚だった模様です。サントリーの宣伝力のせいでしょうか。そういえば、先の開高健はサントリーのPR誌『洋酒天国』の編集長。蘆刈の舞台は奇しくもサントリーの醸造所がある大山崎でした。
こうしてみると調べればいくらでも出てくるでしょうが、「まったりしているうえにかなりしつこい」ことになってきそうなので、はしごはこれくらいにしときましょう。最後を飾るのは、昭和をさらにさかのぼり、大阪出身の民俗学者、折口信夫の大正10(1921)年の「まったり」です。
<町方への道を下る年よりなどの幾人かと、肩を並ベて歩いた時間を憶うと、古國(ふるくに)の懐しさ、南の大きな島で得られなかった、まったりとした味いが、心の中に反芻(にれが)まれる>(アララギ40巻11号)
どうです、折口先生の堂々たるまったりぶりは。夏休みに沖縄を訪れ、続いて九州の壱岐に移った際の報告です。見るもの聞くものすべてが珍しい琉球の国から、万葉集にも登場する壱岐の国へ来た彼は、どこかほっとするとともに懐かしい感覚がまったりと広がったようです……。
おっと、上を向いておなかをさすりながらまったりすごしているうちに、だんだん暑くなってきたぞ。スカイツリーは青空に向かってひたすら上へ上へと伸びておりまして、その周囲にはほかに日をさえぎるものがありません。ああ、この忙しくてお腹のきつい現実から解放されて、永遠の夏休みに向かって蒸発したい。あのタワーの先に登れば、壱岐や沖縄やニライカナイの島々を拝めるのでしょうか。
投稿者 webmaster : 17:35
2012年06月21日
料理本のソムリエ [vol.44]
【 vol.44 】
「まったり」についてマターリと語ってみた
梅雨入り前の6月の晴れの日。行ってきましたよー、東京スカイツリー。近くに会社がある特権ですからね。○○と煙はぐんぐん高いところへと向かいますよ。
浅草から東武線に乗るとあらびっくり。業平橋駅がカナばかりの長ーい名前になってるぞ? この“とうきょうスカイツリー駅”と京成線の押上駅を付帯施設のソラマチがつないでおりまして、スカイツリーはその真ん中あたりにそびえています。団体さんは1階から入りますが、個人の入口は4階の露天の広場スカイアリーナから。見ろ! 人がゴミのようだ! はっはっは!

すみません、嘘です。完全予約制ですからおいそれと登れるわけがありません。東京タワーよりも高い展望台ですから、たぶん道行く人の頭なんぞは、ミジンコどころか針の先っぽでしょう。
ここに来た本当の目的はソラマチの料飲施設の偵察です。観光客の流れをかきわけかきわけ、目的の店までたどり着くとこれまた結構な長さの列。平日の昼間なのに、早くも涙目です。2軒はしごして食事をしたところで、もうギブアップ。同行願った私の先輩はさっそうと3軒目へ足をのばすべく消えてしまいましたが、私はここでまったりスカイツリーでも眺めているといたしましょう。下を向くと苦しいからちょうどいいや。
ところで、この「まったり」なんですけどね。もはや当たり前のように、ゆったり、ゆるーりという意味で使われる言葉になっておりますな。バブルの頃は料理の味の表現として一世を風靡したのですが、今はそっちの用途で見かけるほうが少なくなりました。
2003年刊の『「ことばの雑学」放送局』ではこうしたゆったり系の使い方を間違った大阪弁として紹介しております。さらに『ワードウオッチング ― 現代語のフロッピィ』(私家版・1999年)を取り上げて、ジベタリアンやポスト・バブルのフリーター予備軍の行動様式の形容で使われた事例から、もともとどんより、どろんとしたといったマイナス評価の言葉だったという指摘を紹介しています。なんだか死語だらけですが、流行語をとらえようとすると自然にこうなってしまうかもしれませんね。当時を知る者としては、確かにかつての「まったり」には、そんな投げやりなニュアンスがあった気がします。
ただ、味の表現としての「まったり」の使われ方については、この本からはわかりません。これに関しては、朝日新聞1999年5月22日夕刊の「探検キーワード」でかなり大きなスペースを割いて取り上げているという追記がありました。さっそく見てみましたよ。記事では、80年代半ばに料理評論家の山本益博氏が好んで使っていたと紹介されています。取材を受けた山本氏は「意識して使った記憶はないんですよね」と前置きしながらも、「今にして思うと、上質のフランス料理の、クリームやバターをたっぷり使っていながらすっきり切れのある表現にピタっときたのでしょう」とまんざらでもなさそうです。
ところが99年10月に文庫化された『決定版日本グルメ語辞典』に解説を寄せた山本氏は、自身が本書中でまったりを東京の文化圏で定着させる上で大きな功績のあった人物として描かれているのに異議を唱えておりまして、<わたしの知る限り、まったりの初出は、漫画『美味しんぼ』ではなかろうか>と、その栄誉を譲っております(ちなみにこの本、文庫化前の原題は『食味形容語辞典』なんですが、実際は料理関係の文章表現にことよせたエッセイで、決定版でも辞典でもありません)。さらに山本氏はお茶の家元に、京都ではまったりという表現をどんなときに使うかたずねてみたところ「料理や味には使いませんわ。そうですなぁ、まったりした湯かげんですなぁ、なんていうふうに使いますかしら……」という答えが返ってきたそうで、<フランス料理の凝ったソースではなく、日本料理のお椀の味などにぴったりの形容語ではなかろうか、とそのとき思ったものである>と結論しております。
うーん、どうして湯加減がお椀に結びつくのかよくわかりませんが、お椀の温度なんでしょうか。千澄子氏のカラーブックス『京のお番菜』の写真に「白みそはまったりした味で」ってキャプションが入ってるところをみると、味噌仕立の椀のことかしら? でも、こちらのお茶の先生てば、料理や味には使わないって言ってるし。流派の違いですかね?
ちなみに83年から連載が始まった『美味しんぼ』では「まったり」は早くも1巻第2話で登場します。フォワグラを食べた栗田さんの「まったりとこくのある味が口の中にとろけるようにひろがって…そしてこの香り…」という感想でした。「まったりとしていてそれでいて少しもしつこくない」っていうのが決めゼリフのように知られていますが、どの辺の話に出てくるのでしょう。3巻第3話でスッポンを食べた栗田さんは「こってりとしていて、それで少しもくどくないのね、それにこの舌ざわり」と述べていましたが…。もっとも私は初めのほうの巻をちょっと眺めただけでして、どなたか108巻分チェックして初出をお教えください。
それではまったりとはどんな味を指し、「美味しんぼ」以前にはどんな使われ方をしていたのでしょう。各種辞典の用例やネット検索などで拾い集めてみました(本当は発表年月まで調べたほうがいいのですが、めんどくさいので単行本になった年を示しています)。
先の朝日新聞では江戸料理研究の松下幸子氏が、開高健が小説の『新しい天体』(72年刊)で使っていたはずと指摘しておりまして、記者はさっそく、主人公がたこ焼きをだしに浸す場面で<おつゆがなかなかよくできていて、まったりと含みの深いゆたかさがあり…>というくだりを見つけています。
そこまではよかったのですが、言語学者の寿岳章子氏が「私にとっては、お豆さんとか、おたいさんをたいたもんですね。まろやかだけど、手間暇かけておだしを染み込ませた味」「まったりは、味についてだけいうのと違います」「物腰柔らかやけど、底にしゃんとしたものがある。それがまったり」という意見を展開。さらに宮台真司氏が「まったりと生きよ」やら二面性の表現とやらの持論とからめ出し、なんだか大仰かつ胡散臭い話になって記事は終了、消化不良な感じです。
もしかしたら山本氏は、この記事中で<今の「まったり」と比べてなんだか淡白そう>って感想をもらした朝日新聞記者にミスリードされて、フランス料理の味の表現に使うのをやめて、お椀の形容語であると唱え始めたのかもしれませんね。でもね、開高健は同じ小説の中で、もつ煮込みを<コトコト煮ていくうちに内臓の脂やソースが味噌の味をまったりとしたものに変え、おたがいにいい影響をあたえあう>って書いているんですよ。さらに同氏は「貝塚を作る」(79年刊『歩く影たち』所収)で、べトナムのフークォック島は<精妙で香りの高い胡椒と、まったりとして柔らかく豊潤な味のするニョク・マムが特産品である>とも記しております。
大阪の女性作家といえばこの人ありの田辺聖子は、『歳月切符』(82年刊)の「大阪のおかず」で、<大阪のきつねうどんとかお好み焼きは、「吉兆」や「瓢亭」の結構なるお料理にまさるとも劣らないと思っている。きつねうどんの、あのまったりしたお汁(つゆ)は、決してうす味ではなく、じつに複雑な味で、あれは家庭で出そうとしてもとても出ない味である>と語っています。よーく考えたらたこ焼きを浸すだしの味がまったりなんですから、京料理の上品なお椀の味とはちょっと違うようです。
調子にのって、どんどんいきますよ。同じく大阪出身の富岡多恵子の『冥途の家族』(74年刊)では、<そのおもゆも、まったりとしたおいしいお米の味がした>というくだりがあります。重湯なら、確かにまったりとして少しもしつこくなさそう。ところが「なだ万」創業者一族で東京店の店長だった俳人、楠本憲吉は『たべもの歳時記』(70年刊)で<シャリが関西では甘くて軟かく、いわゆる「まったりした」味を出している>と表現しています。ちなみにvol.40で私が糾弾した「関西おでん炊出し説」は、この本にも載っております。どうやら問題は根が深そうです。
味噌とだしとニョクマムと重湯と大阪ずしに共通する味というのは何なのでしょう。まったりの語感から、とろりとしたもの限定というイメージがあったのですが、ニョクマムやすし飯もありですからねえ…。どうも察するに、旨みのある味が「まったり」のようです。美味しんぼ原作者の雁屋哲氏は多くのグルメ小説やエッセイから作品のネタを仕入れているようですから、まったりという言葉にも親しんでいて、セリフ中に自然に出てきたのかもしれませんね。もっともフランス料理を表現するのに使うのが雁屋流で、そこが人の目を引いたのかもしれません。たとえば3巻第4話で「血を使ったソースはまったりとしていて、カモの肉はジューシイで、それにいい香り!」と栗田さんが興奮しておりました。それにしてもこの人、食事中によくしゃべるなあ。
 柴田書店の本で大阪料理第一人者といえば「喜川」の上野修三さん。『なにわ味噺口福耳福』の中で「京の持ち味、なにわの食い味」という言葉をひいて、まったりは“食い味”であると説明しています。さらに素材の持ち味を生かすためにあくまでも薄味なのが京料理、素材の味を引き出すようにして深みをつけるのが大阪料理とも。
柴田書店の本で大阪料理第一人者といえば「喜川」の上野修三さん。『なにわ味噺口福耳福』の中で「京の持ち味、なにわの食い味」という言葉をひいて、まったりは“食い味”であると説明しています。さらに素材の持ち味を生かすためにあくまでも薄味なのが京料理、素材の味を引き出すようにして深みをつけるのが大阪料理とも。
<ところが近頃、そのまったりが前味(まえあじ)、口に入れてすぐわかるうまみと間違えられてはいまへんやろか。食い味は、前味とも違うし、後でじわっとおいしかったなと感じる後味(あとあじ)とも違うもので、どっちかいうたら、そう、後味に近い中味のことであろうとわたしは思うんです>
うーん大阪弁の世界は奥が深いですね。後味は返り味とも言いまして、飲み込んだあとに、ふっと鼻に抜けるように感じる味のこと。よくお椀は、ひと口めでおいしいと感じるようではだめで、後口で満足するような味つけにせよと言います。ところが最近は前味で勝負、ストレートにがつんとくる料理が好まれてきているんですね。後味がおいしいお椀に対して、だしが利いていないとかいう、わかったふうなコメントも見かけます。「がっつりしていてそのうえくどい」のが時代の好みなのでしょう。(この項続く)
投稿者 webmaster : 15:42
2012年05月25日
料理本のソムリエ [vol.43]
【 vol.43 】
柴田書店と青林書院と勁草書房を結ぶ縁
前回、春の陽気に誘われてのこのこ湯島から本郷まで足をのばした当ブログ主でありますが、賢明なる読者諸氏はすでにご明察の通り、「呑喜」さんはGW休みで閉まっておりました。でも、ぜんぜん悔しくなんかありません。なぜなら財布をうっかり会社に忘れてきちゃってましたからね。えへん。暖かくてジャケットを脱いで椅子の背に引っかけていたのが運のつき。うかうか食事して、さあお会計ってときに気づいた日にゃえらいことになってましたよ。なんて間がいいんでしょう。

仕方なく本郷通りをすごすごと本郷三丁目方面へ向かいます。このあたり、古本屋さんをはじめずいぶんシャッターを閉じた店が多くなりました。カレーの「ルオー」は両隣が閉じてしまってぽつんとさびしそう。東京の真ん中でもシャッター通りが出現するとは嫌な世の中になったもんですなあ。
東大正門前の自然科学と古典籍に強い古本屋、井上書店さんが頑張っていらっしゃるのにちょっと安心。柴田書店は昔こちらから資料を買ったことがあるとかで、会社宛にずっと律儀に古書目録が送られておりました(もったいないから私が横取りしてました)。その向かいの「万定フルーツパーラー」もまだまだ健在ですぞ。うれしいですねえ。ここの時代物の立派なレジスターもまだ現役かな? おっと財布を忘れたのを忘れてドアを開けるところだった。あぶないあぶない。

突き当たりの六叉路の奥にあった、細打ちのいいそばや梅そうめんがおいしい「萬盛庵」さんは、ご主人が亡くなったとかで残念ながら閉店されてしまいました。角にあったレトロで重厚感のある建物には文生書院さんが入っていて、そのいかめしい分厚い扉を押すのはちょっと勇気が必要だったのですが、これも今はありません。もっとも人文古書を扱うかたわらで学術出版にも励む文生書院さん自体は、目と鼻の先に引っ越して今もばりばり活躍中。GW前に古書目録が出たばかりだし、新刊の『在米婦人之友復刻版』にはどんな料理記事が載っているか興味あるぞ。ちょっと寄っていこうかしら…って、一文無しでどうする。全然懲りておりません。
 以前文生書院さんがあった建物の向かいが、これまた学術出版社の青林書院さんの本社ビルです。法律や経済、経営などの社会科学がご専門。さすが天下の東大のお膝元。固ーい出版社が目白押しですなあ。
以前文生書院さんがあった建物の向かいが、これまた学術出版社の青林書院さんの本社ビルです。法律や経済、経営などの社会科学がご専門。さすが天下の東大のお膝元。固ーい出版社が目白押しですなあ。
でもね、固そうにみえて気持ち軟らかめの柴田書店と青林書院は、まんざら赤の他人ってわけでもないんですよ。実は先日、小社の営業部が総出で会社の初版本を整理したのですが、その中からこの通り、青林書院さんの本もでてくるでてくる…。ダンボール1箱分ありました。実は柴田書店創業者の柴田良太は、青林書院の初代社長でもあったのです。

もっとも社長と言っても出資者で、経理担当みたいなもんでして、現場を切り盛りしていたのは逸見俊吾氏です。彼はこれまた学術出版社として有名な勁草書房の創立者でもありました。同社は北陸に展開する大和百貨店の出版部として昭和23年に誕生したのですが、富山出身の逸見氏がその広い人脈を買われて主幹に就いたのです。石川県の物産などを販売する大和百貨店東京支店は銀座資生堂の前で、その3階に勁草書房が入っておりました。
しかし2年後にはテナントの料理店から出火して東京支店の建物は焼失。勁草書房を辞めた逸見氏は、政治家の松村謙三の秘書になりまして、しばらく出版の世界から遠ざかっておりました。ところが肝心の総選挙の時期に逸見氏は、急性盲腸炎をこじらせて長期入院するという運の悪さ。病室で悶々としているところを狙いすまして、彼の才能を惜しんだ柴田良太が、出版界に帰り咲くよう何度も口説きに参ります。良太は3年前に柴田書店を興したばかりでしたが、前職は取次ぎ(本の問屋さん)で仕入れを担当していたため、逸見氏の企画・編集力を知っていたのです。
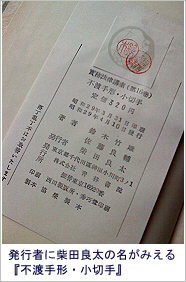 そこで二人で始めたのが青林書院というわけです。100万円の資本金を出した柴田が社長で逸見氏は取締役。昭和28年8月のことで、柴田良太が28歳、逸見氏は30歳でした。
そこで二人で始めたのが青林書院というわけです。100万円の資本金を出した柴田が社長で逸見氏は取締役。昭和28年8月のことで、柴田良太が28歳、逸見氏は30歳でした。
最初に出版したのは武者小路実篤の『生涯を顧みて人生を語る』。さらに『経済学演習講座』『実務法律講座』『仮差押・仮処分』といったヒット作を連発します。しかし元来地味で堅実型、慎重型で露骨に感情を出さない良太と、直情的で単純で楽観的な逸見氏は、二人のプライドも手伝って離反してしまいます。性格の不一致という奴ですね。
良太は本業の柴田書店に専念すべく、株を逸見氏に売り渡しまして青林書院の経営から身を引きます。一方の逸見氏はライバルである有斐閣の向こうを張って『現代法学全書』を発行したり、『法律学ハンドブック』といった本を世に送り出しますが、元来派手好きな性格のために銀座で豪遊したり、芸能人とつきあったりと出費も多く、経営は順風万帆ではありませんでした。株を引き取るために良太に月々払っていた借金も滞る始末です。
そこで起死回生の策として着手したのが、自身の芸能界との人脈を生かしたソノシート付の音楽全集出版です。ソノシートってレコードよりもぺらんぺらんした材質でできていて、ウルトラマンだのオバQだののテレビ主題歌などが入ったものは子供雑誌の付録の定番だったのですが、説明は省きます。音が出る丸いビニール板とでも思ってね。
当時、朝日ソノラマを筆頭に、ソノシート付出版物を世に送る会社はいくつかありましたが、レコード会社の原盤からおこした豪華な青林書院の全集は世間をあっと言わせるものでした。ところが好事魔多し、肝心のソノシートに不良品が大量発生して返品の嵐となり、青林書院は昭和36年に1億3000万円の負債を抱えて倒産してしまいました。このときの一部始終は俊吾氏の伴侶で、与謝野晶子研究者として知られる逸見久美氏(vol.24 に出てきました翁久允の娘さんでもあります)の『女ひと筋の道』が詳しいです。
「青林書院いよいよ倒産」の噂が世に広まると債権者たちは朝から逸見宅に詰めかけ、土地建物、在庫をよこせと迫りますが、どれも何重もの担保となっており、どうにもなりません。残務処理用の虎の子の30 万円を狙って経理部長と営業部社員は退職金をよこせと迫ります。くだんの経理部長は債権者に脅されて、社長が会社の金を着服しているとその場逃れの嘘をつき、事態はさらにこじれます。在庫を押さえようとしにきた取次ぎ側についた営業部社員とそれに反対する社員とで乱闘寸前。社内の空気はもうずたずたです。
このとき柴田良太はすでに青林書院から離れていたため、一連の騒ぎとは無関係でした。息子さんを実家の富山に避難させた逸見久美氏が、小学校へ説明に行ったとき、偶然良太の妻の孝子と出会います。二人は青林書院創業時の取締役で経理に携わった仲でした。
〈昨日からの緊張が急にゆるんだ私は奥さまの顔をみるなり苦境でめぐりあった姉妹のように、「とうとう青林は駄目になってしまったの!」と思わず弱音を吐いてしまった。この人なら私の気持ちを分って下さると思って安心してしまったのか、つい口走ってしまった。…(略)…。奥さまはすでに青林倒産のことは知っていたようすで、「大変ね、辛いでしょう!」とおっしゃるなり、私の手を取って「がんばってね」と涙ながらに力づけて下さった。私も今までこらえていた涙の堰が急に切れてしまったように嗚咽が止まらなかった〉
実は会社の危機に狼狽する俊吾氏を支えていたのは、久美氏(社員の退職金用の170万円は彼女の機転で漬物樽の中でした)でありました。自分が夫を支えなければと、倒産劇の間、終始気丈に振舞い続けていたのです。
しかしこの直後に事態はさらに深刻な方向に向かいます。学校で息子の担任の先生に会って事情を説明しているさなかに放送で久美氏は呼び出されます。債権者の一人である友人が差し向けた弁護士が迎えにきており、逸見社長を安全な旅館に避難させたというのです。社長の姿が消えたと社内は騒然。この間にも支援者の顔をした友人は、憔悴した逸見氏に言葉巧みに迫り「譲歩担保の契約」のハンコをつかせてしまいます。紺屋の白袴とはよく言ったもので、法律書の出版元でありながら、そのハンコが何を意味するのかその時の逸見氏にはわからなかったのです。
この契約に従って、社内に残っていた在庫はその日の夜中にごっそり持っていかれてしまいました。翌日の土曜日の朝、すっかり空っぽになった社内に怒った社員たちは、債権者たちに連絡しますがあとの祭り。この日、不渡りを出した青林書院は倒産しました。創立から8年後の9月16日でした。
二日後の債権者集会には、100人近くの人が押しかけました。社員たちも債権者の味方をし、社長夫妻は針のむしろです。在庫はくだんの友人が抜け駆けして債権替わりに一人占めしたという噂はすでにもれており、不明をなじられます。しかし最大の債権者であるレコード会社は、元はといえば青林書院倒産の元凶であることが次第に明らかになり、債権者側も一枚岩にまとまらず、2時間の集会は結論の出ないまま終わりました。
その後は債権者の委員長となった製本屋の社長が仕切り、債権は一律1割に圧縮するということにして、新会社再建の方向に向かいます。しかし、この委員長は不良編集長(倒産の2年前に自社の新刊を古書店に売って私腹を肥やしていたのを久美氏に目撃されていたのです)と結託して、紙型(活版印刷の原版です)をほかの債権者に内緒でこっそりと弟宅に運び出していたことがわかり、支持を失ってしまいます。こうして怒涛の3カ月を経て、青林書院新社の社長は、債権者の一人だった中央精版印刷社長の草刈親雄氏がつき、再出発の運びとなりました。
以上、これでもかなりはしょって駆け足で見てきましたが、実に生々しい。債権者も生活がかかっていますから仕方ないのかもしれませんが、生き馬の目を抜くというか、仁義のかけらもないというか。
しかし捨てる神あればなんとやらで、理解ある草刈社長に常務として迎えられた逸見氏は、再び本業の専門書でヒットをとばします。またもや新刊書の横流しに手を染めた挙句に、逸見氏追放に走った旧青林書院の社員たちは、草刈氏の逆鱗に触れて首がとび、3年後には見事社長職に返り咲きました。ちなみに倒産以降は銀座の豪遊はぴたりとやめたそうです。代わりに始めたのが骨董蒐集でして、こちらもおぼれると結構危険なように思えますが、逸見氏の眼利きは確かでありまして、南宋の名僧、無門慧開の数少ない自筆双幅を手に入れたのはこの後のお話であります。
 一方、柴田良太のほうでありますが、昭和41年2月、準備中だった『月刊専門料理』の創刊を待たずに、羽田沖全日空遭難事故でこの世を去ります。絶筆は『月刊食堂』編集後記の「年齢と仕事」。41歳でありました。
一方、柴田良太のほうでありますが、昭和41年2月、準備中だった『月刊専門料理』の創刊を待たずに、羽田沖全日空遭難事故でこの世を去ります。絶筆は『月刊食堂』編集後記の「年齢と仕事」。41歳でありました。
133名が亡くなったこの飛行機には、代理店の東弘通信社が札幌雪まつりに招待した多くの出版関係者が乗っておりました。美術出版社大下社長、誠信書房柴田社長、裳華書房吉野社長、共立出版南条社長、春秋社岩淵社長、内外出版社清田社長、啓佑社篠武社長、錦正社中藤社長、旭屋書店早嶋会長といったトップたちです。さらに白水社の篠田次長、池田書店の池田専務、有紀書房の高橋専務、大日本図書の藤原書籍部長など24名が犠牲になりました。この便に同乗していた東弘通信社社長は青林書院の取締役も兼ねておりまして、逸見氏も旅行に誘われていたのですが、まだ再建まもなかったこともあって遠慮したのが、二人の命運を分けました。もし俊吾氏が命を落としていたら、逸見久美氏が経営につき、『鉄幹晶子全集』などの与謝野晶子研究書の数々は生まれなかったかもしれません。なお逸見俊吾氏は平成14年に78歳で大往生されております。
というわけで、柴田書店と青林書院と勁草書房の出版物を並べた企画棚を作りますと、その書店さんはビブリオマニアたちから一目も二目もおかれることまちがいなし(金沢や富山の紀伊國屋書店さんはとくに)。でも、両社の本はきっと相乗効果で売り上げが伸びますが、柴田の本だけ浮きまくること請け合いですけどね。
ちなみに柴田書店はというと、良太亡きあと孝子夫人が急遽2代目社長に就きますが、昭和57年には創業家の手から離れ、10年前には民事再生をいたしました。しかし民事再生というのは法律でがっちり守られての建て直しなので比べるまでもありません。なにせ債権者説明会の真っ最中、すぐ下のフロアの写真スタジオで私はキャビアの食べ比べをしてましたから(笑)。
 いえいえ、普段から社内でキャビアに舌つづみなんぞを打っていたから会社が傾いちゃったわけじゃないんですよ。キャビアだって撮影で使ったもんだし、私が自腹で買ったもんだし。落ち込むのもなんだから、いっちょうこいつで景気をつけてやろうと思いまして。それにしてもあの頃はイランのハタミもロシアのプーチンも外貨が欲しかったせいか、キャビアがかなり安く出回っておりましたなあ。
いえいえ、普段から社内でキャビアに舌つづみなんぞを打っていたから会社が傾いちゃったわけじゃないんですよ。キャビアだって撮影で使ったもんだし、私が自腹で買ったもんだし。落ち込むのもなんだから、いっちょうこいつで景気をつけてやろうと思いまして。それにしてもあの頃はイランのハタミもロシアのプーチンも外貨が欲しかったせいか、キャビアがかなり安く出回っておりましたなあ。
その後、柴田書店は社長は代替わり、なんとか再建しました。一方アメリカが言うところのならず者国家のイランも、憲法をきっちり守ってハタミは大統領選再出馬を見送っておりますが、プーチンはいまだ現役です。世の中、先のことってまったく予想がつきませんね。カスピ海のチョウザメは禁漁となり、キャビアは再び編集者風情にはおいそれと手の届かぬ存在になりましたし。
あ、ちなみに私は会社の新刊を古本屋に流したお小遣いでキャビアを買ったりしてませんからね。柴田書店の本は読者様に高い高いと言われてますが、学術書と比べればたいしたことなくて、危険を冒してまで横流しする旨みが薄いし…こう書くと妙にリアルでますますもって怪しいですが、断じてしておりませんたら。神保町を歩いていて挨拶されてもどこの古本屋さんだかさっぱりわからない、人の顔を覚えられない私ですから、こっそりと悪だくみをしようがないのですよ。だいいち机の上に財布を置きっぱなしで気づかないような間抜けな人間は、そんなに巧妙に立ち回れません。
投稿者 webmaster : 17:23
2012年05月02日
料理本のソムリエ [vol.42]
【 vol.42 】
おでん大好き松崎天民
さて今回は下町独特のおでん種の話題にかこつけて、公園前のおでん屋台で一番安いボールとウインナーばかり買い食いしてた幼き日の思い出や、給食におでん茶飯が初めて出てきた時の驚きをとうとうと語って、昭和気分にたっぷり浸る気満々でいましたが、あんまりしつこいので自重します。なんだかおでん伝道師と思われかねないし…って、これまた前に見たことのある展開。いよいよぼけたかな? すみませんもうしません。ちょっと我慢してもう1回だけおでんの話にお付き合いください。同じ昭和でも戦前の話です。
前回紹介した『日本全国おでん物語』で新井由己氏は、江戸時代創業の大阪の「たこ梅」や明治16年創業の京都の「蛸長」などのだしは鰹節で昆布を使わないこと、関西の家庭でも鰹だしで甘辛の関東煮を作る人が多いことなどから、鰹だし濃口の関東風・昆布だし淡口の関西風というおでんの区分は当てはまらないのではと疑問を呈しています。そこで江戸・明治・大正・昭和のそれぞれの時代に特徴的なおでんが存在していたという仮説を立て、昭和4年創業の銀座の「一平」がおでんを“飲めるスープに改良した”という家伝を紹介して、同店がおでんブームに火をつけて、現在のスタンダードの味を作ったと解釈しておられます。これについては半分賛成ですが、同時代資料の裏づけがほしいところですね。一平の改良が創業時からだったのか、当時画期的だったのかがわかりませんから。
というのも、グルメガイド本の嚆矢である白木正光の『東京名物食べある記』(これは昭和4年版、タイトルをちょっと変えた『大東京うまいもの食べある記』8年、10年版があります)ほか昭和初めのガイドをいくつか見たのですが、それらしい指摘が見当たらないのです。昭和8年版に「一平」銀座店の紹介がありまして、岡本一平の名にちなんで彼の大幅がかかっているとか、一平揚、一平焼なんてのもあるとか、家族連れが多くて新婚早々のカップルが食べにきているとかあるものの、飲めるスープかどうかについては触れられておりませんでした。かたや<スープ煮の関西おでんととんかつで売出した「多助」>なる店がイラスト入りで紹介されていまして、どうやらこの時代、スープ煮のおでんは登場しているようです。
 それでは東京・大阪のどちらのおでんにも精通していた人は、東西の違いをどう感じていて、一平のおでんをどう評していたのでしょう。その適任者は、昭和初めのグルメ雑誌「食道楽」主幹である松崎天民。『大阪食べある記』と『東京食べある記』の2冊のグルメガイドを昭和5年12月・翌年1月と立て続けに上梓しております。しかしこの中には一平どころかスープ煮に関する記述はなく、本場東京のおでんに限るとも、逆に関東煮に軍配が上がるとも書かれておりませんでした。松崎天民は岡山出身で関東の味にはかなり厳しい人なのですが、大阪法善寺の「正弁丹吾」では<謂ふ所の関東煮の風味の、とても水ッぽく甘いのに失望した>なんて書いております。もっとも同店の名誉のために付け加えますと<あの竹の串にさしたおでん其のものには、無条件に降伏しなかったけれども、酒の美味いことには飛上るほど随喜した>そうでして、<少し熱燗に過ぎるけれども、おでんの鍋の前に立つて、赤貝や、バカ貝や、まぐろなどの小串を肴に、一杯二杯と傾ける気分は、大阪ならではの心地がした>と語っております。
それでは東京・大阪のどちらのおでんにも精通していた人は、東西の違いをどう感じていて、一平のおでんをどう評していたのでしょう。その適任者は、昭和初めのグルメ雑誌「食道楽」主幹である松崎天民。『大阪食べある記』と『東京食べある記』の2冊のグルメガイドを昭和5年12月・翌年1月と立て続けに上梓しております。しかしこの中には一平どころかスープ煮に関する記述はなく、本場東京のおでんに限るとも、逆に関東煮に軍配が上がるとも書かれておりませんでした。松崎天民は岡山出身で関東の味にはかなり厳しい人なのですが、大阪法善寺の「正弁丹吾」では<謂ふ所の関東煮の風味の、とても水ッぽく甘いのに失望した>なんて書いております。もっとも同店の名誉のために付け加えますと<あの竹の串にさしたおでん其のものには、無条件に降伏しなかったけれども、酒の美味いことには飛上るほど随喜した>そうでして、<少し熱燗に過ぎるけれども、おでんの鍋の前に立つて、赤貝や、バカ貝や、まぐろなどの小串を肴に、一杯二杯と傾ける気分は、大阪ならではの心地がした>と語っております。
ちなみにこの2冊、今の誠文堂新光社の前身である誠文堂が発行した実用書シリーズで、1冊10銭という安さが売り物です。大きさは87×148mmで今の文庫をさらに2cmくらいスリムにした手帳サイズでして、なかなかモダンなデザインですね。『東京食べある記』は、コレクション・モダン都市文化のシリーズの『グルメ案内記』に『大東京うまい物食べある記 昭和八年版』ともども収録されておりますし、『京阪…』のほうは『大阪のモダニズム』に収録されておりますので、ご関心のある向きはどうぞ。もっともこのサイズからA5版に拡大して復刻しているので、文字がかすれているうえにずっしり重たくてちょっとしんどいです。
グルメ気取りの天民はおでんにあんまり興味がないから、世のおでん屋さんがスープ煮かどうかなんてどうでもよかったのでしょうか。いやいやそれどころか彼こそは、私なんぞは足元にもおよばぬおでん伝道師であります。前々回紹介した『浅草底流記』では「舎人屋」の説明に続いてこんなふうに書かれております。
<いつか天民と一緒にこの屋台にかかったことがある。二人とも幾軒ものカフエーを飲み食ひして廻ったあげくの果てだのに、彼はうまいうまいと言つて茶めしを七杯まで、それも、まるで蟇(がま)が羽虫でも吸ひ込むやうにパクリ込んで曰く、「今夜はこれでいつもより少ない」と>
それでは舎人屋は『東京食べある記』でべたぼめされているかというとさにあらず。屋台店では銀座松屋横の「山平」など広小路のちん屋の前の「壽」だのを挙げているのに、浅草の舎人屋には触れておりません。彼のおでんの合格ラインはかなり高そうです。
実は天民は東京朝日新聞勤務時代におでんに関するコラムを書いております。1912年3月15日の朝刊ですからちょうど100年前ですね。
<…梅はポツポツ散り初(そ)めて、桜に早い十三日、天公何を憤(いか)ってか時ならぬもの降らしたり、地は白砂の銀世界とまでは化(な)らずとも、斯(か)かる夜ぞおでん屋は大繁盛▲お手軽西洋料理の屋台店増加して、江戸前の握り加減、山葵の利き塩梅を誇りとした鮨店は、大分その姿を没したが、代つてメキメキと殖(ふ)えて来たは、飲むにも食ふにも払うにも、万事お手軽で宜いと云ふおでん店、右党にも左利きにも>
実に気持ちよさそうな名調子で、天民の面目躍如といったところですなあ。屋台のほかにもおでんの暖簾を掲げる小料理が増えてきたことや、夏は氷屋、冬はおでん屋に早替わりする店など、すべてを紹介したいところですが、それで終わってしまうのでつまみ食い。
<▲洋服を着た勤め人でも、印半纏着た労働者でも、おでんを好むに於いて同等なり、今より十年前までは礼服で山高帽で、おでんの八ツ頭でも頬張つて御覧あれ、忽ち近所界隈道行く人に、四の五のと取沙汰されたが、今は文明の有りがたさ>
<▲印半纏の兄い、安洋服の腰弁に隣して、紳士級に位すべき鼻髯の連中が、チビリチビリと遣(や)っている図は、正に日本の首都東京に於いてのみ、今日にして見られる光景なり、おでん決して卑しむべからず、おでん屋の商、決して軽蔑すべからず>
当時の人々のちょっと屈折したおでん観がうかがえて面白いですね。まあ、日本料理店が払い下げた残り汁なんかを使っていれば当たり前ですが。礼服でおでん片手にご満悦ってのは現代でもちょっと違和感ありますが、この時代の園遊会では立ち食いできるということでおでんの模擬店が登場し始めています。お座敷おでんなんてのも現れまして、かつて下等な食べものと思われてきたおでんの地位がぐんぐん上昇してきた明治の末の空気を示す貴重な証言です。
夜討ち朝駆け、日に夜を継いで働く新聞社社員にとって、深夜営業の屋台のおでんはありがたい存在でした。vol24の花の茶屋の回でもちょっと顔を出しました『おでんの話』によると、都新聞勤務時代の天民は(彼は大阪新報を皮切りに複数の新聞社を渡り歩いています)、夜の編集作業の合間に数寄屋橋の屋台「富可川」で1杯8銭か10銭の深川飯に舌つづみを打ったそうです(のちに屋台から小料理店まで成長したこの店、深川めしが名物だから「ふかがわ」っていう店名なわけ)。記者時代の苦労をともにしたおでんは天民にとって、美食云々以前に、思い出の詰まった料理だったわけです。
さてこの小冊子『おでんの話』ですが、大正6年創業のおでん屋「富可川本店」主人の井上忠治郎(井上太四郎の親戚ではないですよ)が、昭和7年1月1日に店の15周年誌として出版したもの。もっとも井上両人は友達同士で、太四郎が発行した『弁当の話』にインスパイアされてこの本の発行を思い立ったようです。園遊会出店用の自家用車(ケータリングカーの走り?)や店の内装など、貴重な写真も載っていて興味深いです。天民の“「街頭味覚」の王者”はトリを務めております。

<東京生活二十五年―空しく風塵に老を重ねて来たけれども、私の東京に於る味覚生活のスタートは、実におでん茶飯の屋台店であつた>
<星ヶ岡茶寮の珍味怪味に、一人前七八円、十円を惜しむ貧しい私は、四五十銭にして美味に満腹し得るおでんを探ねて、如何にこの歳月を、舌つづみを打つて来たことであらう>
ほかにも太四郎や林春隆など、忠治郎の友人たちが文を寄せておりますが、中に日本料理研究会初代会長の三宅孤軒による貴重な証言があります。
<処(ところ)で、関西の「関東煮」と東京のおでんとは煮込む具合も、客に出し方も違つてゐたが近頃東京のおでんやは、段々上方式の鍋を使つて来た、だぶだぶと汁沢山の中に、種が浮いてゐるやうな煮方になつて。純東京式の方は、少なくなつて来たやうだ>
<鍋の中の煮つまる具合を見て、汁を加え、その次に鰹節を入れる、あの東京式の煮方の方が、おでん本来の味をよく出すと思ふが、それをしない店が多くなつたのは、翌日に持ち越した時に、品物の色が悪くなるのと、汁が濁つて困るからだそうだ>
日本料理研究会は関西料理の東漸に対抗する形で発足した団体ですから、関西式のおでんに対する目は厳しいですが、道具や調理法に言及しているのはさすがというばかり。確かに昭和の初めにたっぷりの煮汁で煮るおでんが広まり始めたようですが、これはどうも調理法としては後ろ向きな姿勢で、おでん好きが感心するものではなかったのかもしれません。それであまりグルメガイドでは積極的に触れられていなかったのでしょうか。今のような味になるには、さらなる改良が必要だったのか。おでんの進化の過程は一般に思われているように簡単ではなさそうです。
なお、『カフェー考現学』(これも著作選集で復刻されています)の作者であり、大阪毎日新聞を舞台に繁華街や貧民窟の社会探訪記事をものした村嶋歸之も、学生時代におでんに関する一文を雑誌に寄稿しております。こちらは復刻されていないのが残念。
<寒月雲より出で、行人の影法師地に印して明かに、下駄の音高く寒空に冴え返る大路の夜、吾れは四辻のおでん屋に立つの趣味を解す>
天民のコラムの翌年に書かれた文章にしては大時代的。まだ早稲田大の学生で、若書きの文章ですから、ちょっと気負っておりますね。
<本郷の一高屋は、名の如く夜毎に集う白線帽の一高生多く、彼等は茲に酒抜きのおでんを喰うて腹を作り、デカンシヨンを高唱して本郷街に横行濶歩す。城北早稲田の近在にも多くのおでん屋あり。就中(なかんずく)神楽坂上のおでん屋は最も美味也。されど独り三田には多くのレストラントとカツフエーあれど未だ一軒のおでん屋を見ず。可惜(おしむべし)三田の健児、此の美味なる御芋の煮えたをお存じ無き也>
早稲田の学生が慶応を揶揄しているのでちょっと割り引く必要がありそうですが、大正時代の学生とおでんの関係を示した生の証言で、これまたちょっと面白いですね。そういえば古本屋も本郷や早稲田には並んでおりますが、三田にはまったく見当たりません。これも同じ理由からなのでしょうか。
 なんだか本郷の古本屋、もといおでんやに行きたくなってまいりました。東大前の「呑喜」は明治20年創業で、汁たっぷりで煮た「改良おでん」で人気を博したそうです。
なんだか本郷の古本屋、もといおでんやに行きたくなってまいりました。東大前の「呑喜」は明治20年創業で、汁たっぷりで煮た「改良おでん」で人気を博したそうです。
こっちの改良おでんは創業時からなんでしょうか?
昭和のスープ煮おでんの先駆けだったのでしょうか?
今日はGWの中日で白山通りもあんまり混んでないし、東大構内の新緑もきれいだし、湯島からちょっと足をのばしてみましょうか。
投稿者 webmaster : 12:27
2012年04月11日
料理本のソムリエ [vol.41]
【 vol.41 】
大正時代の鶏だしおでんの謎
いやあ、前回は長かったですねえ。お説教みたいな話が続いてまあ退屈なこと。やれやれ、ようやくおでんの話は終わりだと思ったでしょ? ところがどっこい、終わったのは関東大震災後の復興の話だけで、おでん談義はまだ続きますよ。なにせ明治時代の屋台の原価の話でおしまいになってたじゃないですか。これからいよいよレシピの検討に入るわけですからね(この展開、前にも見たことがあるぞ…)。
実は前回紹介した『女が自活するには』なんですが、ちょっと引っかかる記述があるんです。関東大震災の年の冬に出版されたこの本に出てくるおでん種は「こんにゃく、芋、豆腐、がんもどき、等のものから、しのだ、はんぺん、竹輪、さつま揚げの上物までいろいろあります」(一部句読点を補ったり漢字を書き改めています)。明治時代の職業紹介書に見られるおでん像よりもバラエティが充実してきたようです。
 この「しのだ」ってなんだかご存じですか? 「葛の葉」のしのだの狐(って言ってわかるかしら? 安倍晴明のお母さんです)にかけておりまして、油揚げ巻きのことです。百聞は一見にしかず、右の写真の左下隅にあるのがそれであります。ちなみにこの本、すべての掲載店のおでん種を同じアングルで撮影し、同じ縮尺で掲載するという妙なところでやたらに手間をかけた、図鑑マニアの心をくすぐる仕様になっております。
この「しのだ」ってなんだかご存じですか? 「葛の葉」のしのだの狐(って言ってわかるかしら? 安倍晴明のお母さんです)にかけておりまして、油揚げ巻きのことです。百聞は一見にしかず、右の写真の左下隅にあるのがそれであります。ちなみにこの本、すべての掲載店のおでん種を同じアングルで撮影し、同じ縮尺で掲載するという妙なところでやたらに手間をかけた、図鑑マニアの心をくすぐる仕様になっております。
おっと、気になっているのはおでん種ではなくて、その煮汁のほうでした。『女が自活するには』の説明には「煮込の汁は鶏骨の出汁を用いているようで」とあるんですよ、カツオ節でも昆布でもなくて。鶏ガラだしを使ったおでんは『日本全国おでん物語』によりますと九州に見られるそうで、コクがつくので最近ではあちこちで取り入れられるようになってきましたが、まさかこんな時代の本でお目見えしようとは。それでは味つけはといいますと…、調味料については触れられておりませんでした。残念。
ならばと、おでんレシピをちょっと探してみたところ、読売新聞の大正5年12月13日朝刊の「毎日の惣菜」という欄に煮込みおでんがありました。「蒟蒻をゆで三角に切り、八ツ頭をさっと茹で、がんもどき、すじ、焼豆腐などを適宜に切り、鍋に入れ水をたっぷり煮汁(にだし)または鳥の骨三羽位を入れ、汁(つゆ)の半分位になるまで煮込み、醤油を加え、蒟蒻等に味のしみ込むまで煮込みて別に小鍋に取り分け、小皿へは七色または胡椒を添えてすすめる」。おでん種の種類は違いますが、ここでも鶏骨がでてきますね。
ところで寸分違わぬ文章が、5年後の大正10年12月25日朝刊にも再掲載されています。これって当時の「おでん職人連合会」の公式レシピなの? いえいえ、たぶん記者が手を抜いたんでしょう。まさか100年後にねっとり粘着質なブログで記事の使い回しが指摘されるとは、思ってもみなかったでしょうね。まあ、当時の(今も?)レシピ欄なんて埋め草みたいなもんですから、この程度の扱いだったのかもしれません。
震災後の大正13年12月13日読売新聞朝刊には、栄養研究所の発案として煮込みおでんのレシピが載っています。こちらは「八ツ頭100匁(375g)、焼竹輪80匁(300g)、コンニャク70匁(262・5g)、焼豆腐80匁(300g)、ガンモドキ50匁(187・5g)、鳥骨50匁(187・5g)、砂糖、醤油」が材料。砂糖が入ってちょっと甘辛そうなんですが、具の分量しか書かれていないので正確な味付けはわかりません。「八ツ頭は皮をむき、適宜に切りて塩もみして、塩を洗いおとしザットゆで。コンニャクは好みに切りて塩もみし、その他のものは好みに切っておく。右の材料を細かに切った鶏骨と共に鍋に入れかぶるに足る水を加え、充分煮込んで、適宜の砂糖と醤油にて味をつけなお充分に煮込んで供す。(注意)薬味には溶きからし、七色とうがらし、刻み葱、おろし大根等がよい」
 ここで恒例の再現コーナー!(どんどんぱふぱふー) ただし家庭で鶏骨を細かく切るのはとても無理だし、一緒に煮ると鍋の中で邪魔になるので別鍋で鶏だしを取りました(沸かしすぎて白湯になってしまったのでちょっと汁が濁ってしまいましたが)。また八つ頭はさすがに売ってなかったので里芋で代用です。がんもどきは別のレシピで切り分けよというのを見たので、できるだけ大きいのを。それにしても竹輪多すぎ! まあこうした加工品は当時と同じとは限らないので、なんとも言えません。
ここで恒例の再現コーナー!(どんどんぱふぱふー) ただし家庭で鶏骨を細かく切るのはとても無理だし、一緒に煮ると鍋の中で邪魔になるので別鍋で鶏だしを取りました(沸かしすぎて白湯になってしまったのでちょっと汁が濁ってしまいましたが)。また八つ頭はさすがに売ってなかったので里芋で代用です。がんもどきは別のレシピで切り分けよというのを見たので、できるだけ大きいのを。それにしても竹輪多すぎ! まあこうした加工品は当時と同じとは限らないので、なんとも言えません。
同じく大正13年11月刊、村井政善(国立栄養研究所の調理部長だった人です。もっとも前年に彼は辞めて大日本台所司会を立ち上げております)の『最新実用和洋料理』では、材料は「里芋あるいは八ツ頭、味の素匙5杯、コンニャク、焼豆腐、竹輪、がんもどき、竹輪麩、さつま揚げ、鶏骨、右のごとき多種類のもの何でも集めます」。東京人にはおなじみの竹輪麩が登場してますね。「芋の皮をむき、一度ゆでて他のものは好みに切って3つ4つくらいずつさらに串に刺し、鍋に入れ、鶏骨の切ったものを端の方に加え、かぶるくらいの水を入れ、気長く水炊きして後、適宜の砂糖と醤油を加え、充分煮込んで味の素を加味し、なおしばらく煮て皿に盛り、刻み柚子などをちらしてすすめますと結構であります」。うーん、味の素しか分量を示していないので隔靴掻痒。露骨に味の素推しなのは、彼が栄養研究所時代に料理無料講習会で提供を受けたからにほかなりません。
一方大正12年11月12日の東京朝日新聞では、「バラック料理」と銘打って、東京女子割烹学校の指原乙子校長先生のおでんの作り方が紹介されています。震災で焼けだされて仮設暮らしの人たちに、温かいものを食べてもらおうという企画ですね。ここにきて、ようやくおでん種も調味料も分量が明記されました。
材料はがんもどき3枚、コンニャク2枚、サトイモ3合(個数じゃないんですね)。がんもどきは八つ切り(ちょっと小さすぎないか?)、コンニャクは縦半分に切って小口から4分くらいの厚さ(1.3mm。これもちょっと薄すぎる感じがしますが、明治時代の開業本にはとにかく薄く切って利益率を上げろといろいろな本に載っております)に切り、サトイモは大きければ半分に。コンニャクとサトイモを下ゆでして、その湯をがんもどきにかけて油抜きをします。肝心の煮汁ですが、水2合、鰹節茶呑み茶碗1杯くらい、砂糖は同じく3分の1杯、醤油1杯で味加減。煮ながら食べるのがおいしい、とのこと。おやおや竹輪がないのはともかくとして、鶏骨を使っておりませんぞ。朝日新聞たら読売新聞に対抗意識丸出し?
ところが大正15年ともなりますと、読売新聞のおでんレシピからも鶏骨の姿が消えてしまいます。1月26日の朝刊掲載で、東京女子割烹学校に対するは東京割烹女学校(ややこしいね)の秋穂敬子校長先生。5人前の材料は八つ頭2個、こんにゃく2枚、がんもどき3個、竹輪1本、煮出汁3合(540ml)、酒5勺(90 ml)、醤油7勺(126ml)、砂糖大さじ2杯とありまして、だしの種類は書いてない。それにしてもこっちもかなり甘辛そうだ。
大正14年8月の大日本料理研究会編『斬新美味惣菜料理顧問』(大正から戦後まで続いた料理レシピ雑誌「料理之友」の出版元です)では、材料はがんもどき2枚、こんにゃく1枚、里芋3合または八つ頭2個、ちくわ麩2本、さつま揚げ5枚。5寸くらいの昆布を鍋の底に敷きまして、下ごしらえが終ったおでん種を固めて入れ、煮出汁をかぶるほど(およそ3合)加えて火にかけます。煮立ったら煮きりミリン5勺(90ml)あるいは砂糖大さじ山1杯を加え、醤油3勺(54ml)を加え、「一煮してから弱火(とろび)にしてとっぷりと二三時間くらい煮ます」。おお、ようやく昆布が登場しましたよ。「煮えたらば竹串に一個づつさして小皿に受け、溶き芥子を少々つけていただきます」というのがちょっと笑っちゃいますね。串に刺してないとおでんらしくないと思われたのでしょう。それなら初めから刺しておけばよかったのに。熱いし煮くずれしちゃいますよ。
昭和2年11月20日には2年前から始まったばかりのラジオ放送で、煮込みおでんの作り方が紹介されました。こんにゃく、八つ頭、竹輪、さつま揚げ、焼き豆腐、がんもどきという定番の顔ぶれにダイコンが加わりまして、味つけは煮出汁3合(540ml)に対し、砂糖10匁(37・5g)、醤油3勺(54ml)。秋穂校長のレシピよりはずっと醤油が少なくなりましたが、まだそれなりに味が濃いです(実は上の再現おでん、この配合で味付けしてみました。そしたらおでんというよりは旨煮や筑前煮みたいな味に…)。なお、八つ頭と大根は分量外の調味料で下味をつけろとありまして、どうも濃いめの味がお好みのようです。
こうしてみると図らずも、料理レシピがメディアでどのように紹介されるようになったかが、ぼんやり見えてきますね。割烹教授も料理本も明治時代からありましたが、大正に入ると新聞や雑誌、ラジオなどのメディアが料理を多く取り上げるようになりまして、分量も書かれるようになります。これは栄養知識の普及活動などが背景にあるのでしょう。
料理学校の先生が紹介するレシピは実際に町で食べられているおでんそのままではない可能性がありますが(屋台でもこんなに砂糖を使ったんですかねえ)、当時の人たちがおでんをどんな食べものと思っていたのかがうかがわれます。震災前後の煮込みおでんはまだまだかなり味が濃くて煮〆や旨煮っぽい。それにしても大正時代に現れて忽然と消えてしまった鶏骨レシピはいったいなんだったのでしょう。大正大津波のときに長崎あたりのおでん職人が炊き出しでもたらしたんでしょうか。何が江戸から伝わる味で何が当時のスタンダードなんだか、誰か教えてくださいよ。
流行廃りの激しい東京では、お客さんはすぐ新しい味に飛びつくので、昔ながらのおでんでは差別化できなかったのかもしれません。ただし震災後に東京を席捲したとかいう新しいおでんが関西生まれで、当時の「関東煮」と同じだったという確証はありませんが。
 ちなみに大正3年大阪刊の『五円までで出来る営業開始案内』に関東煮屋(かんとうだきや)という言葉が見えまして、関東大震災を機にその名が広まったという説もかなり怪しいことがわかります。「仕入れる原料は小芋、こんにゃく、あげ、貝、天ぷら等で、少し上等になると、かまぼこ、葱ま」とありまして、ねぎまの串(焼き鳥じゃないですよ。マグロと白ネギの串刺しです)が入るのが大阪らしいですね。東京でねぎまといえば煮ながら食べる鍋物でして、先の『惣菜料理顧問』のおでんの項の直前には、ちょうどねぎま鍋が出てきております。
ちなみに大正3年大阪刊の『五円までで出来る営業開始案内』に関東煮屋(かんとうだきや)という言葉が見えまして、関東大震災を機にその名が広まったという説もかなり怪しいことがわかります。「仕入れる原料は小芋、こんにゃく、あげ、貝、天ぷら等で、少し上等になると、かまぼこ、葱ま」とありまして、ねぎまの串(焼き鳥じゃないですよ。マグロと白ネギの串刺しです)が入るのが大阪らしいですね。東京でねぎまといえば煮ながら食べる鍋物でして、先の『惣菜料理顧問』のおでんの項の直前には、ちょうどねぎま鍋が出てきております。
また同じく大正3年大阪刊の『生活難退治 無資本成功』には、関東煮屋を「東京でおでん屋という、大阪とは全然違うが、それはどちらでもよい」とありまして、東京のおでんと大阪の関東煮は同じようでいて違いがあることを意識しているように読めます。
なお大正時代の関東煮屋で使う調味料やだしの種類が分かる資料は見つかりませんでしたが、恐らくたまりや淡口醤油が必須でありましょう。なにせ『生活難退治』がいうことにゃ、「料理店で客へ出して残った刺身の醤油や、吸い物の汁、旨煮、煮肴の汁等を買い集める、というよりもほとんどもらいに行くのだ。仲居や板場にお世辞をふりまいておけば、きっと残しておいてくれる。ほんのわずかな銭でもらってきて、さてそれを関東煮屋へ卸しに回るのだ。廃物利用の一挙両得とはこれらの事であろう。料理店の十軒もあれば優に商売になってゆく。これらはほとんど人の余り知らぬボロイ商いである」。うわー、なんてあけすけな。明治の東京も大正の大阪も、することはあんまり変わりませんなあ。
投稿者 webmaster : 11:19
2012年03月16日
料理本のソムリエ [vol.40]
【 vol.40 】
関東大震災がおでんにもたらしたもの
前回、関西炊き出し隊が東京に関西風おでんブームをおこしただの、江戸から伝わる味の店が失われたために関西風の味つけのおでんが東京を席捲しただのといった、寝ぼけたWikipediaの記事を一笑に付しました。そしたらね、アップしたその日のうちに炊き出し隊の一件が、「関東大震災(1923年)の時、関西の職人の行き来があり、関西風のおでんが関東に逆輸入されていった」という文章に変わっておりましたよ。Wikiの唯一よいところは、修正の履歴が残っていて、直した全過程が追いかけられること。vol39の批判を見てあわてて書き換えたのかしら? いやいや、このブログは読者の方々もご存知の通り、最果ての地の隠れ家ブログですから(会員制でも看板を出していないわけでもないのにね)偶然でしょうね。「かんとうふ煮」の一件は直ってませんでしたし。
修正後はだいぶましになりましたが、それでも及第点はあげられません。直すにあたって紀文食品のHPを参考にされたようですが、そちらでは「時代は大正に入り、東京と大阪の2つのタイプが出会い、おでんがさらに進化するのは、大正12(1923)年の関東大震災で、東西の料理人の行き来がきっかけです」とたくみにぼかした表現なんですよ。それがWikiの書き込みではずいぶん断定的に変わっているうえに、「東西の料理人」が「関西の職人」に劣化コピーされちゃってます。後になるほど研究成果が積み上がって進歩するどころか、引用すればするほどだめになっていくよい見本です。
料理界における「職人」という言葉は、本来は日本料理や寿司、鰻、てんぷらなどの調理師会に所属している雇われの料理人たちのことで、特定の集団を指す専門用語。「職人」という響きにブルーカラーに対する職業差別的な含みがあった時代においても、誇りを持って自称としても使われてきた言葉であり、「主人」と対になるものです(もちろん「職人あがり」のオーナー料理店もありますが、それはそれ)。それなのに、グルメ記者の方々がこだわりのナンタラや一子相伝のカンタラと同じ安直なほめ言葉のニュアンスで使うようになって、わけがわからなくなっています。「そば職人」なんてのも見かけますが、そばの世界にもかつては調理師会があったので、誤解を招くから避けたほうがいいでしょう。「ラーメン職人」にいたっては、たいがいにしたほうがよろしい。
 前にも書きましたように、当時のおでんは屋台の店が主流ですから素人が参入しやすいし、作る人も売る人も資金を出す人も一緒ですから「職人」なんて概念からはほど遠いのです。
前にも書きましたように、当時のおでんは屋台の店が主流ですから素人が参入しやすいし、作る人も売る人も資金を出す人も一緒ですから「職人」なんて概念からはほど遠いのです。
もちろんだからといって、今のおでんまでもが誰でも作れる簡単な料理だと言っているわけではないですよ。むしろ最近は料理店で修業した人がおでん屋さんを始めたり、ひとつの店で各地のだしが味わえたりと、ますます進化しています。ただ、スタートはそうじゃなかったということを頭に入れておいてもらわないと。そもそも日本人って、てんぷらにしてもそばうどんにしてもすしにしても、簡単なスナックのような料理を練り上げて、完成度を上げていくのが好きな国民性ですよね。
100年前のおでんはどこで誰が食べるどんな料理だったのか。明治33年の職業案内『如何にして生活すべき乎』によると、屋台のおでんは「職人、車夫、人足が主たる得意」であり、仕入れ値が5厘のがんもどきは1銭に、4厘のコンニャクは2つに切って1銭に、里芋大100個50銭は200本の串に刺して1本を5厘に、という具合。蒲鉾、ちくわ、はんぺん、焼き豆腐は原価の倍、燗酒と茶飯の利益は1割5分。一晩の売り上げはおでん2円40銭から50銭(利益1円25銭)、酒と茶飯は1円40銭から50銭(利益23銭)。煮汁と光熱費は売り上げの1割を占め、仮に月に20日営業(雨風の日はお休み)とすると、21円60銭が月収となるそうです。ただしこの煮汁の調達法、おっそろしいことに大料理屋から買うとありまして(鍋の残りか?残り汁なのか?)、大阪風とか吸いきれる味加減とかいう以前の問題であります。イニシャルコストはどうなっているかといいますと、屋台や道具一式を貸し出す損料貸がおりまして、月に3円から4円で借りられるそうです。
続いて明治36年の『実験苦学案内』。これは大阪の出版社から出た本なのですが、おでん屋の説明に「東京には専ら行なわれて居って」というくだりがありました。つまり大阪ではまださほどポピュラーではなかったということでしょうか。一夜の純益は85銭とありますが、これは東京で得たデータなのかな? だいぶ儲けが減りましたねえ。
それが明治43年の『無資本実行の最新実業成功法』となると「東京にてはおでん燗酒といひ、大阪にては上燗屋といふ、その他の地方にもこの商売は盛んに行はる、而して多くは港のあるところ、職工の多きところにて、何れかといはば下等の労働者が多きところに盛んなるを見るなり」とありまして、関西でも市民権を確立したようです。ただし鍋に入れる具がちょっと東京の出版物と違います。蒟蒻、里芋、蒲鉾、焼き豆腐は同じなのですが、てんぷら(さつま揚げ? それともごぼ天のことですかね)にニンジン、牛肉とあります。人気があるのは蒟蒻と牛肉で、不人気なのは蒲鉾。とはいえ売れ残りの具は細かく刻んで炊き込んで五目めしにするというのですからさすがです。コロやサエズリは入っておりませんが、おでんのほかに鯨汁や牛肉の味噌煮などを売る店も現れて、そちらのほうが顧客も多くて利益もよいとか。一晩に2円98銭の利益を上げるとありまして、「これよりぼろき商売はなきが如し」と満を持してすすめております。
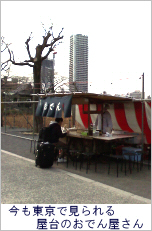 一方同じ明治44年に東京で出版された『職業案内全書』では一夜の純益は60銭から70銭とだいぶ低め。明治41年の『小資本営業の秘訣』では80銭だったので、悪化の一途をたどっているように思えます。これは「廓の大門から花降りかかる仲の町、さては新宿、洲崎、品川、乃至は銀座通り、人形町、十軒店、四谷至る所おでん燗の屋台を見ない所のない」という東京のおでん屋の過当競争状態が原因かもしれません。
一方同じ明治44年に東京で出版された『職業案内全書』では一夜の純益は60銭から70銭とだいぶ低め。明治41年の『小資本営業の秘訣』では80銭だったので、悪化の一途をたどっているように思えます。これは「廓の大門から花降りかかる仲の町、さては新宿、洲崎、品川、乃至は銀座通り、人形町、十軒店、四谷至る所おでん燗の屋台を見ない所のない」という東京のおでん屋の過当競争状態が原因かもしれません。
なお明治後半の苦学生が糊口をしのぐために屋台を引いた件(今ならアルバイトにはげむところなんでしょうが)については、青弓社ライブラリーの『夜食の文化誌』で触れられています。社会学系の学者さんの料理研究は、資料収集がおざなりで推論空論に走るものが多いなか、こちらはなかなかの力作でお勧めです。
ちなみに『無資本実行の…』の関西おでん事情の説明中には「関東だき」という呼び名は見当たりません。つゆの味についても詳しい説明はありませんでしたが、煮汁にかかる費用30銭の内訳は醤油、砂糖、鰹等とありまして、甘辛く煮ていそうです。まあ、この資料ひとつだけではなんともいえませんけどねえ、Wiki先生はどうして「逆輸入した」にそんなにこだわるのか。震災前後のおでんの進化の過程を追いかけるには、当時の資料をあたるしかない。化石の研究みたいなもんですね。汁まで吸える薄味のおでんはいつどこで生まれて、どう伝播したのか。そこの検証を怠って、逆輸入も並行輸入もないもんだ。おでん韓国起源説とレベルはどっこいどっこいです。
それでも紀文食品の東西交流説は、炊き出し説や江戸おでん絶滅説よりは信憑性が高いです。震災に懲りて東京を離れて関西に新天地を求めた人がいたでしょうし、復興特需に惹かれて関西から上京してきた人もいたでしょう。そうした人の移動の中でおでんが大きく変化した可能性は充分ありえます。
でも炊き出し云々はないよねえ。関東大震災がどんな災害だったのかまるでわかっていないことが丸わかり。その場の思いつきを書き込んで得意がっている馬鹿モノは、誰だか知らないけど廊下でバケツを持って反省するように。
当時はラジオもありませんから、大正12年9月1日11時28分に何が起きたのか関西の人たちはすぐに知る手だてがありませんでした。電信を使って得た情報で新聞は号外を発行しましたが(ほとんどの新聞社が被災した東京では、しばらく本紙すら発行できませんでした)、トン・ツーで写真なんぞは送れませんから、未曾有の災害が起こったという文字が躍るだけ。東海道本線は不通ですし(箱根のトンネルは崩落し、根府川駅は地すべりで駅ごと列車が海に流され、多くの犠牲者を出しました)、高速はもちろんガソリンスタンドだってない時代ですから自動車で移動することもできません。軍の飛行機や船、さらに信越線を使って北回りで記者たちがおっとり刀で東京入りし、その惨状が写真入りで紙面に掲載されるようになったのは、地震から2日後のことです。のちにそうした写真を使った絵葉書が大ヒットしまして、その乱発ぶりに不謹慎だと批判されたりもいたしました。

そうした新聞や写真を見て発奮し、手に手に淡口醤油や牛筋やコロを抱えて関西から炊き出し部隊が出発したんでしょうけど、現地入りしたのはいつの段階の話ですかね。東京で関東だきブームがおきるほどの量を提供したそうですが、練り物や豆腐、コンニャクといった材料は築地で買出ししたんですかね。器は発泡スチロールではあるまいな…。
私は女学校の生徒たちが炊き出しをしたとか関東からの避難民を関西の人が温かく受け入れたという報道は見たことがありますが、関西炊き出し団の活躍は寡聞にして知りません。やくざや同業者ににらまれなかったろうか心配です。小回りのきく屋台は震災直後にまっ先に復活していましたからね。
そもそも江戸の味を伝える店が失われたってあなた、立派な什器や家屋の損壊を受けたり、不幸にして女将が亡くなられた料亭ならともかく、屋台でも出せるおでんですよ? それともおでん屋さんばかりが被災して「おでん職人」がみな亡くなったとでも思っているんでしょうか。馬鹿馬鹿しい。店がつぶれて腕をふるう場所がいったん消えたとしても、必ずや復活します。たとえどんな形であったとしても。
地震から3カ月後の12月1日の東京朝日新聞は、「一朝にして下町が焦土に帰した時灰の中から起ち上がって商売の第一声をあげたものは大道の露天商人であった。中には罹災者もあろうが自らの労力と少しばかりの資本を基にして彼等は震災直後おでん屋、すいとん屋、水菓子屋として市民の目前に現れ…」と報じており、指定地や慣行地の外にまではみ出して増えた露天商人の整理が問題になっています。実際、台東区の震災後の区画整理の資料をみていたら、焼け跡の不法占拠者リストの中にちゃっかりおでん屋台がありましたし。あ、もしかしたらこの屋台、大阪からやってきたのかな?
かつてはWikiの説とは逆に「関東大震災を機に東京から移ったおでん屋が、関東風のおでんを関西に持ち込んだため、従来からあった味噌味の田楽と区別するために関東だきと呼ばれるようになった」という説明が一般的でした(たとえば前回挙げた『セブン‐イレブンおでん部会』はこの説をとっています)。これもまた俗説でして、きちんと資料で立証しなければうかつなことは言えないよなあ、とかねがね思っていたのですが、いつの間にかおでん研究は私の知らない次元の高みへと飛翔していたのでした。ああやだやだ。
確かに関東大震災は風俗史的に時代の大きな潮目となっておりまして、料理に関しても例外ではありません。震災後から支那そば屋が流行るようになった、関西料理が東京に広がった、なんていうのがよく知られています。
ただしこれらの通説も、「あのころから流行ったぽい」という域を出ておらず、同時代資料できちんと説明されるまでには至っておりません。たとえば震災直後に発行された雑誌や新聞に、最近屋台のワンタン屋が増えたという記事がありましたが、一過性のブームで終わったものなのか(ワンタンの裏メニューで支那そばも出していたというのなら話は別ですが)、料理史の本を見ていてもぜんぜん出てきません。人間の記憶なんてものはいい加減で、震災のショックで何が前からあったのか頭から飛んでしまい、何がその後に起きたのか、混乱したまま語りつがれるということもありえます。
たとえば震災直後に添田知道が作詞した「復興節」にはこんな詞があります。
―― 学校へ行くにもお供を連れたお嬢さんがゆで小豆を開業し アラマ オヤマ
恥ずかしそうに差し出せば お客が恐縮してお辞儀をして受け取る エーゾ エーゾ
帝都復興 エーゾ エーゾ
ゆで小豆や雑煮、汁粉を売る汁粉屋さん(関西でいうぜんざい屋さん)もまた、素人が開業しやすい店ですね。戦前は女性グループが食べに行ける店として圧倒的な人気を誇ったものですが、今の人はほとんど知らないでしょう。
この復興節、終始底抜けに明るい歌詞と調子でして現代人にはハラハラするような内容ですが、添田の『演歌の明治大正史』によれば、作った本人もおっかなびっくりだったようです。彼は下谷から焼けずにすんだ日暮里へ避難し、急拠刷った唄本の宣伝のために横丁で歌い始めます(当時の演歌というのは、時事ネタを歌にして街頭で歌いあげるものでした)。「夜は暗く死んだように沈みかえっている。そんな中で歌声をあげたりしたら、袋だたきにでもあうのではないか、そんな不安があった。とある横丁でうたいはじめると、たちまち、暗い家々からとび出してきた人々にかこまれた。しかしそれは、不安とは逆な、熱心に聞き入る人々であった」。ちなみに彼は浅草の風俗を活写した『浅草底流記』も書いておりまして、「大衆の食卓 ― 屋台店」の章で、「おでん屋には稀にうまいものもあるが…(略)…何もかも多く駄物屋仕入れである」とし、名店として広小路の「舎人屋」という店をあげています。この店は昭和6年当時で創業25年だそうですから、明治の末からの営業ですね。江戸の味を伝える店が失われ云々に根拠がないのがよくわかります。
大正14年5月19日の東京朝日新聞では、東京市の統計課の調査を報じておりまして震災後には外食の機会が増えたそうです。料理店が300軒に減少したのに対し、簡易な飲食店は1万2533軒を数え、30戸に1軒、150人に1軒(当時の1戸は5人家族が標準なんですね)の割合だとか。実に震災前の2割増し。その内訳ですが、酒肴めしが2437、西洋料理屋1770、汁粉屋1464、そば屋1374、おでん屋1134、すし屋874、喫茶店832、支那料理466。そば屋におよばないもののすし屋を凌駕しております。関西おでん職人組合の勢力拡大の成果だとしたら、その力たるや恐るべし。それにしても大阪うどんや押しずしの職人は、このとき何をやっていたのでしょう。ふがいない。
そのほか震災後、店を失った料理店の女将がおでん屋さんを始めたなんて記事もありました。料理屋のノウハウが流れ込んで、おでんが進化した可能性もありますね。大正12年12月に発行された『女が自活するには』は、震災未亡人も含めたご婦人方を読者層として想定した開業本ですが、汁粉屋とともにおでん屋さんも簡単な商売としてすすめております。屋台を借りる方法のほか、銅の胴壷つきの釜を買って(30円くらい)、軒下を少し作り変えれば開業できるとしています。吸いきれる味のおでんの出現は主婦の発明かもしれませんよ。
投稿者 webmaster : 13:23
2012年03月01日
料理本のソムリエ [vol.39]
【 vol.39 】
ポン酢とおでんとウィキペディアの罠
 3月の声を聞こうとしているのに雪は降るわ、梅の開花は遅れるわ。エアコン新調の金を惜しむ私ですが、コンロ暖房にそうも頼っていられないのでコタツを買いましたぞ。
3月の声を聞こうとしているのに雪は降るわ、梅の開花は遅れるわ。エアコン新調の金を惜しむ私ですが、コンロ暖房にそうも頼っていられないのでコタツを買いましたぞ。
売り場に行って驚いたことには、もはや電気カーペットが季節家電の主流で、コタツは夏場の扇風機以上に少数派。端っこに申し訳程度に積み上げられていました。そういえば掘りゴタツってのは、居酒屋のテーブルの下のことだと思っている人がほとんどだしねえ(あれは暖房じゃないからコタツじゃなくて「掘り込み式」というんですよ)。昔は裏返って腹っていうかヒーター部分をこっちに向けた電気コタツが、売り場にずらりと並んでいたもんですが。当時の製品はお腹がぽっこりしていましたが、今は見事にスリムですね。
何年ぶりかにコタツに入りますと、もう布団から指一本出したくなくなりますよ(誰か代わりにトイレ行ってきてー)。コタツの外は5℃をきってるし。さすが二度と出られぬ東洋のクノッソス。日本のPCメーカーはタッチパッドの製品に対抗するために、コタツをおまけにつければいいのに(キーはコタツの中でブラインドタッチで叩いてね)。もちろんマウスはコードレスじゃない昔ながらのやつで。いっそテレビのリモコンも有線にしてほしいくらい。ミカンがなくなったら持ってきて皮をむいて口に放り込んでくれる二足歩行ロボットを開発してくれれば、なおよし。おお偉大なる国産家電製品たちよ。
ガラパゴス化っていうのはあちらの島の方々にとっても失礼な話で、ジパング化といってほしいですよね。コタツにあたって鍋で晩酌まで始めた日にゃ、現代のエルドラド。ということで今回は、鍋は鍋でも鍋物の本の話です。
小社の鍋料理の書籍には『ひとり鍋ふたり鍋』と『鍋料理』という両極端なものがありまして、かたや和中韓の若手料理人が提案する一人暮らしの家庭用レシピ、かたや鍋専門店のみならず、居酒屋やエスニック料理店にも取材した101種類の業務用レシピ。まあ鍋料理というのは単純ですから、中途半端なコンセプトではわざわざ本を買おうという人はそういないでしょうから。

さらに古い本に『月刊専門料理』の鍋関係の記事をまとめた『料理屋の鍋もの』ってのがありますが、これを語るにはつらい懺悔をせにゃなりません。会社の上司にはないしょだぞ。78ページに「…ポンスの作り方の記録はオランダ通事(通訳)の楢林重兵衛の談話をまとめた『楢林雑話』(一七五八年)に登場するが、ここでは柑橘類の使用についてはまったく触れられていない」とありますがこれは間違いです。そんでもって私が書きました。
言い訳しますとこの文献、小学館の『日本国語大辞典』のポンスの項を見て知ったんです。もちろん原本もチェックしなきゃならんのですが、忙しくてそのひまがない。意を決して閉館ぎりぎりに図書館に駆け込んで、楢林雑話が収録されている『海表叢書』(『広辞苑』の新村出が活字化したものです)を悲しげな音楽が流れる中で開きました。あった、あったよ、よかったーと閉じたのですが、実は次のページに日本国語大辞典に引用されていない続きの文「肉桂、木酢等を入」があったんですよ。木酢ってちょっとピンときませんが、ちゃんと注がありまして「だいだい、梅、柚、枳殻(からたち)などの類、水をとり貯」。果実の絞り汁のことですね。見落としてました。私が再三「STOP ザ 孫引き」キャンペーンを張っているのもこうした自分自身の苦い経験があるからでして。
ポン酢の語源はオランダからきた飲み物の「ポンス」に由来するというのがこれまでの説。『講談社オランダ語辞典』によりますとオランダ語のポンスっていうのは、英語のパンチからきたもので、『中陵漫録』にも記述があるそうです。これによると蒸留酒のアラックにダイダイの汁、砂糖を加えて一煮立ちさせ、水を加えて飲む夏の暑気払いの飲み物だとか。ですが、その名が転じて調味料にも使われるようになった経緯は相変わらずわかりません(負けおしみ)。江戸時代の料理書には「柚じょうゆ」は出てきても、ポンスが見当たらないのです。他人の空似かもしれない飲み物起源説は一考する必要があると言いたかったのですが、ちょっと勇み足でした。私の文の初出は『専門料理』1999年1月号でして、黒歴史として葬り去られるはずだったのが、こともあろうに私の知らない間に2001年に単行本に再録されていたのですよ。ひとこと言ってよー。
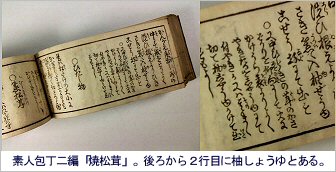
さあ、大変。間違った知識が世に広がってしまったらどうしよう。どうも最近はWikipediaなるWeb上の百科事典もあるらしいぞ…とその時初めてアクセスしてみたところ、ポン酢に醤油を入れるか入れないかで編集合戦してました(呆然)。楢林雑話のナの字もありません。ののしりあったはてにしばらく編集がブロックされていたのですが、解除されたと思ったら今度は語源はポルトガル語という新説が登場しました(さらに呆然)。ポルトガル語のポモは果実の意味で柑橘とイコールじゃないし、それならスペイン語だって充分有力候補になりえます。あるいは同じラテン系のフランス語やイタリア語からかもしれませんよ。
Wikiのはらむ問題はここにありまして、出典や論の根拠が明示されていれば検証しようもあるのですが(もっとも世に出回っている料理本の記述には誤りも多いので、間違ってることはしょっちゅうありますが)、「コンピュータや医学用語の解説はできないけど、普段食べているもののことなら俺でもわかる」と料理をナメてかかっている人たちが、余計な親切心からその場の思いつきの新説を書き足しちゃう。つぎはぎだらけなので、一部に正しい説明が残っていることが災いして、全部が正しいと誤解されちゃうので始末に悪い。Wiki側も出典を明示するよう指導しているみたいだし、おかしな投稿はチェックしているようですが、なにぶんボランティアなので監視の目をすり抜けた例が山とあります。おかげで料理関係の記事を見た日にゃ、目を覆ったり頭を抱えたり首をひねったりお腹がよじれたりと忙しくって仕方ない。料理店や食品会社のHPなどに、ばんばんデジタル孫引き(コピペ)されているけどいいのかしら。
わかっているなら直してやれって? でも、全部一から書き改めるならまだしも箸にも棒にもかからない過去の投稿を生かしつつ修正するのは大変だし、せっかく苦労して直しても誰かにまた書き足されてぶち壊しになっちゃうかもしれないんですよ? 思いつきで「ある」と書くのは簡単ですが、「そんなことはない」と証明するのはなかなか骨が折れます。まあ、そもそもWikiへの書き込みのお作法を知らないもので。すみません。
 ここまで書いて試しにWikiの「おでん」の記事を、おそるおそる開いてみたのですが…。「関東におけるおでん人気は下火になっていたが、関東大震災の時、関西から救援に来た人たちの炊き出しで「関東煮」が振る舞われたことをきっかけとして、人気が回復した」「江戸時代の味を受け継ぐ店は震災によりほとんどが失われていたため、一時期、関西風の味付けをするおでんが東京を席捲した」。涙で顔が上げられません。10年経っても誰一人気づいてくれない(ていうか読まれてない?)ような間違いでくよくよするな、原資料なんか気にするなという力強いメッセージ。蛮勇という名の勇気をもらいました。
ここまで書いて試しにWikiの「おでん」の記事を、おそるおそる開いてみたのですが…。「関東におけるおでん人気は下火になっていたが、関東大震災の時、関西から救援に来た人たちの炊き出しで「関東煮」が振る舞われたことをきっかけとして、人気が回復した」「江戸時代の味を受け継ぐ店は震災によりほとんどが失われていたため、一時期、関西風の味付けをするおでんが東京を席捲した」。涙で顔が上げられません。10年経っても誰一人気づいてくれない(ていうか読まれてない?)ような間違いでくよくよするな、原資料なんか気にするなという力強いメッセージ。蛮勇という名の勇気をもらいました。
「関東煮やなくて広東煮や! けっして関東モンのまねをしたんやない(エセ関西弁)」っていう威勢のいい意見もいまだに見かけますが、その原型となる広東の煮込み料理っていったいなんでしょう? 広東料理に練り物は見あたらないし、コンニャクは四川や雲南のローカル食材だし…。初めて見た謎の中国料理(チャプスイか?)からヒントを得て今のおでんにたどり着いたとしたら、そりゃあかなりの想像力です。
Wikiの関東だきの語源(またかい…)には「かんとうふ煮」説なんてものも挙げられてますが、これに関しては珍しく出典が明示されています。それに従って大阪の「た古梅」のHPへ飛ぶと「蛸や烏賊などを醤油で煮た食べ物を「かんとうふ煮」といい、江戸時代の書物に記述を見ることができます」とありました。とほほほほ…。
 関東煮(「かんとふ煮」ですからね)は今でいう蛸の桜煮のことで、幕末に松山藩から長州藩へ派遣された使節の日記にも出てくる全国的な料理。煮込みのおでんとは違うものであると川上行藏先生が『湯吹きと風呂吹き』で考証しています。一方江戸時代にも「おでん」なる言葉は登場しているのですが、『浮世風呂』にお芋のお田、『浪花の風』に大阪ではコンニャクの田楽をおしなべておでんという、とありましてどちらも味噌田楽のことっぽい。今の煮込みおでんが普及したのは明治のことかもしれないと、川上先生は結論を保留しています。
関東煮(「かんとふ煮」ですからね)は今でいう蛸の桜煮のことで、幕末に松山藩から長州藩へ派遣された使節の日記にも出てくる全国的な料理。煮込みのおでんとは違うものであると川上行藏先生が『湯吹きと風呂吹き』で考証しています。一方江戸時代にも「おでん」なる言葉は登場しているのですが、『浮世風呂』にお芋のお田、『浪花の風』に大阪ではコンニャクの田楽をおしなべておでんという、とありましてどちらも味噌田楽のことっぽい。今の煮込みおでんが普及したのは明治のことかもしれないと、川上先生は結論を保留しています。
がんもどきや練り物の入るおでんは明治の中ごろには確認できますから、幕末から明治維新の頃が転換期なのでしょうか。「おでん燗酒」というのは居酒屋の業態のひとつで、屋台のおでんは苦学生や資金のない人が自活する手段となっており、流行りはじめた洋食屋台なんぞよりもずっとありふれた存在でした。素人料理だったからこそ、具も味つけも何でもありで種類が広がったのかもしれませんね。
串に刺さった豆腐やコンニャクに練り味噌をぬった田楽は、いつの間にか串と味噌の呪縛から解き放たれて鍋ものにまで姿を変えたわけですが、進化の過程で日本各地でいろいろな姿が生み出されています。ガラパゴス諸島のフィンチのように。それを集めたおでん界のダーウィンが『とことんおでん紀行』の新井由己氏です。ただし全国を回ったのはビーグル号ではなくて、新聞配達用の原付バイク。新井氏は日本全国を旅しておでんを食べまくり、串に刺さっていたり、味噌をつけたりする古い形を残した地方のおでんや、独自に発達したおでん種を見出しました。コンビニがおでんを積極的に売るようになってからは、こうした地方差が一般にも知られるようになりましたが、当時としては画期的でした。
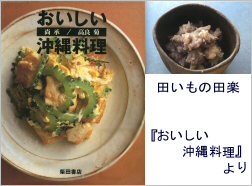 ちなみに沖縄にはおでんというよりキントンみたいな「田芋の田楽」がありますが、その一方で豚足の入ったご当地おでんがあります。台湾でも「黒輪」(オーレン)という名前で知られており、暖かい地方でも食べられているんですね。寒い韓国ならなおのことで、日本語そのままの「おでん」で通じてしまうのですが、つい先日、フジテレビの朝番組で韓国が起源かもしれないなんて、まったくもって不勉強なコメントをしてたそうです。でもWikiの一件を思うと笑えなくなっちゃったなあ。
ちなみに沖縄にはおでんというよりキントンみたいな「田芋の田楽」がありますが、その一方で豚足の入ったご当地おでんがあります。台湾でも「黒輪」(オーレン)という名前で知られており、暖かい地方でも食べられているんですね。寒い韓国ならなおのことで、日本語そのままの「おでん」で通じてしまうのですが、つい先日、フジテレビの朝番組で韓国が起源かもしれないなんて、まったくもって不勉強なコメントをしてたそうです。でもWikiの一件を思うと笑えなくなっちゃったなあ。
どこが起源だなんて意地の張り合いはさておいて、それぞれの地方の個性をいろいろ楽しみたいよねえ。コンビニの商品開発の工夫をレポートする『セブン‐イレブンおでん部会』によると、同チェーンでは2006年からつゆの種類を地方によって6種類に分けているそうです。ためしに大阪出張のついでに食べてみたら、確かにつゆが淡くて淡口醤油ベースな感じ。最近つけてくれるようになった薬味の柚子コショウも、香りがよくって芥子とも違ったアクセントになっていてなかなかおいしい。サンクスはこのところ「チビ太のおでん」なんてテーマで新商品を毎年送り出しているし。おでんの多様な進化、恐るべし。
「さあて今度はコタツでおでんといこうかしら、極楽、極楽、よくぞ日本に生まれけり」と調子にのっていると、「イランにもコルシィーがあるぞよ」という天の声が。イランでもカスピ海沿岸の田舎には水田が広がって柿がなっていて、山に行けばスキーだってできるそうですが、まさかコタツまであろうとは。まあ、写真をごろうじろ。左はイラン最後の皇帝が使っていた冬の宮殿にあるコタツで、高級北欧家具と言われても信じてしまいそう。右は家庭の別荘(!)にある現役のコタツです。床に敷くのはペルシャ絨毯か? わが家の最新家具調コタツがびんぼくさく見えます。なんでもかんでも自分のところが起源で一番で、よそに同じものなどないと思ったら大間違い。井戸の中の蛙、コタツの中のなまけものでありました。

ならばと手当たり次第に寒そうな国名とコタツを組み合わせて検索してみると、民族衣装をまとった人たちのコタツムリ姿が…。アフガニスタンやウズベキスタンには日本そっくりのサンダリが。さらにスペインにはブラセーロという、クロスをかけたテーブルの下に入れる火鉢みたいなものがあるそうです。洋式ゴタツ! なにかと本場のものを取り入れるのに目がない日本のスペイン料理店なら見ることができるのでしょうか。どなたか情報をお待ちしております。
投稿者 webmaster : 10:25
2012年02月16日
料理本のソムリエ [vol.38]
【 vol.38 】
閉じ蓋じゃなくて綴じ蓋なのが日本風
いやいやいや寒いですねー。雪が降った日の朝には会社近くの不忍池も凍ったそうですよ。それでもこの冬は被災地の人たちの苦労を思えばと、社内の暖房の設定は低めをキープ。もっとも自宅は低めどころじゃありません。台所にあるエアコンの使用を控えていたのですが、さすがに正月くらいはね…と再稼動させたらみごとに故障してしまったのですよ。今では日中でも室内温度は10℃を切るのが当たり前で、5℃以下の日だって少なくない。まあ、雪国暮らしの人にとっては暖房がないなんて死活問題であり、東京ならではの贅沢な悩みですが。こいつぁ酒を飲むのにいい口実ができたわいとうそぶいてみたものの、ごめんなさい、あんまり寒いとちょっと飲んだくらいじゃあ足の先があったまらないことを身をもって知りました。子供の頃は、朝起きると部屋の温度計は氷点下だったぞと兄は笑いますが、あんた山小屋じゃあるまいし…。
この機に省エネが自慢の新しいエアコンを購入しようかとも思いましたが、あれって古い機械をはずして破棄して新しいのを取り付けて…とそのたびに、別途料金がみるみるかさんでいくんですねえ。まだ買って7年半だぞ(半泣き)。去年も故障したくせに。エアコンの平均寿命は約10年と聞いていたのに。○発は40年どころか60年だって使う気まんまんなのに。まあ廃炉するには金がかかるってえのは至極当たり前で、いつかは払うべきコストなんでしょうが、想定外の出費は頭も懐も痛いです。
とりあえずほこりだらけの電気ストーブを引っ張り出してはきたものの、これも結構電気を食う割にはあったまるのは局部的。おかげでガスコンロに感謝する毎日です。ことこと煮続ける煮込みや大鍋で湯を沸かす麺類がここぞとばかり威力を発揮します。蓋をしてない鍋で粥を作っただけで気が遠くなるかと思った、あのうだるように暑い8月の夜のことが嘘のよう。ということでvol.27で予告したままほっぽりだしておいた蓋について、今こそ考察いたしましょう。
蓋は鍋の暖房効果と加湿機能を調節する道具…、じゃなくって熱が逃げるのと煮詰まるのを防ぐ道具ですね。ところが取材をしていると日本料理店ってあんまり蓋を見かけません。それどころか柄も耳(取っ手)もないボウルみたいな愛想のない鍋が使われていまして、初めて見たときはたまげました。これはやっとこで鍋の縁を挟んで移動させます。煮詰まってきた汁を煮物全体に回したいときには、やっとこを握った手首のスナップで器用に鍋をくるくる傾けます。
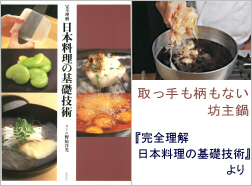 このボウルみたいな丸鍋(坊主鍋ともいいます)は、少しずつ大きさが違っていれば入れ子にして重ねて仕舞えるので、スタック性がよいのが長所です。少しずつ大きさの異なる蓋を用意するのは面倒ですから、適当な大きさの蓋で兼用したりします。
このボウルみたいな丸鍋(坊主鍋ともいいます)は、少しずつ大きさが違っていれば入れ子にして重ねて仕舞えるので、スタック性がよいのが長所です。少しずつ大きさの異なる蓋を用意するのは面倒ですから、適当な大きさの蓋で兼用したりします。
だから鍋の数より蓋が少ないんですね。もちろんプロの厨房にも行平みたいに柄のある鍋もありますが、はまっているべき木製の柄が邪魔なのか抜いてあったりします。
その点、西洋料理の鍋は金属製の丈夫な柄や耳があって当たり前。ピカピカに磨いたソースパンは壁やダクトのフードにずらりとぶら下げるのが流儀でして、邪魔になるわけでもありません。蓋は兼用もいたしますが、鍋にぴったりはまる形で、日本料理よりは使用頻度が高いです。最近はお惣菜屋さんでも見かけるラタトゥイユは、赤ピーマンやズッキーニを鍋で煮込みますが、その際に水は加えず、素材自身の持つ水分で蒸し煮にします。フランス料理で「エテュヴェ」と呼ばれる調理技法でして、蓋の密閉性が高い必要があります。
そもそも日本の鍋蓋は元は木製ですからそんなに密閉性は高くないですね。宮本武蔵が切りつけた刀を塚原卜伝がはっしと受けるあれです。蓋の裏にカッと刃がくいこみ、二人がぴたりと動きを止めるから絵になるのでありまして、もし金属製だとしたら、カアァァァァン…と耳障りな音を立てて刀がはじかれ、武蔵がのけぞり結構間抜け。刃こぼれしたのに逆上して二の太刀で切りかかってくるかもしれません。
なるほど江戸時代の料理本の挿絵を見ていると、鍋墨で黒くなった鉄製の耳つきで、木の蓋がしてある鍋がほとんどです。耳のところにつるをつけてぶら下げて持ち歩いたり、自在鉤にひっかけて囲炉裏にぶら下げられる形です。取っ手も柄も蓋もないボウルみたいな丸鍋が幅をきかせるようになったのはいつ頃からなんでしょう。
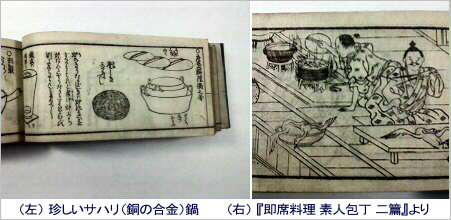
法政大学出版局の『鍋・釜』によりますと、西洋では鍋は鍛造で、鍛冶屋さんがとんてんかんてん叩いて作るものですが、東洋では鋳造で鋳かけ屋さんが作るものだそうです。南部鉄瓶からわかるように、鋳物の鍋は分厚めでかなり重い。やっとこで持ち上げるにはちょっとしんどいです。となると入れ子式全盛はアルミ鍋の普及あたりがターニングポイントのような気もしますが、確証はありません。なにせ考古遺物や民俗資料ならいざ知らず、近代の鍋を扱う酔狂な本は少ないし…。数少ない鍋の専書の一つであるこの本によると韓国では蓋は鉄製なのに対し、中国は木製だそうです。そういえば中華鍋も基本は蓋をしませんね。
ちなみに韓国ではオンドルで家を暖めるので各部屋の前にかまどがあるため、釜型の鍋が使われるのだとか。日本でも、UFOみたいにでっぱりのついた羽釜がすっぽりはまるかまどはおなじみですよね。羽釜の場合はぶ厚くて重い木蓋を使いますが、これは吹きこぼれて持ち上がらないようにした専用の蓋です。もっとも釜は元は湯を沸かす道具だったそうです。そういえばそばやうどんや石川五右衛門をゆでるのは釜だものね。この場合は蓋はしませんね。
ただし韓国はちょっと例外でして、世界的には北の国ほどつる下げタイプの鍋が使われるのだそうです。『オールカラー世界台所博物館』で宮崎玲子氏は、北緯40度以北ではつる下げ式が多くなるという説を打ち立てています。そのため南北に長い日本では、かまどや五徳、七輪に置く鍋と、自在鉤でつる下げる鍋とが共存してまして、つる下げ式は東日本に多いとか。
しかしなぜまた鍋の使われ方に緯度が関わるのでしょう。鍋をつる下げておく囲炉裏や暖炉は、室内の照明を兼ねているのがその理由。のっけてしまうと鍋で火が覆われて明るくなりませんから。緯度が高くなるほど夜の時間が長くなるので、照明の役目が重要になってくるというわけ。
それじゃあ柄のついたフランス料理の鍋はどうやってぶら下げるのだという物言いがあるかと思いますが、これはオーブンの上にのっけて使えるように発達したものです。暖炉で暖と灯りをとる必要性がなくなった、ストーブとランプの時代のものなんですね。もっとも暖炉の中は灰かぐらが立ちやすいから、つる下げ式の時代も蓋は必需品だったのではないかと思いますが。
この本は宮崎氏が世界各地で写した民族博物館や家庭の厨房の写真がずらっと並んでいまして、よそのお宅を覗くようでなかなか面白い。北の国にいけば台所が暖房も兼ねていたわけで、寝室の構造にも影響(シンデレラがどこで眠っていたかとか)しているようです。
一方暑い国はといいますと台所は別棟だったり、七輪のように室外に持ち出せたりして、熱がこもらないように配慮されています。この場合の鍋は火床の上に置くタイプ。また調理方法も短時間で一気に、という方向になるようです。となると中国料理は南方系の影響があるのかなあ。まあ中国料理の加熱方法に関しては歴史的変遷もあるので、結論はちょっと保留したほうがいいかも。そもそも華麗に食材が宙を舞う中国料理店のおなじみの光景も、四千年の昔から見られたものでしょうか。鋳物の鍋を軽々と振っていたというのはちょっと考えづらいです(昔の料理人はよほど力持ちだったのか?)。今の中華鍋は鍛造なのですが、いつ変わったのでしょう?
暑い国の代表であるインドはといいますと、鍋は当然火床に置くタイプで、なんと移動はやっとこ式。インドのカレーが欧風カレーのように延々煮込まないのは、スパイスの香りがとぶからだと思っていたら、台所の環境もからんでいたのですね。ただしインドでもサブジのように蒸し煮にする料理もありますが、そのときには鍋の蓋に水を少量張ったりするのだそうです。元は鍋の周りが暑くて始めたのかもしれませんが、水があれば鍋が過熱しすぎて焦げ付くのを防げる点で、なかなか理にかなっていますね。
 実はこの蓋に水を張る方式、日本料理店でも行なわないわけではありません。ぴったり蓋をして煮続けたい場合に「二枚鍋」(湯煎じゃないですよ)という方法があります。鍋の縁にぬらした布巾を巻いて上から蓋代わりの鍋を重ねます。さらに上にのせた鍋に水を張っておきますと、下の鍋の中の蒸気が蓋で冷やされて吹きこぼれずに、沸騰寸前の状態を保ったまま煮ることができるのです。また煮詰まるのを防ぎたい場合、「油蓋」なんて技法もあります。液面に油を流して蓋代わりにするのです。
実はこの蓋に水を張る方式、日本料理店でも行なわないわけではありません。ぴったり蓋をして煮続けたい場合に「二枚鍋」(湯煎じゃないですよ)という方法があります。鍋の縁にぬらした布巾を巻いて上から蓋代わりの鍋を重ねます。さらに上にのせた鍋に水を張っておきますと、下の鍋の中の蒸気が蓋で冷やされて吹きこぼれずに、沸騰寸前の状態を保ったまま煮ることができるのです。また煮詰まるのを防ぎたい場合、「油蓋」なんて技法もあります。液面に油を流して蓋代わりにするのです。
日本料理店では蓋の出番があまりない一方で、デリケートな蓋の使い方をするのが妙なところ(奇妙じゃなくって妙技の意味ですよ)。たとえば素材が浮かないように落とし蓋なんてものがありますよね。これにもいろいろ使い分けがありまして、柔らかくてくずれやすいアナゴを煮るときはぶつかって崩れないように薄くて柔らかい経木で蓋をしますし、ニシンを煮るのに昆布を落とし蓋代わりに使う「昆布蓋」をする方法もあります。黒豆の場合は厚めの和紙を浮かべます。この「紙蓋」には蜜がしみこみますので、蓋と接触している黒豆にも味がちゃんとしみるというわけです。
実は取っ手なしの丸鍋を使うのは関西系のお店の習慣です。関西料理では「鍋止め」といいまして、煮汁に浸けっぱなしにして冷ます間に味を染み込ませることが多い。そのため厨房に鍋がぞろぞろ並ぶので、柄や取っ手は邪魔に思われたのかもしれません。ましてや西日本はもともと鍋をつる下げない文化なわけですから。
もっとも鍋をつる下げるか、火床に置くかの違いは、蓋をしない理由とはそんなに関係なさそう。蓋をとってかき混ぜ続けなければ焦げつく料理って、あんこを炊くときや、葛を練るときくらいに限られているしねえ。蓋の有無は煮つめるかどうか(水を蒸発させるかどうか)も関わってくるのでは。というわけで鍋と蓋をめぐる謎は深まるばかり。続きはまた次の機会に。
投稿者 webmaster : 16:05
2012年02月01日
料理本のソムリエ [vol.37]
【 vol.37 】
カレーとボルシチと中華饅頭が
ひとつの店に同居するわけ
前回、“ひょんなことから相馬家の食客になった…”と思いっきりはしょらせてもらった、インド独立運動家のラス・ビハリ・ボースと新宿中村屋の縁。実はこの“ひょん”の部分を細かく掘り下げると本が1冊できてしまいます。ホントの話でして、白水社刊の『中村屋のボース』がそれです。日本政府に利用されつつもいかに独立のため戦い続けたか…彼の姿を軸に、戦前の日本におけるインド独立運動をまとめた新進研究者の力作です。
インド総督の爆殺や独立蜂起を計画した若き日のボースは、イギリス植民地政府に追われる身。大正3(1914)年に日本に渡りますが、当時イギリスと同盟を結んでいた日本政府は国外退去命令を出します。オウムの平田君風情とは比べものにならない重要人物を、大国の顔色をうかがう政府の手から守り、民族独立という大義に賛同してかくまう。そんな気骨あるパン屋が中村屋の相馬愛蔵・黒光夫婦でして、当時の人たちからも喝采を浴びました。この本にはサスペンスドラマよろしく、右翼の大物の頭山満宅に居たボースを捕らえようとする警察からの脱出劇や、相馬家での潜伏生活に関する考察もあります。
明治大正時代のインドは、お釈迦様の国として日本人から今以上に親しみと尊敬を向けられており、右翼も社会主義者もその独立を支援する空気がありました。たとえばvol34でちょっと触れた禄亭こと大石誠之助は、明治23(1890)年に渡米してオレゴン大とモントリオール大で学んだ医学者でして、のちにシンガポールとボンペイに渡り、熱帯の風土病を研究しています。そんな彼が社会主義に関心をもったのは、インド時代に見たイギリスの植民地経営に対する義憤から。ちなみに大石はアメリカ留学中に苦学していて家政夫として働いた経験があり、インドからの帰国後には甥の西村伊作(御茶ノ水の文化学園の創立者ですね)とともにレストラン「太平洋食堂」を和歌山に開いたりもしております。妻が作る料理には満足いかずに自分で厨房に立ち、「カレーライスにウニと海苔をかけると至極結構です」と『家庭雑誌』で紹介した大石は、なかなかのグルメではないかとお見受けしております(試してみたらテレビのちょい足しなんぞよりもずっといけました)。なにせ禄亭という号は、都々逸の師匠の鶯亭金升から授かったものですが、この人がまた食いしん坊だからねえ…。
おっと寄り道はこれくらいにしてボースをかくまった相馬夫妻についてでありますが、かなり変わった経歴の持ち主です。愛蔵は内村鑑三の薫陶を受け、長野で養蚕指導をしていた農村改革運動家。妻の黒光のほうはなんだか武将みたいな名前ですが、本名は“良”でして、“こっこう”は『女学雑誌』への寄稿でついたペンネームです。相馬黒光については多くの本が出版されており、聞き語りの回想録『黙移』は平凡社ライブラリーや日本図書センターの自伝シリーズにも入っていますが、彼女の個人史を通観するのであれば、宇佐美承氏の『新宿中村屋 相馬黒光』がよいでしょう。ただし400ページ以上もある厚いこの本の中で、ボースはごく一部に登場するにすぎません。なにしろ相馬黒光の一生は、朝の連続ドラマのモデルにしようものなら1年かけて放送しても終わらないほどエピソードがてんこ盛り。ハードな展開にお茶の間から「朝っぱらからこんな重い話は…」と非難囂々まちがいなしでしょう。
 そもそも中村屋の始まりは本郷の東大正門前にあったパン屋さん。上野の東京芸大にもパンを納める(木炭画に必要ですからね)地元では知られた店でした。ところが元のオーナーの中村萬一氏が米相場で失敗して売りに出されます。それを明治34(1901)年に32歳の相馬愛蔵が購入し、屋号とともに引き継ぎました。東京専門学校(早稲田の前身)を卒業して札幌農学校で養蚕を学んだ愛蔵と、宮城女学校とフェリスを飛び出して明治女学校で学んだ黒光ですから、客商売は初めての経験です。それでも明治37(1904)年シュークリームをヒントにクリームパンとクリームワップル(なぜかワッフルではないんですねえ)を発明して大ヒットさせます。なお中村屋のクリームパンは丸くて、今のようなグローブみたいな形ではありませんでした。クリームは焼くと蒸気が出るので、空気抜きとして切れ目を入れていたのが、あの形に発展したそうです。
そもそも中村屋の始まりは本郷の東大正門前にあったパン屋さん。上野の東京芸大にもパンを納める(木炭画に必要ですからね)地元では知られた店でした。ところが元のオーナーの中村萬一氏が米相場で失敗して売りに出されます。それを明治34(1901)年に32歳の相馬愛蔵が購入し、屋号とともに引き継ぎました。東京専門学校(早稲田の前身)を卒業して札幌農学校で養蚕を学んだ愛蔵と、宮城女学校とフェリスを飛び出して明治女学校で学んだ黒光ですから、客商売は初めての経験です。それでも明治37(1904)年シュークリームをヒントにクリームパンとクリームワップル(なぜかワッフルではないんですねえ)を発明して大ヒットさせます。なお中村屋のクリームパンは丸くて、今のようなグローブみたいな形ではありませんでした。クリームは焼くと蒸気が出るので、空気抜きとして切れ目を入れていたのが、あの形に発展したそうです。
 相馬夫婦はパンがあまり売れない冬の売り上げを伸ばすために和菓子の分野にも乗り出すなど、型にとらわれないアイデアでぐんぐん店を大きくしていきます。明治42(1909)年には新宿に支店を開き、翌々年には今の場所に移って本店にします。新宿が今のような大繁華街になるはるか以前、街道沿いの土ぼこりっぽい町で、紀伊国屋書店さんがまだ炭屋だった時代にもかかわらず、当地の将来性を見抜いたのですからたいしたもの。新宿では彫刻家の荻原碌山や画家の中村彝にアトリエを貸したり(ボースが隠れたのもここでした)、店の2階をロシア文学研究会の会場として提供して、秋田雨雀や島村抱月などのいろいろな文化人と交流します。ちょっとvol12の「メイゾン鴻乃巣」を彷彿とさせますね。
相馬夫婦はパンがあまり売れない冬の売り上げを伸ばすために和菓子の分野にも乗り出すなど、型にとらわれないアイデアでぐんぐん店を大きくしていきます。明治42(1909)年には新宿に支店を開き、翌々年には今の場所に移って本店にします。新宿が今のような大繁華街になるはるか以前、街道沿いの土ぼこりっぽい町で、紀伊国屋書店さんがまだ炭屋だった時代にもかかわらず、当地の将来性を見抜いたのですからたいしたもの。新宿では彫刻家の荻原碌山や画家の中村彝にアトリエを貸したり(ボースが隠れたのもここでした)、店の2階をロシア文学研究会の会場として提供して、秋田雨雀や島村抱月などのいろいろな文化人と交流します。ちょっとvol12の「メイゾン鴻乃巣」を彷彿とさせますね。
夢見勝ちでどこか風来坊の愛蔵と姉御肌で外交的な黒光のコンビは、多くの人たちと出会い、その経験をもとに、店で取り扱う商品をどんどん広げていきました。ちょっと見ただけではいろいろな国の食文化の寄せ集めのように思えますが、実はひとつひとつに濃厚なエピソードと必然性がついてまいります。
 たとえば中華饅頭は、新宿に百貨店が進出してきてピンチに陥った相馬夫妻が、大陸視察旅行中にヒントを得て取り入れたもの。菓子職人を中国から呼び寄せようとしたところ、前例がなくて労働許可がおりなかったために、じゃあ料理店なら問題なかろうと、厨房も作って中国料理も提供し始めてしまいます。水羊羹の缶詰はブラジルに渡って夭折した息子のことを思って、日本の味を海外に届けられるように開発したものです。
たとえば中華饅頭は、新宿に百貨店が進出してきてピンチに陥った相馬夫妻が、大陸視察旅行中にヒントを得て取り入れたもの。菓子職人を中国から呼び寄せようとしたところ、前例がなくて労働許可がおりなかったために、じゃあ料理店なら問題なかろうと、厨房も作って中国料理も提供し始めてしまいます。水羊羹の缶詰はブラジルに渡って夭折した息子のことを思って、日本の味を海外に届けられるように開発したものです。
 中村屋の喫茶部のメニューにはボルシチがありますが、これはボースの後に食客となったロシアの盲目詩人、エロシェンコから学んだもの。海外から船便で運んでいては提供できない生チョコレートを自社で製造すべく、破格の給料でロシア人の菓子職人も雇います。ついでにペチェーニエ(焼き菓子)やガドセック(ガトーセック?)といったロシア菓子も販売しており、これらがロシアクッキーやロシアケーキといったどこか懐かしい日本の洋菓子の源流となったもようです。なお現在新宿中村屋ではロシア菓子は販売しておりませんが、千葉の館山の中村屋さんで味わうことができます。新宿移転後の本郷店をまかされたのは、生え抜きの店員だった「みいどん」こと長束實氏。4畳半に住み込みの従業員、3畳間に相馬夫婦と息子が生活していた本郷時代に苦楽をともにしたスタッフの一人です。その息子の七郎氏の代に当地に移りまして、ロシア菓子の技術を今に伝えているのです。
中村屋の喫茶部のメニューにはボルシチがありますが、これはボースの後に食客となったロシアの盲目詩人、エロシェンコから学んだもの。海外から船便で運んでいては提供できない生チョコレートを自社で製造すべく、破格の給料でロシア人の菓子職人も雇います。ついでにペチェーニエ(焼き菓子)やガドセック(ガトーセック?)といったロシア菓子も販売しており、これらがロシアクッキーやロシアケーキといったどこか懐かしい日本の洋菓子の源流となったもようです。なお現在新宿中村屋ではロシア菓子は販売しておりませんが、千葉の館山の中村屋さんで味わうことができます。新宿移転後の本郷店をまかされたのは、生え抜きの店員だった「みいどん」こと長束實氏。4畳半に住み込みの従業員、3畳間に相馬夫婦と息子が生活していた本郷時代に苦楽をともにしたスタッフの一人です。その息子の七郎氏の代に当地に移りまして、ロシア菓子の技術を今に伝えているのです。
ちなみに山崎製パンや進々堂の初代社長も中村屋の出身。社員の独立は中村屋の社是でもあり、21歳までは月給の3分の2、27歳までは半分を資金として貯金する制度がありました。そのほか、従業員全員に自社株をもたせたり、売上高に応じて配当を出したリ、従業員のために学校を設立したり、亡くなった社員の慰霊祭を毎年行なったり(長束實氏もその一人)と、やることなすこと桁はずれ。“企業は人なり”をモットーに、廉価販売やリベートを許さなかった中村愛蔵の経営精神については、岩波書店の『一商人として』にまとめられており、『相馬愛蔵・黒光著作集2』にも収録されています。
また実際に中村屋に勤めていたスタッフの回想としては、同社菓子部門だった関口保氏による『ピロシキとチョコレート』があります。この本は同じ話が何度もでてきたり、“前に書いたように”とあるのにどこにも見当たらなかったりと、本としての出来がよくないのが残念ですが(編集者出てこーい)、戦前の中村屋の空気を伝えてくれる貴重な証言です。前回のゴロナのエピソードもこの本に出てまいります。
関口氏から見た愛蔵と黒光はなかなか厳しい人でもありましたが、いかにも明治男と明治女らしい感じですね。戦中は食材の調達に苦労したうえ、過労から娘婿のボースを亡くし、戦後も新宿駅前を占拠して闇市を開いていたやくざと法廷で争ったりと、苦労は続きますが、けっしてくじけず見事に会社を復活させてみせました。
ところでボースの同志の一人にインドから京都大学へ留学していたA.M.ナイルがおります。彼は昭和3(1928)年に中村屋でボースに出会い、その人となりと行動力に感銘を受けます。卒業後は満州国に渡り、ラマ僧やイスラム教徒などに扮してモンゴルで対英工作活動を行ない、戦後は東京裁判のパール判事の通訳を務めたりもいたします。こちらは朝の連続ドラマどころか007の映画に登場しそう(あっ、でも敵役になっちゃう…)。ところがインド政府を牛耳る国民会議派からはうとまれ、帰国がかなったのは実に祖国独立の14年後。のちに彼は『知られざるインド独立闘争―A.M.ナイル回想録』で、文字通りインド独立運動に殉じたボースを正しく評価するよう訴えています。
 この革命志士が、日々の糧を得るためのよすがとして44歳のときに開いたのが銀座の「ナイルレストラン」です。目玉焼きも作れないA.M.ナイルをサポートして、今のような有名店に育てた2代目のG.M.ナイルは、テレビなどにもよく登場するのでご存じかもしれませんね。『ナイルさんのカレー天国!!』で面白おかしく描かれているように、自ら“変なインド人”を演じる、取材慣れしたタレント気取りの経営者という印象を持つ人も多いかも。
この革命志士が、日々の糧を得るためのよすがとして44歳のときに開いたのが銀座の「ナイルレストラン」です。目玉焼きも作れないA.M.ナイルをサポートして、今のような有名店に育てた2代目のG.M.ナイルは、テレビなどにもよく登場するのでご存じかもしれませんね。『ナイルさんのカレー天国!!』で面白おかしく描かれているように、自ら“変なインド人”を演じる、取材慣れしたタレント気取りの経営者という印象を持つ人も多いかも。
こうした色眼鏡を吹き飛ばすのが、昨年出版された『銀座ナイルレストラン物語』です。インド料理専門店の先駆者であるG.M.ナイルの破天荒な性格と人生は、波乱万丈の初代にもなかなか負けておりません。初代にとっての料理店経営は意図せず迎えた第二の人生でしたが、2代目にとっては、戦後の混乱をたくましくのりきってきたわが家そのもの。学生時代から店に立ち、カレー粉を輸入し、インドから料理人を招聘するルートを開拓するなど、日本とインドの間に立って苦労してきたからこそ、彼は自信たっぷりでテレビカメラの前に立つことができたのです。ところが全力を注いできたこの店は、あろうことか平成9(1997)年に隣家の火事で焼けてしまいます。茫然自失の彼を尻目に、地上げを狙ってうごめくやくざたち。店舗存続の最大の危機が訪れ……おっとネタばれはこれくらいで。
さまざまな商品展開を行なった中村屋と、たとえインドから料理人を招いてもひたすらカレー一本に絞ってきたナイルレストランとでは、商売の仕方がずいぶん違いますが、どちらも個性的でスケールの大きい経営者であることはまちがいない。「不況に強そうだから外食でもやってみるか」というデモシカ経営者や、ネットの世界に向かってつぶやくばかりの国士きどりたちは、まずは刺激たっぷりなカレーを食べて目を覚ましてくださいね。
投稿者 webmaster : 12:47
2012年01月17日
料理本のソムリエ [ vol.36]
【 vol.36 】
恋と革命は、サラリとして辛口なもの
あけましておめでとうございます…からずいぶん経ちましたね。
みなさん、おせちやカレーはお腹一杯召し上がりましたか? 年もあらたまったというのに当ブログは昨年の話の続きであります。
 実は前回、国際こども図書館に所蔵されているカレー本であえて採り上げなかったものがありました。辛島昇先生の岩波ジュニア新書『インド・カレー紀行』です。この本、ジュニア向けなものですから国会図書館のほうでは所蔵しておりませんし、辛島っていう姓がなんだかペンネーム風だしで、「口当たりのよいやさしい内容だろう」となめてかかると痛い目にあいますよ。岩波ジュニア新書のシリーズは普通の岩波新書より字が大きくて写真がたんまり使われておりますが、時々とんでもないハードな内容のものもまじっておりまして、この本も、昨今の新書(タイトルが無駄に長かったり疑問形だったりするやつ)ですら読むのが億劫という子供舌の人にはお勧めできません。辛島教授は押しも押されもせぬインド史の第一人者でして、取り上げる資料はインドにとどまらず、『エリュトゥラー海案内記』だの『諸蕃志』だのギリシャや中国の文献までぽんぽん出てきます。とはいえ机の上の世界にとどまらず、インド留学時代の寮の食事やスリランカでの客員教授時代の見聞、料理の具体的なレシピなどを盛り込んでおり、読みやすさにも配慮されております。
実は前回、国際こども図書館に所蔵されているカレー本であえて採り上げなかったものがありました。辛島昇先生の岩波ジュニア新書『インド・カレー紀行』です。この本、ジュニア向けなものですから国会図書館のほうでは所蔵しておりませんし、辛島っていう姓がなんだかペンネーム風だしで、「口当たりのよいやさしい内容だろう」となめてかかると痛い目にあいますよ。岩波ジュニア新書のシリーズは普通の岩波新書より字が大きくて写真がたんまり使われておりますが、時々とんでもないハードな内容のものもまじっておりまして、この本も、昨今の新書(タイトルが無駄に長かったり疑問形だったりするやつ)ですら読むのが億劫という子供舌の人にはお勧めできません。辛島教授は押しも押されもせぬインド史の第一人者でして、取り上げる資料はインドにとどまらず、『エリュトゥラー海案内記』だの『諸蕃志』だのギリシャや中国の文献までぽんぽん出てきます。とはいえ机の上の世界にとどまらず、インド留学時代の寮の食事やスリランカでの客員教授時代の見聞、料理の具体的なレシピなどを盛り込んでおり、読みやすさにも配慮されております。
そもそもインドにはカレーっていう料理は存在しない、という話は皆さんどこかでお聞きおよびかと思います。本来は個別にちゃんと料理名がある各種インド料理を、ややこしくって面倒だとばかりに「カレー」で総称しちゃったんですね。大阪のおかんにとってゲーム機は、PS Vitaだろうとドリームキャストだろうと「ピコピコ」なのと同じ心理ですな。
それではこの料理名は何からつけられたのか。本書にはそれに関する考証もあります。インドのスパイシーな汁たっぷりの料理をカリル(karil)と呼び始めたのはポルトガル人。その理由はインドではソースのことをカリーと呼んでいたため…とする説もありますが、南インドのタミル語やカンナダ語の辞書には“kari”は野菜、肉、コショウの意味とあって、ソースではないそうです。野菜と肉とコショウが同じ単語で表現されるとはいったいどういうこと?という疑問がわきますが、辛島教授はスープ料理の具をカリと呼んだのが、ポルトガル人に誤解されて料理名として伝わったのではないかという仮説を立てています。
本書はこのように料理を通してインドの文化交流史を語る内容でして、ちょっとやそっとの辛さや知的刺激では物足りないカレーマニアも満足いく内容になっております。カレー屋さんにいくとシークカバブだのビリヤニだの、やけに中東料理に似た料理を見かけると思ったら、ペルシア文化の影響を受けたムガール帝国の遺産なのだとか。日本人の抱くインド像というのはステレオタイプなものですが、実は文化も料理も多彩かつ重層的で、一筋縄ではいきません。
さて、そんな辛島先生もお勧めなのが、『インドカレー伝』。こちらはさらにインド料理と歴史との関わりに焦点を絞って考察したもので、翻訳書なので厚くて注もびっしり。辛島教授の本と比べて辛さ…じゃなかった難易度3倍ってとこでしょうか。ポルトガルやイギリスの植民地文化にまで考察を広げているのが特徴です。
 カレーがイギリスに渡って小麦粉のルーでとろみをつけるシチューっぽい料理に変わったのと同じように、カツレツがインドではスパイシーにアレンジされたりと、相互に交流があったりします。酸っぱくて辛いのが特徴のビンダルーの原型は、ポルトガル料理のカルネ・デ・ヴィーニョ・エ・アリョスなんですねえ。どこのおかんのせいでこんなに短い名前になっちゃったんでしょう。
カレーがイギリスに渡って小麦粉のルーでとろみをつけるシチューっぽい料理に変わったのと同じように、カツレツがインドではスパイシーにアレンジされたりと、相互に交流があったりします。酸っぱくて辛いのが特徴のビンダルーの原型は、ポルトガル料理のカルネ・デ・ヴィーニョ・エ・アリョスなんですねえ。どこのおかんのせいでこんなに短い名前になっちゃったんでしょう。
ポルトガルの植民地文化の料理は、はるか昔の戦国時代に日本に伝わった可能性がありますが、この分野を扱った本はこれまで見あたらなかったので、干天の慈雨であります。大げさですって? いえいえ、こちとら大真面目です。たとえばスリランカにもポルトガルから伝わったテンプラードワという料理があると『南の島のカレーライス』にありました。これはポルトガル語の「味をつけた、調理した」という意味のテンペラードゥからきていて、油炒めのことだそうです。現在天ぷらの語源については諸説ありますが、これは実に興味深い報告です。あ、ちなみにこの本、カレーライスというタイトルではありますが、スリランカ料理全般について考察したものでありまして、ココナツやモルディブ・フィッシュ(スリランカの鰹節)を活用するこの国の料理はインドとはまた異なる体系をもっています。
さて日本にインドのカレーを初めて紹介したとされるのが、ラス・ビハリ・ボースです。インド独立革命の志士だった彼は日本に逃れ、ひょんなことから新宿でパン屋の「中村屋」を開いていた相馬家の食客となります。のちに帰化して中村屋の娘と結婚したボースは、日本でカレーと呼ばれている食べ物は小麦粉でとろみがつけてあり、母国の料理とほど遠いことに不満をもちます。そこで中村屋が昭和2年に喫茶部を開くにあたって、名物料理としてボース発案のカレー(ただし呼び名はカリーです)を提供し始めたわけです。
 同店がカレーを売り出すにあたっての情熱と力の入れようは、半端なものではありません。具の鶏肉を調達するために専用の農場を開いて軍鶏を飼育し、米は別名“御殿米”と呼ばれた埼玉の“白目米”を使います。ちなみに例の「星岡茶寮」も朝鮮米の早丁租を用いるようになる前は、この白目米を使っていたそうです。
同店がカレーを売り出すにあたっての情熱と力の入れようは、半端なものではありません。具の鶏肉を調達するために専用の農場を開いて軍鶏を飼育し、米は別名“御殿米”と呼ばれた埼玉の“白目米”を使います。ちなみに例の「星岡茶寮」も朝鮮米の早丁租を用いるようになる前は、この白目米を使っていたそうです。
戦前の中村屋のカレーのレシピについては、『カレーなる物語』に昭和7年の『主婦之友』に載ったものが紹介されていますが、ここではせっかくですから開業初期の昭和3年の『婦女界』のレシピをば。『主婦之友』では骨からスープをとったり、ジャガイモを炒めたりしていてこれとは若干違います。大量に仕込まねばならない店のレシピそのままではないでしょうが、多めの油にスパイスの香りを移すところがミソですね。ジャガイモでとろみをつけるのはインド本来のやり方かどうか…。小麦粉のルーに対抗しての措置かもしれません。
鶏はメスの400匁(1500g)ぐらいのサイズで、屠鳥してから6時間くらいのものを使用します。皮ごと骨つきのまま1寸(3cm)くらいのぶつ切りに。タマネギ150匁(562・5g)は四割りにして、1分(3mm)の厚さに小口切りに、ジャガイモ200匁(750g)は皮をむいて2つに切っておきます。バターはたくさん使いまして、鶏に対して2割の80匁(300g)ほどです。鍋に溶かして、タマネギを入れてきつね色に色をつけ、鶏肉を入れて弱火でしばらく加熱します。少し骨ばなれがよくなったところでカレー粉を茶さじ3杯ほど、コショウ、塩を適当に入れ(もし牛乳かヨーグルトがあれば1合ほど入れます)、材料より2寸(6cm)ほど上まで湯を注ぎ、静かに煮ます(水を入れると肉が固くなります)。香料(月桂樹、丁子、肉桂)などがあれば、よく煎じてその汁を少し肉の中に入れます。弱火で1時間ほど煮ると骨ばなれのよい肉になりますから、この時にジャガイモを入れて、柔らかくなって少し形が崩れ、汁がどろりとしてきたら火からおろします。箸休めにはダイコン、キュウリ、トマト、キャベツなどの酢の物を添えます。
なお原文では香料(香辛料)の説明で月桂樹とベイリーブスがだぶって登場しているうえ、煎じ方や使うタイミングがよくわかりません。カレー粉については、インドでは家族の口に合うように14種類を配合するが、日本の家庭で作って好まれるのはBC缶(C&B社)でしょう、とありますが、ちょっと加える量が少ないような気が…。
 当時の茶さじは今でいう小さじにあたるのですが、それにしても…。高価だったせいなのでしょうか。逆にタマネギはもっと多くてもよいのでは? いろいろ疑問に思いつつ再現してみたところ、昨今のジャガイモは優秀なようでしてそう簡単に煮崩れてくれません。
当時の茶さじは今でいう小さじにあたるのですが、それにしても…。高価だったせいなのでしょうか。逆にタマネギはもっと多くてもよいのでは? いろいろ疑問に思いつつ再現してみたところ、昨今のジャガイモは優秀なようでしてそう簡単に煮崩れてくれません。
どろりとするどころかスープカレーよりもスープっぽくなる始末。べ、べつにあんたに食べさせたくて作ったわけじゃないんだからね! このブログってなんか小難しいし、本の映像ばっかりじゃさみしいかなって思っただけなんだから!
とつぜんツンデレ風でごまかしているのは、この印度式カリーのキャッチコピーが「恋と革命の味」だったもんで。中村家に訪問してボース手作りのカレーを実際に食べた子母澤寛の『味覚極楽』によると(『カレーなる物語』ではこれを回想として紹介していますが、それは単行本化の加筆部分のことでして、初出は当時の東京日日新聞の連載記事です。レシピも簡単に紹介していますが、これまた『婦女界』とも違います)、ボースは「本当のカレーはそんなにからいものではない、食べる時にすうーっと甘くて、後から少しずつ辛味が舌に沸いて来るのがいいのです」と語っております…って、しまったあ、これじゃあツンデレの逆じゃないかー。vol.11で触れたパウリスタのコーヒーといい、この時代の恋ってのはずいぶんと大人な味ですなあ。
 一方甘ーい“初恋の味”で一世を風靡したのはカルピスでありますが、この会社が昭和7年から“567十八青春の味”のキャッチコピーで、満を持して売り出した飲み物がゴロナ(5+6+7で18歳ってわけ)です。「星岡茶寮」の納涼宴でも使われましたが、タンニンのオリがたまるために不良品が続出して持て余し、のちに原料や技術をそっくり中村屋にひきとってもらったというエピソードがあるそうです。技術移転を受けた中村屋ではジンをたらすことでオリの発生を防ぎ、喫茶部で提供したとか。ただゴロナって、今でいうガラナのことなんですけど、これってウソかホントか強壮効果があるともいいますよね。“青春の味”ってちょっとストレートすぎますけどよかったのかしら?
一方甘ーい“初恋の味”で一世を風靡したのはカルピスでありますが、この会社が昭和7年から“567十八青春の味”のキャッチコピーで、満を持して売り出した飲み物がゴロナ(5+6+7で18歳ってわけ)です。「星岡茶寮」の納涼宴でも使われましたが、タンニンのオリがたまるために不良品が続出して持て余し、のちに原料や技術をそっくり中村屋にひきとってもらったというエピソードがあるそうです。技術移転を受けた中村屋ではジンをたらすことでオリの発生を防ぎ、喫茶部で提供したとか。ただゴロナって、今でいうガラナのことなんですけど、これってウソかホントか強壮効果があるともいいますよね。“青春の味”ってちょっとストレートすぎますけどよかったのかしら?
ところで中村屋って、中華饅頭や水羊羹の店だとか思ってた方はいませんか? こちらもなめてかかるととんでもないことになりますからね。この話、まだ続きます。
投稿者 webmaster : 17:35
2011年12月21日
料理本のソムリエ [ vol.35]
【 vol.35】
カレーの王子様が
密かに進める日本印度化計画
前回は、最近のカレー本をちょっとくさしたりしましたが、それは歴史に関する記述に限っての話でありまして、実のところ、カレー関係の著作は料理本の中ではまあまあのレベルだと思います(商品開発やテレビ番組への協力などおいしい話がほうぼうに転がっているせいか、片手間仕事になってきている感じの本もおみかけしますが)。欧風カレーやインドカレーなどいろいろなタイプがあって、視野が広くなければならないからでしょうか。
またカレーマニアには自分でも厨房に立つ人たちが多いように思います。食べ歩き本でも作り手の立場から見るので、まがりなりにも分析しようという姿勢がみられますし、自分が好みではない皿に出会っても頭からこれはダメと決めつけない。カレーという料理全般に対する愛情がそこここに感じられます。その点、世の料理評論家と称する方々やグルメサイトの投稿マニアはといいますと…。その昔、カレーを食べすぎると舌が馬鹿になるとか、辛いものを食べすぎると頭が悪くなるとかいう説を聞いたことがあります。もしかしたらですよ、彼らは辛口評論家を名乗ろうとしたあまり、カレーマニアが驚くくらいの尋常ならざる量のカレーを食べて食べて食べまくったのでしょうか。それもきっと自腹で…。なんと過酷な道を選んだ勇者たちか!
カレーはもはや日本の国民食だそうですから、料理本が充実しているのは当然なのかもしれません。みごと国民食の座を勝ち得た理由については、いろいろ言われています。ご飯にかける洋食なので日本人にもなじみがよいから。軍の食事に取り入れられたため兵役経験者を通じて津々浦々まで広まったから。ご飯消費拡大をめざして学校給食に取り入れられたから…などなど。
私はもうひとつ、もともと子供に好まれやすいメニューであったから、というのも挙げたいですね。学童どころか幼児のうちからカレーはおなじみの料理です。のびてしまう麺類と違って冷ましてもそこそこいけますから、猫舌の子供でも大丈夫。箸が使えなくても食べられますし、柔らかい。
握りのおすしは骨はないし手づかみで食べられるのでなかなかの対抗馬ですが、子供の口にはちょっと大きいし、うまく食べないとくずれてしまう。そもそも回らないすし店は、お子様連れはご遠慮願ったりしていてせっかくの市場をスポイルしていますよね。散らしずしで作るものですが、「雛ずし」なんていう習慣があるくらいですから、本来すしは子供となじみがいいのに。小さく握るとネタが多く必要なうえに手間がかかるからですかね?
ラーメンやハンバーグもお子様がたの大好物でありますが、インスタントや冷凍食品となると手抜きという感じがどうしてもしてしまう。その点、カレーなら市販のルーで作れば簡単な割合に豪華そう。野菜もいろいろ入れられるし。レトルトだってこっそり使えば、お母さんの面目が立ちます。一家団欒というイメージもあり、“おふくろの味”の一角を占めるのもむべなるかなであります。
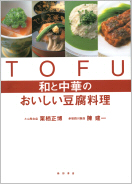 思えば子供向けに特別に仕立てた味でかわいいパッケージの商品が、普通にスーパーにずらっと並んでいるっていうのもなかなか珍しいですよね。一人っ子を大事にする中国に行っても「麻婆豆腐小皇帝」なんて見当たらないものねえ。もっとも、これはこれで売れそうな気もするぞ。子供向けの味つけの麻婆豆腐のレシピは『TOFU和と中華のおいしい豆腐料理』に載っておりますので、中国で商品化を目指す方は勉強してください。
思えば子供向けに特別に仕立てた味でかわいいパッケージの商品が、普通にスーパーにずらっと並んでいるっていうのもなかなか珍しいですよね。一人っ子を大事にする中国に行っても「麻婆豆腐小皇帝」なんて見当たらないものねえ。もっとも、これはこれで売れそうな気もするぞ。子供向けの味つけの麻婆豆腐のレシピは『TOFU和と中華のおいしい豆腐料理』に載っておりますので、中国で商品化を目指す方は勉強してください。
さて本題。こうしたイメージ戦略が効を奏したのか、料理関係の児童書を見ていますとカレー本がやたらに多いことに気づいたのですよ。子供に受けるし、ご両親も買って与えたくなる種類の本なのでしょう。昔はカレーがメインの絵本なんて洒落たものはなかったような気がするのですが、いつの間にやら大増殖しているようです。
 こちとら児童書はまったくの門外漢なものですから、専門図書館へ行ってまいりました。会社から歩いていける上野公園内に「国際子ども図書館」があります。ぞうさんやきりんさんの絵が描かれた原色っぽい建物と思いきや、威風堂々たる重厚なたたずまい。テラスのカフェも併設していて博物館のよう。実はこの建物は明治39年に建てられたもので、つい10年ほど前までは国立国会図書館上野支部だったんです。そういえば児童書専門の神保町ブックハウスも格調高いですが、こちらも元は洋書専門の北沢書店の新刊コーナーでしたっけ。ちょっとよそいきな感じなほうが、やんちゃな子供たちも神妙にしてくれていいかもしれません。ただ吹き抜けで天井が高い石造りの洋風建築は、お子様が泣かれますとわんわん響いてなかなかすごいことになります。
こちとら児童書はまったくの門外漢なものですから、専門図書館へ行ってまいりました。会社から歩いていける上野公園内に「国際子ども図書館」があります。ぞうさんやきりんさんの絵が描かれた原色っぽい建物と思いきや、威風堂々たる重厚なたたずまい。テラスのカフェも併設していて博物館のよう。実はこの建物は明治39年に建てられたもので、つい10年ほど前までは国立国会図書館上野支部だったんです。そういえば児童書専門の神保町ブックハウスも格調高いですが、こちらも元は洋書専門の北沢書店の新刊コーナーでしたっけ。ちょっとよそいきな感じなほうが、やんちゃな子供たちも神妙にしてくれていいかもしれません。ただ吹き抜けで天井が高い石造りの洋風建築は、お子様が泣かれますとわんわん響いてなかなかすごいことになります。
 一方大阪には日本一の蔵書数を誇る「国際児童文学館」がありますが、こっちは立派な本館とは別なところに入口が設けられ、ちょっとちんまりしておりまして、子供向けというよりは研究者向けかも。もともと千里の万博公園内にあったのが、東大阪の府立中央図書館に統合され、建物横にあったレストラン跡に移転したからであります。児童書ってえのは、空いた建物を転用するのが決まりなんですねえ。レストランの居抜きを選んだのは、いま流行りの絵本カフェをめざしたわけではないので、当然カレーメニューもおいてありません。経費節減のためでして、大阪人が好きなんは文楽よりも新喜劇とちゃいまっか、とかいう前知事によるご英断であります。
一方大阪には日本一の蔵書数を誇る「国際児童文学館」がありますが、こっちは立派な本館とは別なところに入口が設けられ、ちょっとちんまりしておりまして、子供向けというよりは研究者向けかも。もともと千里の万博公園内にあったのが、東大阪の府立中央図書館に統合され、建物横にあったレストラン跡に移転したからであります。児童書ってえのは、空いた建物を転用するのが決まりなんですねえ。レストランの居抜きを選んだのは、いま流行りの絵本カフェをめざしたわけではないので、当然カレーメニューもおいてありません。経費節減のためでして、大阪人が好きなんは文楽よりも新喜劇とちゃいまっか、とかいう前知事によるご英断であります。
さてカレーが出てくる児童書ですが、カレー絵本コーナーなんて棚があるわけないし、そもそも専門図書館は原則閉架なので、パソコンの検索機能を使って探すことになります。ところが検索ワードに入れた音引き(“ー”のことです)は省略されてしまうので、うかれだぬきだのおしゃれカレンダーだのカーレンジャーだのすてきな彼だのカレーと関係ないタイトルもぞろぞろ引っかかって、探しづらいこと探しづらいこと…。用語を組み合わせたり絞ったりと苦心して拾い出したのですが、昼間からカレー絵本ばかりをやたらと借り出すおっさんていうのはかなり不気味ですね。
探せば出てくる出てくる。『カレーやしきのまりこさん』『ねえカレーつくってよ』『カレーをつくろう!』『まほうカレー』『カレーライスはこわいぞ』『かえるとカレーライス』などなど…。こうして並べるとひとつのつながったストーリーみたいです。カレー屋敷で作ってもらったカレーを食べたら、魔法にかかって蛙になっちゃった、ってな感じ。
最後の本は実際にはもっとシュールな話でして、山が噴火したらカレーが流れ出てきて、それを蛙が食べるというストーリーです。別に酔っ払っているわけではありません。ナンセンスストーリーを得意とする長新太らしい作品です。文章は落合恵子で、彼が絵のみを手がけた『カレーライスのすきなぺんぎん』も、カレーを食べていたらコップの氷水に小さいペンギンがいたという話。直木賞作家の井上荒野作『ひみつのカレーライス』は、カレーの中から出てきた種を庭に植えたら、カレーの木が生えてきて…。大人的にはこういう理屈抜きの作品が面白いけど、子供受けはどうなんでしょうか。
カレーは不思議なスパイスや外国のイメージと結びつきやすく、魔法や王様となじみがいいことも、絵本や童話のテーマにとりあげられやすい一因でしょう。『いたずらまじょ子とカレーの王子さま』『カレーだいおうのまほう』『王さまのまほうカレー』なんていうのもありました。『王さまのまほうカレー』は絵よりも文字が多い童話ですが、カレー作りに奮闘する王様ストーリーがなかなか読ませます。
ただし『カレーライスは王さまだ』は現実の話であります。給食の調理現場の写真ルポでして、社会科の副読本のようです。人気のカレーにかこつけて、お勉強してもらおうという大人の欲が見え隠れるする本が多いのも、この分野の特徴ですね。もっともカラー写真をふんだんに使ってあったりして、大人の社会科見学みたいで意外と楽しめました。藤田千枝『カレーライスの本』は料理を実験になぞらえて、段取りの大切さを説いたり、加熱で細胞がどう壊れるかを説明したりと、なかなか高度な内容です。
そもそも前回紹介した『カレーライスと日本人』の森枝卓士氏は、この新書本と同時進行で子供向きの『たくさんのふしぎ』という月刊誌にも執筆しておりまして、のちに『カレーライスがやってきた!』というタイトルで独立した本として刊行されております。吉田よし子氏も『カレーライス はじめはどこで生まれたの?』という本を監修しています。カレーを通じて世界の国々や文化を学んでもらおうという企画は結構多い。『おどろうつくろうABC DEカレー』なんていう英語を学べる本もありまして、カレーだけで学校の授業が組めそうなくらいです。
うーん、これだけいろいろあるとなると脳みそは完全にカレー漬け。日本人は将来ますますカレー好きになること間違いありませんな。インドの秘密結社の陰謀でしょうか?
あ、ちなみに私が幼少のみぎりによく読んだ絵本は『モチモチの木』でありました。なぜなら木の実で作るおいしそうなもちが出てくるから。あと絵本といったらこれくらいしか持っていなかったから。ついでに同じ斎藤隆介・滝平二郎コンビの『ちょうちん屋のままッ子』も話の後半で、主人公の長吉が料理店に修業に入るところばかり気に入って繰り返し読んでおりました。そうかあー、器は底の真ん中を一生懸命洗うといいのかあ、とか子供のくせに納得したり。見事に日本料理ファンとして洗脳されております。
さて、この与太ブログの更新も今年はこれでおしまい。最後に明治40年12月30日の読売新聞で紹介されました「ハイカラ年越蕎麦」を紹介いたしましょう。東京割烹女学校が考案したライスカレー式蕎麦料理であります。
 まず豚肉100匁(375g)を細かくつぶし(刃叩き? それともミンチのこと?)、水1升の鍋でアクが煮上がるまで煮上げ、アクをすくい取ります。椎茸20匁(75g)、油揚げ3枚、タマネギ大2個、青カブ大1個を細かくさいの目に切ったものを加えてかき混ぜ、それが柔らかくなるまでもう一度煮上げます。さらにミリン少量を落とし、醤油と食塩を加えて味をととのえます。別に蕎麦の玉10個をざるに入れて熱湯をかけ、湯気をとっておき、かねて煮溶かしたバターの中に入れてかき混ぜ、適宜の容器に盛ります。先の煮上げた材料をかけてできあがりです……ってこれのどこがライスカレー式なのか。上から具をかけているから? それともカレー粉を入れ忘れているんでしょうか…。
まず豚肉100匁(375g)を細かくつぶし(刃叩き? それともミンチのこと?)、水1升の鍋でアクが煮上がるまで煮上げ、アクをすくい取ります。椎茸20匁(75g)、油揚げ3枚、タマネギ大2個、青カブ大1個を細かくさいの目に切ったものを加えてかき混ぜ、それが柔らかくなるまでもう一度煮上げます。さらにミリン少量を落とし、醤油と食塩を加えて味をととのえます。別に蕎麦の玉10個をざるに入れて熱湯をかけ、湯気をとっておき、かねて煮溶かしたバターの中に入れてかき混ぜ、適宜の容器に盛ります。先の煮上げた材料をかけてできあがりです……ってこれのどこがライスカレー式なのか。上から具をかけているから? それともカレー粉を入れ忘れているんでしょうか…。
このレシピの蕎麦はゆでおきのようですが、もちろん普通に乾蕎麦をゆでてもOK。タマネギやカブから甘みが出るので、ミリンは加えなくてもよいかもしれません。ちょっと味が物足りない方は、ほんとにカレー粉を入れてもいいですよ。
ともあれ100年前の“すこぶるハイカった料理”のできあがり。話の種にどうぞお試しください。
投稿者 webmaster : 15:57
2011年12月07日
料理本のソムリエ [ vol.34]
【 vol.34】
第一発見者は別人だった!
船上で侍ボーイが見た謎の外国人、
その手にはいったい何が!?
前回またまたカツ丼の話なんかに寄り道した挙句の果てに、カレー粉の本の話になっちゃいまして、カレーの本は結局まともに登場しませんでしたね。いよいよもってトンカツ偏執者、違ったトンカツ編集者の烙印を押されそうなので、今回こそカレーの本の話といたしましょう。
そもそも私はトンカツじゃなくて、スパイスの歴史を研究して香料諸島に行くのが学生時代の夢だったのですよ。それがどこかで道をまちがえまして、どっちも果たせずになぜかここでこうしてこんなブログを書いています(遠い目)。月刊誌の編集者時代にエスニック特集が組まれたときはそりゃあ嬉しくてサンバルとかカピとか集めて張り切ったものですが、その号はあんまり売れずにがっかりしましたよ(さらに遠い目)。当時としては聞いたこともない香りも知らないスパイスやら調味料の話っていうのは、あんまり関心を引かなかったのかもしれません。
 ですから4年前に小社からカレー専門店から東南アジア料理店まで33店のレシピを集めた『カレーのすべて』が出たときは、読者がついてくるのかひやひやしたものです。ところが意外やアマゾンのレビューをみるとプロ以外の人も買って試しているようで(そのため分量が料理店仕様で多すぎるとかいう不評もありますが、これは小社の本の宿命でして…)、隔世の感がありますねえ。
ですから4年前に小社からカレー専門店から東南アジア料理店まで33店のレシピを集めた『カレーのすべて』が出たときは、読者がついてくるのかひやひやしたものです。ところが意外やアマゾンのレビューをみるとプロ以外の人も買って試しているようで(そのため分量が料理店仕様で多すぎるとかいう不評もありますが、これは小社の本の宿命でして…)、隔世の感がありますねえ。
いまや素人だって各種スパイスを手に入れて汗をかきかき本格的なカレー作りに挑戦する時代。カレーに関する本も汗牛充棟、本棚からこぼれ落ちそうなほど出版されています。レシピ本やガイド本は例によって割愛しても、薀蓄本、雑学本がずいぶん増えました。
その嚆矢は1983年の江原恵の『カレーライスの話』あたりでしょうか。74年に『庖丁文化論』で鮮烈デビューした江原氏は“料理学”の論客をめざした人でありまして、家庭料理の店を経営したこともあり、実体験に裏打ちされたユニークな着眼点が学者さんにない持ち味です。ただし代用教員から料理人になったという経歴のせいか、生粋の料理人を終生の敵と捉えている節があるうえに、高価な料理や外国料理は特権階級のものであるという階級史観臭が全体をおおっておりまして、アジ調っぽい内容です。第一章は友人との会話スタイルになっているのですが、それがまどろっこしくて成功しているとは思えません。料理の理解が中途半端で、敵の姿がはっきり見えないままにいきんでいます。まあ、全共闘世代が好みそうではありますが…。
 続いて1989年の森枝卓士の『カレーライスと日本人』は、海外旅行が珍しくなくなったバブル時代の本らしく、インド人に日本風カレーを食べてもらって感想を求めたり、カレー粉のブランドとして戦前から名高かったC&B社(ちなみに同社の製品は今でも現役です)を訪ねてイギリスに渡ったりと実に活動的です。ポストモダンの80年代というよりは小田実の「何でも見てやろう」的スタンスなのですが、机の上にとどまらずに実地で調べてやろうという姿勢に好感が持てます。ただ取材ルポルタージュという形でまとめてしまったがために、当時はビビッドだった著者の感想や説明が逆にあだになって、今読み返すとどうしても20年前の本という印象を受けてしまう。難しいものですねえ。
続いて1989年の森枝卓士の『カレーライスと日本人』は、海外旅行が珍しくなくなったバブル時代の本らしく、インド人に日本風カレーを食べてもらって感想を求めたり、カレー粉のブランドとして戦前から名高かったC&B社(ちなみに同社の製品は今でも現役です)を訪ねてイギリスに渡ったりと実に活動的です。ポストモダンの80年代というよりは小田実の「何でも見てやろう」的スタンスなのですが、机の上にとどまらずに実地で調べてやろうという姿勢に好感が持てます。ただ取材ルポルタージュという形でまとめてしまったがために、当時はビビッドだった著者の感想や説明が逆にあだになって、今読み返すとどうしても20年前の本という印象を受けてしまう。難しいものですねえ。
文句ばっかりですがこの2冊、著者の個性がはっきり出ている点が、昨今のカレー本とは一味違うところです。現在のカレー本の基礎を作ったといってもいいでしょう。
続いて92年には吉田よし子の『カレーなる物語』が出版されます。熱帯植物の専門家が語るスパイスの説明が売り物なのですが、この本にはひとつ問題が。日本で最初のカレー目撃談として「飯の上にトウガラシ細味に致し、芋のドロドロのようなものをかけ、これを手にて掻きまわして手づかみで食す。至って汚き物なり」と、幕府の第二回遣欧使節団に参加した三宅秀の日記を紹介しておりまして、2000年の井上宏生の『日本人はカレーライスがなぜ好きなのか』や08年の水野仁輔の『カレーライスの謎』などいろいろな本にも引かれております。刀を差した若侍が初めて日本の国を離れ、船中で外国料理を見て目を白黒させる…なんていうエピソードは世の人の好むところでありますから。
ところが02年の小菅桂子の『カレーライスの誕生』では、「三宅秀関係書籍にあたったかぎり目撃情報はどこにもなかったので真偽のほどはわからない」とあります。どうやら軍配は小菅氏に上がるようでして、『サムライ使節団欧羅巴を食す』や『拙者は喰えん! サムライ洋食事始』では、ほとんど同じ文が同じ使節団の岩松太郎の日記にあることが指摘されています。ただし「汚き物なり」ではなくて「きたなき人物の者なり」。カレーが見苦しいのではなくて、食べ方が見苦しく感じられたのですね。ちなみに文久4年2月5日(1864年3月12日)の岩松日記には、この食べ方をしていたのはインド人ではなくアラビア人とあります。彼らは夕陽に向かって三拝したりと(ムスリムの礼拝でしょうか)、日本人の目には奇妙に映ったようです。
まあ正直な話、ほとんどの人にとっては最初にカレーに出会ったらしいお侍が三宅君でも岩松君でも構わないでしょう。ただ94年の『丁髷とらいすかれい』では、表紙にカレーを手にした羽織袴の三宅秀の似顔絵が描かれており、ちょっと勇み足でした。
なお井上氏は三宅秀の日記からと紹介しておきながら、「汚く人物の者なり」と引用しておりまして、吉田氏の本とも微妙に違います。いったいどこが誤りの震源なのかしら。三宅秀のエピソードは何々の本から採りましたと明記してあれば話は簡単だったのですが、それがないからわからない。料理関係の薀蓄本にはよくある話です。お固い研究書じゃないからいいじゃない、というのが理由でしょうが、固くない料理の話こそいろんな本に丸写しされやすいので、間違いが広まりやすくて危険です。書き写していくうちに誤解も生じます。伝言ゲームみたいなものですね。時間が経つにつれて研究が進み、真実に近づいていくかと思いきや、むしろどんどん遠ざかったりします。おまけに今はネットっていう厄介なものもありまして、試しに三宅秀+カレーで検索してみるとぞろぞろぞろぞろ…。
それにつけても皆さんカレーを初めて見た日本人とか、カレー南蛮の発明者とか、ホント初めてが好きですよねえ。いま私がちょっと気になっているのは、日本初の即席カレー「ライスカレーのタネ」を売り出したとされている神田松富町(今の外神田)の「一貫堂」についてでして。
この製品は明治39(1906)年の新聞の広告によると「カレー粉及極上生肉等を調合乾燥し固形体となしたる」とあり、熱湯で溶かしてご飯にかけて食べるそうです。で、さらに続けて「尚流行の蒸パンや(に?)バタの代りに着けて召し食(あが)ると至て結構です」と謳っております。カレーパンの実用新案特許は1927年に出されていると『カレーライスの誕生』にありまして、カレーとパンの組み合わせとしてはずいぶん早いですよね。イギリス人だってカレーはパンじゃなくてライスと食べます。ナンやチャパティの代わりかしら?
 実は一貫堂は蒸しパン用のセイロやパン種の発売元なんですよ。だからこんなに蒸しパン推しなんですね。本業はいったい何だったのでしょう。さらに付け加えるとほぼ同時期、同じ神田でも猿楽町の「蔦の家岡島商店」という店が、やはりライスカレーの種を売り出しております。東京朝日新聞の広告では、こちらの出稿のほうが2ヵ月早いくらいでして、どちらが先に売り出したのかはよくわかりません。翌年3月の広告によると「ライスカレーノ種」で商標登録をとったようですし(一貫堂のほうの広告は「ライスカレー種」「ライスカレイ種」というのがありましたがライスカレーのタネというのは見つかりませんでした)、一貫堂がシチュウ種を発売すればハヤシライスの種を発売するという具合で、手ごわいライバルだったと思うのですが、各種カレー本ではまったく取り上げてもらえていません。
実は一貫堂は蒸しパン用のセイロやパン種の発売元なんですよ。だからこんなに蒸しパン推しなんですね。本業はいったい何だったのでしょう。さらに付け加えるとほぼ同時期、同じ神田でも猿楽町の「蔦の家岡島商店」という店が、やはりライスカレーの種を売り出しております。東京朝日新聞の広告では、こちらの出稿のほうが2ヵ月早いくらいでして、どちらが先に売り出したのかはよくわかりません。翌年3月の広告によると「ライスカレーノ種」で商標登録をとったようですし(一貫堂のほうの広告は「ライスカレー種」「ライスカレイ種」というのがありましたがライスカレーのタネというのは見つかりませんでした)、一貫堂がシチュウ種を発売すればハヤシライスの種を発売するという具合で、手ごわいライバルだったと思うのですが、各種カレー本ではまったく取り上げてもらえていません。
湯で溶くだけではたしておいしく食べられたのかちょっと疑問でありますが、この年の『家庭雑誌』12月号「カレーの話」には、「近頃盛んに広告せられているライスカレー種と言ふもの」というくだりがありまして、結構話題になったようです。ちなみにこの雑誌、堺利彦の創刊でこの号の編集人は大杉栄。また即席の既製品に頼らないカレーの保存法をとくとくと解説した大石禄亭は、大逆事件に連座した大石誠之助のペンネーム。全共闘かぶれなんぞは裸足で逃げだす布陣であります。
そもそもこの製品、「肉を調合乾燥」ってフリーズドライみたいですが、誰の発案で、どのように製造したのでしょう。ほかにも同じような商品に取り組んだメーカーはあったのでしょうか。ここんとこをもう少し掘り下げたいところですね。明治37年から38年の日露戦争の頃に湯に溶かすと中から国旗やらが出てくる懐中汁粉が流行ったそうですが(以前、松江の和菓子屋さんが復刻発売しておりました)、その辺からの発想だったんですかねえ。世のカレー本はずいぶん増えましたが、まだまだわからないことはありそうです。
振り返ってみますと、江原・森枝両氏の本が、岩波新書の向こうを張った三一新書と講談社現代新書に収められているのに対し、吉田・小菅両氏は筑摩プリマーブックスと講談社選書メチエで、井上・水野両氏は平凡社新書に角川SSC新書。時代が反映されてますね。料理の話題がどんな本で語られてきたか、出版文化上どんな扱いを受けてきたかがなんとなくうかがえます。濃い欧風カレーの時代から、本格派をうたったインドカレーが一般にも広まって、近年わっとスープカレーブームが起きたのとなんだかちょっと似てますねえっていうと、たとえが悪いですかね。いやいやいや、スープカレーや井上・水野両氏が本格的じゃないって言ってるんじゃけっしてないですよ。スープカレーは江原氏がいうところの汁かけ飯タイプのカレーの復権であり、カレーの新しい道を示しています。井上氏の本はノンフィクション作家らしい手練なまとめ方だし、水野氏の本はルーやレトルトといった日本のカレー文化の根本を支えている商品にスポットを当てている点でなかなか読ませます。ただ、最近の新書はどっかで読んだことのある話が多くて、ちょっと薄いんですよねえ。まあ、これも好みの問題でありますが。
ちなみに著者のはっきりしないカレー雑学本のたぐいは、それこそ既存の本の寄せ集め色が強いのでここでは取り上げませんでした。ただし84年の『カレーライスの本』は別格でして、カレー写真、じゃなかったカラー写真で阿佐田哲也が我が家のカレーの作り方を伝授したり、官公庁の食堂のカレーライスを食べ比べたりとなかなかひねった内容です。この本はフタバブックスというシリーズで、新書版なのに丸背の上製本というちょっと豪華な作り。のちに双葉文庫から出た『カレーライス物語』と比べるとデザインも企画力も古きよき時代を感じさせますな。
投稿者 webmaster : 17:06
2011年11月24日
料理本のソムリエ [ vol.33]
【 vol.33】
横浜で食べたと君が言ったから
6月2日はカレー記念日
さて今回はトンカツの揚げ方にかこつけて、出張のたびにフィルム現像が上がるまで飲み食いして時間をつぶした大阪のトンカツ屋さんや、5年生のときに引っ越したトンカツ屋のマアちゃんの思い出をしっぽり語って、昭和気分にどっぷり肩まで浸かる気満々でいましたが、あまりにくどいので自重します。なんだかトンカツフリークと思われかねないし。「現像って会社のPCでやるんじゃないの?」とか言われかねないし。前回出オチを書籍部のツイッターでばらされちゃったあげくに、ポテトが芋カツ呼ばわりされてるし。芋カツはサツマイモで作るもんだいっ。どっちもポテトだけど…。
vol30ではカツカレーに、vol31では『西洋料理通』のカレーのレシピに触れたことですし、今度はカレーの本の話にしましょうか。カレーといえば暑い時期の料理書フェアの定番でして、わが社のカレー関連本も夏のほうが動きがいいとか。ちょっと季節はずれな感じもありますが、熱々のカレーは冬食べてもいいもんですよ。「おせちに飽きたらカレーもね」という先賢の格言もあることですし。
それに、なんでも12月1日は、料理研究家や業界有志が立ち上げた団体「カレーうどん100年革新プロジェクト」によって、昨年「カレー南蛮の日」と定められたようですよ。なぜまたこの日かといいますと、カレー南蛮を発明したと言われる「目黒朝松庵」の2代目ご主人、角田酉之助さんの誕生日なんですって。ちなみに「カレーうどん」の日のほうもありまして、8月2日です。6月2日が「カレーの日」、7月2日が「うどんの日」なので、その流れで8月に割り振ったのだそうです。
旧暦の7月2日は半夏生で、香川県の農家の人は田植えを終えたこの日にうどんを食べる風習があったから、ずいぶん前に県の麺業界がこの日をうどんの日に定めたってのは知ってましたが(うどん業界は「おせちに飽きたらうどんもね」と、3年前から「年明けうどん」を提唱し始めたりと、行事化に熱心ですね)、6月2日はカレーの日だったんだあ。なんで?と思ったら、横浜開港記念日にちなんで「横浜カレーミュージアム」が決めたのでした。カレーは横浜から入ってきたから、というのがその名目ですね。じゃあきっと、6月2日は「ホールクコツトレツの日」や「シトルトスプウンの日」の有力候補でもあるんですね。あ、「トンカツの日」のほうはもう決まってまして10月1日だそうですから、6月2日にしちゃだめですよ。10(トン)+1番(勝つ)だから10月1日。日本記念日協会に一件7万3500円もかけて登録されているんだから、勝手に変えちゃあ困りますからね。
このほか協会に認定された記念日には、「イタリア料理の日」(9月17日はきゅういちなな→クチーナ)、「鯛の日」(10月10日はかつての体育の日→鯛食う日)なんていうアイデア5割にこじつけ5割のもありまして、いわれがどうのとか由来がこうのとか言うほうが野暮みたい。とはいえこういうのは、販促に活用したくて決めるもの。だったら、思い切りふざけて笑いをとるかまじめかのどちらかに徹したほうが宣伝効果があるような気も…。創案者の誕生日とかいうのは、冗談なんだか本気なんだかちょっとビミョーですよねえ。そもそも「カレーうどん100年」っていうのがねえ…。おおっと、よせばいいのにご隠居の大人げない物言いがまたぞろ始まりましたよ。
だって、去年はカレーうどんが「日本全国に浸透」してから100年になるっていうのがプロジェクトの旗揚げ理由なんですが、誕生じゃなくて浸透っていうのがなんだか歯に物が挟まったような感じですっきりしないじゃないですか。何をもって浸透したとみなしたのでしょう。カレーうどんが1910年の流行語のトップに躍り出たから? 「この味がいいね」と村井弦斎あたりが言ったからでしょうか?
 カレーうどんの起源は寡聞にして存じ上げないのですが、カレー南蛮の起源については小社刊『蕎麦の事典』に3つの説が挙げられています。
カレーうどんの起源は寡聞にして存じ上げないのですが、カレー南蛮の起源については小社刊『蕎麦の事典』に3つの説が挙げられています。
1) 明治42(1909)年に大阪の谷町5丁目の「東京そば」の角田酉之介が始める。翌年東京に戻って始めたが、東京のそば店は保守的なので苦労し、軌道に乗り始めたのは大正3、4年から。
2) 明治43(1910)年に食料品店田中屋の杉本チヨが、そば店向けのカレー粉を研究して、「地球印 軽便カレー粉」の名称で商標登録した。
3) 明治40(1907)年に早稲田の「三朝庵」が売り出した。
新島繁さんは学究肌の人ですから、諸説あるのでとりあえず並列させたのでしょう。1の説が100周年の根拠(もっとも東京での販売開始ですね。だから浸透なのか?)で、これならまあ2の顔も立ちます。ただし3をとると、去年はカレー南蛮103年になっちゃう。
ちなみに三朝庵は、例のカツ丼を発明したと言われている店でもあります。初代加藤朝治郎氏が大正7,8年に余ったカツを使って今のような卵でとじる和風のカツ丼を始めたとか。これに対しvol30にて紹介した早稲田大学学生発明説は『早稲田大学史記要』2巻1号に載っております。中西敬二郎氏が入学した大正9年当時、早稲田のまわりで昼食を食べられる店は「三朝庵」「大野屋」「高田牧舎」など十指に満たないくらい。中西青年は毎日同じような料理を食べるのに飽きてきて、ひいきにしていた「カフェーハウス」という店に提案して、カツを切ってご飯にのせてメリケン粉と煮合わせたソースをかけて特売品にさせたとか。びらを書いてやって店頭に掲げたところ大当たり。大正10年2月のことでありました。うーん、これでは卵でとじた和風のカツ丼のほうが先で、ソースカツ丼のほうが後に誕生したことになりますね?
中西氏は文楽の研究で早大に奉職しており『早稲田大学八十年誌』の執筆者でもあります。これは早稲田の公式見解なのかなあと思いきや『ベストオブ丼』には、『早稲田学報』に別の説も載っていると紹介されておりました。さすが学問の府ともなると談論風発ですね。1983年の2・3合併号をさっそく見たところ、84歳の卒業生の回想によると、大正6年早稲田の鶴巻町にソースをかけたカツ丼を出す店があったとか。カツが冷めないように火鉢で温めていたなどディテールもリアルで、記憶違いではなさそうです。今は福井県に移転した「ヨーロッパ軒」はもともと早稲田に店を構えており、この回想にある店と同一という見方もあるようです。同店のHPによると、そもそもの始まりは主人の高畠増太郎氏が大正2年の料理発表会で披露したものであるとか。
おっと、これまた複数の説が対立しておりますね。ソースカツ丼のほうが先に生まれたほうが自然ですから、大正10年よりも大正2年誕生説というのは有力ですが、この年に開かれた料理発表会ってのは具体的に何でしょうか…。また先の早稲田学報には続きがありまして、同じ頃に穴八幡のほうには卵とじのカツ丼を出す「高田舎」という店があったというのです。この店は先述の「高田牧舎」の姉妹店だそうですから、中西氏も知っていておかしくないような気も…? さらにカツ丼中西氏発明説を報じた朝日新聞には、当時78歳の読者が旧制中学の頃(入学したばかりならこれも大正6年頃ですね)、甲府の駅前にカツ丼を提供する店があったという反論の投書も寄せられていたとか…。
こうしてみるとカレー南蛮もカツ丼の発明も、どの店で発明されたと断定するのは難しい。いろいろなところで同時並行して誕生した可能性もありますし。となると団体名を「カレー南蛮誕生から約100年プロジェクト」にすれば、より正確だったのですが、うどんを前面にかかげないと困る事情もあったようです。
なお2番目の田中屋は屋号でして、正式名は杉本商店。今も業務用のカレー粉を扱う現役の企業でして、HPによるとそば店向けに開発したカレー粉を商標登録したのは明治43年11月7日だそうです。この日をカレーうどんだか南蛮だかの日にするほうが、筋が通っていて簡単そうな気もしますけど…。
ところで話がちょっと飛びますが、先日、明治の末に出版された『毎日のお惣菜』という横長の料理本を手に入れましてね(表紙がとれちゃっているので200円)。執筆者は和洋料理教授会で、1年365日の献立を提案するという内容でした。料理名の羅列が中心で(毎日のおかずに頭を悩ませないように、今日の献立はこれにしなさい、というわけ)、安直な作りの本だなあと思って、ぱらぱら見ているうちに目が点に。
9月13日の献立に「豚肉に軽便カレー粉」という料理を提案したのを皮切りに、15日は「そばに軽便カレー粉」、17日は「きゃべつに軽便カレー粉」、19日は「牛肉と軽便カレー粉」と一日おきにカレー料理の波状攻撃。21日にまた「豚肉と軽便カレー粉」に戻ったと思ったらヒートアップして、キャベツ、まつたけ、牛肉、ネギとニンジンと、手を変え品を変え毎日カレー漬け。突然始まった軽便カレー粉の無限ループです。29日にいたってはただ「軽便カレー粉」とあるだけでして、そのままご飯にふりかけろとでもいうのでしょうか…。
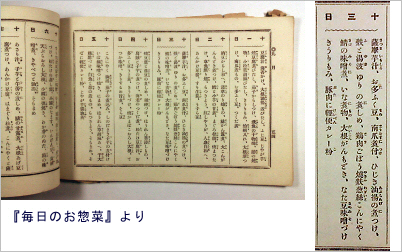
 この調子で年末までカレー三昧が続きまして、12月31日は「人参玉葱と軽便カレー粉」で締めくくるのでありました。これで年明け早々おせちの代わりにカレーが登場したら、一生恨まれそう…と思ったら、別のページでお年玉に軽便カレー粉を勧めておりました。いったい9月13日に何があったのでしょう。カレー粉の日か?
この調子で年末までカレー三昧が続きまして、12月31日は「人参玉葱と軽便カレー粉」で締めくくるのでありました。これで年明け早々おせちの代わりにカレーが登場したら、一生恨まれそう…と思ったら、別のページでお年玉に軽便カレー粉を勧めておりました。いったい9月13日に何があったのでしょう。カレー粉の日か?
ちなみにこの本、レシピも少しは載っているのですが、手軽西洋料理法というコーナーに軽便カレー粉が登場します。牡蠣に水で溶いた小麦粉をつけてヘットで揚げる「牡蠣揚」に「軽便カレー粉を用ゆるも妙なり」。という但し書きがありました。あえてフライにしないでカレー風味のてんぷらにせよというところがこだわりっぽいですね。牛肉のひき肉に水に浸したパンを少し混ぜて、煮たキャベツで巻いて蒸し焼きにする「キャベツ巻」。これまた「軽便カレー粉を用ゆるも妙なり」。味付けがいまいちわかりませんが、ロールキャベツっぽい料理ですからカレー風味も合いそうです。ただ、卵の黄身3個に砂糖少しと煮た2合5勺の牛乳を加え、白身に砂糖を混ぜたものをのせて食べる(固まるのか?)という「煮カスタ」という料理にも、「軽便カレー粉を用意すべし」とありました。どこで使えという指示がないのですが、洋風二色玉子みたいなこの料理、なんだか甘そう。これこそ妙な味になりそうですけど、大丈夫でしょうか…。
 種を明かせばこの本の巻末に、杉本商店がどーんと広告を出しているんです。だからこんなにカレー粉ざんまい。発行は明治43年7月なので、商標登録を取る4カ月前です。100年前からメディアを使ってこんなに積極的に商品を売り込んでいたんですねえ。
種を明かせばこの本の巻末に、杉本商店がどーんと広告を出しているんです。だからこんなにカレー粉ざんまい。発行は明治43年7月なので、商標登録を取る4カ月前です。100年前からメディアを使ってこんなに積極的に商品を売り込んでいたんですねえ。
「●紳士曰く『僕は此の間友人の所で此のカレー粉を蕎麦に応用したのを喫つて見たが頗る美味かつた』●美人曰く『アラマアそんなに美味つて直に間に合ふものなら一瓶買つて見ませうか』●紳士曰く『一瓶と云はずに二三打(ダース)も買つて郷里の卿(おまえ)の御父様や親類の方々へ贈つておあげなさい 春夏秋冬何時でも用ひられる至極便利な食料品だ 而(そう)して価格も非常に低廉いから妙だ』」
うーん、すがすがしいほどストレートな宣伝っぷり。ただ、せっかくだから「そばに軽便カレー粉」のレシピも載せてほしかったなあ。まさかこの紳士が田舎の親類縁者に贈りまくったおかげで、作り方を説明する必要がないくらい、当時の人にとっておなじみの料理だった…ということではないですよね…?
なんていろいろ茶々を入れましたが、確かにカレーうどんはまだ革新できると思います。カレーのスパイスの種類やとろみのつけ方や濃度、うどんの太さや形状などなど、検討の余地ありでしょう。進化したカレーうどんが登場するのは諸手を挙げて大歓迎。ただ、100年目だとか適当な理由をこしらえてアドバルーンを派手に打ち上げただけでは、一過性に終わってしまいますよ。
いっそ来年は、横浜を抱える神奈川県がカレー県に改名して、香川県と一緒にキャンペーンをするっていうのはいかがでしょう。かながわとかがわって他人と思えないし。ついでに行政も提携して効率化を図り、隣の東京や大阪の向こうを張る。「カレーうどん連合から地方分権を!」というキャッチフレーズには、元大阪知事もたじたじかもしれませんよ。
marginheight="0" frameborder="0">
投稿者 webmaster : 14:37
2011年11月10日
料理本のソムリエ [ vol.32]
【 vol.32】
キャベツとソースはなぜデフォなの?
いやあ、前回は長かったですねえ。お経みたいなレシピが続いてまあ退屈なこと。やれやれ、ようやくトンカツの話は終わりだと思ったでしょ? ところがどっこい、終わったのは胃カメラの話だけで、トンカツ談義はまだ続きますよ。なにせ肉の話でおしまいになってたじゃないですか。これからいよいよ揚げる段階に入るわけですからね。くどくて、量が多くて、胸やけするって? 自覚はありますが揚げものが相手なだけに仕方ありませんなあ、と開き直りたいところですが、トンカツ屋さんに怒られちゃいますね。
これまでの洋食研究家の先生たちはどうもイタリア料理には暗いようでしたが、最近はだいぶ世間に知られるようになりました。洋食の歴史なんぞについてはネット上のマニアのHPのほうが詳しいくらいで、ウィンナーシュニッツェルやコトレッタ・アラ・ミラネーゼにも触れられています。ただ皆さん、残念ながら皿の上の料理でばかり考えるものですから、材料やら調理技術などの源泉をたどるまでには至っていないようですね。
 まず第一に日本のトンカツで独特なのはその厚さです。仔牛の骨つきロースで作るカツレツはいきおい骨1本ぶんの厚さになりますが、下ごしらえの工程として肉叩きでぺちんぺちん叩いて平たくします。火の通りが早くて繊維が縮みやすい仔牛肉は、叩いてほぐしてやるとよいそうです。とくにミラノ風の場合は、下粉の小麦粉は打たず、叩きながら衣をなじませるために大事な工程です。確かに明治時代の料理本のカツレツのレシピを見ていても、おおむね肉叩きがちゃんとでてきます(『西洋料理通』には書かれていませんが、まあ、あれはちょっと特殊なので)。しかし現代のトンカツのレシピでは筋切りせよとはあっても、肉叩きは必須とはなってないですね。肉を扱う歴史が浅い日本人はこの肉叩きの効用がわかっていないとは、実家が肉屋さんでもある吉川シェフの弁であります。
まず第一に日本のトンカツで独特なのはその厚さです。仔牛の骨つきロースで作るカツレツはいきおい骨1本ぶんの厚さになりますが、下ごしらえの工程として肉叩きでぺちんぺちん叩いて平たくします。火の通りが早くて繊維が縮みやすい仔牛肉は、叩いてほぐしてやるとよいそうです。とくにミラノ風の場合は、下粉の小麦粉は打たず、叩きながら衣をなじませるために大事な工程です。確かに明治時代の料理本のカツレツのレシピを見ていても、おおむね肉叩きがちゃんとでてきます(『西洋料理通』には書かれていませんが、まあ、あれはちょっと特殊なので)。しかし現代のトンカツのレシピでは筋切りせよとはあっても、肉叩きは必須とはなってないですね。肉を扱う歴史が浅い日本人はこの肉叩きの効用がわかっていないとは、実家が肉屋さんでもある吉川シェフの弁であります。
そういえばむかーし肉屋さんには中肉とか上肉っていう分類がありましたが、今では聞かなくなりましたよねえ。なんだか経済格差っぽい(笑)。肉を使う歴史の浅い日本では、バラやヒレはともかく、部位名で表現したところで普通の主婦にはなじみがなくて、使い分けられなかったからなのでしょう。
そもそも日本では、肉屋さんが切って売ってくれますけど、これって世界的にみたら異色じゃないですか? 塊のままのほうが絶対傷みにくいし、肉汁も逃げないのに。お刺身もそうですが、今ではトレイにきれいに並んでいるのが当たり前。これは肉を自分で触りたくないというお客さんの要望から生まれたサービスなんですかねえ。家庭用冷蔵庫の普及以前から行なわれていたのでしょうか。
最近でこそスーパーでブロックの肉も売ってますが、生姜焼きやトンカツ、カレー用を除けば、薄切りのほうが普通というのも変な話。これは「片」に切った肉を調理する機会の多い、中国料理の影響でしょうか? 単に肉といえば昔は鍋料理が当り前だったからでしょうか?それとも肉がまだご馳走だった時代、紙のように薄―く薄―く切って、たくさんあるように見せたかったからなのでしょうか?
自宅の隣家はかつては肉屋さんでして、けっして肉に縁遠かったわけではないのですが、ステーキなんて夢のまた夢という(ていうか、いまいちどんなものかぴんとこなかった)庶民にとっては、ぶ厚い肉にかぶりつく料理といえばトンカツだったような気がします。それでもおかずのメインはコロッケで(まれにメンチ)、トンカツは家族5人全体で2枚くらいしか買いませんでしたねえ。その代わり、ポテトフライはひとり2個か3個が割り当て。揚げたてをハトロン紙っぽい袋に入れて新聞紙でくるんでもらうのを待っている間に、お駄賃としてポテトフライを楊枝に刺したのを渡されるとうれしかったものです。
 ポテトフライを楊枝に刺せるかって? 棒状のフレンチポテトと勘違いしてませんか? 写真のような4つ切りにして衣をつけて揚げたものなんですけど、ご存じないかなあ。
ポテトフライを楊枝に刺せるかって? 棒状のフレンチポテトと勘違いしてませんか? 写真のような4つ切りにして衣をつけて揚げたものなんですけど、ご存じないかなあ。
こんなふうに肉屋さんが揚げものを売るというのは、ラードやヘットを有効活用しようという発想からなのでしょうが、これまたいつ頃からそうなったのでしょう? コロッケと同列に語られる日本のトンカツは、もはや豚肉フライともいうべき別料理。厚くても芯まで火が通っていて、なおかつ柔らかさと肉汁を失わないようにするのはなかなか高度な技でして、フランス料理やイタリア料理のシェフでもトンカツの揚げ方に興味深々な人は多いようです。揚げる温度を低めから始めて時間をかけるのがコツなのでしょうか…。
 また肉の厚さのほかに、日本のトンカツの特徴には衣のかりかり感があるようにも思います(もちろん、薄い衣をめざしている蓬莱屋さんのような例もありますが)。中食市場の最新のトンカツ事情にも詳しい『デリそうざい2号』によると、パン粉の衣がつんつん飛び出ていることを「剣が立つ」と表現するとか。確かに油でべしゃっとした感じがしなくておいしそう。日本独特の表現ですね。
また肉の厚さのほかに、日本のトンカツの特徴には衣のかりかり感があるようにも思います(もちろん、薄い衣をめざしている蓬莱屋さんのような例もありますが)。中食市場の最新のトンカツ事情にも詳しい『デリそうざい2号』によると、パン粉の衣がつんつん飛び出ていることを「剣が立つ」と表現するとか。確かに油でべしゃっとした感じがしなくておいしそう。日本独特の表現ですね。
これは推測なのですが、日本のパン粉は海外のパン粉とタイプが違うのは、用途がトンカツのせいではないでしょうか。粗いパン粉や生パン粉を使うことで油による長時間の高温加熱が可能となったのでは…。もっとも元になるパンの性質にもよりますし、コロッケはもう火が入っているからそんなに長時間加熱は必要ないし…。
 これは思いつきの仮説でして、小麦粉の専門家の意見をぜひ聞いてみたいと思ったら、『とんかつの誕生』の岡田哲先生は日清製粉の出身でした。この本にはパン粉についても細かい説明がありまして、この点は出色です。ヨーロッパのパン粉は粟粒ほど細かい粒子で、揚げ油が汚れやすい(もっとも『新版 イタリア料理教本』によると、ミラノ風は生パン粉を使うようですが)。炒め焼きやバター焼き用だそうです。
これは思いつきの仮説でして、小麦粉の専門家の意見をぜひ聞いてみたいと思ったら、『とんかつの誕生』の岡田哲先生は日清製粉の出身でした。この本にはパン粉についても細かい説明がありまして、この点は出色です。ヨーロッパのパン粉は粟粒ほど細かい粒子で、揚げ油が汚れやすい(もっとも『新版 イタリア料理教本』によると、ミラノ風は生パン粉を使うようですが)。炒め焼きやバター焼き用だそうです。
一方アメリカのパン粉はブレッダーと呼ばれ、ソーダークラッカー状のものを、細かく粉砕して作るのだそうで、フライドチキンやフィッシュスティック向けなんですね。それに対して、日本のパン粉は不揃いで大きく付着しやすいのだとか。岡田先生は衣がさくさくした歯ざわりで、適度な厚みになると指摘していますが、加熱時間の調整にも貢献していないのかなあ。
とまれトンカツの歴史について研究するには、パン粉の研究も欠かせません。あとは揚げ油に揚げ鍋、加熱機器や燃料の歴史もからんできますが(となると明治以降の天ぷらの歴史にも目配りする必要がありそうですね)、さらに付け加えればキャベツのせん切りも。コロッケやフライもそうですが、どうしてコールスローもどきのキャベツのせん切りが必ずついてくるのでしょう? ドレッシングのかかっていない生キャベツのせん切りは日本独特の付け合せ。森まゆみ氏の『明治大正を食べ歩く』によれば「煉瓦亭」の発明だそうで、日露戦争でスタッフが召集され、手が足りなくなったのがきっかけだとか。ちなみに料理本のソムリエっぽいコメントをはさみますと、この新書はシリーズものでして、『「懐かしの昭和」を食べ歩く』がお勧めです。ご本人が食べた思い出のある店のルポは、ひと味違う臨場感がありますよね。
トンカツ屋のキッチンでアルバイトをしていたかつての上司の話によると、ウソかホントか、トンカツの利益率というのはキャベツで決まるのだそうです。豚もパン粉も卵も小麦粉も、そうは大きく価格変動しないのですが(最近の小麦粉は制度が変わったのでそうでもありませんが)、唯一キャベツは季節や気候に左右されやすいのがその理由。そんなに大変なら添えなきゃいいのにと思うのですが(どちらかといえば生で食べるよりも、煮たり炒めたりするのに向いている野菜ですよねえ)、お客さんが納得しないでしょうね。
西洋野菜の導入の歴史については、GHQ時代のような戦後の話はvol17の大木健二さんのような現場の人の声を聞きたいところですが、明治大正の事情については青葉高先生の『日本の野菜』が頼りになります。野菜が登場する歴史文献を紹介しつつ、育種の立場からの説明が充実。文理両道の達人の読み応えのある本でして、昔は2冊組でしたが1冊にまとめられて使いやすくなりました(おお、前にどっかで聞いたことのあるようなセールストーク)。もっともそんな本書でも、キャベツの来歴については安政年間に栽培が始まり、横浜や函館でわずかに定着したこと、明治7年に勧業寮が山形など5県で試作させたこと、これとは別に北海道開拓使が栽培に成功した、とある程度。ところが明治26年の『蔬菜栽培法』では近年東京近在にて多く培養し、普通の蔬菜店にも販売するものあり、とあるそうです。20年も経たない間にいったい何があったのか。まだカツレツに添えるようになる前のはずなのに、いったい何に使われたのか。漬物ですかね? やれやれ、素材も庶民的なものとなると、歴史をたどるのはなかなかしんどいです。
さらにキャベツといえばソースですよね。夏に書籍部のツイッターでソースをトンカツにかけるかキャベツにかけるかで、盛り上がってましたねー。煉瓦亭がキャベツを添えることを発明する前は、カツレツにソースはつきものだったのでしょうか?

おっと、ソースといってもタルタルソースじゃないですよ。この仕事に就くまでソースっていうのはウスターソースのことと思っていました。ついでに上肉、中肉じゃあありませんが、中濃があるのだから少濃や特濃という呼び方もあるのかと思ってました(笑)。実際は通常のウスターソースととんかつソースの間の濃さなので、中濃なのだそうです。おまけに中濃はもともとは東日本ローカルな商品なのだとか。かつて東京の下町では中濃ソースもジョウゴで瓶に移して量り売りしておりましたが、どろり濃厚ソースが一般的な関西ではどうだったのでしょう?
それにしてもとんかつ専門というカテゴリーがあるとは、イギリス人もびっくり。生キャベツの表面はすべりやすくてソースがからみづらいので、とろみをつける方向へと発達したのでしょうか。リエするというよりは、もはやこれはタレづくりの発想ですよね。お好み焼きには刷毛でぬったりしますしね。
野菜や果物の甘みの溶け込んだこの焦げ茶色のソースは日本独特なものだそうです。気になって東京都ソース工業協同組合の業界史『道程』を閲覧したところ、原料に果物を使うようになったのは戦後の食料難の時代からで、果物は統制外だったからだとか。濃厚タイプのソースの普及も昭和30年代以降だそうで、意外と新しいのにびっくり。日本におけるウスターソースの導入と変遷、メーカーの興亡と普及の過程、地方差についてはさらに掘り下げる必要がありそうですね。これがはっきりしなくては、たこ焼きの誕生もお好み焼きの誕生もソース焼きそばの誕生もソースせんべいの誕生もわかりませんからね。
ほらこの通り、トンカツを糸口に知りたいことはいくらでも出てきます。トンカツという「洋食」はどこもかしこも日本化されてまして、その受容と変化を通して、日本の食文化の特徴が垣間見えてきます。本の1章をあてたくらいじゃ、ブログを3回に分けたくらいじゃ、こりゃとても足りそうにありませんよ。
投稿者 webmaster : 11:00
2011年10月26日
料理本のソムリエ [ vol.31]
【 vol.31】
「西洋料理通」を読む
実は私、先月末ついに取締役に別室へ呼びだされてしまいました。書類を片手に深刻な面持ちです。リストラ? リストラなのか? 変なブログが原因か?
ところが開口一番「産業医の先生から、内視鏡検査を受けたほうがいいという連絡があった」。えええええっ! またなの? また飲めと? …と思ったら、検査済みという連絡が先方に通っていなかったようでして。だいいち検査結果の正式な通知はもうもらっているんですけどね、軽い胃炎だったせいだか知りませんが「1年間経過観察のうえ再検査」なんですよ。また来年にはアレが控えているかと思うとストレスで胃に穴が開きそうなんですけど…。
ということで胃カメラの話は思い出すだけでも胃に悪そうなので、これでもうおしまい。トンカツの話の続きです。
そもそもトンカツの前身である「カツレツ」のルーツをたどるのが大変でありまして、小菅和子氏が日本で最初のカツレツレシピとして紹介している文献からして大問題。『西洋料理通』の「ホールクコツトレツ」がソレなんですが、原文を見てびっくり。

まずこの本についてですが、猫々道人こと仮名垣魯文先生の訳であります。教科書にだって出てくる明治の戯作者で、猫グッズマニアという意外な一面もある御仁。出版は明治5(1872)年で、全部で百十等(「等」は、今でいう「節」や「項」ですね)の料理メモが紹介されています。訳とはいっても、横浜に居留していた某イギリス人が使用人にむけて書いた指示とその訳が原書でして、それを校訂したものとか。原書はカタカナ書きだったところをひらがなに改めたが、外来語はカタカナを残したと凡例にあります。かながき先生なだけにカナの扱いにはうるさいですな。
もっともこうした注意書きが必要なのは、今のような日本語かな表記のルールが確立する前だからでありまして、この本はまだ江戸の出版物の雰囲気を色濃く残しています。木版刷りで、ひらがなは現行のものではなく変体がな(蕎麦屋の看板に書かれているやつです。上の魯文の石碑もそうですね)も混じっていて、促音や拗音の表示はないし(早い話が今なら小さい“っ”や“ゅ”で書くところが小さくなってない)、句読点で区切られてない。現代人には難物です。おまけにカタカナの音写は発音に忠実なような不慣れなようなビミョーな感じでして、本来ついているべきところに半濁点や濁点がなかったりで、ちょっと見なんのことかよくわかりません。たとえばパセリはハリセリイだったりハルセリーだったりペルセリーだったりパンセリーだったり…。いっそ英語のままにしてほしかった。西洋料理の知識があればどうにかこうにか解読できるレベルでして、こんなの当時の人の何の役に立ったのか、とも思いますが、外国の料理の紹介というだけで売れたんですねえ。うらやましいねえ。
そこで句読点を補って活字化したものが『明治文化全集』風俗編に収められているのですが、昭和の初めの仕事なので漢字は旧字のままですし、ルビの振り方の不統一や誤植など結構ケアレスミスが見つかります。誰だい、校訂したのはと思ったら、若き日の高橋邦太郎氏でした…。料理通として有名なフランス語の翻訳家で、小社からも『パリのカフェテラスから』を出版されています。英語なので手を抜いたのか? もっとも編集者の校正ミスの可能性も…(くわばらくわばら)。ここではそこも修正しつつ紹介しましょう。ブログではルビがふれないので、随時カッコで補います。
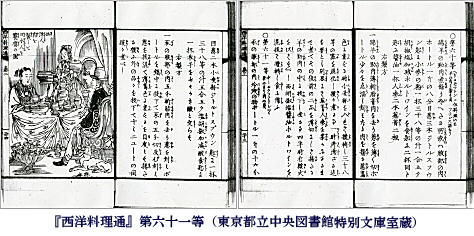
pork cutletのことらしき「ホールクコツトレツ」は、第六十一等にのっておりまして、文章は材料の列挙と「右製方(しかた)」の二つで構成されています。材料は「豚の腋(あばら)部の肉冷残(にあまり)の物/ボートル一斤の十六分目/葱二本/小麦粉ジトルトスプウン匙に一杯/三十八等の汁五合五勺/塩胡椒加減/酸(す)食匙に一杯/芥子を少々かき酸と交らす」。作り方は「豚の腋部の肉五分斬、脂肉(あぶらみ)を去り、葱を刻み、ボートルを鍋中に投下(いれ)て、豚の五分切及び刻み葱を投混(いれまぜ)て、薄鳶色に変ずるを目度とす。揚たる後に外の品々を投下(いれ)て、十ミニュートの間、緩々(ゆるゆる)煮べし」
ね、お経みたいで頭が痛くなるでしょ。ボートルはバターのことで、1斤を600gとするなら16分の1は37.5g、ジトルトスプウン匙はほかのところではシトルトスプウンとして出てくるのですが、なんのことやら。柑橘用のシトラススプーン(sitrus spoon)のことでしょうか、あるいはバースプーンを当時はスティアドスプーン(stirred-spoon)とでも呼んだのでしょうか…。ネギはポロネギではなく、恐らくタマネギの代用品ですね。別のレシピではクローヴを刺したり、オニオンスープのところでもネギを使ったりしていますので。冷残の肉というのはいったん煮て冷ましたもののようです(保存のためでしょうか…)。まあ早い話、豚肉をタマネギとともに多めのバターでソテーして、引き揚げた後、焼き汁を煮溶かしてソースに仕上げる料理のように読めます。
なお約1リットルも加える「三十八等の汁」ですが、原文にあたりますと「クレビーフヲル。ロースト。ミート」でした。変換ミスじゃないですよ。なんでこんなところに句点が入っちゃったのか…。これは恐らくgravy for roast meatでしょう。「やきたる肉に用いる露物」と説明されていますし(グレービーをつゆ物って…)。材料は以下の通りです。「第二等の白汁種(しろにだし)を二合/ハルセリー二撮(つま)み細(こまか)に刻み/ボートル胡桃の実の大きさ/肉豆蒄(にくづく)の末(こな)/丹胡椒いづれも加減」。そんでもって製法は「パンセリー並にボートルを第二等の黒汁の中に投入(いれ)、緩火にて煮る事半時、雲母(きら)を去り善く陶(こ)す。丹胡椒、肉豆蒄を加減の上散投(ちらしこむ)べし」。
丹胡椒には「あかこしょう」とルビがふってあったので、てっきりレッドパッパーかな、と思ったのですが、当時の辞書をみたらカイエンヌペッパーの日本語訳のようです。雲母というのは表面に張った脂やあくの膜のことですかねえ。このレシピの中に今度は「第二等の汁」が出てきますが、いったい白いんだか黒いんだか…。その材料と作り方の詳細はえらくスペースを割くのでもうやめておきましょう。これまたわかりづらいレシピなのですが、牛スネほか鳥獣類の肉でとったブイヨンらしきもの。もっともバターと香辛料がたっぷり入っています。煮出す水の量は少なくて煮込み時間が意外と短めでした。燃料代が高かったからですかねえ。
率直に言って、これって名前がコットレツというだけでまったく違う料理ですよねえ。衣すらついていないし。事実、小菅先生は「いまでいうポークソテー」と説明しています。だったら初めから無視しなさいな。ソテーといっておきながら、原文の変体がなをことごとく読み間違えて「…薄鳶色に変たるを目度とし揚げ、さる後に…」と紹介しておりまして、揚げ物料理っぽい印象を与えております。おかげでトンカツの来歴を扱う本はことごとくふり回されっぱなし。『とんかつの誕生』に至ってはどうしちゃったんだか終始「ホールコットレッツ」と紹介しているし…。fowl cutletでは鳥カツになっちゃいますよ?
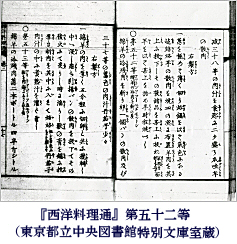 この他人の空似の第六十一等よりもですね、私は第五十二等の「コツトンツ、コールドモツトン」が気になってしかたない。お経だからって、面倒臭がらずにレシピを読まなきゃだめですよ? 隣の第五十三等のほうはカレーのレシピとかで、大変有名なのに…。
この他人の空似の第六十一等よりもですね、私は第五十二等の「コツトンツ、コールドモツトン」が気になってしかたない。お経だからって、面倒臭がらずにレシピを読まなきゃだめですよ? 隣の第五十三等のほうはカレーのレシピとかで、大変有名なのに…。
材料は「綿羊の冷残肉を斬り/卵一個/パンの散肉(ちらし)及び三十七等の鳶色の肉汁(にだし)/丹茄子(あかなす)少々」。作り方は「綿羊の肉を厚く五分程に切、卵と共に攪転(かきまわ)し、中へ浸し忽(たちま)ち引揚、パンの散肉を投下て、その後、火にて炙りし時に滴りし獣の膏(あぶら)を鍋に投(いれ)、厚き斬肉を其中に入れて焙烙(いり)、但し鳶色になるを期とす。丹茄子肉汁の中に煮熟汁(にえじる)を灌(そそ)ぐべし」。
ね? こちらはちゃんと卵もパン粉もつけてまして、動物の油脂で加熱しています。焙烙は煎り焼きのニュアンスではありますが、ミラノ風カツレツを作るときの加熱法はこんな感じ。こちらこそが日本に初めてお目見えしたカツレツレシピではないでしょうか。コツトンツはコツトレツの誤植じゃないですか? それが証拠に、この料理のモツトン(mutton)の「ン」の字は逆に「レ」によく似ていて取り違えやすそう…。なお材料の中の三十七等の煮汁はブラウン・グレービーのことでして、このレシピではいまいち使い方がわかりませんが、トマトを煮て加えるようです。
日本の「カツレツ」は英語圏から来た言葉のカットレットに由来するようですが、もとはフランス語のコートレット、つまり骨つきロース肉から来ています。西洋料理通に出てくる「コツトレツ」は元々の骨つきロース肉のほうの意味なんですね。その証拠にほら、「ホールクコツトレツ」も「コツトンツ、コールドモツトン」も料理名の脇に小さく「豚のきり肉の義」「綿羊の冷肉を斬の義」と説明されておりますでしょう? 本来はただ部位を表すだけの言葉なのに、典型的な調理法がパン粉揚げだったものですから、英語ではそれとイコールにとらえられるようになったというわけです。

 さらに意味が広がって、骨つきロースでなくとも小判状にしてパン粉をつけて揚げた肉料理は英語では何でもカットレット、イタリア語ではコトレッタと呼ばれるようになりました。吉川敏明シェフの『新版イタリア料理教本』には、豚肉以外にもポレンタやモルタデッラに衣をつけて揚げるコトレッタが出てきます(二冊組だったのが、新版では一冊にまとまって引きやすくなりましたよー、とPR)。とくに骨つきロース肉であることを示す場合は、コストレッタとするのだとか(元はラテン語で、フランスでも古語はcosteletteなのです)。
さらに意味が広がって、骨つきロースでなくとも小判状にしてパン粉をつけて揚げた肉料理は英語では何でもカットレット、イタリア語ではコトレッタと呼ばれるようになりました。吉川敏明シェフの『新版イタリア料理教本』には、豚肉以外にもポレンタやモルタデッラに衣をつけて揚げるコトレッタが出てきます(二冊組だったのが、新版では一冊にまとまって引きやすくなりましたよー、とPR)。とくに骨つきロース肉であることを示す場合は、コストレッタとするのだとか(元はラテン語で、フランスでも古語はcosteletteなのです)。
またミラノ風カツレツの項の説明によると、ミラノのコトレッタとウィーンのウィンナーシュニッツェルはどちらがオリジナルなのか本家争いをしているそうです。なるほど『月刊専門料理』1999年7月号「イタリア情報」にその一端が載っておりました。18世紀初めからイタリア建国までの間、ミラノがオーストリア帝国の統治下にある間にウィーンからミラノへ伝わったというのがオーストリア側の主張。それに対してイタリア側は、ウィンナーシュニッツェルに使うのは仔牛のモモ肉で、パン粉をつけてから卵に浸し、ラードで揚げるなど、ミラノ風カツレツとの違いを強調。また1134年のメニューに出てくる「lombolos cum panitio」はパン粉をまぶした肩ロースという意味であること、オーストリアのラデツキー元帥が副官アテムス伯爵にあてた手紙でコストレッタについて説明しているということから、当時ウィーンにはカツレツがなかったというのがその主張です。いやはや、アジアの端っこでカツレツの起源を調べるのは想像以上に大変です。
ここで注目してほしいのは、イタリアでもオーストリアでも仔牛肉から作る料理であることです。フランス語ではレットは小さいという意味で、同じ骨つきロースでも牛だの豚だのの部位を示す場合はただのコートです。カツレツは、それよりはちょっと小さいサイズの肉が取れる家畜、つまり、仔牛や仔羊から作るのが本来の姿でしょう(もっともイタリア語では牛のロースはコスタータでも、豚のロースはコストレッタの組に入るようですが)。
ところが『西洋料理通』にはもうひとつ、第三十等に「サルモン。コツトレツ」が出てまいりまして、こちらは鮭をバターを塗った紙で包んで焙り焼いております。英語では鮭の切り身もまたcutletと呼ばれるようでして、早い話それっぽい形の切り身なら何でもありなんですねえ。おおざっぱといえば、おおざっぱ。ならば何の肉を使ってもパン粉揚げならカットレットとする心情もわかります。日本では仔牛肉にはなじみがありませんから、より手軽な白身肉ということで、鶏や豚から作るようになったのでしょう。最初はチキンのカツレツだのポークのカツレツだのといちいち断っていたのが、はしょって豚(とん)+カツになっちゃった。一方関西のビフカツは、仔牛の代わりに成牛に走ったというわけですね。
豚と牛、どっちも仔牛の代用なことには変わらないのですが、ビフカツのほうが本式という文章も見かけます。やれやれ…。白身の仔牛肉(ヴィール)と赤身の牛肉(ビーフ)ではまったく別の素材でありまして、シンコをコハダ、いやコノシロと一緒にするくらいに無神経。そういえば23日、政府がBSE問題で2001年以降禁止していたフランスからの牛肉輸入の再開を検討し始めたというニュースが入りました。業界が嘱望しているのはフランス産仔牛肉なんだから、アメリカ並みに生後20カ月以下に限ってとっとと再開すればよかったのに、今頃何を言ってんだかなあ、という感じでありますな。
投稿者 webmaster : 10:53
2011年10月13日
料理本のソムリエ [ vol.30]
【 vol.30】
内視鏡検査の〆はトンカツで
先頃私、ついに定期健康診断でひっかかって、胃カメラで再検査されるはめになりました。噂には聞いていましたが、なかなかつらいもんですねえ。太さは覚悟していましたが、管が思っていたよりも柔らかくない。「のどをもっと開いて飲みましょうかー」なんて気軽に言ってきますが、一本うどんをつるつるってえならともかく、こちらで自主的に飲んでるわけじゃないんだから。「こりゃ飲むじゃなくって、突っ込むいうんじゃあボケえ」と心の中で叫んでも、口は開いているのに言葉がでない。向こうも突っ込めなきゃこちらも突っ込めない。ボケ不在の漫才です。
そもそもなぜ当人の目の前にモニターを据えて、どこまでカメラが入ったか胃の中を刻々と見せるのですか。拷問? 拷問なのか? フォワグラや北京ダックとなるために飼育されているアヒルになった気分です(もっともアヒルは痛覚が鈍くて、強制的に餌を食べさせられても苦しくはないそうですが)。「太らせなくったって食卓に上げるくせに、どうして動物虐待とか言うんだろう? 幸せ一杯健康的に育てられ、安心しきったアヒルの信頼を最後の最後で裏切るのとではどちらが罪深いのかしら?」とか「トマトが甘くなるようにぎりぎりまで水を与えないでいると、バケツと柄杓を携えた植物保護団体の運動家に妨害されるのだろうか?」とか哲学的命題を思索して気をまぎらわせましたよ……というのは嘘です。そんな余裕はありません。人間追い詰められると、目の前のことしか頭にありませんからね。とはいえ目の前にあるのはミョーにリアルなR‐15指定映像。苦しさとやるせなさから涙で視界がぼけてきました…。あ、そうか、目をつぶればいいんだ。

こうしてさんざ苦労した挙句の果てが「軽い胃炎みたいですねー」だってさ。定期健康診断の前日は夜8時までに食事を済ませなくてはいけないとかで、あわてて近くのラーメン屋に飛び込んで担担麺を食べたんですが、そのせいでは…? 以前、丸呑みさえすれば調べたいところまで勝手に泳いでいって写してくれる、カプセル状ヒレつき胃カメラが開発されたという報道がありました。なんと一億総人間ポンプ計画! ぜひとも実現してほしいものです。
さて、検査の後は「がんばった自分へのご褒美」(笑)と思って、いそいそとトンカツを食べに行きました。上野近辺はトンカツ屋さんの名店が多くて有名ですが、まあまあ結構なお値段ですし、さすがにこの年齢になると昼にトンカツはちょっと重たくて…。その点、今日は特別だぞ。なにせ今回も夜8時以降何も食べるなっていわれてたからね。
 向かうは「本家ぽん多」。いかにも重そうな木製の立派なドアに臆して入れずにきた名店です。なるほどここのトンカツときたら、あんなに肉は厚いのに衣は色白で、さっくり軽くて油ぎれがよい。揚げ終わったらすぐに油を大きなボウルに移していたのをみて、どんなものを使っているのか会社に戻って『日本の洋食』を調べてみたら、自家製のラードだそうです。むむむ、動物性油だからといって重たいとは限らないのですね。勉強になりました。
向かうは「本家ぽん多」。いかにも重そうな木製の立派なドアに臆して入れずにきた名店です。なるほどここのトンカツときたら、あんなに肉は厚いのに衣は色白で、さっくり軽くて油ぎれがよい。揚げ終わったらすぐに油を大きなボウルに移していたのをみて、どんなものを使っているのか会社に戻って『日本の洋食』を調べてみたら、自家製のラードだそうです。むむむ、動物性油だからといって重たいとは限らないのですね。勉強になりました。
余勢を駆って日を改めて今度は「蓬莱屋」へ。こちらは純和風の建物とヒレ肉が売り物で、衣はごく薄くて濃い狐色と、何から何まで対照的。厚い肉の芯まで火が通るように、揚げてからすぐに切り分けずに、しばらく休ませていたのになるほどと思いましたね。
ところで上野はいつからトンカツの町になったのでしょう。昭和の初めにはすでにトンカツといえば上野のようでしたが、いつ、ここまで普及したのでしょう。
 トンカツの歴史については、そのものずばり『とんかつの誕生』という本がありますが、残念ながらトンカツについては巻末間近の第5章で取り上げられるのみです。著者の岡田哲先生はトンカツにはさほど思い入れはなくて、サブタイトルの『明治洋食事始め』が執筆テーマだったのに、編集者が売れそうなタイトルにしちゃったのでしょう。その証拠に本書ではトンカツの誕生に関する論考は富田仁氏の『舶来事物起源事典』にゲタを預けております。明治28年に銀座の「煉瓦亭」が豚肉のカツレツを始め、大正10年には早稲田高等学院の学生がかつ丼を発明、そして御徒町の「ポンチ軒」島田信二郎が改良し、厚い豚肉を使って箸で食べやすく切り分けたトンカツを昭和4年に発明したというのがざっとのあらましです。さらに大正7年には浅草の「河金」がカツカレーを始めたというところが『舶来事物…』にはない新知見ですね。
トンカツの歴史については、そのものずばり『とんかつの誕生』という本がありますが、残念ながらトンカツについては巻末間近の第5章で取り上げられるのみです。著者の岡田哲先生はトンカツにはさほど思い入れはなくて、サブタイトルの『明治洋食事始め』が執筆テーマだったのに、編集者が売れそうなタイトルにしちゃったのでしょう。その証拠に本書ではトンカツの誕生に関する論考は富田仁氏の『舶来事物起源事典』にゲタを預けております。明治28年に銀座の「煉瓦亭」が豚肉のカツレツを始め、大正10年には早稲田高等学院の学生がかつ丼を発明、そして御徒町の「ポンチ軒」島田信二郎が改良し、厚い豚肉を使って箸で食べやすく切り分けたトンカツを昭和4年に発明したというのがざっとのあらましです。さらに大正7年には浅草の「河金」がカツカレーを始めたというところが『舶来事物…』にはない新知見ですね。
これによると豚のカツレツがトンカツと呼ばれるようになるまで30年以上かかった計算になります。おまけにカツカレーとかつ丼はトンカツのお兄さんのようですが、どちらも切り分けずにでーんと丸のまんまカレーや丼飯に添えていたんですかねえ。かつ丼はスプーンで食べていたのかな?
『舶来事物起原事典』は小菅洋子氏の『にっぽん洋食物語』を参考にしており、トンカツの起源の項目はこの本が典拠であることがわかります。そんでもって『にっぽん洋食物語』はというと1970年刊の『事物起源辞典』(まぎらわしいですね)を参考にしており、ここにはかつ丼とポンチ軒の話はでてくるのですが、煉瓦亭は登場しておりません。たどっていくと、新しい著者が次々と新知見を付け加えることによって、話が深まるどころかこんがらがっていく過程が見えてきます。うーん、Wikiみたいだ。
また岡田先生は、明治大正の料理文献で紹介されているカツレツのレシピを一覧表にまとめて、初出は明治28年の『女鑑』と紹介しています(これは明治24年から42年まで出版された婦人雑誌なのですが、引用中にも参考文献リストにも何月号なのか書かれていません。雑誌記事だってわかってんのかなあ)。うーん、これっぽっちの量で変化を追うのはちょっと危険ですね。なぜなら洋食の場合は翻訳も多いので、現実にその時代の日本のお店や家庭で行なわれている調理法を反映しているとは限らない。また単行本は過去に発表した記事をまとめて出版したりしますし、当時の人たちは(今の人も?)、ちゃっかりよその本のレシピを写したりもいたします。そのため昔の作り方の本と新しい今風の作り方の本が同時期に出版される可能性もありますので、かなりのサンプルを見つけて世の中の流れの変化をつかまねばなりません。
表を見ていると新聞、雑誌から採った情報の絶対量が足りません。本に載っているレシピや料理店なんてのは九牛の一毛、大海の一滴ですからねえ…。ところが岡田先生の本に限りませんが、明治大正の料理の由来を扱った本でみずから雑誌や新聞まであたって丹念に調べた例に出会った試しがありません。例外は、前坊洋氏の労作『明治西洋料理起源』くらいでしょうか……(ちなみにこの本によると明治23年5月4日の新聞『時事新報』に「ポークカトレツト」が登場するそうです)。『にっぽん洋食物語』でこの分野の先鞭をつけた小菅氏は、『近代日本食文化年表』では新聞記事などからの引用も挙げていますが、これは森銑三『明治東京逸聞史』からの孫引きなどでして、ご自身で調べた形跡がどうもうかがえません。
まあ古い雑誌や新聞は所蔵先が少なくて調べるのは大変ですが、料理本にしたって公的な図書館の所蔵状況はけっして良いとはいえないんですよ。たかが料理の作り方の載った本なんか大学図書館では相手にしませんし、公立図書館でも実用書を大事に後世までとっておこうという心理が働きづらいのでしょう。おかげで稀観書の数たるやおびただしいこと…。料理本を調べるなら調べるで、相当な覚悟と手間が必要なんですぞ。
そんなわけでして、洋食の始まりに関する本はおおむね手放しで信じることはできません。自分の足で調べずに安易に過去の著作を孫引き、おっと違った「参考」にするものだから、いつまで経っても同じところで足踏みしていて謎が解明される気配がありません。
一例を挙げましょう。岡田氏の本は「明治洋食事始め」をうたっておきながら明治後半から大正にかけて流行した屋台の洋食の実態についてはほとんど考察しておりません。御維新の頃には珍しくて高級だった洋食も、あっという間に庶民のところまで降りてきまして、露天の屋台商が現れ、普及に一役買いました。当時の素人向け開業案内書に、うどん屋やおでん屋などと一緒に洋食の屋台も候補に挙げられておりまして、フライやシチューのような煮込みものを出していたことがわかります。衛生的にそのほうが安心だったからでしょうね。にぎわう浅草や上野は、そうした屋台の多い土地でした。
カツレツの歴史もこの屋台という業態抜きには語れません。岡田氏自身も例のカツカレーは、大正7年に「東京浅草で、屋台洋食を始めた河野金太郎が始めた」とさらっと紹介しておりますが、それがなんだかわかってない。あともう少し掘り下げてほしかったなあ。たぶん人気料理だから両方ともメニューにおいたものの、什器の数も洗い物の回数も省力したい屋台営業ですから、えいやっと一皿に合体させちゃったんじゃないですかねえ。
 実はあの「蓬莱屋」も屋台からスタートしています。昭和6年10月1日号の『実業之日本』によると、それは大正6年4月4日のことで、創業者の山岡正輝さんは当時42歳。愛媛県の造り酒屋だった山岡さんは家産が傾き、はるばる東京に出て小資本で始められる屋台の洋食屋に賭けたとあります。カツの揚げ方はまったくわからず、隣の天ぷらの屋台の主人に教わったとか。安くてうまいのをめざしたのはもちろんですが、繁盛したのはお客さんが山岡さんの気性にひきつけられたから。ぼろを着た労働者でも平等に扱い、その一方でごねて迷惑をかける酔客は許さない。この年齢だからこそできる客あしらいですね。10年で店を持つという夢には少し遅れましたが、昭和3年9月28日に同じ上野広小路の地で立派な店舗を持つことができたとのこと。記事をなんでもかんでも鵜呑みにするのは危険ですが、店舗開業から3年後に主人に直接取材した内容ですから、戦後の食べ歩きマニアの噂話なぞよりははるかに信頼性が高いでしょう。ご丁寧に日付まで入っていますしね。
実はあの「蓬莱屋」も屋台からスタートしています。昭和6年10月1日号の『実業之日本』によると、それは大正6年4月4日のことで、創業者の山岡正輝さんは当時42歳。愛媛県の造り酒屋だった山岡さんは家産が傾き、はるばる東京に出て小資本で始められる屋台の洋食屋に賭けたとあります。カツの揚げ方はまったくわからず、隣の天ぷらの屋台の主人に教わったとか。安くてうまいのをめざしたのはもちろんですが、繁盛したのはお客さんが山岡さんの気性にひきつけられたから。ぼろを着た労働者でも平等に扱い、その一方でごねて迷惑をかける酔客は許さない。この年齢だからこそできる客あしらいですね。10年で店を持つという夢には少し遅れましたが、昭和3年9月28日に同じ上野広小路の地で立派な店舗を持つことができたとのこと。記事をなんでもかんでも鵜呑みにするのは危険ですが、店舗開業から3年後に主人に直接取材した内容ですから、戦後の食べ歩きマニアの噂話なぞよりははるかに信頼性が高いでしょう。ご丁寧に日付まで入っていますしね。
蓬莱屋のHPを見ますと二度揚げとヒレを使ったカツはここが始まりとありますが、残念なことにこの記事ではそこまで触れておりませんでした。ただ、経営誌なので料理の作り方に関心がなかったかもしれませんし、昭和6年以降の可能性も否定できません。ほかの戦前の文献を見ていると確かに蓬莱屋は昔からヒレカツを売り物にしていたようです。
正直な話、トンカツがらみの発明者はいろいろ候補が挙がっていまして、理路整然と説明するのは困難です。まず日本に伝わったカツレツがあり、それが普及し、進化を遂げた。その過程に関わっていろいろ工夫を加えた人たちがみな発明者として名乗りを上げているために、話が混乱していると思われます。誰が最初かどうかなんてのは、当人の思い込みもあるでしょうし、よそにも同じことを考えついた人がいてもおかしくないでしょうしね。
庶民的な料理ほど記録に残りづらく、起源を調べるのは実に難しい。それなのにテレビだの食べ歩き雑誌だのは、発明秘話を取り上げたがります。唐辛子の伝来じゃありませんが、「だいたい○○年くらい」でもいいと思うのですが、それでは企画にならないようです。
そもそもトンカツの起源と発達史を語るには、オリジナルの「カツレツ」についても視野に入れて考察せにゃなりませんが、もはやスペースがありませんね。ちょっと胃カメラの話で熱くなりすぎました。続きは次回に。
投稿者 webmaster : 11:41
2011年09月27日
料理本のソムリエ [ vol.29]
【 vol.29】
ところでこのブログって何なの?
いつの間にか予告宣伝もなしになあんとなく始まったこのブログ、はたして1年続けさせてもらえるかしら、と思っていたのですが、いつのまにか30の大台に突入寸前、1年と5カ月も続いておりました。
 震災直後は新着情報の欄に『地震の時の料理ワザ』のPDF無料公開という重要なお知らせが貼り付けてあったので、それを押しのけないようにと更新をお休みしているうちにすっかりボケて、1周年を見過ごしておりました。
震災直後は新着情報の欄に『地震の時の料理ワザ』のPDF無料公開という重要なお知らせが貼り付けてあったので、それを押しのけないようにと更新をお休みしているうちにすっかりボケて、1周年を見過ごしておりました。
いまさら約1周半年記念もないのですが、ここであらためてこのブログについて説明しましょう。ときどき料理本からそれてきて、原発とマスコミ批判なんだか古本自慢なんだかおっさんの繰言なんだか、コーナーの趣旨がよくわからなくなったりしますし。
このブログの存在意義は、ずばり!「編集部だより」の埋め草です。当社HPでは新刊の発売がありますと、担当編集者が工夫をこらしてその書籍の見所や編集上の苦労話などを紹介しております(必見ですぞ)。ところが新刊書籍の刊行は編集や印刷の都合で、コンスタントに続くとは限りません。これでは更新がまばらになってしまう。そこで2週に1回くらいのペースで定期的に何か記事を配信し、いつもこのページの存在を気にかけていただこうと、世にあまたある料理本を広く案内するコーナーが設けられたというわけです。そのため新刊書が多い週はお休みしたり、パソコンのハードディスクがお釈迦になった週はお休みしたり、自分の仕事でお尻に火がついた週はお休みしたりと、休み多めで気ままにひっそりと更新しております。
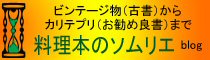 「料理本のソムリエ」というタイトルは良書をガイドしようという狙いからだったのですが、本の紹介はそっちのけでだんだん雑談中心の「料理本のおたく」の色合いが濃くなっております。1年以上経ちました間にわが社HP のコンテンツも充実してきたので、もはや風前の灯といえましょう。
「料理本のソムリエ」というタイトルは良書をガイドしようという狙いからだったのですが、本の紹介はそっちのけでだんだん雑談中心の「料理本のおたく」の色合いが濃くなっております。1年以上経ちました間にわが社HP のコンテンツも充実してきたので、もはや風前の灯といえましょう。
料理本の紹介コーナーにしては、圧倒的シェアを占めるおかずレシピ本をほとんど取り上げておりませんが、これはレシピのよしあしというのは好みが反映しやすくて、誰にでもお勧めできると言い切るのが難しいため(というのが逃げ口上)。読者がどんなライフスタイルなのか(「ごちそうさマウス」が聞きたいステキな奥様なのか、だめんずを旦那にもったOLなのか)、誰のために作るのか(毎日ドカ弁持参の体育会系中学生なのか、「油物は苦手だとあれほど言っているのに!」が口癖の姑なのか)でも、評価基準がずいぶん違ってきますし。まあ専門書の出版社のHPなので、おかずレシピ情報を求めている読者はおるまいし、そもそも家庭の主婦どころか料理人さんすらこのブログを閲覧しているのかしら? たぶん読者は新刊情報を得るためにご覧になる書店関係者やお世話になっている取引関係のかたが多いと思うので、本好き相手を前提に社内報感覚で書かせていただいております。だから、やたらに本郷や湯島界隈の話題が多いです。
営業的には柴田書店の既刊書(それもまだ在庫のあるもの)をもっと取り上げるべきなのですが、そればっかりなのも口はばったいよなあ、写真を多く入れようとするとどうしたって柴田の本から採ることになるしねえ、などと逡巡しているうちに、あっという間にあらぬ方向へと迷走し始めました。おまけに vol.15 でソムリエどころか、ご隠居であることをみずからリークしてしまいました。話題がかびくさい方面に偏っているうえに、いちいち揚げ足取り調なのは年のせいと思って勘弁していただきたく思います。むかーし、月刊誌の書評コーナーを担当していた頃、以前もさんざん見たことのあるような安直な料理本が次々と出版されるのに「お前ら料理本をなめとんのかっ」と切れかけた辛い経験がありまして。なにせ、当時はネットなどありませんから、出版取次の新刊予告を隅から隅まで読んで、おっ、これは取り上げられそうだぞというのを見つけるたびに本屋に走るというアナログな選考方法をしていたので、期待が裏切られると憎さ百倍。これはぜひ紹介したいという料理本を毎月3冊探し出すのが、なかなかの負担でありました。
その点、ここでは冊数の決まりもないし、新刊に限っていないので気楽です。コメント欄がないので炎上もしませんしね。そのぶん、どなたが読んでくださっているのかさっぱりわかりませんが…。
そもそも「専門出版社は取材先がイコール読者なので、読者の顔が見えている」なんて言われますが、そうとも限りませんぞ。料理長さんのところに取材に行っても「若い頃はおたくの本で勉強したよ!」っていうありがたい話をうかがうことはよくありますが、最近の本となると意外と話題になることが少ないのです。お忙しい料理長クラスは普段そんなには本を読まれないようですし、今さらよその人の料理を見て参考にする必要もないのが当然でしょうし。ただ、さんざん「昔は読んだ」と聞かされるのも切ない話です。今はいったいどんな方が柴田書店の本をどう読まれているのでしょう。Amazonを見ても売れてる本だからといって必ずしもコメントがついているとは限らないし……。
その点、綴じ込みの読者ハガキの回答は、ためになりますしはげみになります。お叱りもまた甘んじて受けておりますので、どうかご返信お願いします。でもあえて、あえて言うなら、ほめてくださると担当者はうれしいです。とてもうれしいです(大事なことなので二回言いました)。ただ、ときどき同業他社の本を小社の出版物と勘違いされて、おほめの言葉をくださる方もいらっしゃいますが……。
ハガキの場合、マメに返してくださるのは、どうも料理人さんよりは会社関係や主婦の方が多いようです。それもどうしても年齢層は上のほうに寄っています。ときにはリタイアされた料理好きな方だったり、会社のお偉いさんだったり。こうしたかたは、ときどき思い入れの余り小社に直接電話をかけてくださることもありますが、多忙の折はどうかどうか短めに……。
じゃあ、若い人には小社の本をご覧いただけていないのか。どんな感想を抱かれているのか。ブログやツイッター上に流れているかしらと思って検索しても、これまたそうは多くヒットしません。つぶやきは短いですから、読んでためになったのかならなかったのか、よくわからないこともあるし、ブログはアフィリエイト狙いも多いし……。そもそも料理本ってほかの本との違いを説明しづらく、紹介したり話題に上げたりするのが正直面倒ですよねって書いたりすると、このブログの存在理由が脅かされるのでこの辺でやめておきます。
こうした不安を抱いたときには、本屋さんへと参ります(リアル書店万歳!)。料理本の棚に行くとときどき小社の本を読まれている方がいらっしゃるので、棚の影から星明子ばりに温かい目で見守るわけです(キモっとか言わないでください。承知してるし)。たとえ他社の本でも、何が人気なのか、どこが面白いのかは立ち読みしている人の目の色でわかります。まあできれば小社の本をレジに持っていってもらえるとうれしいので、「買えー、買えー」と念を送ったりもしますが、あんまり効果がありません。
時には若い料理人さんが彼女さん連れで来店して、本の内容をいちいち説明しているなんていうほほえましい場面にでくわすこともあります。「この料理(パテ・アンクルートでした)、今うちの店でも出してるけど、うまいんだよねえー」「えー、こんど食べさせてよー」とか。え? 別にやっかんだりしてませんよ? 会話してもらうとどこをどのように読んでいるのかわかり、いいデータが取れますので大歓迎。もっともいつの間にか料理と違う雑談に変わった挙句の果てに、一冊も買わずに帰られた日にゃ、落胆と殺意のこもった目に変わりますが。でもよく考えたらカップル客の多いカウンター店の料理人さんは、しょっちゅうこういう目にあっているわけですよね。若い皆さんは料理がサービスされたら、お話を中断してすぐに箸をつけましょうね。
その点、電車の中で小社の本を開いている人に出会ったときは、確実に購入してくださっているので(そりゃそうだ)手放しにうれしいです。めったにありませんが。私の先輩は、電車に乗っていたら隣に座った人が自分の編集している雑誌を持っていたのでうれしくなって「その本のどこが面白いですかっ?」って思わず聞いてしまった、なんて話もあります。一般誌やベストセラーをばんばんヒットさせている出版社と比べると、いじらしくも涙ぐましい話です。


私が去年出くわしたのは別冊の『イタリア料理の技法』を読んでいらっしゃるかたでした。ずいぶん古いムックです。先輩に借りたのかなあ。おおっ、そこのページの座談会は私が月刊誌時代に担当した企画だぞっと思ってわくわくして見ていたら、いきなりとばされました(泣)。アーリオ・オーリオのページを熟読されています。まだ修業したての人なのかなあと思っていると、リゾットのページにきたらパスタに戻ってラヴィオリの打ち方をガン見。急に難易度が上がりましたよ。余計なものはいいからパスタをがんがん見せろという意志表示でしょうか。もうどうしたら彼の琴線に触れることができるのか、わかりません。
夜の電車は仕事帰りの料理人さんらしきかたも多いですね。
 『サラダ・サラダ・サラダ』をご覧になっているかたを目撃したこともあります。ところが、座って読んでいるうちに、どうしても仕事疲れのために眠くなってしまう。ぱたんと閉じてはハッ、ばさっと取り落としてはハッ……。最後には観念して大事そうにしっかりと胸に抱きかかえておやすみになってしまいました。うっかり車内に忘れたら大変ですからね。カバンに入れづらいサイズのちょっと高めの本ばかりで申し訳ありません。明日もどうかお仕事頑張ってください。
『サラダ・サラダ・サラダ』をご覧になっているかたを目撃したこともあります。ところが、座って読んでいるうちに、どうしても仕事疲れのために眠くなってしまう。ぱたんと閉じてはハッ、ばさっと取り落としてはハッ……。最後には観念して大事そうにしっかりと胸に抱きかかえておやすみになってしまいました。うっかり車内に忘れたら大変ですからね。カバンに入れづらいサイズのちょっと高めの本ばかりで申し訳ありません。明日もどうかお仕事頑張ってください。
投稿者 webmaster : 18:53
2011年09月14日
料理本のソムリエ [ vol.28 ]
【 vol.28】
トウガラシ伝来は日中韓のどこが先?
9月に入っても暑さがなかなか引かないですね。まるで東南アジアみたいな蒸しっぷり。もわっとした風呂場で生活しているみたいです。こういうときは辛いものが一番とばかりに、会社にイスラエル産のトウガラシがもたらされました。じんわり辛いのとパプリカのような味のと2種類、営業部のT君の到来物です。最近イスラエルでサッカーの試合があったっけ?と首をひねりましたが、どうやら今回はただの夏休みのバカンスのようです。
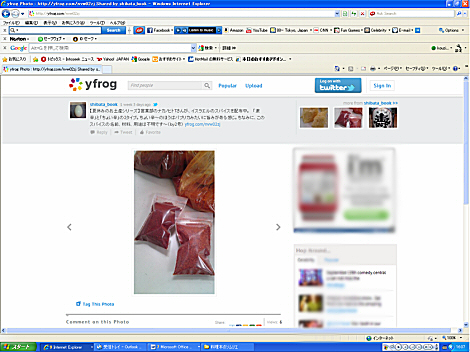
ということで今回はトウガラシがテーマ。海の向こうのとほほな記事をつまみにしたいと思います。ちょっと前、韓国食品研究院は「トウガラシは朝鮮半島に自生していた」という香ばしい(トウガラシだけに?)新説を主張したそうです(4月27日付のexciteニュース“唐辛子は日本から韓国に伝わってきた!? 唐辛子のおもしろ由来”・5月9日付のsearchina“「唐辛子は朝鮮半島に自生していた」韓国人学者が日本伝来説を否定”)。
あいにくハングルが読めないので大きなことはいえませんが、記事を見る限りにおいては、あちらのトウガラシ研究者さんは揃いも揃って漢文を扱うのが苦手のようで、大真面目であらぬ方向に突き進んでいます。韓国では漢字教育が排されて久しいとはいえ、こんなことではご先祖様への冒涜にならないんですかねえ。同研究院の権大泳(クォン・テヨン)博士は、以前もコチュジャンは15世紀から文献に登場しており、この頃からトウガラシは韓国にあったなどと主張しており(2009年2月19日付の中央日報“唐辛子、朝鮮初期にもあった”)、昨日今日で思いついた珍説ではなさそうです。ちなみにヨーロッパに最初にトウガラシをもたらしたのは1493年に帰国したコロンブスだそうですが……。
もっともわが邦の愛国青年におきましても、そそっかしさにおいてはけっして半島の民に負けてはおりません。Wikipediaでは朝鮮の文禄年間に書かれた『芝峰縲絏』に「倭国から来た南蛮椒には強い毒がある」と書かれていると紹介されており、それをそのままコピペして韓国自生説を批判しているHPをいくつも見かけました。まずは落ち着いて芝峰縲絏なる本(?)がどこの所蔵で、そのどのあたりに書いてあるのかを調べてからにしなさいな。反日工作員が仕掛けた釣りかもしれませんぞ。
南米原産のトウガラシがどのようにして東洋世界に広がったかというのは、実はなかなか興味深い話題です。韓国へは日本を経由して伝来したという説はvol.2でも紹介した李盛雨先生が打ち立てたものなのですが、国家の誇りのkimchi(「キムチ」ではありませんよ。発音が違う!とトウガラシのように真っ赤になって怒られちゃいますよ)の主材料が日本伝来などという事実はどうしても認めたくない人たちがいるようです。李先生の衣鉢を継ぐ鄭大聲氏も小社刊『朝鮮食物誌』で、日本経由や中国経由のほか、ヨーロッパから直接もたらされた可能性もあると結論を留保されています。しかし残念ながら当時の宣教師は朝鮮半島では布教活動を行なっておらず、交易船が立ち寄ったという記録もありません。南米の産品の流入は中国や日本が先行したのは明らかです。
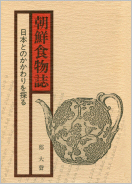
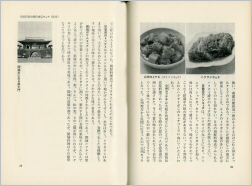
それでは中国→韓国→日本というルートはどうかといいますと、中国にトウガラシが伝来したのもかなり遅いのです。トウガラシ抜きの四川料理なんて考えられない気がしますが、一般に食用されるようになったのは清の時代から。中国文献のトウガラシの初出は1591年の『遵生八牋』とされていますが、ここでは「使い古した筆の先みたいな形で、辛い味」の観賞用植物として登場しております。この本は隠逸思想に基づく理想の生活を述べたものでして、養生のための料理も多く紹介されていることで有名なのですが、明代前半の『易牙遺意』のレシピからの丸写しが多いせいもあってか、食材としては出てきておりません。もっともこんな辛いものは養生のためにならん、と無視したのかもしれませんが。
ちなみに日本におけるトウガラシの記録の初出は『多聞院日記』で1593年。要約すると、「コショウの種をもらって植えてみた。ナスの種のように少し平たく、皮は赤い袋で中に種がたくさん入っている。赤い皮の辛さは肝をつぶす。コショウの味でもなく辛いこと類がない」とあり、コショウであってコショウより辛いこれはどうみてもトウガラシのことでしょう(今でも柚子胡椒なんていいますものね)。日本はすでにこの頃、奈良にまでトウガラシの種が普及していて、常食したかどうかは別として、その味も知られていたことがわかります。それにしても興福寺のお坊さんともあろうものが、辛くて刺激的な植物に興味を示すとは。隠逸なんてとてもできそうにないですね。
いっぽう李盛雨氏の日本伝来説は、李氏朝鮮では1614年の百科全書『芝峰類説』が初出であり、「倭国からきたので俗に倭芥子と呼ぶ」とあることからくるものです。また当時の料理やキムチのレシピにもトウガラシらしきものがまったく見当たらないのも状況証拠としています。理性的な判断ですね。なお前述の『芝峰縲絏』は、どこかの慌て者が“ルイセツ”を誤ってワープロ変換したものでしょう。よく見りゃWikipediaに引用されている内容は『芝峰類説』とおんなじです(だいたい「縲絏」=お縄にかける、捕縛するで、書名としてへんてこなことは明白なんですが……)。
こうなると韓民族の自尊心を保つためにはあっと驚く逆説の韓国史、日本や中国どころかヨーロッパも経由しない“韓国自生説”の出番しかありません。アジアとアメリカがつながった氷河期にトウガラシが渡来し韓半島の奥地でひっそりと生き残っていたのか、コロンブス以前に中南米の文明と李氏朝鮮との間にひそかな交流があったのか……。壮大なロマンにわくわくしてきました。マヤ文字はハングルから作られたのかもしれませんぞ。
実はトウガラシの伝播については2009年刊の『キムチの文化史』で佐々木道雄氏が日韓の多くの資料を渉猟しておりまして、権先生らが挙げた文献にもとうに触れております。宣教師のルイス・フロイスが1577年8月10日の書簡で、日本人が喜ぶ品として酢漬けのトウガラシを挙げていることも指摘しています。ただし、残念なことに佐々木先生も日中韓の伝来時期にやたら拘泥しておりまして、隘路にはまっております。そもそも中国の文献には疎いようで、よせばいいのに中国語版Wikipediaを参照して論を組み立てるものだから、先行研究を無視して遠回りしてみたり……。みなさんどうしてこうもWikiが大好きなのかなあ。なお中国ではGoogle同様にWikiも風当たりが強く、国産の「百度百科」のほうが盛んに使われてまして、トウガラシの由来についての記述もこちらのほうが格段に詳しいです。
ちなみに今の中国語ではトウガラシは「辣椒」ですが、昔は「蕃椒」と呼んでおりました。蕃は蕃国、つまり海外から来た食材を指す言葉ですね。それをいうなら胡椒の「胡」も西域を示す言葉ですからまぎらわしい。実際、当時の文献をみると山椒と胡椒と蕃椒がこんがらがって学者の頭を悩ませている様子がわかります。言葉は変化しますからなおのことで、文献で見つけた単語がトウガラシを指すと同定できる確たる証拠が必要です。
たとえば例の韓国食品研究院の権先生は、1489年の救急マニュアル『救急簡易方』に「卒咳嗽、以梨一顆刺作五十孔、毎孔内以椒一粒…」とあり、文中の“椒”にハングルでコチュと注がつけられていたことから、これはトウガラシであると主張します。しかしこの処方箋は結構いろいろな中国医書に載っておりまして、オリジナルはなんと東晋(4世紀)の時代の『肘後備急方』にまでさかのぼれます。そもそも梨に50の穴を空けて1粒ずつ入れるのに使う「椒」というのは、粒の大きさからいって山椒か胡椒あたりが無難では……。事際、明代の『普済方』は同じ処方箋を川椒(四川のサンショウ)と改めておりました。新高にタイ産のプリッキーヌーを刺すのなら、なんとかなるかなあ。あるいは半島の人は中国の医学書に載っていた薬をまちがえて別の国産材料で一生懸命作ってたってことなんでしょうか(それで治るのか?)。権先生がコチュジャンのことだと主張する「椒醤」も、実山椒のペーストか何かと考えるほうが無理がないと思うのですが……。
中国の文献にでてくる植物名が自国の何にあたるのかを調べるのは古来より「名物学」といいまして、日本でも韓国でも漢文に堪能だった昔の人の研究のほうが今よりよっぽどまともだったりします。江戸時代のトウガラシ研究で出色なのは、平賀源内の『蕃椒譜』。彼が偉いのはここに挙げたような文献集めだけでなく、当時栽培されていたトウガラシを収集、図解するという自然科学的な視点も備えている点です。中には黄色くて金柑のような姿のものや、ハバネロみたいなベル形のものもありますが、いったいどんな味だったのでしょう。


『平賀源内全集』 より
この資料は源内自筆の稿本が昭和になって発見されて、戦前に完全復刻されている(なにしろ上から紙を貼って加筆した部分もオリジナルに忠実に)ため、今でも見ることができますが、そのオリジナルは戦火を逃れることはできたのでしょうか……。
源内の時代から日本のトウガラシ伝来は諸説ありまして、今に至るまで決定打はありません。そもそも数少ない文献を頼りに今さらどこが先に伝来したかを取沙汰したところで、サッカーの試合を韓日戦と呼ぶか日韓戦と呼ぶかのようなもので、さほど建設的とは思えません。多少前後するにせよ日中韓ほぼ同時期に広まったと考えてよいでしょう。実際遺伝子的には三国のトウガラシはかなり近い関係にあるそうです(『トウガラシ 辛味の科学』)。つまらない家元争いのエネルギーはもっと別のところにふりむけてほしいものです。
というのも、世界全体を見渡しても、トウガラシは短期間で一気に広まったようなのです。『世界を変えた野菜読本』を開くとサハラ砂漠以南のアフリカに普及したのが1500年代前半で、インドで数種類のトウガラシが栽培されたのが1540年代とあります。ドイツの植物学者フックスはトウガラシをインドペパー、イギリスのジェラードはギニーペパーとして紹介しており、スペインから東向きに伝わったのではなく、インドやアフリカから逆戻りしたことがわかります。一方、ハンガリーのようにトルコ帝国から伝わるケースもあるようです。こうしてみると16世紀後半が転換期のようでして、あっという間にグローバル化。東アジアの端っこレベルではなく、世界規模で研究したらさぞや面白そう。もっとも各国の文献に通じていなければならず、学際的な大プロジェクトになりそうですが。
既刊の『トウガラシの文化誌』は著者がインド生まれということもあって広く世界に目配りされており、タバスコなども含めていろいろな薀蓄が語られています。また日本の歴史・民族学者たちが結集して自分の研究対象地域のトウガラシの使い方を紹介する『トウガラシ讃歌』は、ありとあらゆる地域(なにせ中南米やヨーロッパはいわずもがな、トルコにアラブ、西アフリカにエチオピアにタンザニア、フィリピン、ネパール、ブータン、チベットまで)の使用法が登場いたします。しかし両書とも惜しいことに、伝播の過程とその影響、つまりトウガラシ渡来以前と以降で食文化がどう変わったのかがよくわかりません。
やれ「中国4000年の味」だとか、「舌は三代」などといいますが、とんでもない。いいとなったら未知の食材でもまたたく間に広がり、それまであった味の体系そのものまで変わってしまう。そこが面白くもあり、知りたくもあります。人間はそれだけ柔軟性を持っている。となると料理は今現在も、刻々と姿を変えていることでしょう。
投稿者 webmaster : 10:03
2011年08月31日
料理本のソムリエ [ vol.27 ]
【 vol.27】
門前の小僧習わぬ粥を語る
うーん、最近のNHKの「ためしてガッテン」はどうしちゃったんですかねえ。前に魚のおろし方について独自解釈を展開されたと思ったら、今度は7月20日の放送で白粥の炊き方を取り上げて、堂々のレシピ本批判。またもや「今やお粥だけのレシピ本も登場!」なんて言いつつ、スタジオに各社の書籍をずらりと並べた挙句、「どうしてこういうレシピができてしまったのかねえ」なんてことを上から目線でのたまっておりました。
 今回はそこに柴田書店の『おかゆ』も入っていたのをこちとら見逃しませんでしたよ。なんだお前、また突っ込んでほしいのか? 誘い受けか?
今回はそこに柴田書店の『おかゆ』も入っていたのをこちとら見逃しませんでしたよ。なんだお前、また突っ込んでほしいのか? 誘い受けか?
ADを呼び出して土下座させるなんて恐喝まがいなことはいたしませんが、何を変だと思ったのか、どこが浅いのかはきちんと明らかにしておきましょう。ハイ、ここでテーマです。「かゆいところに手が届く、かゆの炊き方大解剖」。
この番組では京都の瓢亭さんの朝粥(公共放送ですから店名は明らかにしませんでしたが、誰が見たってわかります)を「究極のお粥」として取り上げておりました。瓢亭さんのお粥は沸騰した湯にといでおいた米を入れて、時折かき混ぜながら炊きまして、うどんをゆでるときのように途中で差し水をします。土鍋ではなく鉄鍋を使い、終始蓋はいたしません。確かに土鍋でお粥を炊く際に普通いわれているような、水から吹きこぼさないようにことこと炊いて、米の粒が崩れるのでけっしてかき混ぜない、という方法とはまったく違いますよね。少々時間が経っても糊のようにならず、おいしく食べられるのが特長だそうです。
だからといって、ちまたの料理本のお粥の炊き方はことごとくまちがいであーる、みたいな演出はいかがなものか。 NHKの「きょうの料理」を俎上に挙げて比較検討するっていうならまだ話はわかりますが。そもそも民放のバラエティ番組ならいざ知らず、「門外不出」「秘義・奥義」を一挙公開って……。北斗神拳かいな。
 この炊き方は「湯炊き」といいます。NHKでは初公開なのかもしれませんが、『瓢亭 四季の料理と器』にも鉄鍋で湯炊きにしている旨ちゃあんと書かれていますね。ちなみに料理屋さんでは急いでごはんを炊きたいときに(足りなくなりそうなときとか)この湯炊きで炊くことがありますが、ご飯の場合はちょっとぱらぱらっとした仕上がりになります。番組内でも分析していたように、米の表面が先に糊化するので、中のでんぷんが溶け出しませんから、固めの炊き具合になるわけですね。それが粥の場合は、粒が崩れにくく、それでいてとろみのついた炊き上がりとなるようです。番組では再現してみた湯炊きの粥を試食して「ご飯に米のとろみをまとわらせたような、お粥界のアルデンテ」と表現していましたが、まさにその通り。
この炊き方は「湯炊き」といいます。NHKでは初公開なのかもしれませんが、『瓢亭 四季の料理と器』にも鉄鍋で湯炊きにしている旨ちゃあんと書かれていますね。ちなみに料理屋さんでは急いでごはんを炊きたいときに(足りなくなりそうなときとか)この湯炊きで炊くことがありますが、ご飯の場合はちょっとぱらぱらっとした仕上がりになります。番組内でも分析していたように、米の表面が先に糊化するので、中のでんぷんが溶け出しませんから、固めの炊き具合になるわけですね。それが粥の場合は、粒が崩れにくく、それでいてとろみのついた炊き上がりとなるようです。番組では再現してみた湯炊きの粥を試食して「ご飯に米のとろみをまとわらせたような、お粥界のアルデンテ」と表現していましたが、まさにその通り。
朝に粥を食べるという習慣は関西のものですから、東京のテレビ局スタッフにはあんまりなじみがないかもしれませんが、かの地の農家では奈良を中心に茶粥が普及しています。これはまず大鍋にほうじ茶を煮出して、そこに米を入れて作ります。鍋に水とほうじ茶の葉と米を一度に入れて煮出しながら炊いてしまう横着な方法もありますが、茶の濃さを調整できませんから少数派のようです。朝食として食べるほか、残りは川の水で冷やして農作業の合い間に食べたりもします(『聞き書 ふるさとの家庭料理 -- 雑炊・おこわ・変わりごはん』)。
瓢亭さんのお粥は、こうした家族で食べる朝食の流れを汲んでいるのではないでしょうか。それに本館の夏の朝食のほか、別館で一年中粥を提供されていますから、家庭以上にたくさん作る必要がありますし、人数分をこまめに焚いて炊きたてを提供するとはいえサービスにはそれなりに時間がかかります。その点で、すぐにふやけて糊状になったりしない湯炊きの利点が生きてきます。いっぽう本に書かれた粥は特別な食事であり、おおかた一人か二人分の一合炊きで、作ったらそのまま食膳に運んですぐ食べることを想定しているから、蓋をして土鍋で時間をかけて炊く方法が一般的なのでしょう。もっとも病気の人や高齢者は、短時間では食べきれないかもしれませんから、湯炊きの粥がお勧めというのは確かにその通り。ガッテンすることしきりです。
一度にたくさんの料理を作るのは、日本料理の世界では「大鍋の仕事」といいます。板前割烹のようなお客さまの目の前で小人数分を作るのは「小鍋の仕事」です。1日1客しか取らない店が偉くて、たくさん作るのは手抜きであるとか勘違いしている素人さんをよく見かけますが、両者は別のノウハウが必要な独立したジャンルです。たくさん仕込むからこそおいしい煮込み料理というものもありますしね。もっとも、究極をめざす会員制隠れ家料理店では、おいしく大量に煮込んだ料理や仕入れの最小ロットが大きな業務用食材でも、余ったぶんは惜しげもなく捨ててしまい、常に理想の状態で理想の料理を提供しているのかもしれませんが。ちなみに日本料理の職人はどちらの仕事もマスターしなければならないと言われてまして、小さな板前割烹での限られた修業経験しかないと、「あいつは大鍋の仕事ができない」とちょっと揶揄されたりいたします。
たくさん提供するといえば、ホテルの朝食バイキングで提供されている白粥などでは、葛でとろみをつけてある例もしばしば見かけますよね。こちらの方法では普通の場合とはどう違うのか、ぜひ科学的に考察してほしかったなあ。
さらにこの番組の最大の問題点なのですが、中国粥についてもまったく言及しておりません。番組冒頭で「各地にある専門店は大人気!」と繁盛風景を映していたのは中国粥の専門店でしたから、その存在を知らないとは言わせませんぞ。そもそも、スタジオに並んだ本の中に、「元気になれる中国とアジアの薬膳粥」というキャッチコピーが書かれた『きれいになれるお粥レシピ』と、ウー・ウェンさんの『北京のやさしいおかゆ』があるのをお見受けしたのですが……。私どもの『おかゆ』にしたって日本の粥と中国粥、両方を取り上げております。
さっそく『きれいになれる…』で紹介されている広東料理の「赤坂璃宮」譚彦彬料理長の炊き方を見ますと……あれあれえー、油をまぶしたお米を湯炊きしておりますよー(立川志の輔調)。なんで番組では触れなかったのでしょう。中国4000年の秘義なのに。
広東では朝から外食でお粥を食べるという習慣があり、専門店で一度に作る量は半端じゃありません。たくさん提供するという目的から、やはり湯炊きが一般的になったのでしょう。それに湯炊きの粥はさらっとしていてもたれづらく、蒸し暑い香港や京都の夏の朝に食べるのに向いているように感じるのですがいかがでしょう。
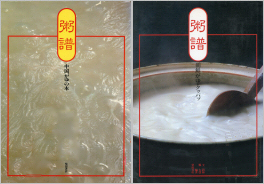 なお、なぜかスタジオに並べてもらえなかった小社刊『粥譜 中国がゆの本』によると広東地方はインディカタイプのパサパサした米が主流で、粒が崩れるくらいまで炊きますが、江南地方はジャポニカタイプの米を使い、お粥も日本とかなり似ているそうです。小社刊の『おかゆ』で紹介されているのは江南の炊き方なんですね。ちなみに先の本はシリーズでして、『粥譜 朝鮮がゆとクッパプ』という本もございます。こちらによると韓国では米をあらかじめゴマ油で炒めてから炊くそうです。ちょっとリゾットみたいですね。
なお、なぜかスタジオに並べてもらえなかった小社刊『粥譜 中国がゆの本』によると広東地方はインディカタイプのパサパサした米が主流で、粒が崩れるくらいまで炊きますが、江南地方はジャポニカタイプの米を使い、お粥も日本とかなり似ているそうです。小社刊の『おかゆ』で紹介されているのは江南の炊き方なんですね。ちなみに先の本はシリーズでして、『粥譜 朝鮮がゆとクッパプ』という本もございます。こちらによると韓国では米をあらかじめゴマ油で炒めてから炊くそうです。ちょっとリゾットみたいですね。
それでは小麦粉文化圏の北京はどうかというと、「稀飯」という名前があるくらいに米の量が少なくて、スープのよう。食べる(吃)ものではなく、飲む(喝)ものだとか。番組では、こうしたさらさらしたお粥は誤嚥(ごえん。食べ物が気管にまちがって入ってしまうこと)の恐れがある「死ぬお粥」・「危険なお粥」として、ばっさり切り捨てておりました。日本人の死因の4位は肺炎であり、そのほとんどは高齢者が発症する誤嚥性肺炎だとおどしていましたが、誤嚥してしまう食べ物っていうのはいつでも必ずお粥なんですかねえ。そりゃあ気をつけねばならないことは重々ガッテンしましたが、好みは人それぞれであり、よしあしをつけるという演出には承服しかねます。中国の人からすれば、日本人は餅(ビン)を食べずに、わざわざ練ってのどに詰まりやすくした「死ぬおこわ」を食べているくせにと笑われちゃいますよ。

日本人は米に粘りやもったり感を求めます。だからコシヒカリがあんなに受けるわけでして、米用の食味計なんてものさえありますが、逆に東南アジアやインドではぱらっとした炊き方を好みます。ですから多めの湯で米を炊いて、途中で湯を捨ててしまう「炊き干し」という調理が一般的。米をゆでている感じですね。日本人は輸入米に対してにおいがあるとか、パサパサしているとか不服を唱えますが、そこがいいという文化もあるわけです。ちなみに江戸時代には炊き干しも行なわれていましたし、大唐米といってインディカタイプの米もありました。同じ品種の米ばかり作っていると田植えや収穫の時期が集中しててんてこ舞いになりますし、いったん日照りや冷害になると全滅する恐れがあるので、同じ農家でも早稲だの乾燥に強いものだのいろいろな品種を同時に栽培していたのです。米も炊き方もいろいろあって、みんな違ってみんないい(by金子みすず)。この方法が正しい、というのはコシヒカリ一辺倒の評価軸しかもたない硬直化した現代人の発想です。
ところで瓢亭さんの湯炊きの粥の作り方のもう一つの特徴は、「蓋をしない」という点にあります。さっそく番組で紹介されたレシピでお粥を炊いてみたのですが、よりによってなぜこの時季にと大公開、いや違った大後悔。いやあ暑いこと暑いこと。朝粥は夏のメニューですから、厨房スタッフの方たちの苦労がしのばれます。
鍋に蓋をするかしないか。これもまた東西の料理技術を比較する上で、大事な問題の一つです。ためしてガッテンでもお粥の話の翌週に放映した節電レシピの回では、あんなに蓋の働きを強調していたのですから、ここにもぜひクローズアップしてほしかったですね。もともと中華鍋は普段から蓋をしませんから、蓋を使わずお粥を炊くのは自然な流れ。日本料理店でも蓋はあんまり出番がないですね。ただし中国にも「沙鍋」のような蓋つきの土鍋もありますし、蒸籠という蒸気を活用する独自の加熱法が……、おっと、これ以上暑苦しい話を続けるのもなんですから、蓋の話はまた別の機会に。
投稿者 webmaster : 10:45
2011年08月10日
料理本のソムリエ [ vol.26 ]
【 vol.26】
なでしこジャパンの食事が気になる
すごかったですね! なでしこジャパンの粘りと折れない心。ウィンブルドンのクルム伊達選手といい、この夏の女子選手の活躍ぶりにはただただ感嘆するばかりです。普段あんまりスポーツ中継に関心のない私も、今回ばかりは話が別。「アナログテレビ終了まであと6日」という親切な字幕とともに後世に残しておくべきと思い、録画予約をしておいたものの、結局テレビの前に座っておりました。よもやの後半戦での引き分け。まさかの延長戦での追いつき。固唾を呑んだPK戦。延長戦直前で止まった録画機能。ああ、朝まで起きてて本当によかった。
 七つ森書館(vol.20参照)近くの旧金花通り、今のサッカー通り商店街ではおめでとうポスターがあちこちに、それこそネパール料理店にまで貼られております。文京区の庁舎の中にまでおめでとう垂れ幕があったのですが、いくら日本サッカー協会とミュージアムが区内にあるからってあんまり関係ないんじゃないかなあ。
七つ森書館(vol.20参照)近くの旧金花通り、今のサッカー通り商店街ではおめでとうポスターがあちこちに、それこそネパール料理店にまで貼られております。文京区の庁舎の中にまでおめでとう垂れ幕があったのですが、いくら日本サッカー協会とミュージアムが区内にあるからってあんまり関係ないんじゃないかなあ。
こうなると優勝翌日の営業部T君のツイッターは試合の感想でぐんぐんタイムラインが伸びているにちがいないと期待して見てみたら、意外やたったひと言で軽ーくスルー。GK頭越しのループシュートのように冷静です。ワールドカップ観戦のために弾丸ツアーで南アフリカに渡り、テレビ出演も果たした剛の者ともなると、女子の強さは周知の事実であって優勝して当然というところなのか。わいのわいのと騒ぐのはにわかファンの証なのでしょうか。
うーむ、しかしこれではなんだか柴田書店的には不完全燃焼。熱くなりやすくて薄っぺらくて(穴が)あきやすい、安っぽいアルミ鍋みたいな私としては、この興奮をどこにぶつけたらよいものやら。そこで今回はサッカーにまつわる料理本をとりあげてみることにしました。なでしこブームに便乗する気まんまんです。

さがしてみると、いやあ、あるもんですねえ。『小学生・中学生のためのジュニアサッカー食事バイブル』はレシピ本なのですが、「アタリ負けしない強い体になりたい」「ひどい筋肉痛になってしまった」というような各種ご要望にこたえて、処方箋のようにメニューが紹介されております。「大事な時に緊張してしまい、いつもミスしてしまう」ジュニアには、気分を落ち着かせる効果のあるハーブを使った「ローズマリーとチーズのホットケーキ」を、「判断力のある頭の回転の早い選手になりたい」ジュニアには、DHAの豊富なイワシの蒲焼丼などが勧められております。至れり尽くせりですねえ。
ユース世代に向けては『強くなりたい中学・高校生選手のためのサッカー食』。サッカー食なんて単語もあるんですねえ。もっとも「野球食」の本もあるみたいで、今やスポーツの世界は根性よりも科学の時代のようです。練習中は疲れていてもすぐに食事をしなければならないので、まんべんなく食べることが大事、量を食べて体を作ること、というのは浦和レッズ永井雄一郎選手のアドバイス。なるほどあれだけハードに体を動かしていると内臓だって参ってしまって、つい好きなものに偏食してしまいがちなんですね。
これらはサッカー好きの息子、娘をもったお母さん向きの本ですが、一流の選手たるものは食生活を自分で管理できるようにならねばなりません。『サッカー ― 自分でできる!勝つための栄養トレーニングアスリートの勝負レシピ』は栄養に関する概説書で、試合2週間前、3日前、前日、当日、試合後の食事で気をつけるべきところを解説。なんだかちょっと双六みたいですが、基本は高糖質食をとって燃料のグリコーゲンを貯め込むことに尽きるようです。ダイエットとは対極にある考え方がちょっと愉快です。
それでは現役選手はどのような食事をしているのかと、『Jリーグの技あり寮ごはん』を開いてみました。神戸ヴィッセルの寮母さんの書いた料理本ときいたので「さあさあ食べた食べた!お代わりはいくらでもあるからねー」みたいなどーんという豪快な料理が並んでいるのかと思いきや、ワンプレートランチでファンシーです。「牛肉のがっつりサラダ」「疲れ知らずのカレーライス」なんていうそれっぽいのもありますが、「ハートの甘辛煮」って……。もはやステーキとトンカツなんて食べてる時代ではないんですねえ。
さて今回紹介するメインディッシュは『サムライブルーの料理人』。アジアカップやワールドカップといった海外遠征に同行し、選手の食事を担当した料理長さんのルポルタージュです。「料理人は見た!あの選手たちの食卓での裏の顔!ニンジンをこっそり皿からよけた○○選手にイエローカード!!」てな感じの暴露本のようなものを期待されるとがっかりしますよ。著者の西芳照さんはこの仕事についてもしばらくは選手の名前と顔が一致しなかったくらい。逆に選手たちをやたらにスター視しないフランクな視線が、試合前後の普段の姿を浮き彫りにしてくれています。
むかーし月刊誌に載せた長野五輪選手村の青木章総料理長のインタビューによると、大勢のスタッフが関わるオリンピックでは、いまでも基本的に食事は主催国が用意するもので、各国の食文化を考慮して工夫を凝らすとか。てっきりワールドカップもそうなのかと思っておりましたが、あちこちに試合会場が分散して転戦に転戦が次ぐワールドカップの場合は、まったく事情が違うんですね。選手団に帯同するシェフがメニューを管理し、宿泊先のホテルの協力を得て作ってもらいます。海外で苦労して食材を調達するのは、ちょっと大使館付きの公邸料理人さんにも似た立場にありますが、外国の他人の厨房に単身乗り込み、そこのスタッフたちの協力を得ながら大人数の料理を作るのですからずっと神経を遣う仕事のようです。
選手たちの食事に求められるのは、第一に安全であること。食事のせいで体調を崩して実力を発揮できなかった、なんてことになったら大変ですから、衛生管理を徹底させます。ですから料理の内容も、うどんだったりお好み焼だったり鶏の照り焼きだったりと、食べなれた普通のものばかりです。第二に選手たちの栄養管理。会場が高地だった南アフリカ大会では、鉄分が不足しないようにアサリやヒジキをメニューに加えるといった具合です。
そして第三が選手たちが元気になる、食卓につくのが楽しみになるような食事を提供すること。西さんはひたすらそこに腐心します。できたての温かい料理を目の前で提供できるように、ホテルのブッフェさながらに調理器具を食堂に据えて「ライブクッキング」を始めたり、好きなものを選べるようにパスタのソースを複数用意したり、高地でもおいしいご飯が炊けるように圧力釜を独断で導入したり……。西さんは「京懐石よこい」の横井清さんの下で5年間修業した経験があり、日本料理の基礎をしっかりと身につけた料理人ですから、冷凍の魚の照り焼なぞよりももっと洒落た本格日本料理を作りたくなってもおかしくない。しかし、あくまでも選手第一に献立を考えています。安全で栄養に優れ、喜ばれる食事。これってどれも外食産業の基本ですよね。
食事を勝つための肉体と精神改造の手段として捉えているだけなら、いきつく果てはドーピングでしょう。それは極論だとしても、栄養学の観点から徹底管理して、カロリー計算ばっちり、必須アミノ酸とビタミンの摂取はぬかりない食事を設計するというのが世の流れかもしれません。となると選手が自分で好きな料理が選べる、おかわりできるなんてのは余計なサービスなのでしょうが、どっこい相手はサッカーマシーンではなく、生きた人間です。食べてうまい食事こそが、次の試合の活力となるのです。
もちろん各国のクラブチームはすでにこの事実に気づいており、試合後すぐに炭水化物を補給できるように帰りのバスの中で温かいパスタが提供されたり、試合前夜にみなで本格的なディナーを囲んだりするそうです。しかし贅沢な食事イコール楽しい食事とは限りません。大事なのはハート(ハツではありませんよ)です。ここぞという重要な試合のときに西さんは、日本を遠く離れた地で食べるとほっとして、やけにおいしく感じられるようなラーメンや親子とじといった「なごみのメニュー」を投入します。
予選で敗退すれば調達した食材は無駄になりますが、もちろん負けることなど想定外。巻末に収録された南アフリカ大会の日記のあちこちから、西さんの苦労とみんなを喜ばせたいという人柄が伝わり、ああ、次の大会こそはこの人たちが決勝戦に導かれますようにという気持ちにさせられます。


ところで肝心のなでしこジャパンの選手団は、会期中にどんな食事をしていたのかも知りたかったのですが、これがよくわからない。優勝トロフィー公開中のサッカーミュージアムも覗いてみたのですが、展示されておりませんでした。ネットで帯同スタッフのリストを見ると料理人は含まれていなかった模様です。とあるテレビの生放送では食事の話題が振られたところ、選手たちはドイツでは醤油かけご飯がブームだった、と口を揃えておりました。ええっと、卵すら入ってませんが……ダイエット中? それとも美食を極めた結果として、あっさりしていてシンプルなものがお好みなのでしょうか。
「勇気を与えてくれた」(by管総理)、「日本人が勇気もらった」(by石原都知事)。ありきたりでちょっと上から目線な(ここは謙虚に「勇気づけられた」でしょう)、つまんないコメントですねえ。もらってばかりいないで、誰か彼女たちに炊きたてのご飯を食べさせてあげてください。
投稿者 webmaster : 17:27
2011年07月19日
料理本のソムリエ [ vol.25 ]
【 vol.25】
島崎藤村が魯山人をモデルに
小説を書いたわけ
(前回の続き) おや、魯山人のことはご存じなのかい? 「美食倶楽部」や「星岡茶寮」も? 意外だねえ。
美食倶楽部は魯山人と中村竹四郎が共同経営していた会員制の店。予約客に骨董店の2階で販売用の器を使って料理を提供した、いわば賞味会だね。「星岡茶寮」は赤坂の日枝神社の隣にあった東京一高価なので評判の料亭。この2つの店を手掛ける間の時期、震災直後の大正12年11月から翌年10月に区画整理で日比谷に移転するまでの1年間弱、魯山人らが井上太四郎と共同で開いていた料理店が芝公園の「花の茶屋」っていうわけです。
そもそもね、せいぜい1、2卓の賞味会の次に手掛けたのが東京一の料亭では、店格が違いすぎやしないかい? 素人がいきなり料亭を切り盛りできるもんかねえ? 器目当ての骨董好きなら、想像以上においしい料理の登場に意表をつかれたり喜んだりしたろうさ。でも料亭では料理がよくて当たり前だし、サービスの質だって求められる。什器が無名時代の魯山人の作品では商品力不足のようにも思える。世の魯山人本はそうした疑問を「魯山人が天才だったから」の一言で片付けているけど、料理店の経営ってぇもんを甘くみちゃいませんかね?
 実際にはホップの美食倶楽部とジャンプの星岡茶寮の間に、ちゃあんとステップ時代の花の茶屋があったというのが真相なんですなあ。骨董を使わず、会員制でもなく、一品料理も出す料理店を立派に切り盛りできたことで、自分の料理やオペレーションに自信を得たんだろうねえ。ちなみに花の茶屋では星岡茶寮に先駆けて、魯山人が手掛けた器を使っていたんですよ。といっても魯山人が自前の窯を持つ前の話で、京都や山代の窯に委託して焼いてもらったものだから、本人としてはまだ満足できなかったかもしれないけれど。
実際にはホップの美食倶楽部とジャンプの星岡茶寮の間に、ちゃあんとステップ時代の花の茶屋があったというのが真相なんですなあ。骨董を使わず、会員制でもなく、一品料理も出す料理店を立派に切り盛りできたことで、自分の料理やオペレーションに自信を得たんだろうねえ。ちなみに花の茶屋では星岡茶寮に先駆けて、魯山人が手掛けた器を使っていたんですよ。といっても魯山人が自前の窯を持つ前の話で、京都や山代の窯に委託して焼いてもらったものだから、本人としてはまだ満足できなかったかもしれないけれど。
「なにしろ、この震災の後ですから、食器もまだ思うようなのが手に入りません。これで器が好いと、同じものでもお客さんがうまく味って下さる。今はそれが利きません。そこへ出すものは、何でも正味の料理だけなんですからね。料理人は骨が折れますよ」。これは『食堂』の中の広瀬さんのセリフだけど、いかにも魯山人が言いそうだよね。
さらに詳しく言うと星岡茶寮の開業当初は5部屋きりで花の茶屋の倍くらいの規模しかなくってね。昭和6年に新館を増築してさらに倍の収容が可能になった。さらに旧館の改築を経て、昭和10年にパンフレットが作られたんだけど、その情報をもとに店規模やスタッフ数が紹介されるもんだから、いきなり大料亭を始めたような印象を受けちゃう。いくら魯山人でも物事には順序ってもんがあるんですよ。
 なぜ、この店が「池の茶屋」のモデルって断言できるのかって? だって場所がおんなじなんだもの。花の茶屋があったのは芝公園18号地―1で、芝公園弁天池の道を挟んだ向かい側。今でこそ、プリンスホテルの下の小さなスペースだけど、当時の弁天池あたりは今よりもずっと広くて桜や紅葉や蓮で知られた行楽地。赤羽橋の市電の停車場に近くて、目と鼻の先は「紅葉館」や「三縁亭」といった有名店。今の人には東京タワーやとうふ屋うかいの近くっていったほうがわかるかな? なかなかの好立地だったようですよ。
なぜ、この店が「池の茶屋」のモデルって断言できるのかって? だって場所がおんなじなんだもの。花の茶屋があったのは芝公園18号地―1で、芝公園弁天池の道を挟んだ向かい側。今でこそ、プリンスホテルの下の小さなスペースだけど、当時の弁天池あたりは今よりもずっと広くて桜や紅葉や蓮で知られた行楽地。赤羽橋の市電の停車場に近くて、目と鼻の先は「紅葉館」や「三縁亭」といった有名店。今の人には東京タワーやとうふ屋うかいの近くっていったほうがわかるかな? なかなかの好立地だったようですよ。
「震災の名残はまだ芝の公園あたりにも深かった。そこここの樹蔭には、不幸な避難者の仮小屋も取払われずにある。公園の蓮池を前に、桜やアカシヤが影を落している静かな一隅が、お三輪の目ざして行ったところだ。葦簾(よしず)で囲った休茶屋の横手には、人目をひくような新しい食堂らしい旗も出ている。それには、池に近い位置に因んで「池の茶屋」とした文字もあらわしてある」
この小説の連載打ち合わせ時の仮タイトルは「池の食堂」だったことからわかるように、弁天池近くの料理店という設定は初めから藤村の頭にあったんでしょうなあ。もちろん広瀬先生こと魯山人が登場するのもね。
「庖丁をとぐ音、煮物揚物の用意をする音はお三輪の周囲に起って、震災後らしい復興の気分がその料理場に漲り溢れた。こうなると、何と言っても広瀬さんの天下だ。そこは新七と、広瀬さんと、お力夫婦の寄合世帯で、互いに力を持寄っての食堂で、誰が主人でもなければ、誰が使われるものでもなかった。唯、実力あるものが支配した。そういう広瀬さんも、以前小竹の家に身を寄せていた時分とは違い、今は友達同志として経営するこの食堂に遠慮は反って無用とあって、つい忙しい時になると、《オイ、君》と新七を呼び捨てだ。新七はそれを聞いても、すこしも嫌な顔をしなかった。どこまでもこの友達の女房役として、共に事に当ろうとしていた」
どうだい、広瀬さんたらいかにも魯山人を髣髴とさせる性格だし、新七は中村竹四郎ばりにサポートに徹してる。「あの先生には泥だらけな護謨(ゴム)靴でも何でもはいて、魚河岸を馳け廻って来るような野蛮なところがあります」と新七が語っているのも、これから世に打って出ようとしていた時期の魯山人らしい。星岡茶寮を開く前は魯山人もちゃんと魚河岸に通っていたんだねえ。もっとも京橋育ちという設定のお三輪さんにとっては魚河岸ってえのは日本橋にあるのが当たり前で、「あの魚河岸ですら最早東京の真中にはなくて、広瀬さんはじめ池の茶屋の人達が月島の方へ毎朝の魚の買出しに出掛けるとは、お三輪には信じられもしなかった」なんてショックを受けているけれど。
ほかにも池の茶屋には支那風の赤い毛氈が敷かれていると描かれているけど、これは白崎秀雄の伝記『北大路魯山人』でも紹介されているし、料理の献立が支那風の桃色の用箋に書かれてたっていうのは、初期の星岡茶寮と同じ手法。どこをどう見ても花の茶屋と魯山人をモデルにしたとしか思えませんよ。
 小説だから、どこまで事実通りかわかるもんかい、だって? そりゃそうだ。現実の花の茶屋は池の茶屋と違って震災前から開いていたし、魯山人が協力する計画も夏には始まっていたからねえ。美食倶楽部で女中として働いていた井上イチと、夫の太四郎が花の茶屋を開いたのは大正11年10月のことで、店は借りていたらしい。芝公園の敷地は東京市の所有だけれど、公園の管理費を稼ぎ出すために一部の区画は民間に貸し出されていて、芝公園18号地―1の使用権は植松太吉って人が持っていた。ところが大正12年7月に中村竹四郎が使用権の譲渡を、8月には水道管の引き込みを申請している。市の土地では何をするにも許可がいるので、借家時代の花の茶屋は満足いく店作りはできなかったんだろうね。そこで井上夫婦は、中村・魯山人コンビの財力とセンスを借りてリニューアルしようと考えたっていうのがあたしの推理。のちに星岡料理の料理主任となる中島貞治郎、「新宿中嶋」の中島貞治さんのお祖父さんは、この頃に魯山人の下に加わっていて、7月22日に鎌倉で開かれた朝飯会を手伝っている。露天に白いクロスをかけたテーブルを並べて開いたこの破天荒な催しは、たぶん花の茶屋リニューアルオープンの宣伝も兼ねていたんでしょうね。
小説だから、どこまで事実通りかわかるもんかい、だって? そりゃそうだ。現実の花の茶屋は池の茶屋と違って震災前から開いていたし、魯山人が協力する計画も夏には始まっていたからねえ。美食倶楽部で女中として働いていた井上イチと、夫の太四郎が花の茶屋を開いたのは大正11年10月のことで、店は借りていたらしい。芝公園の敷地は東京市の所有だけれど、公園の管理費を稼ぎ出すために一部の区画は民間に貸し出されていて、芝公園18号地―1の使用権は植松太吉って人が持っていた。ところが大正12年7月に中村竹四郎が使用権の譲渡を、8月には水道管の引き込みを申請している。市の土地では何をするにも許可がいるので、借家時代の花の茶屋は満足いく店作りはできなかったんだろうね。そこで井上夫婦は、中村・魯山人コンビの財力とセンスを借りてリニューアルしようと考えたっていうのがあたしの推理。のちに星岡料理の料理主任となる中島貞治郎、「新宿中嶋」の中島貞治さんのお祖父さんは、この頃に魯山人の下に加わっていて、7月22日に鎌倉で開かれた朝飯会を手伝っている。露天に白いクロスをかけたテーブルを並べて開いたこの破天荒な催しは、たぶん花の茶屋リニューアルオープンの宣伝も兼ねていたんでしょうね。
芝公園の花の茶屋が井上太四郎、魯山人、中村竹四郎のトロイカ体制の店だったことは、滝波善雅からの伝聞として歴史学者の服部之総も書き留めているのに(『服部之総全集24巻』)、魯山人の経歴では井上どころか花の茶屋自体も無視、省略されることのほうが多いんだよねえ。美食倶楽部の営業期間はたった2年だったことを考えると、こちらも負けないくらい重要な店だと思うんですけどねえ。
白崎秀雄にしてもね、花の茶屋の内装は支那風の趣向が凝らされていたことに気づいていない。そもそも彼の著作の『北大路魯山人』でも、井上太四郎や花の茶屋について詳しく書いてあるのは昭和60年に出した改訂新版のほう。昭和46年の旧版では、ちょっとしか触れられていないうえに井上太四郎の経歴がまちがってる。これは旧版執筆時には、少年時代から魯山人の料理を手伝っていた武山一太を取材していなかったから。だから旧版しか知らない読者は花の茶屋って聞いてもぴんとこないかもね。
藤村が『食堂』を連載したのは大正から昭和に替わる年の暮れ。星岡茶寮の開店後だから、こちらをモデルにしてもよかった。でもあえて花の茶屋のほうを取り上げたのは、それが震災直後の急造りの小さな店だったにも関わらず工夫にあふれていて、新しい時代の足音を予感させていたからじゃないかなあ。武山一太の証言によると、土間には京瓦が敷かれていて、緋毛氈を敷いた床に漆塗りのテーブル、夜は百匁ロウソクをともした手燭を点々と置いたそうですよ。ちょっとダイニング系の店の演出みたい。ちなみに、勘違いしている人がよくいるけど、星岡茶寮は魯山人が始めたんじゃなくて、明治時代に鹿鳴館の向こうを張って建てられた高級料亭。漱石も鴎外も利用していたんですからね。芝公園の花の茶屋の閉店後、魯山人らは東京っ子なら誰でも知っている施設とブランドをそのまま借りて、次の事業を始めたってわけ。これじゃあ明治時代への回帰であって、復興と新時代の象徴として取り上げるのにはちょっとふさわしくないよね。
ただ藤村は魯山人という人物そのものにも興味があったのは間違いない。魯山人の書の腕も高く評価していたみたい。加藤静子に魯山人の作品を送ったはいいが、可哀想に「折角でございましたが、北大路氏の書は、自分としては好きな書ではありませんでした」なんてぴしゃりと言われてる。それにもめげずに昭和3年に彼女と星岡茶寮で結婚式を挙げるんだから、藤村の魯山人びいきはかなりのもんだったんでしょうなあ。志賀直哉が星岡茶寮で食事をして、日記に一言「不味」って書いているのとはえらい違いだね。
いっぽう永井荷風も星岡茶寮で結婚式を挙げているんだけどね、これは魯山人が借りる前の話だから関係ない。さっき初期の星岡茶寮では支那風の紙に献立を書いてよこしたって言ったけど、これは荷風が『断腸亭日乗』に記録していることで、彼が魯山人の料理を食べたのはまちがいない。でもね、たぶん気に入らなかったんだと思いますよ。お三輪さん同様、江戸の空気を愛した荷風には魯山人流は受け入れられなかったんじゃないかなあ。慎重な荷風は志賀直哉と違って日記にそれとは記していないけど、魯山人嫌いの状況証拠が山とあるんだよねえ…って、おい、どうもさっきから静かだと思ったら、聞いてるの?
 長くって退屈だし、検索してもそんな話は出てこないから信じられないって? そりゃそうですよ。ネットやブログに真実があふれていると思ったら大間違い。世間の人はね、漫画やテレビで描かれている魯山人像で充分満足しているし、魯山人研究家なんて顔をしている人たちもね、実際の料理や料理店の歴史なんて、てんで無関心なんだから。ほんとのことを知りたけりゃ、ちゃんと当時の資料を読まなくちゃだめですよ。ほら、『味冴』には「今から五年以前の十月、…(略)…弁天池畔に北大路魯卿先生を名付親として小(ささ)やかな茶店を開きました」って書いてあるし、口絵には魯山人の書も収録されている。白崎秀雄によると、井上夫婦は魯山人に庇を貸して母屋を取られた形になったために怒り出して紛糾したと書いているけど、こうしてみると喧嘩別れで絶交っていうわけでもなさそうだね。当時の人は日比谷に移った花の茶屋は星岡茶寮の系列店か何かと思っていたふしがあるし、花の茶屋は魯山人流の前菜(vol.5参照)を出していたからねえ。
長くって退屈だし、検索してもそんな話は出てこないから信じられないって? そりゃそうですよ。ネットやブログに真実があふれていると思ったら大間違い。世間の人はね、漫画やテレビで描かれている魯山人像で充分満足しているし、魯山人研究家なんて顔をしている人たちもね、実際の料理や料理店の歴史なんて、てんで無関心なんだから。ほんとのことを知りたけりゃ、ちゃんと当時の資料を読まなくちゃだめですよ。ほら、『味冴』には「今から五年以前の十月、…(略)…弁天池畔に北大路魯卿先生を名付親として小(ささ)やかな茶店を開きました」って書いてあるし、口絵には魯山人の書も収録されている。白崎秀雄によると、井上夫婦は魯山人に庇を貸して母屋を取られた形になったために怒り出して紛糾したと書いているけど、こうしてみると喧嘩別れで絶交っていうわけでもなさそうだね。当時の人は日比谷に移った花の茶屋は星岡茶寮の系列店か何かと思っていたふしがあるし、花の茶屋は魯山人流の前菜(vol.5参照)を出していたからねえ。
え、当時の資料を読みたいから、2冊あるなら1冊譲ってくれって? なんだい魯山人の書と聞いたら急に目の色を変えて。嫌ですよだ。ええ、ええ、ケチですとも。
投稿者 webmaster : 14:57
2011年06月28日
料理本のソムリエ [ vol.24 ]
【 vol.24】
忘れられた「花の茶屋」
へっへっへっへっへえ、手に入れちゃいましたよ! 昭和2年10月刊行の「花の茶屋」の機関誌『味冴』5周年記念号! 古書即売会の出品目録をめくっていてこの二文字にぶつかったときは、思わず二度見しちゃいましたよ。会場に並ぶ商品と違って目録掲載品は抽選なものだから、申し込んでから2週間、当りますように当たりますようにと、ずうっと落ち着かなかった。やれやれ、これでひと安心ってなもんだ。
にたにた気持ち悪いですって? だってこの雑誌、あたしの知る限りでは国会図書館にしか所蔵されていないんですよ。おまけについこの間までは小さなマイクロフィルムに、今はデジタルデータにされちゃって、どちらにしてもモノクロの粗い映像でしか見られない。ほおらこの通り、本物の表紙はカラーですよ。銀で刷った秋草風の模様の上に、わざわざ厚めの紙に別刷りにした小室翠雲の南画を貼り付けてある。さずが五周年誌、贅沢な造りだねえ。これは中国の高級食材のケツギョかしら。口絵は日本画の竹内栖鳳と洋画の林重義だね。栖鳳の画題はお得意のカツオだ。活きがよさそうじゃないですか。


何をそんなに興奮しているのかって? ですから、あの戦前の名店「花の茶屋」の機関誌なんですってば。なにせ花の茶屋は文学史の大事な舞台なんですよ。本山荻舟や長谷川伸、直木三十五、江戸川乱歩らが大衆文学を世に認めさせようと立ち上げた「二十一日会」の会場でしたし、芥川賞と直木賞は花の茶屋での会議で生まれたんだから。今でこそ選考会会場は「新喜楽」だけど、時が時ならこの店で開かれたっておかしくないくらい。それが証拠にここにほら、文芸春秋社主の菊池寛も直木三十五も文章を寄せているでしょう。文芸春秋社は昭和2年に麹町から内幸町のダイビルのところに引っ越してきたんで、社員がよく使うようになったのかも。ちなみに花の茶屋があったのはね、今の日比谷シャンテ前の広場あたり。このほかに内幸町の日比谷セントラルビルの裏あたりに支店も開いているしね。
そもそも花の茶屋主人の井上太四郎といえば、丸の内あたりじゃあちょっとした顔だったんですよ。ここに井上がモデルになった割烹着姿の彫像の写真があるでしょう。作者は日名子実三。柴田書店から歩いていけるところにある、日本サッカー協会のシンボルマークの八咫烏をデザインしたのはこの彫刻家なんだから。


それがどうしたですって? じゃあ、東京音頭ならご存じでしょう? あの夏の定番曲はもとはといえば井上太四郎たちが考えついたんですよ。夏といえば田舎に行けば盆踊りがあるが東京にはない、ここは一つ丸の内の繁栄のために街の音頭を作ろうってね。心意気が嬉しいじゃありませんか。このアイデアは芥川賞と違って風呂屋の朝風呂で生まれたそうで、席上(湯船中?)にいたのは井上のほか、西洋料理の「松本楼」の主人だったと作詞担当の西條八十が戦後『唄の自叙伝』で回想してます(『西條八十全集17巻所収』)。もっとも作曲担当の中山晋平は昭和10年の東京日日新聞で、一緒にいたのはおでんで有名な「富可川」主人だったと答えてる。まあどちらにしても井上が関わっていたのはまちがいないでしょう。昭和7年夏に日比谷公園で踊られたこの丸の内音頭を、10月に東京市が大拡張されたのに合わせて翌年替え歌にした。それが今の東京音頭ってわけ。この拡張以前は東京は15区で、品川も目黒も世田谷も大森蒲田も渋谷も中野も豊島も荒川も板橋も足立も葛飾も江戸川もみーんな郡の一部だったんだからね。
おいおい、東京音頭も知らないの? 弱っちまったなあ、現代っ子てのは…。あのね、今もコンビニで売っている「週刊朝日」って雑誌があるでしょう。あれは大正の創刊当時はふた周りくらい大きなサイズのグラフ誌っぽい造りで、アメリカで活躍していたジャーナリストの翁久允を編集長に迎えたハイカラな雑誌だった。井上太四郎は翁と知り合いでね、当時の週刊朝日にしちゃ珍しい料理記事を寄稿してるし、彼にいろんな文化人を紹介してもらったんですよ。もともと彼は顔が広くてね、この雑誌の表紙を描いた小室翠雲に同行して北陸旅行をしたり、富可川主人が発行した小冊子「おでんの話」に松崎天民らと共に寄稿したり。芸術家の岡本太郎がご両親の岡本一平とかの子と一緒にヨーロッパに渡ったとき、送迎会は花の茶屋の箱根支店で開いたんだから。あの柳田國男だって『味冴』の別の号に、「花の茶屋 楽書」って文を寄稿しているし。私にとっちゃ雲の上みたいな古本蒐集の大家、斎藤昌三が報告しているんで『定本柳田國男集別巻5』にはこのタイトルのみ収録されてますけどね、文章そのものは行方知れずなんですよ。だから昭和3年の「味冴」だったら、いったいどれくらいの価値があるか…。あ、この号はいくらしたかっていうと4200円。まあ1万円出したって惜しくはありませんけどね。
え、ここに1000円って書いてあるって? やだね、めざとくて。実はねえ、抽選に当たった雑誌を入り口で受け取って、ほくほくもので即売会の会場に入ったら、いま見たばかりの表紙がこっちを向いて棚にちょこんと置かれてたんですよ。そりゃあ、たまげたねえ。帳場の人に変な顔をされたけど、無視して両方とも買いました。そっちは1000円だったんだけど、ひとケタまちがっていたのかねえ。
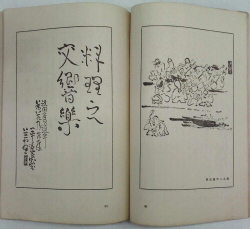

なあんだ、ほんとはそんなに珍しい雑誌じゃないんだろうって? うーん、もしかしたらそうなのかなあ…。大学や公立図書館の蔵書目録に載ってないだけで、学者先生の研究室や書斎には結構転がっているのかなあ。なにせ花の茶屋には、島崎藤村が田山花袋を誘って食事に行っているんだよねえ。そのときのお誘いの手紙は『藤村全集17巻』に載っているし、藤村は花の茶屋をモデルに『食堂』って小説も書いているしねえ。
食堂なら青空文庫に入っているからパソコンで読めるって? まったく、変なことには詳しいんだから。デジタル世代ってぇ奴かい? 本もろくろく買わないで画面でばっかり文字を追ってちゃいけませんよ。「器は料理の着物」って、どっかの人が言ってたろう? 本もおんなじですよ。ただ食べるだけなら使い捨て容器、ただ文字を追うだけならデータのほうが楽で便利だけど、こうして現物の風合いに触れたり、今日はどれくらい読んだかなぁってページの厚さで進み具合を確かめたり、顔の上にのっけて居眠りしたりするのもまた読書の楽しみなんだから。ブログなんてぇ代物を読むのもね、たいがいにしたほうがいいですよ。
だいたい食堂はちょっと可哀想な作品でね。同時期に書かれて同じ単行本に収録された「嵐」がうんと注目されたもんだから、島崎藤村の作品の中じゃあ脇に追いやられちゃった。食堂は新潮文庫の『嵐・ある女の生涯』には入っているものの、巻末の解説はやっぱり嵐中心で、一言も触れてもらえてない。嵐は岩波文庫にもなっているけど、これにいたっては食堂をはずしているからね。そういう事情は本の形で現物を見ないとぴんとこないかもね。
デジタルの食堂は全部読んだかい? ほおらみなさい、いつでも簡単に読めると思うと逆になかなか読まないもんだろう。いいかい、主人公のお三輪さんは京橋の料亭「小竹」の女将でね。関東大震災ですべてを失って浦和に避難してたんだけど、復興途上の東京で息子の新七が独立したもんだから、震災から1年経ったのを機に彼の新店を見にいくっていう話さ。福岡の新聞に連載されたのは震災から4年ちょっと後だから、当時の読者にとってはついこの間の話という設定だね。お三輪さんが震災の際に逃げのびた先が、たまたま店で7年間奉公していたお力と金太郎夫婦のもと。それがきっかけで新七は彼らとともに、従来の割烹店とも違った新しい形の“食堂”を始めたっていう筋書きだ。
「お三輪は震災後の東京を全く知らないでもない。一度、新七に連れられて焼跡を見に上京したこともある。小竹とした暖簾の掛っていたところは仮の板囲いに変って、ただ礎(いしずえ)ばかりがそこに残っていた。香、扇子、筆墨、陶器、いろいろな種類の紙、画帖、書籍などから、加工した宝石のようなものまで、すべて支那産の品物が取りそろえてあったあの店はもう無い。三代もかかって築きあげた一家の繁昌もまことに夢の跡のようであった。その時はお三輪も胸が迫って来て、二度とこんな焼跡なぞを訪ねまいと思った」
「《あれから、お前さん、浦和へ着くまでがなかなか大変でしたよ》とお三輪も思わず焼出された当時の心持を引出された。《平常(ふだん)なら一時間足らずで行かれるところなんでしょう、それを六時間も七時間もかかって……途中で渡れるか渡れないか知れないような橋を渡って……浦和へ着いた頃は、もう真暗サ。あの時は新七が宿屋を探してくれてね。その宿屋でお結飯(むすび)を造ってくれたとお思い……子供がそのお結飯を見たら、手につかんで離さないじゃないか。みんな泣いちまいましたよ……》」
今こうして読むと、ちょっと身につまされるところ、感じ入るところがあるね。震災で奪われた店と江戸の香りの残る街の思い出。そうしたものを踏み越えて新しい道に進もうとする店。料理業界の人にはぜひ読んでほしいねえ。ここに出てくる新七が開いた芝公園の「池の茶屋」のモデルが、「花の茶屋」ってわけ。
そうそう、話が後先になるけど「花の茶屋」は開業当時は芝公園の弁天池の向かいにあったんだよね。“芝公園の花の茶屋”ってきいて、公園の中で団子や飲み物を売ってる売店を想像する人がいるかもしれないけど、そりゃ“飯店”を一膳めし屋と思うのと同じくらいにそそっかしいからね。芝公園てのは住所のことだし、ささやかだけど、京都の丸山公園の茶店風に茶道具などを並べて、素人料理ながらもおでんに鍋、鯛ちりだって出していたんだから。それが震災後に、中国風の調度に変えて一品料理の店として営業し始めた。ほら小説にも、こう書かれているでしょう。
「お三輪は椅子を離れて、木彫の扁額(がく)の掛けてある下へも行って見た。新七に言わせると、その額も広瀬さんがこの池の茶屋のために自分で書き自分で彫ったものであった。お三輪はまた、めずらしい酒の瓶が色彩として置いてあるような飾棚の前へも行って見た。そこにも広瀬さんの心はよく働いていた。食堂の片隅には植木鉢も置いてあって、青々とした蘭の葉が室内の空気に息づいているように見える。どことなく支那趣味の取り入れてあるところは、お三輪に取って、焼けない前の小竹の店を想い起させるようなものばかりであった」
これだけ細かくディテールが描かれているのは、実際の花の茶屋が参考になっているからでしょうね。ちなみにお力夫婦は井上イチと太四郎のことだけど、新七はたぶん中村竹四郎がモデルじゃないかなあ。
それじゃあ広瀬先生のモデルは誰かって? そりゃほれ、星岡茶寮を開く前の北大路魯山人にきまっているじゃあないですか。(この項続く)
投稿者 webmaster : 12:08
2011年06月15日
料理本のソムリエ [ vol.23 ]
【 vol.23】
ガッテンいかない“魚のさばき方”
「料理本の…」というタイトルなのにいきなりテレビの話で申し訳ありません。今回取り上げるのは3月2日NHKが放送しました「ためしてガッテン」の「出た!魚さばき必勝法」です。こりゃまた古い話をいまさら蒸し返して…、と思われるかもしれませんが、震災の前日に書いたため、ずっとお蔵入りしていました(まちがっていつもと違うフォルダに保存したうえ、つい「NHK」なんてわかりづらいファイル名をつけたため、PC内で行方不明になってたせいでもありますが)。いつにも増して長いのですが、我慢してお付き合いください。NHKなので今回は休憩のCMも入りません。「おひけぇなスッテゴサウルス」とか「儲かりマッカートニー」とか「ぼちぼちでスワン」とか「ようこそお越しヤスシキヨシ」とか「ぶぶ漬けでも一杯どうドストエフスキー」とか、楽しい仲間をぽぽぽぽーんと考えたのですが、こちらは全部お蔵入りです。
魚をおろせる人とおろせない人との差は、「ある骨」の存在を認識しているかどうかによる、というのがこの回の放送のキモでして、包丁ではなく刃のついていないステーキナイフでおろすとうまくいくというのが新提案でした。この番組、料理に科学のメスを入れるという視点(それが可能な潤沢な予算はみなさんの受信料のおかげです)がなかなか面白く、「クーブイリチーはだしをとったあとの昆布で作ったほうがうまい」なんて話は、実際に失敗した経験があった当方としてはガッテンすることしきりで勉強になります。ただ、ときどきとんでもないこともやらかします。前にも放送内で、四川料理の基本食材である「酒醸(チュウニャン)」が日本では手に入らないと言いきってました。確かに現地のものは日本の麹とは菌が違うそうですが、業務用製品もありまして、ネット販売でも手に入るんですよねえ。業務妨害とか言われかねませんよ。
結論からいうとこの放送を見ただけでは、アジやサバといった一部の魚しかおろせません。以前カマスをおろそうとして苦労した私の弟がこの放送を見たというので、「こりゃ面白い、素人がテレビの知識を武器におろせるようになるかどうか実験してもらおう」と思ったのですが、彼は彼で大事なポイントの説明が欠けているのにちゃんと気づいておりました。ちえっ。一度でも魚をおろしたことのある人は別のところで頭を悩ませており、それが番組中に描かれていないのが一発で見破られております。
「それじゃあ、魚をおろす際の大事なポイントってなあに?」
「それは魚の骨の構造です」
「ええー、それって放送でも言ってたじゃん、どういうことー??」(立川志○輔風)
はい、ここで今回のテーマです。「コツはコツでも骨違い。憎々しいのは肉間骨(にくかんこつ)」。
まずは図をご覧ください。魚の断面図です。
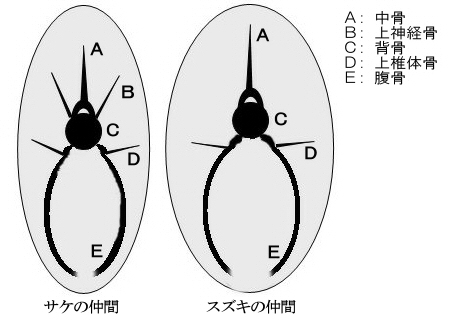
テレビでは骨に着目したのはよいのですが、説明の仕方がいけません。魚の中央に走っている骨をただ「背骨」と一言で片付けているようでは、重要さがまるきりわかっていない証拠です。魚の背骨は人間の背骨と違って突起のように細い骨が突き出しています。そこでここでは脊髄の入った太い部分のみは「背骨」、細く長くのびている骨(神経棘)を含めた場合を「中骨」と呼びわけることにいたします。中骨とは90度の向きに背骨から突き出ている短いほうの骨は「小骨」とします。肋骨は「腹骨」ですね。
テレビで注目していた「ある骨」とはヒレを支える担鰭骨(たんきこつ)なんですが、これはそんなに重要ではありません。なぜなら背ビレや腹ビレ沿いに中骨へと向かって並んでいるため位置がはっきりしていまして、素人でも扱いやすい骨だからです。だいたいは中骨をはずすときにヒレと一緒に取れてしまいますし、身に残ったら残ったで、端なので切り落とせばよいのです。
 魚をきれいにおろせない人は包丁の先端がこの担鰭骨にひっかかるから、と説明していましたが、はたしてそうかなあ。実際に初挑戦の人たちが苦心惨憺おろしている映像を見ていると、みな一気に魚をおろす「大名おろし」と呼ばれる方法でやっておりました。どちらかというとこの方法に問題があるのです。なにしろただでさえ骨に身が残りやすく、「大名のように贅沢なおろし方」という意味のおろし方なんですから。ただし包丁を入れる回数が少なく済みますので、慣れたプロはこの方法も使います(細長い魚に向いています)。
魚をきれいにおろせない人は包丁の先端がこの担鰭骨にひっかかるから、と説明していましたが、はたしてそうかなあ。実際に初挑戦の人たちが苦心惨憺おろしている映像を見ていると、みな一気に魚をおろす「大名おろし」と呼ばれる方法でやっておりました。どちらかというとこの方法に問題があるのです。なにしろただでさえ骨に身が残りやすく、「大名のように贅沢なおろし方」という意味のおろし方なんですから。ただし包丁を入れる回数が少なく済みますので、慣れたプロはこの方法も使います(細長い魚に向いています)。
中骨から身をはずす作業ではテレビの言うとおり、無理に切ろうとせずに、包丁の刃は当てるだけで自然にはがすように切り開いていきます。慣れない素人の場合、身に切り込んでしまって中骨に肉を残しやすい。中骨の柔らかい魚の場合(平たいマナガツオとか)は、逆に骨へ切り込んでしまいそうになることもあります。その点で、刃のないステーキナイフで、身を骨からはがすようにおろしていくのも一つのアイディアでしょう。
問題は小骨です。身に食い込んでいるので切りはずさなければなりません。ステーキナイフではちょっと無理。ところがテレビではそこをさらっと流しています。じゃあ、小骨を切断せずにひっぺがすようにして引っこ抜けというのかしら(小骨が身に深く食い込んでおらず、身質が固い魚であれば、ちょっとくずれて汚くなりますがやってやれないことはありません)と思って見ていたら、ちゃんと切りはずしたようです。三枚におろした後で、小骨を抜く作業について説明をしていたのがその証拠。切断しなけりゃ小骨は身の中に残りませんからね。プロは骨抜きで抜き取りますが、これをおこたると刺身で食べるときに支障となります。
小骨の形や長さは魚種によって差があるうえ、生えている本数も違います。弟がカマスで懲りたのは、身が薄いくせに背骨が太く、柔らかくて崩れやすい身に長い小骨が食い込んでいて取りづらいからです。ちなみに小骨は「肉間骨」と言いまして、「上椎体骨」(じょうついたいこつ)、「上神経骨」などが含まれます。その名の通り肉の中に入っているから厄介なのです。ハモは特に発達していまして、骨切りしなければ食べられないのはそのためです。イワシやニシンの場合は歯ブラシみたいに細くて長い骨が背骨からにょきにょきたくさん生えていますが、これも発達した上椎体骨や上神経骨です。ご関心の向きは緑書房の『新魚類解剖図鑑』をご覧ください。2冊組の旧版時代と違って、オールカラー。魚の骨格の説明がよりわかりやすくなっております。
素人が魚をおろす際のコツは、この一番厄介な小骨を切る作業を後回しにすることです。まず腹の身を中骨からはずします。包丁は背骨と同じ向きにして、刃渡りを長く使うようにします。大名おろしの方法でおろしますと包丁の向きは背骨に対して垂直になるので、中骨と中骨の間にひっかかりやすいのですが、これなら中骨の流れに沿ってすべるようにはがせるはずです。

次にぐるりと180度魚を回して、背側から中骨の上の身を同じ要領ではがします。そして最後に包丁をねかせて力を入れて背骨から小骨と腹骨を切りはずしながら身をはぎ取ります。テレビでもちゃっかり説明なしにこの手順で魚をおろしておりました。ただし逆に背のほうから包丁を入れていたようです。この方法では作業のたびに魚の向きをまな板の上でくるくる変えなければならず、素人は頭がこんがらがりますので、細かく手順を教えてあげるべきでした。
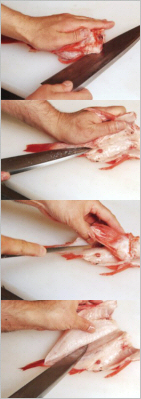 プロの場合はいちいち魚の向きを変えるのが面倒なので(あまり動かすと身が傷みますし)、腹側の身をはがしたのち、背骨から腹骨と小骨を切りはずしてから、背骨を乗り越えるようにして背側の身を切りはずす場合もあります。アジの開きみたいな要領です。ただしそれも、アジのように背骨が平らで乗り越えやすかったり、身質がしっかりしていてめくってもくずれない魚種の場合。背骨が太くて邪魔だったり柔らかいものの場合はちょっとやっかいなので、基本に忠実に腹側、背側、背骨の上と順におろします。
プロの場合はいちいち魚の向きを変えるのが面倒なので(あまり動かすと身が傷みますし)、腹側の身をはがしたのち、背骨から腹骨と小骨を切りはずしてから、背骨を乗り越えるようにして背側の身を切りはずす場合もあります。アジの開きみたいな要領です。ただしそれも、アジのように背骨が平らで乗り越えやすかったり、身質がしっかりしていてめくってもくずれない魚種の場合。背骨が太くて邪魔だったり柔らかいものの場合はちょっとやっかいなので、基本に忠実に腹側、背側、背骨の上と順におろします。
テレビでは、骨格についての説明がないから本を読んでもおろせるようにならないなんて、他社の本(ここ大事なとこ)を映して批判していましたが、正直言って五十歩百歩ですなあ。そもそも骨格を理解することがコツだなんてとっくの昔から言われてきたことです。
 1989年小社刊の『図解・魚のさばきかた』は共著でして、その一人はまだ「分とく山」の店長に就く前だった野崎洋光さん。本書冒頭で魚の骨と包丁の入り方の位置関係をイラストで説明しているのは、野崎さんのアドバイスによるものです。実はここまでつらつら偉そうに書いてこられたのも、この本が下地にあってこそ。当時、およそ120種類もの数の魚の下処理法や出回り時期を解説した本はほかになく、画期的な内容でした。
1989年小社刊の『図解・魚のさばきかた』は共著でして、その一人はまだ「分とく山」の店長に就く前だった野崎洋光さん。本書冒頭で魚の骨と包丁の入り方の位置関係をイラストで説明しているのは、野崎さんのアドバイスによるものです。実はここまでつらつら偉そうに書いてこられたのも、この本が下地にあってこそ。当時、およそ120種類もの数の魚の下処理法や出回り時期を解説した本はほかになく、画期的な内容でした。
しかしこの本は、手順の説明はすべてイラストでモノクロなのと、うっかりタイトルを「魚のさばきかた」としてしまったのが唯一残念なところでした。最近は完全にごっちゃになっていますが、魚は本来「さばく」ものではなくて「おろす」ものなので……。三枚さばきとか、五枚さばきとか言いませんでしょう? イエズス会の宣教師が苦労してまとめてくれたおかげで、戦国時代の庶民の話し言葉がわかる『日葡辞書』にも「vuouo vorosuウヲヲヲロス」(戦国時代だからといって「うぉぉぉ!ころす!」ではありませんよ)「iuouo sanmai voroxini suru イヲヲサンマイヲロシ二スル」という語が出てきます。「さばく」は今は鳥や動物に使われていますね。ちなみにスッポンの場合は関西では「ほどく」がよく使われます。
そこで最近小社では全カラー写真『形別魚のおろし方』という本を出版しましたが、これはvol22でも触れたムック『素材と日本料理』の中から、魚の下処理のページを集めたものです(素材解説と料理のページのほうはこれとは別に『100の素材と日本料理』という単行本になってます)。ただまとめるだけでは前のムックを買ってくだすった人に申し訳ないので、魚種を増やした(それでも計40種ですが)うえにまな板上での魚の頭の向きがわかるようなイラストを入れました。プロセス写真は多いものでは30点とかなり細かく追いかけています。とはいえ、初心者向けにはこれでもまだ足りないくらいでしょう。
テレビの番組製作側としては、魚をおろすのは難しい作業と思い込まずにトライしてほしいというメッセージを込めたかったのでしょう。目のつけどころはよかったと思います。ここで縷々述べてきたような細かい説明は、ややこしそうに思われかねないので避けたのでしょう。しかしいくらなんでもはしょりすぎですし、どんな魚でもガッテン流でうまくいくというのは誇大広告すぎます。カツオやサワラは身割れしやすいし、タイは小骨が太くて固いので気をつけて……。鮮度が落ちてくるとくずれやすいですしね。テレビの方法通りなのにうまくおろせず、トラウマになってしまう主婦が現れないことを祈ります。
あと「目からウロコのさばきワザ」なあんて副題がついてましたが、なぜかウロコの引き方は放送内で触れていませんでしたね。ホンモノのウロコはあちこちに飛び散ったりして厄介ですから、これまた素人にとっては問題なのに……。内臓やエラのはずし方も説明しなかったところから察するに、魚を買うときに魚屋さんに頼んで除いてもらえということなのでしょう。
というわけで、ちょっと読むのにホネな今回の話はこれでおしまい。皆さんガッテンしていただけましたでしょうか。
投稿者 webmaster : 11:18
2011年05月31日
料理本のソムリエ [ vol.22 ]
【 vol.22】
生まれと育ちで異なる魚の香り
香りの話がまだしつこく続きます。前田學さんの一件で失敗した私ですが、香りがテーマの対談企画をあきらめたわけではありませんでした。次に白羽の矢を立てたのは寿司職人の関谷文吉さん。浅草の紀文寿司の4代目で、『魚は香りだ』というそのものずばりなタイトルの著書があります。魚のもつ繊細な香りこそがその個性であると見抜いた慧眼(鼻?)の持ち主です。
この本は関谷さんのデビュー作『魚味礼讃』の続編でして、香りだけではなく、味の表現も豊かです。とくに貝類やイカなどの寿司らしい素材に関しては、おのずと語り口は饒舌となります。「ホッキガイほど強い甘味を訴える貝はありません。ホタテガイの味わいとは違った、もっとネットリした蜜のような濃さがあり、かすかにホヤを想わせるような青臭さが感じられるのです」「アオリイカの味わいはねっとりと、まるで雲のなかにいるようなゆったりとした諧調の甘味です。同じ甘味でもヤリイカの軽快な味とは違い、どっしりと根を張った味調です」というふうに。関口さん独自の解釈と表現ですが、奇をてらおうというのではなく、読者に納得してもらおうという姿勢が感じられます。
さらに産卵期とその前後のシャコの違いや、アンコウの肝とカワハギの肝の脂肪の質について私見を述べたり……。実体験に裏打ちされているので、説得力があります。そこが「この魚の旬はいついつで、江戸川柳(ここはときには万葉集だったりします)ではかくかく描かれていて、栄養は何々で、刺身と煮魚と焼き魚とフライに向いている(ほかに調理法はないのでしょうか?)……」という感じの、どこかから写してきた情報を列挙していっちょうあがりのお手軽解説本とは一線を画しております。
関谷さんは『魚味礼讃』の冒頭で、そうした借り物知識で食を語る世の風潮を批判しております。とある料理評論家はテレビ出演中に刺身を食べたものの、その魚が何だか教えてもらうまでひと言も発することができず、ホウボウであることを知ったとたんに自慢げにとうとうと語り始めるだらしなさ。そのうんちくがどこかで聞いたような話だと思ったら、書棚にあった大学の先生の本に書かれていたのと一緒だったとか。「某氏は自分自身の舌や感性で魚の味を理解しているのではなく、食味というものを書物なり、人から聞いた受け売りの知識だけで判断しているというのが、手にとるようにわかったのです」とかわいそうに一刀両断されております。
さらに返す刀で、「通」を振り回して不勉強さと未熟さを隠そうとする半可通な同業者をもばっさり切り捨てます。「職人に<これはこうして食べるんだ>とか、<こうしてつくったもの以外は偽物だ>などと、高みから自負心の塊みたいな半端な戯言(たわごと)を見下すように聞かされるのも、たまったものではありません」「頑固さだけを売りものにして、<これは秘伝だ>とか、<何十年修業しなければできない>などと、何も知らない素人を相手に何か特別な仕事をしているようなことを言って、さもむずかしそうに見せかけていても、それはただ単に自分のステータスを高く位置づけようとするためだけのことにすぎません」……読んでいてすがすがしいくらいです。
もちろん関谷さんの文にも、江戸時代の文献に登場する魚の記事など、他の著作から抜粋した話が盛り込まれておりますが、ただ切ってつなげたのではなく、自分の関心事に沿って調べられているのがわかります。『魚味礼讃』は雑誌の連載をまとめたもののため完成度が高いせいか、二度も文庫化されたうえにワイド版すら出ておりますが、デビュー作ですから文体に少々気負いもうかがえます。一方『魚は香りだ』のほうは筆致がばらばらなものの、肩の力が抜けておりまして、自在に筆が走っている様子がうかがえます。こちらがいまだに文庫化されないのが残念です。
 このブログ、まいどまいど長すぎるので
このブログ、まいどまいど長すぎるので
このへんでCMといきましょう。
『「止めろって言った」って言うと、「言ってない」って言う。
「危ないって言った」って言うと、「言ってない」って言う。
そうしてあとで不安になって、「止めたよね?」って言うと
「止めなかった」って言う。
あまのじゃくでしょうか。 いいえ、誰でも』 ……
これだけみるとなんだか子供の喧嘩みたいですね。
さて、ここまでなかば興奮気味に紹介して参りましたが、「魚なんて魚くさいだけで、香りに違いなんてあるのかねえ」と半信半疑の方もいらっしゃるかもしれませんね。ましてや冷たい刺身となると、サンマの塩焼きのように香りが四方八方にただようわけではありませんから。それでも刺身を醤油ではなく塩で食べてみると、ほのかな香りでもわかりやすいので、ご関心の向きは一度お試しください。ただしカウンターの日本料理店や寿司店で通ぶって、「あー君、ちょっと塩をくれたまえ」と要求したりすると、撒かれたりしないとも限らないので、馴染みの店やご家庭で実験されたほうがよいでしょう。
よく「日本料理は素材の持ち味を生かしている」といいますが、実は醤油、味噌、鰹節、日本酒、米酢といった香りの強い発酵食品を多用します。ですから、これらの香りでマスキングされてしまう香りがないとも限りません。実際、とある海洋カメラマンから「磯の香りはなんとも思わないが、板前割烹の厨房の独特のにおいが苦手で……」と聞いたことがあります。確かに、煮きった酒とだしとカウンターの白木の香りが混ざったようなむっとしたにおいってありますよね。外国の人が日本の空港に降り立つとまず感じるのは味噌の香り、なんていう話もありますから、自分が慣れきっている香りはあまり感じなくなっているのかもしれません。日本人が思うほど素材の香りを生かせていないかもしれませんよ。
さて日本生まれで日本育ち、スーパーで買ってきた特売の刺身を醤油にどっぷりくぐらせて長年食べてきた私が、初めて同じ魚種でも生まれと育ちで香りが違うことを思い知らされたのは、雑誌の企画で実施した鯛テイスティングでした。vol15で紹介した水テイスティングもそうですが、素材の比較研究にやたら凝っていた時期がありまして、鯛テイスティング企画では神奈川の佐島、明石、鳴門、長崎、佐賀関、ニュージーランド、養殖の鯛をソムリエの田崎真也氏の解説を受けながら食べ比べました。代々新鮮な魚に触れてきた寿司店の主人ならいざ知らず、鈍感な舌の持ち主のわれわれに、はたして差なんてわかるのだろうかとおっかなびっくりトライしてみたのですが、不思議なことに微妙に違う。とくに佐島のタイは海苔のような磯の香りが、明石の鯛はほのかに甲殻類の香りがしまして、明確な個性が感じとれました。
鯛は雑食性なのでエサの違い(もっとも佐島の鯛は海草ばかり食べているわけではないでしょうが)が反映したのでしょうか…。もちろんこれだけの数の鯛を揃えたのですから、ただおいしくいただいただけで終わらせたわけではありませんよ。その時に集めた懐かしい鯛の写真は、別冊専門料理『素材と日本料理』第2巻だったり、柴田書店ブックス『鯛』の図鑑ページでも見ることができます。
ちなみにこの時取り寄せた養殖の鯛は、天然の鯛も扱う業者さんが、天然に近い仕上がり(養殖の鯛は黒っぽかったり、ヒレがすり切れていたりするのです)という自慢の品だったのですが、残念なことにかすかに泥っぽいにおいがしました。これは養殖場では酸化しやすい脂の多いエサを与えているせいなのか、あるいは食べ残したエサが底にたまりやすく、そうした泥のにおいのする水の中で育ったからなのでしょうか…。後日、ヨーロッパで養殖されているテュルボ(ヒラメの一種)の刺身を食べた時にも同じにおいを感じたので、これは日本の養殖魚に限ったことではないのかもしれません。
もっとも「だから養殖はいけないのだ」というつもりは毛頭ありません。しかし養殖魚は、見た目や脂ののりをよくすることも大事ですが、香りという大きな課題があるのに無頓着でいてはいけないと思うのです。養殖業者さんによると改善する方法はあるようなのですが、市場がその努力を評価してくれないのだとか。努力をしてもしなくても「養殖だからこの値段」という相場で一律同じ扱いにされがち。あるいはサイズが揃っているといった要素(ウナギなんかは串を打ったりお重に入れたりする都合上重要らしいです)のほうが優先されたりします。流通業者も消費者も、自分の感覚で商品の味をはっきりと見定めて(食べ定めて?)、評価しようという姿勢が欠けているのでは……。もっと香りと食感(養殖魚の場合のもう一つの課題は、身の固さです)を評価し、向上させる道を探れば、養殖の分野でも世界をリードできそうな気もするのですが。なにしろ世界一魚に親しんでいる魚喰い民族なのですから。
ちなみに関谷さんが魚の香りに着目するようになったのは、ワイン好きだったからだそうです。だから関谷さんの魚の味や香りの表現は具体的で、情報を誰かと共有したいという気持ちが見え隠れしているのでしょう。関谷さんとソムリエさんとなら魚の香りをいかにして意識の俎上にのせるか、どのように表現できるかで、さぞや話が弾むではなかろうか……。ところがいざお店に対談依頼の電話をしましたところ、奥様が出られて大変恐縮したご様子で「最近、身体の調子が悪くて取材は……」とのお返事。それでもどこかの水検査会社の対応とは大違いでした。
それからしばらくして関谷さんは現場を離れ、3年ほど前に亡くなられたと人づてに聞いております。前田さんも、前回紹介した醸造学者の富永さんも、ほぼ同じ頃に亡くなられました。人と人との出会いをセッティングするのが編集者の仕事ですが、なかなかそれすらもうまくいかないものです。
投稿者 webmaster : 09:49
2011年05月18日
料理本のソムリエ [ vol.21 ]
【 vol.21】
言葉で浮かび上がる香りの記憶
このところ食品の放射能汚染の報道が続いておりますね。キノコ、茶、内陸の魚類…。まあ、前例のチェルノブイリで起きたのとだいたい同じパターンですから、これってきっと“想定内”なんでしょう。生産者へのケアもぬかりなくお願いしたいものです。
かといって魚の頭と内臓を除いてセシウム量を計測していたのをごまかしだのと言って、鬼の首を取ったように騒ぐのもどうかと思います。頭と内臓が気になるなら(あら煮用かな?)、それはそれで別に分析を要請すればよろしい。というか食材ごとに可食部と平均的な摂取量を勘案して、もう少し細かく基準を設けたほうがよいのではないでしょうか。日常的にたくさん食べる食材もごく少量しか使わない食材も一律で1kgあたり500ベクレルという規制でくくるのは、ちょっと大雑把すぎると思うのです。確実に割を食うのは乾物類でしょう。ドライハーブを1kg使うのはかなり大変だと思うのですが…。
緩すぎる規制も問題だけれど、かといって風評加害者にはなりたくないので、こんなふうに言葉を選び選びブログを執筆していたら、ここにきて豪胆な発言が飛び出しました。「低線量の放射線はむしろ健康にいい」。東電の顧問さんともなると自らの信念に忠実で一点の曇りもないようです。前回、放射線にはこれ以下なら問題ないという“しきい値”がわかっていないことを説明する際に、「反対する説もあります」とこわごわ注を入れて保身を図った私の小者ぶりに恥じ入りました。追加で説明しておきましょう。
低線量の放射線が健康によいという「ホルミシス仮説」をあつかった概説書のは、「これでみるみる私も健康になった」的な本が多いのですが、学者がきちんと説明したものとなると文春新書の『“放射能”は怖いのか』あたりでしょうか…。これは、ごく弱い放射線が生物の活性をうながすという説で、植物や昆虫で効果が確認されています。ラドン温泉が身体にいいとされているのと同じ理屈ですね。しきい値なし(LNT仮説)を直線グラフで表すなら、しいち値ありは折れ線に、ホルミシスは図のようにさらに急カーブのグラフとなります。グラフの左のほうであれば発ガン率が上がるどころか、むしろ下がるというわけです。
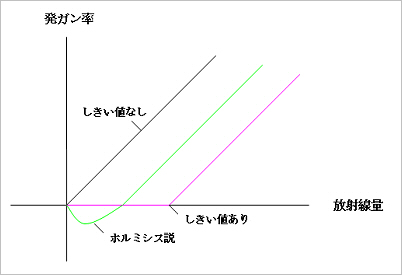
ただしこれもまた仮説でして、どのくらい放射線量が高まると有害に転じるのか、病人や妊婦、乳幼児と健康な大人で違いはないのかといった肝心なところがわかっておりません(温泉でも病気の人や妊婦さんは遠慮していただきますよね)。それで“しきい値なし”という危険性を高く想定した仮説のほうに基づくのが、現在の放射線防護の考え方。君子危うきに近づかず、というスタンスです。レジオネラ菌がどれくらいの個数で肺炎を起こすのかが現時点では不明なので、お風呂の衛生基準は厳しく「不検出」に設定しているのと同じことです。
さらに困ったことに、せっかくの健康にいい放射線も、原発由来のものは処方量をコントロールできておりません。頼んでもいないお薬が誰彼かまわずサービスで配られているってのもずいぶんな話ですが、お薬手帳をもらった記憶がない。複数のお医者さんに処方されて摂りすぎたりやしませんかね? そもそもホルミシス仮説の熱心な旗振り役は(財)電力中央研究所ですしねえ…。壮大な人体実験につき合わせておきながら、自分は安全な所で利口ぶるのは学者さんの悪い癖です。「郡山の校庭の土なんざ、研究用にうちの敷地に引き取りますよ」とでも言えばいいのにね。
そういえば青酸カリよりも強い劇薬のニコチンも、ごく少量なら肝臓の代謝を促すそうですよ。「現在放出された放射性物質の危険性はタバコよりもずっと低い」なんて比較の対象にされていますけど、日本パイプクラブ連盟は禁煙ファシズムだと訴えないのでしょうか?
さてさて前ふりが長くなりましたが、今回は香りについて。 vol.18 の水道水の話の続きです。ミネラルウォーターが人気沸騰中な昨今、ピント外れもいいところですが、前々回を読んで、「え…………、利き水名人の話はあれでおしまい?」「前半分は佐野眞一氏の外食産業取材についてで、利き水名人の話には半分しか割かれていなかったじゃないですか」と思われた方、ご安心ください。
前田學さんが登場する本は、『鼻学』のほかにもまだあります。まずひとつが『婦人公論』の連載「井戸端会議」をまとめたシリーズ。中央公論新社の単行本『経験を盗め』に収録されております。
このシリーズは糸井重里氏をホストに鼎談型式に行なわれたもので、お相手は最相葉月氏。小学館ノンフィクション大賞を受賞した『絶対音感』の著者です。音に鋭敏な人が感じる世界と、香りに鋭敏な人の感じる世界を比べ、語り合おうという狙いですね。もっとも、所詮は違う分野なので話があんまりかみ合っていないような気もいたします。ちなみに前田さんによると、蒸留水でご飯を炊くと、米がよければよいほどそのものずばりのふわーっとしたいいにおいがするのだとか。けれども蒸留水が気が抜けたようなまずい味なのと一緒で、食べるとけっしてうまくないそうです。この本は文庫化されておりますが、全3冊あった同シリーズをいったんばらして内容別に『心と体の不思議編』『奥の深い生活・趣味編』『文化を楽しむ編』の3冊に編集し直してあるため、ちょっと注意が必要です。前田さんの鼎談は『心と体の不思議編』に収録されています。
さてもうひとつは、同じ中央公論から出た『超人へのレッスン』。超人列伝という視点でまとめてあるのがちょっと引っかかりますが、調律士、漁師、旋盤工など10人にそのすぐれた五感について取材したものです。前田さんの談話を一人語り口調でまとめ直してある『鼻学』と違って、この本では著者の質問に対する答えがそのまま収録されています。「採ってきた水を置いておきますと、たとえば〈藻の匂い〉がすぐに〈褐色〉がかった匂いになったり、〈土〉の匂いが〈茶〉の濃くなったような匂いに変わったりする場合、あるいはその匂いが薄くなって〈緑色感〉やいろいろな形で〈緑〉っぽいような色が出てきたり、という変化が起こることがあるんです」といった具合。テープおこししただけのようでわかりにくくはありますが、前田さんの表現法がそのまま収録されているのが興味深いです。紅茶に浸したマドレーヌの香りから幼年時代の記憶について思い出すのとは逆に、特定の言葉に結びついた香りの記憶を思い出しては探りあてているようにも思えます。こちらは中公文庫ではなく徳間書店から、『匠の技 五感の世界を訊く』というおとなしめなタイトルに変えて文庫化されております。
ところで香りを言葉に表現して記憶する前田さんの手法、これはまさしくワインテイスティングと同じと思われませんか?
ソムリエコンテストといえばブラインドテイスティングですが(それはワインを上手にサービスするスキルを磨くためで、こればかりを競っているわけではありませんが)、そんな芸当ができるのも、どの産地のワインがどんな個性を持っているのかをしっかりと記憶しているからです。そのツールの1つとなるのが香りです。ただ「いい香りだなー」では漠然としすぎて頭に残らないので、「フレッシュな果実香」「ミネラル感」「フィニッシュにバニラの香り」などと分析し、イメージすることで、そのワインの個性をはっきりと位置づけることができます。
ただし前田さんとの大きな違いは、ソムリエたちは香りの表現を他人と共有しており、情報を普遍的なものとしている点です。『超人のレッスン』で、前田さんの上司の小島貞男氏が「彼の使う匂いの表現も我々にはよくわからないですよ。〈緑色感〉とか〈靄(もや)の潤いがある〉とか。共通言語じゃないから困るんです。我々にはない感覚だから仕方ないんですけど」とコメントしているのとは対照的です。前田さんは日本で最初の水質テイスターですし、その能力は飛びぬけているので、この技術を共有したくとも共有できる相手はいなかったのでしょう。

 一方ソムリエは、同じ香りを同じ言葉で表現することで、ヴィンテージや産地の違いを理解し合えるようにします。試しに『必携 ワイン基礎用語集』を開くと、ずらりと形容表現が並んでいます。洒落や気分で「枯葉」だの「濡れた犬」の香りなどと言っているのではないわけですね。
一方ソムリエは、同じ香りを同じ言葉で表現することで、ヴィンテージや産地の違いを理解し合えるようにします。試しに『必携 ワイン基礎用語集』を開くと、ずらりと形容表現が並んでいます。洒落や気分で「枯葉」だの「濡れた犬」の香りなどと言っているのではないわけですね。
そうしたワインの香りの世界の奥深さを解説する本としては、ボルドー大で醸造学を学んだ富永敬俊氏の『アロマパレットで遊ぶ―ワインの香りの七原色』があります。ワインの香りを虹の7色になぞらえて、7つのカテゴリーに分類、整理しようという香りのガイドブックです。フルーティアロマ、ハーベイシャスアロマ…とカタカナだらけなうえに、香り成分などの化学用語も飛び出しますが、ワインの教科書よりわかりやすい。これなら、私も少しはワインの香りが覚えられそう、という気にさせられます。
ワインの特定の香りを把握することは、その香りはどんな成分に由来するか、その成分を持つブドウはどんな品種なのか、醸造のどの過程で生じるのかといった謎の解明につながります。そうした香りの研究方法や成果の一端は、同じ著者の『きいろの香り ボルドーワインの研究生活と小鳥たち』で紹介されています。こちらはワインの香りの研究に関する6つの話題で構成されておりまして、これまた化学用語がたびたび登場しますが、科学読み物としてもエッセイとしても楽しめます。理系の本らしく索引が充実しているのも好感が持てます。なお、タイトルは色と香りに関する考察について…ではなく、著者が飼っていた小鳥「きいろ」のこと。ソーヴィニオン・ブランの香りのする不思議な小鳥との出会いと別れについては、本書第5章をご参照ください。近頃、科学者と呼ばれる人たちの純粋な思いや熱意を信じられなくなってきた人に、お勧めです。
投稿者 webmaster : 12:05
2011年04月28日
料理本のソムリエ [ vol.20 ]
【 vol.20】
昆布は放射能から日本人を救うか?
大震災からそろそろ1カ月半。週刊誌やスポーツ新聞は被災地の話題が次第に少なくなるのに比例して、原発事故のほうに重きをおきつつあるように感じます。ちょうど阪神淡路大震災の2カ月後のように。あのとき、マスコミ報道はあっという間に麻原彰晃とオウム一色で染まり、復興に向けての話題はすっかり隅に押しやられたのを思い出しました。中には今振り返ってみれば笑ってしまうような誤情報もありましたね。今の原発記事がそうでない保証はありません。
交通の便が悪いうえに広範囲におよぶ被災地へ取材陣を派遣するには、時間と費用がかかります。被災者の人生と向き合う取材は辛い仕事です。その点、原発関係でしたら現地に行かずとも有識者(?)に語らせるだけで、人目を引く記事を仕立てられます。東京電力も政府も今なら叩き放題で溜飲も下がります。そうしたマスコミの都合に踊らされ、今まさに困っている人たちへの関心を途切れさせないようにしたいものです。
もちろん原発問題を軽んじてよいわけありませんが、いたずらに不安を煽るだけの言論も多くていささか辟易気味でして。ネット文化人やマスコミの論調を見ていると、一夜漬けの急ごしらえな知識で発言している例が多いのにも呆れます。いわば原発ゆとり世代。長年の安全PRの成果なのでしょうか。圧力容器の中がどうなっているのかはっきりわからない以上(燃料棒の溶融ばかり取り沙汰されてますが、15年ほど前にひびが見つかって慌てて交換したシュラウドはどうなっているのでしょう?)、おっかなびっくり手探りで、時間をかけて対処するしかなく、外野がとやかくいってもむなしいだけです。
ところで工学的な考察はともかくとして、原発推進論というのは、証券会社が株や債券を勧めるのとちょっと似ていませんか? 「将来性の低いスイリョクや、枯渇とCO2が心配のカリョクよりも安いんです。分散投資は世の常識ですよ」というのがそのセールストークです。「ハイリスク商品はちょっと」「これからが有望そうなフウリョクやタイヨウコウに投資したい」という意見もなんのその、「そんな万一のことを考えてたら投資なんてできません」「ベンチャー企業に手出しすると火傷しますよ」と押し切られ、営業マンの勧めるがままにゲンパツ社債を買い続けてきたわけです。こうなると推進に賛成か反対かは、うまく売り抜ける自信があるかどうかと同様で、理屈では分かり合えない気がします。
ところがここにきてまさかの破綻。約束が違うじゃないかと胸ぐらを捕まえても、「いやあ災害は予見できませんから」とのらりくらり。そのうえ「また新しい債券を買って運用しなきゃ、今のような生活は続けられませんよ?」ですって。上場予定という触れ込みだったモンジュとかいう株も、今や完全に塩漬け状態だというのに。どうもこの証券会社は悪徳そうな匂いがしますが、気のせいでしょうか。この取引で儲けているのは誰なのか見極める必要がありそうです。ちなみにこのゲンパツという債券、廃炉という満期を迎えたときには償還どころか、支払い額未定の手数料がかかるという噂ですが、まさかそんな間抜けな投資商品はありますまい。
原発と放射能の問題を扱った本としては、かつて広瀬隆氏の一連の著作が話題をさらいましたね。かくいう私も80年代の『東京に原発を!』で原発の胡散臭さを知ったクチでして。原発がそんなに安全なら東京に作ればいい、送電線がいらず(送電ロスは距離に比例するので遠くに原発を作ればそれだけ無駄になります)、排熱は湯として利用できる(原発はその膨大な熱のすべてを活用することができず、温排水の形で捨てているのです)のでいいことずくめではないか、という挑発的な本でして、建設候補地は新宿の淀橋浄水場跡でした。ぼやぼやしていると原発誘致運動が始まってしまうとでも思ったのか、そこに都庁が建ってしまったので、今なら豊洲あたりがいい候補地かもしれませんね。都知事は以前、東京湾に原発を作ってもいいとおっしゃっていましたし。この本はのちに集英社文庫に入りましたが、JICC出版局の元版のほうが構成もデザインも優れていたと思います。
広瀬氏の本はスリリングな書きぶりで読み物としては面白いものの、専門家ではないために科学的には疑問符が多いと言われてますし、陰謀史観もてんこ盛りで副作用が強すぎます。専門家からの批判としては、圧力容器設計者の田中三彦氏の告発『原発はなぜ危険か』(指摘されているのは福島第1原発4号機の圧力容器です。今回点検中だったのは不幸中の幸いでしたね)や、核科学者の立場から生涯を通して反対してきた高木仁三郎氏の一連の著作が古典としてはずせません。
気になる食品に対する影響としては、講談社現代新書の『食卓にあがった死の灰』が、『食卓にあがった放射能』と改題されて七ツ森書館から復刊されております。ちなみに七ツ森書館は柴田書店と本郷時代からのご近所で、DTPでお世話になったりしております。広瀬氏がかぎつけて「マスコミが裏で結託している!」と言われる前に、先手を打って公表しておきたく。まあ互いに得意ジャンルが遠すぎて、共謀しようがありませんが。
この本は、チェルノブイリ原発事故とヨーロッパの食品汚染被害を考察した本でして、当時のソ連政府の広報が後手後手に回って被害を拡大していった様子や、各国政府がどう対応したかが解説されており、他山の石となります。ただし運転中の黒鉛炉が炎上したチェルノブイリと福島原発では状況が違いますし、1986年の事故発生から4年後に出版されたという時代の制約もあります。せっかくだから復刊にあたって、最新のデータと知見も増補してほしかったですね。たとえば東京都はチェルノブイリの事故以降、都内に流通している輸入食品の放射能汚染の検査をずっと続けております。暫定基準の370ベクレルを超える放射性セシウムに汚染された食品は、ここ最近でも06、07、09年に1点ずつ見つかりました(検査した試料の数は06年は257点、07年は270点、09年は329点)。こんなにも影響が続いているのか、こんなにも身近な存在だったのかと驚いた次第です。
放射線防護学の立場から説いたものとしては、安斎育郎氏の『家族で語る食卓の放射能汚染』がわかりやすく、増補改訂版も出ております。食品の放射能汚染の厄介な点は、これ以下ならば大丈夫という“しきい値”がない、すなわち「どんなに微量でも放射線量に比例して癌になる可能性が高まる」(反対する説もありますが決着がついていません)ことにあります。安斎氏はこれを“癌当たりくじ”といういやーな貧乏くじにたとえます。放射能が低ければ(つまり当たりの数が少なければ)、癌になる確率は低くなりますが、低いなりに癌になる可能性は残ります。そのため流通を規制しようにも、どこで区切ってよいのか線引きが難しい。今回放射性セシウムの暫定基準値が370から500ベクレル(野菜の場合)に引き上げられたのは、こうした事情からです。そして実際に癌になったとしても、発癌性物質や天然放射性物質のしわざと区別がつかず、責任を問うこともできません。つまり今後癌になる人が増えたとしても、そのうち誰が当たりを引いたのかは最後までわからないわけです。
 また大人よりも細胞分裂が旺盛な子供のほうが影響を受けやすかったり、放射性物質によって人体に貯まる場所が違うなどの理由から、同じ放射線量でも危険性を単純比較できません。放射性ヨウ素が危険といわれるのは空気や水から取り込みやすいうえに、骨の成長に関わる甲状腺に貯まりやすいためでして、予防には昆布が有効という噂がネット上に広まりました。その出所は、高田純氏の『世界の放射線被爆地調査』あたりではないかと思われます。高田氏は事故があったときの防衛策として、大人の場合は33グラムの量の昆布を食べて、事前に安定ヨウ素を取り込んでおくのが有効であるとしています。ただし食べてから甲状腺に届くまで時間がかかるうえに、昆布のヨウ素の含有量や吸収できる量は一定ではありません。おまけに33グラムはかなりの量(ネット上では量はまちまちで、乾燥重量と明記していないものも多いようですが)。そのため一部の報道でデマと切り捨てられましたが、これは即効性のある安定ヨウ素剤の代替にはならないというだけの話です。ヨウ素剤は、高濃度の放射性雲が迫ってきて肺からも皮膚からも吸収してしまうので、一刻を争うという時に服用するものですから。現時点では差し迫った危険があるわけでもないし、大多数の人は安定ヨウ素剤を入手できませんから、まったく食べないよりはましでしょう。
また大人よりも細胞分裂が旺盛な子供のほうが影響を受けやすかったり、放射性物質によって人体に貯まる場所が違うなどの理由から、同じ放射線量でも危険性を単純比較できません。放射性ヨウ素が危険といわれるのは空気や水から取り込みやすいうえに、骨の成長に関わる甲状腺に貯まりやすいためでして、予防には昆布が有効という噂がネット上に広まりました。その出所は、高田純氏の『世界の放射線被爆地調査』あたりではないかと思われます。高田氏は事故があったときの防衛策として、大人の場合は33グラムの量の昆布を食べて、事前に安定ヨウ素を取り込んでおくのが有効であるとしています。ただし食べてから甲状腺に届くまで時間がかかるうえに、昆布のヨウ素の含有量や吸収できる量は一定ではありません。おまけに33グラムはかなりの量(ネット上では量はまちまちで、乾燥重量と明記していないものも多いようですが)。そのため一部の報道でデマと切り捨てられましたが、これは即効性のある安定ヨウ素剤の代替にはならないというだけの話です。ヨウ素剤は、高濃度の放射性雲が迫ってきて肺からも皮膚からも吸収してしまうので、一刻を争うという時に服用するものですから。現時点では差し迫った危険があるわけでもないし、大多数の人は安定ヨウ素剤を入手できませんから、まったく食べないよりはましでしょう。
一度にたくさん昆布を食べられる料理としては、すぐに思いつくのは昆布巻きですが、日本料理には天井昆布という、昆布の塊のような料理もあります。柔らかく煮た昆布を何層にもぴっしり重ねてからきれいに切り整えたものです。煮昆布はすべりやすいし崩れやすく、難易度が高いため、今では作る料理人が少なくなりました。もしかしたらこれをきっかけに見直されるかもしれませんぞ。家庭の場合は沖縄料理のクーブイリチーがお勧めですね。油と一緒に食べるとヨウ素の吸収がよくなるそうですし。なお、昆布をもどした水にもヨウ素が含まれるので、昆布だしも有効です。


ただし安定ヨウ素であっても摂りすぎが続くと甲状腺の機能を損ねますし、昆布は今後深刻になると思われるセシウム汚染に対しては無力です。これには味噌などの発酵食品がいいとか、玄米にはデトックス効果があるとかいう意見も見かけますが、味噌はせっかく甲状腺に貯めたヨウ素の排出を促すそうですし、米の胚芽や糠層は放射性物質を蓄積しやすいそうですから、タイミングをまちがえると逆効果になるかもしれません。昆布にしても天然の放射性物質であるカリウム40を多く含む食品でして、なかなか悩ましい問題でもあります。まあ、キムチがSARSや新型インフルエンザに効くというのと、同じくらいの額面で受け取っておいたほうがよさそうかもしれません。
癌にならないよう健康に気を遣った食生活を送るべしという意見に異論はありませんが、身体に悪いかもと思いつつ旨い物には目がない私は、きっちり養生できる自信がありません。ちょっとやそっとなら放射性物質を含んだ食品を食べても、自分はくじ運が悪いから大丈夫、と信じて暮らすしかなさそうです。おっと、これでは破綻しないと信じてゲンパツ債を買い続けるのとあんまり変わりませんが、他人に迷惑をかけるわけではありませんからよしとしましょう。
投稿者 webmaster : 13:55
2011年04月08日
料理本のソムリエ [ vo.19 ]
【 vol.19】
関東大震災にめげない石井泰次郎
あの忌まわしい震災から1カ月が経とうとしています。時々思い出したように余震がくるので気が抜けないし、原発の二次災害と被災者の方々の苦難は進行中です。
 3月11日のあの時間、私は遅い昼食を終えて大通りを呑気に歩いていました(vol.11 可否茶館の石碑のある通りです)。お店の人が店頭に飾った商品を大慌てで押さえ始めたのを見て、何が起きたのかと思ったら(鈍感ですね)、いきなり生き物の背中に立っているかのように足元が不安定になりました。見上げると10階建てくらいのビルが一斉に、ムーミンのニョロニョロのように首をふっております。このまま道にいてよいものか。窓ガラスが割れて降ってきたらどうしよう。もっと車道へ避けようか。でも車に轢かれるかもしれない。ビルの中に飛び込もうか。崩れでもしたら大変だ。いやいや日本のビルはしっかりしてるし…。こんなことをぐるぐる考えながら、車道でも舗道でもないガードレールあたりのちゅうぶらりんな場所でおろおろしているうちに、長い揺れは収まりました。あれから1カ月ですが、心は相変わらず落ち着く場所が見つからず、ちゅうぶらりんでおろおろしたままです。
3月11日のあの時間、私は遅い昼食を終えて大通りを呑気に歩いていました(vol.11 可否茶館の石碑のある通りです)。お店の人が店頭に飾った商品を大慌てで押さえ始めたのを見て、何が起きたのかと思ったら(鈍感ですね)、いきなり生き物の背中に立っているかのように足元が不安定になりました。見上げると10階建てくらいのビルが一斉に、ムーミンのニョロニョロのように首をふっております。このまま道にいてよいものか。窓ガラスが割れて降ってきたらどうしよう。もっと車道へ避けようか。でも車に轢かれるかもしれない。ビルの中に飛び込もうか。崩れでもしたら大変だ。いやいや日本のビルはしっかりしてるし…。こんなことをぐるぐる考えながら、車道でも舗道でもないガードレールあたりのちゅうぶらりんな場所でおろおろしているうちに、長い揺れは収まりました。あれから1カ月ですが、心は相変わらず落ち着く場所が見つからず、ちゅうぶらりんでおろおろしたままです。
阪神淡路大震災から1カ月経ったとき、私は取材で神戸入りしました。「いつか店を再開する日のために料理の勉強を続けたいが書店が閉まっていて雑誌が手に入らない、直接送ってほしい」という読者の葉書に感銘を受け、被災地の料理人さんたちはどのように励ましあい、乗り越えたかを取材しようと思ったのです。この時、神戸の街はまだほこりっぽかったのですが片付けが進み、復興の槌音が始まっていました。ホテルに泊まっているのは全国から集った建設会社の人ばかりで、くたびれた背広のおっさんが青い作業服たちに混じって洒落たラウンジで朝食のクロワッサンをつまむのは、その場所に不似合いでなんとも妙な光景でした。その時のことを考えると、今の東北地方は同じ一カ月後でも、復興の歩みが遅々として進んでおらずやりきれません。
当時取材をしていて感じたのは、マスコミの報道からではうかがい知れない苦労であり、当事者ではない我々には、この人たちの傷みはとうてい骨身にしみて理解できないという掻痒感でした。疲労の色が見られる中でも、将来の希望を力強く語ってくださる料理人さんに感銘をうけつつ、こちら側が癒され、励まされてどうする、という無力感にも襲われました。今度の震災でも、そのちゅうぶらりんな感覚は同じです。
だからこそ、直接被害に遭わなかった土地の人たちは、フルに想像力を動員して、被災者の心境や境遇を慮らねばなりません。テレビや新聞から伝わるのはごく一部です。悲惨すぎて取材できない撮影できない光景が、カメラやペンがまだ入っていない場所や事実が、あるはずです。
 柴田書店から『地震の時の料理ワザ』という本が出版されていますが、これは阪神淡路大震災を経験した著者が自分の経験を元に、「自宅で過ごしている被災者」を想定して書かれた本です。被災地報道では避難所の光景ばかりが写されますが、そうした人たちばかりではありません。避難所での食事は炊き出しとなるため、個人の手はおよびませんが、自宅避難者は熱源や材料に制限のある中で、自分の力で毎日の食事を手当てすることを考えねばならない。恥ずかしながらこの本を読んで初めて、そうだったのか、と知った次第です。巨大すぎる被害の映像の影に隠れた、小さな(といっては失礼ですが)無数の個人の苦難は、マスコミの派手な報道にはなじみづらいですが、目を向ける努力を怠ってはなりません。
柴田書店から『地震の時の料理ワザ』という本が出版されていますが、これは阪神淡路大震災を経験した著者が自分の経験を元に、「自宅で過ごしている被災者」を想定して書かれた本です。被災地報道では避難所の光景ばかりが写されますが、そうした人たちばかりではありません。避難所での食事は炊き出しとなるため、個人の手はおよびませんが、自宅避難者は熱源や材料に制限のある中で、自分の力で毎日の食事を手当てすることを考えねばならない。恥ずかしながらこの本を読んで初めて、そうだったのか、と知った次第です。巨大すぎる被害の映像の影に隠れた、小さな(といっては失礼ですが)無数の個人の苦難は、マスコミの派手な報道にはなじみづらいですが、目を向ける努力を怠ってはなりません。
*『地震の時の料理ワザ』より、役に立つと思われるポイントをまとめています。
イラスト付きの内容は、PDFでご覧いただけます。
*同書の売上げの一部を東北地方太平洋沖地震の被災地への義援金とさせていただきます。
ところで地震で崩れた建物を見て思い出すのは、平成17年の耐震偽装事件です。実は世間を大騒がせした木村建設の社長に、発覚の1年前に取材したことがあります。木村建設東京支店は市谷にありまして、古いビルの事務所然とした質素な部屋で話を聞きました。この会社は熊本県八代市の鉄骨業者だったのですが、工事現場に巨大な型枠を組み立ててそこにコンクリートを流して一気に壁を作る「大型型枠工法」を海外から導入し、ホテル建設にのりだしたとのことでした。プレハブ建築でしたら工場で壁を作ったりもするのですが、それを現場で大規模に行なってしまおうというような大胆な発想で、工期短縮につながるというのが売り物です。型枠の組み立てに、鉄骨を運ぶのに使うクレーン技術が役に立った、というようなことを言っておりました。「海外の工法では、地震大国の日本では不安がありませんか?」と尋ねたところ、「わが社は日本免震構造協会の会員でもありますから」と社長は胸を張って答えました。
取材を終えて辞去しようとした戸口で「うちの社長は高齢で、話があっちこっちに飛びますが、うまくまとめられそうですか…?」と、すまなそうな心配そうな顔の支店長(後日テレビで知りました)に尋ねられました。熊本から念願の東京進出を果たしたわけですから、話したいことはたくさんあって脱線するのも当然ですよと答えておきました。彼が扉を閉めたとき、隣の部屋がホテル開業コンサルタントの総研(総合経営研究所)であることに気づき、ああなるほど、ここと組んでいるのかと了解しました。校正のときに了解をとってその辺の情報を加筆したのですが、実はいま関係がぎくしゃくしていて…といわれ、どうやら総研から独立して事業を進めたい様子でした。
一年後、耐震偽装問題が発覚し、マスコミは木村建設と総研、ヒューザーを疑惑のトライアングルなどとおおいに書きたてておりましたが、取材時の町の工場主のような印象とのあまりの差に違和感をもちました。鉄骨を減らせばコンクリートが流しやすくなるのが動機なのだろうかとも思いましたが、そもそもこうした木村建設の独自工法にまで立ち入って言及した記事は、当初みられませんでした。結局のところ、姉歯一級建築士の単独犯行だったわけですが、それでは面白い記事にならないため、よく調べもわかりもせずに煽りたてたのでしょう。国会に証人喚問された木村社長や東京支店長が、あまりにおどおどしていて見ていて痛々しいほどでした。
それでは木村建設が、いわれなく罪を着せられた被害者であるかというとそんなことはありません。設計図に偽装が行なわれたことが内部で発覚したのちも、1カ月近く公にせず、業務を続けました。もっとも隠そうとしていたというよりは、どうにもできずにおろおろしていた、というのが実情でしょう。それでも自分たちが建設したホテルやマンションが欠陥であることを、すぐにでも公表しなければ、万が一大地震があった際に犠牲者がでてしまいます。そこに思い至らず、すぐ行動に移さなかったのが罪なのだと思います。彼らは姉歯にだまされて欠陥建築を作らさせられた被害者ではありますが、加害者の立場でもあるのです。
のちに社長も支店長も有罪とされ(建築偽装とは別件の粉飾決済や書類偽装の罪ですが)、会社は破産、解散しました。ホテルやマンションの価値が失われるなどの経済的な迷惑はかけましたが、人命が失われたわけではありません。それでも、実に厳しい社会的制裁を受ける結果となりました。
ひるがえって福島原発といえば、これはもう誰がみても明らかに特定の会社の責任で深刻な被害が生じ、経済も、健康も、生活もおびやかしています。建屋の水素爆発の発表も、放射性物質の放出データの公表も後手後手で遅れています。今は入院なすっているため実現していないのかもしれませんが、東京電力社長は必ずや国会に証人喚問され、「原発が津波に弱いことを認識しながら故意に隠していたのではないか」と、どこかのブログからにわか知識を蓄えた得意満面な議員先生に詰問される日がくるのでしょう。もしそうでないとしたら、ずいぶんと不平等な話です。
おっと、このブログのタイトル「料理本の…」、とは関係ない話が続きましたね。最後にとってつけたように地震と料理の本の話を。
戦前、日本の料理界における最高権威は石井泰次郎でした。幕府の料理方であった石井家は、宮中の料理を担当していた高橋家の資料を明治になって引き継ぎます。石井治兵衛・泰次郎親子は、日本初の料理雑誌『包丁塩梅』を立ち上げ、家に伝わる資料をもとに日本料理についてまとめた『日本料理法大全』 『日本料理法大成』を出版しています。必ずしも体系的に書かれているわけではないのでちょっと読みづらいのですが、『大全』のほうは新人物往来社から復刻されてますし、第一出版は両書を現代かなづかいに直して『日本料理法大全』 『続日本料理法大全』の2冊に再編集しています。
しかし『大成』を刊行した大正12年、石井家は膨大な資料を関東大震災で焼失してしまうのです。友人であった三村竹清の日記に、落胆する石井の様子が書かれています。ところが、いま、慶応大学には石井泰次郎旧蔵文庫(のちに料理研究家の田村魚菜が購入、寄贈したので正式名は魚菜文庫)が納められており(vol16で紹介した稀観本『豆腐百珍餘録』はこの中の一冊です)、日本有数の料理古文献所蔵数を誇っています。
 これはいったいどういうことか。どうやら石井は震災で多くの蔵書を失った後も、せっせと集めなおしたようなのです。この文庫の資料には、石井独特のクセのある字で書かれた写本もみかけます。コピーのない時代ですから、誰かから借りては写していたのでしょう。震災でもけっして心折れなかった彼の努力のおかげで、今の研究者はずいぶんと助かっているというわけです。なお、石井泰次郎は甥の清水桂一とともに昭和19年に『救荒食物かてもの』を出版しております。これは、米沢藩の上杉鷹山が天明の大飢饉を憂いて出版したサバイバル料理本をもとに活字化したものです。
これはいったいどういうことか。どうやら石井は震災で多くの蔵書を失った後も、せっせと集めなおしたようなのです。この文庫の資料には、石井独特のクセのある字で書かれた写本もみかけます。コピーのない時代ですから、誰かから借りては写していたのでしょう。震災でもけっして心折れなかった彼の努力のおかげで、今の研究者はずいぶんと助かっているというわけです。なお、石井泰次郎は甥の清水桂一とともに昭和19年に『救荒食物かてもの』を出版しております。これは、米沢藩の上杉鷹山が天明の大飢饉を憂いて出版したサバイバル料理本をもとに活字化したものです。
さあて、つまらない話はそろそろ終わりにしましょう。東京は急に暖かくなり、桜が満開です。会社のすぐ近くの上野公園は花を楽しみそぞろ歩く老若男女で大賑わい。自粛せよなどと無粋なことを言ったKY爺さんがおりますが、花見とはカラオケで騒ぎ立てる宴会だとばかり思い込んでいるのでしょうね。想像力と人を慮る心が足りなすぎです。花の下で友人と再会し、無事を祝い、静かに歓談してもよいではないですか。そもそも上から命じられては禁止であって、自粛にはなりません。
桜の季節は年に一度きり。あと何回この花を見られるかは、誰にもわかりません。パソコンを閉じて表に繰り出しませんか。東北の日本酒の1本も携えて。
投稿者 webmaster : 14:58
2011年03月02日
料理本のソムリエ [ vo.18 ]
【 vol.18】
忘れられない利き水名人
かなり期待していたんですよ…。何にですって? 『サンデー毎日』の連載「新忘れられた日本人」の「東京都水道局きっての利き水名人」の回です。2月6日号の目次にあるのをネットで発見しまして、佐野眞一先生ならではの取材力に期待して、いそいそとコンビニに向かいました。ところが開いてみれば「え…………、これだけ?」。なにしろ前半分は霞ヶ浦の上下水道問題についてでして、利き水名人の業績については1ページしか割かれていないじゃないですか。当然次号に続きがあるのだと勘違いしてしまいました。このままでは前田學さん、また忘れられちゃいますよ…。
正直な話、この雑誌連載は、宮本常一の名著『忘れられた日本人』にあやかろうとして、とかく誤解を生みやすいタイトルをつけた編集部に責任があるように思われます。内容から判断するに「佐野眞一のお蔵出し」とするのが正しい。長年の取材生活で得た情報から、過去の単行本の抜粋や紙幅の都合上取り上げなかったような小ネタに光を当てた読み物です。今回の記事を読むと、霞ヶ浦のほうが過去の取材対象で、前田さんは「新忘れられた日本人」というタイトルに合わせるために引っ張り出されたようです。だから通りいっぺんの話で、新味がないのでしょう。
そんな無理をするくらいなら、この連載で外食産業の名物社長たちを取り上げてほしいのですが、サンデー毎日さん、いかがなものでしょう。なにしろ佐野氏の単行本処女作は『戦国外食産業人物列伝』(猪瀬直樹、山根一真、小板橋二郎と組んだグループ915名義の著作は除きます)なのですから。この本は、養老乃瀧の木下藤吉郎、ロイヤルの江頭匡一、すかいらーくの茅野亮、小僧ずしの山木益次、ロッテリアの重光武雄、日本マクドナルドの藤田田、吉野家の松田瑞穂という7人の外食チェーン創業者を取り上げたルポルタージュです。誰も彼も濃いキャラクターの持ち主のうえに、ここに切り込むのが若き日のぎらぎらした目の佐野眞一。よくある社長礼讃ビジネス成功譚に終わらず、なんでもあぶりだしてやろうとぐりぐり彼らの人生観にがぶりよります。グループ915の仲間だった小板橋氏もほぼ同時期に『外食産業の経営戦略』という本を上梓しておりまして、どうやら取材データはかなり共通しているようなのですが、その利用方法が全然違うのも面白い。それぞれのタイトルが示している通り、小板橋氏の本は企業研究であるのに対し、佐野氏の関心はもっぱら企業戦略の分析よりも人間像とその動機を探り出すことにあり、その後の作風がすでにここにも表われております。
「新忘れられた日本人」の連載では、一般にもよく知られている藤田田や江頭匡一しかお蔵出しされていないようですが、むしろ残りの5人のほうが断然「忘れられた…」のタイトルにふさわしい。割愛した話題がいくらでもありそうですから、ぜひともご一考をお願いします。
ちなみに佐野先生の初期作品には『業界紙諸君!』というのもありまして、こちらもアクの強い登場人物揃い。海千山千の業界紙のオーナーや編集者を取り上げたものです。たった一人で『蒟蒻新聞』の発行に心血を注ぎ続けた村上貞一氏などは、ちょっと胸が熱くなる話でして、単行本『新忘れられた日本人』にも収録されております。こちらは『戦国外食産業…』と違って、めでたく文庫化されております。
ただ、この中にホテル業界「誌」を発行している小社と創業者の柴田良太も登場しているんですよね……。もともと柴田書店が自動車関係の出版物でスタートしたこと、江上トミ著の『私の料理』がヒットしたこと、飛行機事故で志半ばで亡くなったことなどのエピソードを交えながら、結構好意的に取り上げてくださっているのですが、内幕をよく知っているだけに残念ながらいまいち。取材されているのは当時『月刊ホテル旅館』編集長だった松坂健氏でして、読んでいると、親戚の叔父さんが街頭インタビューを受けているのに出くわしたみたいにこそばくなるという個人的な事情もありますが…。



佐野先生のほうも、ホテル業界誌の空気はそれまで取り上げてきた業界新聞のオーナーとは勝手が違って、面食らったり呆れたりしたそうです。そもそも柴田書店クラスでは、外食産業の雄や各種業界を震え上がらせるこわもてなジャーナリストたちとは格が違いますから、筆のふるい甲斐がなかったのではないですかねえ。
それでも何とか面白エピソードを入れようとして、「あそこ(柴田書店のことです)の組合は猛烈に強く、社員は好き放題だった。ヨーロッパ取材と称して、一カ月レンタカーを借り切り、毎晩三ツ星のレストランで食事をする。そんな大名取材ができたのも、ホテルや外食産業の伸びが異常だったからで、仮にほかの業界だったらとっくに潰れていたはずだ」なんていう談話が紹介されていますが、こりゃ買いかぶりすぎです。いくら組合が強くとも、取材旅行は業務ですから。こんなのほほんとした楽しいものではなかったと聞いています。
おっと、寄り道が過ぎました。涙なくしては語れないフランス長期足軽取材の真相については、いつかまた日をあらためて。今回は元東京都水道局主査、水のにおいの検査員を務めてきた前田學さんに関わる本について紹介するはずでした。
前田さんについては、水質研究の第一人者であるの小島貞男氏が『水道水をおいしく飲む』などの各著作で再三触れていまして(もっとも匿名でM氏とあるのがほとんどですが)、佐野先生の先の記事もその範疇を出るものではありません。ここにちょっとまとめてみましょう。
前田さんが水道局に入ったのは1947年で、初めから水のテイスターだったわけではありません。パリやロンドンのように水道水のテイスターを東京にも置こうということになり、試験室に勤務する人たちがかたっぱしからテストされ、その中から実力が見込まれて抜擢されました。
あるかないかの淡い“水の香り”をかぎ分ける、前田さんのたぐいまれな能力がフルに発揮されたのは62年のエピソード。地下鉄工事中に水があふれ出てきたのですが、天然の湧き水なのか水道水なのか原因がわからない。それを前田さんがにおいから朝霞浄水場から送られてきた水と判断しました。しかし工事現場は朝霞浄水場の配水地域ではありません。同浄水場の水を運ぶ本管は工事現場から30mも離れているし、まだ新しくて水もれしそうにない。それでも試しに朝霞浄水場の水を止めてみたら、湧いていた水がぴたりと止まった。はたして掘り返してみると、この水道管にひびが入っていたのが見つかったのです。
また東京、千葉、埼玉の120万世帯の水道水で異臭騒ぎがあった77年の正月。休み中の前田さんが駆り出され、においを頼りに利根川をさかのぼることになりました。100km上流の坂東橋でピークに達していて、そこから先は問題ない。そこで今度は坂東橋付近の支流をたどったところ、果たして工場の汚水池があふれていることがつきとめられました。
前田さんの能力は、資料によって違っていまして普通の人の100倍と書いてあるものもあれば、利根川にコップ1杯の排水を捨てたくらいの濃度をかぎ分けることができるというものもありまして、よくわかりませんがどちらにしてもたいしたもの。1984年に組織された旧厚生省の「おいしい水研究会」のメンバーであり、雑誌、テレビといろんなメディアに登場されていましたので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんね(ちなみに旧環境庁の「名水百選」が選ばれたのは1985年。林野庁の「水源の森百選」が1995年で旧国土庁の「水の郷百選」は1996年。縦割り行政と省庁間競争のにおいがぷんぷんします。てっきりこの辺の謎が次回の「新忘れられた…」で取り上げられると思っておったのですが)
佐野先生は「前田は、味覚や嗅覚に微妙な狂いが生じないよう、コーヒー、タバコは一切口にせず、整髪料もまったくつけたことがない」と文章を締めくくっていますが、これは誤り。前田さんはこの仕事に着く前は、タバコを吸っていましたし、整髪料も使っていたそうです。もちろん天分の才はあったのでしょうが、この能力は後天的に開発されたもので、においがかぎ分けられるようになったのは仕事について3、4年目からだとか。だから香水や酒、コーヒーの香りについては普通の人並みで、かぎわけられるのは水だけだそうです。
前田さんはどんな訓練を積んだのか。その謎の答えは、製薬会社の日本グラクソが香りに関するインタビューを集めた『鼻学―鼻の文化考』に収録されています。水の香りを認識、記憶するための第一ステップは、言葉に表して具体的にイメージすること。前田さんは、たとえば川の水全般に感じられる「植物のある場所を通った緑色感」を、四季で表現します。春はうすーい緑。夏は緑が深くなって、秋には枯れていく。さらに土、艶、潤い、もや、透明度、乾燥度といった独自の表現方法を作り出して、その水がどんな個性があるかを見(利き)定めたというのです。たとえば先の朝霞浄水場の水の特徴は甘い砂糖の香り、それも黒砂糖ではなく白砂糖、というふうに。ちなみにうすーい緑色の水だったら、たいていおいしい水なのだとか。
タネを明かすと、私が前田學さん情報に妙に詳しいのは、取材しそこねた悔しい思い出があるからでして。もう10年以上前、毎日新聞のインタビュー記事で読んだ前田さんの記憶法に感銘を受け、ソムリエの田崎真也さんとの香りを切り口にした対談を企画したのです。新聞社に電話をして連絡先を教えていただき(その時には水道局を辞めて、水質検査の会社勤務でした)、さっそく電話を入れました。ところが前田さんは会社に常駐しているわけではないとか。それでは何時、何曜日に出社するのか教えてほしい、とお願いしても「さあ、いつ来ますかねえ(笑)」という人を小馬鹿にした返事。何度電話しても適当にあしらわれ、企画書を送って、ともかく取り次いでほしいと頼んでもなしのつぶて。東京のはるか西にある会社ですから、アポなしで押しかけて交渉するにはリスキーだし…。そんなこんなで企画倒れ。
これが新聞や週刊誌なら扱いが違っていたのでしょうか。業界誌はつらいですねえ。
投稿者 webmaster : 15:30
2011年02月10日
料理本のソムリエ [ vo.17 ]
【 vol.17】
平成と大正のアーティチョーク祭り
昨年の話で恐縮ですが、仕事納めの大掃除で会社のロッカーの引き出しを整理していた時のこと。何年も前に壊れて引き出せなくなっていたのを直して、特例で使わせてもらっていたのですが、所属部署が変わったためにかねてから引き渡しを求められていたものでして。99年租借ではなかったのか…なんてこぼしつつも、不法占拠は不法占拠、引き出し2つ分の資料をすべて片付けましたとも。
そうしたら料理店のパンフレットの束(そんなものまでとっておくからいくつ引き出しがあっても足りないのだと思われるかもしれませんが、余計なお世話です)の間から、懐かしい人の手紙が出てまいりました。昨年の1月に93歳で亡くなられた、築地市場の青果卸店「大祐」の大木健二会長からです。1999年に店(市場ではコマといいます)の権利を得て2倍の広さに拡張したときのもので、ワープロではなく手書きのコピー。ちょっとうれしい発見です。ステルギジュツだのダンシャリだのといった耳障りのいいキャッチフレーズは、まとめてゴミ箱行きですね。
大木さんの功績については、料理の世界にたずさわる人たちなら、大なり小なりお聞き及びでしょう。戦後、急速に需要が伸びた西洋野菜の調達と、国内産地の開拓に努めた業界のパイオニアです。フランス料理やイタリア料理のシェフの「現地で使っているあの野菜を日本で手に入れたい」という要望に応えるべく奔走された一生でした。
手紙には行間に嬉しさがあふれている新店の案内文とともに、市況情報、そして「第3回アーティチョーク祭り」のお知らせもありました。これはイタリアのアーティチョークの収穫祭にヒントを得たもので、料理人さんや流通関係者を調理師学校に招いてアメリカ産だのイタリア産だの各種アーティチョークの食べ比べを行ない、アーティチョークの魅力についてもっと知ってもらおうという催しです。本来なら輸出元の大使館や輸入商社が行なうべき企画なのに、大木会長の個人的な熱意でもって開催しておりました。あれから10年以上経ち、イタリア産のアーティチョークもずいぶん認知が広まりましたが、陰でこうした地道な努力があったことは記憶にとどめておきたいです。

このアーティチョーク一つをとっても、かつては調べるのが大変でした。98年頃にイタリア産の輸入が始まったとき、雑誌に図鑑として写真を載せたはいいが、マモーレとコン・スピネの説明文の位置を取り違えてしまったのは苦い思い出です。
西洋野菜は料理人さんが使う通称と市場での呼び名が違うものも多く、なかなか厄介です。新人の頃にまず困ったのはエンダイブとアンディーブ。エンダイブはフランス料理店でいうシコレ・フリゼ。アンディーブはチコリとイコールだというのがなかなか覚えられず、レシピ取材のときに混乱してしまう。おまけに私が入社した頃は西洋野菜を扱った写真入りの図鑑といえば、唯一シェフシリーズの『料理野菜図鑑』があるのみでした。これは後に名著『十皿の料理』をものした大本幸子さんが中央公論社時代に編集したムックで、「素材から迫る新しい料理書」と謳っているように、現場の目線に立っておりとても役に立ちました。人づてに聞いた話では、大本さんとしてはまだまだ納得いかない部分もあったそうですが…。
実は外国の野菜や家禽・家畜に関する情報というのはあまり世に出回っておりません。世界の野草や野鳥に関する図鑑はどこの図書館でも目にするのですが、人間が作った「品種」に関する本というのは、おおむね農業や畜産業の専門家向け。さらにこうした専門家たちは国内の栽培品種や飼育品種で手一杯ですから、外国のものにはあまり詳しく言及してくれません。
それでは海外の著者の翻訳本ならどうかというと、古くは万有ガイドシリーズの『西洋野菜の百科』、のちに出版された『西洋野菜料理百科』があるくらいで、これまた数が少ない。それに日本の読者を想定して書かれていなかったり、翻訳がこなれていなかったりで、どうも隔靴掻痒な感じがありました。
 とくにイタリア関係は地方種などもあって難しく、担当者は現地から送ってもらった種苗カタログが頼りになる存在だと申しておりました。まあ、それもこれもインターネット普及前夜の話ですが。逆にネット世界は便利のようでいて情報があふれすぎており、正解に適確にたどりつくのには結構骨が折れます。百聞は一見にしかずとはよく言ったものでして、今でも現地取材にかなうものはありません。小社刊『野菜のイタリア料理』では、プーリアのトラットリーアの家庭風の野菜料理や露天の野菜売り、畑の写真などもありまして、彼の地の空気をよく伝えておりますよ。
とくにイタリア関係は地方種などもあって難しく、担当者は現地から送ってもらった種苗カタログが頼りになる存在だと申しておりました。まあ、それもこれもインターネット普及前夜の話ですが。逆にネット世界は便利のようでいて情報があふれすぎており、正解に適確にたどりつくのには結構骨が折れます。百聞は一見にしかずとはよく言ったものでして、今でも現地取材にかなうものはありません。小社刊『野菜のイタリア料理』では、プーリアのトラットリーアの家庭風の野菜料理や露天の野菜売り、畑の写真などもありまして、彼の地の空気をよく伝えておりますよ。
さて大木さんの思い出話に戻しますと、西洋野菜の特徴や来歴は本で調べることができても、日本での産地状況や実際の流通事情は会長に教えていただくのが常でした。はるか昔、会長がムスクランとはどんなものか調べていた時に(ムスクランはサラダ用の葉物のミックスなので、事情を知らないとなんだかヌエみたいで正体がわかりづらい代物なのです)、『月刊専門料理』の小さな記事が頼りになったとかで、後々まで恩義に感じてくださっていました。新人編集者のわれわれも可愛がってもらい、築地場内の寿司店の中のどの職人さんの腕がよいか教わったり…。会長はイタリア料理のシェフと現地に渡って市場を回り、プンタレッレ(うにょうにょ伸びあがったような妙な形のイタリア野菜でして、一般には複数形のプンタレッラとか略してプンタとか呼ばれています)やペコリーノ(羊乳で作る固いチーズです)と一緒に生のまま食べるソラマメなど、ほれ込んだ野菜を日本に導入すると、真っ先に編集部に連絡してくださいました。

 そんな大木会長なのですが、取材していて「いいのかなあ」と思ったのがキクイモのこと。ショウガのような形の根菜なのですが、会長はこれを「トッピーナンポ」と呼ぶのです。フランス語でキクイモを指すトピナンブールがなまったようなのですが(ちなみに英語ではエルサレムアーティチョーク。なんでまたこんな妙な名前がついたかは『西洋野菜料理百科』をご覧ください)、業界のトップリーダーがこんな名前で呼ぶとそれが広まってしまうぞ、と内心危惧したものです。大木会長も野菜流通のプロとはいえ育種の専門家ではないので、産地がつけた変な野菜名を踏襲したり、誤解されている点がありまして(アスペルジュ・ソバージュをアスパラガスの野生種とするとか)、老婆心ながら心配しておりました。
そんな大木会長なのですが、取材していて「いいのかなあ」と思ったのがキクイモのこと。ショウガのような形の根菜なのですが、会長はこれを「トッピーナンポ」と呼ぶのです。フランス語でキクイモを指すトピナンブールがなまったようなのですが(ちなみに英語ではエルサレムアーティチョーク。なんでまたこんな妙な名前がついたかは『西洋野菜料理百科』をご覧ください)、業界のトップリーダーがこんな名前で呼ぶとそれが広まってしまうぞ、と内心危惧したものです。大木会長も野菜流通のプロとはいえ育種の専門家ではないので、産地がつけた変な野菜名を踏襲したり、誤解されている点がありまして(アスペルジュ・ソバージュをアスパラガスの野生種とするとか)、老婆心ながら心配しておりました。
ところがこのトッピーナンポ、大木会長が間違って覚えていたのではなく、市場でずっと古くから使われていた通称なんですね。その著作『洋菜ものがたり』によると、戦時中には食糧増産のために大々的に作られていたとかで、戦中派の会長としては特別な思い入れがあったようです。ちなみにこの本は、大木会長の野菜の輸入と産地化の苦闘がわかる貴重な一冊なのですが、市況などを扱う日本デシマルという特殊な会社から出版されたため、一般書店には流通せず、あまり人の目に触れなかったのが残念です。
実は冒頭に述べた仕事納めの後のこと。平日の午後が丸まる空くなんて貴重な機会ですから、さっそく図書館へ行って大正時代の婦人雑誌を読んでいたら、思いがけずキクイモにぶつかりました。医史学者として名高い富士川游が、糖尿病にきく野菜としてドイツから持ち帰ったキクイモを、俳人の岡野知十に譲っていたのです。ところが知十がフランス料理店主の奥田駒蔵(vol12参照)にたずねたところ、すでに東京の野菜市場ではキクイモを扱っていて(ジャガイモより少し高いくらい)、「トッピ」の略語で通じるとか。「私かたなどでも気取ってトッピを用いましても、そうとは知らずにやっぱり馬鈴薯で食べられてしまいます。あなたもそうであったのでしょう」と苦笑されたそうです。本格志向の料理人さんの思い入れは、今も昔もなかなかお客さんには伝わらないものですねえ。
富士川游はキクイモの普及に熱心でして、鎌倉の自宅で栽培し、知十のような友人に配ったり、キクイモ試食会を開いてその普及に努めていたようです。いわば大正時代のエルサレムアーティチョーク祭り。ドイツ文学者にして江戸漢詩にも造詣の深い、息子の富士川英郎著『読書好日』によると、大正4年には上野不忍池近くの料理店でキクイモ料理2品、卵料理2品の試食会を開いたとあります。富士川游は医学者仲間たちを呼んで、こうした催しをたびたび実施しており、田端の「天然自笑軒」(芥川龍之介の友人の店です)で本家アーティチョークの試食会も開いております。
彼が医学博士号(今の博士号とは格が一桁も二桁も違います)を授与されたときの記念パーティの席では、キクイモの薄切りを二杯酢に漬けて香の物代わりにしてみたエピソードを披露したそうで、かなり日常的にキクイモを楽しんでいたことがわかります。一方岡野知十はというと、ヘットや胡麻油で素揚げにしたり、試食会用に寒天で寄せたお菓子に仕立ててもらったり…。知十は奥さんが料理研究家ということもあって、文学界きっての料理通でもありました(ちなみにどの魯山人本もご関心がないようですが、美食倶楽部の発起人の1人です)。家族で仲良く発行していたタブロイド版の『料理研究』という雑誌は、フランス文学者である息子の岡野馨がフランスの文献を翻訳紹介していたというからかなり本格的です。ちなみに、ここに富士川游が投稿したキクイモの紹介文は『富士川游全集』で読むことができます。
なお富士川英郎の手元には5号分の『料理研究』が残っていたそうで、87年刊行の『読書好日』には写真まで載っております。ですが、2006年に神奈川近代文学館に寄贈された富士川英郎の資料や蔵書中には現物が見当たりません。京都大学の富士川文庫は古医書のコレクションで、東大の知十文庫は江戸時代の俳書で、それぞれ名高いのですが、もちろん『料理研究』は含まれていません。料理雑誌なんて、所詮まっさきにダンシャリされる対象ですからねえ。どなたかのロッカーの底にひっそりと眠ってはいないものでしょうか。
投稿者 webmaster : 10:21
2011年01月25日
料理本のソムリエ [ vo.16 ]
【 vol.16】
日本に飛び火した豆腐問題
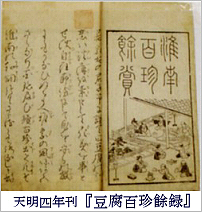 前回の記事をアップしたちょうどその日、デパートの古書市の出品目録を眺めておりましたら、超貴重本と紹介したばかりの『豆腐百珍餘録』が載っており、仰天しました。私の知る限り、この本のオリジナルは慶応大学にしかありません。あわてて注文を入れたのですが、これを書いている段階では抽選結果はまだ不明です。落胆のあまり旅に出てしまって次回はお休みするかもしれません。
前回の記事をアップしたちょうどその日、デパートの古書市の出品目録を眺めておりましたら、超貴重本と紹介したばかりの『豆腐百珍餘録』が載っており、仰天しました。私の知る限り、この本のオリジナルは慶応大学にしかありません。あわてて注文を入れたのですが、これを書いている段階では抽選結果はまだ不明です。落胆のあまり旅に出てしまって次回はお休みするかもしれません。
そわそわしつつ『料理文献解題』や『江戸時代料理本集成』の解説をもう一度よく読み返したら、この本は『豆腐百珍』の出版元が購版、つまり『豆華集』の版元から購入したとありました。vol.1で申し上げた版木を同業者に売り渡すというケースでして、江戸と大阪で対立していたわけではなかったのですね。昔の出版人も結構紳士的だったということで、ここに訂正いたします。
そんなこんなでまた豆腐の話です。
漢字の「豆腐」なんですが、最近は「豆富」という書き方も目にしますね。食品なのに「腐」という字はどうも、という心理によるようです。「そもそも豆が腐ったのなら納豆じゃないか」というのは昔からよく聞く異議申し立てですが、「いやいや、腐という字には、集める、柔らかいという意味があるんです」と説明されているものをみかけます。
ところが清の皇帝が作った国家公認(何しろこれを批判した本は禁書、著者は死刑になったくらいです)の『康煕字典』にも、全15巻で世界最大を誇る諸橋『大漢和辞典』にも、「腐」の字の意味を集めるだの柔らかいだのとする説明が見当たらないんですよ。腐という字が気になるのは中国の人も同じなようで、元代には「菽乳」(菽は豆の意味です)という別名も考え出されております。
ちなみに豆腐は紀元前2世紀に淮南王、劉安が発明したことになっておりますが、これまたまゆつばものでして、それから1000年間、文献に豆腐の二文字がまったく登場しません。豆腐の歴史の研究は篠田統先生が権威でして、日本風俗史学会誌に1968年に発表された「豆腐考」で縦横無尽に史料を駆使して中国と日本の豆腐について考証されています(雑誌を探すのは大変ですが、さいわい『全集日本の食文化』3巻に収められております)。それによると、豆腐なる食品が初めて登場した文献は北宋の時代の『清異録』。おまけに南宋や元の文献によると四川省では別名「黎其」「黎祁」「来其」とも呼ばれておりました。表記法がいくつもあるだなんて、なんだか外来語の当て字っぽいですよねえ。
そこで篠田先生が主張するのは、豆腐は唐の中期以降に乳製品作りにヒントを得て生まれたものとする遊牧民族由来説です。当時、乳腐と呼ばれる食品がありまして(こちらは隋の料理書に載っており、唐の歴史書にも登場します)、その豆版ではないかというわけです。唐の頃の乳腐の作り方は不明ですが、明代の『本草綱目』によると漉して煮立てた牛乳に、酢を入れて沈殿させ、漉し集めて汁を絞って固めたものとありまして、カッテージチーズみたいです。豆腐の場合は、加熱した豆乳ににがり(塩化マグネシウム)や石膏(硫酸カルシウム)を凝集剤として加えて作ります。チーズよりも固まるのがずっと早くて水きりしなくても作れないことはないのですが、固めの木綿豆腐であれば穴開き容器に詰めて「ゆ(上澄み)」を除きます。チーズと豆腐の作り方は確かによく似ています。
ところがそれに異を唱えたのが、臼研究の泰斗、故・三輪茂雄先生。粉体工学に基づいて科学的に臼を研究されていた三輪先生は、98年10月に調査団を組んで安徽省淮南を訪問し、博物館で漢代の明器(墓に納められていたミニチュア)の構造を分析した結果、それを大豆を水挽きするのに使った石臼と判定しました。さらに中国人研究者に『文物考古三十年』という文献に漢代の墓に豆腐作りプロセスを描いた石刻画があると教えられ、「淮南起源俗説論は完全に否定された」と『粉と臼』で述べておられます。のちに法政大出版局の『粉』では、滋賀県立大の菅谷文則先生から提供を受けたとし、くだんの石刻画のイラストを掲げております。
しかし、これにはどうやら大きな誤解と、日本人の預かり知らぬ問題があるのです。三輪先生はすたれつつあった石臼製粉の復権に力を尽くした蕎麦界の恩人。柴田書店の『そばうどん』に連載を持ち、著書『石臼の謎』では石臼の製作方法を紹介され、これを頼りに石臼を自作する蕎麦屋さんもいらっしゃいます。摩擦熱の少ない石臼で大豆を挽くことで、蕎麦と同様によりおいしい豆腐が作れることを熱く提唱されてきました。しかしそんな大恩があるからこそ、三輪先生の勘違いがこれ以上広まる前に訂正しておかねばならないと思いまして、ちょっと長いのですが説明いたします。


この石刻画が見つかったのは河南省密県打虎亭にある後漢時代の豪族の墓です。邸宅を模した造りで、2号墓は日本の古墳のように彩色画で、1号墓のほうは石版に薄く彫った線画(画像石といいます)で内壁が豪華に飾られておりました。1960年に発見第一報が、72年と87年にはもっと詳しい発掘報告が中国の考古学雑誌に載り、多くの画像石が紹介されたのですが、豆腐作りを描いた肝心の図についてはまったく触れられておりません。
三輪先生が証拠文献とする『文物考古三十年』は、正しくは『文物考古工作三十年』でして、刊行の翌々年の81年に平凡社から『中国考古学三十年』のタイトルで翻訳も出ております。打虎亭漢墓の紹介文では、「租税を取り立てる状況を描いた画像石は、漢末の地主階級が農民に対して地租を過酷に搾取したことの縮図である。百戯の壁画も彼らが宴会に遊びたわむれている腐りきった生活を生き生きと描いている。打虎亭第一号墓には豆腐工房を石刻しているが、この一幅の絵は豆類に加工して、副食品をつくった生産の絵柄であり、中国の豆腐づくりが後漢末期より遅れることのないことが証明された」とあります。いやあ、時代を感じさせますねえ。肝心の画像石は写真もイラストも載っておらず、豆腐作りと断じた根拠は不明です。この本は49年の建国から79年までの輝かしい考古発見を各省ごとにまとめたものでして、人民中国の学問の大躍進を称揚するのが目的ですから、少しハッタリ気味でもおかしくありません。
 この遺跡の全貌は、93年に河南省文物研究所から出版された『密県打虎亭漢墓』でようやく明らかになりました。問題の画像石は東側に張り出た小部屋の南壁西側にあり、高さ95cm横120cm。
この遺跡の全貌は、93年に河南省文物研究所から出版された『密県打虎亭漢墓』でようやく明らかになりました。問題の画像石は東側に張り出た小部屋の南壁西側にあり、高さ95cm横120cm。
写真をHPに転載するのは著作権の問題があるかもしれないので、私が線をなぞってイラスト(左)におこしてみました。

帽子をかぶった人物たちが何かを漉したり、かき混ぜたり、四角い箱に重石をして絞っている光景が描かれているようですが、表面が何箇所もはがれていてわかりづらい。石臼とされる絵には挽き手(にぎり)が見えないうえ、豆腐作りに欠かせない加熱シーンが欠けているという致命的な欠陥があります。また工程図の上には壺の絵がたくさん描かれているのですが、これらが豆腐作りと結びつきません。同じ南壁の東側にはもっと保存状態のよい、鳥をさばいたり調理する光景を描いた画像石がありまして、対になると考えると酒を仕込むシーンのほうがふさわしいようにも思えます。
三輪先生が『粉』で紹介したイラストを見たことのある人は、「おやおや、ご隠居さんたら絵が下手くそなうえに老眼かい?」と思われるかもしれませんね。こちらでは臼の形がしっかり描かれておりますから。実は『粉』のイラストは、中国の江西省で『農業考古』という雑誌の編集主任を務める陳文華という学者が91年1月号で発表したものでして、『文物考古工作三十年』を見ていない三輪先生はすっかり勘違いされたようです。
陳先生は慌てて撮影したボケ気味の写真から壁画の下一段分だけを取り出して描きおこしたものの、つい微妙に自説に都合のよい方向へ修正してしまいました。初めから豆腐の図であると思い込んで調査したため、先入観が働いてしまったんですね。93年に鮮明な写真が公開されたため、孫機という学者が醸造シーンと推定し、「豆腐問題」というタイトルの新説を提出。一般新聞にまで取り上げられてしまいました。
そこで陳先生は同じ『農業考古』の98年3月号誌上で、これまでの経緯と一部描き直したイラストを提示し、釈明したうえで反論します。すると孫先生は考古学の新聞にて再反論、陳先生は雑誌でまた反論。なあなあですまさずに反論を正面から受け止める姿勢はあっぱれですが、中国では学問の世界でも面子がからむと冷静さを欠き、泥沼化する傾向があります。また淮南では豆腐村という施設を作って毎年9月には豆腐祭りを開き、豆腐発祥の地で売り出しており、今さら引っ込みがつきません。事情を知らぬ日本人学者は、「海外でも支持されている」というふうに、それと気づかないまま自説補強のお先棒を担がされてしまうというわけです。この画像石の解釈は、最新の技術で撮影するなどしてさらに慎重に検討する必要があるでしょう。
百歩譲って漢の時代で豆腐が作られていたとしても、それが淮南に起源を持つとは限りません(密県は淮南の近くではありますが、それでも400kmは離れています)。またなぜ「腐」という字が使われるのか、なぜ1000年間も文献に現われなかったかは謎のままです。vol.2で述べたように中国人は料理や技術を書き残すのに熱心ではありませんでしたから、豆腐料理や豆腐作りの史料が見当たらないのは仕方ないにせよ、農業書や博物書、辞書なら残っています。これらの大豆についての説明文中に、ひと言「みなさんご存じの豆腐の材料です」とでも書かれてよさそうなものです。
篠田先生は黎其(れいき)は西域の言葉か梵語(インドの言葉)の可能性があると述べております。また6世紀に書かれた(現在伝わっているのは宋代に改訂増補された版ですが)『玉篇』という字書では、「酉支酉氏」(入力できないのでへんとつくりに分解しましたが、とりへんに支と氏の漢字2文字に見立ててください。発音は篠田先生によれば「りき」です)を「乳腐」と説明しているのにも着目されています。豆腐は乳製品大国でベジタリアンも多いインドから、仏教文化とともに中国にもたらされ、寺という特殊な世界に伝えられてきたのではないでしょうか。中国に伝わる膨大な仏典の中に、別の名前で素知らぬ顔で豆腐が隠れているのかもしれません。
豆腐がチーズの大豆版であるなら、かびをつけて熟成させるのも自然な流れ。麹を使って作る沖縄の「豆腐よう」や中国の「腐乳」の存在も納得できます。なお豆腐百珍の撰にはもれたものの、わが邦にも、ひと口大の「酢豆腐」なる発酵食品がありまして…。
おっとご隠居は長話がすぎますね。続きはご自身で調べてみてください。
投稿者 webmaster : 15:45
2011年01月13日
料理本のソムリエ [ vo.15 ]
【 vol.15】
素材と100の日本料理
前回、前々回はどうも説教くさかったですね。以前このブログを読んで、落語のご隠居みたいという感想をくださった方がいらっしゃいました。本質をずばりと突いていて、実に言い得て妙と思わず膝を叩きましたですよ。小難しくて長くてくどいうえに、昔話と説教がミックスされている。そのうえよく知らないことでもさも知っているかのよう。素人が本で読んだ手品のタネを自慢げに語っているみたいです。
そんな自覚があるのに、強情で聞き分けのないのもご隠居の特徴。反省せずに今年も続ける所存ですので、よろしくお願いいたします。
さて新年1回目の更新分ですが、ご隠居らしく江戸時代の料理本の話題から。前回紹介した『万宝料理秘密箱』ですが、別名を『玉子百珍』とも申します。この本には鶏料理や川魚料理も登場するのですが、なにぶん100以上の玉子料理を扱っているため、後に再版する際にこのサブタイトルがつけられたのです。この「○○百珍」という書名はどこかで目にされたことがあるのでは? ○○という素材を使った100種類のレシピ集というスタイルをとるこれらの本は「百珍物」とも呼ばれるのですが、その最初の本が天明2(1782)年に出版された『豆腐百珍』です。著者は大阪の篆刻家、曾根学川。100通りもの豆腐のレシピを尋常品、通品、佳品、奇品、妙品、絶品の6種類に分類するというユニークな構成が評判を博し、翌年には同じ著者により続編の『豆腐百珍続編』が、翌々年には著者とは無関係の江戸の版元から『豆華集』が出版されました。二匹め、三匹めのドジョウを狙う出版界の体質は今も昔も変わりませんね。ちなみに便乗本の『豆華集』の出現に『豆腐百珍』の出版元は黙っておりません。序文を除いて曾根先生にこれまでの経緯を解説してもらい、『豆腐百珍余録』とタイトルのみを変えてそのままの内容で出版します。本家にコピーし返されては、抗議もできなかったでしょう。もっとも、さすがに売れなかったらしく、今や『豆華集』『豆腐百珍余録』のどちらも1、2冊しか所蔵が知られていない超貴重書であります。
一方豆腐モノの本が売れなくなったくらいでくじける出版界ではありませんぞ。ならばと『鯛百珍料理秘密箱』に『海鰻(はも)百珍』、『蒟蒻(こんにゃく)百珍』に『甘藷(いも)百珍』なるものまで次々と類似書が出版されました。曾根学川は、今の世でも通用する「素材別レシピ集」というジャンルの確立者として出版界の殿堂入りは間違いありません。ちなみに原田信男教授の『料理百珍集』は、現代語訳ではありませんが、これら江戸時代の百珍物を7種類集めて活字にしてあり便利です。

 『豆腐百珍』と『豆腐百珍続編』は私どもの『とうふの本』でも活字化されていますが、今は絶版。尋常品はともかく、絶品の豆腐料理って何なのかちょっと気になりますよね。『万宝料理秘密箱』と同様に教育社新書から現代語訳が、さらに新潮社のとんぼの本シリーズからはカラーの写真入り『豆腐百珍』も出ていますので、そちらをご覧になるとよいでしょう。後者は「なべや」の福田浩氏が100品すべての再現にトライ。試食の感想つきという凝りようです。
『豆腐百珍』と『豆腐百珍続編』は私どもの『とうふの本』でも活字化されていますが、今は絶版。尋常品はともかく、絶品の豆腐料理って何なのかちょっと気になりますよね。『万宝料理秘密箱』と同様に教育社新書から現代語訳が、さらに新潮社のとんぼの本シリーズからはカラーの写真入り『豆腐百珍』も出ていますので、そちらをご覧になるとよいでしょう。後者は「なべや」の福田浩氏が100品すべての再現にトライ。試食の感想つきという凝りようです。
さて『豆華集』では失敗したものの、豆腐はいろんな展開が可能な素材ですから、明治以降も豆腐百珍の衣鉢を継ぐ続編は絶えませんでした。1935年には精進料理の「白雲庵」の林春隆氏が『新撰豆腐百珍』(のちに中公文庫に入りました)を、62年には「辻留」の辻嘉一氏が『現代豆腐百珍』を出版しております。

 小社でも『豆腐100珍NOW』という単行本を出しておりました。こちらは先の福田浩氏が和風、山本豊氏が中華風、さらに料理研究家の大原照子氏が洋風豆腐料理を担当。ただし82年刊ですから、ナウいかどうかはご容赦のほどを。最新の本は96年の礒本忠義氏による『豆腐料理』ですが、こちらは豆腐だけでなく、さらにおからや豆乳、湯葉や高野豆腐などを使った料理も登場しまして150種以上。昨今の読者の方々は豆腐ばかりで100種類どまりでは、なかなか満足していただけませんからね。
小社でも『豆腐100珍NOW』という単行本を出しておりました。こちらは先の福田浩氏が和風、山本豊氏が中華風、さらに料理研究家の大原照子氏が洋風豆腐料理を担当。ただし82年刊ですから、ナウいかどうかはご容赦のほどを。最新の本は96年の礒本忠義氏による『豆腐料理』ですが、こちらは豆腐だけでなく、さらにおからや豆乳、湯葉や高野豆腐などを使った料理も登場しまして150種以上。昨今の読者の方々は豆腐ばかりで100種類どまりでは、なかなか満足していただけませんからね。
ところで豆腐は水のよい土地で作るに限るとよくいいます。だから京都の豆腐はおいしいのだ、とも。確かにたっぷり水を含んでおりますから、水のよしあしは味を左右するのかもしれません。
ところが見落とされがちなのは、豆腐を浮かべる水なんです。以前雑誌の水の特集企画で、豆腐にどんな影響が出るか、面白半分に実験したことがあります。エントリーしたのは、ビルの貯水槽からこんこんと湧き出る「柴田書店の“おいしい水”」とわざわざ徳島から運んだ井戸水、アルカリイオン水、軟水系と硬水系の2種類のミネラルウォーターでした。これらの水を張った容器に、町の豆腐屋で買った平凡豆腐とデパートで買った富山産大豆とにがり製のエリート豆腐をそれぞれ浸けたのち、3時間後に一度新しい水に取り替えて、さらにひと晩置いてから試食したのです。
ビルの貯め水に浸かった豆腐はたとえ生まれはエリートであっても、氏より育ち、悪い環境に染まって嫌なにおいがついてしまいました。せっかく取り寄せた井戸水も、汲んでから時間が経っておりますし、輸送に使ったポリタンクのにおいもあり、あまり結果ははかばかしくありません。その点、ミネラルウォーターは効果的だったのですが、両者で味がまったく違うのです。軟水系のほうは、豆腐の持ち味といえば聞こえはよいのですが、酸味というか大豆の渋みというか、ちょっと嫌な味も引き出してしまう。ところが硬水系のほうはミネラル多めなのが効を奏したのか、なんだか胡麻豆腐を思わせるようなクリーミーな感じになっていました。アルカリイオン水のほうもそうした変化が若干ありましたが、とにかく硬水の効果には驚かされました。大豆の香りも甘みも引き出され、普通の豆腐と高級豆腐の差などは吹き飛んでしまうほどでした。
まあ、それ以上は追求しなかったので、その時たまたまだったのか、何かミネラル分が原因だったのか(アルカリイオン水の原理は電気分解で人工的にアルカリ基のミネラルを添加することにありますから)、詳しくはわかりません。ただ、簡単にできる実験なので、ご関心の向きはお試しあれ。もしかしたら豆腐と水のベストな組み合わせが見つかるかもしれませんよ。漫画の『美味しんぼ』の第1話で山岡先生は見事豆腐を食べ分けておりますが、こうした姑息なトリックを用いたならば、どんな結果になったことやら。
 この漫画では豆腐に旅をさせるな、というキャッチフレーズも紹介しておりますが、連載が始まった80年代と違って、豆腐の作り方も多様化しております。以前は豆腐容器に1丁ずつ流し込んで作る「充填豆腐」は、水っぽくてくずれやすいのをごまかすため、なんて言われていましたが、今の製品は充填豆腐でも結構しっかり固く作っています。充填するのは機械のラインの衛生環境を保ち、保存性を高めるほうに目的があるようでして、確かに最近のスーパーの豆腐は日持ちがよいですよね。
この漫画では豆腐に旅をさせるな、というキャッチフレーズも紹介しておりますが、連載が始まった80年代と違って、豆腐の作り方も多様化しております。以前は豆腐容器に1丁ずつ流し込んで作る「充填豆腐」は、水っぽくてくずれやすいのをごまかすため、なんて言われていましたが、今の製品は充填豆腐でも結構しっかり固く作っています。充填するのは機械のラインの衛生環境を保ち、保存性を高めるほうに目的があるようでして、確かに最近のスーパーの豆腐は日持ちがよいですよね。
また小さなザルに詰めた「ざる豆腐」は水切りがよいせいか、これまた結構輸送に耐えます。おかげで京都だの大分だのから長旅してきた豆腐を、東京でも見かけるようになりました。ただし、芽胞という状態で眠っている細菌は加熱に強いので、豆腐作りの加熱工程くらいでは完全に殺菌できませんから、どうしたって缶詰のように長くは持ちませんが。
まあ実を言いますと、どんな名水から作った豆腐でも、旅をしない新鮮な豆腐でも、肝心なのは料理の腕。先の『新撰豆腐百珍』では、「茶と豆腐は水質よりも煮方の巧拙に拠るところ多し」と喝破しております。素材自慢よりもまずは基本の調理をしっかりと、ということですね。
投稿者 webmaster : 18:24
2010年12月22日
料理本のソムリエ [ vo.14 ]
【 vol.14 】
黄身返し卵にトライ!!
今回もエル・ブジつながりの話です。フェランの料理は意表をつくファーストインパクトに重きをおいておりますが、これってちょっと科学マジックに似ていますね。この素材はこういうふうに調理するのが当たり前、この料理は本来こういうもの、といった常識が覆されるところに面白みがあります。
ただし、マジックショーを楽しむには観客は演者の指示に従わねばなりません(トランプの中から1枚選んでほしいと言われたのに、むんずと3枚つかみ取ったりしたら、ステージが台無しになりますよね)。エル・ブジの料理も同様で、食べるのに店が指定する作法や手順を踏まねばならないものがあります。たとえば前回紹介した二層式のグリーンピースのスープは、冷めないうちに一気に飲んでもらわないと効果が半減します。ですが、店側から指示されるのがわずらわしい、お仕着せだと感じる人には面白くないでしょう。
また世の中には、マジックを娯楽として楽しめない人たちもいます。驚かされるのを素直に喜べない、「だまされた、くやしーい」と感じる性分の人です。タネを教えるまでは絶対に解放してくれなかったり…。常に自分が優位に立っていないと気がすまないんでしょうか。実は食通ぶっている自慢しいの料理評論家やブロガーにはこのタイプの人たちが結構います(その証拠に、彼らは自分だけが知っている“隠れた名店”を紹介するのが大好きですし、自分の知らない特別なサービスを受けている客がいると思い込んだら敵意を丸出しにしたりもします)。
さらに覆そうにも、常識を持ち合わせていないと覆しようがありません。「この料理は当然こういう味のはずだ…」という知識のある人ほど意表をつかれるのです。エル・ブジのスペシャリテの一つにカリフラワーを細かくきざんでまるでクスクスのように仕立てた料理がありますが、カリフラワーもクスクスも見たことも食べたこともない人にとっては、単なる未知の料理でしかありません。
だからエル・ブジの料理は誰にでもお勧めできるものではありません。ところが日本のマスコミは、世界で一番予約の難しい店、世界最高の料理(最先端と最高は別のものなのに)などといった浅薄な取り上げ方をしました。マジックショーを見る前に半可通の第三者からタネ明かしされても、そんなに楽しいものではないと思うのですが…。
エル・ブジ風の料理を作る人たちも増えましたが、同じタネで見よう見まねで演じられても、同じ感動を与えることができるとは限りません。すぐれたマジシャンはタネが奇想天外なわけでも手先がずば抜けて器用なわけでもなく、話術や誘導の仕方にこそ本領があります。エル・ブジの料理も、その魅力を理解して、そこを自分なりにお客に伝えようとしないとただの素人芸に終わってしまいます。忘年会の隠し芸の手品がいまいちつまらないのは、演者がつい自慢げに見せてしまうから。エンターテイメントとして観客を楽しませようという配慮が欠けているのが原因です。「流行のエル・ブジ風です! どうです、すごいでしょう?」と得意満面で説明されては、お客さんは鼻白んでしまいます。
 そもそもサプライズ料理や見立て料理であれば、スペインくんだりに範を求めようとせずとも、わが国には江戸時代からの伝統があります。その筆頭が「黄身返し玉子」。黄身と白身の位置関係が反転していて、黄身が外側に、白身が芯に詰まっているという世にも不思議な玉子料理です。天明5(1785)年の『万宝料理秘密箱』という料理書に出ておりまして、料理研究家の奧村彪生氏が再現してみせたレシピ本で見ることができます。奥村氏は篠田統先生(vol.3参照)が主宰した料理文献の講読会のメンバーであり、講読会ではこの本を読み解きながら料理の再現にも努めてきたそうで、一部は現代人向けにアレンジするなどの工夫もされています。卵白に金箔を加えて湯煎で焼いたり、ゆで玉子を四角く整形してみたり、紫蘇に漬けてみたりというふうに、現代人には思いもつかないようなアイデアが詰まっており、興味深いです。ただしこのレシピ本のキャッチフレーズは「いきなり差がつく自慢できる111のレシピ集」なんですが、世にも珍しい江戸の玉子料理が作れても自慢はほどほどにしたほうが賢明だと思いますよ。
そもそもサプライズ料理や見立て料理であれば、スペインくんだりに範を求めようとせずとも、わが国には江戸時代からの伝統があります。その筆頭が「黄身返し玉子」。黄身と白身の位置関係が反転していて、黄身が外側に、白身が芯に詰まっているという世にも不思議な玉子料理です。天明5(1785)年の『万宝料理秘密箱』という料理書に出ておりまして、料理研究家の奧村彪生氏が再現してみせたレシピ本で見ることができます。奥村氏は篠田統先生(vol.3参照)が主宰した料理文献の講読会のメンバーであり、講読会ではこの本を読み解きながら料理の再現にも努めてきたそうで、一部は現代人向けにアレンジするなどの工夫もされています。卵白に金箔を加えて湯煎で焼いたり、ゆで玉子を四角く整形してみたり、紫蘇に漬けてみたりというふうに、現代人には思いもつかないようなアイデアが詰まっており、興味深いです。ただしこのレシピ本のキャッチフレーズは「いきなり差がつく自慢できる111のレシピ集」なんですが、世にも珍しい江戸の玉子料理が作れても自慢はほどほどにしたほうが賢明だと思いますよ。
さて黄身返し玉子の製法ですが、万宝料理秘密箱によると、殻に針で穴を開け、糠味噌に3日間ほど漬けてからゆでると、黄身と白身がひっくり返るというのです。しかし実際にはこの方法ではうまくいきません。そのため、ハッタリの類として片付けられていました。
ところが登場から200年余り経った平成の世になって、黄身返し玉子を再現することに、京都女子大学の八田一郎先生が見事成功しました。当時の卵は有精卵だったので、孵化が始まって3日から4日目頃には卵黄が水っぽい状態になる一方で、卵白のほうは粘度が高まります。そのためショックを与えて卵黄を崩してやれば、卵黄が卵白をくるんだ状態が作れることがわかったのです。
この成功をうけてテレビ番組でも黄身返し卵が取り上げられ、無精卵を使った黄身返し卵の再現法も紹介されています。『続々伊東家の食卓裏ワザ大全集21世紀版』に収録されているのは、卵に小さな穴を開けて、そこから針金を突っ込んで卵黄を強引に崩してしまうという方法です。ところがこの方法も難しいらしく、慣れた人でも2回に1回くらいしかうまくいかないとか。
のちに八田先生は、卵をぶんぶんゴマ(子供の頃にボタンで作ったアレです)の原理で激しく回転させて卵黄を崩すという方法を開発しました(本は見当たりませんでしたが、日清食品のインスタントラーメン発明記念館のHPで詳しく紹介されています)。以前伊東家の方法ではうまく作れず、あきらめていた私ですが、早速これに飛びついてみました。その成果が下の写真。回しすぎて殻の中でとき卵状態になったらしく、「黄身だけ玉子」になってしまいました。まあ、これはこれでぷりぷりした食感で、面白い味ではありましたが(負け惜しみ)。その後、再トライしてみたものの、殻が破れて爆発したり・・・。
一番右の物が比較的うまくいきましたが、黄身返し玉子の道は遠く険しいです。

それにしても『万宝料理秘密箱』ってタイトルからして手品の本みたいですよね。著者もそれを意識していたのかもしれません。アマチュアマジシャンにしてミステリー作家だった故・泡坂妻夫氏の『大江戸奇術考』に「奇術と料理」という1章がありまして、そこで料理と手品の近縁関係について解説されております。江戸の末に刊行された『料理こんだて手品伝授』という本にも黄身返し玉子が紹介されているのだそうですが、これは既存の料理本2種と手品の解説本2種を勝手に組み合わせたという、ずいぶん安直な本なのだとか。作者にしてみれば料理のコツも手品のタネ明かしも、読者ニーズは同じと思ったのでしょうね。テレビの裏ワザ番組の人気の高さに通じるものがあるような気もいたします。
 そういえば江戸時代きっての名料亭である「八百善」では、鉢植えの茄子を枝につけたまま漬物にしてみせたという話もあります。また『万宝料理秘密箱』と同じ天明5年に出版された『大根料理秘伝抄』という本に紹介されている「輪違大根」は、鎖のような形に切り出されておりまして(左のイラストの要領です)まるで曲芸のようです(そういえば、以前これの作り方について、テレビ局から会社に問合せがきたことがありました)。こうしたちょっとした不思議は、宴席を盛り上げるいいスパイスになったことでしょう。ただし鉢植えナスの漬物も、輪違大根も、食べておいしいとは思えません。あくまでも余興にすぎず、ここに重きをおいては本末転倒です。
そういえば江戸時代きっての名料亭である「八百善」では、鉢植えの茄子を枝につけたまま漬物にしてみせたという話もあります。また『万宝料理秘密箱』と同じ天明5年に出版された『大根料理秘伝抄』という本に紹介されている「輪違大根」は、鎖のような形に切り出されておりまして(左のイラストの要領です)まるで曲芸のようです(そういえば、以前これの作り方について、テレビ局から会社に問合せがきたことがありました)。こうしたちょっとした不思議は、宴席を盛り上げるいいスパイスになったことでしょう。ただし鉢植えナスの漬物も、輪違大根も、食べておいしいとは思えません。あくまでも余興にすぎず、ここに重きをおいては本末転倒です。
エル・ブジの料理を取り上げるマスコミの一部は、こうした手品的料理とごっちゃにしているような気もします。彼の本質は今までにない方法で、新しい触感や味を生み出す試みのほうにあると思うのですが。
投稿者 webmaster : 18:12
2010年12月15日
料理本のソムリエ [ vo.13 ]
【 vol.13 】
レシピを公表する勇気と侠気
前回紹介した五色の酒ですが、フェラン・アドリアのスペシャリテである「ミント風味のグリーンピースのスープ」みたいだ…と思われた方がいるかもしれません。この料理は冷たいスープの上に熱いスープをそっと流し、2層の状態にしたもの。それと知らずにくいっと一気に飲み干すと、湯気を立てていた熱いスープのはずが途中で冷たいスープに変わる。飲み始めと飲み終わりで温度差のある液体が口の中に飛び込んできて驚かされるという仕掛けです。五色の酒は色のコントラストの美しさに価値を置きますが、こちらは温度のコントラストがポイントでして、同じグリーンピースのスープでも、温度が異なれば引き出されるおいしさも違うことがよくわかります。一品で二度おいしい、というわけです。
 こうした意外性に満ちた料理を発表し続けたのが、スペインのロサスという非常に交通の便の悪いところにありながら、世界中からお客を集めるレストラン「エル・ブジ(el Bulli)」です(カタルーニャ方言の発音に近い「エル・ブリ」と表記するほうが正しい、と言い立てる本もありますが、フェランを日本に紹介した功労者であるスペイン料理研究家の渡辺万里氏に敬意を表して、標準スペイン語のエル・ブジで通させていただきます。向こうじゃ普通にスペイン発音で呼ばれているそうですし)。欧米の料理界に旋風を巻き起こし、日本でもいろんな媒体で取り上げられました。いっとき、エル・ブジをまねた料理もあちこちで見かけましたね。一方で彼の料理は意表をつくだけだとか、科学実験みたいで肝心の味はさっぱりだとか毀誉褒貶も激しかったです。
こうした意外性に満ちた料理を発表し続けたのが、スペインのロサスという非常に交通の便の悪いところにありながら、世界中からお客を集めるレストラン「エル・ブジ(el Bulli)」です(カタルーニャ方言の発音に近い「エル・ブリ」と表記するほうが正しい、と言い立てる本もありますが、フェランを日本に紹介した功労者であるスペイン料理研究家の渡辺万里氏に敬意を表して、標準スペイン語のエル・ブジで通させていただきます。向こうじゃ普通にスペイン発音で呼ばれているそうですし)。欧米の料理界に旋風を巻き起こし、日本でもいろんな媒体で取り上げられました。いっとき、エル・ブジをまねた料理もあちこちで見かけましたね。一方で彼の料理は意表をつくだけだとか、科学実験みたいで肝心の味はさっぱりだとか毀誉褒貶も激しかったです。
私自身はエル・ブジの料理を食べたことがありませんので、わざわざスペインまで出向いて召し上がられた方たちの足元にも及びませんが、それを承知で一言申しますと、持ち上げる方もけなす方も日本のマスコミはどこまでわかっているんですかね…。エル・ブジの料理書としては、CD‐ROMつきの角川書店の『エルブリ1998‐2002』や凝った造りのファイドンの『エル・ブリの一日』などやたらにぶ厚くて高価な本が知られているため、なかなかお手にとりづらいのかもしれませんが、渡辺氏の『エル・ブジ至極のレシピ集』や私どもの『エル・ブジ コレクション』や『スペインが止まらない』のシリーズもございます。こちらは薄くても料理のレシピが載っておりますので、ちゃんと読んでよく勉強するように。

というのも、いわゆるリョーリヒョーロンカの方々は、精神論や経験談はお好きなのですが、料理のレシピにはご関心ない。「料理長こだわりのどこそこ産のホンモノの食材を使った(この食材の説明がまた、体がかゆくなるほど知ったかぶりで恥ずかしい)」と「旬の素材の持ち味を引き出している(でも、その持ち味ってどんなもので、どうやって引き出したのかはえてして書いてない)」という2種類の決め台詞で、法務大臣並の激務を乗り切ってこられた。そんな方たちが突然、エル・ブジの料理の作り方がいかにユニークであるかを訳知り顔で語り出したものだから、ちょっと苦笑してしまいました。
音楽を鑑賞するのに楽譜を読めなければならない、楽器の一つも弾けなければならないという道理はありません。でも、まがりなりにも評論家を自称されるなら楽譜にも目を通したほうが、いえ、せめて楽器の名前くらいは知っておいたほうがよいのでは…。レシピからは食事の感動やリアルな味を想像するのは困難ですが、料理の構造と作り手の意図くらいは探れます。ところが普段からレシピを読み飛ばしてらっしゃる評論家先生やブロガー先生ほど、聞きかじりの薀蓄を語りたがるんですよねえ。感動や味を表現する筆力のなさを隠すためなんでしょうかねえ。
まあ、レシピが読める同業者においても、フェランの真意をどこまで理解できているかというと、難しいのは事実なんですが。たとえばフェランは、ソースをガスでムース状にしたり、海草由来の凝固剤で固めたゼリーを温めて提供したりというように新しい食感の創造に熱心ですよね。しかし口に入れた時の印象を左右するのは固さや温度以外にも、料理のポーション、すなわちどれくらいの大きさのものが口に入るかも重要なんです。ちょっとぴんとこないかもしれませんが、試しにティースプーンでちまちまカレーを食べてみてください。普段とちょっと違う印象に、ひと口の量が味に深く関わっていることがわかると思います。
エル・ブジの料理のもう一つの特徴である、串に刺したりスプーンにのせたりする盛り付けは、見た目の奇抜さや美しさだけでなく、口に入る量をコントロールする効果もあります。そこを計算に入れて味を組み立てているわけです。ところが、日本のエル・ブジもどきの料理はこうしたプレゼンテーションだけをなぞってただ刺したり、のせたりしただけのものも多かったように見受けられます。おまけにエル・ブジ風をやたら喧伝するものだから、事前にどんな料理が出てくるか想像できて驚きもありません。
フェランのほうからすれば、エル・ブジまがいの料理が世に広まることは、自分の首を絞めることになります。映画館でミステリー大作を封切る前に、下手なライターが書いたノベライズであらすじが広まってしまうようなものです。にもかかわらず、新しいアイディアを公表しているところに彼のすごさがうかがえます。マスコミに公表することで発明のプライオリティを確立するという合理的な考えです。また、アイディアは真似されてもされなくてもいつか陳腐化するのは避けられませんが、そのスピードを上回る速さで新しい料理を創造できるという自信のなせるわざでもあるのでしょう。
一方日本の料理人の世界では、同じ店のスタッフの間でさえ調理上の秘密を隠すなんてみみっちい話をよく聞きます。鍋洗いのスタッフが鍋底に残った汁を味見できないようにわざと洗剤を入れてから渡すとか、肝心要の作業は別室でこっそり行なうとか。それでいて、「あいつにおれの仕事を盗まれた」とかなんとか、やたら言い立てる。まあ、おおむねこういうタイプの料理人は、自分の技量がたいしたことがないのがばれるのが怖くて隠しているのでしょう。
祇園の料理人、西岡長久氏の随筆『京料理のこころ にしきぎ』にこんな話が出てきます。著者の師匠がこれまでの仕事を集大成した本の出版記念パーティ上で「この書物が出版、販売された今日この時より、私たちのどの店においても、この書物に写された、いずれの趣向や演出も使ってならないと覚悟するように申し送った」というのです。その店で修業しているスタッフや弟子たちにしてみれば、せっかく習ってきた料理を師匠が本で公表するのはただでさえ面白くないでしょうが、師匠からすればそんな了見はとんでもない、過去の私の料理なんぞは越えてみせよと、ハッパをかけたというわけです。
ちなみに西岡氏のこの本は『宗教と現代』という仏教関係の雑誌の連載をまとめたものだけあって、ちょっとまじめすぎるほどまじめな内容なのですが、文体に品があり、知識の丸写しなどではなく著者の経験が散りばめられていて読み応えがあります。何より仕事の悩みや正直な気持ちが書かれていまして、好感がもてます。
西岡氏はもう1冊『西花見小路 料理人の伝言』という随筆も出しておりまして、こちらは新聞連載をまとめているため1話2ページの構成なうえに話題も季節の料理が中心で、気軽に楽しめます。それでいて食材の描写にも持ち味の表現にも西岡氏独自の視点があり、料理評論家諸氏の追随を許しません。巻末にはちょっと長くて厳しい内容の「料理人をめざす若者に」という章がありますが、これは、すでに料理人になってかれこれ何年という人たちも、これから料理人をめざすにはちょっと勇気のいるおじさんたちも、ぜひ読んでいただきたい。たとえばこんな一文も。
「新しい発見をした時など、そのまますぐに教えるのは、いささか惜しいような気がすることもある。もう少し、自分の手の中で暖めておきたい気持ちだけれど、結局、教えてしまって、喜びをわかち合う。人が真似て、同じようなものが作られるが、それは仕方がない。新しい料理を考え、創り出す行為は逆の場合だってあり得るのだから」
新しい料理を思いついた誇らしさとちらりとよぎる独占欲。しかしそれを上回る、感動と進歩をみんなと共有したいという気持ち。ああ、この人は心底料理好きなんだなあ、というのが伝わってきます。そして、弟子への愛情も。
投稿者 webmaster : 16:49
2010年11月22日
料理本のソムリエ [ vo.12 ]
【 vol.12 】
五色の酒とレコードコンサート
しつこいようですが、まだまだカフェーの話が続きますよ。
前に説明したプランタンが明治44(1911)年4月、パウリスタが12月開業ですが、そのちょうど間の8月に開業したのが精養軒経営の「カフェー・ライオン」です。都市の女性の勤め先といえば電話の交換手か洋品店の店員か、といった時代ですから、女学校出の才女たちがこぞってこの店の女給さんとなり、人気を集めました。ところが震災の後に斜め向かいにライバル店が出店。獅子と虎の対決と噂されます。この店こそが永井荷風が通った「カフェー・タイガー」でして、こちらは昭和のカフェーブームを牽引する有名店となります(ここのナンバーワンが魯山人の器を使ったことで知られる「おけい寿司」を開くお慶さんです)。一方ライオンは昭和6(1931)年に大日本麦酒に経営に代わり、ビアホールとなりました。その地で今も営業を続けるのが「銀座ライオン5丁目店」というわけです。
プランタン、パウリスタ、ライオンは大正時代のカフェーの三羽烏ですが、それに一歩先駆ける先輩格として必ず語られるのが「メイゾン鴻ノ巣」です(表記は一定しておらず、鴻之巣、鴻乃巣とも書きます)。なにしろ前回紹介した『珈琲飲みある記』によると、松山省三がプランタンを開いた動機は鴻ノ巣のコーヒーのうまさにあったそうですから。
 ただし、この店をはたしてカフェーとして紹介していいものか、ちょっと迷います。詩人の木下杢太郎によると主人はキャバレーやカフェーといわれるのは嫌っていたとのことですし、久保田万太郎は料理3品にパンと果物、コーヒーがついて50銭だったと語っておりますし。当初日本橋小網町の鎧橋のたもとに店を構えていたこともあって、その立地がセーヌ川の左岸にあった本場パリのカフェを連想させ、フランス文化にあこがれた文学青年たちが通ったようです。木原店、京橋と二度の移転を経た後はさらに本格的なフランス料理店となりまして、多くの文化人の集まりに使われました。たとえば芥川龍之介は『羅生門』の出版記念パーティを鴻ノ巣で行なっており、その際に店の主人に「本是山中人」と揮毫したことが知られております。
ただし、この店をはたしてカフェーとして紹介していいものか、ちょっと迷います。詩人の木下杢太郎によると主人はキャバレーやカフェーといわれるのは嫌っていたとのことですし、久保田万太郎は料理3品にパンと果物、コーヒーがついて50銭だったと語っておりますし。当初日本橋小網町の鎧橋のたもとに店を構えていたこともあって、その立地がセーヌ川の左岸にあった本場パリのカフェを連想させ、フランス文化にあこがれた文学青年たちが通ったようです。木原店、京橋と二度の移転を経た後はさらに本格的なフランス料理店となりまして、多くの文化人の集まりに使われました。たとえば芥川龍之介は『羅生門』の出版記念パーティを鴻ノ巣で行なっており、その際に店の主人に「本是山中人」と揮毫したことが知られております。
鴻ノ巣はコーヒー史を扱う本だけでなく、カクテル史の文脈の中でも登場します。なにしろ日本バーテンダー協会会長の長谷川幸保氏が銀座に開いたバーの名前は、この店にあやかってか、「鴻の巣」(後に鴻之巣と改称。現在は閉店)でありました。
鴻ノ巣ではパンチやカクテルが名物で、中でも「五色の酒」で知られていました。これは色違いのリキュールを混ざらないようにそおっと注いで層状にしたもの。ステアしたり、シェイクしたりして作るカクテルと対極にあります。なお大正浪漫ただよう「五色の酒」とは日本での呼び名でして「プース・カフェ」というのがオリジナル名称。フランス語でコーヒーを押しやるもの、という意味です。つまるところ食後酒ですね。
 はたしてどんなレシピなのでしょう。幸い小社はカクテル関連の本はたくさん出版しており、資料には事欠きませんぞ。
はたしてどんなレシピなのでしょう。幸い小社はカクテル関連の本はたくさん出版しており、資料には事欠きませんぞ。
『新版バーテンダーズマニュアル』ではグレナデンシロップ、メロンリキュール、バイオレット、ホワイトペパーミント、ブルーキュラソー、ブランデーを6分の1ずつ。これでは6色の酒ですが、7色使った「レインボー」という仲間もあります。逆に『バー・ラジオのカクテルブック』ではカルア、クレーム・ド・バイオレット、ペパーミント、ブルーキュラソーを4分の1ずつの4色。『カクテルレシピ1380』はグレナデン・シロップ、マラスキーノ、クレーム・ド・ミント、クレーム・ド・バイオレット、イエローシャルトリューズ、ブランデーを6分の1ずつ。なおこの本には「プース・カフェ・アメリカン」というカクテルのレシピもありまして、こちらはマラスキーノ、オレンジキュラソー、グリーンシャルトリューズ、アニゼット、ブランデーで作るのですが、仕上げにブランデーに火をつけます。『カクテルホントのうんちく話』によると、プース・カフェはナポレオン時代に流行ったシャス・カフェに端を発し、19世紀半ば過ぎにはいろいろな種類が生まれたそうで、最後にブランデーを浮かべるのが暗黙の了解だったとか。

要は比重の重い順に注いで層にすればよいわけで、瓶から直接注がずにバースプーンで静かに移すのがこつ。かつてかなり流行したようで、リキュールグラスよりも細い「プース・カフェグラス」という専用グラスすらありました。カフェー・プランタンでも提供しておりまして、松山省三の息子である河原崎國太郎は自伝『女形芸談』中で、実家のバーテンダーが作る五色の酒を心をときめかせて見ていたと子供時代の思い出を語っています。
さて鴻ノ巣名物五色の酒ですが、これは日本文学史上、有名な事件のきっかけとなります。前回も登場しました平塚らいてう主宰の女性雑誌『青鞜』がその舞台です。明治45(1912)年6月。まだ10代だった青鞜社員の尾竹紅吉が、単身鴻ノ巣に雑誌広告を取りに行きました折に、主人に五色の酒を飲ませてもらいます。鴻ノ巣は『奇蹟』『ザムボワ』『スバル』など各種文芸雑誌に広告を入れておりまして(スバルにはプランタンの開店あいさつと並んで広告が入っております)、文学界のよきパトロンでもあったのです。
紅吉が青いストローで虹のような酒を飲む(実際は彼女は飲まなかったらしいのですが、背伸びしたい年頃だったようで)感動を誌上に寄せると、青鞜の活動を疎ましく思っていた保守派の格好の攻撃材料に。同時期に紅吉たちが吉原を見学した「吉原登楼事件」と合せて「女だてらに白昼堂々と酒を飲む」「女文士の吉原遊び」と揶揄し、面白おかしく新聞ネタにされてしまいます。責任を感じて青鞜を辞めた彼女は、のちに陶芸家の富本憲吉の妻となります。
ちなみに大正7(1918)年に出版された『料理小説集』の著者である吉田静代は、紅吉に興味をもって青鞜の支援会員となり、大正2(1913)年10月にメイゾン鴻ノ巣で開かれた仲間の上京歓迎会に出席しております。彼女の自伝『ひとつの流れ』によりますと、歓迎会では騒動の発端になった五色の酒も飲んだとか。くだらぬ新聞中傷などに負けないぞ、という意思表示だったのでしょうか。
この『料理小説集』は小説中の料理が登場するシーンをピックアップし、その料理のレシピを紹介したもの。今でも雑誌などで人気の企画の元祖ですね。もっとも彼女自身も青鞜に作品を発表しているくらいですから、選ぶ小説が実に渋い。吉田静代は料理研究家の宇野弥太郎の原稿(恐らく「西洋料理法大全」)をまとめたり、宇野が料理長を務めた料亭の帳場を手伝ったこともあり、まさに適任者でした。料理小説集は1995年に復刻されたのですが、小規模出版で入手は困難です。もっとも97年には構成を変え、年譜を省略した編集版が『折々の料理』のタイトルで再び世に出されております(こちらはなぜか表紙に魯山人の器の写真が使われております)。
ところでメイゾン鴻ノ巣が料飲文化に貢献したのはカクテルだけではありません。ロシアからサモワールを輸入して、知り合いに送っていることが与謝野寛・晶子夫妻宛の手紙から判明しています。また鴻ノ巣は支店として、京橋ですっぽん料理店「○や(まるや)」を始めておりまして、若き日の魯山人が料理を指導したというエピソードが白崎秀雄の『北大路魯山人』に出て参ります。
下岡蓮杖ばりにアクティブで、軟派な文士とも硬派なフェミニストたちとも分け隔てなく付き合う鴻巣主人。彼はいったい何者なのか。その謎は『祖父駒蔵とメイゾン鴻之巣』で、明らかにされております。本書はタイトルの文のほか、著者の奧田万里氏の日常をスケッチしたエッセイなど22編を集めた書で料理本ではありませんが、魯山人が彫ったメイゾン鴻ノ巣の看板がわかる貴重な外観写真を見ることができます。
 なお、駒蔵は若い頃にすっぽん料理店で修業したと語っていたとか。新聞広告を調べてみると「○や」の開業は美食倶楽部どころか、魯山人の骨董店「大雅堂」の開業よりも先ですし、その開業以前からメイゾン鴻ノ巣では毎週金曜日にすっぽん料理を提供しています。となると魯山人が指導したというのは、かなり割り引いて考えたほうがよさそうです。むしろ逆なのかもしれませんぞ。
なお、駒蔵は若い頃にすっぽん料理店で修業したと語っていたとか。新聞広告を調べてみると「○や」の開業は美食倶楽部どころか、魯山人の骨董店「大雅堂」の開業よりも先ですし、その開業以前からメイゾン鴻ノ巣では毎週金曜日にすっぽん料理を提供しています。となると魯山人が指導したというのは、かなり割り引いて考えたほうがよさそうです。むしろ逆なのかもしれませんぞ。
今や忘れられた奧田駒蔵(なにしろ白崎の本には奧田慶太郎という誤った名前で登場します)の事蹟について、10月に開かれた「食生活史懇話会」では、奧田万里氏と音楽史研究者の奧田恵二氏のご夫妻に講演していただきました。その席では鴻ノ巣で開かれた蓄音機コンサートの曲も披露されたのですが、これまたバッハやシューベルトといった古典ではなく、ストラヴィンスキーやリヒャルト・シュトラウスなど当時最新の音楽だったとのことです。音楽愛好家にとっては、同時代の希少な音源を最新オーディオ機材で聞けるめったにない機会。かつてのジャズ喫茶のような役目を果たしたのでしょう。
それにしても駒蔵のマルチタレントぶりと交際範囲の広さには驚かされます。関根正二ら若い洋画家の作品を買って彼らの活動を支えただけでなく、みずからも文人風の絵をよくして個展を開き、店で発行した雑誌の表紙も自分で描いております。東京の蒲田には自分で設計したアトリエを建て、御茶ノ水の文化学院の創立メンバーとしてフランス料理を教え、学校の表札も彼の字でした。映画の「寒椿」(南野陽子主演ではありませんよ。水谷八重子のデビュー作。青鞜社員だった林千歳も登場します)に、モブキャラクターとして出演したという伝承もあります。震災後の復興の無理がたたって若くして亡くならなければ、後世にもっと名を残したことでしょう。
投稿者 webmaster : 18:08
2010年11月08日
料理本のソムリエ [ vo.11 ]
【 vol.11 】
2軒の日本最初の喫茶店
HPにアップされた前回の文章を通して読み返したところ、慄然といたしました。これでは「いまどきのカフェには暗いくせに、キャバクラについては営業許可についてまで詳しいおっさん」と思われかねない…。違いますからね。知っているのはカフェーのほうです。その証拠に今回も引き続きカフェーの本の話を。
日本のカフェーの第1号は、「カフェー・プランタン」であることは前回述べましたが、これは「カフェーと名乗った最初の店」という意味でして、「日本最初の喫茶店」となるとちょっと様子が違います。これはなかなか厄介な問題でして、明治の新聞や広告ビラにより、当時コーヒーを提供していた店がいくつか確認されておりますが、どれくらいの期間営業していたか、どんな業態だったかわからないものばかり。
たとえば明治9(1876)年4月7日付けの東京絵入新聞に、画家にして写真家の下岡蓮杖が浅草の奥山に「御安見所(またの名を油絵茶屋もしくはコーヒー茶屋)」を開いたという記事が載っております。偉人の肖像画や函館戦争、台湾出兵のパノラマ絵を飾り、入場料は1銭5厘でもれなくコーヒーつきという趣向。これは当時珍しかった油絵の見世物小屋でして、喫茶店のプロトタイプというにはちょっと無理がありますね。なお、この記事中にはコーヒーとはいかなる飲み物なのか、一切説明がありません。喫茶店はまだ存在しなくとも、当時急速に増えていた西洋料理店ではコーヒーも提供しており、認知が進んでいたのでしょうか。
ちなみに『下岡蓮杖写真集』の解説によると彼はかなりのアイデアマンだがやや大風呂敷の気がありまして、パノラマ絵に石版印刷、乗合い馬車に人力車、牛乳販売にガス灯設置を日本で初めて手がけたのは自分だと語っていたそうです。この写真集は料理本ではありませんが、蕎麦を食べる女性たち(せいろで1人2枚ずつです)や、桶にのせたまな板で魚をおろす女性、天秤棒を担いだ豆腐売りや魚売り、金沢八景の料亭「千代本」といった明治初期に写された貴重な写真が掲載されておりまして、食文化的にもちょっと興味深いです。それからついでにトリビアですが、「星岡茶寮」の共同経営者だった中村竹四郎は下岡の最後の弟子であります。
それでは開業日時が確認できるうえ、明らかに欧州のカフェーを目指していた店はどこかというと、明治21(1888)年4月13日に上野の西黒門町に開店した「可否茶館」です。オーナーの名前は鄭永慶。彼は江戸時代の初めに日本に亡命した鄭成功の末裔でして、中国語通訳として幕府に仕えた家系のために中国風の名乗りですが、れっきとした日本人です。
可否茶館については版画家にして明治文化研究家の奥山儀八郎氏が再評価し、1940年には可否茶館が開業時に発行した小冊子をわざわざ復刻しております。この小冊子は可否茶館の開業広告のほか、世界のカフェ事情を紹介したもの。この復刻版を入手した内田百けん(黒澤明の映画「まあだだよ」の主人公ですね)が、明治製菓別館の喫茶室でいにしえの可否茶館に思いをはせる小文が『御馳走帖』に収録されています。御馳走帖は言わずとしれた料理エッセイの名作の1つですね。過去に書いた料理関係の文を集めて、戦後間もない1946年9月に発行した本で、活字にも、食べ物にも飢えていた時代にぴたりとはまって大評判をとりました。二度の新訂版が出ているうえに、今は文庫で読むことができます。
 さて、戦後奥山氏は中国人説などの誤った鄭永慶像を正すべく、1957年に『珈琲遍歴』を刊行し、詳細を紹介しました(これは1200部限定出版だったのですが、のちに旭屋出版から2度復刻されました)。翌58年には東京都喫茶業環境衛生同業組合と東京中日新聞の共催で、可否茶館開設70周年記念・喫茶まつりが開かれたと、62年小社刊行の『珈琲飲みある記』にあります。本書の著者、寺下辰夫氏は鄭家と縁戚関係のある川口家の出身。奥山氏とはコーヒー研究仲間であります。
さて、戦後奥山氏は中国人説などの誤った鄭永慶像を正すべく、1957年に『珈琲遍歴』を刊行し、詳細を紹介しました(これは1200部限定出版だったのですが、のちに旭屋出版から2度復刻されました)。翌58年には東京都喫茶業環境衛生同業組合と東京中日新聞の共催で、可否茶館開設70周年記念・喫茶まつりが開かれたと、62年小社刊行の『珈琲飲みある記』にあります。本書の著者、寺下辰夫氏は鄭家と縁戚関係のある川口家の出身。奥山氏とはコーヒー研究仲間であります。
 寺下氏は1963年4月号の『月刊食堂』でも可否茶館について詳しく述べておりまして、それによると、鄭永慶は上流階級のサロンである鹿鳴館に対抗し、庶民階級のための喫茶室であり、知識や親睦の“共通の広場”を作ろうとしたのが開業の動機だったそうです。
寺下氏は1963年4月号の『月刊食堂』でも可否茶館について詳しく述べておりまして、それによると、鄭永慶は上流階級のサロンである鹿鳴館に対抗し、庶民階級のための喫茶室であり、知識や親睦の“共通の広場”を作ろうとしたのが開業の動機だったそうです。
たかが喫茶店にずいぶん大仰な感じもしますが、鄭は明治7(1873)年にアメリカのエール大学に留学しており、帰国後は岡山の師範学校の教頭職に就いた経験もあります。留学時代に知ったコーヒーショップやカフェの文化を日本に紹介しようというのが、鄭の志でした。そのため可否茶館はただコーヒーを提供するだけでなく、新聞や雑誌の読める閲覧室や化粧室、フランスのカフェで流行っていたビリヤードも備えておりました。
しかし、鄭の夢は当時においては早すぎました。店を閉じた鄭は37歳でシアトルで没するのですが、失意の渡航と鄭の眠る地については、いなほ書房の星田宏司氏が『日本最初の喫茶店―可否茶館の歴史』でつまびらかにされておりますので、そちらをご覧ください。巻末には鄭が配った例の小冊子も採録しておりまして、彼の理想としたところがわかります。
 なお寺下氏は先の『月刊食堂』の記事中で、可否茶館の跡地に記念碑を建てたいとも述べておりました。
なお寺下氏は先の『月刊食堂』の記事中で、可否茶館の跡地に記念碑を建てたいとも述べておりました。
それから40年。星田氏ら鄭永慶の生涯に魅かれた人たち、鄭一族の子孫会、日本コーヒー文化学会や珈琲業界といった数多くの有志の協力によって、2008年4月に記念碑が建てられました。実はこの場所は、柴田書店の入っているビルから歩いて1分の距離。SANYO東京ビルの横にありまして、大通り道を挟んではるか先には上野松坂屋が望めます。
松坂屋が可否茶館の開業時にはまだ和風の呉服屋だったことを考えると、その先進性がうかがえます。
さて可否茶館から経ること20余年。明治44(1911)年12月12日に銀座に開店したのが「カフェー・パウリスタ」です。同店は日東珈琲の前身であり、創業の地には1970年に同名の喫茶店が復活し、今も営業を続けています。パウリスタの歴史については、店で配られているパンフレットからもうかがえますが、ここは一つ、日東珈琲元社長の長谷川泰三氏による『日本で最初の喫茶店「ブラジル移民の父」がはじめたカフェーパウリスタ物語』という長ーいタイトルの本で、さらに深く味わってほしいものです。
おっと、またまた「日本最初の喫茶店」が登場して参りましたが、コーヒーを主力商品とした純粋な「喫茶店」という業態の第一号という意味では、この店もまた日本初を冠する資格があるでしょう。パウリスタとはサンパウロっ子という意味のポルトガル語。ブラジル移民の父と呼ばれる水野龍は、その功績からサンパウロ州政府から無償でコーヒー豆の提供を受けました。ただし、日本にブラジルコーヒーを紹介、普及させるという条件つき。そのために開いた店がパウリスタだったのです。
なにしろ無償ですから安く提供できました。プランタンが文化人が集まるちょっと敷居の高い店だったのに対し、学生でも入れる金額と雰囲気でした。普通のカフェーでは女給さんがサービスするのに対し、パウリスタでは海軍士官風の制服を着た少年たちが給仕した点も大きく異なります。どうも硬派なのが社風のようです。商品のキャッチフレーズからして「鬼の如く黒く、恋の如く甘く、地獄の如く熱きコーヒー」ですし。
もっともパウリスタには瀟洒な女性用ルームもありました。「元始、女性は実に太陽であった」で有名な平塚らいてう(こちらも映画になりましたね)の女性解放誌『青鞜』のメンバーたちが、愛用していたそうです。そのほか多くの文学者たちがパウリスタを訪れ、同店を作品の中で描写しておりますが、詳しくは長谷川氏の著作で。
コーヒーを普及させるのが設立目的ですから多店展開にも熱心で、支店があったと推測される場所は全国26カ所におよぶそうです。大正末には関東大震災とサンパウロ州のコーヒー無償期間が切れたダブルパンチで、これらの店舗を手放してしまいますが、日本各地にコーヒー文化の芽を広めたのは間違いありません。水野龍は震災の翌年に65歳でブラジルに渡り、大戦中の帰国を挟みますが、92歳で彼の地で亡くなっております。
こうしてみると喫茶店黎明期の創業者たちは、ずいぶんと情熱家で、社会貢献に熱心です。時代が違うといえばそれまでですが、株価に一喜一憂し、テレビ出演に熱を上げるような昨今の飲食店経営者にちょっと煎じて飲ませてやりたい気がします。
投稿者 webmaster : 11:07
2010年10月06日
料理本のソムリエ [ vo.10 ]
【 vol.10 】
カフェ、はじめました
また丼の話の続きです。実は、第7回の文章にひとつだけ気がかりな点がありました。一度に料理を提供できる簡便さをアピールしたいが余り、丼を江戸時代の「ワンプレートランチ」とたとえましたが、今でもこの言葉って有効なのか。「ワンプレートランチって、ちょー受けるんですけどぉー」とか失笑されていないか。
 意を決して斯界の権威、『cafe sweets』編集長に問い合わせたところ、特に珍しいことでもないので最近はあまり使われていないそうです。恐る恐る最新号を開いてみたところ、色とりどりの野菜のランチはたくさん並んでいるけれども、確かに「ワンプレートランチ」なるキャプションは見当たらない。「カフェごはん」もすっかり世の中に定着し、もはや取り立てて言上げすることでもなくなったのですね。年齢はとりたくないものです。
意を決して斯界の権威、『cafe sweets』編集長に問い合わせたところ、特に珍しいことでもないので最近はあまり使われていないそうです。恐る恐る最新号を開いてみたところ、色とりどりの野菜のランチはたくさん並んでいるけれども、確かに「ワンプレートランチ」なるキャプションは見当たらない。「カフェごはん」もすっかり世の中に定着し、もはや取り立てて言上げすることでもなくなったのですね。年齢はとりたくないものです。
 ちなみに柴田書店の看板雑誌『cafe sweets』が創刊したのは2001年3月。スターバックスの日本上陸が1998年でして、ちょうどこの頃からカフェというスタイルの店が爆発的に増えたと記憶しております。小社刊の『カフェをはじめてみませんか?』は第1章の「ケーススタディ」で、8店のカフェの開業までの経緯と苦労を紹介しておりますが、ほとんどが2000年前後の開業。ただし、もっとも古株のNews Cafeのオープンは95年であります。オーナーの伊原佳代子さんは、90年代初めに東京にアメリカンスタイルのカフェができつつあり、カフェ開業を決意した95年には表参道にオープンエアのカフェが目立ち始めていたと、当時を述懐されています。
ちなみに柴田書店の看板雑誌『cafe sweets』が創刊したのは2001年3月。スターバックスの日本上陸が1998年でして、ちょうどこの頃からカフェというスタイルの店が爆発的に増えたと記憶しております。小社刊の『カフェをはじめてみませんか?』は第1章の「ケーススタディ」で、8店のカフェの開業までの経緯と苦労を紹介しておりますが、ほとんどが2000年前後の開業。ただし、もっとも古株のNews Cafeのオープンは95年であります。オーナーの伊原佳代子さんは、90年代初めに東京にアメリカンスタイルのカフェができつつあり、カフェ開業を決意した95年には表参道にオープンエアのカフェが目立ち始めていたと、当時を述懐されています。
 この店は「カフェ・デ・プレ」表参道店のことでしょう。レストランひらまつグループの「カフェ・デ・プレ」は東京のオープンエアのカフェの嚆矢でして、1号店が広尾に開店したのは93年10月。見通しのよいガラスの扉で外と店を仕切る開放的な造りで、店名をプリントしたオーニングテントのひさしの下、道路に面したテラス席が並ぶ…。こうしたフランスらしい造作のカフェの登場は実に画期的でした。渋谷のBUNKAMURAには89年にフランスの「ドゥマゴ」の支店がオープンしておりますが、こちらはビル内での営業だったのに対し、デ・プレはまさに街角のカフェそのもの。
この店は「カフェ・デ・プレ」表参道店のことでしょう。レストランひらまつグループの「カフェ・デ・プレ」は東京のオープンエアのカフェの嚆矢でして、1号店が広尾に開店したのは93年10月。見通しのよいガラスの扉で外と店を仕切る開放的な造りで、店名をプリントしたオーニングテントのひさしの下、道路に面したテラス席が並ぶ…。こうしたフランスらしい造作のカフェの登場は実に画期的でした。渋谷のBUNKAMURAには89年にフランスの「ドゥマゴ」の支店がオープンしておりますが、こちらはビル内での営業だったのに対し、デ・プレはまさに街角のカフェそのもの。
 月刊専門料理93年12月号で平松宏之シェフは「10代でフランスに憧れ始めた時から自分の中に蓄積してきた“フランス”を、レストランを通して、ビストロを通して、カフェを通してそれぞれに表現していくのが夢だった」とそのコンセプトを明確に語っています。
月刊専門料理93年12月号で平松宏之シェフは「10代でフランスに憧れ始めた時から自分の中に蓄積してきた“フランス”を、レストランを通して、ビストロを通して、カフェを通してそれぞれに表現していくのが夢だった」とそのコンセプトを明確に語っています。
実は「カフェ・デ・プレ」よりも2年前、開業間もない原宿のフランス料理店「ル・カーナヴァル」を取材したことがあるのですが、ここもまた外見がフランスのカフェそっくり。外の空気を感じることのできるテラス席を設け、パリの街角を演出するのが中嶋芳男シェフのこだわりでした。たまたまこの店が建物の地階に位置し、公道ではなく吹き抜けの中庭に向けて開かれた構造なので実現できたそうです。というのも当時は保健所が、開放的な造りの店に対して難を示していたのです(レストランを開店する際に、店舗設計が完成した段階で、衛生上の問題がないか保健所の指導を受ける必要があります)。カフェ・デ・プレも営業当初に保健所から、店の外までテーブルをせり出さないように、と厳しく指導されたとも聞いています。
原宿と広尾では保健所の所管が違いますので確かなことは言えませんが、いまや日本でもテラス席を当たり前のように見かけるようになったのは、こうしたシェフたちの熱意の積み重ねのおかげではないでしょうか。それは、なんとなく洒落ているからまねしてやろう、という軽い気持ちではなく、フランスの文化とエスプリを日本に紹介しようという強い意志があったからこそだと思うのです。
そもそもトルコに端を発したカフェというスタイルの飲食店はドイツ、イタリア、イギリス、フランスと欧州を席巻、それぞれに独自の発展を遂げます。単なる食事の場所にとどまらず、文学者や評論家が意見を戦わせ、新進の画家が集い、芸人が腕を磨く、文化を生み出す装置でありました。そうした欧州のカフェを論じる本は彼の地でも多く出版されており、翻訳も出ております。めまぐるしく登場する多くの人物にパリやロンドンのカフェを語らせる『カフェの文化史』は、文字がびっしりでエスプレッソをマグカップで読むような読後感。一方『ヨーロッパのカフェ文化』は、1章ごとに異なる国のカフェ文化が紹介され、アメリカンコーヒーのようにさらりと読めます。お好みに合せてどうぞ。
さらに突っ込んで知りたい方は各国論がお勧めです。『ウィーンのカフェ』はドイツ、『コーヒー・ハウス』はイギリス、『カフェ ユニークな文化の場所』はフランスを取り上げておりまして、それぞれの国柄に応じて、カフェがどのように受け入れられ、発達したのかをわかりやすく概観しています。
またフランスのカフェを支える人々については『パリ物語 グルメの都市をつくった人々』がスポットをあて(中公文庫にはずばり『パリのカフェをつくった人々』のタイトルで収録されています)、フランスの地方出身者とパリとの関係を解き明かしてくれます。たとえばパリのカフェのスタッフはオーベルニュ出身者が多いのはなぜか。放牧とチーズ作りが主産業のこの地からパリへ出稼ぎにきた若者たちが、水売りなどの重労働に従事し、のちには炭屋を開きます。その店の一角で珈琲や酒を飲ませるようになったのが後にカフェへと姿を変えていったそうです。
またブラッスリーのオーナーはアルザス人が多い。そもそもブラッスリーとはビール醸造所の意味で、ドイツ国境に接するアルザスで生まれた“ビールを飲ませる食堂”ですから、これは当然といえば当然のこと。ところがブラッスリーの屋台でカキの殻をむくエカイエという職業は、サヴォワ人が多いそうです。サヴォワは海どころかスイスに近い山国なのですが、舗道に面したふきっさらしの屋台で水仕事ができるのは、寒さに強いサヴォワ人だからこそ、なんだとか。
ちょっとできすぎた話と思われるかもしれませんが、ここ日本にも同様の事例があります。厳寒の冬の海で海苔を摘み取る作業は、江戸時代から農閑期に出稼ぎにきた諏訪の人たちがたずさわってきました。その伝統をうけて海苔の収穫が機械化されたのちも、海苔の入札の際に格付け検査をする検査員は長野県の出身者が多かったそうです。長年海苔に触れてきたプロだから、海苔を見極める力もすぐれているというわけ。詳しくは海苔業者からの聞き語りである『山国からやってきた海苔商人』をご覧下さい。
おっと話が横道にそれました。実はパリのカフェという業態が日本に紹介されたのは、これが初めてではありません。明治の末、日本の文化人たちはあこがれのパリにあるような「文学カフェ」を求めました。それに応えて画家の松山省三が明治44(1911)年に銀座に開いた「カフェー・プランタン」がその始まりといわれています。
大正モダンの時代にブレイクした日本の「カフェー」(カッフェー、カフェエなどとも表記されています)はパリのカフェと違って、ギャルソンではなく女給さんたちが給仕し、彼女たちは時代の最先端を進む働く女性としてもてはやされました。
しかし昭和に入って不況を迎えるとカフェーは次第に姿を変えていきます。大阪資本の女給の「エロサービス」(!)を売り物にした店が東京に進出し、大流行。当時のことですから、このキャッチフレーズから想像されるほど過激なものではなく、キャバクラみたいな感じです。店の女給さんを紅白2チームに分けて競わせたり、トップの女給さんが有名になったりしたところもよく似ています。
ですから今でも日本の法律上、カフェー(今のカフェのことではありませんよ)は風俗営業の「2号営業」に分類されています。このカテゴリーに含まれるのはほかに「料理店」と「待合」でして、キャバクラも該当します。料理店が風俗営業というのはかなり違和感がありますが、これは飲食以外に遊興も提供する店を指す狭い定義でして、早い話が芸者さんを呼んだり、お酌してもらえる料亭さんのことですね(「待合」は同じく芸者さんを呼べる店ですが、料理を自前で作らずに、仕出しで済ませる業態をいいます)。純粋に料理だけを提供する板前割烹などは「飲食店」というカテゴリーに入りまして、風営法の規制は受けません。逆に2号営業の対象であれば、住宅地への出店が規制される場合がありますし、公安委員会に届けねばなりません。
こうしてみるとテラス席を備えた東京のカフェの流行は、明治の末の初心に帰るルネサンス運動とも言えます。通りに面したテラスに知った顔を見つけて、ふらりと立ち寄り、しばし語らい会う…。ネットカフェの時代ですから、そうした交流はもはや電脳の世界だけなのかもしれませんが。
投稿者 webmaster : 17:17
2010年09月24日
料理本のソムリエ [ vo.9 ]
【 vol.9 】
江戸時代の蕎麦マニアたち
さて、いよいよドンブリの話の続きです。
かけそばの誕生のいきさつは1751年に書かれた『蕎麦全書』という本に出ております。この本は、当時の特色あるそば店を列挙したり、蕎麦や薬味の製法を解説したりと、全書という名に恥じない詳しさで、江戸時代のそばに関する薀蓄を語るときには欠かせない種本です。以下は下巻の「ぶっかけそば始りの事」から。
「新材木町に信濃屋と云ふ有り。是元祖也。其本は省略のため製し始めし也。尤も粗々たる一小家なり。此辺、車力、軽子多く集り会する場処なり。此ぶっ懸そばを製し出せしは、立ちながらも食するの便りにしたり」
新材木町は今の堀留町あたりで、日本橋の魚河岸にも近い。ここの信濃屋という小さな店が元祖だそうです。築地の回で説明した軽子や車力たちが、作業着のまま立食いするのに便利なように始めたもので、当時は下品な食べ方とされていました。しかし猪口や汁注ぎなどの付属品を必要としないので簡便なうえに、寒い時期には温かくして出すこともでき、広まったというのです。
なお前々回に取り上げた「けんどん争い」の最中で滝沢馬琴は「そば切の器物は、予が小児の頃は皿也。今は多くは平をも用ひ、小蒸籠又丼鉢をも用れど…」と述べております。馬琴は蕎麦全書完成よりもあとの1767年生まれ。この頃のそばは皿盛りだったということは、まだまだ、もりが中心だったのでしょう。それが馬琴と山崎美成とが大喧嘩した1825年には、平椀や丼も使われるようになった。つまり、かけそばが普及していったということを示しています。
かけそばを丼で提供するとなると、麺も汁もたっぷりの量が必要です。ひいては、明治時代以降に普及した支那そばも、日本人向けにスープたっぷりに仕立てるのが通常スタイルとなりました。一方中国はというと、前々回述べたようにドンブリという器はありませんから、この地で食べられる麺類は、タレで和えた和え麺であったり、汁と一緒に食べたとしても小椀に盛るものでした。最近ではタンタンメンは汁なしが本格的だという事実が広く知られるようになりましたが、それもそのはず、汁たっぷりのタンタンメンやラーメンは日本独自のものです。ちなみにタンタンメンは屋台風に担いで売り歩いたから「担々麺」でありまして、「坦々麺」と書くのは誤りです。もっとも日本式のものにはこの字をあてると決めれば、うまく呼び分けることができるかもしれません。
さて話を戻して蕎麦全書ですが、これは出版販売された本ではなく、手書きの原稿として伝わったもので、戦前はごく一部の人たちにしか存在を知られていませんでした。それを聞きつけ、広く紹介したのが故・新島繁氏です。『蕎麦うどん名著選集第1巻』と『食の風俗民俗名著集成第4巻』に収録されていますが、文語体のままなので、藤村和夫氏がさらに現代語に訳して解説をつけた『現代語訳「蕎麦全書」伝』が便利です。
「さらしな総本店」の店主でもあった新島氏は、蕎麦の歴史の研究に熱心で、同人雑誌「さらしなそば」を発行するほか、「日本麺食史研究所」を立ち上げて資料の蒐集に努めました。その蔵書はそばに直接かかわる資料はもちろん、民俗学や江戸文学などまで目配りした、日本一のそばコレクションです。

 世にあまたある江戸関係書をながめると、寿司に比べてそばの歴史に関する薀蓄がやたら充実しているのは、新島氏が世のそば好きたちを結集し、資料を積極的に紹介し、考証してきたからにほかなりません。新島氏の著作には、「さらしなそば」への寄稿を集めた『蕎麦今昔集』や『蕎麦の世界』のような編著のほか、江戸時代のそば文献を紹介する『近世蕎麦随筆集成』、『蕎麦史考』、そして新島氏が校正作業後に急逝され、最後の著作となった『蕎麦年代記』などの専著があります。どれも文献にきちんとあたった学術的な内容で、箱入りの重厚感ある本です。
世にあまたある江戸関係書をながめると、寿司に比べてそばの歴史に関する薀蓄がやたら充実しているのは、新島氏が世のそば好きたちを結集し、資料を積極的に紹介し、考証してきたからにほかなりません。新島氏の著作には、「さらしなそば」への寄稿を集めた『蕎麦今昔集』や『蕎麦の世界』のような編著のほか、江戸時代のそば文献を紹介する『近世蕎麦随筆集成』、『蕎麦史考』、そして新島氏が校正作業後に急逝され、最後の著作となった『蕎麦年代記』などの専著があります。どれも文献にきちんとあたった学術的な内容で、箱入りの重厚感ある本です。

 いっぽう気軽に読めるものとしては、編著の『蕎麦の事典』や、そばに関わる年中行事や地方のそば民俗を紹介して中公文庫にも収録された『そば歳時記』あたりがよいでしょう。
いっぽう気軽に読めるものとしては、編著の『蕎麦の事典』や、そばに関わる年中行事や地方のそば民俗を紹介して中公文庫にも収録された『そば歳時記』あたりがよいでしょう。
蕎麦の世界を見渡すと、新島氏のほかにも研究熱心な業界人が多いですね。たとえば浮世絵蒐集では、『そばの浮世絵』を出版した「風流田舎そば」の故・山本重太郎氏や、小社から『そばの歴史を旅する』を出版した「増音」の故・鈴木啓之氏の名が挙がります。
蕎麦全書の著者である日新舎友蕎子(にっしんしゃゆうきょうし)と名乗る人物も、店で食べるそばには満足せず、自らそばを打つと書いておりますが、こちらは同業者ではなく、当時のそばマニアと思われます。
ちなみに江戸時代のそば好きは友蕎子さんだけではなかったようです。蕎麦全書には仲間の「谷村氏」が、「平岡氏」とどちらがそばをたくさん食べられるか競争したエピソードが載っております。○○氏という呼び方から察するに、彼らは武士階級だったのではないでしょうか。二人の勝負の行方はというと、両名とも大重箱に盛った1升以上の量のそばをなんなくクリア。さらにお代わりを椀で出し続けたところ、どちらも21杯食べてみせた。さらに平岡氏はそらまめご飯を2杯たいらげてみせたとのことです。大食がたたってか、のちに平岡氏は亡くなりますが、谷村氏は70歳になんなんとしても起居壮健、以前のようにそばを食べたとか。
また友蕎子は、そば好きの親友2人(名前は不明)と連れ立って、量がやたらと多い日本橋馬喰町(新材木町の近くです)の蕎麦屋をわざわざ訪ねたりもしています。「そばを好みて馬喰町そば試ざるも遺念也。格物の一つ也」(そば好きとしては馬喰町のそばを食べたことがないというのも心残りだ。これは物事の理を究めるためである)というのが、動機です。“遺念”だの朱子学用語の“格物”だのと仰々しくて言い訳がましいのが、これまた武士っぽい。「どうだい、ちまたで話題のメガ盛りそばを食べに行こうじゃないか」というのが真相でしょう。
さて、うどん粉どころかヒエが入っているという噂すらあるこの店に、まずいのを承知のうえで入った友蕎子ら3名。直径30cmほどの大鉢に崩れんばかりに盛ったそばに、3人前が一つに盛ってあるのかと勘違いします。煮干しを使ったその汁はなまぐさく、胸につかえてなかなか食べられない。「いかもの食い」の友だち(もしかしたら谷村氏かもしれません)が1人前と半分を食べて手伝ってくれたものの、友蕎子ともう1人はギブアップ。少し残して店を出ようとしたら、お代わりをしているお客を見てさらに驚いたり……。のちのちまで話の種となったことでしょう。『蕎麦全書』のさまざまなそばに関わる情報は、こうした仲間との交流の中で集まったものかもしれません。
このように江戸時代にも確かにそばマニアと呼ばれる人たちがいたと思われます。蕎麦全書にはそば好きで、いろいろ工夫し、道具まで自分で作ってそばをふるまう凝り性の「土田氏」なる人物が出て参ります。しかし土田氏は、出来不出来があって満足いくそばが打てないことに気を病み、そば打ちを止めてせっかくの道具を譲ってしまいます。
 また小社刊の「そばうどん」38号には江戸の各種料理書に出てくるそば汁の作り方について、千葉大名誉教授の松下幸子先生が紹介しておりますが、その1つ『黒白精味集』に「平尾正斎」と「横田甚左衛門殿」のそば打ち方法が登場します。この写本が書かれたのは『蕎麦全書』の5年前。著者である江戸川散人こと孤松庵(コショウにかけた筆名でしょうか)は、友蕎子グループと面識はなかったのでしょうか…。ちなみにさすがの新島氏も、『黒白精味集』には調査は及んでおりません。そば研究はまだまだ奥が深いのです。
また小社刊の「そばうどん」38号には江戸の各種料理書に出てくるそば汁の作り方について、千葉大名誉教授の松下幸子先生が紹介しておりますが、その1つ『黒白精味集』に「平尾正斎」と「横田甚左衛門殿」のそば打ち方法が登場します。この写本が書かれたのは『蕎麦全書』の5年前。著者である江戸川散人こと孤松庵(コショウにかけた筆名でしょうか)は、友蕎子グループと面識はなかったのでしょうか…。ちなみにさすがの新島氏も、『黒白精味集』には調査は及んでおりません。そば研究はまだまだ奥が深いのです。
プロである新島氏も、マニアの友蕎子も、自分でそばを打つために、そばに対する理解と思い入れが深いのが単なる食べ歩き好きとは違うところ。それでいて、自分が打つそばに自信はあっても、それ以外は認めないというような姿勢はありません。とにかくそばが大好きで、そばに関することなら何でも知ろうとし、それを後世まで伝えようとしてくれたのに感謝です。
平成の時代にもそば打ち自慢のマニアたちがたくさんいるようですが、批評家然として天狗になっている者も見られます。正直、愛が足りませんぞ。
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
marginheight="0" frameborder="0">
投稿者 webmaster : 18:12
2010年09月09日
料理本のソムリエ [ vo.8 ]
【 vol.8 】
帝国ホテル初代料理長のノート
前回の続き、かけ蕎麦の始まりについて…と言いたいところですが、
ちょっと寄り道です。
 いま、日比谷の「帝国ホテル」では「帝国ホテルと芸術都市パリの輝き ―1890」というロビー展示を開催中で、遅まきながら見学してきたばかりなものでして…。帝国ホテルは今年が120周年。それを記念しての企画です。会期は9月30日までですので、ご関心のある方はお急ぎを。ちなみに柴田書店は今年60周年。ちょうど半分ですね。「柴田書店と文教地区本郷の賑わい ―1950」を文京区役所あたりでロビー展示するには、あと60年頑張る必要がありそうです。その布石として、小社のほうは全国書店でブックフェアの開催中ですので、こちらもお見逃しなく。
いま、日比谷の「帝国ホテル」では「帝国ホテルと芸術都市パリの輝き ―1890」というロビー展示を開催中で、遅まきながら見学してきたばかりなものでして…。帝国ホテルは今年が120周年。それを記念しての企画です。会期は9月30日までですので、ご関心のある方はお急ぎを。ちなみに柴田書店は今年60周年。ちょうど半分ですね。「柴田書店と文教地区本郷の賑わい ―1950」を文京区役所あたりでロビー展示するには、あと60年頑張る必要がありそうです。その布石として、小社のほうは全国書店でブックフェアの開催中ですので、こちらもお見逃しなく。
さて帝国ホテルが誕生した1890年は、フランス革命から101年後。前年の1889年には革命100周年を記念した博覧会が開かれ、エッフェル塔が建設されています。ちなみにパリの「ホテル・リッツ」開業は1898年。当時のヨーロッパの観光文化やホテル文化も進化の最中であり、そうした同時代の最新モードを意識しての開業だったことがよくわかります。
 帝国ホテルというとフランク・ロイド・ライトが設計したライト館が名高いですが、今回の展示では大正11年(1922)に焼失した木造時代の旧館の写真も見ることができます。焼失当時、新館のライト館は本来なら竣工していたはずでしたが、天才のインスピレーションに振り回されて工期が遅れに遅れ、まだ建設途上でした。帝国ホテルは3年前の大正8年にも別館が焼失したばかりで、いよいよもって経営の一大危機を迎えます。そのため、当時の支配人の林愛作氏は責任をとって帝国ホテルを去ることになります。
帝国ホテルというとフランク・ロイド・ライトが設計したライト館が名高いですが、今回の展示では大正11年(1922)に焼失した木造時代の旧館の写真も見ることができます。焼失当時、新館のライト館は本来なら竣工していたはずでしたが、天才のインスピレーションに振り回されて工期が遅れに遅れ、まだ建設途上でした。帝国ホテルは3年前の大正8年にも別館が焼失したばかりで、いよいよもって経営の一大危機を迎えます。そのため、当時の支配人の林愛作氏は責任をとって帝国ホテルを去ることになります。
そのほかにもライト館をめぐるエピソードは尽きません。フランク・ロイド・ライトと日本人建築家下田菊太郎との確執、新築披露のパーティ当日に迎えた関東大震災、林氏の後を継いだ犬丸徹三支配人のライト館に対する複雑な感情、戦後のライト館取り壊しと保存問題……。もっともこれらについては、すでにいろいろなメディアに取り上げられています。詳しくは『帝国ホテルライト館の謎』に譲るといたしましょう。
帝国ホテルの支配人というと犬丸徹三、犬丸一郎父子が有名で、ライト館建設に奔走した林氏の存在は長らくその影に隠れていました。それが20年前の開業100周年の際に出版された社史『帝国ホテル百年史』において再びスポットが当たり、林氏の功績が広く知られるようになったそうです。社史というと戦前の出来事などは適当にさらっと流しておいて、調べやすい最近の話題と企業の都合のいい情報だけを盛り込んだいい加減なものも少なくないのですが、この本は1000頁を越えるぶ厚さで、日本のホテル史資料としても使える内容の濃いもの。当時の新聞や雑誌にも目配りして資料を収集しております。
また同ホテルは『帝国ホテル百年の歩み』も同時刊行していますが、どちらも私家本なので、図書館でなければ見ることは難しい。社史編纂チームのメンバーのひとり、武内孝夫氏が『帝国ホテル物語』をまとめておりますので、こちらをご覧になるのがよいでしょう。ちなみに帝国ホテルを去った林支配人のその後に関しては、昨年出版された『甲子園ホテル物語』にて知ることができます。日本の旅館文化を取り入れた新しいホテルの姿を模索する林氏の先見の明に驚かされます。
さて、そんな総力を尽くした『百年史』ですが、帝国ホテル初代料理長については「吉川某」とあるのみで、未詳とされておりました。第一ホテル支配人にして食文化史研究家でもあった村岡實氏は中公新書の『日本ホテル小史』中で、パレスホテルに在籍していた田中徳三郎シェフから1971年に聞いた話として、吉川シェフは横浜の「グランドホテル」系だったと紹介していますが、それ以上の情報はありません。田中シェフは大正2年(1913)の帝国ホテル入社なので、先輩から伝え聞いていたのでしょう。先の大正8年の火災のために帝国ホテルの古い資料は失われており、同社に吉川シェフに関する文献は残っていなかったそうです。
ところがこのたび吉川シェフのフルネームが判明し、今回の展示で写真も披露されました。7月21日付の東京新聞朝刊によると、一昨年ひ孫にあたる方から帝国ホテル側に連絡があり、明らかになったそうです。
新聞報道によると初代料理長の名は吉川兼吉。1853年生まれで横浜グランドホテルで修業したのち、鹿鳴館を経て、帝国ホテルに入ったとのことです。鹿鳴館というと日本人高官が慣れない格好でステップを踏むダンスホールなんていうイメージがありますが、営業形態としてはホテルだったのです。
横浜グランドホテルの沿革については、『横浜外国人居留地ホテル史』がもっとも正確でしょう。戦前のホテルの歴史をまとめた研究書としては、運輸省観光部に在籍していた宮川肇氏がまとめた『日本ホテル略史』が筆頭に上げられるのですが、なにぶん敗戦まもない1946年の刊行でして、間違いも散見します。その点、各開業年で横浜の外国人ホテルを整理した同書では、改装休業中だった横浜グランドホテルの営業再開日が明治6年(1873)8月16日であることをつきとめるなど、『日本ホテル略史』の誤りを訂正しています。
同書によると横浜グランドホテルは新規開業からしばらくの間、料理長が二転三転したのですが、初代料理長はフランス人のルイ・ベギューだったそうです。ベギュー(Beguex)は村岡氏の『日本人と西洋食』では、江戸幕府の支援で開かれた日本初の本格的ホテルである「築地ホテル」の料理長として、新発見の明治4年(1871)の晩餐会のメニューとともに紹介されています。ひょっとして同一人物かもしれません。築地ホテルが明治5年(1872)に焼失してしまった後、横浜に移ったと考えればつじつまが合います。彼は明治8年(1875)にレストランを開業するためにホテルを辞めるのですが、うまくいかなかったのか、今度は明治15年(1882)に「神戸オリエンタルホテル」の前身である「オテル・ド・コロニー」を立ち上げております。
これらのホテルはどれも帝国ホテルと同クラスの高級ホテルであり、多くの料理人が巣立っています。ルイ・ベギューの功績はなかなかだと思うのですが、その名前自体が正確なのか不安ですし(神戸オリエンタルホテルの経営者は日本ホテル略史にはL.Bageaxと書かれているそうなのですが、これでは発音はバゴ。そのせいかルイ・ビゴーと紹介し、ベギューとは別人としている本もあります)、謎に包まれた人物です。
なお横浜グランドホテルは関東大震災の被害を受けて廃業してしまいますが、それに代わるホテルとして横浜市の支援のもとで、昭和2年(1927)年に「ニューグランドホテル」が開業します。こちらのホテルもまた料理に力を入れていたことで知られ、スイス人のサリー・ワイル料理長の下では、荒田勇作、馬場 久、小野正吉ほか多くの料理人が修業しています(ワイル氏に関しては『初代総料理長サリー・ワイル』という評伝が出ております)。ちなみに帝国ホテル4代目料理長の内海藤太郎氏は、ワイル氏の下に就いた後、神戸オリエンタルホテルの料理長に就任しておりまして、これらのホテルの厨房に交流があったことがわかります。
さて本好き料理好きとしては、今回のロビー展示でもっとも目を引いたのは吉川兼吉の料理ノート(複製)でした。その隣には、先だって亡くなられた村上信夫料理長のノートや氏がフランス修業中に購入したラルース・ガストロノミックやギッド・キュリネールも展示されておりました。村上氏のノートはラヴィオリの作り方のメモ。吉川シェフのノートもラヴィオリについて書かれたページが開かれておりまして、気がきいております。
ラヴィオリのページの隣は牛腎臓洋酒煮。吉川シェフは腎臓にロギョンとルビをふっていることから、フランス語については、耳からではなく読んで学んだと思われます(フランス語で腎臓はrognonとつづりますが、発音はロニョンですから)。となるとルイ・ベギューの下で直接学んだわけではなかったのか……。いろいろ想像が膨らみます。
先の新聞によると吉川シェフは帝国ホテルを辞めたあと、明治天皇や朝鮮の李王家の料理人を務め、1935年に朝鮮の地で亡くなったとか。後半生もエピソードに満ちていそうで興味がつきません。日本の西洋料理の基礎を作った料理人となると、フランスに渡って修業した田中徳三郎氏や秋山徳蔵氏などが有名ですが、それも、前の世代が築いた基礎があってこそ。西洋料理黎明期の開拓者たちの功績は、さらに掘り起こしていかねばならないでしょう。
投稿者 webmaster : 14:45
2010年08月10日
料理本のソムリエ [ vo.7 ]
【 vol.7 】
ジャパン・クール“DONBURI”
前回は牛丼のお話をしましたが、この丼=ドンブリは、あだやおろそかには扱えない、日本の誇る偉大な発明であります。アメリカの吉野家はBEEF BOWLと称しているらしいですが、カタカナで書くと肉だんごみたい。
ここはぜひ、DONBURIをワールドワイドにしていただきたいですね。
 というのも、ドンブリという器にはご飯とおかずを一緒に盛る、すなわち一人前を一つの器で簡単にサービスできます。江戸時代に発明されたワンプレートランチであり、料理提供スタイルの革新だったのです。鰻丼、天丼、カツ丼、親子丼、深川丼等々、庶民的なメニューが生まれるにはドンブリが欠かせませんでした。同じような用途の器にお重があり、こちらのほうが歴史が古いのですが、鰻重、天重、カツ重となるとちょっと高級なイメージです。何度も塗り重ねて作る漆器は大きくなればなるほど、製作の手間が増えて高価になるせいでしょうか。漆器には「鰻椀」という大型の平椀もあるのですが、最近はとんとみかけません。
というのも、ドンブリという器にはご飯とおかずを一緒に盛る、すなわち一人前を一つの器で簡単にサービスできます。江戸時代に発明されたワンプレートランチであり、料理提供スタイルの革新だったのです。鰻丼、天丼、カツ丼、親子丼、深川丼等々、庶民的なメニューが生まれるにはドンブリが欠かせませんでした。同じような用途の器にお重があり、こちらのほうが歴史が古いのですが、鰻重、天重、カツ重となるとちょっと高級なイメージです。何度も塗り重ねて作る漆器は大きくなればなるほど、製作の手間が増えて高価になるせいでしょうか。漆器には「鰻椀」という大型の平椀もあるのですが、最近はとんとみかけません。
なおドンブリは日本独自の食文化ですから、中国には天津丼も中華丼も存在しません。これらは日本生まれの中国料理です。伝統的な中国陶磁を見ていると「鉢」や「?」「海碗」といった似た形の器はあっても、丼と呼ぶのにぴったりなものがなかなかありません。とくに牛丼を盛るときに使うような深くて背の高いもの(下の写真の左端のタイプ)は見当たりません。浅くて口の開いたラーメン用のドンブリと比べても、中国の鉢はもっと腰に丸みがあります(右から2番目のタイプが近いかんじです)。大きさもドンブリよりは大きめです。
取り分けるのが基本の中国料理の場合、鉢には料理を人数分盛り付けるわけですから、口が大きく開いていて丸みがあってたっぷり盛れるほうがよい。一人前が基本の日本のドンブリとは設計思想が違うわけです。
「丼」という漢字は「鰹」のような日本人が作り出した国字ではありませんが、もともと「ドンブリ」という意味はなく、日本であとから器の意味が付け加えられました。本来は「井」の篆書体でして(井上さんや石井さんの実印には丼の字が彫られているはずです)、中国でも使われなくなった古い字です。中国の人が「牛丼」という看板をみてもなんのことやらわからない(もっとも最近は「丼」という字ともども、中国でも認知が高まっているようですが)のは、こうした理由からです。

このようにドンブリは日本独自のものなのですが、謎だらけ。まず、なぜ丼という漢字が当てられたのかがわからない。俗に井戸の中にドンブリを投げ込んだ様子を表しており(「井」の中に「ヽ」=ドンブリが入っているように見えるというわけです)、その時の水音が「ドンブリ…」と聞こえたので、この器の名前を「ドンブリ」というとか…。もっともらしい説明ですが、井戸の中に器を投げ込んで、どうやって回収するつもりなのか。そもそも何のために放り込むのか。ちょっと理由がわかりません。
水音説に説得力がないとなると、語源もわからなくなります。「どん」+「ぶり」という発音はどこかしら怪しい感じで日本語っぽくありません。そのため、「湯鉢」(スープの鉢)と書いて朝鮮語で「タンバル」と発音する器が日本に入ってきて、なまってドンブリになったという説もあります。これは戦前の朝鮮陶磁研究家、浅川巧が『朝鮮陶磁名考』で言い出したもので、講談社現代新書の『食文化の中の日本と朝鮮』にも採用されている比較的有名な説です。
しかしこれも根拠が弱い。まず朝鮮陶磁でドンブリに相当する形の食器が、中国同様ポピュラーではない。なにせ朝鮮は、料理は金属の器に盛る文化なのですから。それに戦国時代に朝鮮の陶工と一緒にドンブリが伝わったのならわかりますが、朝鮮との国交が制限されていた江戸時代も後半になってから、なぜ突然朝鮮の呼び名が普及することになったのかがわからない。そもそも中国陶磁や李朝陶磁において「湯鉢」という器形を聞いたことがない。浅川氏は「朝鮮の蕎麦屋、一膳めしやで使われている器」が湯鉢と呼ばれていると紹介しているのですが、これって逆に日本から輸入されたのではないかという疑問がわきます。巧は兄の伯教ともども朝鮮陶磁の研究で有名ですが、朝鮮にぞっこんの彼の主張はややもすれば牽強付会なところがあります。
現在有力なのは「けんどんや」という外食業態にちなむという説です。漢字で「慳貪屋」と書きまして、慳貪とは、つっけんどんなこと。サービスはそっけなく、一人前を盛りきりで提供し(お代わりのない一膳めし屋です)、現金掛値なし。こうした飲食店で使う器が「けんどん振り」と呼ばれ、縮んでドンブリになったというのです。
しかし、これもどうもストンと腹に落ちない。そもそも愛想のない「けんどんや」という外食産業の実態が今一つ不明なのです。けんどんやにヒントを得て始まったのが、けんどんそば。その配達用の箱が「けんどん箱」で、これが蕎麦を運ぶ「岡持ち」へと進化するのですが、のちに装飾の立派な「大名けんどん」という箱も現われます。これでは豪華なんだか、そっけないんだか、言葉として矛盾しております。
実際に江戸時代の段階で、何のことかわからなくなる始末でして、「けんどん争い」なるディベートすら行なわれています。論争の主は南総里見八犬伝の著者である滝沢馬琴と、雑学考証の大家である山崎美成。彼らは自慢のお宝グッズ(この時代ですから骨董書画や考古遺物など)を披露し合う「耽奇会」というサークルを開いていたのですが、文政8年(1825年)そこで出品された「大名けんどん」の由来について手紙で大激論を交わします。『新燕石十種2巻』の「けんどん争ひ」や『兎園小説別集』(日本随筆大成第二期4巻)の「けんどん名義」によると、美成はけんどんやにちなむと主張するのに対し、馬琴はけんどんとは本箱に似た型の麺類を運ぶ道具のことであると主張。(つまり馬琴の時代になると、大名けんどんもけんどんやも何のことかよくわからなくなっているのです)泥沼化した挙句、言葉尻をつかんだ言い合いになり、絶交してしまいます。ネットの論争を見ているようでちょっと不毛な印象です。
とまあ、けんどんがよくわからない以上、ドンブリという器の名称の由来もよくわからないのですが、そもそもドンブリがいつ生まれ、どのように普及したかという研究が、これまた乏しいのです。
私の知る限り、ドンブリ史をまとめた唯一無二の研究は、寺島孝一先生の『アスファルトの下の江戸』「どんぶりと割箸」の章です。寺島先生は、東大埋蔵文化研究所で江戸遺跡の発掘に従事していたため、この本では文献だけを眺めていると見落としがちな江戸の人々の日常や道具に光を当てています。たとえば屋根の材質や硯、めんこなどで、考古遺物を通じて江戸の食生活について考える章もあります。「どんぶりと…」の章ではドンブリという単語が出てくる文献を探すとともに、当時のドンブリが、現代人が思い浮かべるそれと同じものかどうかを絵画資料から探っていきます。
さて、ここからは寺島先生の受け売り。丼という語は元禄時代(1688 ‐ 1703年)に書かれた『男重宝記(重宝記資料集成 第11巻所収)』(これは当時の男性向けハウツー本です)にも出てきますが、意識して使われるようになったのは天明年間(1781 ‐ 1789年)だそうです。例の滝沢馬琴の兄の羅文が「近世丼という器出て、あまねくもてはやされる」と記録しております。羅文によると、大きさは10cm未満から30cmを越えるものまでいろいろ、底が細くて口が広く、饅頭を盛ったり、鰹の三杯酢を盛ったりと大活躍していたとのこと。朝鮮語の「湯鉢」を語源とするのに無理があるのが、ここからわかりますね。ちなみにドンブリにご飯が盛られるようになったのは、鰻丼が先駆けだったようです。文化年間(1804 ‐ 1817年)に鰻好きの芝居のパトロンが、観劇中に冷めないようにドンブリに鰻とご飯を入れて蓋をして取り寄せたのが始まりだそうです。
 小社の『蕎麦の事典』には、例の「けんどんや」や「けんどん箱」についても説明がありますが、都合のいいことに表紙に江戸時代の丼を描いた浮世絵が載っております。「花街模様薊色縫」という歌舞伎の1シーンで、屋台の二八蕎麦屋でかけ蕎麦(麺が太くてうどんみたいに見えるのはご愛嬌)を食べているのですが、六角形の小鉢のような形で今のドンブリとはかなり違います。ところが絵師の三代豊國が同じ画題で描く別バージョンの浮世絵もありまして、こちらは今のドンブリに近い釣鐘型。江戸時代の人の中でドンブリのイメージはいまだ固まっていなかったのでしょう。それが次第に使いやすいように、今の形へと進化していったと思われます。
小社の『蕎麦の事典』には、例の「けんどんや」や「けんどん箱」についても説明がありますが、都合のいいことに表紙に江戸時代の丼を描いた浮世絵が載っております。「花街模様薊色縫」という歌舞伎の1シーンで、屋台の二八蕎麦屋でかけ蕎麦(麺が太くてうどんみたいに見えるのはご愛嬌)を食べているのですが、六角形の小鉢のような形で今のドンブリとはかなり違います。ところが絵師の三代豊國が同じ画題で描く別バージョンの浮世絵もありまして、こちらは今のドンブリに近い釣鐘型。江戸時代の人の中でドンブリのイメージはいまだ固まっていなかったのでしょう。それが次第に使いやすいように、今の形へと進化していったと思われます。
ところでこの浮世絵は、日本料理史上のもう一つの大革命を示しています。それはもり蕎麦から、かけ蕎麦への進化。後世のラーメンへとつながる汁そば文化の誕生です。これについてはまた後日に。
投稿者 webmaster : 11:48
2010年07月23日
料理本のソムリエ [ vo.6 ]
【 vol.6 】
牛鍋と牛丼、二つのチェーン
前回に引き続き、築地つながりの話題です。
牛丼の吉野家(ヨシの字は土に口と書くほうなのですが、ここではご勘弁を…)の1 号店は築地市場内にあります。もっとも明治32(1899)年の創業地は日本橋の魚河岸でして、市場が移ったのに合せて築地に移転しました。となると、築地市場が豊洲に移ったあかつきは、今度もまたお供するのでしょうか…。
材料が牛肉なのに、なぜ魚河岸に縁が深いのか。それは牛丼が今も昔も「早い」「安い」が喜ばれた商品だったからです。魚河岸には、商品を運び、仕分けし、競り場に並べる「軽子」(かるこ)と呼ばれる作業員たちがたくさんおりました。彼らが仕事の合間に、土足で立ったままでも食べられるような手軽な食事が牛丼だったわけです。
 明治40年代の職業案内書を見ると、牛丼屋は「牛飯屋」「牛肉煮込屋」などと呼ばれておりまして、屋台でも営業できるし、小資本で参入できて利益率も高いと紹介されております。材料は切り出し肉や内臓。その昔は犬や馬の肉を混ぜた不届き者もあったとありますが…。
明治40年代の職業案内書を見ると、牛丼屋は「牛飯屋」「牛肉煮込屋」などと呼ばれておりまして、屋台でも営業できるし、小資本で参入できて利益率も高いと紹介されております。材料は切り出し肉や内臓。その昔は犬や馬の肉を混ぜた不届き者もあったとありますが…。
この牛肉煮込とちょっと混同されやすいのが牛鍋でして、両者は単価が違います。こちらは文明開化の寵児として明治の初めごろにブームを呼んだ業態でして、牛丼よりはずっと高級です。
牛鍋の話といえば必ず登場するのが別名「いろは大王」こと、木村荘平。彼こそは日本の外食チェーンの始祖であります。創業は明治11(1878)年。材料は一括で仕入れ、営業成績の載った社内日報を発行するなど、近代的な手法で牛鍋店の経営を行ない、店名の“いろは”にちなんで48店の展開を目指しました。ただし彼は、フランチャイズチェーン(FC)ではなく、自分の妹たちやお妾さんに店を持たすという究極の方法で、家族経営とチェーンの両立を図ったのが現代人にはまねできないところ。酉の日には全従業員とその家族をぞろぞろ連れて参詣し、店の存在をPRしました。なお料理を運ぶ店の女中さんは「軽子」と呼ばれていたそうです。
荘平は何人お妾さんを持つつもりだったのかはわかりませんが、子供たちには生まれた順に数字で名前を割り振りました。なんだか昔の中国みたいですが、30人もいるとなると、そうしないと覚えきれなかったのかもしれません。いろはチェーンはカリスマ創業者が亡くなると傾き始め、大正元年(1912)年には倒産してしまいますが、木村家の遺伝子は優秀で、奇術師の荘七、画家の荘八、作家の荘十、映画監督の荘十二など、多くの文化人を輩出しております。
エビスビールの大日本麦酒醸造会社を興し、競馬場を始め、現在の日本の火葬場の基礎を作るなど、とにかく型破りな経営者だった木村荘平については『悲願千人斬の女』が詳しいです。表題の由来となった松の門三艸子、芦原将軍、稲垣足穂、そして木村荘平と、破天荒な人生を送った4人の人物を取り上げた至極まじめな本なのですが、タイトルにインパクトを狙いすぎて損をしているように思えます。いろはチェーンの店は何店あったのか、いい加減な憶測がまかりとおっていたのですが、本書では19店中15店の住所まで調べ上げており、正確を期そうという執筆姿勢には頭が下がります。
さて、話を吉野家に戻しましょう。こちらにも木村荘平にも負けないカリスマ社長、松田瑞穂がおりました。明治時代から素人でも参入しやすい業態としてみられていた牛丼屋ですが、1968年に吉野家が新橋に初めて支店を開いたその時から、今のようなチェーン店隆盛時代が始まります。
松田氏はアメリカ式のセントラルキッチンやFCをいち早く導入し、10年後には目標の200店を早々と達成。アメリカにも進出し、さらに300店舗の目標を掲げてチェーンの拡大を目指します。しかしその急拡大が災いして資金繰りがショートし、115億円の負債を抱えて1980年に会社更生法の適用を申請、倒産の憂き目にあいます。
絶好調だった吉野家がつまづいたのは、味の低下に原因があったと分析されています。具体的には粉末ダレや冷凍漬物、フリーズドライの牛肉の導入であり、それが顧客離れを招いたのです。これだけみると、素材の質を落として利益を上げようとした安直な姿勢のつけが回ったかのように見えますが、その狙いは別のところにありました。粉末ダレは店ごとに味がぶれるのを押さえるためと輸送コスト削減、冷凍漬物は白菜の値段の季節変動を回避すること、フリーズドライの加工牛肉は当時あった牛肉輸入制限枠にとらわれずに輸入できることから導入に踏み切ったのです。しかし、それにともなう味の低下を軽視すぎた。策士策におぼれたり、という感じです。
 吉野家の松田社長はたいへんなアイデアマンでした。当時の吉野家では、米においても画期的な技術を導入しています。
吉野家の松田社長はたいへんなアイデアマンでした。当時の吉野家では、米においても画期的な技術を導入しています。
というのも、小社の「月刊食堂」のバックナンバーを見ていたら、1974年8月号の社長インタビューで松田氏は「空気洗米の導入」をアピールしていたのです。圧縮空気を吹き付けてヌカを落としたこの米は日持ちがよく(当時はいったん研いでから乾燥させた米が業務用として出回っていたのですが、水分を含むので日持ちが悪かったのです)、アルバイトでも簡単に炊けると彼は強調していました。これって今でいう無洗米と狙いは同じではないか。しかし米と米をこすりあわせて研ぐ、まったく水を使わない無洗米が登場したのは90年代からです。空気でヌカはどの程度まで落とせたのか、どこの精米機メーカーが開発し、どうして普及しなかったのか、今となっては謎です。
ほかにも松田社長は3億円を投じて、各チェーン店の売り上げを本部や自宅のコンピュータのモニタでチェックするシステムを導入しています。70年代のパソコン(おっと当時はマイコン、もちろんBASICですね)といえばマニアの手製がお決まりで、静電気で部品を壊さないように台所でアースしながら組み立てていた時代ですから、そのハイテクぶりたるや恐るべしです。松田社長のニーズに技術が追いついていなかった。悲劇の経営者というしかありません。
1987年に債務を100%返却して奇跡の復活を遂げた吉野家は、その後も話題に事欠きませんでした。吉野家を取り上げたビジネス書には、デフレ時代の象徴として注目したものとしては『新国民食吉野家!』(01年)『吉野家の牛丼280円革命』(02年)が、BSE禍の影響を受け、牛丼販売中止がニュースになった頃には『吉野家』『がんばれ!!吉野家』(06年)『吉野家安部修仁 逆境の経営学』(07年)が出版されています。しかし、これらの本は発行年が下がるにつれ、倒産はプロジェクトX的な感動エピソードの一つとして語られがちな気がします。
 ところが会社更生終結の翌年に小社から出版された『ドキュメント吉野家再建』を読むと、そんな簡単なものではありません。動揺する社内の建て直しと団結、ノウハウ流出による分離独立店の防止、債権者との駆け引き、FCオーナーの説得など、きれいごとだけでは済まない企業の苦悩までもが描かれています。企業の危機とその克服の実例として、興味深い。
ところが会社更生終結の翌年に小社から出版された『ドキュメント吉野家再建』を読むと、そんな簡単なものではありません。動揺する社内の建て直しと団結、ノウハウ流出による分離独立店の防止、債権者との駆け引き、FCオーナーの説得など、きれいごとだけでは済まない企業の苦悩までもが描かれています。企業の危機とその克服の実例として、興味深い。
そもそもビジネス書は成功例と自慢話に満ちているものですが、失敗を正面きってとらえた本はなかなか珍しい存在でもあります。経営者たちは、戦国武将の格言を覚えたり、女子マネージャーに甲子園に連れていってもらうひまがあったら、こういった先人の苦労から学びとってほしいものです。
吉野家が再建できたのは、原点に立ち返って味の向上をめざし、再建セールを打つことで再び吉野家ファンの支持を集めたことが大きかった。この成功以降、吉野家はあくまでも牛丼を商品の柱とする単品主義を守るとともに、全店一斉フェアでのてこ入れを重視するようになります。
7月28日、また吉野家は安売りフェアに踏み切り、松屋やゼンショーもこれを迎え撃ちます。一般マスコミは牛丼戦争などと面白おかしく取り上げるばかり。安売りフェアも乱発するようになると、単なる消耗戦にすぎなくなります。どうせなら歩調を揃えて、「3チェーン合同企画による牛丼安売りゴールデン週間」とでもしたほうが(3店食べ歩くと何かもらえるとか)、牛丼ファンを増やす楽しいイベントになる気がするのですが…。もっと外食産業全体の活性化につながるような、建設的な方向には持ってこれないものでしょうか。
投稿者 webmaster : 17:08
2010年06月23日
料理本のソムリエ [ vo.5 ]
【 vol.5 】
魯山人先生、築地へ行く
ある魯山人本に、北大路魯山人は美食倶楽部時代に、築地へみずから足を運んで魚を仕入れていた、という記述がありました。前回申し上げた築地信仰のよい例でして、もうどこから突っ込んでよいものやらわかりません…。
まず第一に、魯山人が美食倶楽部を開いていたのは大正時代ですから、魚河岸といえば日本橋のこと。美食倶楽部があったのはそこから1kmも離れていない京橋東仲町です。まあ、これは誰にでもわかるケアレスミスですが。
問題は、魯山人が魚河岸へ足を運んだ事実をどう解釈するかです。市場に足を運ぶのをおっくうがる凡百の料理人と比べて、さすが魯山人先生は偉かった、とおっしゃりたいようなのですが、そんな現代感覚で簡単に物事を解釈してもらっちゃ困ります。
 というのも、東京の料理人さんの回顧録を見ると、料亭の魚の仕入れは店の主人、すなわち経営者の担当で、料理長は市場に行く習慣はないとあるんです。
というのも、東京の料理人さんの回顧録を見ると、料亭の魚の仕入れは店の主人、すなわち経営者の担当で、料理長は市場に行く習慣はないとあるんです。
小社の『味を奏でる人たち』は、15人の料理長の修業時代の話をまとめたものですが(その中には、短い時期ですが魯山人のいた星岡茶寮も体験している桑原清二氏も登場します)、この本の中で銀座「松本楼」に務めていた宮澤退助氏は、主人が包丁を握ることの多い関西は別として、「料理人が河岸に行くようになったのは戦後のことじゃないでしょうか」とまで語っております。もちろんこれは高級料亭の話でして、小料理屋や食堂では話が別だと思いますが…。
市場は現金支払いですから、財布を握る者でなければ相手にしません。とはいえ雇い人に大金を預けた日には、ピンハネされないとも限らない。経営者は胴巻きに現金を入れて羽二重姿で市場に向かい、高級魚を扱う上物屋の帳場で仕払って、荷物は見習いの若い料理人が潮待茶屋から大八車で持ち帰るというのが通常の仕入れスタイルだったようです。実際、戦前の経営者座談会を読むと、せっかく自分が仕入れた魚に対して「こんなもの仕入れやがって使えやしない」と料理長に陰口を叩かれるのが、しゃくに障ると嘆いています。
その点、美食倶楽部の経営は友人の中村竹四郎と共同ですから、魯山人は経営者といえなくもありません。主人みずから包丁を持つ「板前割烹」という業態が広がったのは大震災以降ですから、魯山人のような存在は珍しかったかもしれません。
それでは築地市場が仮営業を始めた昭和の初め、すなわち星岡茶寮時代の魯山人はどうしていたかというと、昭和6年の料理雑誌で市場関係者が証言しています(匿名記事なのですが、私は前回紹介した『魚河岸怪物伝』に登場する長谷川秀雄とにらんでいます)。
星岡茶寮は前の晩に問屋に電話注文して翌朝届け、品物の鑑定は問屋まかせという「大名買い」の代表例。とにかくその日に河岸にあるものの一流品を選んで、これ以上の物はございませんと言って届けなければ気に入らない。問屋としてはいいお得意様だが、高くつくので見方によっては下手な買出しだと、見切られております。
ちなみにこの記事では、主人なり店の目利きのできるスタッフなりが買い出しにきて、一渡り河岸中の品物と相場を見て歩いて大勢を見定めたうえで行きつけの問屋で買うのを「健実買い」、あちこち河岸をうろうろあさって、とにかく安いものを買うのを「素人買い」と呼んでおり、健実買いをする主人の店を好意的に紹介しています。
 もっともこの暴露記事に恥じたのか、星岡茶寮の仕入れはその後、料理主任の担当となったようです。昭和10年頃に星岡茶寮主任となった松浦沖太氏は、「日本料理の四季」4号のインタビューによると、大抜擢されたときの魯山人の決めゼリフが「明朝から買出しに行け」だったそうです。またある時松浦氏は、魯山人に「毎日買出しに、どんな気持ちで行っているのか」と尋ねられ、「新鮮でいいものを買うようにしています」と答えたところ、「それは当たり前だよ、俺だったらその日の天気を考えてものを買うよ」と教えられたそうです。
もっともこの暴露記事に恥じたのか、星岡茶寮の仕入れはその後、料理主任の担当となったようです。昭和10年頃に星岡茶寮主任となった松浦沖太氏は、「日本料理の四季」4号のインタビューによると、大抜擢されたときの魯山人の決めゼリフが「明朝から買出しに行け」だったそうです。またある時松浦氏は、魯山人に「毎日買出しに、どんな気持ちで行っているのか」と尋ねられ、「新鮮でいいものを買うようにしています」と答えたところ、「それは当たり前だよ、俺だったらその日の天気を考えてものを買うよ」と教えられたそうです。
北鎌倉住まいで夜にならないと店に来なかった魯山人ですが、たまには築地に行くこともありました。昭和11年4月21日に、星岡茶寮で発行していた機関誌『星岡』のスタッフと松浦氏を連れて、自動車で築地に通うのは自分が初めてだろうと自慢たっぷりに案内しております。松浦氏は以前も魯山人とともに築地に来たことがあるようで、魯山人はすぐに人込みの中にまぎれて姿が見えなくなってしまうのだとか。松浦氏が料理主任になったのは21歳の若さですから、初めのうちは魯山人が付き添ったのかもしれません。
 まあ、こんなふうに最近の魯山人に関する文章は時代背景をまったく無視して書かれているので、実に的はずれ。
まあ、こんなふうに最近の魯山人に関する文章は時代背景をまったく無視して書かれているので、実に的はずれ。
そもそも魯山人唯一の料理本『春夏秋冬 魯山人の料理王国』は、かつて発表した文章を昭和30年頃にかなり書き改めたうえで一冊にまとめたものなのですが、初出一覧でその旨を断っていないため、一部は星岡茶寮時代に書かれた文として通用しています。
『魯山人著作集』に至っては、オリジナルの戦前発表の文と変更後の単行本の文を両方とも収録したあげく、どちらも初出は同じ雑誌としています。読めば似たような話が二回でてくるので、誰か気づきそうなものですが…。『魯山人の料理王国』は新装版が別の出版社から出たり、『魯山人味道』に収録されたり、文庫化されたりと、注意書きをつける機会は何度となくあったのですが、いつまで経っても改善されません。
おかげで美食倶楽部や星岡茶寮の料理がどんなものだったかは、正しく認識されていません。その最たるものが、日本料理店が料理を一品ずつ提供するのは魯山人が始めたものという俗説です。一品出しの提供スタイルは江戸時代の料理本『即席料理素人包丁』にすら見ることができるのですが…。
すべての料理を膳や懸盤に盛りつけて、いっせいに客の人数分を運ぶには、それなりの広さの盛り付け台と大人数の仲居さんが必要です。それにこの手法だと、いったん料理を運んだら次は膳を引くまで仕事がありません。花嫁修業目的の奉公人をたくさん抱えた大名屋敷じゃあるまいし、人材派遣所から日雇いで仲居さんを雇うようになった明治大正時代、人件費がかかって仕方ありません。
そもそも魯山人が一品出しを創始したとしたら、普通と異なる提供法に仰天した客があちこちに書き残すでしょうが、そんなものは見たことがありません。当時書かれた星岡茶寮の評判を総合すると、「前菜」という提供スタイル、中国料理と日本料理の折衷を図った国際色あふれる料理、果物を多用するハイカラなデザートの3点が、よそと違って珍しかったようです。そのほか書家として、その日の献立を書いて客に配るサービスを行なった点(もっとも後にはスタッフに代筆させるようになりましたが)、陶芸家としては、大ぶりの鉢やまな板皿を焼き、それを食器に使用したという点もみのがせない特徴です。
魯山人の前菜は、4つの四角い皿を組み合わせ、おばんざい風の料理を盛ったもので、今の日本料理の前菜や先付とはかなり雰囲気が違います。この“偶数の小皿盛り”というスタイルはむしろ中国の江南料理の前菜に近い。そもそも彼は友人の樫田十次郎の奥さんが主催する支那料理講習会に通っていたため、中国の調理技法に基礎があるのです。星岡茶寮の名物料理に魚の姿揚げである「琥珀揚」がみられるのもそのためです(ちなみにこの料理は『魯山人の料理王国』にも登場していますが、魯山人が勘違いして昭和10年に命名したと書き改めたために、その来歴がさっぱりわからなくなっています。初出は昭和8年の料理講習会なのですが…)。なにしろ魯山人は美食倶楽部時代には、日本料理には油脂が足りないので改革したいと婦人雑誌のインタビューで述べているくらいですから。
果物を多用したのも当時有名な話でして、逆に「星岡茶寮は値段は高いが、実際に高価な素材は果物ばかりだ」と悪口を書かれたりしています。昭和9年の日本料理研究会の展示会でも果物の盛り合わせを出品していますので、本人も自信があったのでしょう。
小社刊の『日本料理入門』の著者藤本憲一氏は、昭和10年に星岡茶寮に入り、のちに姉妹店の銀茶寮の料理長を務めていた料理人ですが、本書中で再現している星岡茶寮時代の料理写真からも先の3つの特徴がうかがえます。丸のままの果物が盛り付けられているのは、今にしてみると少し野暮ったい印象も受けますが、当時の雑誌に載った写真もこんな感じでしてリアルです。



こうしてみると魯山人の料理は実に近代的なセンスがうかがえる反面、今の人が想像しているようなしっとりとした趣きのある感じではありません。最初に挙げた“築地に仕入れに通う魯山人”と同じく、現代人の感覚が生んだまぼろしのような気がしてなりません。
投稿者 webmaster : 15:07
2010年06月02日
料理本のソムリエ [ vo.4 ]
【 vol.4 】
ワンダーランド、謎多き築地
 先日、会社にラーメン店のかたから電話がありました。
先日、会社にラーメン店のかたから電話がありました。
つけ麺のスープ用にウルメイワシの煮干しを大量に仕入れたく、その入手方法を知りたいとのことです。畑違いの本にもかかわらず、小社刊の『だしの基本と日本料理』を読んで勉強されたそうで、嬉しい限りです。
ちなみに小社にはそうした熱心なラーメン屋さんに向けた、『プロのためのラーメンの本』 『プロのためのラーメンの本2』という別冊もございます(PR)。
『プロのためのラーメンの本』には、だし素材の図鑑を載せておりまして、そこにあるようにウルメイワシの煮干しは近年品薄なのです。



このラーメン屋さんは築地の鰹節屋さんに連絡したが、そこは鰹節専門だったため、残念ながら扱っていなかったそうです。そもそも東京の鰹節店はそば店が上得意なので、品揃えもそば向きのものが多いですね。かびつけをしていない裸節は関西、煮干しは中京の問屋が積極的に扱うなど、だし素材には地域差があります。
最近は、食材は何でもかんでも築地に集まると考えられがちですが、必ずしも築地がナンバーワンとは限りません。海産物でも車エビや海苔など、昔から市場外流通が中心のジャンルもありますし、場内の鮮魚においても、築地といえども取り扱う魚種に地域色があるのです。輸送に時間がかかる地域の鮮魚は、商品力に乏しいですから、高値がつかない限り、積極的には取り扱いません。東京のマーケットでは高値がつくのは何と言ってもすし種。逆にすし種に使わない魚種、たとえばハタ科の白身魚などについては、築地市場は弱い印象を受けます。
築地はテレビや雑誌に多く紹介されるようになりましたが、こうした実態は必ずしも理解されていません。築地で食材を仕入れさえすれば、材料費を惜しまない素人のほうがプロよりもおいしい料理が作れると豪語する、神をも(料理人をも?)恐れぬ本すら現れています。築地神話は肥大化する一方です。
そうした一方で、市場内から自らについて語り、築地とはどんなところなのか、理解してもらおうという動きが出てきました。今年2月に出版された小山田和明氏の『聞き書き築地で働く男たち』(平凡社新書)は、築地で働くさまざまな業種の大先輩にインタビューし、過去を振り返ってもらったもの。失われていく貴重な時代の証言です。マグロのような派手な世界だけでなく、練り物だの、小揚げ(競りの荷役)だの、ターレットトラックや台車だのといった市場を構成する様々なジャンルに目配りされている点で、他書の追随を許しません。ただし、それだけにマニアックで、市場に関する基本知識がないとその面白さを味わいきれないところがあります。
 築地に関する基礎知識はどうやって仕入れたらよいか。ほぼ同じ時期に仲卸し3代目の生田與克氏が『たまらねぇ場所築地魚河岸』(学研新書)を出版しております。ただし、これは全体に妙なべらんめえ(江戸弁?)の語り口で書かれていてちょっと読みにくい。しゃべり口調は生田氏の持ち味のひとつですが、大修館書店から出した『築地魚河岸ことばの話』のほうが、一文一文が短いために読みやすい仕立てになっています。こちらはオールカラーという贅沢な造りの用語集であるため、知りたいことが端的につかめます。もっとも用語集なので、一から筋道立てて知りたい人には不向きですが。
築地に関する基礎知識はどうやって仕入れたらよいか。ほぼ同じ時期に仲卸し3代目の生田與克氏が『たまらねぇ場所築地魚河岸』(学研新書)を出版しております。ただし、これは全体に妙なべらんめえ(江戸弁?)の語り口で書かれていてちょっと読みにくい。しゃべり口調は生田氏の持ち味のひとつですが、大修館書店から出した『築地魚河岸ことばの話』のほうが、一文一文が短いために読みやすい仕立てになっています。こちらはオールカラーという贅沢な造りの用語集であるため、知りたいことが端的につかめます。もっとも用語集なので、一から筋道立てて知りたい人には不向きですが。
がっつり築地について学びたい人には、ハーバード大の人類学者による『築地』(木楽社)が3年前に出版されています。日本人なら見落としそうな一見当たり前のことまできめ細かく調べ上げていますが、かなりの厚さで学術的。市場に出入りしたことがない読者は、やはり生田氏の新書から入門したほうがいいかもしれません。
ひとつ難をいえば、これらの本は歴史の解説に若干物足りないところがあります。何代も続いている店も少なくないため、当事者たちにはばかったのかもしれませんが、築地誕生のいきさつは、現在の移転問題を考えるためにも知っておくべきことだと思うのですが…。なにしろ移転問題を問う政治家アンケートの中に「市場が移転すると日本の食文化の伝統が破壊されてしまう」という回答があったのには驚きました。移転が原因で破壊されてしまう程度の伝統なら、日本橋から移ったときにとっくに失われていることでしょう。
日本橋魚市場の移転は明治時代からの懸案事項でした。それは衛生問題や狭さの問題もありましたが、魚の輸送に鉄道を利用するようになったという点も見逃せません。大正時代の東京案内書を読むと、貨物で運ばれてきた魚を上野駅、東京駅、両国駅から、いちいち運び込んでいたとあります。そのため大正後半には、品川から東海道線を引き込めるうえに、大型船も横付けできる芝浦の埋め立て地に移転することが一応内定したのですが、反対が多くて迷走。関東大震災直後に、とりあえず仮設市場が置かれたのですが評判が悪く、海軍跡地の築地が急浮上したのです。
ところが建設に時間がかかったうえに、市場関係者の既得権をめぐって揉めに揉め、仮営業の状態が昭和10年まで続きました。オープン後も不買運動が続いたすえ、16年には配給制度が始まるので仲買制度は廃止されてしまいます。戦後は戦後で物資不足。統制経済が解除された25年になって、ようやく築地は本格稼動したと言ってよいでしょう。
ちょうどこの年刊行の岩波写真文庫の『魚の市場』を見ると、魚は木樽や木箱で運ばれており、現在の築地とはだいぶ様子が違います。市場に入荷する魚の半分は鉄道で、残り半分は船で届き、トラック輸送はたったの5%です。いまや輸送手段はトラック中心ですから、湾岸の豊洲のほうが道が混まなくて便利という意見はたしかにその通りです。
なお戦前、戦中の築地をめぐる騒動については、尾村幸三郎氏の『魚河岸怪物伝』(かのう書房)から断片的に知ることができます。この本は小山田氏の築地で働く人たちが語る自分史とはちょっと違って、市場の大物たちの列伝です。人物にスポットを当てているため体系的ではありませんが、動き出した築地がどれほど多くの難問を抱えていたかは実感できます。
かつての昭和の移転は実に時間がかかりましたが、荷主へのリベート請求や偽の相場情報を流すといった不正も一掃でき、近代的な市場システムに移行することに成功しました。今回も移転するにせよ再整備するにせよ時間をかけて取り組むべきですし、先入観や誤解に基づく外野の介入は謹んでほしいものです。
まあ個人的には今の場所で市場を続けてほしいというのが、正直な気持ちではありますが。忙しい料理人さんにとっては築地の近さと地下鉄日比谷線で行ける便のよさがありがたく、移転すると通えなくなるという声が上がっています。編集者としては、仲卸しでの取材中に知り合いの料理人さんとばったり遭遇、なんていうハプニングがこれからも続いてほしいものです。
投稿者 webmaster : 14:20
2010年05月21日
料理本のソムリエ [ vo.3 ]
![]()
【 vol.3 】
あまたある寿司の薀蓄本の元ネタは?

 小社は蕎麦関係の本は得意としておりますが、すしとなると正直なところあまり出版点数がありません。
小社は蕎麦関係の本は得意としておりますが、すしとなると正直なところあまり出版点数がありません。
最近では銀座「鮨処おざわ」主人の技術を紹介する『すしの技 すしの仕事』、 別冊OYSYシリーズの『すし』 (ちなみに本文イラスト担当はテレビドラマ「キッパリ!」の原作者さん)あたりでしょうか…。

 しかし忘れてならないのが、すし業界の金字塔ともいうべき重要書籍、篠田統先生の『すしの本』です。
しかし忘れてならないのが、すし業界の金字塔ともいうべき重要書籍、篠田統先生の『すしの本』です。
前回李盛雨氏の恩師として登場した篠田先生は、食物史の大家としてこの世界で知らない者はおりません。本書はその著書『中国食物史』(柴田書店)と並んで名高い、料理史研究の古典的名著です。
1966年に初版が出たあとわずか5年で12版を重ねて改訂増補、93年には新装復刻しました。いまは岩波現代文庫に入っています。
もともと理系だった篠田先生は、すしを調理学、生化学、食物史の3点から総合的に捉えようとしました。そうすることで、難しそうなテーマを難解に説くのが学問だと思っている学者たちの視界には入らない、すしというジャンルに、光を当てようとしました。
増補版の序文には、「日本中のだれもが知っている「すし」のように身近なものでも学問の対象として立派に通用するし、また実際、秘伝ばかりに頼って学問的の綿密な研究を怠ってはその進化、発展は困難であること、ならびに、その研究結果を表現するのには日本中のだれもが使う言い表わし方で十分であることなどを、この本で示したかった」とあり、パイオニアの意気込みと苦労がしのばれます。
ただし握りずしにしか興味のない人には、この本はあまりお勧めできません。というのも、篠田先生がすしに関心をもったのは琵琶湖の鮒ずしとの出会いからで、その研究目的はすしの歩みと広がりを掘り起こすことにありました。日本各地に伝わる様々なすしの種類や分布を紹介し、中国に始まるすしの歴史を解き明かすなかで、江戸時代に誕生した握りずしについては全体の10分の1も触れておりません。
 しかし篠田先生は握りずしを軽視していたわけではありません。関西人である自分よりも江戸前ずしを語るのにふさわしい人がいるだろうと、道を譲ったのです。
しかし篠田先生は握りずしを軽視していたわけではありません。関西人である自分よりも江戸前ずしを語るのにふさわしい人がいるだろうと、道を譲ったのです。
篠田先生が握りずし研究を託したのは、日本橋吉野鮨本店の吉野昇雄さん。野口元夫の芸名を持つ俳優でもあり、映画「タンポポ」にも出演している異色の寿司店主人です。吉野さんが亡くなる半年前の1990年に出されたのが『鮓、鮨、すし―すしの事典』(旭屋出版)で、こちらは歴史文献を集めるとともに昔を知る同業者に取材した、握りずし学の集大成です。篠田先生の薫陶を受けたことが序文で語られ、巻末には先生との対談も収録しています。
その後、発酵文化と郷土食という視点からすしをとらえる篠田先生の研究は、『すしの歴史を訪ねる』(岩波新書)などの著作がある日比野光敏氏に受け継がれました。すし店主が仕事の内容や自分史を語る本も増えました。いっぽう握りずしの歴史をさらに深く追いかける作業はというと、吉野氏以降ほとんど進展していない印象をうけます。90年以降、すしマニアが薀蓄を語る本は枚挙にいとまがありませんが、どれもこれも篠田・吉野両氏の成果の丸写しです。
その一例を挙げましょう。最近江戸時代のすしを再現するという企画をあちこちで見かけますが、その典拠になっているのが1910(明治43)年に書かれた『家庭鮓のつけかた』です。1825(文政7)年頃に握りずしを発明したという説もある老舗「與兵衛鮓」のレシピをイラスト入りで細かく紹介したもので、当時のすしの実態がわかって実に面白い資料です。吉野氏の解説つきで1989年に主婦の友社より『偲ぶ與兵衛の鮓』というタイトルで復刻もされています。
 かつての江戸前ずしはすし種を醤油に浸けたり酢で締めたりとひと手間加えてあるため、つけ醤油はいりませんでした。またすし飯に砂糖を加えないのが一般的でした。
かつての江戸前ずしはすし種を醤油に浸けたり酢で締めたりとひと手間加えてあるため、つけ醤油はいりませんでした。またすし飯に砂糖を加えないのが一般的でした。
そうした古い姿の江戸前ずしがこの本からうかがえます。
しかしだからといって、明治も末の本のレシピで「江戸時代のすしもこうでした」というのは短絡的すぎやしないでしょうか。この本に収録されている握りずしの図版は、1877(明治10)年開催の内国勧業博覧会に出品された絵の再利用であることが、吉野氏の調査で判明しています。そのため、なんとなくレシピも明治10年のままだろうという誤解を招いたようです。
すしの展示というのは奇妙な感じがしますが、日本の産業をアピールする目的で開かれたこの博覧会では、特産品から最新機械まで、国産品ならなんでもかんでも出品されていました。さらに分厚い出品解説書が作られまして、こちらも復刻版がありますし、オリジナルも古本屋で見かけます。試しに開いてみたところ、與兵衛鮓のレシピがちゃあんと載っておりました。
明治10年の與兵衛鮓のレシピと43年のレシピを比較すると、まずすし酢の配合比が違うことがわかります。43年のほうは酢と塩が同割で塩がずいぶん多いのですが、10年のレシピでは2対1でむしろ現在に近い。それでいてカスゴダイやアジの場合、塩と酢に浸ける時間が、10年では43年の倍の1時間。エビは20分間(!)をかけてゆでるのはどちらも同じですが、43年のレシピでは塩をあてて15分から20分間おいた後、酢に20分間浸してから三杯酢に1、2分漬けるのに対し、10年は1時間20分も塩をあてておく一方で、酢で洗うだけで、さらに三杯酢ではなくミリン醤油で調味した酢にくぐらせています。
保存のためなのか、明治の初めのほうが塩味、酢味が突出していそうです。
ところが大正時代の末に実際に與兵衛鮓を食べた吉野氏によると、菓子のように甘かったそうなのです。たとえ老舗の名店といえども、時代に応じて常に変化しなければならなかったのでしょうか。
![]()
投稿者 webmaster : 13:38
2010年05月19日
料理本のソムリエ [ vo.2 ]
![]()
【 vol.2 】
チャングムの宮中料理のレシピって?
前回、中国には料理文献があまり伝わっていないと書きましたが、その理由は出版文化の違いにあります。儒教の国に生まれた彼らにとって、政治や思想などの堅い話題こそが著述すべき事柄であり、実用書なぞは二の次だったわけです。中国の古文献は出版ジャンルに偏りがあり、農業書以外の技術書や旅行案内、娯楽書のたぐいもそう多くはありません。
 それはお隣の韓国も似たようなもの。ただ、韓国は中国と違って料理人は女性であり、女子供用の表記法であるハングルもありました。そのため家庭の味を伝える資料も若干残っているのが中国と違う点です。
それはお隣の韓国も似たようなもの。ただ、韓国は中国と違って料理人は女性であり、女子供用の表記法であるハングルもありました。そのため家庭の味を伝える資料も若干残っているのが中国と違う点です。
こうした料理書を詳細に研究し、韓国料理史という分野を開拓した李盛雨氏は、日本の篠田統先生の教え子であり、先生の勧めで自国の食文化研究を始めたそうです。韓国だけでなく、留学していた大阪の図書館に所蔵されていた朝鮮王朝の資料なども調査されています。その著書『韓国料理文化史』(平凡社)は、日本料理と比較する視点も持ち合わせているので、その研究は深く、客観的です。日本料理史や中国料理史の研究書にもこれだけの内容の本はなかなかありません。
 ところで朝鮮の王宮では、女官たちが料理を作っていたのはチャングムのドラマを見た人ならご存知でしょう。その伝統を唯一受け継ぎ、韓国の人間国宝になったのが故・黄慧性先生です。彼女も戦前福岡と京都の女学校に留学しており、その日本語はそんじょそこらの日本人よりもずっと美しく、上品な言葉遣いでした。黄先生は日本で対談本『韓国の食』(平凡社)を出版していますが、この対談は日本語で行なわれたのでしょう。
ところで朝鮮の王宮では、女官たちが料理を作っていたのはチャングムのドラマを見た人ならご存知でしょう。その伝統を唯一受け継ぎ、韓国の人間国宝になったのが故・黄慧性先生です。彼女も戦前福岡と京都の女学校に留学しており、その日本語はそんじょそこらの日本人よりもずっと美しく、上品な言葉遣いでした。黄先生は日本で対談本『韓国の食』(平凡社)を出版していますが、この対談は日本語で行なわれたのでしょう。
 私が黄先生に会ったのは、小社の『韓国料理 伝統の味四季の味』のためでした。著者の李信徳先生の「恩師である黄先生に序文を寄せていただき、著者写真にはツーショットで写りたい」というたっての願いで、担当編集者とカメラマンが急遽韓国に渡ることになったのです。携行人数合わせに同行しないかとお呼びがかかり、私も私費で大阪経由韓国行きという次第に相なりました。
私が黄先生に会ったのは、小社の『韓国料理 伝統の味四季の味』のためでした。著者の李信徳先生の「恩師である黄先生に序文を寄せていただき、著者写真にはツーショットで写りたい」というたっての願いで、担当編集者とカメラマンが急遽韓国に渡ることになったのです。携行人数合わせに同行しないかとお呼びがかかり、私も私費で大阪経由韓国行きという次第に相なりました。
黄先生はゲラを見ながら、「あらあ、この料理はどうしてこうしたのー」などと笑いながら質問され、李さんは大汗をかきながら写真を説明していました。弟子が立派な本を世に出したのを喜びつつも指導を忘れない、師匠と弟子の厳しくも温かいやりとりでした。
その日の夜は黄先生の紹介で、あちらの国立劇場で行なわれた李朝の宴会を再現する舞台を観覧しました。1795年に開かれた、国王の母の還暦を祝う宴会の式次第『園幸乙卯整理儀軌』が伝わっており(この本は大阪府立図書館にもあります)、それに基づくものです。料理は日本の神饌のような高盛り。宴席に運ばれた作り物の巨大な桃の中から鶴が飛び出てきて舞い踊る演出には度肝を抜かれました。さすがにこれはフィクションだろうと思いきや、『園幸乙卯整理儀軌』にこのシーンが描かれているのを見てさらに驚きました。

 ただ李朝の宴会はそんな愉快な演出ばかりでなく、長幼の序を重んじるために挨拶と順序にうるさく、同じ動作の繰り返しが非常に多く感じられました。きっと宮中もそういう堅い雰囲気だったのでしょう。その点、ドラマのチャングムは自由奔放なうえ、料理描写がずいぶんと美味しんぼ調です。歴史ドラマではありますが、日本でいうなら暴れん坊将軍的な立ち位置の作品と思って鑑賞するのが正解でしょう。
ただ李朝の宴会はそんな愉快な演出ばかりでなく、長幼の序を重んじるために挨拶と順序にうるさく、同じ動作の繰り返しが非常に多く感じられました。きっと宮中もそういう堅い雰囲気だったのでしょう。その点、ドラマのチャングムは自由奔放なうえ、料理描写がずいぶんと美味しんぼ調です。歴史ドラマではありますが、日本でいうなら暴れん坊将軍的な立ち位置の作品と思って鑑賞するのが正解でしょう。
そもそもチャングムは16世紀前半が舞台の物語ですが、韓国に現存するもっとも古いレシピ集『飲食知味方』は1670年頃書かれたもので、これは宮廷ではなく家庭の主婦が娘のために書き残したものです。ドラマで登場する料理は黄先生の娘さんの監修ですが、李朝の宮廷料理といってもずっと下がった後世のものを下敷きにしています。
私が訪問した当時の韓国では宮廷料理は実にマイナーな存在で、新羅ホテルほか2、3軒でしか味わえませんでした。それがドラマをきっかけに一気にブームが起きて、今では宮廷料理店がそこらじゅうに見られるとか。2006年に亡くなった黄先生は、どう感じていらっしゃったのでしょうか。
![]()
投稿者 webmaster : 10:10
2010年05月06日
料理本のソムリエ
ビンテージ物(古本)からカリテプリ(お勧め良書)まで
給料のほとんどを新旧料理本に捧げる書籍編集者 T氏が、
ワインよろしくその来歴や特徴を、余計な薀蓄てんこ盛りで解説します。
【 vol.1 】
日本の料理本の数の多さは世界一!
 柴田書店の本で、古書業界でもっとも評価が高いのは、川上行藏先生編集による『料理文献解題』でしょう。これは室町時代や江戸時代に書かれた料理本について、どんな内容でどこの図書館が所蔵しているのか、表紙の写真入りで解説する本です。
柴田書店の本で、古書業界でもっとも評価が高いのは、川上行藏先生編集による『料理文献解題』でしょう。これは室町時代や江戸時代に書かれた料理本について、どんな内容でどこの図書館が所蔵しているのか、表紙の写真入りで解説する本です。
つまりブックガイドでして、古書店にとっては仕入れや値付けの参考書として使えるありがたい存在なわけです。なにしろ今のようにインターネットで古文献の情報が簡単に検索できるようになる以前は、定価以上で販売されていましたから。
 仕入れの参考書と聞いて、驚かれる方がおいでかもしれません。「この本で取り上げられている江戸時代の料理本が、いまだに古書店で売られているの?」と問われれば、答えはイエスです。
仕入れの参考書と聞いて、驚かれる方がおいでかもしれません。「この本で取り上げられている江戸時代の料理本が、いまだに古書店で売られているの?」と問われれば、答えはイエスです。
当時ベストセラーだった料理書は、出版点数の多さが物を言いまして、200年、300年経った平成の世まで失われず、無事伝わっているのです。
 かくいうわが柴田書店ももう何十年も前の話ですが、資料用に江戸時代の料理書を大量購入しています。ところがその直後、江戸時代の料理本の有名どころ50種類が『江戸時代料理本集成』のタイトルで臨川書店から復刻されてしまったので、希少価値はずいぶん薄れてしまいましたが。
かくいうわが柴田書店ももう何十年も前の話ですが、資料用に江戸時代の料理書を大量購入しています。ところがその直後、江戸時代の料理本の有名どころ50種類が『江戸時代料理本集成』のタイトルで臨川書店から復刻されてしまったので、希少価値はずいぶん薄れてしまいましたが。



臨川書店の復刻はオリジナルの本(原書といいます)とまったく同じサイズにし、糸で束ねる和とじの技法で製本するというかなりの凝りようでして、ただ写真製版したような味気ないものとはわけが違います。横長の本もあれば、小さい本もある、原書に忠実な復刻本で、これを手にしてもちょっとした江戸気分が味わえます。
なお復刻というのは正しくは「覆刻」と書きまして、「かぶせてきざむ」というのが本来の意味。江戸時代の本は版画のように文字を板に彫って刷られました。そこで元の本をばらして各ページを裏返し、板(版木といいます)にかぶせるように貼り付けて、裏写りした字に沿って彫ればあら不思議、新しい版木が作れます。コピー機のない江戸時代に本を複製するには、ひたすら手で写すしかありませんでしたが、大量に複製するには、この覆刻という技術が使われたのです。
江戸時代には中国で書かれた古い薬の本を、人命を救うために覆刻して普及させた、という美談もあります。オリジナルの本を彫るのに使えば、貴重な一冊が失われてしまうわけですから。この本は本家中国でもとっくに失われた稀少本であったため、覆刻本が里帰りして驚かせています。
 ちなみに版木は摩滅するまで何度も使えるため、版元が資金繰りのために同業者に売り渡すこともしばしばでした。料理書の中には明治時代に入ってからも引き続き刷られたケースすらあります。絵も内容も昔のままですが、版元の住所が江戸ではなく、東京になっているのでそれとわかります。また内容は昔のままなのに、人物がちょんまげ姿は変だろうと、絵の部分だけ新しく彫り直している例もあります。
ちなみに版木は摩滅するまで何度も使えるため、版元が資金繰りのために同業者に売り渡すこともしばしばでした。料理書の中には明治時代に入ってからも引き続き刷られたケースすらあります。絵も内容も昔のままですが、版元の住所が江戸ではなく、東京になっているのでそれとわかります。また内容は昔のままなのに、人物がちょんまげ姿は変だろうと、絵の部分だけ新しく彫り直している例もあります。
それだけ多くの料理書が出版されたのは、読者ニーズがあったからにほかなりません。日本人ほど料理書に親しんできた民族は、世界でもまれでしょう。フランスやイギリスでは近世に入ると各種料理書が出版されましたが、部数においては日本ほどではないように思います。中国においては、量はおろか種類も実に少なく、1910年に中華民国が成立する以前の料理本は20か30種類程度でしょう。これには農業書や養生の秘訣の本も含めての話で、料理のレシピだけを扱った純粋な料理書と言える本はもっと少ないのです。おかげで中国料理の歴史は、その実像をたどるのは非常に困難です。
日本の場合は反対に、文献がありすぎて研究がなかなか進みません。なにしろ版木で刷って販売された正式な刊行物も多いうえに、料理人たちが書き留めた手書きの料理本がたくさんあるからです。『料理文献解題』に収録された料理本は明治以降のものも数点含みますが、厳選して全200種類。このほかにも料理本は次々発見されていますし、ただの献立やちょっとした覚書のようなもの、料理の作り方にも触れている実用書まで対象を広げれば、それこそ無数にあります。
それでも、江戸時代の料理本を現代語に訳して解説をつけたり、当時の料理を復元するなど、研究は続けられています。『江戸時代料理本集成』も、崩し字のままでは読めない読者のために、洋装の活字本に仕立て直して索引をつけた「翻刻版」が出ています。
池波正太郎の小説中に、あたかも見てきたようなリアルさで料理シーンが描写されているのも、こうした豊富な蓄積があってこそなのです。
投稿者 webmaster : 10:25











